疾患概要
定義
慢性閉塞性肺疾患(COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease)とは、タバコ煙などの有害物質の長期吸入により、気道と肺に慢性的な炎症が起こり、不可逆的な気流制限をきたす疾患です。
COPDは主に以下の2つの病態を含みます:
- 肺気腫:肺胞壁が破壊され、肺胞が異常に拡張した状態
- 慢性気管支炎:気道に慢性炎症が起こり、咳と痰が3ヶ月以上、2年連続で続く状態
多くの患者は両方の要素を持っており、現在は包括的な概念として「COPD」という病名が使われます。
COPDの最も重要な特徴は:
- 不可逆的な気流制限:一度破壊された肺胞は元に戻りません(喘息は可逆性)
- 進行性:治療しても徐々に悪化します(禁煙により進行速度は正常化)
- 予防可能:禁煙により発症・進行を予防できます
- 全身性疾患:肺だけでなく、全身に影響を及ぼします
COPDは「タバコ病」とも呼ばれ、原因の約90%が喫煙です。日本における死亡原因の第10位を占め、高齢化と喫煙率の高さにより、重要な公衆衛生上の課題となっています。
疫学
日本におけるCOPD患者数は約530万人と推定されていますが、診断・治療を受けているのはその約1割程度(約22万人)に過ぎません。これを診断のギャップと呼び、多くの潜在患者が「年のせい」「タバコのせい」と考え、医療機関を受診していません。
年齢では、40歳以上の約8.6%(約530万人)がCOPDと推定されています。加齢とともに有病率は上昇し、70歳以上では約17%に達します。長年の喫煙による累積的なダメージが原因のため、中高年以降に症状が顕在化します。
性別では、喫煙率を反映して男性が女性より圧倒的に多く、男女比は約9:1です。ただし、近年は女性の喫煙率上昇に伴い、女性のCOPD患者も増加傾向にあります。
死亡では、COPDは日本における死亡原因の第10位(2022年)を占め、年間約1万6千人が死亡しています。世界的には死亡原因の第3位であり、2030年には第1位になると予測されています。
予後は重症度により大きく異なります。軽症では健康な人とほぼ変わらない予後ですが、重症になると予後不良です。特に急性増悪(AECOPD)を繰り返すと、肺機能低下が加速し、生命予後が著しく悪化します。増悪による入院後の1年死亡率は約20〜30%に達します。
社会的負担も大きく、医療費(入院、在宅酸素療法など)、労働力の損失、介護負担など、経済的影響が問題となっています。
重要な点:COPDの多くは診断されておらず、適切な治療を受けていません。早期発見・早期治療により、QOL(生活の質)と予後を改善できるため、スパイロメトリー(肺機能検査)による診断が重要です。
原因
COPDの原因の約90%は喫煙です。
喫煙関連
- 喫煙:COPD患者の約90%に喫煙歴があります。喫煙者の約15〜20%がCOPDを発症します
- 喫煙量と期間:喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が400以上でCOPDのリスクが高まります。例:1日20本×20年=400
- 受動喫煙:本人が喫煙しなくても、周囲のタバコ煙への曝露でリスクが上昇します
- 禁煙:禁煙により肺機能低下速度は正常化しますが、既に失われた肺機能は回復しません
喫煙がCOPDを引き起こすメカニズム: タバコ煙に含まれる有害物質(タール、ニコチン、一酸化炭素、フリーラジカルなど)により、気道と肺胞に慢性炎症が起こります。炎症細胞(好中球、マクロファージ)から放出されるプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)が肺胞壁の弾性線維を破壊します。
通常、プロテアーゼはアンチプロテアーゼ(プロテアーゼ阻害物質、特にα1-アンチトリプシン)により制御されていますが、喫煙によりこのバランスが崩れ、肺胞破壊が進行します。これをプロテアーゼ・アンチプロテアーゼ不均衡説と呼びます。
その他のリスク因子
- α1-アンチトリプシン欠損症:遺伝性疾患で、アンチプロテアーゼが欠損しているため、若年(40歳以前)で肺気腫を発症します。日本人には稀ですが、欧米人では重要な原因です。非喫煙者でも発症します
- 職業性・環境性曝露:粉塵(炭鉱、建設業)、化学物質、大気汚染への長期曝露。特に発展途上国では、バイオマス燃料(薪、牛糞など)の燃焼による室内空気汚染が重要な原因です
- 小児期の呼吸器感染症:幼少期の重症肺炎により肺の発育が障害されると、COPDリスクが上昇します
- 気道過敏性:喘息の既往があると、COPDのリスクが上昇します
- 遺伝的素因:同じ喫煙量でもCOPDになる人とならない人がいるのは、遺伝的感受性が関与していると考えられています
重要な点:
- 喫煙者全員がCOPDになるわけではなく(約15〜20%)、また非喫煙者でも発症することがあります(約10%)
- ただし、喫煙が圧倒的に最大のリスク因子であり、禁煙が最も重要な予防策です
- COPDは予防可能な疾患です。禁煙により発症を防ぎ、進行を遅らせることができます
病態生理
COPDの病態を理解することは、症状や治療の根拠を理解する上で重要です。
正常な肺の構造と機能
正常な肺では、気管支が枝分かれして最終的に肺胞に至ります。肺胞は約3億個あり、総表面積は約70㎡(テニスコート半面)に達します。肺胞壁は薄く(約0.5μm)、毛細血管が密接しており、ここで酸素と二酸化炭素のガス交換が行われます。
呼気時には、気管支の弾性収縮力と肺胞壁の弾性反跳力により、空気が押し出されます。
COPDにおける病態変化
COPDでは、気道病変と肺胞破壊の両方が起こります。
1. 肺胞の破壊(肺気腫)
タバコ煙などの有害物質により、肺胞壁に慢性炎症が起こります。炎症細胞(好中球、マクロファージ)から放出されるプロテアーゼ(特にエラスターゼ)が、肺胞壁の弾性線維を破壊します。その結果、肺胞壁が壊れて融合し、大きな袋状の空間(ブラ、ブレブ)が形成されます。
肺胞破壊の結果:
- ガス交換面積の減少:肺胞表面積が減少し、酸素の取り込みと二酸化炭素の排出が障害されます
- 弾性反跳力の低下:肺胞壁の弾性線維が破壊されるため、肺の弾性反跳力が失われます
- 気道の虚脱:呼気時に気道を支える構造が失われるため、気道が潰れやすくなります
2. 気道の病変(慢性気管支炎)
慢性炎症により、気道に以下の変化が起こります:
- 気道粘膜の肥厚:炎症により粘膜が腫れます
- 粘液分泌の増加:杯細胞が増生し、粘液分泌が過剰になります
- 気道のリモデリング:慢性炎症により気道壁が線維化して硬くなり、不可逆的な狭窄が生じます
- 気道平滑筋の収縮:炎症により気道が収縮しやすくなります
3. 気流閉塞のメカニズム
COPDでは、不可逆的な気流制限(airflow limitation)が特徴的です。これは主に以下のメカニズムによります:
- 気道の炎症と狭窄:慢性気管支炎により、気道粘膜が肥厚し、粘液分泌が増加して気道が狭くなります
- 気道の虚脱:肺気腫により肺の弾性反跳力が低下すると、呼気時に気道が潰れて閉塞します(動的気道虚脱)
- 気道のリモデリング:慢性炎症により気道壁が線維化して硬くなり、可逆性が失われます
4. 呼気時の空気の閉じ込め(air trapping)
気流閉塞により、呼気時に空気を十分に吐き出せなくなり、肺に空気が残ります。これをair trapping(空気の閉じ込め)と呼びます。その結果、過膨張(hyperinflation)が生じ、肺が常に膨らんだ状態になります。
過膨張により:
- 残気量(RV)の増加:肺に残る空気の量が増えます
- 機能的残気量(FRC)の増加:安静呼気位での肺気量が増加します
- 横隔膜の平坦化:過膨張により横隔膜が押し下げられて平坦になり、呼吸筋の効率が低下します
- ビア樽状胸郭(樽状胸):胸郭が前後に膨らみ、樽のような形になります
5. ガス交換障害
肺胞破壊により、ガス交換面積が減少し、換気血流比不均等が生じます。換気(空気の出入り)は良いが血流が悪い部分や、その逆の部分ができ、効率的なガス交換ができなくなります。
その結果:
- 低酸素血症(PaO2低下):特に進行期や増悪時に顕著
- 高二酸化炭素血症(PaCO2上昇):重症例で見られ、呼吸不全の徴候
6. 肺高血圧症と右心不全(肺性心)
進行したCOPDでは、低酸素血症により肺血管が収縮し、肺高血圧症が生じます。また、肺胞破壊により肺の毛細血管床が減少し、肺血管抵抗が上昇します。肺高血圧症が続くと、右心室に負担がかかり、右心不全(肺性心、cor pulmonale)を合併します。
右心不全の徴候:
- 下腿浮腫
- 肝腫大
- 頸静脈怒張
- 腹水
7. 全身性の影響
COPDは肺だけでなく、全身に影響を及ぼす全身性疾患です:
- 骨格筋萎縮:特に下肢の筋力低下。全身性炎症、低栄養、活動性低下が原因
- 体重減少、るいそう:呼吸仕事量の増加と食欲不振による
- 骨粗鬆症:ステロイド使用、活動性低下、喫煙が原因
- 心血管疾患:COPDは虚血性心疾患のリスク因子
- 抑うつ・不安:約40%に見られます
- 貧血、多血症:低酸素血症が続くと、代償的に赤血球が増加(多血症)
8. 急性増悪(AECOPD: Acute Exacerbation of COPD)
COPDの経過中、呼吸器感染症(細菌、ウイルス)、大気汚染、心不全などにより、呼吸困難が急激に悪化することがあります。これを急性増悪と呼び、入院や人工呼吸管理が必要になることがあり、予後を悪化させる重要な病態です。
増悪により肺機能低下が加速し、QOLが低下し、死亡リスクが上昇します。増悪の予防が極めて重要です。
症状・診断・治療
症状
COPDの症状は、初期にはほとんど無症状であることが多く、徐々に進行します。
主な呼吸器症状
- 労作時呼吸困難:最も重要な症状で、初期には階段や坂道を上る時に息切れを感じます。進行すると、平地歩行や着替えなどの日常生活動作でも息切れが出現し、最終的には安静時にも呼吸困難が見られます。mMRC(modified Medical Research Council)呼吸困難スケールで評価されます:
- Grade 0:激しい運動でのみ息切れ
- Grade 1:平地を急いで歩く、緩い坂を登る時に息切れ
- Grade 2:息切れのため同年代より歩くのが遅い、平地でも立ち止まる
- Grade 3:100m歩行または数分歩行で立ち止まる
- Grade 4:着替えで息切れ、家から出られない
- 慢性の咳と痰:特に慢性気管支炎を合併している場合、朝起きた時の咳と痰が特徴的です。痰は通常、白色または粘液性ですが、感染を合併すると黄色や緑色の膿性痰になります
- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー):気道が狭窄しているため、呼吸時にゼーゼーという音が聞こえます
- 呼気延長:息を吐くのに時間がかかります。「吐きにくい」「息が吐ききれない」と訴えます
身体所見
- ビア樽状胸郭(樽状胸):過膨張により、胸郭が前後に膨らみ、樽のような形になります
- 呼吸補助筋の使用:呼吸困難が強いと、首や肩の筋肉(胸鎖乳突筋、斜角筋)を使って呼吸します
- 口すぼめ呼吸:自然と口をすぼめて息を吐くようになります。これにより気道内圧を保ち、気道虚脱を防ぎます
- 呼吸音の減弱:肺気腫により肺胞が破壊されているため、聴診で呼吸音が小さくなります
- 呼気延長:呼気が吸気より長くなります
- 打診で過共鳴音:過膨張により、胸部を叩くと太鼓のような高い音がします
- チアノーゼ:低酸素血症が進行すると、口唇や爪床が紫色になります
- 右心不全の徴候(進行期):下腿浮腫、肝腫大、頸静脈怒張
全身症状
- 体重減少、るいそう:呼吸仕事量の増加と食欲不振により体重が減少します。進行例では著しいるいそう(cachexia)が見られます
- 全身倦怠感:慢性的な低酸素血症と呼吸困難により、疲れやすくなります
- 骨格筋の萎縮:特に下肢の筋力低下が見られ、歩行困難につながります
- 抑うつ・不安:約40%に見られ、QOLを著しく低下させます
進行期・重症例の症状
- 安静時呼吸困難:常に息苦しく、横になることも困難になります
- 起坐呼吸:横になると呼吸困難が増悪し、座位や前傾姿勢でいることを好みます
- 会話困難:息切れのため、長い文章を話せなくなり、単語でしか話せなくなります
- 食事困難:食事中の息切れにより、食事摂取が困難になります
- 日常生活動作(ADL)の著しい制限:入浴、着替え、トイレ歩行なども困難になります
急性増悪の症状
- 呼吸困難の急激な増悪
- 咳、痰の増加
- 痰の色の変化(黄色、緑色の膿性痰)
- 発熱
- 全身倦怠感の増強
- 意識レベルの低下(高二酸化炭素血症による)
COPD患者の表現型
従来、COPDは臨床的特徴により以下のように分類されていました(現在はあまり使われません):
- Pink puffer(ピンク・パファー):肺気腫が主体。やせ型、呼吸困難が強い、チアノーゼは少ない
- Blue bloater(ブルー・ブローター):慢性気管支炎が主体。肥満、チアノーゼあり、浮腫、多血症
診断
COPDの診断は、臨床症状、喫煙歴、身体所見、スパイロメトリー(呼吸機能検査)を総合して行われます。
病歴聴取
- 労作時呼吸困難、慢性の咳・痰の有無
- 喫煙歴:喫煙指数(1日の本数×年数)を計算。400以上でリスク高
- 職業性・環境性曝露の有無
- 増悪の頻度
スパイロメトリー(最も重要)
COPDの診断にはスパイロメトリーが必須です。気流閉塞の有無を評価します。
COPD診断基準: 気管支拡張薬吸入後に、FEV1/FVC < 0.70であれば、気流閉塞があると判定され、臨床症状と併せてCOPDと診断されます。
- FEV1:1秒量(1秒間に吐き出せる空気の量)
- FVC:努力肺活量(最大限吸って、最大限速く吐き出した空気の量)
- FEV1/FVC:1秒率(FEV1をFVCで割った値)
重要な点:
- 気管支拡張薬吸入後の値で判定します(可逆性を除外するため)
- FEV1/FVC<0.70は不可逆的な気流閉塞を示します
- 喘息では気流閉塞が可逆的(気管支拡張薬で改善)ですが、COPDでは不可逆的です
COPDの重症度分類(GOLD分類): FEV1の予測値に対する割合により、病期(ステージ)を分類します:
- GOLD 1(軽症):FEV1 ≧80%予測値
- GOLD 2(中等症):50% ≦ FEV1 <80%予測値
- GOLD 3(重症):30% ≦ FEV1 <50%予測値
- GOLD 4(最重症):FEV1 <30%予測値
胸部X線検査
COPDの診断補助として実施されます。特徴的所見:
- 肺の過膨張:横隔膜の平坦化、心陰影の縮小
- 肺野の透過性亢進:肺胞破壊により肺が黒く写ります
- ブラ、ブレブ:大きな気腫性変化
胸部CT検査
肺気腫の程度、分布、ブラの有無を詳細に評価できます。低吸収領域(LAA: Low Attenuation Area)として肺気腫が描出されます。手術適応の判断や、肺容量減少手術(LVRS)の適応評価に有用です。
血液ガス分析
進行期や増悪時に実施し、低酸素血症、高二酸化炭素血症の有無を評価します。在宅酸素療法の適応判定にも必要です。
その他の検査
- 呼吸筋力測定:呼吸筋の筋力を評価
- 6分間歩行試験:運動耐容能を評価。SpO2の低下を確認
- 心エコー検査:肺高血圧症、右心不全の評価
- α1-アンチトリプシン測定:若年発症例(40歳未満)や非喫煙者では欠損症を疑い測定
鑑別診断
気管支喘息との鑑別が重要です:
- 喘息:可逆性の気流閉塞、若年発症、アレルギー歴、変動する症状
- COPD:不可逆性の気流閉塞、中高年発症、喫煙歴、進行性の症状
ただし、喘息とCOPDの合併(ACO: Asthma-COPD Overlap)も約10〜20%に見られ、両者の特徴を併せ持ちます。ACOは純粋なCOPDより予後が良い傾向があります。
治療
COPDの治療目標は、症状の軽減、運動耐容能の改善、増悪の予防、QOLの向上、予後の改善です。
禁煙(最も重要)
COPDの進行を遅らせる唯一の確実な方法が禁煙です。禁煙により、肺機能低下速度が正常化し、症状が改善し、生命予後が改善します。既に失われた肺機能は回復しませんが、それ以上の悪化を防ぐことができます。
禁煙支援:
- 禁煙の重要性を繰り返し説明します
- 禁煙補助薬:ニコチン置換療法(ガム、パッチ)、バレニクリン(チャンピックス)
- 禁煙外来の紹介
- 禁煙成功を称賛し、再喫煙しても責めずに再チャレンジを促します
薬物療法
COPD治療の中心は気管支拡張薬です。
吸入気管支拡張薬
- 長時間作用性抗コリン薬(LAMA):チオトロピウム、グリコピロニウムなど。1日1回吸入で、気管支を拡張し、呼吸困難を改善します。COPDの第一選択薬です
- 長時間作用性β2刺激薬(LABA):インダカテロール、ホルモテロールなど。気管支を拡張し、呼吸機能を改善します
- LAMA+LABA配合剤:より強力な気管支拡張効果が得られます。中等症以上で使用されます
- 短時間作用性気管支拡張薬(SABA、SAMA):サルブタモール、イプラトロピウムなど。症状出現時のレスキュー薬として使用します
吸入ステロイド薬(ICS)
COPDの第一選択ではありませんが、以下の場合に使用されます:
- 喘息を合併している場合(ACO)
- 増悪を繰り返す場合(年2回以上、または1回以上の入院)
- 好酸球数が高い場合(血中好酸球≧300/μL)
通常、LABA+ICS配合剤またはLAMA+LABA+ICS(トリプル療法)として使用します。
ICS使用時の注意:肺炎リスクの増加が報告されており、必要性を慎重に判断します。
その他の薬剤
- 去痰薬:カルボシステイン、アンブロキソールなど。痰の喀出を促進
- テオフィリン:気管支拡張作用と抗炎症作用。副作用に注意
- マクロライド少量長期療法:増悪を繰り返す例で検討。アジスロマイシン250mg週3回など
ワクチン接種
感染予防のため、インフルエンザワクチン(毎年)と肺炎球菌ワクチン、COVID-19ワクチンの接種が推奨されます。
酸素療法
進行期で低酸素血症が持続する場合、在宅酸素療法(HOT: Home Oxygen Therapy)が導入されます。
HOTの適応:
- 安静時PaO2 ≦55 Torr
- または安静時PaO2 56〜60 Torrで、睡眠時または運動時の著しい低酸素血症、肺高血圧症、多血症、心不全などを伴う場合
酸素療法により、低酸素血症を改善し、息切れを軽減し、QOLを向上させ、生命予後を改善します。1日15時間以上の酸素吸入が推奨されます。
重要な注意点:COPD患者では、高濃度酸素投与によりCO2ナルコーシス(高二酸化炭素血症による意識障害)を起こすリスクがあるため、通常は低流量(1〜2L/分)から開始します。
呼吸リハビリテーション
呼吸リハビリテーションは、COPDの包括的治療の重要な柱です。以下の要素を含みます:
- 運動療法:歩行訓練、自転車エルゴメーター、筋力トレーニング
- 呼吸訓練:口すぼめ呼吸、腹式呼吸、呼吸筋トレーニング
- 栄養指導:適切な栄養摂取と体重管理
- 患者教育:疾患の理解、服薬指導、増悪の早期発見と対処
- 心理的サポート:不安、抑うつへの対応
呼吸リハビリテーションにより、運動耐容能が改善し、息切れが軽減され、QOLが向上し、増悪による入院が減少します。薬物療法と同等かそれ以上に重要な治療です。
外科的治療
- 肺容量減少手術(LVRS):重症肺気腫で、特に上葉優位の気腫性変化がある場合、気腫性変化の強い部分を切除することで、残存する正常な肺の機能を改善します
- 気管支鏡的肺容量減少術(BLVR):気管支鏡で一方向弁やコイルを留置し、気腫性変化の強い部分を虚脱させる新しい治療法
- 肺移植:若年者(65歳以下)で、内科的治療に反応しない最重症例が適応
急性増悪(AECOPD)の治療
- 気管支拡張薬の増量(SABA+SAMAのネブライザー吸入)
- 全身ステロイド投与(プレドニゾロン30〜40mg/日を5〜14日間)
- 抗菌薬(痰が膿性の場合、または重症例)
- 酸素療法(SpO2 88〜92%を目標)
- 非侵襲的陽圧換気(NPPV)または気管挿管による人工呼吸管理
増悪は予後を悪化させるため、増悪の予防が重要です。禁煙、ワクチン接種、適切な薬物療法、早期発見・早期治療が鍵となります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 非効果的呼吸パターン:気流閉塞と過膨張による呼吸の浅速化
- ガス交換障害:肺胞破壊による換気血流比不均等と低酸素血症
- 非効果的気道浄化:喀痰増加と咳嗽反射の低下
- 活動耐性低下:呼吸困難と全身衰弱による日常生活動作の制限
- 栄養摂取消費バランス異常:呼吸仕事量の増加と食欲不振による体重減少
- 不安・恐怖:進行性疾患であることへの不安、呼吸困難への恐怖
- 社会的孤立:在宅酸素療法や活動制限による社会的孤立
- 非効果的自己健康管理:禁煙継続困難、吸入手技の習得不足
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
COPD患者の多くは、長年の喫煙歴があり、「タバコを吸っていたから仕方ない」という諦めや自責の念を抱いています。また、症状が徐々に進行するため、「年のせい」と考え、医療機関受診が遅れることが多いです。
診断後も、禁煙の継続が最大の課題です。ニコチン依存により禁煙が困難な患者も多く、繰り返しの禁煙支援が必要です。禁煙の重要性を説明しつつ、患者を責めるような態度は避け、「今からでも遅くない」「禁煙すれば進行を遅らせられる」というポジティブなメッセージを伝えます。
吸入薬の正しい使用方法を理解し、継続することも重要です。吸入手技が不適切だと効果が得られないため、実際に吸入してもらい、手技を確認します。
栄養-代謝パターン
COPD患者の約30〜50%に栄養不良が見られます。呼吸仕事量の増加によりエネルギー消費が増え、呼吸困難により食事摂取が困難になるためです。食事中の息切れにより、少量しか食べられなくなります。
体重減少は予後不良のサインであり、BMI<21または体重減少>5%/6ヶ月は栄養不良と判定されます。体重、BMI、血清アルブミン値、総リンパ球数を定期的にモニタリングします。
栄養管理として、高カロリー・高タンパク・高脂肪の食事を少量頻回で提供します。脂肪はエネルギー密度が高く、CO2産生が少ないため推奨されます。食事中の息切れを軽減するため、食前に気管支拡張薬を使用し、酸素流量を上げます。経口栄養補助食品も活用します。
活動-運動パターン
労作時呼吸困難により、活動耐性が著しく低下します。息切れを恐れて活動を避けるようになり、さらに廃用性の筋力低下が進む負のスパイラル(deconditioning spiral)に陥ります。
呼吸状態の継続的モニタリングが重要です。呼吸数、SpO2(安静時と労作時)、呼吸パターン、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を観察します。口すぼめ呼吸や呼吸補助筋の使用も確認します。
活動と休息のバランスを保ちます。過度の安静は廃用症候群を招きますが、過度の活動は低酸素血症を悪化させます。患者のペースに合わせた活動を支援し、息切れが強い時は休息を促します。
呼吸リハビリテーションは極めて有効です。呼吸法の指導(口すぼめ呼吸、腹式呼吸)、運動療法(歩行訓練、筋力トレーニング)を取り入れます。理学療法士と連携し、個別プログラムを実施します。
睡眠-休息パターン
呼吸困難、咳、痰により、睡眠が障害されます。夜間の低酸素血症が進行すると、睡眠の質が低下し、日中の倦怠感が増強します。
睡眠環境を整え、静かで落ち着いた環境を提供します。臥位で呼吸困難が増悪する場合は、半座位または座位で休息できるよう、クッションや椅子を準備します。夜間の酸素投与により、低酸素血症を改善し、睡眠を確保します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の合併にも注意します。COPD患者の約10〜15%にSASが合併し、オーバーラップ症候群と呼ばれ、予後を悪化させます。
コーピング-ストレス耐性パターン
COPDは進行性で治癒困難な疾患であり、患者は大きな心理的ストレスを抱えます。「徐々に息ができなくなる」「苦しんで死ぬのではないか」という恐怖、長年の喫煙による自責の念、家族への負担、役割の喪失、将来への絶望感など、さまざまな問題に直面します。
COPD患者の約40%に不安・抑うつが見られ、これがQOLをさらに低下させ、服薬アドヒアランスを低下させ、増悪リスクを高めます。患者の心理的反応を理解し、傾聴の姿勢を持って接します。怒り、否認、抑うつなども自然な反応であることを理解し、受け止めます。
必要に応じて、精神科医、臨床心理士、緩和ケアチーム、ソーシャルワーカー、患者会(日本呼吸器障害者情報センターなど)と連携します。
役割-関係パターン
呼吸困難により、仕事や家庭内での役割を果たせなくなり、アイデンティティの喪失を感じることがあります。酸素チューブにつながれた生活により、外出が困難になり、社会的孤立が進みます。
在宅酸素療法(HOT)導入後も、ポータブル酸素ボンベを使用すれば外出可能であることを説明します。酸素濃縮器や携帯用酸素ボンベの使用方法を指導し、安全に外出できるよう支援します。
家族の介護負担も大きいため、家族への支援も重要です。介護方法の指導、レスパイトケアの提供、社会資源の紹介を行います。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 正常な呼吸
COPD患者にとって最も重要なニードです。気流閉塞と肺胞破壊により、呼吸が著しく障害されています。
呼吸困難の緩和には:
- 体位の工夫:前傾姿勢(オーバーテーブルに枕を置いてもたれる)が楽なことが多いです。この姿勢により、呼吸補助筋を使いやすくなり、横隔膜の動きが改善します
- 呼吸法の指導:口すぼめ呼吸が最も重要です。鼻から吸って(1〜2秒)、口をすぼめてゆっくり吐く(4〜6秒)ことで、気道内圧を保ち、気道虚脱を防ぎます。腹式呼吸も有効ですが、過膨張が強い患者では効果が限定的なこともあります
- 気管支拡張薬の適切な使用:吸入薬を正しく使用することで、気管支を拡張し、呼吸を楽にします。吸入手技を確認し、必要に応じて修正します
- 酸素療法:低酸素血症がある場合、適切な酸素流量を維持します。ただし、COPD患者では高濃度酸素投与によりCO2ナルコーシスを起こすリスクがあるため、通常は低流量(1〜2L/分)から開始し、SpO2 88〜92%を目標にします(健常者の90%以上とは異なることに注意)
- 環境調整:室温、湿度を適切に保ち、換気を行います。扇風機で顔に風を当てるのも効果的です
喀痰管理も重要です。慢性気管支炎を合併している場合、喀痰が増加します。十分な水分摂取(1日1500〜2000mL)、去痰薬、体位ドレナージ、スクイージング(胸部を軽く叩く)、ハフィング(短く強く息を吐く咳の方法)により喀出を促します。
2. 適切な飲食
呼吸仕事量の増加により、エネルギー消費が増えています。また、食事中の息切れにより摂取量が減少します。高カロリー・高タンパク・高脂肪の食事を少量頻回で提供し、栄養状態を維持します。
食前に気管支拡張薬を使用し、酸素流量を上げる、食事を小分けにする、口すぼめ呼吸を取り入れるなどの工夫をします。食事中の会話を控えめにし、食事に集中できる環境を作ります。
十分な水分摂取も重要で、痰の喀出を促進します。
3. 排泄
活動耐性の低下により、トイレ歩行でも息切れが生じます。ポータブルトイレの使用や、酸素チューブを延長してトイレまで届くようにするなどの工夫をします。
便秘は腹部膨満を引き起こし、横隔膜を押し上げて息切れを増悪させるため、下剤や緩下剤を適切に使用し、排便コントロールを行います。
4. 体位の保持と変換
呼吸を楽にするため、患者が最も楽な体位を見つけられるよう支援します。多くの場合、半座位または前傾姿勢が楽です。クッションや枕、オーバーテーブルを使用し、安楽な姿勢を保持します。
過膨張により横隔膜が平坦化しているため、臥位では呼吸がさらに困難になります。夜間も半座位またはリクライニングチェアで休息する患者もいます。
8. 身体を清潔に保つ
入浴は呼吸困難を増悪させるため、全身状態に応じて、入浴、シャワー浴、清拭を選択します。入浴時は酸素流量を上げ、浴室を温めます。入浴前後の休息も重要です。
進行期では、清拭や部分浴で対応し、無理な入浴は避けます。清潔保持は患者の尊厳と快適さを保つために重要です。
9. 危険の回避
- 感染予防:呼吸器感染症は急性増悪の主要な誘因です。手指衛生を徹底し、人混みを避け、マスクを着用します。インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、COVID-19ワクチンの接種を推奨します
- 転倒予防:低酸素血症や全身衰弱により転倒リスクが高まります。酸素チューブに引っかかる危険もあります。ベッド周囲を整え、歩行時は見守ります
- 酸素機器の安全管理:在宅酸素療法では、火気厳禁です。酸素濃縮器やボンベの周囲2m以内では、タバコ、ガスコンロ、ストーブなどを使用しないよう指導します。酸素使用中の喫煙は火災の原因となり、非常に危険です
- 吸入薬の適切な使用:吸入手技が不適切だと効果が得られません。実際に吸入してもらい、手技を確認します
急性増悪の徴候(呼吸困難の急激な増悪、痰の量や色の変化、発熱、全身倦怠感の増強)に注意し、異常があればすぐに受診するよう指導します。
14. 学習
疾患の病態、経過、治療について、患者の理解度に応じて説明します。COPDは進行性の疾患であるが、禁煙や適切な治療により進行を遅らせることができることを伝えます。
禁煙指導が最優先です。禁煙の重要性を繰り返し説明し、禁煙補助薬や禁煙外来を紹介します。禁煙成功を称賛し、再喫煙しても責めずに再チャレンジを促します。
吸入薬の正しい使用方法を指導します。吸入手技が不適切だと効果が得られないため、実際に吸入してもらい、手技を確認します。各種吸入器(MDI、DPI、SMI)により手技が異なるため、個別に指導します。
在宅酸素療法の指導:
- 酸素濃縮器、ポータブルボンベの使い方
- 酸素流量の調整(安静時と労作時)。COPD患者では高流量は危険であることを説明
- 火気厳禁(タバコ、ガスコンロ、ストーブから2m以上離す)
- トラブル時の対応(停電、機器の故障)
- 外出時の準備(ボンベの残量確認、予備ボンベ)
呼吸法の指導:口すぼめ呼吸、腹式呼吸、呼吸と動作の同調(動作時に息を吐く)
増悪の早期発見と対処:増悪の徴候(呼吸困難の増悪、痰の増加・色の変化、発熱)を説明し、早期受診の重要性を伝えます。
エネルギー温存のテクニック:
- 座って作業する
- 道具を使う(長い柄のブラシなど)
- 動作をゆっくり行う
- こまめに休憩する
利用可能な社会資源:身体障害者手帳、介護保険、訪問看護、呼吸器リハビリテーション、患者会などを紹介します。
看護計画・介入の内容
- 呼吸状態の継続的モニタリング:呼吸数、SpO2(安静時と労作時)、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を定期的に観察します。呼吸パターン(口すぼめ呼吸、呼吸補助筋の使用)も確認します。急性増悪の徴候に注意します
- 呼吸法の指導と実践支援:口すぼめ呼吸、腹式呼吸を指導し、日常生活の中で実践できるよう支援します。動作と呼吸の同調(動作時に息を吐く)も指導します。実際にやって見せ、患者に練習してもらい、フィードバックします
- 気管支拡張薬の適切な使用支援:吸入手技を確認し、正しく使用できるよう指導します。吸入後のうがいも忘れずに行うよう伝えます。吸入薬の効果と副作用について説明します。定期的に手技を再確認します
- 酸素療法の管理:低酸素血症を改善するため、適切な酸素流量を維持します。安静時と労作時でSpO2を測定し、必要に応じて酸素流量を調整します。COPD患者ではSpO2 88〜92%を目標とし、高濃度酸素によるCO2ナルコーシスに注意します
- 呼吸困難の緩和:体位の工夫(前傾姿勢)、呼吸法の指導、環境調整(扇風機、室温・湿度)、薬物療法(気管支拡張薬)により、呼吸困難感を軽減します
- 喀痰管理:十分な水分摂取を促し、去痰薬を適切に使用します。体位ドレナージやスクイージングにより喀出を促進します。喀痰の量、色、粘稠度を観察し、感染の兆候に注意します
- 活動と安静のバランス:過度の安静は廃用症候群を招きますが、過度の活動は低酸素血症を悪化させます。患者のペースに合わせた活動を支援し、疲労や息切れが強い時は休息を促します。エネルギー温存のテクニック(座って作業する、道具を使うなど)を指導します
- 呼吸リハビリテーション:理学療法士と連携し、呼吸筋訓練、呼吸法の指導、運動療法(歩行訓練、自転車エルゴメーター、筋力トレーニング)を実施します。運動耐容能の向上とQOLの改善を目指します。負のスパイラルを断ち切ることが重要です
- 栄養管理:体重、食事摂取量を記録し、栄養状態を評価します。高カロリー・高タンパク・高脂肪の食事を少量頻回で提供します。食事中の息切れを軽減するため、食前に気管支拡張薬を使用し、酸素流量を上げます。経口栄養補助食品も活用します
- 禁煙支援:禁煙の重要性を繰り返し説明します。患者の準備段階を見極め、禁煙補助薬(ニコチン置換療法、バレニクリン)や禁煙外来を紹介します。禁煙成功を称賛し、再喫煙しても責めずに再チャレンジを促します。家族の協力も得ます
- 感染予防指導:手洗い、うがい、マスク着用、人混みを避けることを指導します。インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、COVID-19ワクチンの接種を推奨します。感染徴候(発熱、痰の色の変化、呼吸困難の増悪)があれば早期受診するよう伝えます
- 心理的支援:患者の思いを傾聴し、不安や恐怖を受け止めます。進行性疾患への恐怖、自責の念、将来への絶望感に対し、希望を支える関わりを意識します。「今できること」に焦点を当て、小さな目標の実現を支援します。必要に応じて専門家(精神科医、臨床心理士)と連携します
- 在宅酸素療法の指導:酸素濃縮器、ポータブルボンベの使用方法、安全管理(火気厳禁)、トラブル時の対応、外出時の準備などを具体的に指導します。実際に機器を操作してもらい、理解度を確認します。酸素使用中の喫煙は絶対に禁止であることを強調します
- 家族への支援:家族の介護負担を理解し、サポートします。在宅療養の準備、介護方法の指導、社会資源の紹介を行います。家族の疲労やストレスにも配慮し、レスパイトケアを提案します。家族も禁煙することが望ましいです
- 多職種連携:医師、薬剤師、栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカー、訪問看護師などと連携し、包括的なケアを提供します。定期的なカンファレンスで情報共有し、ケア方針を統一します
- アドバンス・ケア・プランニング(ACP):患者の価値観、人生の目標、医療に対する希望を確認します。終末期医療についての意思決定を支援し、患者の意思を尊重したケアを提供します
よくある疑問・Q&A
Q: COPDは治りますか?一度破壊された肺は元に戻りますか?
A: 残念ながら、一度破壊された肺胞は元に戻りません。COPDは進行性の疾患で、完治は困難です。ただし、禁煙により、肺機能低下の速度を正常化させることができます。つまり、それ以上の悪化を防ぐことができます。
また、適切な治療(気管支拡張薬、呼吸リハビリテーション、酸素療法など)により、症状を軽減し、QOL(生活の質)を改善し、増悪を予防し、生命予後を改善することができます。
COPDは「治す」のではなく「上手に付き合う」疾患です。適切な管理により、多くの患者は充実した生活を送ることができます。
Q: タバコをやめても意味がないのでしょうか?もう手遅れですか?
A: いいえ、今からでも遅くありません。禁煙は、COPDの進行を遅らせる最も確実で効果的な方法です。禁煙により:
- 肺機能低下速度が正常化します(非喫煙者と同じ速度になります)
- 症状(咳、痰、息切れ)が改善します
- 増悪の頻度が減少します
- 生命予後が改善します
- 肺がんや心血管疾患のリスクも低下します
既に失われた肺機能は回復しませんが、それ以上の悪化を防ぐことができます。COPD患者にとって、禁煙は最も重要な治療です。
禁煙は難しいかもしれませんが、禁煙補助薬(ニコチン置換療法、バレニクリン)や禁煙外来のサポートを受けることで、成功率が上がります。ぜひチャレンジしてください。何度失敗しても、再挑戦することが大切です。
Q: 在宅酸素療法を始めると言われました。酸素を使うと酸素がないと生きられなくなるのではないですか?
A: これはよくある誤解です。酸素は依存性のある薬物ではありません。酸素を使うから酸素なしで生きられなくなるのではなく、肺機能が低下して低酸素血症が進行したから酸素が必要になったのです。
在宅酸素療法(HOT)により:
- 低酸素血症が改善され、息切れが軽減します
- 日常生活動作が楽になり、QOLが向上します
- 肺高血圧症の進行を遅らせます
- 生命予後が改善します(1日15時間以上の酸素吸入で)
酸素は「制限」ではなく、「より楽に生活するための道具」と考えてください。ポータブル酸素ボンベを使用すれば外出も可能で、買い物や散歩、旅行も楽しめます。
Q: 酸素を吸いすぎると危険と聞きました。本当ですか?
A: COPD患者では、高濃度酸素投与により二酸化炭素(CO2)ナルコーシスを起こすリスクがあります。
通常、呼吸は主にCO2濃度の上昇により刺激されますが、重症COPD患者では慢性的に高CO2血症があり、CO2による呼吸刺激が鈍くなっています。その代わり、低酸素血症が呼吸刺激の主役になっています。
高濃度酸素を投与すると、低酸素血症が改善されて呼吸刺激が弱まり、呼吸回数が減少し、CO2がさらに貯留して意識障害を起こすことがあります。これがCO2ナルコーシスです。
ただし、これは高濃度酸素(高流量)を投与した場合に起こるリスクで、通常の在宅酸素療法(1〜2L/分程度)では問題ありません。医師の指示通りの酸素流量を守ることが重要です。勝手に流量を上げてはいけません。
Q: 呼吸リハビリテーションは本当に効果がありますか?息切れするのに運動して大丈夫ですか?
A: はい、呼吸リハビリテーションは非常に効果的です。薬物療法と同等かそれ以上に重要な治療です。
COPD患者は、息切れを恐れて活動を避けるようになり、さらに筋力が低下し、ますます動けなくなるという負のスパイラルに陥ります。呼吸リハビリテーションは、この悪循環を断ち切ります。
呼吸リハビリテーションにより:
- 運動耐容能(どれだけ動けるか)が改善します
- 息切れが軽減されます
- QOL(生活の質)が向上します
- 不安・抑うつが改善します
- 増悪による入院が減少します
運動は、理学療法士が個別に評価し、適切な強度で行われます。SpO2をモニタリングしながら、安全に実施できます。息切れしながらも、少しずつ活動を増やしていくことで、身体が適応し、楽に動けるようになります。
Q: COPD患者さんが急に呼吸困難を訴えたらどうすればいいですか?
A: まず呼吸状態を迅速に評価します。SpO2、呼吸数、呼吸パターン、チアノーゼの有無、意識レベルを確認します。急性増悪、気胸、心不全、肺塞栓症などの可能性を考えます。
応急処置:
- 患者を楽な体位(半座位、前傾姿勢)にします
- 酸素投与を開始または流量を調整します(医師の指示に基づく)。ただし、COPD患者では高濃度酸素によるCO2ナルコーシスに注意し、通常は低流量から開始します。SpO2 88〜92%を目標にします
- 口すぼめ呼吸を促します
- 穏やかに声をかけ、「ゆっくり呼吸してください」「そばにいますよ」と安心させます
- 直ちに医師に報告し、指示を仰ぎます
医師の診察により原因が特定されれば、それに応じた治療(気管支拡張薬、ステロイド、抗菌薬、NPPVなど)が行われます。
Q: 家族がCOPDの終末期です。自宅で看取りたいのですが、可能ですか?
A: はい、可能です。適切なサポート体制があれば、在宅での看取りは実現できます。
在宅療養のサポート:
- 訪問診療:医師が定期的に自宅を訪問し、症状管理や処方を行います
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、症状観察、医療処置、療養指導を行います
- 訪問介護:ヘルパーが身体介護や生活支援を行います
- 24時間対応:多くの在宅医療機関は24時間連絡可能で、緊急時にも対応します
在宅でも、酸素療法、モルヒネによる呼吸困難の緩和、NPPV、点滴などの医療処置が可能です。症状緩和ケアにより、苦痛を最小限にすることができます。
ただし、家族の介護負担は大きいため、レスパイトケアの利用も検討します。また、「自宅で」という希望が変わることもあり、柔軟に対応することが大切です。
まずは、主治医、緩和ケアチーム、地域の訪問看護ステーション、地域包括支援センターなどに相談してみてください。
まとめ
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、タバコ煙などの有害物質の長期吸入により、気道と肺に慢性炎症が起こり、不可逆的な気流制限をきたす疾患です。日本には約530万人の潜在患者がいますが、診断・治療を受けているのは約1割のみです。
病態の本質は、肺胞破壊(肺気腫)と気道病変(慢性気管支炎)による不可逆的な気流制限です。一度破壊された肺胞は元に戻らず、進行性に呼吸機能が低下します。過膨張により横隔膜が平坦化し、呼吸効率が低下します。
症状は、労作時呼吸困難が特徴的で、進行すると安静時にも呼吸困難が出現します。慢性の咳、痰、呼気延長、ビア樽状胸郭も見られます。診断はスパイロメトリーが必須で、FEV1/FVC<0.70で気流閉塞と判定されます。
治療の最優先は禁煙であり、肺機能低下の進行を正常化させる唯一確実な方法です。薬物療法では気管支拡張薬(LAMA、LABA)が中心で、進行期では在宅酸素療法、呼吸リハビリテーションが重要です。急性増悪は予後を悪化させるため、予防と早期治療が重要です。
看護の要点は、呼吸法の指導(口すぼめ呼吸)、呼吸困難の緩和、禁煙支援、栄養管理、呼吸リハビリテーション、心理的支援です。体位の工夫、気管支拡張薬の適切な使用、酸素療法(SpO2 88〜92%目標)により呼吸困難を緩和します。
COPD患者は、進行性で治癒困難な疾患に直面し、大きな不安を抱えています。傾聴の姿勢を持ち、患者の思いを受け止め、「今できること」に焦点を当てた希望を支える関わりが大切です。禁煙の重要性を伝えつつ、患者を責めず、ともに歩む姿勢が重要です。
実習では、呼吸困難という苦痛に寄り添い、その人らしく生きることを支える看護を実践しましょう。COPDは予防可能な疾患であり、禁煙により発症・進行を防げることを啓発することも看護師の重要な役割です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

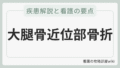
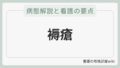
コメント