疾患概要
定義
肺結核とは、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)が肺に感染することで起こる感染症です。結核菌は主に飛沫核感染(空気感染)により人から人へ伝播し、感染後に免疫力が低下した際に発症します。
肺結核は初感染結核と二次結核(再活性化結核)に分類されます。初感染結核は初めて結核菌に感染した際に発症するもので、主に小児に見られます。二次結核は、過去に感染した結核菌が長期間体内に潜伏し、免疫力低下時に再び活動を始めることで発症するもので、成人に多く見られます。
結核は感染症法で2類感染症に指定されており、診断した医師は直ちに保健所への届出が義務付けられています。また、排菌している患者は入院勧告の対象となり、感染拡大防止のための隔離が必要です。
疫学
日本における結核患者数は減少傾向にありますが、依然として年間約1万人の新規患者が報告されています。2023年の罹患率は人口10万人あたり約8.2人で、欧米先進国と比較するとまだ高い水準にあります。
高齢者に多く、新規患者の約60%が70歳以上です。これは、若い頃に結核菌に感染した人が、加齢による免疫力低下により発症するケースが多いためです。また、都市部での罹患率が高く、特に大阪、東京などの大都市圏で患者数が多い傾向があります。
近年は外国生まれの結核患者も増加しており、特に20〜30代では約30%を占めています。結核高蔓延国からの来日者や技能実習生での発症が問題となっています。
ハイリスク群として、HIV感染者、糖尿病患者、透析患者、免疫抑制薬使用者、栄養不良者、ホームレス、医療従事者などが挙げられます。
原因
肺結核の原因は結核菌の感染です。感染経路は主に飛沫核感染(空気感染)で、排菌している結核患者が咳やくしゃみをした際に飛散した結核菌を含む微細な飛沫核(5μm以下)を吸い込むことで感染します。
結核菌は非常に小さく軽いため、空気中に長時間浮遊し、換気の悪い密閉空間では感染リスクが高まります。ただし、すべての結核患者が感染源となるわけではなく、喀痰塗抹検査で陽性(排菌陽性)の患者からの感染が主です。
発症の危険因子
- HIV感染症(最も重要なリスク因子)
- 免疫抑制薬の使用(ステロイド、生物学的製剤など)
- 糖尿病
- 慢性腎不全、透析患者
- 栄養不良、低体重
- 悪性腫瘍
- 高齢
- 喫煙
- アルコール依存症
- 塵肺症(珪肺)
感染しても必ず発症するわけではなく、感染者のうち約10〜15%が生涯で発症すると言われています。感染後2年以内の発症が最も多く、その後は免疫力が低下した時に発症します。
病態生理
肺結核の病態は、感染→免疫応答→組織破壊という過程をたどります。
感染と初期反応
結核菌が気道から吸入されると、肺胞に到達し、肺胞マクロファージに貪食されます。しかし、結核菌は細胞内寄生菌であり、マクロファージ内で生き延び、増殖することができます。初感染では結核菌は肺の中下肺野に到達し、そこで初期病変(初期変化群)を形成します。
細胞性免疫の成立
感染後2〜8週間で、T細胞を中心とした細胞性免疫が成立します。感作されたT細胞がマクロファージを活性化し、結核菌を封じ込めようとします。この過程で類上皮細胞やラングハンス型巨細胞を含む肉芽腫(結核結節)が形成されます。
肉芽腫の中心部では、結核菌と炎症細胞が壊死し、乾酪壊死(チーズのようにもろい壊死組織)が生じます。これが結核に特徴的な病理所見です。乾酪壊死部分は酸素や栄養が乏しく、結核菌の増殖が抑えられるため、多くの場合は石灰化して治癒に向かいます。
初感染結核と潜伏感染
免疫が正常に働く場合、初感染では結核菌は完全には排除されず、肉芽腫内に休眠状態で残ります。これを潜伏結核感染(LTBI: Latent TB Infection)と呼びます。この状態では症状はなく、他人への感染力もありませんが、結核菌は生きたまま体内に存在しています。
二次結核(再活性化)
免疫力が低下すると、休眠していた結核菌が再び活動を始めます。これが二次結核(再活性化結核)です。成人の肺結核の大部分がこのタイプで、特に肺尖部(上葉の尖端部分)に好発します。これは、肺尖部が酸素濃度が高く、結核菌の増殖に適しているためです。
活動性結核では、乾酪壊死が気管支に穿破して空洞形成が起こります。空洞内には大量の結核菌が存在し、これが喀痰に混じって排出されることで、他人への感染源となります。空洞壁から気管支を通じて結核菌が散布され、気管支播種により同側や対側の肺に新たな病変を形成します。
粟粒結核
免疫力が著しく低下している場合、結核菌が血行性に全身に播種され、粟粒結核(miliary tuberculosis)が発症します。肺だけでなく、肝臓、脾臓、骨髄、髄膜など全身の臓器に小さな結核病変(粟粒大の結節)が無数に形成される重症型です。
このように、肺結核の病態は免疫と結核菌の攻防であり、免疫力の状態が発症と進行を左右します。
症状・診断・治療
症状
肺結核の症状は緩徐に進行し、初期には非特異的な症状が多いため、診断が遅れることがあります。
主な呼吸器症状
- 持続する咳:2週間以上続く咳が特徴的で、最も重要な症状です
- 痰:初期は少量ですが、進行すると膿性痰や血痰が出ます
- 喀血:空洞形成により血管が破綻すると、大量喀血を起こすこともあります
- 呼吸困難:進行例や広範囲の病変で見られます
- 胸痛:胸膜に病変が及ぶと胸膜炎を起こし、胸痛が出現します
全身症状
- 微熱:特に午後から夕方にかけての37℃台の微熱が続きます
- 寝汗:夜間に大量の寝汗をかくことが特徴的です
- 全身倦怠感:疲れやすく、だるさが続きます
- 体重減少:食欲低下と代謝亢進により、体重が減少します
- 食欲不振:徐々に食欲が落ちていきます
高齢者では典型的な症状が乏しく、食欲不振や体重減少、倦怠感などの非特異的症状のみの場合があります。また、糖尿病患者では症状が急速に進行することがあります。
重症型の症状 粟粒結核では高熱、呼吸困難、全身衰弱が急速に進行し、髄膜炎を合併すると頭痛、意識障害、けいれんなどが出現します。
診断
肺結核の診断は、臨床症状、画像所見、細菌学的検査を総合して行います。
胸部X線・CT検査 肺尖部や上葉に陰影、空洞形成、気管支播種像(粒状影の散布)などが見られます。陳旧性病変では石灰化や胸膜肥厚を認めます。粟粒結核では両側肺野にびまん性の粒状影が無数に見られます。ただし、画像所見だけでは確定診断できないため、細菌学的検査が必須です。
喀痰検査(最も重要)
- 塗抹検査:喀痰を染色(チール・ネルゼン染色、蛍光染色)して顕微鏡で観察します。結核菌は抗酸菌として赤く染まります。結果は数時間〜1日で判明し、塗抹陽性であれば感染力が強いと判断されます
- 培養検査:結核菌を培養して確定診断します。結果判明まで4〜8週間かかりますが、菌種同定と薬剤感受性検査が可能です
- 核酸増幅検査(PCR法):結核菌のDNAを検出する方法で、1〜2日で結果が出ます。迅速診断に有用ですが、死菌も検出するため培養検査の補助として使用されます
ツベルクリン反応(ツ反)・IGRA検査
- ツベルクリン反応:結核感染の有無を調べる皮膚テストですが、BCG接種の影響を受けるため、日本ではスクリーニングとしての有用性は限定的です
- IGRA(インターフェロン-γ遊離試験):血液検査で結核感染を診断します。T-SPOT、クォンティフェロンなどがあり、BCG接種の影響を受けないため、潜伏結核感染の診断に有用です。ただし、活動性結核と潜伏感染の区別はできません
気管支鏡検査 喀痰が採取できない場合や、気管支結核が疑われる場合に行います。気管支洗浄液を採取して細菌検査を行います。
確定診断 喀痰培養で結核菌が検出されることで確定診断となります。塗抹陽性でも、培養で他の抗酸菌(非結核性抗酸菌)が検出される場合があるため、培養結果が重要です。
治療
肺結核の治療は多剤併用化学療法が原則で、標準治療では4剤併用療法を行います。
標準治療(初回治療・薬剤感受性結核)
初期強化期(2ヶ月間)
- イソニアジド(INH)
- リファンピシン(RFP)
- ピラジナミド(PZA)
- エタンブトール(EB)またはストレプトマイシン(SM)
の4剤を毎日内服します。この時期に結核菌を大量に殺菌し、再発を防ぎます。
維持期(4ヶ月間)
- イソニアジド(INH)
- リファンピシン(RFP)
の2剤を継続します。残存する休眠菌を殺菌します。
合計6ヶ月間の治療が標準で、治療中断は再発や薬剤耐性化のリスクとなるため、服薬遵守が極めて重要です。
直接服薬確認療法(DOTS: Directly Observed Treatment, Short-course) 確実な服薬を支援するため、医療従事者や保健師が患者の服薬を直接確認する方法です。特に服薬中断のリスクが高い患者(ホームレス、アルコール依存症、精神疾患など)に対して実施されます。
多剤耐性結核の治療 イソニアジドとリファンピシンの両方に耐性がある場合を多剤耐性結核(MDR-TB)と呼び、治療は非常に困難です。注射薬を含む5〜6剤を18〜24ヶ月間使用する必要があり、治療成功率は50〜70%程度です。
副作用のモニタリング 抗結核薬には肝障害、視神経障害、腎障害、末梢神経障害などの副作用があるため、定期的な血液検査、肝機能検査、視力検査などのモニタリングが必要です。
隔離と退院基準 排菌陽性の患者は感染症病床に隔離され、陰圧個室で管理されます。退院基準は、2週間以上の適切な治療を受け、喀痰塗抹検査が連続3回陰性になることです。退院後も保健所の管理下で治療を継続します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 非効果的気道浄化:咳嗽、喀痰による気道クリアランスの低下
- 感染伝播リスク状態:排菌による他者への感染拡大の可能性
- 栄養摂取消費バランス異常(摂取不足):食欲不振、体重減少による栄養状態の悪化
- 非効果的自己健康管理:長期服薬の必要性に関する知識不足や服薬中断のリスク
- 社会的孤立:隔離治療による孤独感、結核への偏見による社会的孤立
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン 多くの患者は、初期症状が軽微なため医療機関受診が遅れ、診断時には既に進行していることがあります。結核と診断されることで、感染症への恐怖や周囲への感染不安を抱きます。隔離治療の必要性を理解していても、精神的な負担は大きく、特に高齢者では環境変化による見当識障害のリスクもあります。
服薬アドヒアランスに関する評価が非常に重要です。治療期間が6ヶ月と長く、症状が改善すると自己判断で服薬を中断する患者もいるため、服薬の重要性について繰り返し説明し、服薬状況を確認します。アルコール依存症、精神疾患、ホームレスなどの社会的背景がある場合は、DOTS実施の必要性を検討します。
栄養-代謝パターン 結核患者の多くは食欲不振と体重減少を認めます。結核による代謝亢進、炎症による消耗、抗結核薬の副作用(食欲不振、悪心)などが原因です。栄養状態の悪化は免疫力をさらに低下させ、治療効果を妨げるため、積極的な栄養管理が必要です。
体重、BMI、血清アルブミン値、総リンパ球数などで栄養状態を評価し、高カロリー・高タンパク食を提供します。食事摂取量が不十分な場合は、経口栄養補助食品の使用や、必要に応じて輸液による栄養補給を検討します。
また、抗結核薬の副作用である肝障害の早期発見のため、定期的に肝機能検査(AST、ALT、ビリルビン)を確認します。悪心や食欲不振が強い場合は、副作用の可能性も考慮し、医師に報告します。
活動-運動パターン 全身倦怠感、呼吸困難、栄養状態の悪化により、活動耐性が低下しています。排菌陽性の間は隔離個室での生活となり、活動範囲が制限されます。長期臥床は筋力低下や廃用症候群のリスクとなるため、症状に応じて適度な運動を促します。
呼吸状態の観察が重要で、咳嗽の頻度や性状、喀痰の量と性状、呼吸困難の程度、SpO2、呼吸音の聴診を定期的に行います。喀血の既往がある場合は、大量喀血のリスクがあるため、バイタルサインの変化に注意します。
睡眠-休息パターン 咳嗽により夜間の睡眠が妨げられることが多く、特に臥位では咳が増悪しやすいです。寝汗も特徴的で、夜間に大量の発汗により寝衣や寝具が濡れ、不快感から睡眠が障害されます。隔離個室での孤独感や疾患への不安も、睡眠障害の原因となります。
咳嗽軽減のため、上半身を挙上した体位や、加湿器の使用が有効です。寝汗がある場合は、こまめに寝衣交換や清拭を行い、快適な睡眠環境を整えます。
役割-関係パターン 結核への偏見や差別はまだ存在し、患者は社会的孤立感を感じやすいです。隔離治療により家族や友人との面会が制限され、孤独感が増強します。職場や学校への復帰に対する不安、家族への感染不安も大きなストレスとなります。
患者の心理的支援が重要で、傾聴の姿勢を持ち、不安や悩みを表出できる環境を作ります。家族への接触者健診の必要性を説明し、感染予防策を指導します。退院後の社会復帰支援として、保健所や医療ソーシャルワーカーとの連携も必要です。
コーピング-ストレス耐性パターン 長期治療、隔離、偏見、経済的負担など、結核患者が抱えるストレスは多岐にわたります。特に若年者や働き盛りの患者では、休職による経済的困窮、キャリアへの影響など、深刻な問題が生じることがあります。
ストレス対処能力を評価し、適切なサポート体制を整えます。医療費は公費負担制度があり、経済的支援が受けられることを説明します。心理的サポートが必要な場合は、精神科や臨床心理士との連携も検討します。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 正常な呼吸 咳嗽や喀痰により気道クリアランスが低下しているため、効果的な喀痰排出を支援します。体位ドレナージ、十分な水分摂取、加湿により痰の喀出を促します。喀血の既往がある場合は、激しい咳嗽を避け、安静を保つよう指導します。
呼吸状態の悪化や大量喀血の徴候(血痰の増加、胸痛、呼吸困難の増悪)に注意し、異常があればすぐに医師に報告します。
2. 適切な飲食 食欲不振や体重減少に対し、高カロリー・高タンパクの食事を少量頻回で提供します。患者の嗜好を考慮し、食べやすい食事形態を工夫します。栄養補助食品の活用も有効です。
水分摂取は喀痰の喀出を促進するため、1日1500〜2000mL程度を目標に勧めます。ただし、抗結核薬の副作用で悪心がある場合は無理に摂取させず、症状に応じて対応します。
6. 衣類の着脱 寝汗が多いため、吸湿性の良い寝衣を選び、こまめに交換します。発汗後は冷えないよう注意し、清拭や更衣を行います。
8. 身体を清潔に保つ 寝汗により皮膚が不快な状態になりやすいため、毎日の清拭や入浴(可能であれば)により清潔を保ちます。口腔内も乾燥しやすいため、口腔ケアを定期的に実施します。
9. 危険の回避 感染拡大防止が最優先です。排菌陽性の患者は陰圧個室に隔離し、入室時は医療従事者はN95マスク(微粒子用マスク)を着用します。患者が個室外に出る際は、サージカルマスクを着用させます。
喀痰などの分泌物は感染性廃棄物として適切に処理し、リネンや食器も専用のものを使用するか、適切に消毒します。手指衛生を徹底し、接触感染予防も行います。
大量喀血のリスクがある患者では、急変時の対応(止血剤の準備、医師への連絡体制)を整えておきます。
12. 遊び、レクリエーション 隔離により活動が制限されるため、精神的な負担が大きくなります。読書、音楽、テレビ、スマートフォンなど、個室内でできる気分転換の方法を提案します。可能であれば、窓から外が見える個室を提供し、開放感を持てるよう配慮します。
14. 学習 結核の病態、感染経路、治療の必要性、服薬の重要性について、患者の理解度に応じて繰り返し説明します。特に、服薬中断が再発や薬剤耐性化を招くことを強調します。退院後の生活指導(服薬継続、定期受診、咳エチケット、栄養管理、禁煙)も丁寧に行います。
家族や接触者への感染予防教育も重要で、接触者健診の必要性、感染の兆候、予防策について説明します。
看護計画・介入の内容
- 標準予防策+空気感染予防策の徹底:排菌陽性患者は陰圧個室に隔離し、入室時はN95マスクを着用します。ガウンや手袋も適宜使用し、退室時は手指衛生を確実に行います。患者が個室外に出る際は必ずサージカルマスクを着用させます
- 喀痰の観察と管理:喀痰の量、性状(膿性、血性)、色、臭いを観察し、記録します。喀痰採取は適切な方法で行い、培養検査や塗抹検査の結果をモニタリングします。喀血の兆候があれば直ちに医師に報告します
- 服薬管理と教育:抗結核薬の服薬状況を毎日確認し、服薬時間や方法を指導します。副作用(肝障害、視力障害、末梢神経障害、胃腸症状)について説明し、異常があれば報告するよう伝えます。DOTSが必要な患者では、保健師と連携して服薬確認体制を整えます
- 栄養状態の評価と改善:体重測定、食事摂取量の記録、血液検査(アルブミン、総リンパ球数)により栄養状態を評価します。高カロリー・高タンパクの食事を提供し、嗜好を考慮して食欲を促進します。栄養補助食品も活用します
- 呼吸状態のモニタリング:咳嗽の頻度、喀痰の量、呼吸困難の程度、SpO2、呼吸音を定期的に観察します。喀血や大量喀血の徴候に注意し、バイタルサインの変化を見逃しません
- 副作用モニタリング:定期的な血液検査(肝機能、腎機能、血算)の結果を確認し、肝障害や腎障害の早期発見に努めます。視力障害(エタンブトールの副作用)の有無を確認し、視力検査を定期的に実施します。末梢神経障害(イソニアジドの副作用)に対しては、しびれや痛みの有無を確認します
- 心理的支援:隔離による孤独感や不安に対し、傾聴の姿勢を持ち、患者の思いを受け止めます。結核への偏見や差別に対する不安も理解し、正しい知識の普及に努めます。定期的に訪室し、コミュニケーションを取ることで孤立感を軽減します
- 退院指導と保健所連携:退院後も保健所の管理下で治療を継続する必要性を説明します。定期受診、服薬継続、咳エチケット(マスク着用、手洗い)、栄養管理、禁煙などの生活指導を行います。保健師と情報共有し、退院後のフォローアップ体制を整えます
- 接触者健診の説明:家族や同居者への接触者健診の必要性を説明し、保健所への連絡を促します。感染予防策(換気、マスク着用、手洗い)についても指導します
- 清潔保持と環境整備:寝汗が多いため、こまめに寝衣交換や清拭を行います。個室内の換気を適切に行い、清潔な環境を維持します。喀痰や血痰で汚染されたティッシュなどは感染性廃棄物として適切に処理します
よくある疑問・Q&A
Q: 結核はどのように感染するのですか?普通の会話でもうつりますか?
A: 結核は飛沫核感染(空気感染)によって伝播します。排菌している結核患者が咳やくしゃみをすると、結核菌を含む非常に小さな飛沫核(5μm以下)が空気中に放出され、それを吸い込むことで感染します。飛沫核は軽いため空気中に長時間浮遊し、換気の悪い密閉空間では感染リスクが高まります。ただし、普通の会話程度では感染リスクは低く、長時間の密接な接触が主な感染経路です。また、食器や衣類を介した接触感染はほとんどありません。重要なのは、すべての結核患者が感染源となるわけではなく、喀痰塗抹検査で陽性(排菌陽性)の患者からの感染が主であることです。
Q: BCG接種を受けていれば結核にかからないのですか?
A: BCG接種は結核予防に一定の効果がありますが、完全に予防できるわけではありません。BCGは特に乳幼児の重症結核(粟粒結核、結核性髄膜炎)の予防には高い効果がありますが、成人の肺結核に対する予防効果は限定的です。日本では生後1歳までにBCG接種が定期接種として行われていますが、その効果は10〜15年程度で減弱すると言われています。そのため、成人では免疫力が低下した際に発症することがあります。BCG接種を受けていても、結核の症状があれば医療機関を受診することが重要です。
Q: 結核の治療期間はなぜ6ヶ月も必要なのですか?途中でやめてはいけないのですか?
A: 結核菌は増殖速度が非常に遅く、また一部の菌は休眠状態で潜んでいるため、完全に殺菌するには長期間の治療が必要です。治療開始後2〜3週間で症状は改善し、塗抹検査も陰性化しますが、この時点ではまだ体内に休眠菌が残っています。これらを完全に殺菌しないと再発のリスクが高くなります。
服薬を途中でやめることは非常に危険です。中途半端に治療を中断すると、残存した結核菌が薬剤に対して耐性を獲得し、薬剤耐性結核が発生します。多剤耐性結核は治療が極めて困難で、治療期間が2年近くに及び、治療成功率も低下します。そのため、症状が消えても自己判断で服薬を中断せず、医師の指示通り6ヶ月間しっかりと服薬を継続することが絶対に必要です。
Q: 結核患者さんの看護をする時、マスクはどのようなものを使えばいいですか?普通のマスクではダメですか?
A: 排菌陽性の結核患者さんの個室に入る際は、N95マスク(微粒子用マスク)の着用が必要です。普通のサージカルマスクでは、結核菌を含む飛沫核(5μm以下)を通過させてしまうため、空気感染を防ぐことができません。N95マスクは0.3μmの微粒子を95%以上捕集できる高性能マスクで、顔に密着させて装着することで空気感染を防ぎます。
装着時はフィットテスト(マスクが顔に密着しているか確認するテスト)を行い、隙間がないことを確認します。マスクのサイズが合っていないと効果がないため、自分に合ったサイズを選ぶことも重要です。患者さんが個室外に出る際は、患者さん自身がサージカルマスクを着用すれば、周囲への感染リスクを減らすことができます。
Q: 結核はもう昔の病気ではないのですか?若い人でもかかりますか?
A: 結核は決して「昔の病気」ではなく、現在でも日本で年間約1万人が新たに発症している現役の感染症です。確かに患者数は減少傾向にありますが、依然として2類感染症として重要な疾患です。
若い人でもかかります。特に20〜30代では、結核高蔓延国(東南アジア、アフリカなど)からの来日者や外国人技能実習生での発症が増えています。また、免疫抑制薬を使用している患者(関節リウマチの生物学的製剤使用者など)、HIV感染者、栄養状態が悪い人などは、年齢に関係なく発症リスクが高まります。若年者でも、2週間以上続く咳や微熱、体重減少などの症状があれば、結核を疑って医療機関を受診することが大切です。
Q: 結核患者さんが使った食器や衣類は特別な消毒が必要ですか?
A: 結核は空気感染であり、食器や衣類を介した接触感染はほとんどありません。したがって、通常の洗浄・洗濯で十分です。食器は他の患者と同様に食器洗浄機で洗浄すれば問題ありません。衣類やリネンも通常の洗濯で構いませんが、喀痰や血痰で汚染されたものは感染性廃棄物として処理するか、手袋を着用して取り扱い、十分に洗浄します。
特別な消毒が必要なのは、喀痰や血液で汚染された物品です。結核菌は乾燥や紫外線に弱いため、日光に当てることも有効です。ただし、医療機関では標準予防策に基づき、すべての患者の血液・体液に接触する可能性がある場合は手袋を着用し、適切に処理することが基本です。
まとめ
肺結核は結核菌による感染症で、飛沫核感染(空気感染)により伝播し、現在でも年間約1万人が日本で発症している重要な疾患です。決して「昔の病気」ではなく、特に高齢者や免疫力が低下している人に多く見られます。
病態の本質は、結核菌と宿主の免疫の攻防です。感染後に細胞性免疫が成立し、肉芽腫を形成して結核菌を封じ込めますが、免疫力が低下すると再活性化して発症します。肺尖部の空洞形成が特徴的で、この空洞内の大量の結核菌が喀痰とともに排出され、感染源となります。
診断は喀痰検査(塗抹、培養、PCR)が最も重要で、胸部X線やCT検査、IGRA検査も併用されます。治療は多剤併用化学療法が原則で、標準治療では6ヶ月間の服薬が必要です。服薬中断は再発や薬剤耐性化を招くため、服薬遵守が治療成功の鍵となります。
看護の要点は、空気感染予防策の徹底です。排菌陽性患者は陰圧個室に隔離し、医療従事者はN95マスクを着用します。患者の呼吸状態、栄養状態、服薬状況を継続的にモニタリングし、副作用の早期発見にも努めます。隔離による孤独感や結核への偏見に対する心理的支援も重要です。
患者教育では、服薬継続の重要性、退院後の定期受診、咳エチケット、栄養管理、禁煙などを指導します。保健所との連携により、DOTSや接触者健診を適切に実施し、感染拡大防止と再発予防に努めます。
実習では、感染予防策を確実に実施し、自分自身と周囲の人を守ることが最優先です。患者さんは隔離や偏見により精神的に辛い状況にあるため、正しい知識を持ち、温かく寄り添う姿勢が大切です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
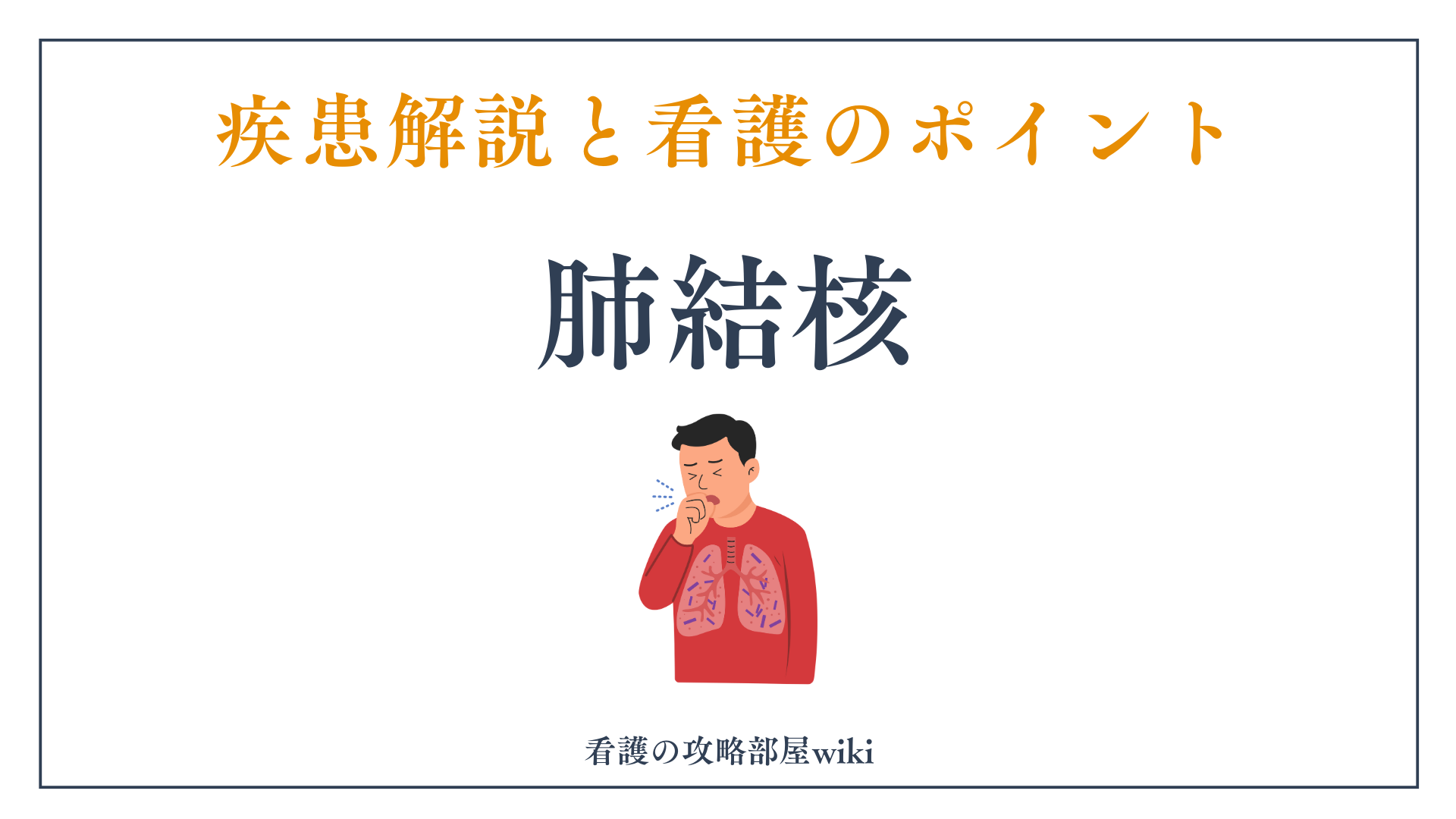

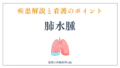
コメント