疾患概要
定義
多発性硬化症(Multiple Sclerosis:MS)は、中枢神経系の慢性炎症性脱髄疾患です。自己免疫機序により脳・脊髄の白質を中心に多発性の炎症性脱髄病巣が形成され、時間的・空間的に多発する神経症状を呈します。再発寛解型、一次進行型、二次進行型に分類され、多くは再発と寛解を繰り返しながら進行します。若年成人に好発し、身体機能の多様な障害をきたしますが、適切な治療により症状の改善と進行抑制が期待できる疾患です。
疫学
日本における多発性硬化症の有病率は人口10万人当たり約18人で、患者数は約2万人と推定されます。欧米と比較して有病率は低く、アジア系では視神経脊髄炎(NMOSD)の頻度が高い特徴があります。男女比は約1:3で女性に多く、発症年齢は20-40歳代がピークです。病型別では再発寛解型が約85%を占め、一次進行型は約10%、二次進行型は再発寛解型から10-15年で移行することが多いとされています。緯度勾配があり、赤道から離れるほど有病率が高くなる傾向があります。
原因
多発性硬化症の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的素因と環境因子の相互作用により発症すると考えられています。遺伝的要因ではHLA-DRB1*15:01が最も強い関連を示し、IL2RA、IL7R、CD40などの免疫関連遺伝子の多型も関与します。環境因子としてEBウイルス感染、ビタミンD欠乏、喫煙、肥満、ストレスなどが発症リスクを高めます。分子擬態により、ウイルス抗原と髄鞘蛋白の類似性から自己免疫反応が惹起されると考えられています。
病態生理
多発性硬化症では自己反応性T細胞が血液脳関門を通過し、中枢神経系で髄鞘蛋白(ミエリン塩基性蛋白、プロテオリピド蛋白)に対する免疫反応を引き起こします。Th1/Th17細胞の活性化により炎症性サイトカイン(IFN-γ、IL-17、TNF-α)が産生され、ミクログリアとマクロファージが活性化されます。急性期では炎症により髄鞘が破壊され(脱髄)、神経伝導が障害されます。慢性期では希突起膠細胞の障害により再髄鞘化が不完全となり、軸索変性が進行します。脳萎縮と認知機能障害も進行性に出現し、不可逆的な障害となります。
症状・診断・治療
症状
症状は病巣の部位により多彩で、視覚症状(視神経炎による視力低下、視野欠損、複視)、運動症状(片麻痺、歩行障害、協調運動障害)、感覚症状(しびれ、異常感覚、痛み)、排尿・排便障害、認知機能障害が認められます。特徴的症状としてLhermitte徴候(頸部前屈時の電撃様疼痛)、Uhthoff現象(体温上昇時の症状悪化)、易疲労性があります。再発寛解型では急性増悪(24時間以上持続する新たな症状)と寛解(症状の改善・消失)を繰り返し、一次進行型では緩徐進行性の歩行障害が主体となります。認知機能障害は約50%で認められ、情報処理速度低下、注意・集中力低下、記憶障害が特徴的です。
診断
診断は2017年改訂McDonald診断基準に基づいて行われます。時間的多発性(異なる時期の症状)と空間的多発性(異なる部位の病変)の証明が必要で、MRI、脳脊髄液検査、誘発電位検査により診断を支援します。MRIではT2強調像でのhyperintense lesion、ガドリニウム造影での造影病変により活動性病変を検出します。脳脊髄液検査ではオリゴクローナルバンド、IgG index上昇、髄液細胞数軽度増加を認めます。鑑別診断では視神経脊髄炎、急性散在性脳脊髄炎、血管炎、感染症、腫瘍などを除外します。疾患活動性評価にはEDSS(拡張障害状態評価尺度)が用いられます。
治療
治療は急性期治療、再発予防治療、対症療法に分けられます。急性期治療ではステロイドパルス療法(メチルプレドニゾロン1g×3-5日間)により炎症を抑制し、効果不十分例では血漿交換療法を考慮します。再発予防治療では疾患修飾薬(DMD)としてインターフェロンβ、グラチラマー酢酸、フィンゴリモド、ナタリズマブ、オクレリズマブなどを使用します。高活動性MSではナタリズマブ、オクレリズマブ、アレムツズマブなどの高効力薬を選択します。対症療法では痙縮(バクロフェン)、排尿障害(抗コリン薬)、疲労(アマンタジン)、疼痛(抗てんかん薬)に対する治療を行います。リハビリテーションも重要な治療要素です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 身体可動性障害:脱髄による運動機能低下と歩行障害
- 認知機能障害:中枢神経系病変による情報処理能力の低下
- 排尿障害:神経因性膀胱による排尿困難と失禁
ゴードン機能的健康パターン
活動・運動パターンでは運動機能障害の程度(筋力低下、協調運動障害、歩行能力)、易疲労性の影響、日常生活動作の自立度を詳細にアセスメントします。EDSSによる客観的評価と主観的な困難さの両面から評価することが重要です。認知・知覚パターンでは認知機能障害(情報処理速度、注意・集中力、記憶力)、感覚障害(しびれ、異常感覚)、疼痛の有無と程度を評価します。排泄パターンでは神経因性膀胱による排尿障害、排便障害の程度と日常生活への影響を把握します。
ヘンダーソン14基本的ニード
身体の位置を動かし、望ましい肢位を保持するでは運動機能障害に応じた移動・移乗方法、歩行補助具の選択、転倒予防対策を検討します。痙縮に対する体位管理や関節可動域訓練も重要です。正常に排泄するでは神経因性膀胱の管理、残尿測定、感染予防、必要に応じた導尿指導を行います。学習するでは認知機能障害に配慮した疾患教育、服薬指導、症状管理方法の習得を支援します。働くこと、達成感を得るでは障害の程度に応じた就労継続への支援、職場環境の調整を検討します。
看護計画・介入の内容
- 運動機能維持・ADL支援:個別的なリハビリテーション計画の立案、歩行補助具の適切な選択と使用指導、転倒予防対策、痙縮管理(ストレッチ、体位変換)、疲労管理(活動と休息のバランス)
- 認知機能支援・情報提供:認知機能に配慮した情報提示方法、記憶補助具の活用、集中力維持のための環境調整、家族への認知機能障害の説明と対応方法指導
- 症状管理・治療支援:再発の早期発見と対応、疾患修飾薬の効果と副作用の観察、体温管理(Uhthoff現象の予防)、ストレス管理、定期受診の重要性説明
よくある疑問・Q&A
Q: 多発性硬化症は治る病気ですか?進行を止めることはできますか?
A: 多発性硬化症は現在のところ根治治療はない慢性疾患ですが、疾患修飾薬により再発を大幅に減少させ、進行を遅らせることは可能です。特に早期治療開始により、将来の障害蓄積を予防できることが分かっています。現在の治療薬は再発率を約30-70%減少させ、MRI病変の新規出現を約80-90%抑制します。再発寛解型MSでは多くの患者さんで長期間にわたり軽微な症状で安定し、普通の社会生活を送ることができます。完治は困難ですが、適切な治療により症状をコントロールしながら充実した人生を送ることは十分可能です。
Q: 疾患修飾薬にはどのような種類がありますか?副作用が心配です
A: 疾患修飾薬には注射薬(インターフェロンβ、グラチラマー酢酸)、経口薬(フィンゴリモド、ジメチルフマル酸、テリフルノミド)、点滴薬(ナタリズマブ、オクレリズマブ、アレムツズマブ)があります。効果と副作用はバランスを考慮して選択され、軽症例では副作用の少ない薬剤から開始し、高活動性MSでは高効力薬を使用します。主な副作用は感染症、肝機能障害、心機能への影響などですが、定期的な検査により早期発見・対処が可能です。個々の患者さんの病状と生活スタイルに応じて最適な薬剤を選択し、副作用を最小限に抑えながら治療効果を最大化することが可能です。
Q: 日常生活で気をつけることはありますか?症状を悪化させる要因はありますか?
A: 体温上昇は症状を一時的に悪化させる(Uhthoff現象)ため、暑い環境、激しい運動、入浴時の高温、発熱時は注意が必要です。冷却ベストやエアコンの活用、ぬるめの入浴をお勧めします。ストレス管理も重要で、十分な睡眠、規則正しい生活、リラクゼーションにより再発リスクを軽減できます。感染症予防では手洗い・うがいの徹底、予防接種(不活化ワクチン)の接種が重要です。適度な運動は症状改善に効果的で、水中運動、ヨガ、ピラティスなどがお勧めです。禁煙も進行抑制に重要です。
Q: 妊娠・出産は可能ですか?薬の影響はありませんか?
A: 多発性硬化症があっても妊娠・出産は可能です。妊娠中は再発率が低下し、特に妊娠後期では著明に減少します。ただし、産後3-6ヶ月は再発リスクが高まるため注意が必要です。疾患修飾薬の多くは妊娠中は中止が必要ですが、グラチラマー酢酸やインターフェロンβは比較的安全とされています。妊娠前には疾患活動性を安定化させ、産科と神経内科の連携による管理が重要です。授乳も多くの場合可能で、授乳中でも使用できる薬剤があります。家族計画については医師と十分相談し、最適な治療計画を立てることで安全な妊娠・出産が可能です。
まとめ
多発性硬化症は中枢神経系の慢性炎症性脱髄疾患として、若年成人の人生に長期間にわたって影響を与える疾患です。しかし、疾患修飾薬の進歩により予後は大幅に改善し、適切な治療により症状をコントロールしながら充実した社会生活を送ることが可能な疾患となっています。
看護の要点は多様な神経症状への包括的対応と長期的な自己管理支援です。多発性硬化症は病巣の部位と程度により症状が大きく異なるため、患者さん一人ひとりの症状パターンを詳細にアセスメントし、個別性の高い看護計画を立案することが重要です。
運動機能障害への対応では、現在の能力を最大限活用できるよう適切な補助具の選択と環境調整を行い、転倒予防と廃用症候群の予防を図ります。リハビリテーションとの連携により、機能維持・改善を継続的に支援することが大切です。
認知機能障害への支援では、患者さんの理解力や記憶力に配慮した情報提供方法を工夫し、日常生活での困りごとに対する具体的な対処法を提案します。家族への教育により、認知機能の変化への理解と適切な支援方法を習得してもらうことも重要です。
疾患修飾薬による治療では、薬剤の効果と副作用について十分説明し、治療継続への動機づけを行います。定期的な検査の重要性と副作用の早期発見について教育し、患者さんが安心して治療を継続できるよう支援します。
再発予防では、症状の変化に対する観察力を高め、早期受診の重要性を説明します。ストレス管理、体温管理、感染症予防など、日常生活でできる予防策について具体的に指導することが大切です。
心理社会的支援では、若年での発症による将来への不安、身体機能の変化への適応、社会的役割の変化などに共感的に対応し、患者さんが希望を持って生活できるよう支援することが重要です。ピアサポートや患者会の活用により、同じ疾患を持つ仲間との交流を促進することも効果的です。
実習では患者さんの現在の機能と将来への希望の両方に焦点を当て、その人らしい生活の継続を支援する視点が重要です。多発性硬化症は確かに慢性疾患ですが、適切な治療と管理により多くの患者さんが活動的で充実した人生を送っています。希望を持って治療に取り組めるよう、患者さんとその家族を支援し、質の高い人生の実現に向けて包括的なケアを提供していきましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
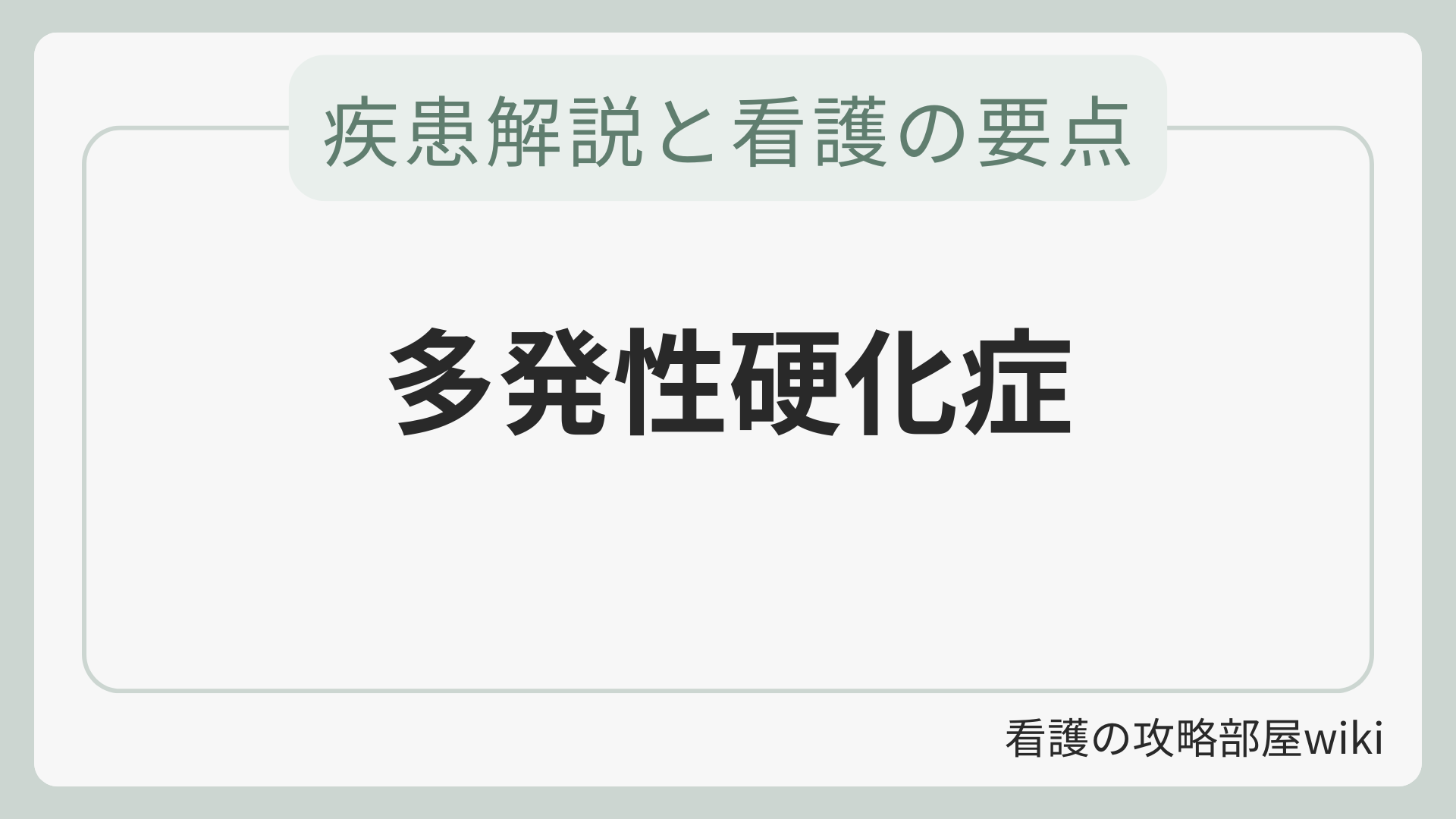
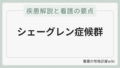
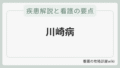
コメント