疾患概要
定義
糖尿病とは、膵臓のβ細胞が産生するインスリンが不足したり、インスリンの効きが悪くなったりすることで、血液中のブドウ糖(血糖)が高い状態が続く疾患です。
糖尿病は、単一の疾患ではなく、複数の異なる原因により、高血糖状態が引き起こされる疾患群です。最も一般的な分類として、1型糖尿病(Type 1 Diabetes)と2型糖尿病(Type 2 Diabetes)があります。
糖尿病の最大の危険性は、無症状のままに血管が傷つき、やがて脳梗塞、心筋梗塞、腎不全、失明などの重篤な合併症が起こることです。つまり、糖尿病は「沈黙の病」であり、早期発見と継続的な管理が、患者さんの人生の質と寿命を大きく左右する極めて重要な疾患です。
疫学
糖尿病は、世界的にパンデミック状況にあり、患者数は年々増加しています。日本では、糖尿病患者さんは約1,000万人(2019年の国民健康・栄養調査)と推計されており、さらに予備軍を含めると約2,000万人にのぼるとされています。
つまり、日本国民の約6人に1人が糖尿病患者さんであり、約3人に1人が糖尿病患者さんまたは予備軍であるということです。
2型糖尿病が全体の約95%を占める一方で、1型糖尿病は約5%です。
発症年齢は、2型糖尿病は通常50代以上で多いですが、最近では2型糖尿病の若年化が問題となっており、30~40代での発症も増加しています。一方、1型糖尿病は、若年者(特に小児)での発症が多いですが、成人での発症もあります。
男女差は、男性の方が有病率が高い傾向があります。
糖尿病による合併症(脳梗塞、心筋梗塞、腎不全、失明)は、日本における主要な死亡原因および身体障害の原因となっており、糖尿病の予防と管理は、個人の健康だけでなく、社会経済的に極めて重要な課題です。
原因
糖尿病の原因は、疾患のタイプにより大きく異なります。
1型糖尿病:
自己免疫機序により、膵臓のβ細胞が破壊される疾患です。患者さん自身の免疫系が、β細胞を「敵」と認識して攻撃し、β細胞が徐々に(または急速に)破壊されます。
その結果、インスリンの産生が著しく低下または消失し、高血糖が起こります。
原因としては、遺伝的素因(HLA遺伝子型など)と環境因子(ウイルス感染、食事成分など)の相互作用により、自己免疫が引き起こされると考えられています。
2型糖尿病:
インスリン分泌不全とインスリン抵抗性(インスリンの効きが悪い状態)が主な原因です。多くの場合、インスリン抵抗性が先行し、その後、それを補うために膵臓がインスリンを過剰産生し、やがて膵臓が疲弊してインスリン分泌が低下していくというメカニズムが想定されています。
2型糖尿病の危険因子には、肥満、運動不足、高カロリー食、ストレス、加齢などの生活習慣因子と、遺伝的素因が関与します。
その他の糖尿病:
膵炎、膵がんなどの膵疾患、ステロイド薬の使用、肝硬変などにより、続発性の高血糖が起こります。
病態生理
1型糖尿病の病態
第1段階:自己免疫の発動
何らかの環境因子(例えば、ウイルス感染、食事成分の分子模倣など)により、免疫系が活性化され、膵臓のβ細胞に対する自己抗体(例えば、GAD抗体、IA-2抗体)が産生されます。
第2段階:β細胞の破壊
自己抗体を含む免疫細胞(T細胞、B細胞など)が、膵臓のβ細胞を攻撃し、β細胞が破壊されます。
この過程は、通常数ヶ月から数年かけてゆっくり進行しますが、時には急速に進行することもあります。
第3段階:インスリン分泌の著しい低下または消失
多くのβ細胞が破壊されると、インスリンの産生が著しく低下し、最終的にはほぼ完全に消失します。
その結果、血液中のグルコースが高い状態(高血糖)が続き、患者さんはインスリン治療に依存するようになります。
2型糖尿病の病態
第1段階:インスリン抵抗性の発展
肥満(特に内臓脂肪の蓄積)、運動不足、高カロリー食などにより、細胞がインスリンに対する感受性を失っていきます。
通常、インスリンが細胞表面のインスリン受容体に結合すると、細胞内にグルコースが取り込まれます。しかし、インスリン抵抗性では、インスリンが結合してもグルコースが十分に取り込まれないという状態になります。
第2段階:代償性インスリン過剰分泌
インスリン抵抗性に対応するため、膵臓のβ細胞はより多くのインスリンを産生・分泌しようとします。この過度なインスリン分泌により、当初は血糖が比較的保たれています。
この段階は「インスリン抵抗性と高インスリン血症の段階」と呼ばれ、患者さんは高血糖を自覚しません。しかし、この段階でも血管は着しく傷つけられており、動脈硬化が進行しています。
第3段階:インスリン分泌不全の顕在化
代償性インスリン過剰分泌が長年続くと、膵臓のβ細胞が疲弊し、やがてインスリン分泌能が低下していきます。
その結果、高血糖が顕在化し、患者さんが糖尿病と診断されるようになります。
第4段階:血管障害の蓄積
高血糖が数年から数十年続くと、複数の機序により血管が傷つきます。
- 高血糖による酸化ストレスの亢進:ブドウ糖が過剰にあると、非酵素的にタンパク質と結合(糖化)し、活性酸素が産生されます。
- 終末糖化産物(AGE)の蓄積:糖化タンパク質がさらに化学変化して、AGEが形成されます。AGEは血管や神経を傷つけます。
- インスリン抵抗性に伴う高インスリン血症の有害作用:高インスリン血症は、それ自体が血管内膜を傷つけ、血管の硬化を促進します。
- 脂質異常症:インスリン抵抗性により、トリグリセリドが上昇し、HDLコレステロールが低下するという脂質異常が起こり、これが動脈硬化を加速させます。
これらの複数の機序により、糖尿病患者さんの血管は、加速度的に傷つき、動脈硬化が進行していきます。
症状・診断・治療
症状
糖尿病の症状は、疾患の進行段階により大きく異なります。
初期段階:
多くの2型糖尿病患者さんは、完全に無症状です。高血糖が存在しても、患者さんは何も自覚しません。つまり、患者さんが糖尿病に気づくのは、健診で血糖値が高いと指摘された時、あるいはすでに合併症が起こっている時です。
高血糖の典型的な症状(血糖が非常に高い場合):
- 多尿:尿の量が増える。患者さんは「夜中に何度もトイレに行く」と訴えることがあります。
- 多飲:喉が渇いて、水をたくさん飲む。
- 疲労感と倦怠感:身体がだるく、疲れやすい。
- 体重減少:食べているのに体重が減ってしまう(特に1型糖尿病の急性発症時)。
これらの症状は、血糖が非常に高い場合(通常、空腹時血糖>250mg/dL)に起こり、診断時にはこれらの症状を訴える患者さんは少ないです。
1型糖尿病は、急速な発症が特徴的です。患者さんは「1~2週間で急激に症状が出現した」と訴えることが多いです。重症例では、糖尿病ケトアシドーシス(DKA)という生命を脅かす急性合併症が起こることもあります。
合併症の症状:
- 網膜症による視力低下:糖尿病患者さんの成人失明の最大原因
- 腎症による腎不全:透析が必要になる主要な原因
- 神経障害による手足の痛みやしびれ:特に下肢の感覚が低下し、足潰瘍のリスクが高まる
- 心筋梗塞や脳梗塞:糖尿病患者さんは、非糖尿病患者さんより2~4倍高い心血管疾患のリスクを有する
診断
糖尿病の診断には、複数の診断基準が使用されます。
空腹時血糖検査:
- 正常:空腹時血糖 <100mg/dL
- 空腹時血糖異常(IFG):100~125mg/dL
- 糖尿病:≥126mg/dL
随時血糖検査:
- 糖尿病:≥200mg/dL(かつ糖尿病症状がある場合)
75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT):
75gのブドウ糖を飲ませ、2時間後の血糖値を測定します。
- 正常:2時間値 <140mg/dL
- 耐糖能異常(IGT):140~199mg/dL
- 糖尿病:≥200mg/dL
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)検査:
過去1~3ヶ月の平均血糖値を反映する指標です。
- 正常:<5.6%
- 糖尿病予備軍:5.6~6.4%
- 糖尿病:≥6.5%
1型糖尿病の診断:
自己抗体(GAD抗体、IA-2抗体、ICA、ZnT8抗体など)の測定により、自己免疫が関与していることを確認します。
尿検査:
糖尿(尿中ブドウ糖の出現)が認識されます。ただし、血糖がそれほど高くない場合は、尿糖が出現しないこともあります。
タンパク尿の出現は、糖尿病腎症の指標です。
その他の検査:
- 血液検査:電解質、腎機能、脂質、肝機能などを評価
- 尿検査:タンパク尿、微量アルブミン尿(早期腎症の指標)
- 眼科検査:網膜症の有無を評価
- 神経学的検査:神経障害の有無を評価
治療
糖尿病の治療は、血糖コントロール(目標:HbA1c <7.0%、個別に調整される)と、危険因子管理(高血圧、脂質異常症、喫煙など)が二つの柱です。
1型糖尿病の治療:
インスリン療法が必須です。患者さんは毎日、複数回のインスリン注射が必要です。
インスリン療法には複数の方法があります。
- 強化型インスリン療法:基礎インスリン(長時間作用型インスリン)1~2回と、食事時の追加インスリン(速効性インスリン)3回の合計4回注射
- インスリンポンプ療法:皮下にカテーテルを挿入し、プログラム可能なポンプが連続的にインスリンを供給
- 持続グルコース測定システム(CGM):血糖を連続的に測定し、患者さんが血糖変化をリアルタイムに知ることができるシステム
2型糖尿病の治療:
段階的なアプローチが取られます。
第1段階:生活習慣改善
- 食事療法:カロリー制限、塩分制限、バランスの取れた栄養
- 運動療法:週150分以上の中等度運動
- 体重管理:肥満患者さんの5~10%の体重減少で、血糖コントロールが著しく改善
第2段階:薬物療法
複数のクラスの薬剤が利用可能です。
- メトホルミン:インスリン抵抗性を改善。第一選択薬。
- DPP-4阻害薬:インクレチン作用を増強。
- GLP-1受容体作動薬:インスリン分泌を促進。心血管保護作用もあります。
- SGLT2阻害薬:腎臓でのグルコース再吸収を阻害。最近の治療ガイドラインで推奨度が高まっています。
- スルホニル尿素薬:インスリン分泌を促進。低血糖のリスクがあり、最近は使用が限定的。
- α-グルコシダーゼ阻害薬:炭水化物の吸収を遅延。
- インスリン:血糖コントロールが十分でない場合、インスリン治療が追加されます。
危険因子の管理:
- 高血圧の管理:降圧薬(ACE阻害薬、ARBなど)
- 脂質異常症の管理:スタチン系薬剤
- 禁煙:喫煙は糖尿病患者さんの心血管疾患リスクを著しく高めます。
合併症の予防と管理:
- 眼科検査の定期実施:網膜症の早期発見と治療
- 腎機能検査の定期実施:腎症の早期発見と進行予防
- 足の定期検査:神経障害と足潰瘍の予防
- 心血管疾患の予防:アスピリンなどの抗血小板薬の使用
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 知識不足:疾患、危険因子、治療、生活管理について
- 生活習慣改善への抵抗感(特に食事療法、運動療法)
- 薬物療法の継続困難
- インスリン自己注射への不安と抵抗感
- 低血糖と高血糖エピソードへの対応困難
- 合併症発症に対する不安
- 社会的役割と職業活動の制限に伴う心理的苦痛
- 自己管理能力の低下
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さんが糖尿病をどの程度重大な問題と認識しているかが重要です。無症状の患者さんは「治療の必要性がない」と考えることもあり、定期受診や治療の継続を拒否することがあります。
栄養-代謝パターンでは、患者さんの現在の食習慣を詳細に評価し、食事療法の必要性と実行可能性を判断することが極めて重要です。
活動-運動パターンでは、患者さんの現在の身体活動量と、運動療法の実行可能性を評価します。
ストレス-対処パターンでは、ストレスが血糖コントロールを悪化させることが知られているため、患者さんのストレス源と対処方法を評価することが重要です。
自己認識-自己概念パターンでは、患者さんが自分自身を「糖尿病患者」としてどのように認識しているか、そしてその認識が患者さんの自己管理にどのように影響しているかを評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
栄養と水分は、糖尿病患者さんにおいて最も重要かつ困難なニードです。患者さんが食事療法を受け入れ、実行可能な食生活改善を行うことが、糖尿病管理の成否を左右します。
活動と運動では、医師の指示に基づいた段階的な運動習慣の確立が重要です。
個人の衛生と身だしなみでは、特に足の衛生管理が重要です。神経障害により感覚が低下している場合、患者さんは足の小さな傷に気づかず、感染が進行して足潰瘍になる危険があります。
危機的状況への安全として、低血糖と高血糖ケトアシドーシスの両方のリスク認識が重要です。
看護計画・介入の内容
- 糖尿病の疾患教育:「沈黙の病」という本質の理解:患者さんと家族に対して、「糖尿病は、無症状のままに血管が傷つき、やがて重篇な合併症が起こる『沈黙の病』である」ことを強調することが極めて重要です。この理解により、患者さんが症状がなくても治療と管理の継続が必要であることを認識します。
- 危険因子と合併症に関する教育:患者さんに対して、糖尿病がもたらす合併症(脳梗塞、心筋梗塞、失明、腎不全、足潰瘍)の具体的なリスクを、患者さんの年齢と危険因子に基づいて説明することが、患者さんの危機感と治療への動機づけを高めます。
- 食事療法への具体的支援:患者さんの現在の食習慣を詳細に把握し、実行可能な食事改善目標を一緒に立てることが重要です。栄養士との連携により、患者さん個人に合わせた食事プランを作成することが効果的です。完璧な食事療法を求めるのではなく、「小さな継続可能な改善」を重視することが重要です。
- 運動習慣の確立支援:医師の許可に基づいた、患者さんが安全に行える運動を提案することが重要です。「週150分の運動」という目標も、患者さんのライフスタイルに合わせて、「毎日20分のウォーキング」「通勤時に1駅前で降りて歩く」など、具体的で実行可能な運動に翻訳することが重要です。
- 薬物療法の継続支援:特に2型糖尿病患者さんでは、「症状がないから」という理由で薬を中止する患者さんが多くいます。薬の役割(血管を守る、将来の合併症を予防する)を繰り返し説明し、薬の継続の重要性を伝えることが重要です。
- インスリン自己注射への支援:1型糖尿病患者さんや、インスリン治療が必要になった2型糖尿病患者さんに対して、インスリン自己注射への不安や恐怖を理解し、注射技術の教育と心理的サポートが重要です。多くの患者さんは、初めて注射をする時に強い不安を感じますが、実際に行った後は「思ったより簡単だった」と感じることが多いです。
- 血糖自己測定の習慣づけ:血糖測定機器の使用方法を指導し、毎日の血糖測定を習慣づけることが重要です。血糖値の変化を「数値」で認識することで、患者さんの自己管理への動機づけが高まります。
- 低血糖の認識と対応教育:インスリンやスルホニル尿素薬を使用している患者さんは、低血糖のリスクを有しています。低血糖の症状(冷汗、手の震え、動悸、頭痛)を認識させ、症状が出現した場合の対応(ブドウ糖や甘い飲料の摂取)を教育することが重要です。
- 高血糖ケトアシドーシス(DKA)と高浸透圧高血糖症候群(HHS)への認識:特に1型糖尿病患者さんでは、DKAという生命を脅かす急性合併症が起こる可能性があります。患者さんと家族が、「激しい倦怠感、嘔吐、呼吸が速くなる、意識が低下する」などの症状を認識し、これらの症状が出現した場合は躊躇なく119番通報することを強調することが重要です。
- 足の定期的な検査と衛生管理:糖尿病患者さんは、神経障害により足の感覚が低下し、足潰瘍のリスクが高くなります。患者さんに対して、毎日足を観察する習慣(赤くなっていないか、傷がないか、など)をつけさせ、靴擦れや小さな傷が大きなトラブルに発展することを理解させることが重要です。
- 眼科検査と腎機能検査の定期実施の重要性の強調:網膜症や腎症は、早期に発見されれば進行を遅延させることが可能です。患者さんに対して、定期的な眼科検査と腎機能検査の重要性を繰り返し強調することが重要です。
- 禁煙支援:喫煙は糖尿病患者さんの心血管疾患リスクを著しく高めます。患者さんが喫煙している場合は、禁煙の強力な支援が必要です。
- 高血圧と脂質異常症の管理:糖尿病患者さんでは、高血圧と脂質異常症が同時に存在することが多く、これらが心血管疾患のリスクを著しく高めます。患者さんに対して、複数の危険因子の同時管理の重要性を説明することが重要です。
- ストレス管理と心理的サポート:ストレスは血糖値を上昇させ、糖尿病の悪化につながります。患者さんが実践可能なストレス軽減法(瞑想、深呼吸、ヨガ、など)を提案することが重要です。
- 患者教育グループと患者支援組織の活用:患者会や糖尿病教室など、同じ状況にある患者さん同士の交流は、患者さんの自己管理への動機づけと情報交換に有効です。
- 家族への教育:患者さんの食事準備をする家族に対して、食事療法の重要性と具体的な調理方法を説明することが重要です。また、低血糖が起こった場合の対応方法を家族が知っていることが、患者さんの安全を守ります。
よくある疑問・Q&A
Q: 糖尿病と診断されましたが、症状がありません。治療は本当に必要ですか?
A: はい、治療は極めて重要です。糖尿病の最大の危険性は、無症状のままに血管が傷つくことにあります。患者さんが症状を自覚した時には、すでに血管がかなり傷つけられていることが多いです。つまり、「今、何も症状がない」ことは、「治療の必要がない」ことを意味しません。むしろ、「今から治療と管理を開始することで、将来の合併症を予防できる」という視点が重要です。
Q: 1型糖尿病と2型糖尿病は何が違いますか?
A: 最も重要な違いは、原因と治療です。
1型糖尿病は、自己免疫によりβ細胞が破壊される疾患であり、インスリン治療が必須です。患者さんは生涯、毎日複数回のインスリン注射が必要です。
2型糖尿病は、インスリン分泌不全とインスリン抵抗性が主な原因であり、生活習慣改善と複数の種類の薬物療法が可能です。一部の患者さんは、生活習慣改善のみで血糖が正常化することもあります。
Q: 糖尿病患者さんは甘い物を完全に避けなければいけませんか?
A: いいえ。完全な甘い物の禁止は、生活の質を著しく低下させ、かえって患者さんのアドヒアランス(治療継続)を損なう可能性があります。重要なのは、適切な量、適切なタイミングで、甘い物を摂取することです。例えば、「毎日少量のチョコレートを、夜間の低血糖を予防するため食べる」ということは可能です。栄養士と相談して、患者さんが継続可能な食事療法を立てることが重要です。
Q: インスリン注射を始めたら、一生注射が必要ですか?
A: これは、糖尿病のタイプにより異なります。
1型糖尿病の患者さんは、生涯インスリン注射が必要です。
2型糖尿病の患者さんでも、インスリン治療が開始された場合、その後の血糖コントロール改善により、インスリンが中止される可能性もあります。ただし、一度インスリン治療が開始されると、多くの場合継続が必要になります。
重要なのは、「インスリン注射を始めたら一生注射」という極端な考え方ではなく、「現在の血糖状態に応じた、最適な治療方法を選択する」という視点です。
Q: 低血糖が起こった場合、何をしたらよいですか?
A: 低血糖の症状が出現した場合(冷汗、手の震え、動悸、頭痛、意識の混濁など)は、迅速な対応が重要です。
患者さんが意識がある場合は、すぐにブドウ糖(10~15g)を摂取することが重要です。ブドウ糖がない場合は、砂糖が入ったジュースやキャンディでも可能です。
15分後に再度血糖測定して、血糖が正常化したか確認します。それでも低いままの場合は、再度ブドウ糖を摂取します。
患者さんが意識がない場合は、躊躇なく119番通報することが重要です。
Q: 糖尿病患者さんが運動中に低血糖が起こる可能性はありますか?
A: はい。インスリンやスルホニル尿素薬を使用している患者さんでは、運動中や運動直後に低血糖が起こる可能性があります。患者さんに対して、運動前に軽食を摂取すること、運動中に血糖測定機を持参すること、などの対策が重要です。
Q: 糖尿病患者さんが視力が低下してきました。これは何ですか?
A: これは、糖尿病網膜症の可能性があります。糖尿病網膜症は、糖尿病患者さんの成人失明の最大原因です。視力低下が認識された場合は、すぐに眼科医の診察を受けることが重要です。早期に発見されれば、レーザー治療やその他の治療により、失明を予防できる可能性があります。
Q: 糖尿病患者さんが激しい倦怠感と嘔吐を訴えています。これは何ですか?
A: これは、高血糖ケトアシドーシス(DKA)の症状の可能性があります。これは、特に1型糖尿病患者さんで起こる生命を脅かす急性合併症です。患者さんが激しい倦怠感、嘔吐、呼吸が速くなる、意識が低下するなどの症状を示す場合は、躊躇なく119番通報することが重要です。DKAは医学的緊急事態であり、初期治療が生命を守ります。
Q: 糖尿病患者さんが職場で低血糖のエピソードを経験しました。職場復帰はできますか?
A: 多くの場合、適切な血糖管理により、患者さんは通常の仕事に復帰可能です。ただし、「安全性上、低血糖が許容されない職種(例えば、操縦士、ドライバー、危険機械のオペレーター)」では、制限が必要になることもあります。医師と相談して、患者さんの職業と低血糖リスクの関係を判断することが重要です。
まとめ
糖尿病は、世界的にパンデミック状況にある疾患であり、日本でも約1,000万人が罹患しており、約2,000万人が予備軍です。
糖尿病の最大の特徴は、無症状のままに血管が傷つき、やがて脳梗塞、心筋梗塞、腎不全、失明などの重篇な合併症が起こる「沈黙の病」であるということです。
看護の役割は、患者さんが「今、症状がないから治療は不要」という危険な誤解を持たないよう、継続的に教育することです。同時に、患者さんが自分の疾患と向き合い、生活習慣改善と薬物療法を継続できるよう支援することが重要です。
食事療法と運動療法は、糖尿病管理の基盤です。しかし、患者さんが「完璧な食事療法と毎日の運動」を求めるのではなく、「小さく継続可能な改善」を重視することが、患者さんの長期的な自己管理を支援します。
1型糖尿病患者さんは、毎日複数回のインスリン注射とセルフモニタリングが必須であり、インスリン治療への適応と心理的サポートが重要です。
2型糖尿病患者さんでは、複数の危険因子(高血圧、脂質異常症、喫煙)の同時管理が、心血管疾患の予防に極めて重要です。
低血糖と高血糖ケトアシドーシスの両方のリスク認識、そして低血糖時の対応方法を、患者さんと家族が知っていることが、患者さんの生命を守ります。
定期的な眼科検査と腎機能検査により、網膜症と腎症の早期発見と進行予防が可能です。
糖尿病患者さんの多くは、長期間にわたって治療と自己管理を継続する必要があります。看護師は、患者さんが疾患と向き合い、治療と管理を継続し、充実した人生を送ることができるよう、長期的で思いやりのあるサポートを提供することが重要です。
実習では、様々な段階の糖尿病患者さんと向き合い、患者さんが「沈黙の病」である糖尿病の本質を理解し、自己管理への動機づけを高めるための看護の本質を学ぶ貴重な機会になるでしょう。
免責事項
・本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断
・治療の根拠ではありません。
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります。
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください。
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
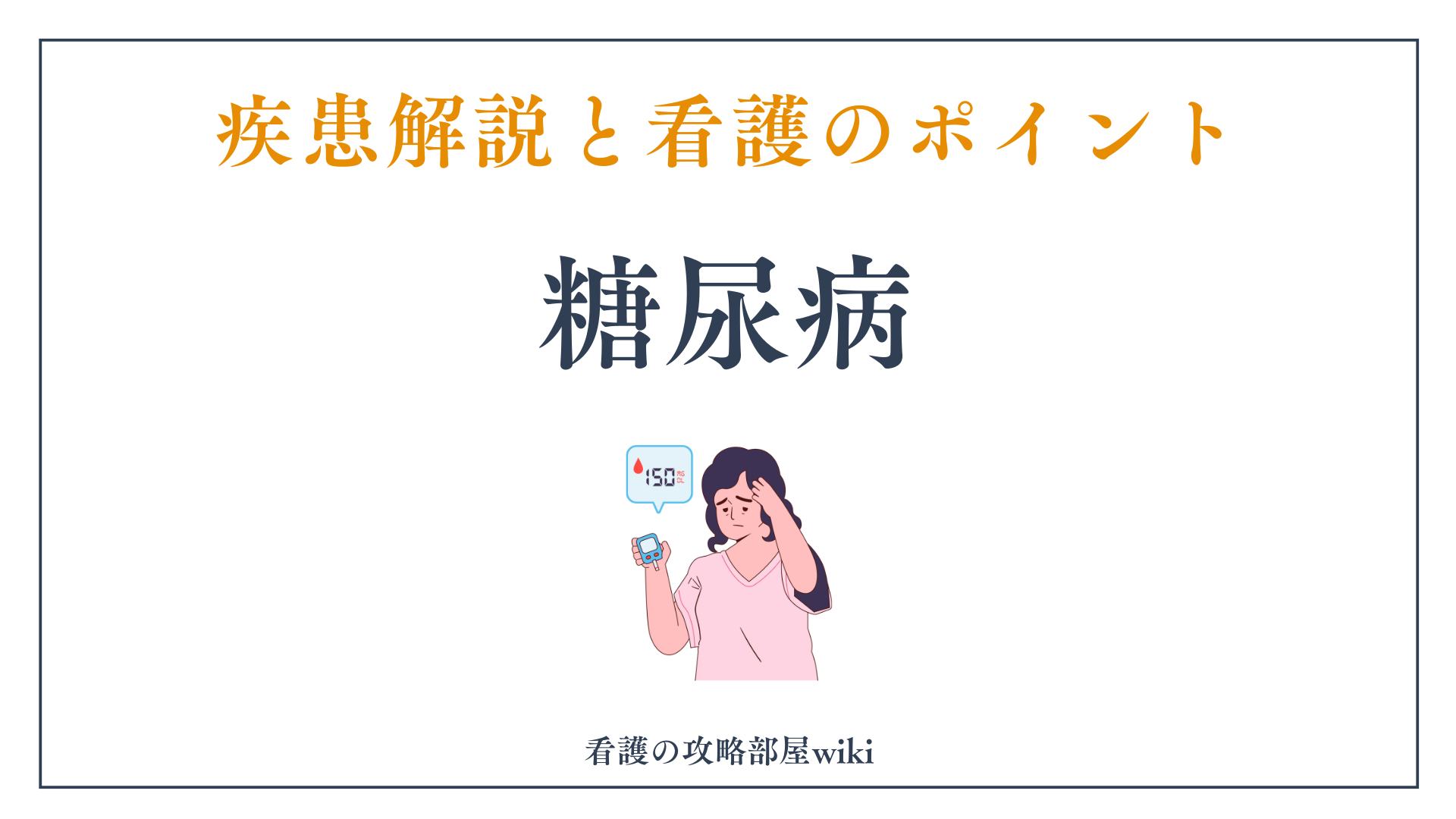
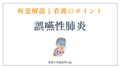
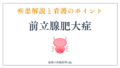
コメント