疾患概要
定義
間質性肺炎とは、肺の間質(肺胞と肺胞の間の組織)に炎症が起こり、線維化(組織が硬くなること)が進行する疾患の総称です。通常の「肺炎」が肺胞内に炎症が起こるのに対し、間質性肺炎は肺胞の壁や肺胞を支える組織に炎症が起こることが特徴です。
間質性肺炎は、200種類以上の疾患を含む大きな概念で、間質性肺疾患(ILD: Interstitial Lung Disease)とも呼ばれます。原因により以下のように分類されます:
原因が明らかな間質性肺炎
- 膠原病関連:関節リウマチ、全身性強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎、シェーグレン症候群などに合併
- 薬剤性:抗がん剤、免疫チェックポイント阻害薬、抗不整脈薬、漢方薬など
- 職業性・環境性:石綿(アスベスト)、シリカ、過敏性肺炎(カビ、鳥の羽毛など)
- 放射線肺炎:放射線治療後に発症
原因不明の間質性肺炎(特発性間質性肺炎: IIPs)
- 特発性肺線維症(IPF: Idiopathic Pulmonary Fibrosis):最も多く、予後不良
- 非特異性間質性肺炎(NSIP)
- 特発性器質化肺炎(COP)
- 急性間質性肺炎(AIP):急速に進行し、予後極めて不良
- その他
間質性肺炎の特徴は、進行性の肺の線維化により、肺が硬くなり、ガス交換ができなくなることです。一度線維化した肺は元に戻らず、呼吸不全に至ります。
疫学
日本における間質性肺炎の正確な患者数は不明ですが、特発性肺線維症(IPF)の患者数は約2〜3万人と推定されています。高齢化に伴い、間質性肺炎の患者数は増加傾向にあります。
年齢では、特発性肺線維症は60歳以上の高齢者に多く、発症のピークは70歳代です。ただし、薬剤性や膠原病関連の間質性肺炎は若年者にも見られます。
性別では、特発性肺線維症は男性が女性の約2倍多く発症します。喫煙が関与している可能性が指摘されています。一方、膠原病関連の間質性肺炎は、膠原病自体が女性に多いため、女性に多く見られます。
予後は原因や病型により大きく異なります。特発性肺線維症の診断後の生存期間中央値は約3〜5年と予後不良です。急性増悪を起こすと死亡率が50%以上と極めて高く、重篤な疾患です。一方、ステロイドや免疫抑制薬が効きやすい病型(NSIPなど)では、比較的予後良好です。
薬剤性間質性肺炎は、免疫チェックポイント阻害薬の使用増加に伴い増えており、がん治療の重要な合併症として注目されています。
原因
間質性肺炎の原因は多岐にわたりますが、大きく分けて原因が明らかなものと、原因不明(特発性)のものがあります。
膠原病関連
- 関節リウマチ:約10〜20%に間質性肺炎を合併
- 全身性強皮症:約70〜80%に合併し、予後を左右する重要な合併症
- 多発性筋炎・皮膚筋炎:特に抗ARS抗体陽性例で高率に合併
- シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデスなど
薬剤性 薬剤性間質性肺炎を起こしやすい主な薬剤:
- 抗がん剤:ブレオマイシン、ゲフィチニブ、メトトレキサートなど
- 免疫チェックポイント阻害薬:ニボルマブ、ペムブロリズマブなど(近年増加)
- 抗不整脈薬:アミオダロン
- 漢方薬:小柴胡湯など
- 抗リウマチ薬:メトトレキサート、リウマトレックス
薬剤性は投与開始後数週間から数ヶ月で発症することが多く、薬剤中止により改善することがあります。
職業性・環境性
- アスベスト(石綿):石綿肺を起こし、肺がんや中皮腫のリスクも高める
- シリカ(二酸化ケイ素):珪肺を起こす
- 過敏性肺炎:カビ、鳥の羽毛、化学物質などへの繰り返し曝露により発症
- 夏型過敏性肺炎:家屋内のカビ(トリコスポロン)
- 鳥関連過敏性肺炎:インコ、ハトなどの羽毛や糞
- 農夫肺:干し草のカビ
放射線肺炎 乳がん、肺がん、食道がんなどの放射線治療後、照射野に一致して発症します。治療後1〜3ヶ月で発症することが多いです。
特発性(原因不明) 特発性肺線維症(IPF)を含む特発性間質性肺炎は、原因が特定できません。遺伝的素因、喫煙、ウイルス感染、胃食道逆流などが関与している可能性が指摘されていますが、明確な原因は不明です。
病態生理
間質性肺炎の病態は、炎症→線維化→肺の硬化→ガス交換障害という経過をたどります。
正常な肺の構造
肺は、気管支が枝分かれして最終的に肺胞という小さな袋に至る構造をしています。肺胞の壁は非常に薄く(約0.5μm)、毛細血管が密接しており、ここで酸素と二酸化炭素のガス交換が行われます。肺胞と肺胞の間には、間質と呼ばれる結合組織があり、膠原線維や弾性線維、毛細血管、リンパ管などが含まれています。
炎症の開始
何らかの原因(薬剤、自己免疫、未知の因子など)により、肺の間質に炎症が起こります。炎症細胞(リンパ球、好中球、好酸球など)が間質に集まり、炎症性サイトカインが放出されます。これにより、肺胞壁が厚くなり、ガス交換が障害され始めます。
この段階では、原因を除去したり、ステロイドなどの抗炎症治療により、炎症を鎮めることができれば、ある程度可逆的です。
線維化の進行
炎症が持続すると、線維芽細胞が活性化され、膠原線維が過剰に産生されます。これが線維化です。線維化により、肺胞壁は厚く硬くなり、肺全体の柔軟性が失われます。これを蜂巣肺(honeycomb lung)と呼び、胸部CTで蜂の巣状の構造として観察されます。
一度線維化した組織は元に戻らないため、この段階では不可逆的な変化となります。
ガス交換障害と拘束性換気障害
線維化により肺胞壁が厚くなると、酸素が血液中に拡散しにくくなり、拡散障害が生じます。その結果、低酸素血症が出現します。
また、肺が硬くなることで、肺が十分に膨らまなくなり、拘束性換気障害(肺活量の低下)が生じます。肺のコンプライアンス(柔軟性)が低下するため、呼吸仕事量が増加し、呼吸困難が出現します。
初期は労作時のみ低酸素血症が見られますが、進行すると安静時にも低酸素血症が出現し、常に酸素投与が必要になります。
肺高血圧症の合併
線維化が進行すると、肺の毛細血管が破壊され、肺血管抵抗が上昇します。その結果、肺高血圧症を合併し、右心不全に至ることがあります。
急性増悪
特発性肺線維症では、突然呼吸状態が急速に悪化する急性増悪が起こることがあります。急性増悪の原因は不明ですが、感染、外科手術、肺生検などが誘因となることがあります。急性増悪は予後極めて不良で、死亡率が50%以上に達します。
特発性肺線維症の特徴
特発性肺線維症(IPF)は、通常型間質性肺炎(UIP: Usual Interstitial Pneumonia)というパターンを示し、胸部CTで蜂巣肺や牽引性気管支拡張が特徴的です。進行性の線維化により、徐々に呼吸機能が低下し、予後不良です。
症状・診断・治療
症状
間質性肺炎の症状は、病型や進行度により異なりますが、共通する特徴があります。
主な呼吸器症状
- 労作時呼吸困難:最も重要な症状で、初期には階段や坂道を上る時に息切れを感じます。進行すると、平地歩行や着替えなどの日常生活動作でも息切れが出現し、最終的には安静時にも呼吸困難が見られます
- 乾性咳嗽:痰を伴わない乾いた咳が持続します。特発性肺線維症では約80%に見られ、患者のQOLを著しく低下させます
- 捻髪音(fine crackles):聴診で、背中の下部(肺底部)に、髪をひねったような細かい音(パチパチ、ベリベリという音)が聴かれます。これは間質性肺炎の特徴的な身体所見です
- ばち指(clubbing finger):指先が太鼓のばちのように丸く膨らみ、爪が湾曲します。特発性肺線維症で約50%に見られます
全身症状
- 倦怠感:慢性的な低酸素血症により、全身の倦怠感が続きます
- 体重減少:呼吸仕事量の増加と食欲不振により体重が減少します
- 発熱:急性間質性肺炎や薬剤性では発熱を伴うことがあります
進行期の症状
- 安静時呼吸困難:常に息苦しく、横になることも困難になります
- チアノーゼ:低酸素血症により、口唇や爪床が紫色になります
- 右心不全症状:肺高血圧症を合併すると、下腿浮腫、肝腫大、頸静脈怒張などが出現します
急性増悪の症状
特発性肺線維症の急性増悪では、数日から数週間の経過で急激に呼吸困難が増悪し、発熱、咳の増加、低酸素血症の進行が見られます。緊急入院と集中治療が必要になります。
原因疾患による特徴
- 膠原病関連:関節痛、皮疹、レイノー現象などの膠原病症状を伴います
- 過敏性肺炎:抗原への曝露後、数時間で発熱、咳、呼吸困難が出現し、抗原を避けると改善します
- 薬剤性:薬剤開始後数週間から数ヶ月で発症し、薬剤中止により改善することがあります
診断
間質性肺炎の診断は、臨床症状、身体所見、血液検査、画像検査、呼吸機能検査、時に肺生検を組み合わせて行われます。
胸部X線検査
初期には正常または軽度の変化のみですが、進行すると両側肺野の網状影や粒状影が見られます。末期には蜂巣肺による嚢胞状変化が確認されます。
胸部高解像度CT(HRCT)検査(最も重要)
間質性肺炎の診断に最も有用な検査です。病変の分布、性状、進行度を詳細に評価できます。
特発性肺線維症(UIPパターン)の特徴的所見:
- 蜂巣肺(honeycomb lung):下肺野・胸膜直下に蜂の巣状の嚢胞が集簇
- 網状影:不規則な線状陰影
- 牽引性気管支拡張:線維化により気管支が引っ張られて拡張
- すりガラス影は軽度:線維化が主体
その他の病型では、すりガラス影が主体であったり、コンソリデーション(肺の実質化)が見られたりと、パターンが異なります。
呼吸機能検査
拘束性換気障害が特徴で、以下の所見が見られます:
- 肺活量(VC)の低下:%VC <80%
- 1秒率(FEV1.0%)は正常または上昇:閉塞性ではないため
- 拡散能(DLCO)の低下:肺胞壁の肥厚によりガス交換が障害
進行度の評価や治療効果の判定に重要です。
血液ガス分析
低酸素血症(PaO2低下)が見られます。初期は労作時のみですが、進行すると安静時にも低酸素血症が持続します。
血液検査
- KL-6(Krebs von den Lungen-6):間質性肺炎のマーカーで、活動性や重症度を反映します。KL-6 >500 U/mLで間質性肺炎を疑います
- SP-D(surfactant protein-D):肺胞上皮細胞の障害マーカー
- LDH:間質の炎症により上昇
- 炎症マーカー:CRP、白血球数
- 自己抗体:膠原病の合併を調べるため、抗核抗体、リウマトイド因子、抗CCP抗体、筋炎特異的抗体などを測定
気管支鏡検査
気管支肺胞洗浄(BAL: Bronchoalveolar Lavage)により、肺胞内の細胞成分を分析します。リンパ球増加、好中球増加、好酸球増加などのパターンから、病型の推定ができます。
肺生検
確定診断が困難な場合、外科的肺生検(胸腔鏡下または開胸)により肺組織を採取し、病理学的に診断します。ただし、侵襲的な検査であり、特に進行例では手術リスクが高いため、慎重に適応を判断します。
診断のステップ
- 臨床症状、身体所見から間質性肺炎を疑う
- 胸部HRCTで間質性肺炎の存在を確認
- 原因の検索:薬剤歴、職業歴、環境曝露、膠原病の有無を確認
- 病型の診断:画像所見、血液検査、気管支鏡検査、肺生検を組み合わせて診断
- 重症度評価:呼吸機能検査、血液ガス分析、画像所見から評価
治療
間質性肺炎の治療は、原因、病型、進行度により大きく異なります。
原因が明らかな場合
- 薬剤性:原因薬剤の中止が最優先です。ステロイド投与が行われることもあります
- 過敏性肺炎:抗原の回避が最重要です。急性期にはステロイド投与を行います
- 膠原病関連:基礎疾患の治療として、ステロイドや免疫抑制薬を使用します
特発性肺線維症(IPF)の治療
従来はステロイドや免疫抑制薬が使用されていましたが、効果が乏しいことが判明しています。現在は抗線維化薬が標準治療です。
抗線維化薬
- ピルフェニドン(ピレスパ):線維化の進行を抑制します。軽症〜中等症に使用
- ニンテダニブ(オフェブ):複数の成長因子受容体を阻害し、線維化を抑制します
これらの薬剤は、肺機能の低下速度を約50%遅らせることが示されていますが、線維化を元に戻すことはできません。副作用として、ピルフェニドンでは光線過敏症、食欲不振、悪心が、ニンテダニブでは下痢が高頻度に見られます。
ステロイドや免疫抑制薬が有効な病型
非特異性間質性肺炎(NSIP)、特発性器質化肺炎(COP)、過敏性肺炎、膠原病関連間質性肺炎などでは、ステロイド(プレドニゾロン)や免疫抑制薬(シクロホスファミド、アザチオプリン、タクロリムスなど)が使用されます。
酸素療法
低酸素血症が進行した場合、在宅酸素療法(HOT: Home Oxygen Therapy)が導入されます。安静時や労作時のSpO2を評価し、SpO2 <90%となる場合は酸素療法の適応です。
酸素投与により、低酸素血症を改善し、息切れを軽減し、生活の質を向上させることができます。また、肺高血圧症の進行を遅らせる効果もあります。
肺移植
若年者(65歳以下)で、内科的治療に反応しない進行性の間質性肺炎では、肺移植が最終的な治療選択肢となります。日本でも年間約80例の肺移植が行われていますが、ドナー不足が深刻な問題です。
急性増悪の治療
特発性肺線維症の急性増悪は予後極めて不良で、以下の治療が試みられますが、効果は限定的です:
- ステロイドパルス療法(メチルプレドニゾロン1000mg/日×3日間)
- 免疫抑制薬(シクロホスファミド)
- 人工呼吸管理
- 体外式膜型人工肺(ECMO)
急性増悪の死亡率は50%以上と高く、救命できても長期予後は不良です。
リハビリテーション
呼吸リハビリテーションは、間質性肺炎患者のQOL向上に有効です。呼吸筋訓練、運動療法(歩行訓練、自転車エルゴメーター)、栄養指導、患者教育を組み合わせて実施します。運動耐容能が改善し、息切れが軽減されます。
緩和ケア
進行性の間質性肺炎では、早期から緩和ケアを導入し、呼吸困難、咳、疼痛、不安などの症状緩和を図ります。モルヒネは呼吸困難感の緩和に有効です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- ガス交換障害:肺の線維化による拡散障害と低酸素血症
- 非効果的呼吸パターン:拘束性換気障害による呼吸の浅速化
- 活動耐性低下:呼吸困難と低酸素血症による日常生活動作の制限
- 不安:進行性疾患であることへの不安、予後への恐怖
- 非効果的コーピング:慢性疾患の受容困難、将来への絶望感
- 栄養摂取消費バランス異常:呼吸仕事量の増加と食欲不振による体重減少
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
間質性肺炎の診断は、患者にとって大きな衝撃です。特に特発性肺線維症と診断された場合、進行性で治癒困難な疾患であることを理解し、強い不安と恐怖を抱きます。「息ができなくなって死ぬのか」「いつまで生きられるのか」という疑問や恐れを持つことが多いです。
患者がどの程度病状を理解しているか、どのような思いを抱いているかを確認します。診断の受け止め方は個人差が大きく、積極的に情報を求める人もいれば、詳しくは知りたくない人もいます。患者の準備状態を見極め、ペースに合わせた情報提供と心理的支援を行います。
喫煙歴のある患者では、自責の念を抱くことがあります。また、膠原病に合併した場合、「基礎疾患だけでも大変なのに、さらに肺まで」という負担感を感じます。患者の罪悪感や負担感に配慮し、責めるような言動は避けます。
治療への希望、療養場所の希望、延命治療の意思などについても、適切なタイミングで確認します。
栄養-代謝パターン
間質性肺炎患者の多くは、食欲不振と体重減少を認めます。呼吸仕事量の増加によりエネルギー消費が増え、呼吸困難により食事摂取が困難になるためです。咀嚼や嚥下の際にも息切れが生じ、食事が苦痛になります。
栄養状態を評価するため、体重、BMI、血清アルブミン値、総リンパ球数を定期的にモニタリングします。体重減少は予後不良のサインでもあります。
栄養管理として、高カロリー・高タンパクの食事を少量頻回で提供します。食事中の息切れを軽減するため、食前に酸素流量を上げる、食事を小分けにする、口すぼめ呼吸を取り入れるなどの工夫をします。経口栄養補助食品も活用します。
抗線維化薬の副作用(悪心、食欲不振、下痢)により、さらに栄養摂取が困難になることがあります。副作用対策として、制吐薬、止瀉薬を適切に使用します。
活動-運動パターン
労作時呼吸困難により、活動耐性が著しく低下します。階段昇降、坂道歩行、入浴、着替えなどの日常生活動作で息切れが生じ、進行すると安静時にも呼吸困難が出現します。Performance Status(PS)を評価し、患者の活動レベルに応じた援助を提供します。
呼吸状態の継続的モニタリングが最重要です。呼吸数、SpO2(特に労作時)、呼吸パターン、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を観察します。捻髪音を聴診し、病状の変化を評価します。
酸素療法が導入されている場合、適切な酸素流量を維持し、効果を評価します。労作時にはSpO2が低下するため、活動時の酸素流量調整が必要です。
活動と休息のバランスを保ちます。過度の安静は廃用症候群を招きますが、過度の活動は低酸素血症を悪化させます。患者のペースに合わせた活動を支援し、息切れが強い時は休息を促します。
呼吸リハビリテーションは有効で、呼吸筋訓練、呼吸法の指導(口すぼめ呼吸、腹式呼吸)、運動療法を取り入れます。理学療法士と連携し、個別プログラムを実施します。
睡眠-休息パターン
呼吸困難、咳、不安により、睡眠が障害されます。夜間の低酸素血症が進行すると、睡眠の質が低下し、日中の倦怠感が増強します。
睡眠環境を整え、静かで落ち着いた環境を提供します。臥位で呼吸困難が増悪する場合は、半座位または座位で休息できるよう、クッションや椅子を準備します。
夜間の酸素投与により、低酸素血症を改善し、睡眠を確保します。必要に応じて、睡眠薬や抗不安薬も使用しますが、呼吸抑制に注意します。
コーピング-ストレス耐性パターン
間質性肺炎、特に特発性肺線維症は進行性で予後不良の疾患であり、患者は大きな心理的ストレスを抱えます。「徐々に息ができなくなる」「苦しんで死ぬのではないか」という恐怖、家族への心配、役割の喪失、将来への絶望感など、さまざまな問題に直面します。
患者の心理的反応を理解し、傾聴の姿勢を持って接します。怒り、否認、抑うつなども自然な反応であることを理解し、受け止めます。
希望を支える関わりが重要です。「何もできない」のではなく、「今できることがある」という視点で支援します。小さな目標(孫との外出、趣味の継続など)を共有し、その実現を支援します。
必要に応じて、精神科医、臨床心理士、緩和ケアチーム、ソーシャルワーカーなどと連携します。患者会や難病支援団体の情報提供も有効です。
役割-関係パターン
呼吸困難により、仕事や家庭内での役割を果たせなくなり、アイデンティティの喪失を感じることがあります。酸素チューブにつながれた生活により、外出が困難になり、社会的孤立が進みます。
在宅酸素療法(HOT)導入後も、ポータブル酸素ボンベを使用すれば外出可能であることを説明します。酸素濃縮器や携帯用酸素ボンベの使用方法を指導し、安全に外出できるよう支援します。
家族の介護負担も大きいため、家族への支援も重要です。介護方法の指導、レスパイトケアの提供、社会資源の紹介を行います。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 正常な呼吸
間質性肺炎患者にとって最も重要なニードです。線維化により肺が硬くなり、ガス交換が障害されているため、呼吸困難が主症状となります。
呼吸困難の緩和には:
- 体位の工夫:半座位、前傾姿勢(オーバーテーブルに枕を置いてもたれる)が楽なことが多いです。横になると呼吸困難が増悪する場合があります
- 酸素療法:低酸素血症を改善し、息切れを軽減します。安静時と労作時で必要な酸素流量が異なるため、活動時には酸素流量を上げます
- 呼吸法の指導:口すぼめ呼吸(鼻から吸って、口をすぼめてゆっくり吐く)により、気道内圧を保ち、呼吸を楽にします
- 薬物療法:モルヒネは呼吸困難感を緩和します。鎮咳薬も使用されます
- 環境調整:室温、湿度を適切に保ち、換気を行います。扇風機で顔に風を当てるのも効果的です
咳が強い場合、鎮咳薬を使用しますが、痰がある場合は去痰薬も併用します。乾性咳嗽が主体ですが、感染を合併すると喀痰が増加します。
2. 適切な飲食
呼吸仕事量の増加により、エネルギー消費が増えています。また、食事中の息切れにより摂取量が減少します。高カロリー・高タンパクの食事を少量頻回で提供し、栄養状態を維持します。
食前に酸素流量を上げる、食事を小分けにする、口すぼめ呼吸を取り入れるなどの工夫をします。嚥下時にむせると低酸素血症が悪化するため、とろみをつけるなど嚥下しやすい形態にします。
十分な水分摂取も重要で、痰の喀出を促進します。
4. 体位の保持と変換
呼吸を楽にするため、患者が最も楽な体位を見つけられるよう支援します。多くの場合、半座位または座位が楽です。クッションや枕を使用し、安楽な姿勢を保持します。
長時間の同一体位は褥瘡や筋肉疲労のリスクとなるため、定期的な体位変換を促します。ただし、体位変換時は低酸素血症に注意し、ゆっくりと行います。
8. 身体を清潔に保つ
入浴は呼吸困難を増悪させるため、全身状態に応じて、入浴、シャワー浴、清拭を選択します。入浴時は酸素流量を上げ、浴室を温めて湯気で呼吸を楽にします。入浴前後の休息も重要です。
進行期では、清拭や部分浴で対応し、無理な入浴は避けます。
9. 危険の回避
- 感染予防:呼吸器感染症は急性増悪の誘因となるため、手指衛生を徹底し、人混みを避けます。インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの接種を推奨します
- 転倒予防:低酸素血症や全身衰弱により転倒リスクが高まります。酸素チューブに引っかかる危険もあります
- 酸素機器の安全管理:在宅酸素療法では、火気厳禁です。酸素濃縮器やボンベの取り扱い、トラブル時の対応を指導します
- 薬剤の副作用モニタリング:抗線維化薬の副作用(光線過敏症、悪心、下痢)、ステロイドの副作用(感染、骨粗鬆症、糖尿病)に注意します
急性増悪の徴候(呼吸困難の急激な増悪、SpO2の低下、発熱、咳の増加)に注意し、異常があればすぐに受診するよう指導します。
14. 学習
疾患の病態、経過、治療について、患者の理解度に応じて説明します。進行性の疾患であることを理解してもらいつつ、抗線維化薬により進行を遅らせることができることを伝えます。
在宅酸素療法の指導が重要です:
- 酸素濃縮器、ポータブルボンベの使い方
- 酸素流量の調整(安静時と労作時)
- 火気厳禁(タバコ、ガスコンロ、ストーブから2m以上離す)
- トラブル時の対応(停電、機器の故障)
- 外出時の準備(ボンベの残量確認、予備ボンベ)
服薬指導も重要で、抗線維化薬の服薬継続の重要性、副作用とその対処法を説明します。ピルフェニドンでは日光を避ける、ニンテダニブでは下痢時の対応などを指導します。
呼吸リハビリテーション(呼吸法、運動療法)、栄養管理、感染予防、急性増悪の徴候と早期受診の重要性についても教育します。
利用可能な社会資源(難病医療費助成、訪問看護、介護保険、身体障害者手帳など)についても情報提供します。
看護計画・介入の内容
- 呼吸状態の継続的モニタリング:呼吸数、SpO2(安静時と労作時)、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を定期的に観察します。捻髪音を聴診し、病状の進行を評価します。急性増悪の徴候(呼吸困難の急激な増悪、発熱、咳の増加)に注意します
- 酸素療法の管理:低酸素血症を改善するため、適切な酸素流量を維持します。安静時と労作時でSpO2を測定し、必要に応じて酸素流量を調整します。酸素カニューレやマスクの装着状態、皮膚トラブルの有無を確認します
- 呼吸困難の緩和:体位の工夫(半座位、前傾姿勢)、呼吸法の指導(口すぼめ呼吸、腹式呼吸)、環境調整(扇風機、室温・湿度)、薬物療法(モルヒネ、抗不安薬)により、呼吸困難感を軽減します
- 活動と安静のバランス:過度の安静は廃用症候群を招きますが、過度の活動は低酸素血症を悪化させます。患者のペースに合わせた活動を支援し、疲労や息切れが強い時は休息を促します
- 呼吸リハビリテーション:理学療法士と連携し、呼吸筋訓練、呼吸法の指導、運動療法(歩行訓練、自転車エルゴメーター)を実施します。運動耐容能の向上とQOLの改善を目指します
- 栄養管理:体重、食事摂取量を記録し、栄養状態を評価します。高カロリー・高タンパクの食事を少量頻回で提供します。食事中の息切れを軽減するため、食前に酸素流量を上げる、食事を小分けにするなどの工夫をします
- 薬物療法の副作用管理:抗線維化薬の副作用(光線過敏症、悪心、下痢)、ステロイドの副作用(感染、骨粗鬆症、糖尿病、消化性潰瘍)に注意し、予防と対策を行います。定期的な血液検査で肝機能、腎機能、血糖値をモニタリングします
- 心理的支援:患者の思いを傾聴し、不安や恐怖を受け止めます。進行性疾患への恐怖、予後への不安、将来への絶望感に対し、希望を支える関わりを意識します。「今できること」に焦点を当て、小さな目標の実現を支援します
- 在宅酸素療法の指導:酸素濃縮器、ポータブルボンベの使用方法、安全管理(火気厳禁)、トラブル時の対応、外出時の準備などを具体的に指導します。実際に機器を操作してもらい、理解度を確認します
- 感染予防指導:手洗い、うがい、マスク着用、人混みを避けることを指導します。インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの接種を推奨します。感染徴候(発熱、咳の増加、痰の色の変化)があれば早期受診するよう伝えます
- 家族への支援:家族の介護負担を理解し、サポートします。在宅療養の準備、介護方法の指導、社会資源の紹介を行います。家族の疲労やストレスにも配慮し、レスパイトケアを提案します
- 多職種連携:医師、薬剤師、栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカー、訪問看護師などと連携し、包括的なケアを提供します。定期的なカンファレンスで情報共有し、ケア方針を統一します
- アドバンス・ケア・プランニング(ACP):患者の価値観、人生の目標、医療に対する希望を確認します。終末期医療についての意思決定を支援し、患者の意思を尊重したケアを提供します
- 緩和ケア:進行期では、呼吸困難、咳、疼痛、不安などの症状を総合的に緩和します。QOL(生活の質)の向上を目指し、患者が「その人らしく」過ごせるよう支援します
よくある疑問・Q&A
Q: 間質性肺炎と普通の肺炎はどう違うのですか?
A: 「肺炎」という言葉が共通していますが、炎症が起こる場所が異なります。普通の肺炎(細菌性肺炎など)は、肺胞の中に炎症が起こり、肺胞内に膿や水が溜まります。抗菌薬により治癒し、肺は元通りになります。
一方、間質性肺炎は、肺胞の壁(間質)に炎症が起こり、線維化(組織が硬くなる)が進行します。一度線維化すると元に戻らず、進行性に肺機能が低下します。抗菌薬は効かず、治療法も大きく異なります。
症状も、普通の肺炎では発熱、黄色い痰、胸痛が主ですが、間質性肺炎では労作時呼吸困難、乾性咳嗽が主症状です。
Q: 間質性肺炎は治りますか?薬で線維化は元に戻りますか?
A: 残念ながら、一度線維化した肺は元に戻りません。特発性肺線維症(IPF)は進行性の疾患で、完治は困難です。ただし、抗線維化薬(ピルフェニドン、ニンテダニブ)により、線維化の進行を遅らせることができます。これらの薬は、肺機能の低下速度を約50%遅らせることが示されています。
原因が明らかな間質性肺炎(薬剤性、過敏性肺炎など)では、原因を除去し、早期にステロイド治療を行えば、改善や治癒が期待できることもあります。また、ステロイドが効きやすい病型(NSIP、COPなど)では、治療により線維化の進行を抑えられます。
早期発見、早期治療が重要で、適切な治療により進行を遅らせ、QOLを維持することが目標となります。
Q: 在宅酸素療法を始めると言われました。一生酸素を吸い続けなければならないのですか?
A: 間質性肺炎の場合、線維化が進行して低酸素血症が持続しているため、多くの場合、長期的な酸素療法が必要になります。ただし、「一生酸素を吸う」というより、「酸素を使うことで、より楽に生活できる」と考えてください。
在宅酸素療法(HOT)により、低酸素血症が改善され、息切れが軽減し、日常生活動作が楽になります。また、肺高血圧症の進行を遅らせ、生命予後を改善する効果もあります。
酸素を使用しても外出は可能です。ポータブル酸素ボンベを使用すれば、買い物や散歩、旅行もできます。酸素は「制限」ではなく、「生活の質を向上させる道具」と考えることが大切です。
薬剤性や過敏性肺炎など、可逆性のある病型では、治療により改善し、酸素療法が不要になることもあります。
Q: 間質性肺炎の急性増悪とは何ですか?予防できますか?
A: 急性増悪とは、特発性肺線維症などの慢性間質性肺炎で、突然呼吸状態が急激に悪化する病態です。数日から数週間の経過で、呼吸困難が急激に増悪し、発熱、咳の増加、低酸素血症の進行が見られます。死亡率が50%以上と予後極めて不良です。
急性増悪の原因は明確ではありませんが、感染、外科手術、肺生検、吸引、胃食道逆流などが誘因となることがあります。完全に予防することは困難ですが、以下の対策が推奨されます:
- 感染予防:手洗い、うがい、マスク着用、ワクチン接種
- 不要な侵襲的検査を避ける:肺生検などは慎重に適応を判断
- 胃食道逆流の治療:プロトンポンプ阻害薬の使用
- 禁煙:喫煙は急性増悪のリスクを高めます
急性増悪の徴候(呼吸困難の急激な増悪、SpO2の低下、発熱)があれば、直ちに医療機関を受診することが重要です。
Q: 間質性肺炎の患者さんの呼吸困難が強い時、どう対応すればいいですか?
A: まず呼吸状態を評価します。SpO2、呼吸数、呼吸パターン、チアノーゼの有無、意識レベルを確認します。急性増悪や感染の合併、心不全の可能性を考えます。
応急処置:
- 患者を楽な体位(半座位、前傾姿勢)にします
- 酸素投与を開始または流量を上げます(医師の指示に基づく)
- 扇風機で顔に風を当てると、呼吸困難感が軽減されます
- 穏やかに声をかけ、「ゆっくり呼吸してください」「そばにいますよ」と安心させます
- 直ちに医師に報告し、指示を仰ぎます
薬物療法:
- モルヒネ:呼吸困難感を緩和します。少量から開始し、効果を見ながら調整します
- 抗不安薬:不安が強い場合、抗不安薬(ロラゼパムなど)が有効です
原因が特定されれば、それに応じた治療(感染なら抗菌薬、急性増悪ならステロイドパルス療法など)が行われます。
慢性の呼吸困難に対しては、日常的に呼吸法の指導、体位の工夫、環境調整、酸素療法の最適化を行います。
Q: 家族が間質性肺炎です。自宅で看取りたいのですが、可能ですか?
A: はい、可能です。在宅での看取りを希望される患者さん・ご家族は多く、適切なサポート体制があれば実現できます。
在宅療養のサポート:
- 訪問診療:医師が定期的に自宅を訪問し、症状管理や処方を行います
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、症状観察、医療処置、療養指導を行います
- 訪問介護:ヘルパーが身体介護や生活支援を行います
- 24時間対応:多くの在宅医療機関は24時間連絡可能で、緊急時にも対応します
在宅でも、酸素療法、モルヒネによる呼吸困難の緩和、点滴などの医療処置が可能です。症状緩和ケアにより、苦痛を最小限にすることができます。
ただし、家族の介護負担は大きいため、レスパイトケア(一時的に入院や施設で預かる)の利用も検討します。また、「自宅で」という希望が変わることもあり、柔軟に対応することが大切です。
まずは、主治医、緩和ケアチーム、がん相談支援センター、地域の訪問看護ステーション、地域包括支援センターなどに相談してみてください。
まとめ
間質性肺炎は、肺の間質に炎症が起こり、線維化が進行する疾患の総称です。原因により、膠原病関連、薬剤性、職業性・環境性、特発性などに分類され、200種類以上の疾患が含まれます。
病態の本質は、炎症から線維化への進行です。一度線維化した肺は元に戻らず、進行性に肺が硬くなり、拘束性換気障害と拡散障害により低酸素血症が進行します。特発性肺線維症(IPF)は最も多く、予後不良で、診断後の生存期間中央値は3〜5年です。
症状は、労作時呼吸困難と乾性咳嗽が特徴的で、進行すると安静時にも呼吸困難が出現します。身体所見では、捻髪音とばち指が特徴的です。
診断は、胸部高解像度CT(HRCT)が最も重要で、蜂巣肺、網状影などの所見から病型を推定します。呼吸機能検査では拘束性換気障害と拡散能低下が見られます。
治療は、原因と病型により異なります。特発性肺線維症では抗線維化薬(ピルフェニドン、ニンテダニブ)が標準治療で、線維化の進行を遅らせます。ステロイドが効く病型では、ステロイドや免疫抑制薬が使用されます。低酸素血症が進行した場合、在宅酸素療法(HOT)が導入されます。
看護の要点は、呼吸困難の緩和、酸素療法の管理、呼吸リハビリテーション、栄養管理、心理的支援です。体位の工夫、呼吸法の指導、環境調整、薬物療法により呼吸困難を緩和します。在宅酸素療法の指導、感染予防、急性増悪の早期発見も重要です。
間質性肺炎、特に特発性肺線維症は進行性で予後不良の疾患であり、患者と家族は大きな不安を抱えます。傾聴の姿勢を持ち、患者の思いを受け止め、希望を支える関わりが大切です。早期から緩和ケアを導入し、QOLの維持を目指します。
実習では、呼吸困難という苦痛に寄り添い、その人らしく生きることを支える看護を実践しましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

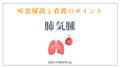

コメント