疾患概要
定義
糖尿病性網膜症は、糖尿病の三大合併症の一つで、持続的な高血糖により網膜の血管が障害される疾患です。網膜毛細血管の閉塞と透過性亢進により、網膜虚血、出血、浮腫、新生血管形成などが生じます。進行により単純糖尿病網膜症、前増殖糖尿病網膜症、増殖糖尿病網膜症に分類され、最終的には失明に至る可能性があります。糖尿病発症から15-20年経過すると約80%の患者に何らかの網膜症が出現し、失明原因の第2位を占める重要な疾患です。
疫学
日本の糖尿病患者約1,000万人のうち、約300万人が糖尿病性網膜症を合併していると推定されます。1型糖尿病では発症から5年以内にはほとんど出現せず、15年で約80%、20年以上で約95%に網膜症が認められます。2型糖尿病では診断時に既に約20%で網膜症が存在し、発症から10年で約40%、20年で約80%に達します。HbA1cが8.0%以上、罹病期間が長い、血圧コントロール不良、腎症合併などが進行の危険因子となります。近年、糖尿病治療の向上により重篤な増殖網膜症は減少傾向にあります。
原因
糖尿病性網膜症の根本的原因は慢性的な高血糖です。高血糖により糖化最終産物(AGEs)が蓄積し、網膜血管の内皮細胞や周皮細胞が障害されます。また、プロテインキナーゼC活性化、ポリオール代謝経路の亢進、酸化ストレスなども血管障害に関与します。血管透過性の亢進により血液網膜関門が破綻し、毛細血管の閉塞により網膜虚血が生じます。虚血により血管内皮増殖因子(VEGF)などの血管新生因子が産生され、異常な新生血管の形成が促進されます。
病態生理
糖尿病性網膜症の病態は段階的に進行します。単純糖尿病網膜症では毛細血管瘤、点状・斑状出血、硬性白斑(脂肪やタンパク質の沈着)が出現します。前増殖糖尿病網膜症では軟性白斑(網膜梗塞巣)、静脈異常、網膜内細小血管異常(IRMA)が加わり、網膜虚血が進行します。増殖糖尿病網膜症では新生血管、線維血管組織の増殖により、硝子体出血、牽引性網膜剥離、血管新生緑内障などの重篤な合併症が生じます。糖尿病黄斑浮腫は任意の段階で合併し、視力低下の主要因となります。
症状・診断・治療
症状
糖尿病性網膜症は初期は無症状で進行することが特徴です。単純網膜症から前増殖網膜症の段階では視力低下や自覚症状はほとんどありません。糖尿病黄斑浮腫が生じると中心視力の低下、変視症(物が歪んで見える)、中心暗点が出現します。増殖網膜症では硝子体出血により突然の視力低下や飛蚊症、光視症が生じます。牽引性網膜剥離では視野欠損が進行し、血管新生緑内障では眼痛、充血、急激な視力低下を認めます。症状が出現した時点では既に進行していることが多いため、定期的な眼底検査が重要です。
診断
診断は眼底検査が基本で、散瞳下での詳細な観察が必要です。フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)では血管透過性亢進、毛細血管閉塞領域、新生血管の検出が可能で、病期分類と治療方針決定に重要です。光干渉断層計(OCT)は黄斑浮腫の診断と経過観察に有用で、網膜厚の定量的測定により治療効果を評価できます。超広角眼底撮影により周辺部網膜の詳細な観察が可能となり、病変の見落としを防げます。血液検査ではHbA1c、血糖値、腎機能を評価し、全身状態との関連を把握します。
治療
治療の基本は血糖コントロールの改善です。DCCT研究により厳格な血糖管理が網膜症の発症・進行を有意に抑制することが証明されています。目標はHbA1c 7.0%未満ですが、低血糖リスクを考慮して個別に設定します。レーザー光凝固術は網膜症治療の基本で、汎網膜光凝固術により新生血管の退縮を図り、局所光凝固術により黄斑浮腫を改善します。抗VEGF薬硝子体注射(ラニビズマブ、アフリベルセプトなど)は黄斑浮腫や増殖網膜症に対する新しい治療法として効果が期待されています。重篤な硝子体出血や牽引性網膜剥離には硝子体手術が必要となります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 感覚知覚変調(視覚):網膜血管障害に関連した視力低下・視野欠損
- 血糖値不安定リスク状態:不適切な血糖管理に関連した網膜症進行の危険性
- 不安:進行性視覚障害と失明への恐怖
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは糖尿病と網膜症に対する患者の理解度と自己管理能力を評価します。血糖自己測定、薬物療法の継続性、食事療法の実践状況、定期受診の継続性を詳細に把握します。認知・知覚パターンでは視力低下や視野欠損の程度と日常生活への影響を評価し、血糖自己測定への影響、インスリン注射の手技への支障、低血糖症状の認識能力を確認します。栄養・代謝パターンでは糖尿病食事療法の実践状況と血糖コントロールへの影響を評価し、視覚障害による食事準備の困難さも考慮します。
ヘンダーソン14基本的ニード
学習するでは視覚障害が糖尿病の自己管理学習に与える影響を評価し、視覚に頼らない血糖測定方法や音声機能付き血糖測定器の導入を検討します。安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは視覚障害による低血糖時の危険認識能力の低下や、インスリン注射時の安全性を評価します。働くこと、達成感を得るでは視覚障害による職業への影響と、糖尿病管理との両立について支援ニーズを把握します。
看護計画・介入の内容
- 血糖管理・合併症予防:厳格な血糖コントロールの重要性説明、HbA1c目標値の理解促進、血糖自己測定の継続支援、低血糖予防と対処法の指導、定期的な眼科受診の重要性説明
- 視覚障害対応・安全管理:視力に応じた血糖測定器具の選択支援、インスリン注射の安全な手技指導、視覚障害に適応した生活環境整備、緊急時対応方法の確立、家族への協力依頼
- 心理的支援・疾患受容:視覚障害への不安に対する共感的対応、段階的な病状説明と希望の維持、視覚障害者支援制度の紹介、同病者との交流機会の提供、家族の心理的支援
よくある疑問・Q&A
Q: 血糖値が良くなれば視力は回復しますか?網膜症は治りますか?
A: 残念ながら一度生じた網膜症の変化は基本的に不可逆性で、失われた視力の完全な回復は期待できません。しかし、厳格な血糖管理により網膜症の進行を大幅に抑制することは可能です。DCCT研究では厳格な血糖管理により網膜症の発症リスクが76%、進行リスクが54%減少することが示されています。早期であれば軽微な変化は改善することもあり、何より進行防止のために血糖コントロールの改善は極めて重要です。
Q: レーザー治療は痛いですか?視力は良くなりますか?
A: レーザー光凝固術は外来で行える治療で、点眼麻酔により痛みは最小限に抑えられます。治療中に軽い痛みや眩しさを感じることがありますが、多くの患者さんが耐えられる程度です。レーザー治療の目的は視力の改善ではなく、現在の視機能の保持です。新生血管の退縮や浮腫の軽減により、失明や重篤な視力低下を防ぐことができます。治療後は一時的に視野の一部が欠ける場合がありますが、失明を防ぐために必要な治療です。
Q: 抗VEGF薬の注射は安全ですか?どのくらいの頻度で必要ですか?
A: 抗VEGF薬の硝子体注射は比較的安全な治療で、重篤な副作用の頻度は低いとされています。感染症のリスクは約0.1%以下で、厳重な無菌操作により予防できます。治療頻度は病状により異なりますが、初回は月1回を3回連続、その後は症状に応じて2-3ヶ月ごとに行うことが多いです。OCTによる網膜厚測定で治療効果を評価し、必要に応じて追加治療を行います。注射後は感染予防のため眼をこすらず、異常があれば直ちに受診してください。
Q: 糖尿病と診断されました。いつから眼科を受診すべきですか?
A: 1型糖尿病では発症から5年後以降、2型糖尿病では診断時から直ちに眼科受診が必要です。2型糖尿病では診断時に既に網膜症が存在することがあるためです。その後は年1回以上の定期検査が推奨されますが、網膜症がある場合は3-6ヶ月ごと、血糖コントロール不良の場合はより頻回な検査が必要です。妊娠糖尿病や妊娠中の糖尿病では妊娠初期と各妊娠期ごとの検査が重要です。症状がなくても必ず定期受診を継続してください。
まとめ
糖尿病性網膜症は糖尿病の重要な慢性合併症として、患者さんの視機能と生活の質に深刻な影響を与える疾患です。病態の特徴は無症状での進行であり、症状が出現した時点では既に進行していることが多いため、予防的アプローチが極めて重要となります。
看護の中核は厳格な血糖管理の支援と定期的な眼科受診の促進です。糖尿病性網膜症の発症・進行は血糖コントロールと密接に関連しており、HbA1c 7.0%未満の維持が網膜症予防の基盤となります。血糖自己管理能力の向上を支援し、患者さんが継続的に良好な血糖コントロールを維持できるよう包括的にサポートすることが重要です。
視覚障害への適応支援も重要な看護の視点です。視力低下は糖尿病の自己管理に大きな影響を与えるため、視覚に頼らない血糖測定方法の習得や安全なインスリン注射手技の確立が必要です。また、低血糖時の症状認識や対処能力への影響も考慮し、安全な糖尿病管理を継続できるよう支援します。
心理的支援では、失明への恐怖や将来への不安に対して共感的に関わり、患者さんが希望を持って治療に取り組めるよう支援することが大切です。現在の医療技術により多くの患者さんで視機能の保持が可能であることを伝え、前向きな治療参加を促進します。
実習では糖尿病と眼疾患の両面からのアプローチを心がけましょう。血糖コントロールの状況と網膜症の進行度を総合的に評価し、個別性のある看護計画を立案することが重要です。また、家族への教育も含めた包括的なケアにより、患者さんが糖尿病と糖尿病性網膜症の両方を適切に管理し、豊かな人生を継続できるよう支援していきましょう。予防可能な失明を防ぐことは、患者さんの人生の質を大きく左右する重要な看護の役割です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
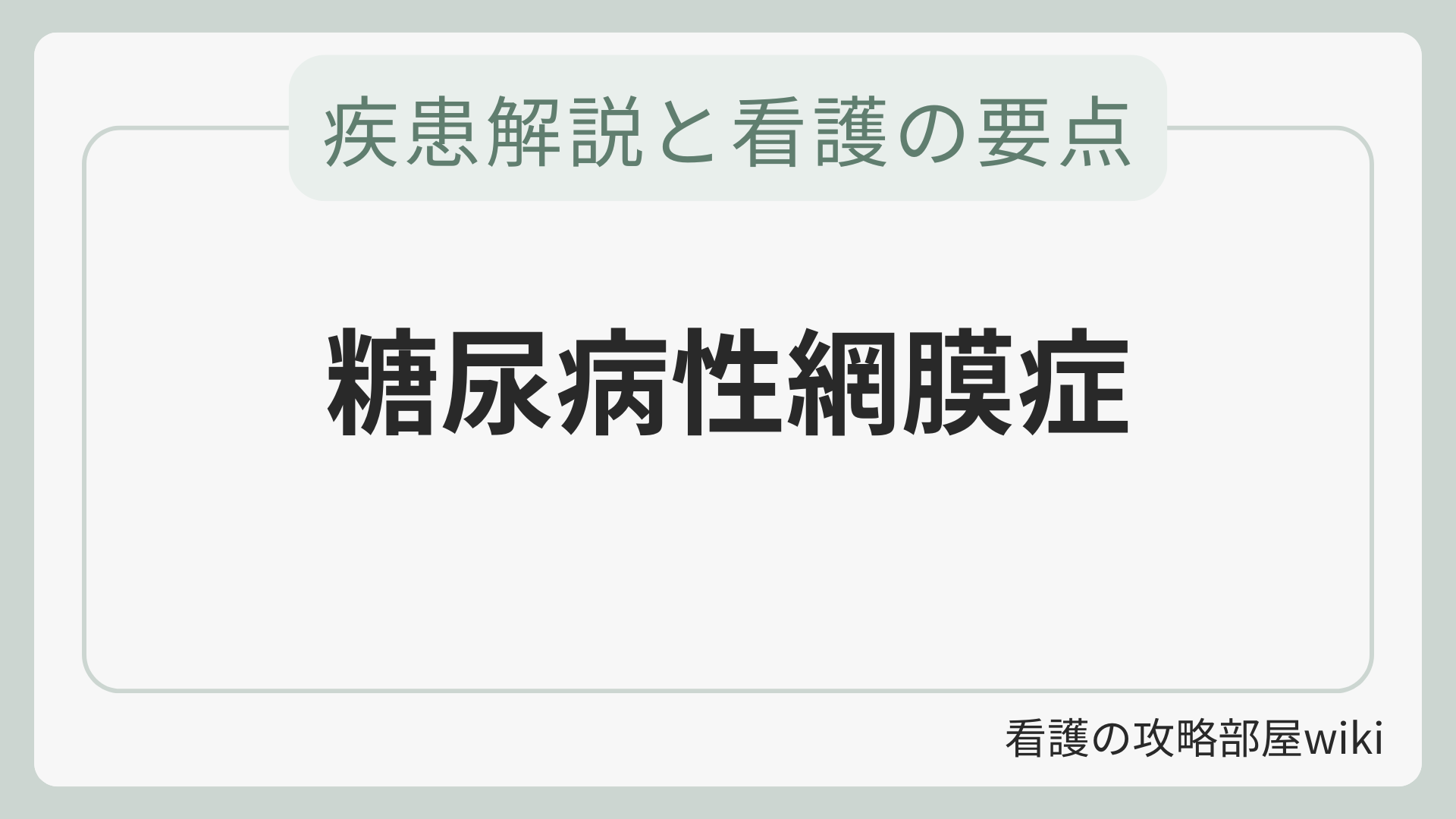
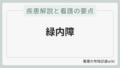
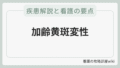
コメント