疾患概要
定義
多発性骨髄腫(Multiple Myeloma:MM)は、骨髄中の形質細胞が腫瘍化して無制限に増殖する血液がんです。形質細胞は本来、B細胞(リンパ球の一種)が分化した細胞で、抗体(免疫グロブリン)を産生して身体を感染から守る役割を担っています。しかし多発性骨髄腫では、この形質細胞が異常に増殖し、骨髄を占拠してしまいます。さらに、腫瘍化した形質細胞(骨髄腫細胞)はMタンパクと呼ばれる異常な抗体を大量に産生し、これが様々な臓器障害を引き起こします。「多発性」という名前は、骨髄の複数の部位に同時に腫瘍細胞が存在することに由来しています。
疫学
多発性骨髄腫は高齢者に多い疾患で、発症年齢の中央値は約65〜70歳です。50歳以下での発症は稀で、加齢とともに発症率が上昇します。日本における年間発症率は人口10万人あたり約5人程度とされており、血液がん全体の約10〜15%を占めます。男女比はやや男性に多く、約1.5:1です。欧米では黒人の発症率が白人の約2倍と高いことが知られています。高齢化社会の進展に伴い、患者数は増加傾向にあります。
原因
多発性骨髄腫の明確な原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。加齢が最も重要なリスク因子であり、遺伝子の異常が蓄積することで発症すると推測されています。その他、放射線被曝、化学物質への曝露(農薬、有機溶剤など)、慢性的な抗原刺激(慢性感染症、自己免疫疾患など)が関連している可能性が指摘されています。また、MGUS(意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症)という前がん状態から進行することがあり、MGUSの患者さんは年間約1%の確率で多発性骨髄腫に移行します。家族歴がある場合も発症リスクがやや高くなることが知られています。
病態生理
多発性骨髄腫の病態は、骨髄腫細胞の増殖とMタンパクの過剰産生という2つの柱から理解できます。
まず、骨髄内で腫瘍化した形質細胞が異常増殖すると、正常な造血が妨げられます。これにより、正常な赤血球、白血球、血小板の産生が減少し、貧血、感染症のリスク増加、出血傾向といった問題が生じます。特に貧血は初発症状として最も多く見られます。
骨髄腫細胞は破骨細胞を活性化させる物質(IL-6、RANKLなど)を分泌します。破骨細胞は骨を溶かす細胞で、これが過剰に活性化されると骨吸収が進み、骨破壊が起こります。その結果、骨に穴が開いたような状態(punched out lesion:打ち抜き像)や、病的骨折、脊椎圧迫骨折などが発生します。骨が溶けることで血中カルシウム濃度が上昇し、高カルシウム血症を引き起こすこともあります。
骨髄腫細胞が産生するMタンパクは、単一のクローン(1つの腫瘍細胞から増えた細胞群)由来の異常な免疫グロブリンです。このMタンパクが大量に産生されると、血液の粘度が上昇して過粘稠度症候群を引き起こし、血流が悪くなります。また、正常な免疫グロブリンの産生が抑制されるため、易感染性(感染症にかかりやすくなる)が生じます。
Mタンパクの一部やその断片(軽鎖:ベンス・ジョーンズタンパク)は腎臓で濾過されますが、大量に存在すると腎臓の尿細管に沈着し、腎障害を引き起こします。これを骨髄腫腎と呼び、多発性骨髄腫の予後を左右する重要な合併症です。高カルシウム血症、脱水、感染症、造影剤の使用なども腎障害を悪化させる要因となります。
また、骨髄腫細胞や骨破壊により血液中に放出された物質が神経を圧迫したり、アミロイドーシス(異常なタンパク質が臓器に沈着する病態)を合併したりすることで、神経障害や臓器障害を引き起こすこともあります。
症状・診断・治療
症状
多発性骨髄腫の症状は多彩ですが、初期には無症状のことも多く、健康診断での異常値から発見されることもあります。主な症状は「CRAB症状」という頭文字で覚えると整理しやすいでしょう。
C(Calcium elevation:高カルシウム血症)では、血中カルシウム濃度の上昇により、悪心・嘔吐、便秘、多尿、口渇、倦怠感、意識障害などが出現します。重症化すると昏睡に至ることもあります。
R(Renal insufficiency:腎機能障害)では、Mタンパクによる腎障害で、浮腫、尿量減少、血圧上昇、倦怠感などが見られます。進行すると透析が必要になることもあります。
A(Anemia:貧血)は最も頻度の高い症状で、動悸、息切れ、倦怠感、めまい、顔面蒼白などが現れます。骨髄腫細胞が正常な造血を妨げることで生じます。
B(Bone lesions:骨病変)では、骨痛(特に背部痛、腰痛、肋骨痛)、病的骨折、脊椎圧迫骨折による神経症状(しびれ、麻痺、排尿障害)などが出現します。骨痛は動作時に増強し、安静で軽減する特徴があります。
その他の症状として、易感染性による肺炎や尿路感染症の反復、過粘稠度症候群による頭痛、視力障害、出血傾向、血小板減少による出血症状などがあります。また、アミロイドーシスを合併すると心不全や末梢神経障害が生じることもあります。
診断
診断は血液検査、尿検査、画像検査、骨髄検査を組み合わせて行われます。
血液検査では、Mタンパクの検出が重要です。血清タンパク電気泳動でM蛋白のピーク(Mスパイク)を確認し、免疫電気泳動や免疫固定法でMタンパクの型(IgG、IgA、IgD、IgE、軽鎖のみなど)を同定します。また、β2ミクログロブリン、LDH、アルブミンなどは予後の評価に使用されます。血算では貧血、白血球減少、血小板減少を確認し、血清カルシウム、クレアチニンで合併症を評価します。
尿検査では、ベンス・ジョーンズタンパク(尿中の軽鎖)を検出します。24時間蓄尿を行い、尿中タンパク電気泳動で測定します。
画像検査では、全身の骨X線検査で打ち抜き像や骨融解像を確認します。近年では全身MRIやPET-CTがより早期の骨病変の検出に有用とされています。CT検査は骨折のリスク評価や脊椎圧迫骨折の評価に用いられます。
骨髄検査は確定診断に必須です。骨髄穿刺・生検により、骨髄中の形質細胞の割合(10%以上で診断基準を満たす)を確認し、形態や染色体異常を評価します。染色体検査やFISH法により予後に関わる遺伝子異常を調べることもあります。
診断基準としては、骨髄中のクローン性形質細胞が10%以上、または生検で証明された形質細胞腫に加えて、臓器障害(CRAB症状または特定のバイオマーカー異常)があることが必要です。
治療
治療方針は、患者さんの年齢、全身状態、臓器障害の有無、染色体異常などを総合的に評価して決定されます。
移植適応がある場合(一般に65〜70歳以下で全身状態が良好)は、自家造血幹細胞移植を含む治療が標準です。まず、寛解導入療法として、プロテアソーム阻害薬(ボルテゾミブなど)、免疫調節薬(レナリドミド、サリドマイドなど)、デキサメタゾン(ステロイド)を組み合わせた多剤併用療法を行います。効果が得られたら、自分の造血幹細胞を採取・保存し、大量化学療法(メルファラン大量療法)を行った後に、保存しておいた造血幹細胞を戻す(移植する)治療を行います。移植後は維持療法として免疫調節薬を継続することが推奨されています。
移植非適応の場合(高齢者や併存疾患がある場合)は、プロテアソーム阻害薬、免疫調節薬、デキサメタゾンを組み合わせた治療を継続的に行います。近年では、モノクローナル抗体薬(ダラツムマブなど)も使用され、効果を上げています。
支持療法も重要で、骨病変に対してはビスホスホネート製剤やデノスマブ(破骨細胞の働きを抑える薬)を投与し、骨折予防と骨痛の軽減を図ります。腎障害に対しては十分な水分補給と電解質管理、高カルシウム血症に対しては輸液とビスホスホネート製剤の投与を行います。感染予防のために予防的抗菌薬の投与や、貧血に対しては輸血やエリスロポエチン製剤の使用を検討します。
放射線療法は、限局した骨病変や脊髄圧迫などに対して局所的に行われます。
再発・難治性の場合は、さらに多様な薬剤(カルフィルゾミブ、イキサゾミブ、ポマリドミドなど)や、CAR-T細胞療法などの新しい治療法も選択肢となっています。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛(骨病変による骨痛)
- 活動耐性低下(貧血、骨痛、病的骨折リスク)
- 感染リスク状態(免疫機能低下)
- 転倒・骨折リスク状態(骨病変)
- 不安(予後、治療の副作用への不安)
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
多発性骨髄腫は治療により寛解は得られても完治が難しい疾患です。患者さんが診断や予後をどのように受け止めているか、治療への理解度や意欲はどうかをアセスメントします。長期にわたる治療となるため、患者さん自身が疾患と向き合い、治療を継続する意欲を支える関わりが重要です。
栄養-代謝パターン
貧血や治療の副作用(悪心・嘔吐、口内炎)により食欲不振が生じやすくなります。また、高カルシウム血症では悪心・嘔吐、便秘が出現します。体重変化、食事摂取量、BMI、血清アルブミン値などを評価し、栄養状態の維持に努めます。腎機能障害がある場合は、タンパク質や塩分の制限が必要になることもあります。
排泄パターン
高カルシウム血症では多尿が見られ、脱水のリスクが高まります。また、腎機能障害では尿量減少や浮腫が出現します。尿量、尿の性状、排尿パターンを観察し、水分出納バランスを管理します。便秘は高カルシウム血症やオピオイド系鎮痛薬の使用で生じやすく、予防的な対応が必要です。
活動-運動パターン
骨痛、貧血、病的骨折のリスクにより、活動が制限されます。しかし、過度の安静は骨量減少や筋力低下、深部静脈血栓症のリスクを高めるため、安全な範囲での活動維持が重要です。疼痛の程度、ADLの自立度、転倒リスクを評価し、個別的な活動計画を立てます。脊椎圧迫骨折や脊髄圧迫がある場合は、神経症状(しびれ、麻痺、排尿障害)の観察も必要です。
睡眠-休息パターン
骨痛により夜間の睡眠が妨げられることがあります。疼痛コントロールの状況、睡眠時間、睡眠の質を評価し、必要に応じて鎮痛薬の調整や睡眠薬の使用を検討します。体位の工夫(クッションの使用など)も効果的です。
認知-知覚パターン
高カルシウム血症では意識レベルの低下や見当識障害が出現することがあります。また、末梢神経障害(化学療法の副作用やアミロイドーシスによる)では、しびれや痛みが生じます。意識レベル、見当識、疼痛の程度と部位を評価します。骨痛は動作時に増強するため、疼痛の評価には体動との関連も確認します。
役割-関係パターン
長期治療により、仕事や家庭での役割が変化します。患者さんが自身の役割をどのように認識しているか、家族のサポート体制はどうかを評価します。社会的孤立や役割喪失感に対する支援が必要です。
ストレス-コーピングパターン
診断時のショック、再発への不安、長期治療への負担など、患者さんは大きなストレスを抱えています。ストレスへの対処方法、サポートシステムの有無を評価し、必要に応じて心理的サポートや専門家への相談を調整します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸する
貧血により息切れや動悸が生じやすくなります。呼吸回数、呼吸音、SpO2、活動時の呼吸状態を観察します。また、肺炎などの感染症にも注意が必要です。
適切に飲食する
栄養状態の維持が重要です。食事摂取量、体重、血清アルブミン値を評価し、少量頻回食や高カロリー食品の活用、口内炎への対処などを行います。腎機能障害がある場合は、水分・電解質・タンパク質の管理が必要です。
正常に排泄する
水分出納バランスの管理が重要です。特に腎機能障害がある場合は、尿量、浮腫、電解質異常を注意深く観察します。高カルシウム血症では脱水予防のための十分な水分摂取を促します。便秘の予防も重要です。
身体の位置を動かし、またよい姿勢を保持する
骨痛や病的骨折のリスクがあるため、体動時の注意が必要です。急激な体動や重いものを持つことは避け、体位変換時は複数人で対応します。ベッド柵の使用や転倒予防の環境整備も重要です。
睡眠と休息をとる
骨痛による睡眠障害に対して、鎮痛薬の適切な使用、体位の工夫、環境調整(照明、温度など)を行います。疼痛コントロールが不十分な場合は、医師と連携して薬剤の調整を検討します。
適当な衣類を選び、着たり脱いだりする
ADLの自立度に応じて、着脱しやすい衣類の選択や介助の程度を調整します。骨痛がある場合は、着脱時の体動に配慮します。
体温を正常範囲内に保つ
感染症のリスクが高いため、発熱の有無を定期的に観察します。発熱時は速やかに医師に報告し、感染源の検索と治療を開始します。
身体を清潔に保ち、身だしなみを整える
感染予防のために清潔を保つことが重要ですが、骨痛や貧血により入浴が負担となることもあります。全身状態に応じて、入浴方法(全身浴、シャワー浴、清拭)を選択します。化学療法中は皮膚の観察も重要です。
危険を回避する
転倒・骨折のリスクが高いため、環境整備(床の整理、手すりの設置)、適切な履物の選択、移動時の見守りや介助が必要です。また、感染予防のための手洗い、マスク着用、人混みを避けるなどの指導も行います。
他者とコミュニケーションをもつ
長期治療により社会的孤立が生じやすくなります。患者さんの思いを傾聴し、家族や医療チームとのコミュニケーションを支援します。患者会の情報提供も有効です。
自分の信仰に従って礼拝する
診断や予後に対する不安、死生観について患者さんが語る機会を持つことも重要です。スピリチュアルなニーズにも配慮します。
達成感をもたらすような仕事をする
治療により仕事を休職・退職せざるを得ない場合もありますが、可能な範囲での役割の継続や、新たな生きがいの発見を支援します。
遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する
体調に応じて、趣味や楽しみを継続できるよう支援します。活動制限がある中でも、患者さんが楽しみを見出せるよう工夫します。
学習する
疾患や治療についての理解を深め、自己管理能力を高められるよう教育的支援を行います。パンフレットや患者向けの資料を活用します。
看護計画・介入の内容
- 疼痛管理:骨痛の程度をペインスケールで評価し、鎮痛薬(NSAIDs、オピオイド、放射線療法など)の効果を確認します。疼痛が増強する動作を避け、体位の工夫やクッションの使用で安楽を図ります。
- 転倒・骨折予防:病室環境の整備(床の整理、手すりの設置、滑り止めマット)、移動時の見守りや介助、適切な履物の選択を行います。急激な体動や重量物の持ち上げを避けるよう指導します。
- 貧血への対応:活動時のバイタルサイン測定、活動と休息のバランス調整、必要に応じた輸血療法の実施を行います。めまいや立ちくらみがある場合は、ゆっくり動作するよう指導します。
- 感染予防:手洗い・うがいの励行、マスク着用、人混みを避ける、生ものを避けるなどの指導を行います。発熱時は速やかに受診するよう説明します。化学療法中は特に注意が必要です。
- 腎機能の管理:水分出納バランスの観察、尿量測定、体重測定、浮腫の有無を確認します。十分な水分摂取(2000ml/日以上)を促し、脱水を予防します。腎機能データ(BUN、クレアチニン)の推移を確認します。
- 高カルシウム血症の観察:意識レベル、悪心・嘔吐、便秘、多尿の有無を観察します。異常があれば速やかに医師に報告し、輸液やビスホスホネート製剤の投与を行います。
- 化学療法の副作用管理:悪心・嘔吐、口内炎、末梢神経障害(しびれ、痛み)、骨髄抑制(感染、出血)などの副作用を観察し、予防的な制吐剤の投与、口腔ケア、感染予防などを行います。
- 栄養管理:食事摂取量の観察、体重測定、血清アルブミン値の確認を行います。食欲不振がある場合は、少量頻回食、高カロリー食品の活用、経口栄養補助食品の利用を検討します。
- 心理的サポート:患者さんの不安や悩みを傾聴し、疾患や治療についての理解を深めるための教育的支援を行います。家族も含めた支援体制を整え、必要に応じて心理士やソーシャルワーカーとの連携を図ります。
- 自己管理教育:退院後の生活指導(感染予防、転倒予防、内服管理、受診のタイミングなど)を行い、患者さんが安心して自宅療養できるよう支援します。
よくある疑問・Q&A
Q: 多発性骨髄腫は完治する病気ですか?
A: 残念ながら、現時点では完治は難しい疾患です。しかし、治療法の進歩により、多くの患者さんで寛解(病気の勢いが抑えられた状態)が得られ、生存期間も大幅に延長しています。近年では、プロテアソーム阻害薬、免疫調節薬、モノクローナル抗体薬などの新しい治療薬が登場し、以前は数年だった生存期間が10年以上に延びるケースも増えています。「がんと共に生きる」という視点で、病気をコントロールしながら生活の質を保つことが治療の目標となります。患者さんには、治療により症状が改善し、日常生活を送れる可能性があることを伝え、希望を持って治療に取り組めるよう支援しましょう。
Q: 骨痛が強い患者さんへの看護で、特に注意すべき点は何ですか?
A: 骨痛は多発性骨髄腫の患者さんにとって最もQOLを低下させる症状の一つです。まず、疼痛の程度、部位、性質、増悪因子・軽減因子を詳しくアセスメントすることが重要です。骨痛は動作時に増強し、安静で軽減する特徴があるため、体動時には細心の注意が必要です。特に、急激な体動や重いものを持つことは病的骨折のリスクを高めるため避けます。体位変換や移乗時は複数人で対応し、患者さんに「これから動きますよ」と声をかけ、痛みがないか確認しながらゆっくり行いましょう。また、疼痛コントロールが不十分な場合は、医師と連携して鎮痛薬の種類や投与量、投与時間の調整を検討します。患者さんが「痛みを我慢しなくてよい」と理解し、痛みがある時は遠慮せず伝えられる関係性を築くことも大切です。
Q: 自家造血幹細胞移植の前後で、看護師として特に注意すべきことは何ですか?
A: 自家造血幹細胞移植は、大量化学療法により骨髄機能が完全に抑制されるため、移植前後の管理が非常に重要です。移植前は、造血幹細胞の採取(アフェレーシス)を行いますが、この際に低カルシウム血症やしびれなどの副作用が出ることがあるため、症状の観察が必要です。移植後は、造血が回復するまでの約2〜3週間は無菌室または準無菌室での管理が必要で、厳密な感染管理が求められます。白血球(特に好中球)が極度に減少する時期は、わずかな感染でも重症化するリスクがあるため、発熱や感染徴候を見逃さないよう観察します。また、口内炎、下痢、悪心・嘔吐などの副作用も強く出るため、症状緩和と栄養管理が重要です。輸血(赤血球、血小板)の必要性も高まります。患者さんは長期間の隔離により精神的にも辛い時期を過ごすため、心理的サポートも欠かせません。造血が回復し、退院後も感染予防は継続が必要で、日常生活での注意点を丁寧に指導しましょう。
Q: 高カルシウム血症が起こるとどうして意識障害が出るのですか?また、どのように対応すればよいですか?
A: 高カルシウム血症では、血中カルシウム濃度の上昇により神経や筋肉の興奮性が低下します。カルシウムは神経伝達や筋収縮に重要な役割を果たしていますが、濃度が高すぎると逆に神経細胞の機能が抑制され、意識レベルの低下や見当識障害、傾眠、昏睡などの中枢神経症状が出現します。また、高カルシウム血症は脱水を伴うことが多く、これがさらに症状を悪化させます。
看護師としての対応は、まず早期発見が重要です。意識レベルの変化、見当識障害、悪心・嘔吐、便秘、多尿、口渇などの症状を観察し、異常があれば速やかに医師に報告します。血清カルシウム値を確認し、高値であれば緊急対応が必要です。治療としては、大量輸液(生理食塩水)で脱水を補正し、カルシウムの尿中排泄を促進します。また、ビスホスホネート製剤(ゾレドロン酸など)やカルシトニン製剤を投与し、骨吸収を抑制してカルシウム値を下げます。輸液中は、水分出納バランスの厳密な管理、心不全の徴候(呼吸困難、浮腫)の観察、電解質の推移確認が必要です。意識障害がある場合は、転倒・転落予防、誤嚥予防も重要になります。
まとめ
多発性骨髄腫は、骨髄中の形質細胞が腫瘍化し、骨破壊や臓器障害を引き起こす血液がんです。病態の核心は、骨髄腫細胞の異常増殖とMタンパクの過剰産生にあり、これらが貧血、骨病変、腎障害、高カルシウム血症、易感染性といった多彩な症状を引き起こします。
看護の要点は、疼痛管理、転倒・骨折予防、感染予防、腎機能の管理、そして心理的サポートです。特に骨病変による骨痛と病的骨折のリスクは患者さんのQOLを大きく低下させるため、安全な環境整備と体動時の配慮が不可欠です。また、免疫機能の低下により感染症にかかりやすくなるため、厳密な感染管理と早期発見が重要です。
治療は長期にわたり、完治は困難ですが、新しい治療薬の登場により予後は改善しています。患者さんが希望を持ち、病気と共に生きていけるよう、身体的ケアと心理的サポートの両面から支援することが求められます。
実習では、骨痛の程度や転倒リスクを丁寧にアセスメントすること、感染徴候を見逃さないこと、そして長期治療に伴う患者さんの不安や葛藤に寄り添うことを意識しましょう。多発性骨髄腫の患者さんは、診断時のショックや予後への不安を抱えながらも、治療を継続し、日常生活を送ろうとしています。その姿勢を尊重し、個別性を大切にした看護を提供してください。
また、高齢者に多い疾患であるため、加齢に伴う他の併存疾患(糖尿病、高血圧、心疾患など)への配慮や、ポリファーマシー(多剤併用)のリスクにも注意が必要です。多職種と連携しながら、包括的な視点で患者さんを支えていきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません

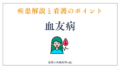
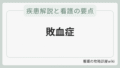
コメント