疾患概要
定義
炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease: IBD)は、腸管に慢性的な炎症を引き起こす原因不明の疾患群です。主に潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis: UC)とクローン病(Crohn’s Disease: CD)の2つが含まれます。
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に限局した炎症が特徴で、直腸から連続的に口側へ広がります。一方、クローン病は口腔から肛門までの消化管全域に発生する可能性があり、全層性の炎症と非連続性の病変(とびとびの炎症)が特徴です。
両疾患とも慢性の経過をたどり、寛解(症状が落ち着いている状態)と増悪(症状が悪化する状態)を繰り返すことが多いです。厚生労働省の指定難病に指定されています。
疫学
日本における炎症性腸疾患の患者数は近年増加傾向にあります。
潰瘍性大腸炎の患者数は約22万人以上とされ、発症年齢は20〜30代の若年層と50〜60代に2つのピークがあります。男女比はほぼ同等か、やや男性に多い傾向です。
クローン病の患者数は約7万人以上で、発症年齢は10〜20代の若年層に多く見られます。男女比は約2:1で男性に多いという特徴があります。
欧米諸国と比較すると日本の発症率は低いものの、食生活の欧米化などの影響で増加が続いており、今後も患者数の増加が予想されています。地域差については、都市部でやや多い傾向が指摘されています。
原因
炎症性腸疾患の明確な原因は解明されていませんが、遺伝的素因、環境要因、免疫異常の3つが複雑に関与していると考えられています。
遺伝的素因としては、家族内発症が見られることから遺伝的な関連が示唆されています。特定の遺伝子変異が発症リスクを高めることも分かっていますが、単一の遺伝子で発症するわけではありません。
環境要因では、食生活の欧米化(高脂肪・高タンパク食)、喫煙、ストレス、腸内細菌叢の変化などが関与すると考えられています。興味深いことに、喫煙はクローン病のリスク因子ですが、潰瘍性大腸炎では逆に保護的に働くという報告があります。
免疫異常については、本来は無害である腸内細菌や食物成分に対して、免疫システムが過剰に反応してしまい、自分の腸管を攻撃してしまうという自己免疫的なメカニズムが考えられています。
病態生理
炎症性腸疾患の病態は、両疾患で異なる特徴を持ちます。
潰瘍性大腸炎の病態では、炎症は必ず直腸から始まり、連続的に口側へ広がっていきます。炎症は粘膜と粘膜下層に限局し、深い層までは及びません。病変部では粘膜のびらんや潰瘍が形成され、出血しやすい状態になります。長期経過すると粘膜の萎縮や偽ポリープの形成が見られることもあります。炎症の範囲により、直腸炎型、左側大腸炎型、全大腸炎型に分類されます。
クローン病の病態は、より複雑です。炎症は消化管のどの部位にも発生する可能性がありますが、特に回腸末端部と大腸に好発します。特徴的なのは全層性の炎症で、粘膜から漿膜まで腸管壁全体が侵されます。このため、狭窄や瘻孔、膿瘍などの合併症を起こしやすくなります。病変は非連続性で、正常な腸管と病変部が交互に存在する「とびとび」の分布を示します。内視鏡で観察すると「敷石状外観」と呼ばれる特徴的な所見が見られることがあります。
両疾患に共通するのは、Th1/Th2バランスの異常や制御性T細胞の機能不全などの免疫学的異常が背景にあることです。炎症性サイトカインの過剰産生により、持続的な炎症反応が引き起こされます。
症状・診断・治療
症状
潰瘍性大腸炎の主な症状
血便、粘血便、下痢、腹痛が中心的な症状です。特に血便は最も特徴的な症状で、多くの患者さんが経験します。排便回数の増加、しぶり腹(便意はあるのに出ない感じ)、夜間の排便なども見られます。重症例では発熱、体重減少、貧血、頻脈などの全身症状も出現します。症状の程度により軽症、中等症、重症に分類されます。
クローン病の主な症状
腹痛、下痢、体重減少が中心です。潰瘍性大腸炎と異なり、血便は比較的少なく、腹痛が主体となることが多いです。病変部位により症状は異なり、小腸型では腹痛や下痢、小腸大腸型では腹痛・下痢・血便、大腸型では血便や下痢が主症状となります。肛門部病変(痔瘻、裂肛、肛門周囲膿瘍)は約半数の患者さんに見られ、診断の重要な手がかりとなります。
両疾患に共通する腸管外合併症
関節炎、結節性紅斑、壊疽性膿皮症などの皮膚症状、ブドウ膜炎などの眼症状、胆石症、腎結石などが見られることがあります。
診断
潰瘍性大腸炎の診断
診断は臨床症状、内視鏡検査、病理組織検査を総合して行います。内視鏡では直腸から連続的な炎症、びまん性の発赤、易出血性粘膜、血管透見像の消失などが観察されます。病理組織では陰窩膿瘍、杯細胞の減少、粘膜の炎症細胞浸潤などが特徴的です。
血液検査では炎症反応(CRP上昇、白血球増加)、貧血、低アルブミン血症などが見られます。便培養で感染性腸炎を除外することも重要です。
クローン病の診断
診断はより複雑で、臨床症状、内視鏡検査、画像検査、病理組織検査を組み合わせて行います。内視鏡では縦走潰瘍、敷石状外観、非連続性病変が特徴的です。小腸病変の評価には小腸内視鏡やカプセル内視鏡、CT・MRIエンテログラフィーなどが用いられます。
血液検査では炎症反応の上昇、貧血、低栄養状態の指標が見られます。便中カルプロテクチンは腸管炎症の評価に有用です。
治療
潰瘍性大腸炎の治療
治療の基本は薬物療法です。軽症から中等症では5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA、メサラジンなど)が第一選択となります。症状に応じて経口薬、注腸薬、坐薬を使い分けます。
中等症から重症、または5-ASA製剤で効果不十分な場合はステロイドを使用します。ステロイドは強力な抗炎症作用がありますが、長期使用による副作用(易感染性、骨粗鬆症、糖尿病など)に注意が必要です。
ステロイド抵抗性や依存性の症例には免疫調節薬(アザチオプリンなど)や生物学的製剤(抗TNFα抗体、抗インテグリン抗体など)、JAK阻害薬などが使用されます。
重症例や薬物療法が無効な場合、大量出血、穿孔、中毒性巨大結腸症などの合併症がある場合は外科手術(大腸全摘術)が検討されます。
クローン病の治療
治療は病変の部位、範囲、活動性、合併症の有無により異なります。軽症から中等症では5-ASA製剤やステロイドから開始しますが、クローン病では潰瘍性大腸炎ほど5-ASA製剤の効果は高くありません。
中等症以上では免疫調節薬や生物学的製剤が積極的に使用されます。特に生物学的製剤は粘膜治癒を目指す治療として重要な位置づけです。
栄養療法も重要で、特に小腸病変が主体の場合、成分栄養剤(エレンタールなど)による栄養療法が有効です。腸管の安静と栄養改善の両方に効果があります。
狭窄、瘻孔、膿瘍などの合併症がある場合は外科手術が必要となります。ただし、クローン病は手術しても再発しやすいため、可能な限り腸管を温存する方針がとられます。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 下痢に関連した排泄パターンの変調
- 頻回の排便・腹痛に関連した活動耐性低下
- 疾患に対する不安・ボディイメージの混乱
- 栄養吸収障害に関連した栄養不良のリスク
- 薬物療法の長期化に関連したアドヒアランス低下のリスク
- 慢性疾患に伴う社会的孤立のリスク
ゴードン機能的健康パターン
栄養-代謝パターン
頻回の下痢や腹痛により、食事摂取量が減少しやすく、低栄養状態に陥りやすいです。体重、BMI、血清アルブミン値、総タンパク値などを定期的に評価します。貧血の有無も重要な指標です。食事内容、食事回数、食べられないもの、症状と食事の関連についてアセスメントします。クローン病では特に低残渣食が推奨されることがあり、患者さんの理解度と実践状況を確認します。脱水症状の有無(口渇、皮膚の乾燥、尿量減少)にも注意が必要です。
排泄パターン
排便回数、便の性状(血便、粘血便、水様便など)、腹痛の有無と程度を詳細に観察します。夜間の排便は患者さんの睡眠を妨げ、QOLを大きく低下させるため、特に注意が必要です。トイレの場所や頻度により、外出や社会活動が制限されていないか確認します。肛門周囲の皮膚トラブル(びらん、発赤)の有無も観察し、適切なスキンケアを指導します。ストーマ造設されている場合は、ストーマケアの実施状況と受容状態を評価します。
活動-運動パターン
腹痛や頻回の排便により、日常生活動作が制限されていないか評価します。疲労感の程度、活動後の症状悪化の有無を確認します。適度な運動は心身の健康に有益ですが、活動期には無理をせず休息をとることが重要です。寛解期には適度な運動を推奨し、体力の維持・向上を図ります。
睡眠-休息パターン
夜間の排便や腹痛により睡眠が妨げられることが多く、睡眠時間、睡眠の質、日中の眠気の有無を評価します。十分な休息がとれていないと症状が悪化しやすく、また精神的ストレスも増大します。環境調整や生活リズムの見直しを支援します。
認知-知覚パターン
疾患や治療に関する理解度を評価します。特に生物学的製剤の自己注射を行っている場合は、手技の理解と実施状況を確認します。腹痛の部位、性質、程度、持続時間を詳しく聴取し、症状のパターンを把握します。疼痛管理の方法についても評価が必要です。
自己知覚-自己概念パターン
慢性疾患を持つことへの受容状態、ボディイメージの変化(特にストーマ造設例)、自己効力感の程度を評価します。若年発症が多いため、進学、就職、結婚などのライフイベントに対する不安や葛藤を抱えていることが多く、丁寧な傾聴が必要です。
役割-関係パターン
家族関係、友人関係、職場や学校での人間関係について評価します。疾患により社会的役割が果たせなくなっていないか、孤立していないかを確認します。家族の疾患理解とサポート体制も重要な評価項目です。
コーピング-ストレス耐性パターン
ストレスは症状悪化の要因となるため、ストレス源の有無、ストレス対処方法を評価します。寛解と増悪を繰り返す疾患の特性上、不確実性への対処が求められます。患者さんのコーピングスタイルを理解し、効果的なストレス管理方法を一緒に考えます。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常な呼吸をする
重症例では貧血や低栄養により、呼吸状態に影響が出ることがあります。バイタルサイン、特に呼吸数や酸素飽和度を観察します。
適切に飲食する
最も重要なニードの一つです。食事摂取量、食事内容、食事と症状の関連を詳細に観察します。栄養状態の評価(体重、BMI、血液データ)を行い、必要に応じて栄養士と連携した栄養指導を実施します。脱水予防のための水分摂取も重要です。
身体の老廃物を排泄する
排便状況の詳細な観察が必要です。排便回数、便の性状、腹痛の有無を記録し、症状の変化を早期に発見します。肛門周囲のスキンケアを適切に行い、皮膚トラブルを予防します。
身体の位置を動かし、また適切な肢位を保持する
腹痛時の安楽な体位を一緒に見つけます。活動と休息のバランスを考慮し、過度な安静や無理な活動を避けるよう支援します。
睡眠と休息をとる
夜間の症状により睡眠が妨げられやすいため、睡眠環境の調整、症状コントロールの工夫を行います。十分な休息は症状の安定に不可欠です。
適当な衣類を選び、着脱する
ストーマ造設例では、装具が目立ちにくい衣類の選択を支援します。頻回の排便に対応しやすい衣類の工夫も有用です。
衣類の調節と環境の調整により、体温を正常範囲に維持する
活動期の発熱に注意し、体温管理を行います。発熱は病状悪化のサインとなることがあります。
身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
肛門周囲の皮膚の清潔保持とスキンケアが重要です。頻回の排便により皮膚トラブルが起きやすいため、適切な洗浄方法と保湿を指導します。
環境の危険因子を避け、また他者を傷害しない
免疫抑制療法中は感染リスクが高まるため、手洗い、うがい、人混みを避けるなどの感染予防行動を指導します。生物学的製剤の自己注射時の針刺し事故予防も重要です。
自分の感情、欲求、恐怖あるいは気分を表現して他者とコミュニケーションをもつ
疾患への不安、将来への心配、日常生活の困りごとなどを表出できる環境を整えます。同じ疾患を持つ患者会の情報提供も有効です。
自分の信仰に従って礼拝する
患者さんの価値観や信念を尊重し、スピリチュアルな側面へのケアも考慮します。
達成感のあるような仕事をする
慢性疾患でありながら、社会的役割を果たし、自己実現できるよう支援します。就労支援、復学支援の情報提供も重要です。
遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する
疾患があっても楽しみや趣味を持ち続けられるよう支援します。寛解期には積極的な社会参加を推奨します。
正常な発達および健康を導くような学習をし、発見をし、あるいは好奇心を満足させる
疾患や治療に関する正しい知識の習得を支援します。自己管理能力を高めるための教育を継続的に行います。
看護計画・介入の内容
- 排便状況の詳細な観察と記録を行い、症状の変化を早期に発見する(回数、性状、量、随伴症状を含む)
- 水分出納バランスを観察し、脱水予防のための十分な水分摂取を促す
- 栄養状態を定期的に評価し、体重測定、食事摂取量の記録を行う
- 症状増悪因子(食事内容、ストレス、疲労など)を患者さんとともに特定し、回避方法を検討する
- 肛門周囲の皮膚状態を観察し、適切なスキンケア方法を指導する(微温湯洗浄、刺激の少ない石鹸の使用、保湿剤の塗布)
- 疼痛の程度を評価し、必要に応じて鎮痛薬の使用を検討する。非薬物的疼痛緩和法(体位の工夫、温罨法など)も提案する
- 薬物療法のアドヒアランスを確認し、服薬の重要性、副作用への対処法を説明する
- 生物学的製剤の自己注射を行っている場合、手技の確認と手技習得の支援を行う
- 感染予防行動(手洗い、うがい、マスク着用、人混みを避けるなど)を指導する
- 十分な睡眠と休息がとれるよう環境を整え、必要に応じて医師に睡眠薬の処方を相談する
- ストレス管理方法(リラクセーション法、趣味の時間の確保など)を一緒に考え、実践を支援する
- 患者さんの不安や悩みを傾聴し、心理的サポートを提供する
- 疾患や治療に関する正しい知識を提供し、自己管理能力を高める教育を行う
- 家族への疾患説明と介護指導を行い、家族のサポート体制を整える
- 社会資源(難病医療費助成制度、患者会、就労支援など)の情報を提供する
- ストーマ造設例では、ストーマケアの指導とボディイメージの変化への心理的サポートを行う
- 外来通院時には症状の変化、生活状況、困りごとを確認し、継続的な支援を提供する
よくある疑問・Q&A
Q: 潰瘍性大腸炎とクローン病の一番の違いは何ですか?
A: 大きな違いは病変の部位と深さです。潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に限局し、直腸から連続的に広がります。一方、クローン病は口から肛門まで消化管全体に発生する可能性があり、全層性の炎症が特徴です。また、症状としては潰瘍性大腸炎は血便が主体、クローン病は腹痛が主体という違いもあります。この違いを理解すると、観察のポイントや患者さんへの説明がしやすくなりますね。
Q: 食事制限はどの程度必要なのでしょうか?
A: 実は一律の食事制限はありません。患者さんごとに症状を悪化させる食品が異なるため、個別に見極めることが重要です。一般的には、活動期には低残渣食、脂肪制限食が推奨されますが、寛解期には特に厳しい制限は不要です。ただし、クローン病で狭窄がある場合は、繊維の多い食品や固形物を控える必要があります。患者さんが「これを食べると調子が悪い」という経験を大切にし、その情報を看護記録に残しておくことが、継続的なケアに役立ちます。
Q: 生物学的製剤の副作用で特に注意すべきことは?
A: 最も注意が必要なのは感染症のリスクです。生物学的製剤は免疫を抑える作用があるため、結核、肺炎、敗血症などの重篤な感染症を起こすリスクが高まります。使用前には必ず結核の検査(ツベルクリン反応、クォンティフェロン、胸部X線など)を行います。投与中は発熱、咳、倦怠感などの感染症状に注意し、早期発見・早期対応が重要です。患者さんには手洗い、うがい、人混みを避けるなどの感染予防行動の重要性を繰り返し説明しましょう。
Q: 患者さんから「一生この病気と付き合わないといけないのですか?」と聞かれたら、どう答えればよいですか?
A: とても難しい質問ですが、正直に「現在の医学では完治は難しいですが、適切な治療で症状をコントロールし、普通の生活を送ることは十分可能です」と伝えることが大切です。寛解維持という概念を説明し、症状が落ち着いた状態を長く保つことが治療の目標であることを伝えます。また、医療の進歩により新しい治療法が次々と開発されていることも希望のメッセージとして伝えられます。大切なのは、患者さんの不安に寄り添いながら、病気があっても前向きに生活できることを一緒に考える姿勢です。
Q: 若い患者さんから就職や結婚について相談されたらどうすればいいですか?
A: まず、患者さんの気持ちをしっかり受け止めることが大切です。「この病気があっても就職や結婚はできます」という前向きなメッセージを伝えつつ、具体的な不安(面接での説明、勤務形態、妊娠・出産の可能性など)について一つずつ話し合います。就職については、難病医療費助成制度を利用していることや、定期的な通院が必要なことを面接でどう伝えるか、トイレに頻繁に行く可能性があることをどう説明するかなど、実践的なアドバイスができるとよいですね。妊娠・出産については、寛解期であれば可能であること、使用できる薬剤や使用できない薬剤があることを説明し、必要に応じて医師と相談するよう促します。
Q: ストーマを造設することになった患者さんへのケアで大切なことは?
A: ボディイメージの変化への心理的サポートが最も重要です。特に若い患者さんでは、外見の変化に対する受容に時間がかかることがあります。患者さんのペースに合わせて、焦らずに関わることが大切です。実際のストーマケアでは、装具の選択、交換手技、皮膚トラブルの予防、日常生活での工夫(入浴、衣類、運動など)について段階的に指導します。同じ経験をした患者さんの体験談を聞く機会を設けたり、ストーマ外来の利用を勧めることも効果的です。「ストーマがあっても普通の生活ができる」という具体例を示すことで、希望を持ってもらえます。
まとめ
炎症性腸疾患は、若年層に好発する慢性疾患であり、寛解と増悪を繰り返すという特徴があります。潰瘍性大腸炎は大腸粘膜に限局した連続性の炎症、クローン病は消化管全層におよぶ非連続性の炎症という病態の違いを理解することが、適切な看護につながります。
症状としては、潰瘍性大腸炎では血便、クローン病では腹痛が主体となることが多く、この違いが観察のポイントになります。
看護の核心は、排泄パターンの管理と栄養状態の維持、そして心理的サポートの3つです。頻回の排便や腹痛により、患者さんのQOLは大きく低下するため、症状の詳細な観察と早期対応が求められます。また、慢性疾患であることから、長期的な視点での自己管理能力の向上が重要です。
治療面では、5-ASA製剤やステロイド、生物学的製剤など様々な薬物療法があります。特に生物学的製剤使用時の感染予防は看護の重要な役割です。薬物療法の効果と副作用を適切に評価し、患者さんのアドヒアランス向上を支援することが求められます。
患者さんの多くは思春期から若年成人期に発症するため、進学、就職、結婚、妊娠・出産といったライフイベントに対する不安を抱えています。疾患があっても自己実現できるよう、社会資源の活用や具体的な生活の工夫を一緒に考える姿勢が大切です。
実習では、患者さんの身体症状だけでなく、心理社会的な側面にも目を向けましょう。「病気を持ちながらどう生きるか」という患者さんの思いに寄り添い、長期的な視点で支援する姿勢が、炎症性腸疾患看護の基本となります。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
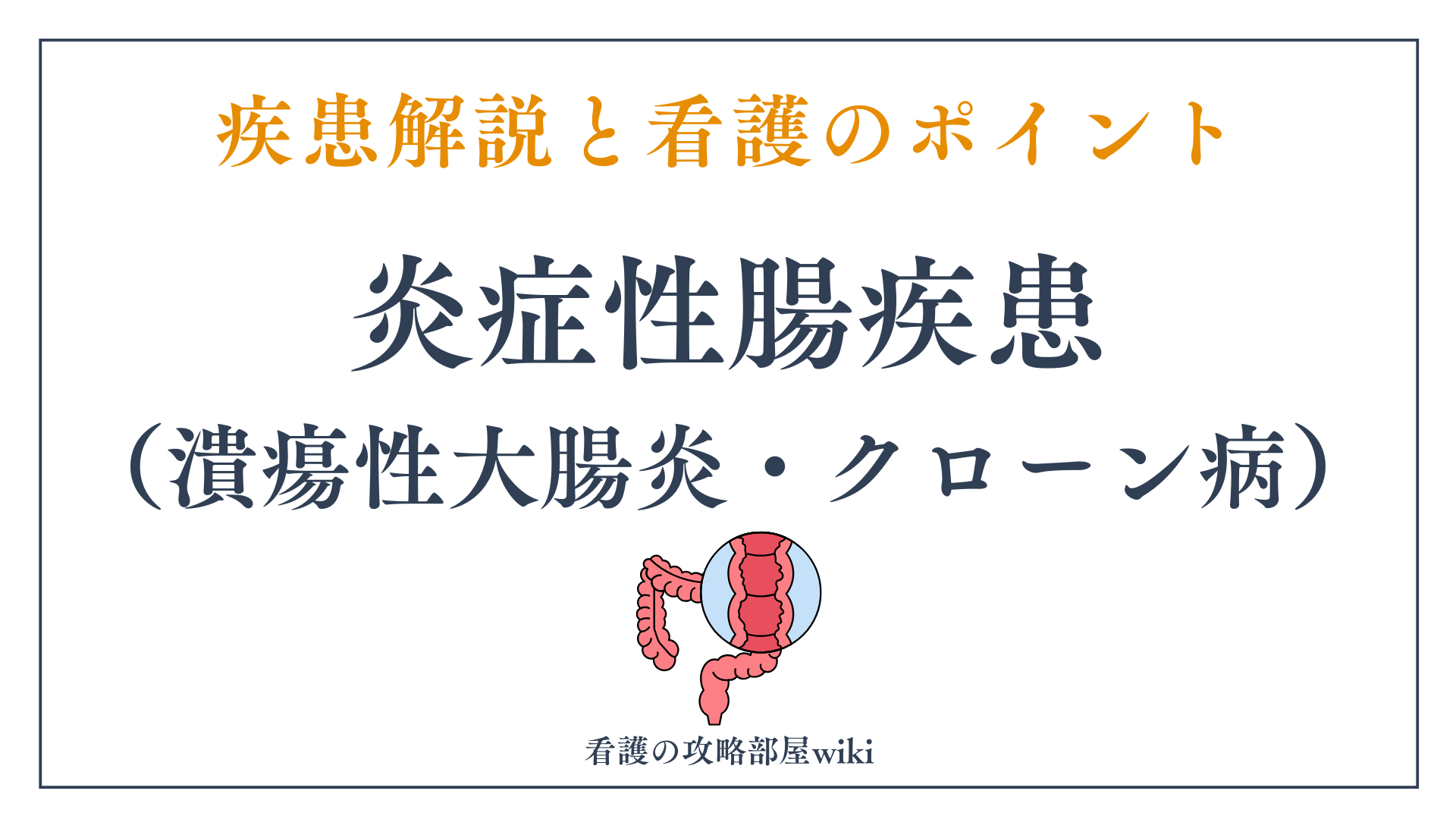
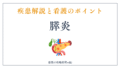
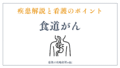
コメント