疾患概要
定義
結核とは、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)による慢性感染症です。主に肺に感染する肺結核が約85%を占めますが、リンパ節、骨・関節、腎臓、脳など全身の臓器に感染する肺外結核もあります。結核菌は抗酸菌の一種で、酸やアルカリに抵抗性があり、乾燥にも強く、外界で数ヶ月間生存可能です。感染力が強く、空気感染により人から人へ伝播する重要な感染症です。
疫学
結核は世界三大感染症の一つで、WHOによると世界で年間約1000万人が発症し、約150万人が死亡しています。日本では年間約15,000人が新たに発症し、約2,000人が死亡している重要な感染症です。高齢者に多く、新規患者の約70%が65歳以上で、特に80歳以上での発症率が高くなっています。
外国生まれの患者も増加傾向にあり、全体の約10%を占めています。多剤耐性結核(MDR-TB)や超多剤耐性結核(XDR-TB)も世界的に問題となっており、治療困難例が増加しています。日本の結核発症率は人口10万人あたり約11人で、中蔓延国に分類されています。
原因
結核の感染は空気感染(飛沫核感染)により起こります。感染性のある肺結核患者が咳やくしゃみをすることで、結核菌を含む飛沫核(直径5μm以下)が空気中に浮遊し、これを吸入することで感染します。感染=発病ではなく、感染者の約10%のみが生涯のうちに発病します。
発病の危険因子として、HIV感染、糖尿病、悪性腫瘍、ステロイド・免疫抑制薬の使用、透析、胃切除後、高齢、栄養不良、アルコール依存症などがあります。特にHIV感染者では健常者の約100倍発病しやすくなります。
感染源として最も重要なのは塗抹陽性肺結核患者で、1人の感染性患者から年間約10人に感染させる可能性があります。集団感染では学校、職場、医療機関、高齢者施設などの閉鎖的環境で発生しやすくなります。
病態生理
結核菌が肺胞に到達すると、マクロファージに貪食されますが、結核菌は細胞内で生存・増殖します。初感染では初期変化群(原発巣+リンパ節炎)が形成され、多くの場合は細胞性免疫により菌の増殖が抑制されます。この段階では症状はなく、潜在性結核感染症(LTBI)の状態となります。
免疫が低下すると菌が再活性化し、肉芽腫性炎症が生じます。結核特有の類上皮細胞肉芽腫が形成され、中心部に乾酪壊死を伴います。壊死組織が空洞を形成すると、菌が気道に排出され感染性となります。
細胞性免疫が結核の病態の中心で、Th1細胞からのインターフェロンγが重要な役割を果たします。ツベルクリン反応やインターフェロンγ遊離試験(IGRA)は、この細胞性免疫を利用した診断法です。血行性散布により粟粒結核を起こすこともあり、これは重篤な病型です。
症状・診断・治療
症状
結核の症状は緩徐に進行する慢性症状が特徴的です。呼吸器症状として、2週間以上続く咳(初期は乾性、進行すると湿性)、喀痰、血痰・喀血、呼吸困難、胸痛などが見られます。血痰は結核の重要な症状で、特に3週間以上続く咳と血痰があれば結核を強く疑います。
全身症状として、微熱(特に午後から夕方)、体重減少、食欲不振、全身倦怠感、寝汗などが現れます。これらの症状はB症状と呼ばれ、結核の特徴的な症状です。高齢者では典型的な症状を呈さないことがあり、食欲不振や体重減少のみで発見されることもあります。
肺外結核では感染部位により症状が異なります。結核性リンパ節炎では無痛性リンパ節腫脹、結核性髄膜炎では頭痛・嘔吐・意識障害、腎結核では血尿・頻尿、骨・関節結核では疼痛・腫脹などが見られます。
進行期では空洞形成により大量喀血、気胸、呼吸不全を来たすことがあり、粟粒結核では全身に散布されて重篤な状態となります。
診断
結核の診断は症状、画像診断、細菌学的検査を組み合わせて行います。胸部X線検査では、上肺野や肺尖部の陰影、空洞形成、胸膜肥厚などが特徴的所見です。胸部CT検査はより詳細な病変の評価が可能で、早期病変の発見や活動性の評価に有用です。
細菌学的検査が確定診断に最も重要で、喀痰塗抹検査(抗酸菌染色)、培養検査、核酸増幅検査(PCR)を実施します。塗抹陽性は感染性が高いことを示し、培養陽性で確定診断となります。培養には6-8週間を要するため、PCRによる迅速診断も重要です。
薬剤感受性検査は適切な治療薬選択のため必須で、標準的な4剤(イソニアジド、リファンピシン、エタンブトール、ピラジナミド)に対する感受性を調べます。IGRA(インターフェロンγ遊離試験)は潜在性結核感染症の診断に有用です。
病理学的検査では、ラングハンス型巨細胞を含む類上皮細胞肉芽腫と乾酪壊死が結核に特徴的な所見です。
治療
結核の治療は多剤併用化学療法が基本で、標準治療法では4剤(イソニアジド、リファンピシン、エタンブトール、ピラジナミド)を2ヶ月間投与後、2剤(イソニアジド、リファンピシン)を4ヶ月間投与する計6ヶ月間の治療を行います。
DOTS(Directly Observed Treatment, Short-course)では、医療従事者や家族が服薬を直接確認することで、確実な服薬と治療完遂を図ります。服薬中断は耐性菌出現の最大の原因となるため、DOTSは重要な治療戦略です。
多剤耐性結核(MDR-TB)では、セカンドライン薬を用いた18-24ヶ月間の治療が必要で、副作用も多く治癒率も低下します。潜在性結核感染症(LTBI)では、イソニアジド単剤を6-9ヶ月間投与します。
手術療法は薬物療法に抵抗性の限局性病変や大量喀血に対して考慮されますが、現在では稀です。感染対策として、塗抹陽性患者では空気予防策(陰圧個室、N95マスク)が必要で、通常は治療開始後2週間程度で感染性が低下します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 感染拡大リスク(結核菌の空気感染に関連した)
- 非効果的気道クリアランス(肺病変による喀痰増加に関連した)
- 栄養摂取不足(慢性消耗性疾患に関連した)
- 社会的孤立(感染症に対する偏見・隔離に関連した)
- 非効果的治療計画管理(長期間の多剤併用療法に関連した)
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは感染の危険因子と治療への理解を評価します。免疫状態、基礎疾患、生活環境、接触者の有無、結核に対する知識と理解度、服薬に対する意識を詳しく聴取し、感染拡大防止と治療継続への支援策を検討しましょう。
栄養・代謝パターンでは慢性消耗による栄養状態の詳細な評価が重要です。体重減少の程度、食欲・食事摂取量の変化、血清アルブミン値、BMIなどを評価し、栄養状態の改善と免疫機能の向上を図る栄養計画を立案します。
役割・関係パターンでは社会生活への影響と社会復帰への準備を評価します。職場や学校での対応、家族関係、経済状況、社会的偏見への対処方法を把握し、社会復帰に向けた包括的な支援を検討します。
ヘンダーソン14基本的ニード
呼吸のニードでは肺機能と感染性の評価が重要です。咳嗽の性状、喀痰の量・性状、血痰の有無、呼吸困難の程度、酸素飽和度を継続的に観察し、呼吸機能の改善と感染性の低下を評価します。
栄養のニードでは慢性消耗状態の改善が重要です。食欲増進策、高蛋白・高カロリー食の提供、体重モニタリング、栄養補助食品の活用などにより、栄養状態の改善と治癒促進を図ります。
安全のニードでは感染拡大防止が最重要です。適切な隔離、感染防護具の使用、環境整備、接触者検診の実施などにより、患者と周囲の人々の安全を確保します。
看護計画・介入の内容
- 感染管理:空気予防策の実施、陰圧個室管理、N95マスクの適切な使用、感染性評価
- 呼吸ケア:効果的な咳嗽・喀痰法の指導、体位ドレナージ、酸素療法、呼吸リハビリテーション
- 服薬管理:DOTS実施、服薬指導、副作用の観察、アドヒアランス向上支援
- 栄養管理:食事内容の調整、栄養補助、体重測定、食欲増進策
- 心理的支援:疾患受容の支援、偏見・差別への対処、家族関係の調整
- 社会復帰支援:職場・学校との連携、経済的支援の調整、継続治療体制の構築
よくある疑問・Q&A
Q: 結核はどのようにして感染しますか?
A: 空気感染(飛沫核感染)により感染します。感染性のある肺結核患者が咳やくしゃみをすると、結核菌を含む直径5μm以下の飛沫核が空気中に浮遊し、これを吸入することで感染します。接触感染や食べ物からの感染はありません。ただし、感染しても必ず発病するわけではなく、感染者の約90%は一生発病しません。免疫力が低下した時に発病リスクが高まります。
Q: 結核の治療期間はどのくらいですか?
A: 標準的な肺結核では6ヶ月間の治療が必要です。最初の2ヶ月間は4種類の薬(イソニアジド、リファンピシン、エタンブトール、ピラジナミド)を服用し、その後4ヶ月間は2種類の薬(イソニアジド、リファンピシン)を継続します。毎日確実に服薬することが重要で、途中で中断すると耐性菌が出現し、治療がより困難になります。
Q: 家族や職場の人への感染は心配ないですか?
A: 治療開始後約2週間で感染性は大幅に低下します。この期間は接触者との面会制限や隔離が必要ですが、その後は通常の生活が可能になります。接触者検診を実施して感染の有無を確認し、必要に応じて治療を行います。家族には胸部X線検査や血液検査(IGRA)を実施し、感染が確認されれば潜在性結核感染症の治療を検討します。
Q: 結核の薬の副作用はありますか?
A: 各薬剤に特有の副作用があります。イソニアジドでは末梢神経炎(手足のしびれ)、リファンピシンでは肝機能障害・尿の赤変、エタンブトールでは視覚障害、ピラジナミドでは肝機能障害・高尿酸血症などです。定期的な血液検査で肝機能や腎機能をチェックし、副作用の早期発見に努めます。副作用が出現しても自己判断で中断せず、必ず医師に相談することが重要です。
Q: 完治後も再発の可能性はありますか?
A: 適切な治療を完遂すれば再発率は非常に低い(1-2%程度)です。ただし、治療中断や不適切な治療では再発リスクが高まります。また、HIV感染や免疫抑制状態では再感染のリスクもあります。治療完了後も定期的な胸部X線検査による経過観察が重要で、咳や発熱などの症状が出現した場合は早期受診が必要です。
まとめ
結核は結核菌による慢性感染症であり、現在でも世界的に重要な感染症の一つです。看護師として重要なのは、感染拡大の防止、適切な治療の継続支援、患者の社会復帰への包括的な支援です。
特に厳格な感染管理の実施、DOTSによる確実な服薬支援、栄養状態の改善、心理社会的支援、接触者への適切な対応が看護の要点となります。結核は長期間の治療が必要で、社会的偏見も存在するため、患者の尊厳を保ちながら継続的な支援を行うことが重要です。
実習では感染管理技術の習得、呼吸器症状の観察技術、患者教育の実践などを学ぶ機会があると思います。また、患者・家族の不安や偏見に寄り添う姿勢を大切にし、根拠に基づいた説明と心理的支援を提供してください。
結核は確実に治癒可能な疾患である一方、適切な管理を怠ると重大な公衆衛生上の問題となります。個人の治療と公衆衛生の両面を考慮した看護ケアを提供し、患者が安心して治療を継続し、社会復帰できるよう専門的な支援を行っていきましょう。多職種との連携により、医学的管理から社会復帰支援まで包括的なケアの提供が求められます。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
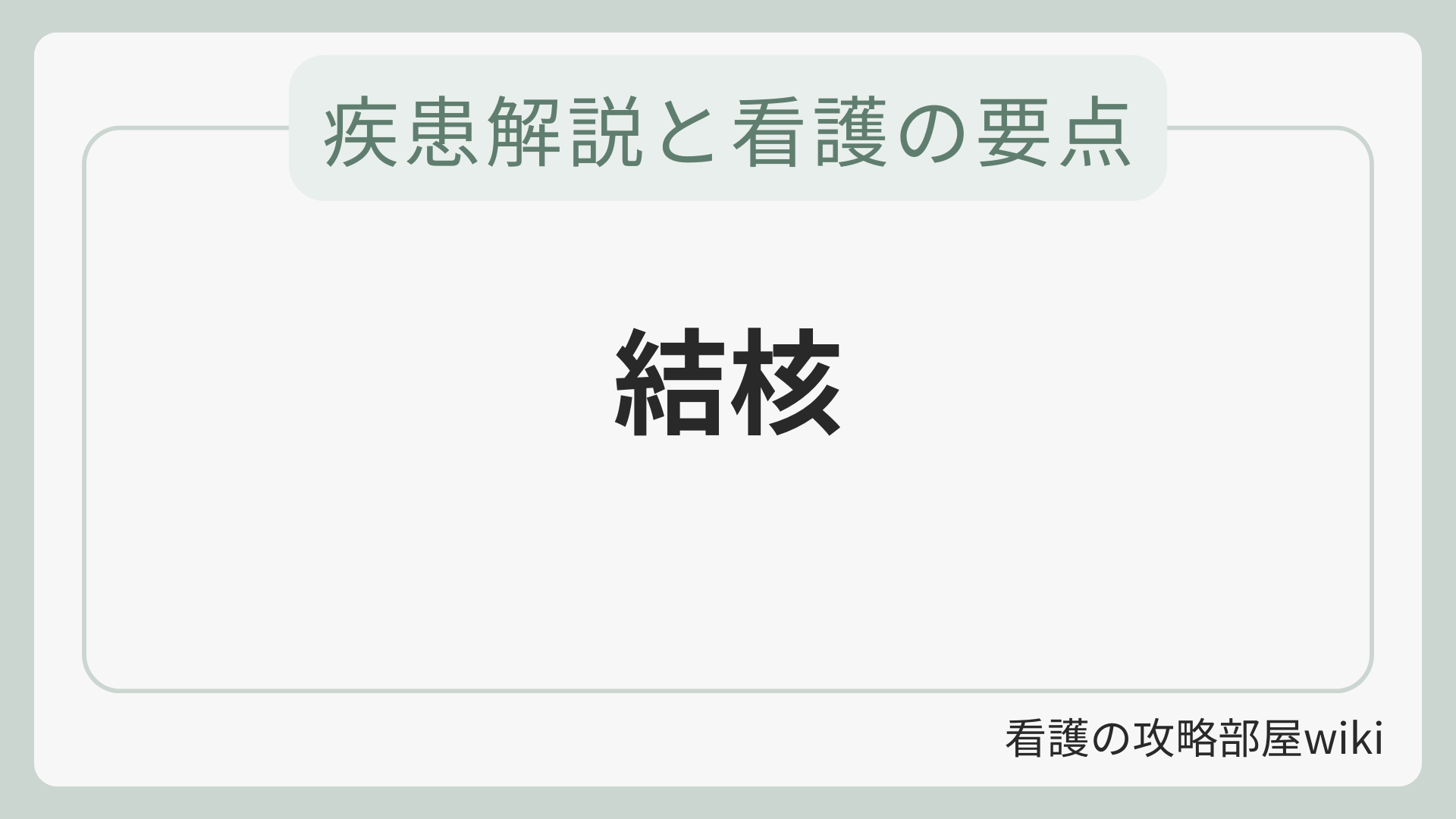
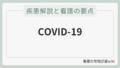
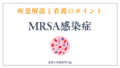
コメント