疾患概要
定義
MRSA感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus)による感染症です。MRSAは通常の抗菌薬(β-ラクタム系抗菌薬)が効かない多剤耐性菌であり、医療現場で最も重要な薬剤耐性菌の一つとなっています。黄色ブドウ球菌は本来、健康な人の鼻腔や皮膚に常在する菌ですが、MRSAは抗菌薬の選択圧により耐性を獲得した菌株です。感染症を発症すると治療が困難で、重症化しやすいという特徴があります。
疫学
MRSAは世界中の医療機関で問題となっており、日本の医療機関におけるMRSA検出率は入院患者の約50〜60%にのぼります。特に長期入院患者、ICU入室患者、術後患者、免疫不全患者で検出率が高くなっています。
MRSA感染症は市中感染型(CA-MRSA)と医療関連感染型(HA-MRSA)に分類されます。従来は病院内での感染が主でしたが、近年は市中でも健康な若年者に皮膚感染症や重症肺炎を起こすCA-MRSAが問題となっています。HA-MRSAは高齢者や基礎疾患を持つ患者に多く、術後創部感染、人工呼吸器関連肺炎(VAP)、カテーテル関連血流感染(CRBSI)などの医療関連感染として発症します。
原因
MRSA感染症の発症には、保菌状態から感染症への移行という過程があります。
まず、MRSAの保菌(コロニゼーション)が起こります。これは菌が体表に付着しているだけで、感染症を発症していない状態です。保菌の危険因子として、長期入院、広域抗菌薬の使用歴、手術歴、侵襲的医療デバイスの留置(中心静脈カテーテル、尿道カテーテル、気管挿管など)、褥瘡や創傷の存在、免疫抑制状態などが挙げられます。
保菌者が感染症を発症する要因として、宿主の免疫力低下、皮膚・粘膜バリアの破綻(手術創、褥瘡、カテーテル刺入部など)、侵襲的処置の実施、基礎疾患の悪化などがあります。
医療従事者の手指を介した伝播がMRSA拡散の最も重要な経路です。適切な手指衛生が行われないと、患者から患者へ容易に伝播します。また、環境表面(ベッド柵、オーバーテーブル、医療機器など)に付着したMRSAも感染源となります。
病態生理
黄色ブドウ球菌は様々な病原因子を持つ細菌で、MRSAもこれらの因子により組織障害を引き起こします。
MRSAが皮膚や粘膜のバリアを突破すると、組織に侵入して局所感染を起こします。コアグラーゼという酵素により血漿を凝固させてフィブリンの壁を形成し、自らを白血球の攻撃から守ります。また、毒素(エンテロトキシン、表皮剥脱毒素、TSS毒素など)を産生し、組織障害や全身性の炎症反応を引き起こします。
局所感染では、皮膚・軟部組織に膿瘍を形成しやすいのが特徴です。毛嚢炎、せつ、よう、蜂窩織炎などの皮膚感染症として発症します。手術創に感染すると、創部感染症(SSI)を起こし、創部の発赤、腫脹、膿性分泌物、離開などが見られます。
肺炎を発症すると、気道粘膜に炎症が生じ、肺胞に浸出液が貯留します。特に人工呼吸器関連肺炎(VAP)として発症することが多く、膿性痰、発熱、酸素化の悪化を呈します。MRSA肺炎は壊死性の変化を起こしやすく、重症化しやすいという特徴があります。
菌血症・敗血症では、MRSAが血流に侵入して全身に播種します。これは生命を脅かす重篤な病態で、高熱、悪寒戦慄、頻脈、血圧低下、意識障害などのSIRSやショック症状を呈します。血流に入ったMRSAは心内膜、骨、関節、脊椎などに播種し、感染性心内膜炎、骨髄炎、化膿性関節炎、脊椎炎などの転移性感染症を引き起こすことがあります。
MRSAはバイオフィルムを形成する能力を持ち、カテーテルや人工物の表面に付着すると、抗菌薬や免疫系から保護された環境を作り出します。これがカテーテル関連血流感染の原因となり、治療を困難にします。
症状・診断・治療
症状
症状は感染部位により大きく異なります。
皮膚・軟部組織感染症では、発赤、腫脹、熱感、疼痛が主な症状です。毛嚢炎では毛穴を中心とした小膿疱が、せつ・ようでは硬結を伴う有痛性の腫瘤が形成されます。蜂窩織炎では皮膚の広範囲に発赤と腫脹が広がり、境界が不明瞭です。手術創感染では、創部からの膿性分泌物、創部離開、周囲の発赤・腫脹が見られます。
肺炎では、発熱、咳嗽、膿性痰(黄色〜緑色)、呼吸困難が主症状です。胸部聴診で断続性ラ音(coarse crackles)が聴取されます。人工呼吸器装着患者では、吸引時の膿性分泌物の増加、酸素化の悪化(PaO2/FiO2比の低下)、胸部X線での新規浸潤影が重要な所見です。
菌血症・敗血症では、38℃以上の高熱または36℃未満の低体温、悪寒戦慄、頻脈(100回/分以上)、頻呼吸、血圧低下が見られます。重症例では意識障害、乏尿、チアノーゼなどのショック症状を呈し、多臓器不全に進展することがあります。
カテーテル関連血流感染(CRBSI)では、発熱とともにカテーテル刺入部の発赤、腫脹、圧痛、膿性分泌物が認められることがあります。ただし、局所症状がなくても菌血症を起こしている場合もあるため注意が必要です。
骨髄炎・化膿性関節炎では、患部の疼痛、腫脹、発赤、熱感、可動域制限が見られます。脊椎炎では背部痛と神経症状を呈することがあります。
診断
診断には、感染が疑われる部位からの検体採取と培養検査が必須です。
培養検査では、血液、喀痰、膿、尿、創部分泌物、体液などから検体を採取します。培養でMRSAが検出され、かつ感染症の臨床症状があれば、MRSA感染症と診断されます。重要なのは、保菌と感染症の区別です。単にMRSAが検出されただけでは感染症とは言えず、臨床症状や炎症反応と合わせて総合的に判断します。
薬剤感受性試験により、どの抗菌薬が有効かを確認します。MRSAはβ-ラクタム系抗菌薬に耐性ですが、バンコマイシン、テイコプラニン、リネゾリド、ダプトマイシンなどには感受性があることが多いです。
血液検査では、白血球数増加(特に好中球増加)、CRP上昇、プロカルシトニン上昇などの炎症反応を認めます。重症例では血小板減少、凝固異常、肝腎機能障害などが見られることもあります。
画像検査は感染部位の評価に有用です。肺炎では胸部X線やCTで浸潤影や膿瘍形成を確認します。骨髄炎や深部膿瘍の診断にはMRIが有用です。
治療
MRSA感染症の治療は、適切な抗MRSA薬の投与と感染源のコントロールが基本です。
抗MRSA薬として、第一選択はバンコマイシン(点滴静注)です。重症感染症では血中濃度をモニタリングしながら投与量を調整します。その他、テイコプラニン(点滴静注)、リネゾリド(点滴または経口)、ダプトマイシン(点滴静注)などが使用されます。軽症の皮膚感染症では、経口薬としてリネゾリドやST合剤が使用されることもあります。
治療期間は感染部位により異なり、単純な皮膚感染では1〜2週間、肺炎では2〜3週間、菌血症では最低2週間(合併症がある場合は4〜6週間以上)、骨髄炎では4〜6週間以上と長期になります。
感染源のコントロールも極めて重要です。膿瘍がある場合は切開排膿を行い、感染した創部は適切なデブリードマンが必要です。カテーテル関連血流感染では、カテーテルの抜去が原則です。人工物感染(人工関節、ペースメーカーなど)では、人工物の除去が必要になることもあります。
支持療法として、適切な輸液管理、栄養管理、バイタルサインの安定化、合併症の治療などを行います。重症敗血症やショックの場合は、ICUでの集中治療が必要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 感染:薬剤耐性菌による組織侵襲に関連した全身性または局所性感染
- 体温調節障害:感染性発熱に関連した高体温
- 感染伝播リスク状態:MRSA保菌に関連した他患者への感染拡大の可能性
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
MRSA感染症の予防と管理において、手指衛生の徹底が最も重要です。医療従事者は患者ケアの前後、体液に触れた後、患者周囲の環境に触れた後には必ず手指衛生を実施します。MRSAは接触感染で伝播するため、標準予防策に加えて接触予防策を実施します。個室隔離が望ましく、難しい場合は同じ耐性菌保菌者のコホーティング(同室管理)を検討します。入室時には手袋とガウンを着用し、退室時には適切な手順で脱ぎ、手指衛生を行います。
栄養-代謝パターン
感染症による発熱や異化亢進により、エネルギー消費が増加します。栄養状態の低下は免疫機能をさらに低下させ、感染症の遷延や創傷治癒の遅延につながります。食事摂取量、体重変化、血清アルブミン値、総リンパ球数などの栄養指標を評価し、必要に応じて栄養サポート(高カロリー食、栄養補助食品、経腸栄養、静脈栄養など)を検討します。特に高齢者や慢性疾患患者では、積極的な栄養管理が治療成績を左右します。
排泄パターン
抗MRSA薬(特にバンコマイシン)は腎毒性があるため、尿量と腎機能のモニタリングが重要です。尿量減少や血清クレアチニン値の上昇があれば、速やかに医師に報告します。また、尿道カテーテル留置は尿路感染とMRSA保菌のリスク因子となるため、不要なカテーテルは早期に抜去します。下痢がある場合、抗菌薬関連下痢や偽膜性腸炎の可能性も考慮し、便の性状と回数を観察します。
活動-運動パターン
重症MRSA感染症では、全身状態が不良でベッド上安静を要することが多くあります。長期臥床は褥瘡発生、筋力低下、深部静脈血栓症のリスクを高めます。可能な範囲で早期離床とリハビリテーションを促進しながら、褥瘡予防のための体位変換、除圧マットの使用、皮膚の観察を行います。また、呼吸器感染症では、体位ドレナージや呼吸理学療法が排痰促進に有効です。
認知-知覚パターン
高熱や敗血症により意識レベルが低下することがあります。意識レベル(JCS、GCS)、見当識、反応性を定期的に評価します。創部や関節の疼痛は患者のQOLを低下させるため、疼痛スケールを用いた評価と適切な鎮痛薬の使用が必要です。隔離による精神的苦痛も大きいため、患者の不安や孤独感に配慮した心理的サポートも重要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常な呼吸(呼吸のニード)
MRSA肺炎や人工呼吸器関連肺炎では、呼吸状態の継続的な観察が不可欠です。呼吸数、呼吸パターン(努力呼吸、陥没呼吸の有無)、SpO2、動脈血液ガス分析、胸部聴診所見を評価します。痰の性状(色、量、粘稠度)と喀痰培養結果を確認し、効果的な排痰を促すために、体位ドレナージ、吸引、ネブライザー療法などを実施します。人工呼吸器装着患者では、口腔ケアの徹底、カフ圧管理、半座位の保持がVAP予防に重要です。
正常な体温の保持(体温調節のニード)
MRSA感染症では高熱が持続することが多く、体温を4時間ごと(状態により2時間ごと)に測定します。38.5℃以上の発熱時は解熱薬の使用を検討しますが、発熱は感染に対する生体防御反応でもあることを理解します。クーリングを行う際は、悪寒戦慄や末梢循環不全を起こさないよう注意します。発熱により発汗が多い場合は、脱水予防のための水分補給と、快適性維持のための更衣や清拭を頻回に行います。
清潔と身だしなみ(清潔のニード)
皮膚の清潔保持はMRSAの定着を減らし、二次感染を予防します。毎日の入浴または清拭を実施し、特に腋窩、鼠径部、皮膚の襞などMRSAが定着しやすい部位は丁寧に洗浄します。褥瘡や創傷がある場合は、創部の適切な管理(洗浄、被覆材の交換)を行います。口腔内もMRSAの保菌部位となるため、口腔ケアを1日2回以上実施します。リネン類は毎日交換し、使用後は適切に処理します。
看護計画・介入の内容
- 感染徴候の観察:バイタルサイン測定(体温、脈拍、呼吸数、血圧を4時間ごと、重症例では1〜2時間ごと)、SIRS基準の評価(体温>38℃または<36℃、心拍数>90回/分、呼吸数>20回/分、白血球>12,000または<4,000/μL)、感染部位の局所所見観察(発赤、腫脹、熱感、疼痛、分泌物の性状と量)、血液検査データの確認(白血球数、CRP、プロカルシトニン、培養結果)、臓器機能のモニタリング(意識レベル、尿量、呼吸状態)
- 抗MRSA薬の管理:投与時間の厳守(特にバンコマイシンは血中濃度維持が重要)、投与方法の確認(点滴速度、投与時間)、副作用の観察(腎機能障害:尿量減少、クレアチニン上昇、聴器毒性:耳鳴り、難聴、アレルギー反応:発疹、そう痒感)、血中濃度測定の実施とタイミング(トラフ値の採血)、リネゾリド使用時の副作用観察(血小板減少、末梢神経障害、乳酸アシドーシス)
- 感染対策の実施:標準予防策+接触予防策の徹底、個室隔離または同室管理(コホーティング)、入室時の手袋・ガウン着用、退室時の適切な個人防護具の脱衣と手指衛生、手指衛生の5つのタイミング遵守(患者接触前、清潔/無菌操作前、体液曝露後、患者接触後、患者周囲環境接触後)、環境清掃の徹底(ベッド柵、オーバーテーブル、医療機器の毎日清掃)、使用物品の専用化または使い捨て製品の使用、リネン類の適切な取り扱い
- 医療デバイスの管理:中心静脈カテーテルの必要性の毎日評価と不要なラインの抜去、カテーテル刺入部の観察(発赤、腫脹、圧痛、分泌物)とドレッシング交換、尿道カテーテルの早期抜去検討と適切な管理、気管挿管チューブの適切な固定とカフ圧管理、人工呼吸器回路の取り扱いと交換
- 創傷管理:創部の観察(大きさ、深さ、滲出液の性状と量、肉芽形成、周囲の発赤・腫脹)、適切な創部洗浄(生理食塩水または微温湯)、ドレッシング材の選択と交換頻度の決定、膿瘍がある場合の切開排膿の介助、壊死組織除去(デブリードマン)の介助、ドレーン管理(排液量・性状の観察、固定確認)
- 患者・家族教育:MRSA感染症とMRSA保菌の違いの説明、感染対策の必要性と方法の説明、手指衛生の重要性と正しい方法の指導、隔離による精神的負担への配慮と説明、退院後の生活指導(手洗い、入浴、リネン管理、食器の取り扱いなど)、家族の不安への対応と正しい知識の提供(日常生活では過度な心配は不要であることの説明)
- 多職種連携:感染制御チーム(ICT)との連携、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)からの助言の活用、医師への感染徴候の迅速な報告、薬剤師との薬剤管理の連携、栄養士との栄養管理の連携、理学療法士との早期離床・リハビリの連携
よくある疑問・Q&A
Q: MRSAの患者さんを担当することになり不安です。看護学生が感染することはありますか?
A: 適切な感染対策を実施すれば、健康な看護学生がMRSAに感染するリスクは極めて低いので安心してください。MRSAは健康な人の皮膚に付着しても感染症を起こすことはほとんどありません。重要なのは標準予防策と接触予防策の徹底です。患者ケア時には手袋とガウンを着用し、ケア後は手袋を外してから石鹸と流水で手洗い、またはアルコール手指消毒を確実に行います。自分の顔(特に鼻や口)を触らないよう意識することも大切です。もし手袋をしていない手で患者や環境に触れてしまった場合でも、すぐに手指衛生を行えば問題ありません。実習では、指導者に手技を確認してもらいながら、正しい感染対策を身につける良い機会と捉えましょう。
Q: MRSA保菌者と感染症患者では、看護ケアに違いがありますか?
A: はい、違いがあります。保菌(コロニゼーション)は、MRSAが体表に付着しているだけで感染症の症状がない状態です。一方、感染症は、MRSAが組織に侵入して炎症反応を起こし、発熱、局所の発赤・腫脹・疼痛などの症状がある状態です。保菌者では抗MRSA薬の投与は通常不要ですが、感染症患者には治療が必要です。ただし、感染対策は両者とも同様に徹底します。なぜなら、保菌者も他の患者への感染源となり得るからです。保菌者が必ず感染症を発症するわけではありませんが、免疫力が低下したり手術を受けたりすると、保菌していたMRSAが感染症を起こすリスクがあります。そのため、保菌者でも標準予防策+接触予防策を実施し、他患者への伝播を防ぎます。
Q: MRSA患者の部屋から出る際、ガウンと手袋はどの順番で外せばよいですか?
A: 個人防護具(PPE)の脱ぎ方の順番は、汚染面を触らないことが原則です。正しい手順は以下の通りです。まず、手袋を外します。一方の手袋の外側を反対側の手袋をした手でつかみ、裏返しながら外します。外した手袋を残った手袋をした手で持ち、手袋をしていない手の指を残った手袋の内側に入れて裏返しながら外し、まとめて廃棄します。次にガウンを外します。首紐と腰紐を外し、肩から腕を抜きながら、ガウンの外側が内側になるように裏返して丸め、廃棄します。この際、ガウンの外側(汚染面)には触れないようにします。最後に手指衛生を必ず行います。この一連の動作は患者の部屋を出る前、または出た直後に行います。実習では、最初は指導者に見てもらいながら正しい手順を確実に身につけましょう。
Q: バンコマイシンを投与している患者さんで、どのような副作用に注意すればよいですか?
A: バンコマイシンの主な副作用は腎機能障害と聴器毒性です。腎機能障害の早期発見のため、尿量を正確に測定し(通常0.5mL/kg/時以上あることを確認)、血清クレアチニン値や尿素窒素(BUN)を定期的にチェックします。尿量が減少したり、クレアチニン値が上昇したりした場合は、すぐに医師に報告します。聴器毒性では、耳鳴りや難聴が生じることがあるため、患者に「耳が聞こえにくくなっていませんか」「耳鳴りはありませんか」と定期的に尋ねます。また、急速な点滴投与によりレッドマン症候群(顔面・上半身の発赤、掻痒感、血圧低下)が起こることがあるため、投与速度を守り(通常1時間以上かけて投与)、投与中は患者の様子を観察します。バンコマイシンは血中濃度をモニタリングしながら投与量を調整する薬剤なので、トラフ値(次回投与直前の血中濃度)測定のための採血タイミングを正確に守ることも重要です。
Q: MRSA患者さんの使用した食器や衣類は、特別な処理が必要ですか?
A: 病院内では通常の処理で問題ありません。食器は、通常の洗浄と熱水消毒または食器洗浄機での処理で十分です。MRSAは熱や乾燥に弱く、60℃以上の熱水で死滅します。食器を患者専用にする必要もありません。衣類やリネンは、他の患者のものと分けてビニール袋に入れて搬送し、通常の洗濯工程で処理されます。家庭では、通常の洗濯で問題ありませんが、熱湯(80℃以上)で洗うとより確実です。患者さんや家族に対しては、「特別な消毒は必要なく、普通の洗浄で大丈夫です」と説明し、過度な不安を軽減することが大切です。ただし、膿や血液などで明らかに汚染された衣類は、まず汚れを洗い流してから洗濯するよう指導します。
Q: MRSA保菌者が手術を受けることになりました。どのような注意が必要ですか?
A: MRSA保菌者の手術では、術後感染症のリスクが高いため、特別な対策が必要です。
まず、術前除菌が検討されます。鼻腔内保菌者には、ムピロシン軟膏を鼻腔内に塗布する除菌療法が行われることがあります。また、クロルヘキシジンやポビドンヨードを含む消毒薬での全身清拭を術前に数日間行うこともあります。これらにより、手術部位へのMRSA汚染のリスクを減らすことができます。
周術期の抗菌薬予防投与では、通常の予防的抗菌薬に加えて、抗MRSA薬(バンコマイシンやテイコプラニン)が併用されることがあります。これは手術中から術後にかけて投与され、手術部位感染(SSI)を予防します。
手術室では、標準予防策と接触予防策を継続し、手術器械や環境の汚染を最小限にします。術後は創部の厳重な観察が重要で、発赤、腫脹、熱感、膿性分泌物などのSSIの徴候を早期に発見します。
看護師の役割として、患者にMRSA保菌の事実を説明し、術前除菌の必要性を理解してもらうこと、除菌処置を確実に実施すること、術後の創部管理を徹底することが求められます。また、患者が「MRSA保菌者だから手術ができないのでは」と不安に思うこともあるため、「適切な対策をすれば安全に手術ができます」と説明し、精神的サポートを提供することも大切です。
よくある疑問・Q&A(続き)
Q: MRSA感染症の患者さんの隔離はいつまで続けるのですか?
A: 隔離解除の基準は施設により異なりますが、一般的には以下の条件を満たした場合に検討されます。
感染症が治癒していること、つまり発熱などの症状が消失し、創部が治癒し、炎症反応(白血球数、CRP)が正常化していることが前提です。その上で、連続3回の培養検査で陰性が確認された場合に隔離解除となることが多いです。培養検査は、鼻腔、咽頭、創部、尿など、以前にMRSAが検出された部位から採取します。検査の間隔は通常1週間おきです。
ただし、完全な除菌は困難であることも理解しておく必要があります。培養陰性でも、実際には少数のMRSAが残っている可能性があります。そのため、隔離は解除しても、その患者の医療ケアでは引き続き標準予防策を徹底します。
長期療養型病院や高齢者施設では、完全除菌を目指すよりも、感染症を発症していなければ日常生活の制限を最小限にするという考え方もあります。保菌者を隔離し続けることは、患者のQOLを著しく低下させ、精神的苦痛を与えるため、各施設のポリシーに従って適切に判断されます。
Q: 実習でMRSA患者を受け持った後、他の患者のケアもしてよいのですか?
A: これは実習施設の方針によりますが、基本的には適切な感染対策を実施すれば問題ありません。
重要なのは、MRSA患者のケアが終わった後、必ず手袋とガウンを外し、手指衛生を確実に行うことです。この手順を正しく実施すれば、看護師の手や衣服にMRSAが残ることはほとんどありません。
ただし、実習生の場合は、まだ感染対策の手技に不慣れなこともあるため、施設によっては「MRSA患者を受け持った学生は、その日は他の患者のケアは行わない」という方針をとることもあります。これは伝播リスクを最小限にするための慎重な対応です。
もし他の患者のケアも行う場合は、ケアの順番を考慮します。一般的には、感染リスクの高い患者(免疫不全、新生児、術直後など)を先にケアし、MRSA保菌者や感染症患者は最後にケアする方が安全です。
迷ったときは必ず指導者に確認し、施設のルールに従いましょう。自己判断で行動せず、不明点はその都度質問することが、安全な実習につながります。
まとめ
MRSA感染症は、薬剤耐性を獲得した黄色ブドウ球菌による感染症であり、治療が困難で重症化しやすいという特徴があります。特に免疫力の低下した患者や侵襲的医療処置を受けている患者では、生命を脅かす重篤な感染症に進展する可能性があります。
病態の本質は、通常の抗菌薬が効かない耐性菌が組織に侵入し、毒素や酵素により組織障害を引き起こすことにあります。治療には抗MRSA薬の適切な使用と感染源のコントロールが必須です。
看護の最重要ポイントは、手指衛生を中心とした感染対策の徹底と早期発見・早期治療のための観察です。医療従事者の手指がMRSA伝播の主要経路であることを常に意識し、手指衛生の5つのタイミングを確実に実践することが、MRSA感染拡大防止の鍵となります。また、抗MRSA薬の副作用モニタリング、医療デバイスの適切な管理、創傷ケア、栄養管理など、多角的なケアが求められます。
患者教育では、MRSA保菌と感染症の違い、日常生活での過度な不安は不要であること、ただし感染対策(特に手洗い)の重要性は継続すること、退院後の生活で特別な制限は基本的に必要ないことなどを、わかりやすく説明することが大切です。また、隔離による精神的苦痛に配慮し、患者や家族の不安に寄り添う姿勢も重要です。
実習では、MRSA患者のケアを通じて、感染対策の基本と重要性を実践的に学ぶことができます。標準予防策と接触予防策を正しく実施する技術、感染徴候を早期に発見する観察力、多職種と連携して感染管理を行う姿勢を養いましょう。適切な感染対策は患者を守るだけでなく、自分自身と他の患者、そして医療環境全体を守ることにつながります。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません

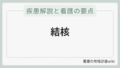
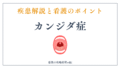
コメント