疾患概要
定義
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスによる急性呼吸器感染症で、季節性の流行を特徴とする感染症です。A型、B型、C型に分類され、臨床的に重要なのはA型とB型です。高い感染力と急激な症状の発現が特徴で、一般的な風邪症候群とは区別される疾患です。インフルエンザA型は抗原変異により世界的大流行(パンデミック)を引き起こす可能性があり、公衆衛生上重要な感染症として位置づけられています。合併症により重篤化することがあるため、ハイリスク患者への対応が特に重要となります。
疫学
日本では毎年冬季(12月~3月)に流行し、年間約1,000万人が罹患します。学童期での感染率が最も高く、学校や保育園などの集団生活の場で急速に拡散します。死亡者数は年間約3,000人で、その多くは65歳以上の高齢者です。超過死亡(インフルエンザ流行期の死亡者増加数)は年間約1万人と推定されています。A型インフルエンザは10-40年周期で大きな抗原変異を起こし、パンデミックを引き起こします。近年では2009年の新型インフルエンザ(H1N1pdm09)が記憶に新しく、院内感染対策の重要性が再認識されました。
原因
インフルエンザウイルスはオルトミクソウイルス科に属するRNAウイルスで、A型、B型、C型に分類されます。A型は表面抗原のヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の組み合わせにより亜型が決定されます(H1N1、H3N2など)。感染経路は主に飛沫感染で、咳やくしゃみにより飛散したウイルスを吸入することで感染します。接触感染(汚染された手指を介した感染)も重要な感染経路です。潜伏期間は1-3日で、発症1日前から発症後7日頃まで他者への感染力があります。ウイルスは抗原変異(連続変異、不連続変異)により免疫を回避し、反復感染や流行を引き起こします。
病態生理
インフルエンザウイルスは上気道粘膜に感染し、上皮細胞内で増殖します。ウイルスの増殖により細胞が破壊され、炎症反応が引き起こされます。全身症状の発現にはサイトカイン(インターロイキン、インターフェロンなど)の大量産生が関与し、これが発熱、筋肉痛、倦怠感などの全身症状を引き起こします。ウイルス感染により粘膜バリア機能が低下し、細菌の二次感染(肺炎球菌、黄色ブドウ球菌など)が起こりやすくなります。高齢者や基礎疾患患者では免疫応答の低下により重症化しやすく、若年者では過剰免疫反応により急激に悪化することがあります。
症状・診断・治療
症状
インフルエンザの症状は突然の発症が特徴的で、38℃以上の高熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠感などの全身症状が急激に出現します。呼吸器症状として咳嗽、咽頭痛、鼻汁、鼻閉が認められますが、一般的な風邪に比べて全身症状が強いことが特徴です。小児では発熱、嘔吐、下痢が主症状となることがあり、熱性けいれんを起こすこともあります。高齢者では発熱が軽微で、食欲不振、活動性低下、意識レベルの変化が主症状となる場合があります。合併症として肺炎、脳症、心筋炎、中耳炎などがあり、特に乳幼児や高齢者、基礎疾患患者で注意が必要でしょう。
診断
診断は臨床症状と迅速抗原検査により行われます。迅速抗原検査は発症後12-48時間で最も検出率が高く、15分程度で結果が得られます。ただし、発症極早期や発症後時間が経過した場合は偽陰性となる可能性があります。RT-PCR法はより高感度ですが、結果判明まで時間を要するため、一般的には迅速検査が用いられます。臨床診断では、流行期における急激な発症、高熱、全身症状の組み合わせが重要な判断材料となります。白血球数は正常または軽度減少、CRPは軽度上昇程度で、細菌感染症との鑑別に有用です。胸部X線検査は肺炎合併の評価に必要となります。
治療
治療の基本は対症療法と抗ウイルス薬の投与です。ノイラミニダーゼ阻害薬(オセルタミビル、ザナミビル、ラニナミビル、ペラミビル)は発症48時間以内の投与により症状の軽減と罹病期間の短縮が期待できます。エンドヌクレアーゼ阻害薬(バロキサビル)は1回の内服で治療が完了する新しい薬剤です。解熱にはアセトアミノフェンを使用し、アスピリンはライ症候群のリスクがあるため小児では禁忌です。対症療法として十分な水分摂取、安静、室内の加湿が重要です。抗菌薬はウイルス感染には無効ですが、細菌の二次感染が疑われる場合に投与されます。重症例では入院治療により全身管理と合併症対策を行います。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 感染拡大リスク状態
- 高体温
- 脱水リスク状態
- 活動耐性低下
- 非効果的気道クリアランス
- 急性疼痛
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、感染予防に対する理解度、手洗いやマスク着用などの感染対策の実施状況を評価します。栄養-代謝パターンでは発熱による食欲不振、水分摂取量の減少、脱水症状の有無を詳細に観察しましょう。活動-運動パターンでは全身倦怠感による活動制限の程度、呼吸困難の有無を評価します。睡眠-休息パターンでは発熱や咳嗽による睡眠障害、十分な休息が取れているかを確認することが重要です。認知-知覚パターンでは頭痛、筋肉痛、関節痛の程度と疼痛緩和の効果を評価し、小児では熱性けいれんや意識レベルの変化にも注意が必要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常な呼吸では咳嗽の性状、喀痰の有無、呼吸困難の程度を観察し、肺炎合併の早期発見に努めます。適切な飲食では発熱による脱水予防のため、こまめな水分摂取を促し、食欲不振時は消化の良い食事を提供します。正常な体温の維持では発熱パターンの観察、解熱対策の実施、熱中症予防が重要でしょう。身体の清潔保持と衣服の着脱では発汗による不快感の軽減、清拭による清潔保持を行います。安全で害のない環境の保持では感染拡大防止のための隔離対策、室内環境の調整(温度、湿度)が必要です。学習の側面では感染予防方法、早期受診の重要性について患者・家族への教育を行います。
看護計画・介入の内容
- 感染拡大防止対策:標準予防策の徹底、飛沫予防策の実施、手指衛生の指導、適切な隔離期間の管理
- 発熱・疼痛管理:体温モニタリング、解熱剤の適切な使用、冷却法や温罨法による症状緩和
- 脱水予防:水分バランスの観察、経口摂取の促進、必要に応じた輸液療法の管理
- 呼吸器症状の緩和:加湿による気道の保護、体位ドレナージ、咳嗽に対する対症的ケア
- 合併症の早期発見:肺炎、脳症、心筋炎等の症状観察、バイタルサインの継続的モニタリング
よくある疑問・Q&A
Q: インフルエンザの感染予防で最も重要なポイントは何ですか?
A: 手指衛生の徹底が最も重要です。アルコール系手指消毒薬または石けんと流水による手洗いを、患者接触前後、汚染された可能性のある物品に触れた後に必ず実施します。飛沫予防策として、患者との距離を1メートル以上保つ、サージカルマスクの着用、患者の咳エチケットの指導も重要です。ワクチン接種は感染予防と重症化予防に有効で、特に医療従事者や高リスク患者への接種が推奨されます。流行期には人混みを避ける、十分な睡眠と栄養による体調管理も感染予防に寄与するでしょう。
Q: インフルエンザ患者の解熱剤使用で注意すべきことは?
A: アセトアミノフェンを第一選択とし、アスピリンやアスピリン系薬剤は禁忌です。特に小児ではライ症候群(急性脳症と肝機能障害)のリスクがあるため、絶対に使用してはいけません。解熱剤の使用は38.5℃以上の発熱で、患者の苦痛が強い場合に限定します。過度な解熱は免疫機能を低下させる可能性があるため、完全に平熱まで下げる必要はありません。NSAIDs(イブプロフェン、ジクロフェナクなど)も脳症のリスクを高める可能性があるため、小児では避けるべきでしょう。
Q: インフルエンザ患者の隔離期間はどのように設定すべきですか?
A: 発症した日を0日として、発症後5日間かつ解熱後2日間(幼児では3日間)の隔離が基本です。ただし、症状の軽快傾向と解熱が条件となります。抗ウイルス薬を服用している場合でも同様の期間が必要で、薬剤投与により隔離期間が短縮されることはありません。免疫不全患者では排泄期間が延長する可能性があるため、個別に判断が必要です。学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」が出席停止期間と定められています。医療機関では症状消失まで飛沫予防策を継続するでしょう。
Q: インフルエンザの合併症で特に注意すべき症状は何ですか?
A: 肺炎の兆候として、持続する発熱、呼吸困難、胸痛、膿性痰の出現に注意します。インフルエンザ脳症では、意識障害、けいれん、異常行動(特に小児)が重要な症状です。心筋炎では胸痛、動悸、息切れ、不整脈が認められます。細菌の二次感染では、一旦解熱した後の再発熱、白血球数・CRPの上昇が特徴的です。高齢者では症状が典型的でない場合があり、食欲不振、活動性低下、軽度の意識レベル低下も重要な兆候となります。これらの症状が認められた場合は、迅速な医師への報告と適切な治療が必要でしょう。
まとめ
インフルエンザは高い感染力を持つ急性感染症であり、看護師には感染拡大防止と適切な症状管理の両方が求められます。特に医療機関では院内感染防止のため、標準予防策と飛沫予防策の徹底が極めて重要です。患者の症状緩和と同時に、他の患者や医療従事者への感染拡大を防ぐための対策を確実に実施することが看護師の重要な役割でしょう。
インフルエンザの症状は急激に発現し、特に高熱による脱水や全身倦怠感により患者のQOLが著しく低下します。個別性を重視した症状緩和により、患者の苦痛を最小限に抑え、早期回復を支援することが重要です。また、ハイリスク患者(高齢者、妊婦、基礎疾患患者、小児)では合併症のリスクが高いため、継続的な観察と早期発見・早期対応が患者の予後を左右します。
予防教育も看護師の重要な役割で、患者・家族に対する感染予防方法の指導、ワクチン接種の重要性の啓発、早期受診の必要性について継続的に教育することが求められます。実習では、感染症看護の基本的な技術と知識を身につけ、根拠に基づいた感染対策を実践してください。また、急性期の症状管理から回復期の生活指導まで、患者の状態に応じた段階的な看護の重要性も学んでいただければと思います。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
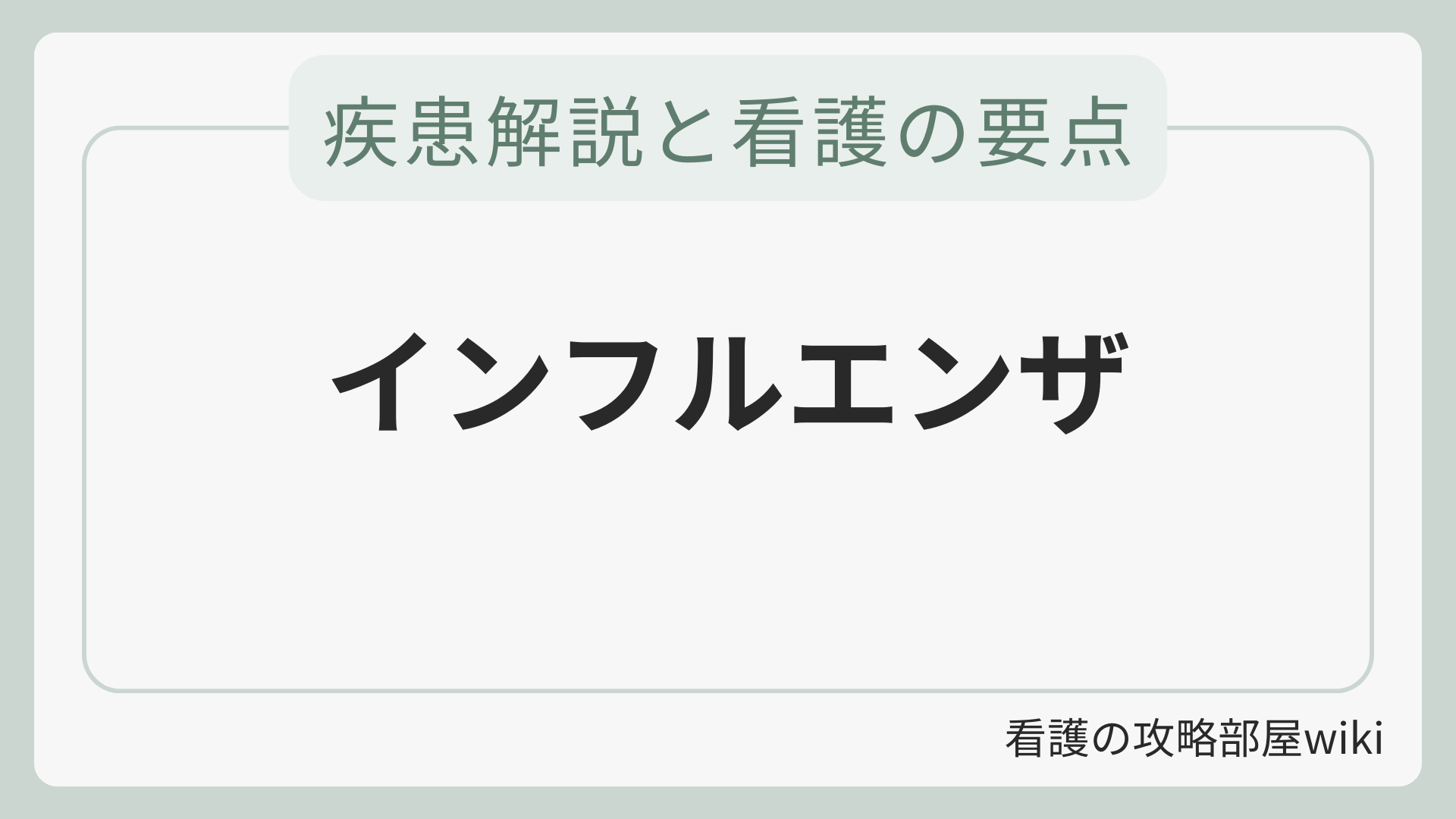
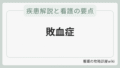
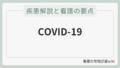
コメント