疾患概要
定義
カンジダ症は、カンジダ属真菌(主にCandida albicans)による感染症です。カンジダは健康な人の皮膚や口腔、消化管、腟などに常在する日和見感染菌であり、通常は無害ですが、免疫力の低下や常在菌叢のバランスが崩れたときに病原性を発揮します。感染部位により口腔カンジダ症、食道カンジダ症、皮膚カンジダ症、腟カンジダ症、カンジダ血症など様々な病型があります。
疫学
カンジダ症は世界中で見られる一般的な真菌感染症です。腟カンジダ症は成人女性の約75%が一生に一度は経験すると言われており、そのうち約半数が再発を経験します。口腔カンジダ症は新生児や高齢者、免疫不全患者に多く見られます。
近年、医療の高度化に伴い、長期入院患者や集中治療を受ける患者、広域抗菌薬使用患者、中心静脈カテーテル留置患者などで侵襲性カンジダ症(カンジダ血症)の発生が増加傾向にあります。特に免疫抑制状態の患者では重篤化しやすく、死亡率も高いため注意が必要です。
原因
カンジダ症の発症には、宿主側の要因と環境要因が関与します。
宿主側の主な危険因子として、免疫機能の低下(HIV感染症、糖尿病、悪性腫瘍、臓器移植後、ステロイド薬や免疫抑制薬の使用)、抗菌薬の長期使用による常在菌叢の乱れ、妊娠やホルモン療法によるホルモンバランスの変化、高齢や新生児期などが挙げられます。
環境要因としては、高温多湿の環境、不適切な衛生管理、密閉性の高い衣類の着用、中心静脈カテーテルや尿道カテーテルなどの医療デバイスの長期留置、経管栄養や高カロリー輸液などがあります。
特に医療現場では、複数の危険因子が重複することでカンジダ症のリスクが著しく高まることを理解しておく必要があります。
病態生理
通常、カンジダは皮膚や粘膜に少数存在していても、正常な免疫機能と常在菌叢のバランスにより増殖が抑制されています。しかし、このバランスが崩れると、カンジダが異常増殖して病原性を発揮します。
表在性カンジダ症では、皮膚や粘膜の局所でカンジダが増殖します。口腔カンジダ症では、口腔粘膜上皮にカンジダが侵入・増殖し、白苔(はくたい)と呼ばれる白色の偽膜を形成します。これは剥離可能ですが、剥がすと下に発赤やびらんが見られます。
腟カンジダ症では、腟内のpHバランスが崩れることで、通常は乳酸菌が優位な腟内環境でカンジダが増殖します。カンジダは腟粘膜に炎症を起こし、酒粕状・カッテージチーズ状の特徴的な帯下を生じます。
皮膚カンジダ症は、特に皮膚の湿潤部位(指間、乳房下、鼠径部、臀部など)で発生しやすく、皮膚のバリア機能が低下した部位でカンジダが角質層に侵入し、炎症と浸軟を引き起こします。
侵襲性カンジダ症は、カンジダが血流に侵入して全身に播種する重篤な病態です。中心静脈カテーテルなどの医療デバイスや消化管粘膜の損傷部位から血流に入ったカンジダは、全身の臓器(腎臓、肝臓、脾臓、肺、脳、眼など)に播種して深部臓器感染を起こします。カンジダ血症は敗血症を呈し、多臓器不全に至ることもある生命を脅かす病態です。
症状・診断・治療
症状
症状は感染部位によって大きく異なります。
口腔カンジダ症では、舌や口腔粘膜に白色の偽膜(白苔)が出現します。偽膜は容易に剥離でき、剥がすと下に発赤やびらんが見られます。患者は口腔内の違和感、味覚異常、灼熱感、嚥下時痛を訴えることがあります。新生児では哺乳困難を呈することもあります。
食道カンジダ症は、免疫不全患者に多く見られ、嚥下困難、嚥下時痛、胸骨後部痛が主な症状です。症状が強いと経口摂取が困難になり、体重減少につながります。
腟カンジダ症では、外陰部と腟の強い掻痒感が特徴的です。白色の酒粕状・カッテージチーズ様の帯下が増加し、外陰部の発赤、腫脹、灼熱感、性交時痛を伴います。掻痒感は非常に強く、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
皮膚カンジダ症は、皮膚の襞や湿潤部位に発赤、びらん、浸軟を生じます。病変の辺縁には小膿疱や小水疱が見られることがあります。指間のカンジダ症では、皮膚の浸軟と白色化が特徴的です。
カンジダ血症・侵襲性カンジダ症では、発熱、悪寒、頻脈、血圧低下などの敗血症症状を呈します。眼内炎を合併すると視力障害が生じ、心内膜炎では心雑音が聴取されることがあります。これらは生命予後に直結する重篤な病態です。
診断
診断は臨床症状と検査所見を総合して行います。
表在性カンジダ症の診断には、病変部の擦過物や分泌物の直接鏡検が有用です。KOH(水酸化カリウム)処理後に顕微鏡で観察すると、酵母型真菌と仮性菌糸が確認できます。培養検査も行われますが、カンジダは常在菌でもあるため、培養陽性だけでは感染症と診断できないこともあります。
口腔カンジダ症では、白苔の視診と擦過検査で診断します。食道カンジダ症の確定診断には内視鏡検査が必要で、食道粘膜に白色の偽膜や潰瘍が観察されます。
侵襲性カンジダ症の診断には、血液培養が重要ですが、感度が低く(約50%)、陰性でも侵襲性カンジダ症を除外できません。近年では、β-Dグルカンなどの真菌マーカーが補助診断に用いられます。画像検査で深部臓器の膿瘍形成を評価することもあります。
治療
治療は感染部位と重症度により異なります。
表在性カンジダ症では、局所抗真菌薬が第一選択です。口腔カンジダ症にはミコナゾールゲルやアムホテリシンBシロップなどの口腔用抗真菌薬を使用します。腟カンジダ症には抗真菌薬の腟錠やクリームを使用し、通常3〜6日間の治療で改善します。皮膚カンジダ症には抗真菌薬の外用剤(クリームや軟膏)を使用します。
中等症以上の表在性カンジダ症や侵襲性カンジダ症では、全身性抗真菌薬の投与が必要です。第一選択薬はアゾール系抗真菌薬(フルコナゾール、ボリコナゾールなど)やキャンディン系抗真菌薬(ミカファンギン、カスポファンギンなど)です。重症例や治療抵抗性の場合は、アムホテリシンBが使用されることもあります。
治療と並行して、原因となる危険因子の除去や改善が重要です。不要な抗菌薬の中止、糖尿病のコントロール改善、中心静脈カテーテルなどの医療デバイスの抜去または交換、免疫抑制薬の減量(可能であれば)などを検討します。
侵襲性カンジダ症では、早期診断と迅速な抗真菌薬投与が予後を左右するため、ハイリスク患者では予防的抗真菌薬投与が行われることもあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 感染:免疫機能低下または常在菌叢の乱れに関連したカンジダの異常増殖
- 皮膚統合性障害:カンジダ感染に関連した皮膚・粘膜の炎症とびらん
- 急性疼痛:粘膜の炎症に関連した掻痒感、灼熱感、疼痛
ゴードン機能的健康パターン
栄養-代謝パターン
口腔カンジダ症や食道カンジダ症がある場合、口腔内痛や嚥下時痛により経口摂取が困難になります。食事摂取量、体重変化、栄養状態(血清アルブミン値など)を継続的に評価します。特に免疫不全患者では、栄養状態が感染症の重症度や治癒に大きく影響するため、栄養サポートが重要です。糖尿病患者では、血糖コントロールがカンジダ症の発症や治療効果に直結するため、血糖値のモニタリングと管理が必須となります。
排泄パターン
腟カンジダ症では、帯下の性状(色、量、臭い、粘稠度)、外陰部の掻痒感や灼熱感の程度を観察します。尿道カテーテル留置患者では、カンジダ尿路感染症のリスクがあるため、尿の性状と検査データを確認します。侵襲性カンジダ症で腎臓に播種した場合は、尿量減少や腎機能障害を呈することがあるため、尿量と腎機能マーカーの観察が重要です。
活動-運動パターン
侵襲性カンジダ症では、発熱や全身倦怠感により活動耐性が著しく低下します。バイタルサインの変化(発熱、頻脈、血圧低下)を注意深く観察し、敗血症性ショックの早期発見に努めます。また、長期臥床による皮膚カンジダ症のリスクも高まるため、適切な体位変換と皮膚の乾燥保持が必要です。
認知-知覚パターン
カンジダ症による掻痒感や疼痛は、患者のQOLを著しく低下させます。特に腟カンジダ症の掻痒感は非常に強く、睡眠障害や日常生活への支障をきたすため、症状の程度を定期的に評価し、適切な症状緩和を図ります。侵襲性カンジダ症で脳や眼に播種した場合は、意識レベルの変化や視力障害が生じる可能性があるため、神経学的所見の観察も重要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常な呼吸(呼吸のニード)
侵襲性カンジダ症で肺に播種した場合、呼吸困難や低酸素血症を呈することがあります。呼吸状態(呼吸数、呼吸音、SpO2)を観察し、異常があれば速やかに医師に報告します。人工呼吸器管理中の患者は、口腔内や気管内のカンジダ増殖のリスクが高いため、適切な口腔ケアと気道管理が重要です。
清潔と身だしなみ(清潔のニード)
カンジダは湿潤環境を好むため、皮膚の清潔と乾燥保持が予防と治療の基本です。特に皮膚の襞(乳房下、鼠径部、指間など)は丁寧に洗浄し、よく乾燥させます。失禁がある患者では、速やかに清拭し、皮膚を乾燥させることでカンジダ症の予防につながります。口腔カンジダ症の予防には、食後の口腔ケアと義歯の清潔保持が重要です。腟カンジダ症では、外陰部の清潔保持と通気性の良い下着の使用を指導します。
正常な体温の保持(体温調節のニード)
侵襲性カンジダ症では発熱が主要な症状です。体温を定期的に測定し、発熱パターンを把握します。発熱時は適切なクーリングや解熱薬の使用を検討しますが、発熱自体が感染に対する生体反応でもあることを理解し、過度な解熱は避けます。また、発熱による発汗で皮膚が湿潤すると、表在性カンジダ症のリスクが高まるため、衣類や寝具の交換も重要です。
看護計画・介入の内容
- 感染徴候の観察:バイタルサイン測定(特に発熱、頻脈、血圧の変化)、病変部の観察(範囲、色調、分泌物の性状)、全身状態の評価(倦怠感、食欲不振の程度)、血液検査データの確認(白血球数、CRP、β-Dグルカンなど)、カンジダ血症のリスク評価(中心静脈カテーテル留置、広域抗菌薬使用、TPN施行など)
- 薬物療法の管理:抗真菌薬の確実な投与(投与時間、投与方法の遵守)、副作用の観察(肝機能障害、腎機能障害、アレルギー反応など)、局所抗真菌薬の適切な塗布方法の指導、口腔用抗真菌薬の使用方法の説明(食後に使用、長時間口腔内に留めるなど)、腟錠の挿入方法と使用期間の指導
- 皮膚・粘膜の管理:清潔保持と乾燥維持(入浴・清拭の実施、皮膚の襞の丁寧な乾燥)、湿潤環境の改善(通気性の良い衣類の選択、頻繁な体位変換)、皮膚の観察(発赤、びらん、浸軟の有無と範囲)、外用薬の適切な塗布、口腔ケアの実施(食後、就寝前の口腔清掃)、義歯の清潔管理
- 危険因子の除去・軽減:不要な抗菌薬の中止に関する医師との相談、血糖コントロールの確認と管理(糖尿病患者)、中心静脈カテーテルの適切な管理と不要なラインの抜去検討、尿道カテーテルの早期抜去の検討、免疫状態の評価と改善策の検討
- 症状緩和:掻痒感の軽減(冷罨法、抗ヒスタミン薬の投与)、疼痛管理(鎮痛薬の適切な使用)、口腔内痛のある患者への食事工夫(刺激の少ない軟らかい食事、適温の食事)、心理的サポート(特に腟カンジダ症患者へのプライバシー配慮と精神的支援)
- 患者・家族教育:カンジダ症の原因と予防方法の説明、清潔保持と乾燥維持の重要性の指導、抗真菌薬の使用方法と完治までの継続の必要性、再発予防の生活指導(通気性の良い衣類、適切な体重管理、糖尿病のコントロールなど)、症状悪化時の受診基準の説明、性感染症との違いの説明(腟カンジダ症の場合、性行為で感染するわけではないことを理解してもらう)
よくある疑問・Q&A
Q: カンジダ症は性感染症ですか?
A: 腟カンジダ症は性感染症ではありません。カンジダは元々体内に常在している真菌で、免疫力の低下や常在菌叢のバランスが崩れたときに発症します。性行為により発症するわけではなく、性交渉のない女性や子どもにも発症します。ただし、性行為によりパートナーに感染することはまれにあるため、症状がある間は性交渉を控えることが推奨されます。患者さんが「性感染症だから恥ずかしい」と誤解していることがあるため、正しい知識を伝えて不安を軽減することが大切です。
Q: 口腔カンジダ症の患者さんに口腔ケアをする際、白苔は取り除いた方がよいですか?
A: 白苔を無理に剥がすことは避けるべきです。白苔を強く擦って剥がすと、下の粘膜にびらんや出血を生じ、かえって痛みを増強させたり、二次感染のリスクを高めたりします。口腔ケアでは、柔らかいスポンジブラシや綿棒で優しく拭う程度にとどめましょう。抗真菌薬の治療が効果を発揮すれば、白苔は自然に減少していきます。口腔ケアの目的は、口腔内を清潔に保ち、新たなカンジダの増殖を防ぐことです。また、口腔用抗真菌薬は食後に使用し、使用後は一定時間飲食を控えてもらうことで、薬剤が口腔内に留まり効果を発揮します。
Q: 中心静脈カテーテルを留置している患者さんで、カンジダ血症を疑う場合、どのような観察が必要ですか?
A: カンジダ血症は初期症状が非特異的なため、ハイリスク患者では常に疑いを持つ姿勢が重要です。観察のポイントは、まず発熱(特に抗菌薬投与中にもかかわらず持続する発熱)、悪寒戦慄、頻脈、血圧低下などの全身性炎症反応症候群(SIRS)の徴候です。また、カテーテル刺入部の発赤、腫脹、膿性分泌物などの局所感染徴候も観察します。血液培養でカンジダが検出された場合、眼内炎の合併を評価するため、視力障害や眼痛の有無も確認します。カンジダ血症は死亡率が高い重篤な病態であり、早期発見・早期治療が予後を左右するため、少しでも異常を感じたら速やかに医師に報告することが重要です。
Q: 腟カンジダ症の患者さんから「市販薬で治療してもよいか」と聞かれました。どう答えればよいですか?
A: 初めて症状が出た場合や、症状が重い場合は医療機関の受診を勧めることが基本です。なぜなら、腟カンジダ症と似た症状を呈する他の疾患(細菌性腟症、トリコモナス腟炎、性感染症など)との鑑別が必要だからです。ただし、過去に医師の診断を受けてカンジダ症と確定しており、同じような症状が再発した場合は、市販の腟錠や外用薬を使用することも選択肢の一つです。しかし、市販薬を使用しても3〜4日で改善が見られない場合や症状が悪化する場合は、必ず医療機関を受診するよう説明します。また、妊娠中や糖尿病などの基礎疾患がある場合は、市販薬の使用前に医師に相談することが望ましいと伝えましょう。
Q: 広域抗菌薬を長期使用している患者さんで、カンジダ症を予防するためにできることはありますか?
A: 広域抗菌薬の使用は常在菌叢を乱し、カンジダ症の重要な危険因子です。予防策として、まず不要な抗菌薬は早期に中止するよう、医師と相談することが大切です。また、口腔ケアの徹底により口腔カンジダ症を予防できます。食後と就寝前の丁寧な口腔清掃、義歯使用者では義歯の清潔管理が重要です。皮膚カンジダ症の予防には、皮膚の清潔と乾燥維持が基本で、特に皮膚の襞や湿潤しやすい部位の丁寧なケアが必要です。失禁がある場合は速やかに清拭し、皮膚を乾燥させます。栄養状態と免疫状態の維持も重要なため、適切な栄養管理を行います。ハイリスク患者(免疫不全、長期ICU入室、広域抗菌薬長期使用など)では、予防的抗真菌薬投与が検討されることもあります。
Q: カンジダ症の患者さんのケアで、看護師自身が感染することはありますか?
A: カンジダは日和見感染菌であり、健康な医療従事者が通常のケアで感染することはほとんどありません。ただし、標準予防策の遵守は必須です。患者の体液や分泌物に触れる可能性がある場合は手袋を着用し、ケア後は石鹸と流水による手洗いを行います。特に皮膚カンジダ症や腟カンジダ症のケアでは、病変部に直接触れる可能性があるため、適切な個人防護具の使用が重要です。また、自分自身の健康管理も大切で、免疫力が低下している時期(過労、睡眠不足、ストレス過多など)は注意が必要です。カンジダ血症の患者のケアでは、血液や体液への曝露を避けるため、標準予防策を確実に実施しましょう。
まとめ
カンジダ症は、通常は無害な常在菌であるカンジダが、免疫力の低下や常在菌叢のバランスの乱れにより病原性を発揮する日和見感染症です。表在性カンジダ症から生命を脅かす侵襲性カンジダ症まで、幅広い病態を呈します。
病態の本質は、宿主の防御機能とカンジダの病原性とのバランスが崩れることにあります。そのため、治療は抗真菌薬の投与だけでなく、危険因子の除去や改善が極めて重要です。
看護の重要ポイントは、ハイリスク患者の早期発見と予防的ケア、そして皮膚・粘膜の清潔と乾燥維持です。特に口腔ケア、皮膚の襞のケア、不要な医療デバイスの早期抜去検討など、日常的な看護ケアがカンジダ症の予防に直結します。
患者教育では、カンジダ症が性感染症ではないこと、清潔と乾燥保持の重要性、抗真菌薬の完遂の必要性、再発予防のための生活習慣について、具体的に説明することが大切です。
実習では、免疫不全患者や長期入院患者などのハイリスク患者を担当する機会があるでしょう。日常的な観察とケアがカンジダ症の予防につながることを理解し、標準予防策を遵守しながら、患者個々のリスク因子を評価し、適切なケアを提供する力を養いましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
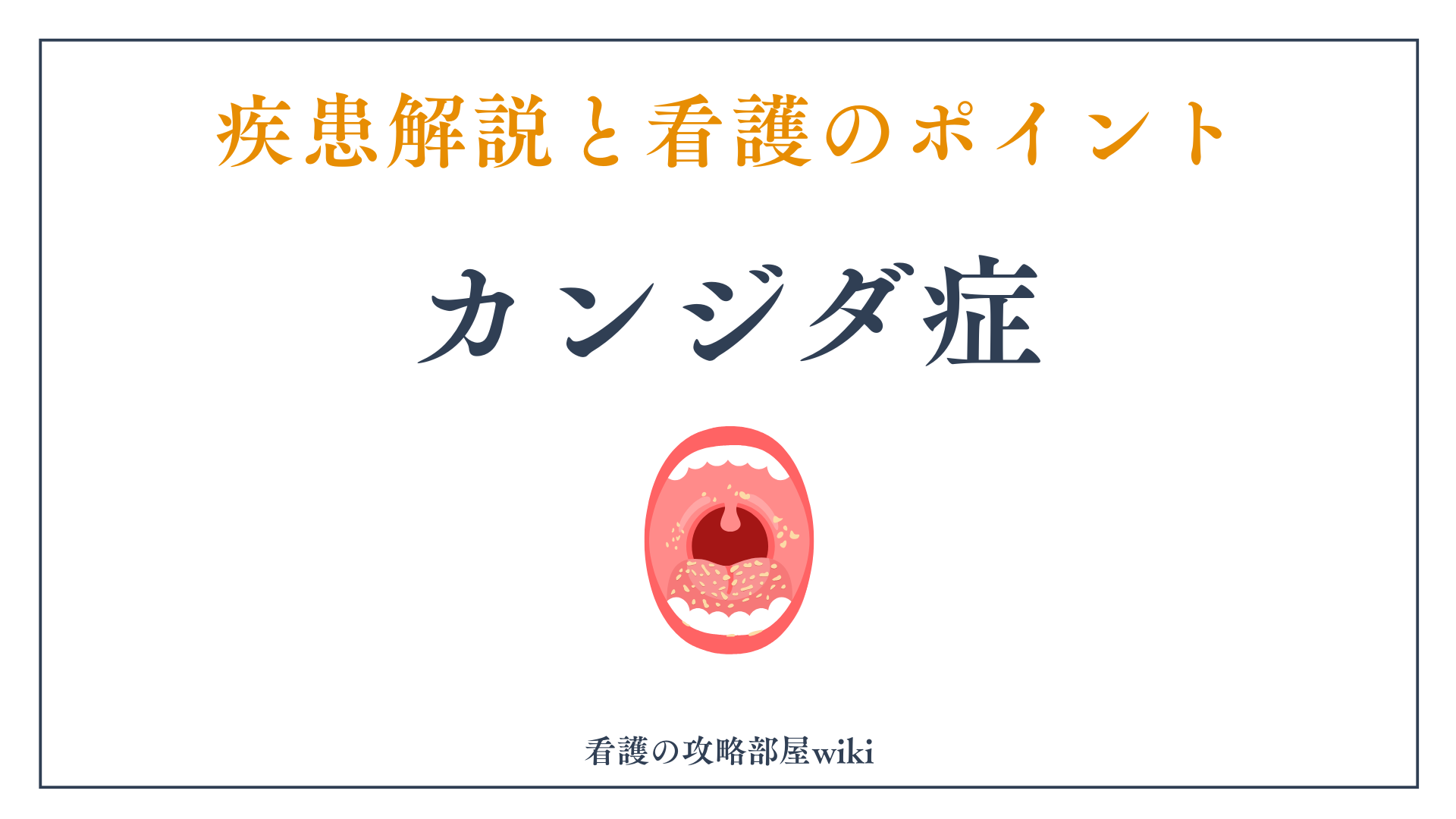
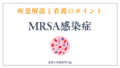
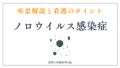
コメント