疾患概要
定義
蜂窩織炎(cellulitis)は、皮下組織を中心とした急性化膿性炎症で、境界不明瞭なびまん性の感染症です。皮膚の小さな外傷や既存の皮膚疾患から細菌が侵入し、皮下脂肪組織や筋膜に沿って急速に拡大します。発赤、腫脹、熱感、疼痛の4つの炎症徴候を呈し、重篤化すると壊死性筋膜炎や敗血症に進展する可能性があるため、早期診断・早期治療が重要な疾患です。
疫学
蜂窩織炎は年間約200万人が罹患する比較的頻度の高い皮膚軟部組織感染症です。あらゆる年齢に発症しますが、高齢者、糖尿病患者、免疫不全患者で重症化しやすい傾向があります。好発部位は下肢(特に下腿)で全体の約60%を占め、次いで上肢、顔面、体幹の順となります。男女差はありませんが、職業や生活環境により外傷を受けやすい人に多く見られます。近年、高齢化や糖尿病患者の増加に伴い患者数は増加傾向にあります。
原因
主要な原因菌はβ溶血性連鎖球菌(A群、B群、C群、G群)と黄色ブドウ球菌です。A群β溶血性連鎖球菌(化膿性連鎖球菌)は最も頻度が高く、急速な拡大と重篤化を特徴とします。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)による感染も増加しています。誘因として外傷(切り傷、虫刺され、注射針による刺創)、既存の皮膚疾患(湿疹、水虫、褥瘡)、免疫力低下(糖尿病、ステロイド使用、悪性腫瘍、高齢)、リンパ浮腫、静脈不全などが挙げられます。
病態生理
皮膚のバリア機能が破綻した部位から細菌が侵入し、皮下組織で急速に増殖します。細菌の産生する毒素や酵素(ヒアルロニダーゼ、ストレプトキナーゼなど)により組織結合が破壊され、感染が周囲に拡大します。炎症性メディエーターの放出により血管透過性が亢進し、発赤、腫脹、熱感、疼痛が生じます。重症例では全身性炎症反応症候群(SIRS)を呈し、敗血症性ショックに進展することがあります。A群溶血性連鎖球菌では壊死性筋膜炎への進展リスクが高く、劇症型溶血性連鎖球菌感染症では急激な多臓器不全により致命的となることがあります。
症状・診断・治療
症状
局所症状として発赤、腫脹、熱感、疼痛の4大徴候を認めます。発赤は境界不明瞭で周囲に拡大し、皮膚は光沢を帯びて緊張します。圧痛が強く、軽い接触でも疼痛を訴えます。進行すると水疱形成や皮膚壊死を生じることがあります。全身症状として発熱、悪寒戦慄、倦怠感、食欲不振を認め、重症例では意識障害、血圧低下などのショック症状が出現します。リンパ管炎を伴う場合は患部から中枢に向かう赤い線状の発赤(red streak)を認めます。所属リンパ節腫脹も特徴的な所見です。
診断
診断は臨床症状と理学所見により行われます。血液検査では白血球数増加、CRP上昇、赤沈亢進などの炎症反応を認めます。血液培養は菌血症の検出に重要で、重症例では必須です。膿瘍形成が疑われる場合は超音波検査やCT検査が有用です。細菌培養検査は排膿がある場合に実施しますが、蜂窩織炎では膿瘍形成が少ないため培養陽性率は低くなります。迅速診断キットによりA群溶血性連鎖球菌の検出が可能です。鑑別診断として深部静脈血栓症、丹毒、壊死性筋膜炎、痛風発作などがあります。
治療
治療は抗菌薬治療が基本で、重症度により経口または静注薬を選択します。軽症例ではペニシリン系(アモキシシリン/クラブラン酸)またはセフェム系抗菌薬の経口投与を行います。中等症以上では入院の上、ペニシリンG大量静注やセフォタキシムなどの静注薬を使用します。MRSA感染が疑われる場合はバンコマイシンやリネゾリドを使用します。支持療法として患肢挙上、安静、鎮痛薬投与を行います。切開排膿は膿瘍形成時に考慮され、壊死組織の除去(デブリドマン)が必要な場合もあります。治療期間は通常10-14日間です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:皮下組織の炎症に関連した患部の疼痛
- 皮膚統合性障害:細菌感染による皮膚・皮下組織の炎症と破壊
- 感染拡大リスク:細菌感染の進行による全身感染症の危険性
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは患者の感染に対する理解度と予防行動を評価します。糖尿病や免疫不全などの基礎疾患の管理状況、皮膚ケアの実践、外傷予防への意識を詳細に把握します。活動・運動パターンでは患部の疼痛や腫脹による活動制限の程度を評価し、患肢挙上や安静の必要性を判断します。認知・知覚パターンでは疼痛の程度と性質、鎮痛薬の効果を評価し、発熱による意識レベルの変化を観察します。
ヘンダーソン14基本的ニード
清潔で健康な皮膚を維持し、衣服で身体を守るでは感染部位の適切な処置方法と清潔保持、健側皮膚の感染予防について指導します。創部の観察方法、ドレッシング交換の手技、手指衛生の重要性を説明します。身体の位置を動かし、望ましい肢位を保持するでは患肢挙上による浮腫軽減と疼痛緩和、適切な体位保持について指導します。安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは感染拡散防止と再発予防のための環境整備について支援します。
看護計画・介入の内容
- 症状観察・重症化予防:発赤範囲のマーキングと経時的観察、疼痛・腫脹の程度評価、全身状態の継続的モニタリング(バイタルサイン、意識レベル、尿量)、重症化徴候の早期発見
- 感染管理・創部ケア:適切な創部処置とドレッシング管理、標準予防策の実施、手指衛生の徹底、患肢挙上による循環改善、抗菌薬の適切な投与管理
- 疼痛管理・ADL支援:鎮痛薬の適切な使用と効果判定、非薬物的疼痛緩和法(冷却、固定)、活動制限に応じたADL支援、段階的な活動拡大の支援
よくある疑問・Q&A
Q: 蜂窩織炎はうつりますか?家族への感染予防はどうすればよいですか?
A: 蜂窩織炎自体は直接的にはうつりませんが、原因菌(特に黄色ブドウ球菌)は接触により伝播する可能性があります。手指衛生の徹底が最も重要で、患部に触れた後は必ず石鹸と流水で手洗いするか、アルコール系手指消毒薬を使用してください。タオルや衣類の共用は避け、患部から出た浸出液で汚染された物品は適切に処理します。家族が皮膚に傷がある場合は特に注意が必要ですが、基本的な感染対策により十分予防可能です。
Q: どのくらいで治りますか?仕事復帰はいつからできますか?
A: 適切な抗菌薬治療により、通常2-3日で症状の改善が見られ、1-2週間で治癒します。ただし、糖尿病などの基礎疾患がある場合や重症例では治癒に時間がかかることがあります。仕事復帰は症状の程度と職種により異なりますが、発熱が解熱し、患部の疼痛が軽減すれば軽作業から段階的に復帰可能です。立ち仕事や重労働の場合は、腫脹が改善するまで休業が必要な場合もあります。医師と相談しながら復帰時期を決定してください。
Q: 糖尿病があると治りにくいのでしょうか?気をつけることはありますか?
A: 糖尿病があると血糖コントロール不良により感染が治りにくく、重症化しやすい傾向があります。高血糖は白血球機能を低下させ、創傷治癒を遅延させます。厳格な血糖管理(目標HbA1c 7.0%未満)が最も重要で、食事療法、薬物療法を継続してください。足の観察を毎日行い、小さな傷や水虫も早期に治療します。適切な靴の選択、足の清潔保持、保湿ケアにより皮膚トラブルを予防します。症状が軽微でも早期受診することで重症化を防げます。
Q: 再発を防ぐにはどうすればよいですか?
A: 再発予防には皮膚の外傷予防と基礎疾患の管理が重要です。皮膚の清潔保持と保湿ケアにより皮膚バリア機能を維持し、小さな傷も適切に処置してください。水虫や湿疹などの皮膚疾患は早期治療し、爪切りは深爪を避けて慎重に行います。下肢の循環改善のため適度な運動を行い、リンパ浮腫がある場合は圧迫療法を継続します。免疫力維持のため規則正しい生活、バランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけ、基礎疾患(糖尿病、腎疾患など)の適切な管理を継続してください。
まとめ
蜂窩織炎は皮下組織の急性化膿性炎症として、適切な治療により治癒が期待できる一方で、重篤化すると生命に関わる可能性がある疾患です。早期診断・早期治療により多くの症例で良好な予後が得られますが、基礎疾患を有する患者では重症化リスクが高いため、特に注意深い管理が必要となります。
看護の要点は症状の継続的観察と重症化の早期発見です。発赤範囲のマーキングによる感染拡大の評価、全身状態の変化の把握、疼痛の程度評価など、詳細で継続的なアセスメントが適切な治療介入につながります。
感染管理では標準予防策の徹底と適切な創部ケアにより、感染拡散防止と治癒促進を図ります。患肢挙上や安静保持などの支持療法も症状改善に重要な役割を果たします。
患者教育では疾患の理解促進と再発予防のための生活指導が重要です。特に糖尿病患者では血糖管理の重要性と皮膚ケアの方法について具体的に指導し、自己管理能力の向上を支援することが再発防止につながります。
心理的支援では、急激な症状の出現と疼痛による患者さんの不安に共感的に対応し、治療への協力と安心感の提供に努めることが大切です。
実習では患者さんの全身状態の変化に注意を払いながら、個別性のある看護計画を立案しましょう。基礎疾患の有無、年齢、職業、生活環境などを総合的に評価し、その人らしい生活の早期回復を支援することが重要です。また、予防教育を通じて再発防止に向けた具体的で実践可能な方法を提案し、患者さんのQOL向上に貢献していきましょう。蜂窩織炎は予防可能な疾患であり、適切な知識と行動により多くの症例で再発を防ぐことができることを忘れずに、希望を持った看護を提供することが大切です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
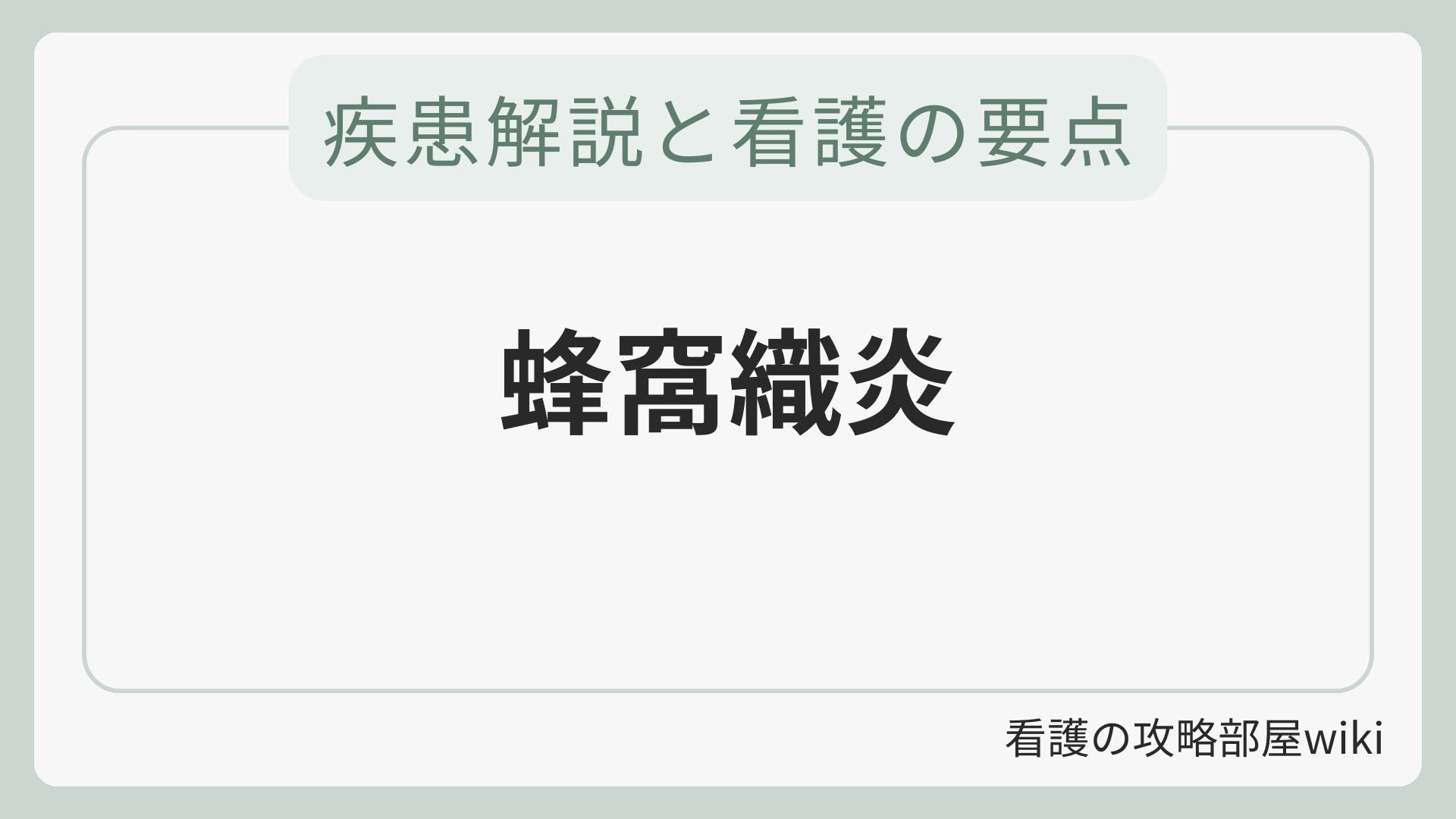
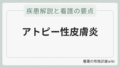
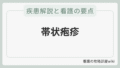
コメント