疾患概要
定義
気管支喘息(以下、喘息)とは、気道に慢性的な炎症が起こり、発作性に気道が狭窄(狭くなる)する疾患です。気道の炎症により気道粘膜が腫れ、粘液分泌が増加し、気道平滑筋が収縮することで、空気の通り道が狭くなります。
喘息の重要な特徴は:
- 可逆性の気流制限:気道狭窄は自然にまたは治療により改善します(COPDは不可逆性)
- 気道過敏性の亢進:わずかな刺激(冷気、運動、煙など)で気道が過剰に反応して狭窄します
- 慢性気道炎症:症状がない時も気道に炎症が持続しています
喘息発作時には、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、呼吸困難、咳、胸苦しさが出現します。発作は夜間から早朝に起こりやすく、季節の変わり目や感冒時に悪化しやすい特徴があります。
喘息は年齢により特徴が異なります:
- 小児喘息:多くはアレルギー性で、成長とともに寛解することがあります
- 成人喘息:成人発症の喘息は非アレルギー性が多く、治りにくい傾向があります
重症の喘息発作は生命に関わることがあり、喘息死(年間約1,500人)を防ぐため、適切な管理が重要です。
疫学
日本における喘息患者数は約800万人(人口の約6〜7%)と推定されています。小児では約5〜10%、成人では約3〜5%に喘息が見られます。
年齢では、小児期と成人期に二峰性の発症ピークがあります。小児喘息の約70〜80%は3歳までに発症し、思春期までに約50〜70%が寛解します。成人喘息は40歳以降に発症することが多く、小児期の再発例と成人発症例があります。
性別では、小児期は男児に多く(男女比2:1)、成人期では女性にやや多い傾向があります。
喘息死は、年間約1,500人で、1990年代(年間約6,000人)と比べて大幅に減少しています。これは、吸入ステロイド薬の普及や喘息管理の向上によるものです。ただし、高齢者の喘息死は依然として多く、約90%が65歳以上です。
社会的影響も大きく、喘息発作による救急受診、入院、学校・仕事の欠席など、QOL(生活の質)と生産性に影響を及ぼします。適切な管理により、ほとんどの患者は正常な生活を送ることができます。
近年の傾向:都市化、大気汚染、住環境の変化(気密性の高い住宅でのダニ・カビの増加)、食生活の欧米化などにより、喘息患者は増加傾向にあります。
原因
喘息の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的素因と環境因子の相互作用により発症すると考えられています。
遺伝的素因
喘息には家族集積性があり、両親が喘息の場合、子どもが喘息になる確率は約50〜70%、片親の場合は約20〜30%です。アトピー素因(アレルギーを起こしやすい体質)を持つ人に多く見られます。
環境因子
アレルゲン(抗原) 喘息発作の誘因となる主なアレルゲン:
- ダニ(ハウスダスト):最も重要なアレルゲン。布団、カーペット、ぬいぐるみなどに生息
- 花粉:スギ、ヒノキ、ブタクサ、イネ科など
- 動物のフケや毛:イヌ、ネコ、ハムスターなど
- カビ:アルテルナリア、アスペルギルスなど。湿気の多い場所に発生
- ゴキブリ:糞や死骸がアレルゲンとなる
- 食物:卵、牛乳、小麦、そば、ピーナッツなど(主に小児)
非アレルギー性誘因
- 感染症:ウイルス感染(風邪、インフルエンザ)が喘息悪化の最多原因
- 運動:運動誘発喘息(特に寒冷・乾燥した環境下での運動)
- 気象変化:気温・気圧の変動、季節の変わり目
- 冷気:冷たい空気の吸入
- 大気汚染:PM2.5、排気ガス、タバコ煙
- 刺激性物質:香水、化粧品、洗剤、殺虫剤、ペンキなどの強い臭い
- ストレス・心理的要因:強い感情(笑い、泣き)、不安、緊張
- 薬剤:
- アスピリンや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):アスピリン喘息
- β遮断薬:気管支を収縮させる
- 月経:女性では月経周期に伴い悪化することがある
- 胃食道逆流症(GERD):胃酸の逆流が気道を刺激
危険因子
- アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎の合併
- 受動喫煙(特に小児)
- 肥満:成人喘息のリスク因子
- 低出生体重
- 早産
病態生理
喘息の病態を理解することは、症状や治療の根拠を理解する上で重要です。
正常な気道と喘息の気道
正常な気道では、気管支の内腔が広く、空気がスムーズに出入りします。気管支壁は、粘膜、粘膜下組織、平滑筋、軟骨から構成されています。
喘息の気道では、以下の3つの変化が起こり、気道が狭くなります:
- 気道粘膜の浮腫(腫れ):炎症により粘膜が腫れます
- 気道平滑筋の収縮:気管支を取り囲む平滑筋が収縮し、気道が締め付けられます
- 粘液分泌の増加:粘液が過剰に分泌され、気道内腔を塞ぎます
慢性気道炎症
喘息の本態は慢性気道炎症です。症状がない時も気道に炎症が持続しており、これが気道過敏性を引き起こします。
炎症には、好酸球、肥満細胞、T細胞(Th2細胞)などの炎症細胞が関与します。これらの細胞から、炎症性メディエーター(ヒスタミン、ロイコトリエン、サイトカインなど)が放出され、気道に以下の変化をもたらします:
- 血管透過性亢進→浮腫
- 気管支平滑筋収縮
- 粘液分泌亢進
- 気道上皮の損傷
気道過敏性の亢進
慢性炎症により、気道がわずかな刺激に対しても過剰に反応するようになります。これを気道過敏性の亢進と呼びます。健常者では問題ない程度の刺激(冷気、運動、笑い、煙など)で、喘息患者では気管支が収縮し、発作が誘発されます。
喘息発作のメカニズム
アレルゲンや刺激物質が気道に入ると:
- 肥満細胞が活性化され、ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質を放出(即時相反応:数分以内)
- これにより気道平滑筋が収縮し、粘液分泌が増加
- 数時間後、好酸球などの炎症細胞が気道に集まり、炎症が増強(遅発相反応:4〜12時間後)
- 炎症が持続し、気道過敏性がさらに亢進
気流制限
気道が狭窄すると、気流制限が生じます。特に呼気(息を吐く)時に気道が虚脱しやすく、空気を吐き出しにくくなります。その結果:
- 呼気延長:息を吐くのに時間がかかります
- 喘鳴:狭くなった気道を空気が通る際にゼーゼー、ヒューヒューという音がします
- 過膨張:空気が肺に残り、肺が膨らんだ状態になります
ガス交換障害
気道狭窄により、換気血流比不均等が生じ、ガス交換が障害されます。その結果:
- 低酸素血症(PaO2低下):軽症〜中等症発作で見られます
- 高二酸化炭素血症(PaCO2上昇):重症〜最重症発作で見られます。これは呼吸不全の徴候で、非常に危険です
気道リモデリング
喘息が長期間コントロールされないと、気道に不可逆的な構造変化(リモデリング)が起こります:
- 気道壁の肥厚
- 平滑筋の増生
- 粘膜下の線維化
これにより、気道狭窄が固定化し、治療への反応性が低下します。したがって、早期から適切な治療を行い、炎症をコントロールすることが重要です。
喘息発作の重症度
喘息発作は重症度により分類されます:
- 小発作:動作で少し苦しい、SpO2 96%以上
- 中発作:動作でかなり苦しい、会話で途切れる、SpO2 91〜95%
- 大発作:安静時も苦しい、会話困難、SpO2 90%以下
- 最重症発作(呼吸不全):チアノーゼ、意識障害、呼吸音減弱(silent chest)、PaCO2上昇
最重症発作は生命に関わるため、緊急入院と集中治療が必要です。
症状・診断・治療
症状
喘息の症状は、発作性かつ可逆性であることが特徴です。
典型的な症状
- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー):最も特徴的な症状で、狭くなった気道を空気が通る際に聞こえる音です。患者自身も聞こえますし、周囲の人にも聞こえることがあります
- 呼吸困難(息苦しさ):空気が出入りしにくくなり、「息が吸えない」「胸が締め付けられる」と訴えます。特に呼気(息を吐く)が困難です
- 咳:乾性咳嗽(痰を伴わない)が多いですが、発作が進行すると粘稠な痰を伴うことがあります。夜間から早朝の咳が特徴的で、これを咳喘息と呼ぶこともあります
- 胸苦しさ、胸の圧迫感:胸が重い、締め付けられる感じを訴えます
症状の特徴
- 発作性:症状は急に出現し、数分から数時間(時に数日)続いた後、治まります
- 時間的変動:夜間から早朝(午前2〜4時)に悪化しやすい
- 季節性:季節の変わり目、特定の季節(花粉の時期など)に悪化
- 可逆性:気管支拡張薬により速やかに改善します
身体所見
- 頻呼吸:呼吸数が増加します
- 呼吸補助筋の使用:首や肩の筋肉を使って呼吸します
- 起坐呼吸:座位や前傾姿勢を好みます
- 呼気延長:息を吐くのに時間がかかります
- 聴診で喘鳴:両側の肺野に喘鳴が聴かれます
- 胸郭の過膨張:空気が肺に残るため、胸が膨らんだ状態になります
- チアノーゼ:重症発作では口唇や爪床が紫色になります
- 頻脈:心拍数が増加します
- 発汗:冷や汗をかくことがあります
重症発作の徴候(危険サイン)
以下の徴候があれば、直ちに救急受診が必要です:
- 会話ができない(単語しか話せない)
- 歩けない、起き上がれない
- SpO2 90%以下
- チアノーゼ
- 意識障害、混迷
- Silent chest(呼吸音が聞こえない):空気の移動がほとんどなく、極めて危険
- 努力呼吸の減弱(疲労困憊)
咳喘息
喘鳴や呼吸困難がなく、慢性的な咳のみが症状として現れる喘息の一型です。夜間から早朝の咳、会話や運動後の咳が特徴で、気管支拡張薬が有効です。放置すると典型的な喘息に移行することがあります。
診断
喘息の診断は、臨床症状、身体所見、呼吸機能検査、アレルギー検査を総合して行われます。
病歴聴取
- 喘鳴、呼吸困難、咳、胸苦しさの有無
- 症状の発作性、時間的変動(夜間〜早朝)
- 誘因(アレルゲン、運動、感冒、天候など)
- アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎の既往
- 家族歴(喘息、アレルギー疾患)
- 喫煙歴、受動喫煙
呼吸機能検査(スパイロメトリー)
喘息診断の中心的検査です。
- 閉塞性換気障害:1秒率(FEV1/FVC)<70%
- 可逆性の確認:気管支拡張薬吸入後、FEV1が12%以上かつ200mL以上改善すれば、可逆性ありと判定され、喘息を強く疑います
発作がない時(寛解期)は正常なこともあり、その場合は気道過敏性試験を行います。
気道過敏性試験
メサコリンやヒスタミンを吸入させ、FEV1が20%低下する濃度を測定します。喘息患者では低濃度で気道が収縮し、気道過敏性の亢進が確認されます。
呼気NO(一酸化窒素)測定
気道の好酸球性炎症を反映します。喘息では呼気NO濃度が上昇します(≧22ppb)。非侵襲的で簡便な検査です。
血液検査
- 好酸球数:アレルギー性炎症で増加
- IgE:総IgEが上昇(アトピー型喘息)
- 特異的IgE:アレルゲン特異的IgE抗体を測定し、原因アレルゲンを同定
アレルギー検査
- 皮膚プリックテスト:アレルゲンを皮膚に刺入し、反応を確認
- 特異的IgE抗体検査(RAST):血液検査で複数のアレルゲンに対する抗体を測定
胸部X線検査
喘息自体の診断よりも、他疾患の除外や合併症(気胸、肺炎など)の確認に有用です。発作時は過膨張が見られることがあります。
鑑別診断
- COPD:不可逆性の気流制限、喫煙歴、中高年発症
- 心不全:起坐呼吸、下腿浮腫、心拡大
- 肺塞栓症:突然の呼吸困難、胸痛、リスク因子
- 過換気症候群:不安、四肢のしびれ、テタニー
- 声帯機能不全:吸気時の喘鳴
治療
喘息治療の目標は、症状のコントロール、正常な日常生活の維持、発作の予防、呼吸機能の正常化、喘息死の回避です。
喘息治療の基本
- 慢性炎症の抑制(長期管理薬による)
- 発作時の速やかな対処(発作治療薬による)
- 誘因・増悪因子の除去(環境整備、アレルゲン回避)
- 患者教育(自己管理能力の向上)
長期管理薬(コントローラー)
症状がない時も毎日使用し、気道炎症を抑制します。
吸入ステロイド薬(ICS)(最も重要)
- 喘息治療の第一選択薬で、中心的役割を果たします
- 気道の炎症を直接抑制し、発作を予防します
- フルチカゾン、ブデソニド、ベクロメタゾンなど
- 副作用:嗄声(声のかすれ)、口腔カンジダ症(吸入後のうがいで予防)
- 全身性の副作用は少ないですが、高用量長期使用では骨密度低下に注意
長時間作用性β2刺激薬(LABA)
- 気管支を拡張し、12〜24時間効果が持続
- ICSと併用(ICS/LABA配合剤)することで相乗効果
- サルメテロール、ホルモテロール、インダカテロールなど
- 単独使用は禁忌(喘息死のリスク増加)
ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)
- 炎症性メディエーターであるロイコトリエンの作用を阻害
- 経口薬で使いやすい
- モンテルカスト、プランルカストなど
- 運動誘発喘息やアスピリン喘息に有効
テオフィリン徐放製剤
- 気管支拡張作用と軽度の抗炎症作用
- 血中濃度モニタリングが必要(中毒に注意)
生物学的製剤(重症喘息に使用)
- 抗IgE抗体(オマリズマブ):アレルギー性喘息
- 抗IL-5抗体(メポリズマブ):好酸球性喘息
- 抗IL-4/13受容体抗体(デュピルマブ):好酸球性喘息、アトピー型喘息
- 注射薬で高額ですが、重症喘息に劇的な効果
発作治療薬(リリーバー)
発作時に速やかに気管支を拡張します。
短時間作用性β2刺激薬(SABA)
- サルブタモール(サルタノール、ベネトリンなど)
- 吸入後数分で効果が現れ、4〜6時間持続
- 発作時の第一選択薬
- 使用頻度が増えたら(週3回以上)、コントロール不良のサイン
全身ステロイド薬
- 中等症以上の発作では経口または静注ステロイド
- プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン
- 速やかに炎症を抑制
喘息発作の治療
小発作〜中発作
- SABA吸入を20分ごとに3回まで繰り返す
- 改善しなければ受診
大発作
- 救急受診または救急車を呼ぶ
- 酸素投与
- SABA頻回吸入(ネブライザー)
- 全身ステロイド投与(経口または静注)
- 改善なければアミノフィリン点滴
最重症発作(呼吸不全)
- ICU入室
- 酸素投与、必要に応じて人工呼吸管理
- 大量ステロイド静注
- アミノフィリン持続点滴
- 硫酸マグネシウム点滴
環境整備とアレルゲン回避
- ダニ対策:寝具のこまめな洗濯、防ダニカバー、掃除機がけ
- カビ対策:換気、除湿
- ペット:飼育を避ける、または寝室に入れない
- 禁煙:本人の禁煙と受動喫煙の回避
- 室内環境:カーペット、ぬいぐるみを減らす
患者教育
- 喘息の病態理解
- 正しい吸入手技の習得
- ピークフローモニタリング
- 喘息日記の記録
- 喘息アクションプランの作成:発作時の対処法を個別に作成
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 非効果的呼吸パターン:気道狭窄による呼吸困難
- ガス交換障害:気流制限による低酸素血症
- 不安・恐怖:発作時の窒息感と死への恐怖
- 非効果的自己健康管理:疾患理解不足、吸入手技の習得不足
- 活動耐性低下:呼吸困難による日常生活制限
- 睡眠パターン混乱:夜間発作による睡眠障害
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
喘息患者の多くは、「喘息は治らない」という認識を持ち、長期的な疾患管理の必要性を理解していないことがあります。特に症状が軽快すると、自己判断で薬を中止してしまう患者がいます。
慢性炎症の持続と長期管理薬(特にICS)の継続の重要性を理解してもらうことが重要です。症状がなくても気道に炎症が残っており、治療継続が必要であることを説明します。
吸入薬の正しい使用方法を習得することも重要です。吸入手技が不適切だと薬剤が気道に届かず、効果が得られません。実際に吸入してもらい、手技を確認し、必要に応じて修正します。
アレルゲンや誘因の認識と回避も重要です。患者自身が何が発作を誘発するかを把握し、可能な限り避けるよう指導します。
栄養-代謝パターン
発作時は呼吸困難により食事摂取が困難になります。また、全身ステロイド使用時は食欲亢進や高血糖に注意が必要です。
肥満は成人喘息のリスク因子であり、また喘息コントロールを悪化させます。適正体重の維持を支援します。
活動-運動パターン
運動誘発喘息により、運動を避けるようになることがあります。しかし、適度な運動は喘息患者にも推奨されます。運動前のβ2刺激薬吸入、ウォームアップにより、運動誘発喘息を予防できることを説明します。
発作時は活動を制限し、安静を保ちます。呼吸困難が強い時は、座位または前傾姿勢が楽なことが多いです。
呼吸状態の継続的モニタリングが重要です。呼吸数、SpO2、呼吸パターン、呼吸困難の程度、喘鳴の有無を観察します。重症発作の徴候(会話困難、SpO2<90%、意識障害、silent chest)に注意します。
睡眠-休息パターン
夜間から早朝の発作により、睡眠が著しく障害されます。夜間の咳や喘鳴で何度も覚醒し、不眠が続くと、日中の倦怠感、集中力低下、QOL低下につながります。
夜間症状の頻度は喘息コントロールの重要な指標です。週1回以上の夜間症状があれば、コントロール不良と判定され、治療のステップアップが必要です。
就寝前の長期管理薬の確実な使用、寝室の環境整備(ダニ対策、適温・適湿)、就寝前のカフェイン摂取を避けるなどの指導を行います。
コーピング-ストレス耐性パターン
喘息発作は、患者に強い不安と恐怖を引き起こします。「息ができない」という窒息感は、死への恐怖を伴います。発作の予測不可能性も不安を増大させます。
発作時の不安は、さらに発作を悪化させる悪循環を生みます。不安により過換気となり、気道狭窄が増悪します。
患者の不安を傾聴し、「そばにいます」「大丈夫です」と声をかけ、安心感を与えます。落ち着いてゆっくり呼吸するよう促します。
ストレスが喘息悪化の誘因となることがあります。ストレス管理、リラクゼーション法(腹式呼吸、瞑想など)の指導も有効です。
役割-関係パターン
小児喘息では、学校での体育の制限、修学旅行への参加困難、友人との遊びの制限などにより、社会的孤立を感じることがあります。過度な制限は避け、可能な限り正常な活動を促します。
成人喘息では、職場での理解不足、発作による欠勤、職業選択の制限などが問題となることがあります。
家族の理解と協力も重要です。特に小児では、親が疾患を理解し、適切な管理を行うことが不可欠です。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 正常な呼吸
喘息患者にとって最も重要なニードです。気道狭窄により呼吸が著しく障害されます。
発作時の呼吸状態の観察:呼吸数、SpO2、呼吸パターン、呼吸困難の程度、喘鳴の有無を頻回に観察します。重症発作の徴候(会話困難、SpO2<90%、チアノーゼ、意識障害、silent chest)に注意し、異常があれば直ちに医師に報告します。
呼吸困難の緩和:
- 体位管理:座位または前傾姿勢(オーバーテーブルに枕を置いてもたれる)により、呼吸補助筋を使いやすくします
- 落ち着きを保つ:穏やかに声をかけ、「ゆっくり呼吸してください」「大丈夫ですよ」と安心させます。不安が発作を悪化させるため、患者を落ち着かせることが重要です
- 気管支拡張薬の投与:SABA吸入により速やかに気管支を拡張します。ネブライザーまたは定量噴霧式吸入器(MDI)を使用します
- 酸素療法:低酸素血症がある場合、酸素投与を行い、SpO2を90%以上に維持します
- 環境調整:室温、湿度を適切に保ちます。加湿により気道を湿潤させ、痰の喀出を促進します
薬物療法の管理:
- 発作治療薬(SABA)を指示通りに投与します
- 中等症以上の発作では、全身ステロイドを経口または静注で投与します
- 重症発作では、アミノフィリン点滴、硫酸マグネシウム点滴なども使用されます
2. 適切な飲食
発作時は呼吸困難により食事摂取が困難です。軽快後は通常の食事を摂取できますが、食物アレルギーがある場合は原因食物を除去します。
水分摂取は重要で、脱水を予防し、痰の喀出を促進します。
3. 排泄
特に問題ないことが多いですが、全身ステロイド使用時は高血糖により多尿になることがあります。
6. 衣類の着脱
発作時は努力呼吸により発汗することがあります。寝衣が湿った場合は交換し、快適さを保ちます。
8. 身体を清潔に保つ
発作時は呼吸困難により入浴が困難です。症状が軽快してから入浴を促します。
9. 危険の回避
- 重症発作の早期発見:SpO2低下、会話困難、チアノーゼ、意識障害、silent chestなどの徴候に注意し、直ちに医師に報告します
- 薬剤の副作用モニタリング:全身ステロイドの副作用(高血糖、消化性潰瘍、易感染性、精神症状)、β2刺激薬の副作用(振戦、動悸、低カリウム血症)に注意します
- アレルゲン・誘因の回避:病室にアレルゲン(花、ぬいぐるみなど)を持ち込まないよう家族に説明します
- 感染予防:感冒が喘息悪化の最多原因です。手洗い、マスク着用、人混みを避けるなどの感染予防策を指導します
14. 学習
喘息の自己管理には、患者教育が不可欠です。
疾患の理解:喘息は慢性気道炎症であり、症状がなくても炎症が持続していることを説明します。長期管理薬の継続の重要性を理解してもらいます。
吸入手技の指導:吸入薬の正しい使用方法を実演し、患者に実際に吸入してもらい、手技を確認します。定量噴霧式吸入器(MDI)、ドライパウダー吸入器(DPI)、ソフトミスト吸入器(SMI)など、デバイスにより手技が異なります。吸入後のうがいを忘れずに行うよう指導します。
ピークフローモニタリング:ピークフローメーター(息を吐く速さを測定する器具)の使用方法を指導します。毎朝・毎晩測定し、記録することで、喘息のコントロール状態を把握できます。ピークフロー値が普段の80%未満に低下したら、発作の前兆と考え、対処します。
喘息日記の記録:症状、ピークフロー値、使用した薬剤を毎日記録します。これにより、コントロール状態や誘因を把握できます。
喘息アクションプランの作成:医師と相談し、発作時の対処法を個別に作成します。「ゾーン」により対応を決めます:
- 緑ゾーン(良好):通常の長期管理薬を継続
- 黄ゾーン(注意):症状悪化やピークフロー低下時、SABA使用や長期管理薬増量
- 赤ゾーン(危険):重症発作時、救急受診
アレルゲン・誘因の回避:環境整備(ダニ対策、カビ対策)、禁煙、感染予防、運動前のβ2刺激薬吸入などを指導します。
緊急時の対応:重症発作の徴候(会話困難、SpO2低下、チアノーゼ、意識障害)があれば、直ちに救急受診または救急車を呼ぶよう指導します。
看護計画・介入の内容
- 呼吸状態の継続的モニタリング:発作時は、呼吸数、SpO2、呼吸パターン、呼吸困難の程度、喘鳴の有無を15〜30分ごとに観察します。重症発作の徴候(会話困難、SpO2<90%、チアノーゼ、意識障害、silent chest)に注意し、異常があれば直ちに医師に報告します
- 発作時の速やかな対処:SABA吸入を速やかに実施します。効果を観察し、改善が不十分であれば再吸入(20分ごとに最大3回)または医師に報告します。中等症以上では全身ステロイドを投与します
- 体位管理と環境調整:座位または前傾姿勢により呼吸を楽にします。室温・湿度を適切に保ち、加湿により気道を湿潤させます。患者が落ち着ける環境を整えます
- 心理的支援:発作時の不安と恐怖を理解し、穏やかに声をかけ、「そばにいます」「大丈夫です」と安心感を与えます。落ち着いてゆっくり呼吸するよう促します。不安が発作を悪化させることを理解し、患者を落ち着かせることに努めます
- 酸素療法の管理:低酸素血症がある場合、酸素投与を行い、SpO2を継続的にモニタリングし、90%以上を目標にします
- 薬物療法の管理:気管支拡張薬、ステロイド薬を指示通りに投与します。薬剤の効果と副作用を観察します。β2刺激薬の副作用(振戦、動悸、低カリウム血症)、全身ステロイドの副作用(高血糖、消化性潰瘍、易感染性)に注意します
- 吸入手技の指導と確認:患者に実際に吸入してもらい、手技が正しいか確認します。不適切な場合は修正し、繰り返し練習します。吸入後のうがいを忘れずに行うよう指導します
- ピークフローモニタリングの指導:ピークフローメーターの使用方法を指導し、毎日測定して記録するよう促します。ピークフロー値の変化により、コントロール状態を把握できることを説明します
- 喘息日記の記録支援:症状、ピークフロー値、使用した薬剤を毎日記録するよう促します。記録により、誘因やコントロール状態を把握できることを説明します
- 喘息アクションプランの作成支援:医師と相談し、発作時の対処法を個別に作成します。ゾーン別の対応(緑・黄・赤)を明確にし、緊急時の連絡先を記載します
- アレルゲン・誘因回避の指導:環境整備(ダニ対策、カビ対策、ペット対策)、禁煙、感染予防(手洗い、マスク、ワクチン接種)、運動前のβ2刺激薬吸入などを具体的に指導します
- 家族への教育と支援:特に小児喘息では、家族が疾患を理解し、適切な管理を行うことが不可欠です。吸入補助、環境整備、発作時の対応などを指導します。家族の不安も傾聴し、サポートします
- 服薬アドヒアランスの向上:長期管理薬の継続の重要性を繰り返し説明します。症状がなくても気道炎症が持続しており、治療継続が必要であることを理解してもらいます。服薬状況を確認し、中断している場合は理由を聞き、解決策を一緒に考えます
- 退院指導:長期管理薬の継続、吸入手技、ピークフローモニタリング、喘息日記の記録、アレルゲン回避、発作時の対応、緊急受診の目安、定期受診の重要性を説明します。喘息アクションプランを渡し、説明します
よくある疑問・Q&A
Q: 喘息は完治しますか?
A: 喘息は慢性疾患であり、多くの場合完治は困難です。ただし、適切な治療により、ほとんどの患者は症状を良好にコントロールし、正常な生活を送ることができます。
小児喘息の約50〜70%は思春期までに寛解します。これを「治った」と表現することもありますが、成人期に再発することもあります。
成人発症の喘息は治りにくく、長期的な管理が必要です。しかし、「治らない」からといって悲観する必要はなく、適切な治療で「コントロールされた状態」を維持できます。
Q: 吸入ステロイドは危険ではないですか?副作用が心配です。
A: 吸入ステロイド(ICS)は喘息治療の最も重要な薬剤であり、適切に使用すれば安全性が高い薬です。全身性の副作用はほとんどありません。
ICSは気道に直接作用し、全身への吸収は少量です。そのため、経口ステロイドで懸念される全身性副作用(骨粗鬆症、糖尿病、感染症、ムーンフェイスなど)はほとんど起こりません。
主な副作用は局所的なもの:
- 嗄声(声のかすれ):吸入後のうがいで予防できます
- 口腔カンジダ症:吸入後のうがい、スペーサーの使用で予防できます
ICSを使用しないと、気道炎症が持続し、発作を繰り返し、気道リモデリング(不可逆的な気道の変化)が進行します。その結果、治療への反応性が低下し、より多くの薬剤が必要になります。
ICSは「副作用を恐れて使わない」のではなく、「副作用を予防しながら適切に使う」ことが重要です。
Q: 症状がないので薬をやめてもいいですか?
A: いいえ、症状がなくても長期管理薬(特にICS)は継続してください。
喘息の本態は慢性気道炎症です。症状がない時も、気道には炎症が残っており、気道過敏性が亢進しています。この状態で治療を中断すると、再び発作が起こりやすくなります。
実際、「症状が良くなったから」と自己判断で薬を中止し、数週間〜数ヶ月後に発作を起こして救急受診する患者が多くいます。
薬の減量や中止は、医師と相談の上、慎重に行います。通常、良好なコントロールが3〜6ヶ月以上続いた場合に、段階的に減量を検討します。
Q: 発作治療薬(SABA)をよく使うようになったのですが、大丈夫ですか?
A: SABA(サルブタモールなど)の使用頻度が増えたら、喘息コントロールが悪化しているサインです。速やかに医師に相談してください。
SABAは発作時に速やかに気管支を拡張し、症状を緩和しますが、気道炎症を抑制する作用はありません。SABAばかり使って長期管理薬(ICS)を使用しないと、気道炎症が持療し、発作を繰り返すという悪循環に陥ります。
また、SABAの過度な使用(週3回以上、特に毎日)は、喘息死のリスクを高めることが知られています。
SABAの使用頻度が増えたら、長期管理薬のステップアップが必要です。医師に相談し、治療を見直してもらいましょう。
Q: 運動すると発作が起こるので、運動を避けた方がいいですか?
A: いいえ、適切な対策をすれば、運動は可能です。むしろ、適度な運動は喘息患者にも推奨されます。
運動誘発喘息を予防する方法:
- 運動前のβ2刺激薬吸入(15〜30分前)
- ウォームアップ:いきなり激しい運動をせず、徐々に強度を上げます
- 環境選択:寒冷・乾燥した環境を避け、温暖・湿潤な環境で運動します
- 口呼吸を避ける:鼻呼吸により、吸気を温め湿らせます
また、喘息のコントロールが良好であれば、運動誘発喘息は起こりにくくなります。長期管理薬を適切に使用し、コントロールを維持することが重要です。
多くの喘息患者がスポーツで活躍しています。適切な管理により、運動制限のない生活が可能です。
Q: 喘息の患者さんが発作を起こしたらどうすればいいですか?
A: まず呼吸状態を評価し、発作の重症度を判断します。
軽症〜中等症発作:
- 患者を落ち着かせ、座位または前傾姿勢にします
- SABAを吸入させます(定量噴霧式吸入器またはネブライザー)
- 効果を観察し、20分後に再評価します
- 改善が不十分であれば、20分ごとに最大3回まで吸入を繰り返します
- それでも改善しなければ医師に報告します
重症発作(会話困難、SpO2<90%、チアノーゼ、意識障害):
- 直ちに医師に報告し、指示を仰ぎます
- 酸素投与を開始します
- 座位または前傾姿勢にします
- 全身ステロイドの投与準備をします
- バイタルサイン、SpO2を頻回に測定します
最重症発作(silent chest、意識障害、呼吸音減弱):
- 緊急事態です。直ちに医師を呼び、救急カートを準備します
- 酸素投与、ルート確保
- ICU入室の準備
発作時は、患者の不安が発作を悪化させるため、穏やかに声をかけ、「大丈夫です」「そばにいます」と安心感を与えることも重要です。
まとめ
気管支喘息は、気道の慢性炎症により、発作性に気道が狭窄する疾患です。日本には約800万人の喘息患者がおり、小児から高齢者まで幅広い年齢層に見られます。
病態の本質は、慢性気道炎症→気道過敏性亢進→可逆性の気流制限です。症状がない時も気道に炎症が持続しており、わずかな刺激で発作が誘発されます。一度破壊された肺胞は元に戻らないCOPDと異なり、喘息の気道狭窄は可逆性であることが特徴です。
症状は、喘鳴、呼吸困難、咳、胸苦しさが発作性に出現します。夜間から早朝に悪化しやすく、季節の変わり目や感冒時に増悪します。診断は臨床症状とスパイロメトリーで気流制限の可逆性を確認することが重要です。
治療の中心は吸入ステロイド薬(ICS)による慢性炎症の抑制です。症状がなくても毎日使用し、気道炎症をコントロールします。発作時は短時間作用性β2刺激薬(SABA)で速やかに気管支を拡張します。環境整備と患者教育も治療の重要な柱です。
看護の要点は、発作時の迅速な対処、呼吸状態のモニタリング、心理的支援、吸入手技の指導、自己管理能力の向上です。発作時は呼吸状態を頻回に観察し、重症発作の徴候を早期に発見します。患者の不安を受け止め、落ち着きを保つよう支援します。
喘息は慢性疾患ですが、適切な治療により、ほとんどの患者は症状を良好にコントロールし、正常な生活を送ることができます。患者教育により自己管理能力を高め、発作予防と早期対処ができるよう支援することが重要です。
実習では、発作時の迅速な対応と、患者の不安への共感的な関わりが求められます。喘息は生命に関わる疾患であり、重症発作の徴候を見逃さないよう、注意深い観察を心がけましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
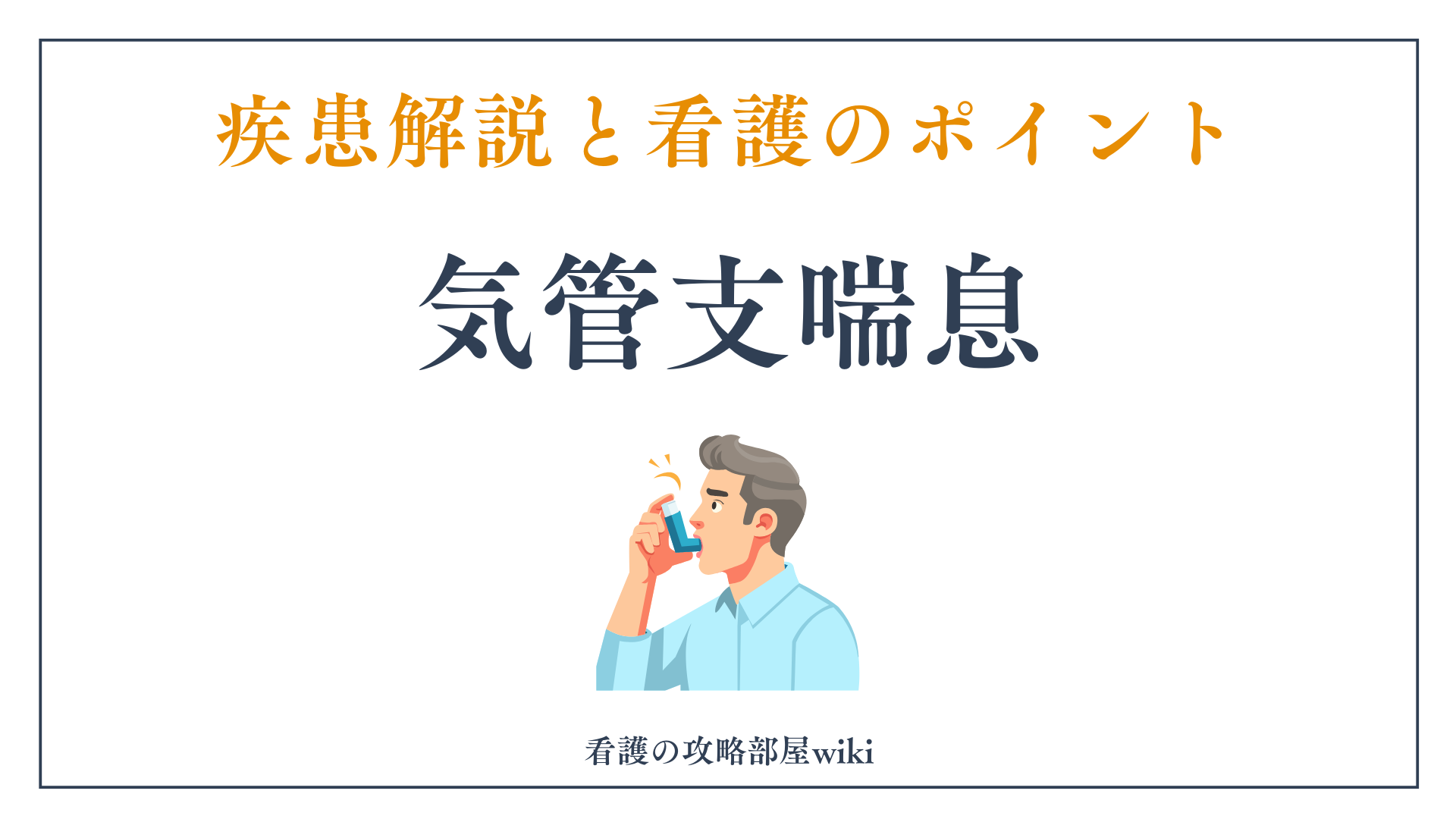
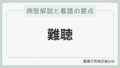
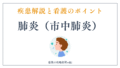
コメント