疾患概要
定義
肺炎とは、細菌、ウイルス、真菌などの病原微生物が肺に感染し、肺胞や間質に炎症が起こる疾患です。肺胞内に炎症性滲出液や膿が貯留することで、ガス交換が障害され、呼吸困難や低酸素血症が生じます。
肺炎は発症場所により以下のように分類されます:
市中肺炎(CAP: Community-Acquired Pneumonia) 病院外(日常生活の場)で発症する肺炎です。健康な人や基礎疾患のある人が、外来受診前または入院後48時間以内に発症したものを指します。本記事では、この市中肺炎を中心に解説します。
院内肺炎(HAP: Hospital-Acquired Pneumonia) 入院後48時間以降に発症する肺炎で、院内の耐性菌による感染が問題となります。
医療・介護関連肺炎(NHCAP: Nursing and Healthcare-Associated Pneumonia) 介護施設入所者、通院で透析や化学療法を受けている患者など、医療や介護に接する機会が多い高齢者・免疫不全者に発症する肺炎です。誤嚥性肺炎が多く含まれます。
市中肺炎は、肺炎球菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマ、クラミジア、レジオネラ、ウイルス(インフルエンザウイルス、RSウイルス、SARS-CoV-2など)などが主な原因菌です。
重症度により治療方針が異なるため、診断時にA-DROP(エードロップ)スコアなどの重症度分類を用いて評価します。
疫学
肺炎は日本における死亡原因の第5位(2022年)を占め、年間約7万5千人が死亡しています。高齢化に伴い、肺炎による死亡者数は増加傾向にあり、特に高齢者では死亡原因の上位を占めます。
年齢では、乳幼児と高齢者に多く発症します。特に65歳以上の高齢者では、免疫力の低下、基礎疾患の合併、誤嚥のリスク増加により、肺炎の発症率と死亡率が著しく上昇します。
季節性では、冬季にインフルエンザウイルスや肺炎球菌による肺炎が増加します。インフルエンザ流行後に細菌性肺炎(特に肺炎球菌、黄色ブドウ球菌)を合併することが多く、これを二次性細菌性肺炎と呼びます。
原因菌では、市中肺炎の約30〜40%が肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)によるもので最多です。次いで、インフルエンザ菌、マイコプラズマ、クラミジア、レジオネラ、ウイルスなどが続きます。ただし、約30〜40%は原因菌が特定できません。
予後は、若年健常者では良好ですが、高齢者や基礎疾患を持つ患者では重症化しやすく、死亡率が高まります。重症肺炎の死亡率は約20〜30%に達します。
COVID-19の影響:2020年以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による肺炎が重要な問題となっています。COVID-19肺炎は、重症化すると急性呼吸窮迫症候群(ARDS)に至ることがあります。
原因
市中肺炎の原因は、病原微生物の感染です。
主な原因菌
肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)(約30〜40%)
- 市中肺炎の最多原因菌
- 健常者の鼻咽頭に常在していることが多い
- 急性発症し、発熱、膿性痰、胸痛が特徴的
- 高齢者、脾摘後、慢性肺疾患、糖尿病、アルコール依存症などでリスクが高い
- ワクチン(肺炎球菌ワクチン)による予防が可能
インフルエンザ菌(Haemophilus influenzae)(約10%)
- 特に慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に多い
- 喫煙者でリスクが高い
マイコプラズマ(Mycoplasma pneumoniae)(約5〜10%)
- 若年者(小児〜青年)に多い
- 頑固な乾性咳嗽が特徴で、「歩く肺炎(walking pneumonia)」とも呼ばれる
- 家族内や学校、職場などで集団発生することがある
- 症状は比較的軽いことが多いが、遷延することもある
クラミジア(Chlamydophila pneumoniae)(約3〜5%)
- 若年者から高齢者まで幅広い年齢層に発症
- 発熱、咳、頭痛が主症状
レジオネラ(Legionella pneumophila)(約1〜3%)
- 冷却塔、循環式浴槽、温泉などの水系から感染
- 高熱、意識障害、下痢、低ナトリウム血症が特徴
- 重症化しやすく、死亡率が高い
ウイルス
- インフルエンザウイルス:冬季に流行し、ウイルス性肺炎または二次性細菌性肺炎を起こす
- RSウイルス:乳幼児や高齢者に多い
- SARS-CoV-2(新型コロナウイルス):COVID-19肺炎
- その他:アデノウイルス、パラインフルエンザウイルスなど
その他の原因菌
- 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus):インフルエンザ後の二次感染で重要
- クレブシエラ(Klebsiella pneumoniae):アルコール依存症、糖尿病患者に多い
- 嫌気性菌:誤嚥性肺炎の原因
リスク因子
- 高齢(65歳以上)
- 喫煙
- 基礎疾患:COPD、糖尿病、心不全、腎不全、肝硬変、悪性腫瘍
- 免疫抑制状態:ステロイド使用、化学療法、HIV感染、脾摘後
- 誤嚥のリスク:嚥下障害、脳血管障害、認知症、意識障害
- インフルエンザ罹患
- アルコール依存症
- 栄養不良
病態生理
肺炎の病態は、病原体の侵入→肺胞の炎症→ガス交換障害という過程をたどります。
正常な防御機構
健康な肺には、病原体の侵入を防ぐさまざまな防御機構があります:
- 上気道での濾過:鼻毛や粘液により大きな粒子を捕捉
- 咳反射:気道に異物が入ると咳で排出
- 粘液-線毛クリアランス:気道粘膜の線毛運動により、粘液とともに病原体を排出
- 肺胞マクロファージ:肺胞に到達した病原体を貪食
- 免疫グロブリン:IgA、IgGなどの抗体による防御
これらの防御機構が破綻すると、病原体が肺胞に到達し、感染が成立します。
感染の成立
病原体が肺胞に到達すると、肺胞マクロファージが活性化され、炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-1、IL-8など)を放出します。これにより、好中球などの炎症細胞が肺胞に集まり、炎症反応が起こります。
肺胞の変化(病理学的過程)
肺炎球菌性肺炎の典型的な経過:
- 充血期(1〜2日):肺胞壁の毛細血管が拡張し、充血します
- 赤色肝変期(2〜4日):肺胞内に赤血球、好中球、フィブリンが貯留し、肺が肝臓のように赤く硬くなります
- 灰色肝変期(4〜8日):赤血球が減少し、白血球が増加して、肺が灰色になります
- 融解期(8日以降):炎症が治まり、マクロファージが滲出物を貪食・除去し、正常に戻ります
ガス交換障害
肺胞内に炎症性滲出液や膿が貯留すると、肺胞が空気ではなく液体で満たされ、肺の実質化(consolidation)が起こります。その結果:
- 換気障害:肺胞に空気が入らなくなります
- 拡散障害:肺胞壁が厚くなり、ガス交換が障害されます
- 換気血流比不均等:換気のない肺胞にも血流があるため、シャント(無効な血流)が生じます
これにより、低酸素血症(PaO2低下)が生じます。
全身への影響
肺炎では、炎症性サイトカインが全身に放出され、全身性炎症反応症候群(SIRS: Systemic Inflammatory Response Syndrome)を引き起こすことがあります。重症化すると:
- 敗血症:血液中に細菌が侵入し、全身に播種
- 敗血症性ショック:血圧低下、臓器灌流不全
- 急性呼吸窮迫症候群(ARDS):肺の広範な炎症により、重度の呼吸不全
- 多臓器不全:腎不全、肝不全、DICなど
原因菌による病態の違い
- 肺炎球菌:急性発症、大葉性肺炎(肺葉全体が実質化)、胸膜炎を伴うことが多い
- マイコプラズマ、クラミジア:間質性肺炎のパターン、比較的軽症
- レジオネラ:肺外症状(消化器症状、意識障害)を伴いやすい、重症化しやすい
- ウイルス:両側性の間質性肺炎、びまん性肺胞障害(DAD)
高齢者の肺炎の特徴
高齢者では:
- 症状が非典型的(発熱がない、咳が少ない)
- 誤嚥性肺炎が多い
- 基礎疾患の悪化を伴いやすい
- 脱水、電解質異常を起こしやすい
- 重症化しやすく、死亡率が高い
症状・診断・治療
症状
肺炎の典型的な症状は、呼吸器症状と全身症状に分けられます。
呼吸器症状
- 咳:最も多い症状です。初期は乾性咳嗽(痰を伴わない)ですが、進行すると湿性咳嗽(痰を伴う)になります
- 痰:黄色〜緑色の膿性痰が特徴的です。肺炎球菌では錆色の痰が見られることがあります
- 呼吸困難:肺胞の実質化により換気が障害され、息切れが生じます
- 胸痛:胸膜に炎症が及ぶと、深呼吸や咳で増悪する鋭い胸痛(胸膜痛)が出現します
- 喘鳴:気道に炎症が及ぶと、ゼーゼーという呼吸音が聞かれることがあります
全身症状
- 発熱:高熱(38℃以上)が急激に出現することが多いです。ただし、高齢者では発熱がないこともあります
- 悪寒・戦慄:高熱に伴い、ガタガタと震える悪寒が見られます
- 全身倦怠感:強い疲労感、だるさを訴えます
- 頭痛:発熱に伴う頭痛が見られます
- 食欲不振
- 筋肉痛、関節痛:全身性の痛みを訴えることがあります
身体所見
- 頻呼吸:呼吸数が増加(20回/分以上)します
- 頻脈:心拍数が増加(100回/分以上)します
- 打診で濁音:肺の実質化により、打診で濁い音が聴かれます
- 聴診で水泡音(crackles):肺胞内の滲出液により、パチパチという音が聴かれます
- 気管支呼吸音:実質化した肺では、通常肺野では聴かれない気管支呼吸音が聴取されます
- チアノーゼ:低酸素血症が進行すると、口唇や爪床が紫色になります
原因菌による特徴的症状
- 肺炎球菌:急性発症、高熱、膿性痰、胸痛(胸膜炎)
- マイコプラズマ:頑固な乾性咳嗽、比較的軽症、若年者に多い
- レジオネラ:高熱、意識障害、下痢、低ナトリウム血症、重症化しやすい
- インフルエンザ:インフルエンザ症状(高熱、関節痛、筋肉痛)後の肺炎
高齢者の非典型的症状
高齢者では典型的な症状が乏しく、以下のような非特異的症状で発見されることがあります:
- 発熱がない、または微熱のみ
- 咳が少ない
- 食欲不振、活気がない
- 意識レベルの低下、せん妄
- 転倒
- 基礎疾患の悪化(心不全、糖尿病のコントロール悪化など)
診断
肺炎の診断は、臨床症状、身体所見、画像検査、血液検査、微生物検査を総合して行われます。
胸部X線検査(最も重要)
肺炎の診断に必須の検査です。肺野の浸潤影(白く写る)が確認されれば、肺炎と診断されます。
浸潤影のパターン:
- 大葉性肺炎:肺葉全体が均一に白く写ります(肺炎球菌に多い)
- 気管支肺炎:気管支周囲に散在性の浸潤影が見られます
- 間質性肺炎:肺の間質にすりガラス影や網状影が見られます(マイコプラズマ、ウイルスに多い)
胸部CT検査
胸部X線で診断が不明確な場合や、合併症(膿胸、肺膿瘍)の評価に有用です。COVID-19肺炎では、特徴的なすりガラス影がCTで確認されます。
血液検査
- 白血球数:細菌性肺炎では増加(>10,000/μL)、ウイルス性では正常〜減少
- CRP(C反応性タンパク):炎症マーカーで上昇します
- プロカルシトニン:細菌感染で上昇し、ウイルス感染では上昇しません。細菌性とウイルス性の鑑別に有用
- 血液ガス分析:低酸素血症(PaO2低下)の程度を評価
微生物検査
原因菌の同定と適切な抗菌薬選択のために重要です。
- 喀痰グラム染色・培養:原因菌を同定します。ただし、適切な喀痰(唾液ではなく気道からの痰)を採取する必要があります
- 血液培養:重症例では血液中に細菌が侵入していることがあり、血液培養で検出されます
- 尿中抗原検査:肺炎球菌、レジオネラの抗原を尿中から検出します。迅速診断が可能です
- 迅速抗原検査・PCR検査:インフルエンザ、COVID-19、マイコプラズマなどの診断
重症度評価(A-DROPスコア)
日本呼吸器学会が推奨する市中肺炎の重症度分類です。以下の5項目を評価します:
- A(Age):男性70歳以上、女性75歳以上
- D(Dehydration):BUN 21mg/dL以上または脱水あり
- R(Respiration):SpO2 90%以下(PaO2 60 Torr以下)
- O(Orientation):意識障害あり
- P(Pressure):血圧(収縮期血圧)90mmHg以下
- 0項目:軽症(外来治療)
- 1〜2項目:中等症(外来または入院)
- 3項目:重症(入院治療)
- 4〜5項目:超重症(ICU入室考慮)
この評価により、外来治療か入院治療かを判断します。
治療
肺炎の治療は、抗菌薬療法が中心です。重症度、年齢、基礎疾患、原因菌に応じて抗菌薬を選択します。
抗菌薬療法
原因菌が判明するまでは、経験的治療(empiric therapy)として、市中肺炎で頻度の高い原因菌をカバーする抗菌薬を選択します。
外来治療(軽症〜中等症)
- ペニシリン系:アモキシシリン
- マクロライド系:アジスロマイシン、クラリスロマイシン(マイコプラズマ、クラミジアもカバー)
- レスピラトリーキノロン:レボフロキサシン、モキシフロキサシン(高齢者、基礎疾患がある場合)
入院治療(中等症〜重症)
- セフェム系+マクロライド系:セフトリアキソン+アジスロマイシン
- レスピラトリーキノロン:レボフロキサシン
- 重症例:カルバペネム系、抗MRSA薬の追加も検討
治療期間は通常5〜7日間ですが、重症例や合併症がある場合は延長します。
ウイルス性肺炎の治療
- インフルエンザ:オセルタミビル(タミフル)、ザナミビル(リレンザ)などの抗インフルエンザ薬
- COVID-19:レムデシビル、デキサメタゾン、抗体カクテル療法など(ガイドラインに従う)
支持療法
- 酸素療法:低酸素血症(SpO2<90%)がある場合、酸素投与を行います
- 輸液:脱水の補正、栄養補給
- 解熱鎮痛薬:アセトアミノフェン、NSAIDsにより発熱と痛みを緩和
- 去痰薬:痰の喀出を促進
- 栄養管理:十分なカロリーとタンパク質の摂取
重症肺炎の治療
- 人工呼吸管理:呼吸不全が進行した場合、非侵襲的陽圧換気(NPPV)または気管挿管による人工呼吸管理
- 昇圧薬:敗血症性ショックでは、ノルアドレナリンなどの昇圧薬を使用
- ICU管理:集中治療室での全身管理
予防
- 肺炎球菌ワクチン:65歳以上、基礎疾患のある人に推奨。PPSV23(23価多糖体ワクチン)とPCV13(13価結合型ワクチン)の2種類があります
- インフルエンザワクチン:毎年の接種により、インフルエンザおよび二次性細菌性肺炎を予防
- COVID-19ワクチン:重症化予防に有効
- 禁煙:喫煙は肺炎のリスクを高めます
- 口腔ケア:誤嚥性肺炎の予防に有効
- 手洗い、マスク着用:感染予防の基本
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- ガス交換障害:肺胞の実質化による換気障害と低酸素血症
- 非効果的気道浄化:喀痰増加と咳嗽反射の低下
- 体温調節障害:発熱による体温上昇
- 活動耐性低下:呼吸困難と全身衰弱による日常生活動作の制限
- 体液量不足:発熱、発汗、食事摂取不良による脱水
- 不安:急性発症と呼吸困難による不安
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
肺炎は急性発症することが多く、患者は突然の高熱と呼吸困難に驚き、不安を抱きます。特に若年健常者では、「なぜ自分が肺炎になったのか」という疑問を持つことがあります。
高齢者では、症状が非典型的で、本人も家族も肺炎と気づかずに受診が遅れることがあります。意識レベルの低下や食欲不振のみで発見されることもあります。
基礎疾患(COPD、糖尿病、心不全など)がある場合、肺炎により基礎疾患が悪化するリスクがあります。患者の既往歴、服薬状況、アレルギー歴を確認します。
喫煙歴のある患者には、禁煙の重要性を説明します。喫煙は肺炎のリスクを高め、治癒を遅らせます。
栄養-代謝パターン
発熱、食欲不振、呼吸困難により、食事摂取が困難になります。発熱により代謝が亢進し、エネルギー消費が増加します。また、発汗や不感蒸泄により水分喪失が増加し、脱水のリスクが高まります。
体重、体温、血圧、尿量、血清アルブミン値、電解質を評価し、脱水や栄養不良の有無を確認します。口渇、皮膚ツルゴールの低下、尿量減少、BUN上昇などが脱水の徴候です。
水分・電解質バランスを維持するため、十分な水分摂取(経口または輸液)を促します。食事は、高カロリー・高タンパクで消化の良いものを少量頻回で提供します。
発熱により食欲が低下している場合、解熱後に食欲が戻ることを説明し、無理に食べさせず、患者のペースに合わせます。
活動-運動パターン
呼吸困難、発熱、全身倦怠感により、活動耐性が著しく低下します。ベッド上安静が必要な場合もあります。
呼吸状態の継続的モニタリングが最重要です。呼吸数、SpO2、呼吸パターン、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を頻回に観察します。呼吸音を聴診し、水泡音の有無や範囲を確認します。
呼吸数が増加(頻呼吸>24回/分)、SpO2が低下(<90%)、呼吸困難の増悪、チアノーゼの出現などがあれば、直ちに医師に報告します。
活動と休息のバランスを保ちます。急性期は安静が必要ですが、過度の臥床は廃用症候群や肺炎の悪化(無気肺、分泌物の貯留)を招きます。症状が改善してきたら、段階的に活動を促します。
睡眠-休息パターン
発熱、咳、呼吸困難により、睡眠が著しく障害されます。夜間の咳で何度も覚醒し、不眠が続くと、体力回復が遅れます。
睡眠環境を整え、静かで落ち着いた環境を提供します。体位の工夫(半座位)、鎮咳薬や解熱薬の適切な使用により、睡眠を確保します。
コーピング-ストレス耐性パターン
急性発症の肺炎は、患者に強い不安を引き起こします。「息ができない」という恐怖、高熱による苦痛、入院による生活の中断など、さまざまなストレスに直面します。
患者の不安を傾聴し、病状の説明や治療の見通しを伝えることで、不安を軽減します。家族との面会や連絡を促し、精神的サポートを提供します。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 正常な呼吸
肺炎患者にとって最も重要なニードです。肺胞の実質化により換気が障害されているため、呼吸困難が主症状となります。
呼吸状態の観察:呼吸数、SpO2、呼吸パターン、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を頻回に観察します。呼吸音を聴診し、水泡音(crackles)の有無や範囲を確認します。
呼吸困難の緩和:
- 体位管理:半座位または座位により、横隔膜を下げ、肺の拡張を促進します
- 酸素療法:低酸素血症がある場合、適切な酸素流量を設定し、SpO2を90%以上に維持します
- 深呼吸・咳嗽指導:深呼吸により肺を拡張し、無気肺を予防します。咳により痰を喀出させます
- 加湿:加湿器やネブライザーにより気道を湿潤させ、痰の喀出を促進します
- 薬物療法:気管支拡張薬、去痰薬を適切に使用します
喀痰管理:痰の量、色、粘稠度を観察します。膿性痰(黄色、緑色)は細菌感染を示唆します。痰の喀出が困難な場合、体位ドレナージ、スクイージング(胸部を軽く叩く)、吸引により喀出を促します。
2. 適切な飲食
発熱により水分喪失が増加し、脱水のリスクが高まります。十分な水分摂取(1日1500〜2000mL以上)を促します。経口摂取が困難な場合は、輸液により水分・電解質を補給します。
食事は、高カロリー・高タンパクで消化の良いものを提供します。食欲不振がある場合は、少量頻回食とし、患者の嗜好を考慮します。発熱時は冷たいものが好まれることもあります。
3. 排泄
十分な尿量(1日1000mL以上)があるか確認します。尿量減少は脱水の徴候です。発熱により発汗が増加するため、こまめに寝衣やシーツを交換し、清潔と快適さを保ちます。
6. 衣類の着脱
発熱、発汗により、頻繁な寝衣交換が必要です。吸湿性の良い寝衣を選び、発汗後は速やかに交換します。発汗後は冷えないよう注意し、清拭や更衣を行います。
8. 身体を清潔に保つ
発熱により発汗が多いため、毎日の清拭や可能であればシャワー浴により清潔を保ちます。口腔内も乾燥しやすいため、口腔ケアを定期的に実施します。特に高齢者では、口腔内の細菌が誤嚥により肺炎を悪化させるリスクがあるため、口腔ケアは重要です。
9. 危険の回避
- 感染拡大防止:飛沫感染予防のため、患者にマスク着用を促します。医療従事者は標準予防策を実施します
- 転倒予防:発熱、低酸素血症、全身衰弱により転倒リスクが高まります。ベッド周囲を整え、ナースコールを手の届く位置に配置します
- 薬剤の副作用モニタリング:抗菌薬の副作用(アレルギー、下痢、肝障害、腎障害)に注意します。発疹、呼吸困難、ショックなどのアレルギー症状が出現した場合は、直ちに医師に報告します
- 合併症の早期発見:胸膜炎、膿胸、肺膿瘍、敗血症などの合併症に注意します。胸痛の増悪、発熱の持続、意識レベルの低下などがあれば報告します
体温管理:発熱により体温が上昇します。体温を定期的に測定し、高熱(38.5℃以上)がある場合は、解熱薬(アセトアミノフェン)を使用します。クーリング(氷嚢を頸部、腋窩、鼠径部に当てる)も有効ですが、過度のクーリングは悪寒を引き起こすため注意します。
14. 学習
疾患の病態、治療、予防について、患者の理解度に応じて説明します。
服薬指導:抗菌薬は指示通りに最後まで服用することが重要です。症状が改善しても自己判断で中止すると、再発や耐性菌出現のリスクがあることを説明します。
退院後の生活指導:
- 十分な休息と栄養摂取
- 禁煙(喫煙者の場合)
- 水分摂取
- 咳エチケット(マスク着用、手洗い)
- ワクチン接種(肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン)の推奨
- 再発の徴候(発熱、咳、呼吸困難の再出現)があれば早期受診
誤嚥予防の指導(高齢者、嚥下障害がある場合):
- 食事時の姿勢(座位または半座位)
- ゆっくり食べる、一口量を少なくする
- とろみをつける
- 口腔ケアの重要性
看護計画・介入の内容
- 呼吸状態の継続的モニタリング:呼吸数、SpO2、呼吸パターン、呼吸困難の程度を1〜2時間ごとに観察します。呼吸音を聴診し、水泡音の有無や範囲を確認します。急激な呼吸状態の悪化があれば直ちに医師に報告します
- 酸素療法の管理:低酸素血症を改善するため、適切な酸素流量を維持します。SpO2を継続的にモニタリングし、90%以上を目標にします。酸素カニューレやマスクの装着状態、皮膚トラブルの有無を確認します
- 体位管理と呼吸介助:半座位または座位により呼吸を楽にします。深呼吸を促し、無気肺を予防します。体位変換により分泌物の移動と喀出を促進します
- 喀痰管理:痰の量、色、粘稠度を観察し、記録します。十分な水分摂取、去痰薬、加湿により痰の喀出を促します。体位ドレナージ、スクイージング、必要に応じて吸引により気道クリアランスを維持します
- バイタルサインの観察:体温、脈拍、血圧、呼吸数を定期的に測定します。発熱の程度と推移、頻脈や血圧低下(敗血症性ショックの徴候)に注意します
- 解熱対策:高熱(38.5℃以上)がある場合、解熱薬を投与します。クーリング(氷嚢)も併用しますが、過度のクーリングは避けます。発汗後は寝衣交換と清拭を行い、快適さを保ちます
- 水分・栄養管理:十分な水分摂取(経口または輸液)を促し、脱水を予防します。尿量、皮膚ツルゴール、粘膜の湿潤度を観察します。食事摂取量を記録し、栄養状態を評価します。高カロリー・高タンパクの食事を少量頻回で提供します
- 感染管理:標準予防策を実施します。飛沫感染予防のため、患者にマスク着用を促します。手指衛生を徹底し、医療従事者間での感染拡大を防ぎます
- 薬物療法の管理:抗菌薬を指示通りに投与します。アレルギー反応(発疹、呼吸困難、ショック)に注意し、異常があれば直ちに中止して医師に報告します。抗菌薬の副作用(下痢、肝障害、腎障害)もモニタリングします
- 活動と安静のバランス:急性期は安静が必要ですが、過度の臥床は廃用症候群や肺炎の悪化を招きます。症状が改善してきたら、段階的に活動を促します。深呼吸や咳嗽練習、ベッド上での四肢運動なども取り入れます
- 心理的支援:急性発症と呼吸困難による不安を傾聴し、受け止めます。病状の説明、治療の見通しを伝え、安心感を提供します。家族との面会や連絡を促し、精神的サポートを提供します
- 合併症の観察:胸膜炎(胸痛の増悪)、膿胸、肺膿瘍、敗血症(発熱の持続、意識レベルの低下、血圧低下)などの合併症に注意します。異常があれば早期に報告します
- 退院指導:服薬の重要性、禁煙、栄養摂取、水分摂取、ワクチン接種、再発の徴候と早期受診について説明します。高齢者や嚥下障害がある場合は、誤嚥予防の指導も行います
よくある疑問・Q&A
Q: 肺炎はうつりますか?家族にうつす心配はありますか?
A: 肺炎を起こす病原体(細菌、ウイルス)は感染する可能性がありますが、肺炎そのものが直接うつるわけではありません。つまり、肺炎患者から病原体が他の人にうつり、その人が肺炎を発症するかどうかは、その人の免疫力や基礎疾患によります。
感染経路は主に飛沫感染(咳やくしゃみによる飛沫)と接触感染(手指を介した感染)です。予防策として:
- 患者はマスクを着用する
- 咳エチケット(咳をする際はティッシュや肘で口を覆う)
- 手洗いの徹底
- 家族もマスク着用と手洗いを行う
特に、インフルエンザウイルスやCOVID-19などのウイルス性肺炎は感染力が強いため、注意が必要です。
Q: 肺炎と風邪はどう違うのですか?
A: 風邪は主に上気道(鼻、喉)の感染症で、鼻水、喉の痛み、軽い咳、微熱が主症状です。通常、数日〜1週間で自然に治癒します。
一方、肺炎は下気道(気管支、肺)の感染症で、高熱(38℃以上)、膿性痰、呼吸困難、胸痛などの症状が出現し、胸部X線で肺に浸潤影が確認されます。治療には抗菌薬が必要で、治療しないと重症化し、命に関わることもあります。
風邪が長引いたり、症状が悪化したりする場合は、肺炎に移行している可能性があるため、医療機関を受診してください。特に、高熱、呼吸困難、膿性痰が出現した場合は要注意です。
Q: 抗菌薬はどのくらいの期間飲む必要がありますか?途中でやめてもいいですか?
A: 肺炎の治療では、通常5〜7日間の抗菌薬投与が必要です(重症例や合併症がある場合はさらに長期)。症状が改善しても、医師の指示通りに最後まで服用することが非常に重要です。
途中で自己判断で中止すると:
- 肺炎が再発する
- 細菌が完全に死滅せず、耐性菌(抗菌薬が効かない菌)が出現するリスクがある
「熱が下がったから」「咳が楽になったから」といって勝手にやめず、必ず処方された分を全部飲み切ってください。
Q: 肺炎球菌ワクチンを打てば肺炎にならないのですか?
A: 肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎を予防するワクチンです。肺炎球菌は市中肺炎の最多原因菌(約30〜40%)ですので、ワクチンにより肺炎のリスクを大幅に減らすことができます。
ただし、すべての肺炎を予防できるわけではありません。肺炎はインフルエンザ菌、マイコプラズマ、ウイルスなど、さまざまな病原体でも起こります。そのため、肺炎球菌ワクチンに加えて、インフルエンザワクチンの接種も推奨されます。
接種推奨対象:
- 65歳以上の高齢者
- 慢性肺疾患(COPD、喘息)、心疾患、糖尿病、腎不全などの基礎疾患がある人
- 免疫抑制状態の人
- 喫煙者
Q: 高齢者は肺炎になりやすいのですか?なぜですか?
A: はい、高齢者は若年者に比べて肺炎になりやすく、また重症化しやすいです。理由は以下の通りです:
- 免疫力の低下:加齢により免疫機能が低下し、病原体への抵抗力が弱まります
- 基礎疾患の合併:COPD、心不全、糖尿病、腎不全など、肺炎のリスクを高める基礎疾患を持つことが多いです
- 誤嚥のリスク:嚥下機能が低下し、食べ物や唾液が気道に入る誤嚥が起こりやすくなります。口腔内の細菌が肺に入ることで誤嚥性肺炎を起こします
- 咳反射の低下:気道に異物が入っても咳で排出する力が弱まります
- 栄養状態の悪化:栄養不良により免疫力が低下します
また、高齢者の肺炎は症状が非典型的で、発熱がない、咳が少ないなど、気づきにくいことがあります。食欲不振、活気がない、意識レベルの低下などの非特異的症状で発見されることもあります。
予防策として、ワクチン接種、口腔ケア、栄養管理、禁煙、誤嚥予防が重要です。
Q: 肺炎の患者さんが急に呼吸困難を訴えたらどうすればいいですか?
A: まず呼吸状態を迅速に評価します。SpO2、呼吸数、呼吸パターン、チアノーゼの有無、意識レベルを確認します。
応急処置:
- 患者を半座位または座位にします
- 酸素投与を開始または流量を上げます(医師の指示に基づく)
- 穏やかに声をかけ、「ゆっくり呼吸してください」「そばにいますよ」と安心させます
- 直ちに医師に報告し、指示を仰ぎます
考えられる原因:
- 肺炎の悪化
- 胸水の増加
- 気胸の合併
- 肺塞栓症
- 心不全の合併
- 敗血症性ショック
医師の診察により原因が特定されれば、それに応じた治療が行われます。肺炎患者の急激な呼吸状態の悪化は、重篤な合併症の可能性があるため、迅速な対応が必要です。
まとめ
肺炎は、病原微生物が肺に感染し、肺胞に炎症が起こる疾患です。市中肺炎は病院外で発症し、肺炎球菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマ、ウイルスなどが主な原因です。日本における死亡原因の第5位を占め、特に高齢者では重要な疾患です。
病態の本質は、病原体の侵入→肺胞の炎症→肺の実質化→ガス交換障害です。肺胞が炎症性滲出液や膿で満たされることで、換気が障害され、低酸素血症が生じます。
症状は、発熱、咳、膿性痰、呼吸困難、胸痛が特徴的です。高齢者では症状が非典型的で、発熱がない、咳が少ないなど、診断が遅れることがあります。診断は胸部X線で肺野の浸潤影を確認することが必須です。
治療は抗菌薬療法が中心で、重症度、原因菌に応じて抗菌薬を選択します。支持療法として、酸素療法、輸液、解熱鎮痛薬も重要です。予防には、肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチンの接種が推奨されます。
看護の要点は、呼吸状態の継続的モニタリング、酸素療法の管理、喀痰管理、水分・栄養管理、解熱対策、感染管理です。呼吸数、SpO2、呼吸困難の程度を頻回に観察し、急激な悪化を早期に発見します。体位管理、深呼吸・咳嗽指導、喀痰の喀出促進により、呼吸機能を改善させます。
肺炎患者は、急性発症と呼吸困難により強い不安を抱きます。傾聴の姿勢を持ち、患者の不安を受け止め、病状の説明と治療の見通しを伝えることで、安心感を提供します。
実習では、呼吸状態の観察と適切な判断、迅速な対応が求められます。バイタルサインの変化を見逃さず、異常があれば直ちに報告する姿勢を持ちましょう。肺炎は適切な治療により回復可能な疾患ですが、重症化すると生命に関わるため、早期発見・早期治療が重要です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

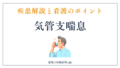
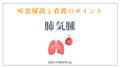
コメント