疾患概要
定義
妊娠高血圧症候群(Hypertensive Disorders of Pregnancy: HDP)は、妊娠20週以降に初めて高血圧を認める場合、または高血圧に蛋白尿を伴う場合と定義されます。高血圧は収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上を指します。従来は「妊娠中毒症」と呼ばれていましたが、現在は病態の理解が進み、妊娠高血圧症候群という名称に変更されました。重症化すると母児ともに生命に関わる重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
疫学
妊娠高血圧症候群は全妊娠の約3〜7%に発症し、妊産婦死亡原因の上位を占める重要な疾患です。初産婦、高齢妊娠(35歳以上)、多胎妊娠、肥満、糖尿病や腎疾患などの合併症を持つ妊婦に多く見られます。近年の晩婚化や高齢出産の増加により、発症リスクのある妊婦が増えています。また、低出生体重児や早産の原因としても重要で、周産期医療における大きな課題となっています。
原因
妊娠高血圧症候群の根本的な原因は完全には解明されていませんが、胎盤形成不全が中心的な役割を果たすと考えられています。妊娠初期の胎盤形成過程で、らせん動脈のリモデリング(血管の拡張・弾性化)が不十分だと、胎盤への血流が低下します。これにより胎盤が虚血状態となり、様々な血管作動物質や炎症性サイトカインが母体血中に放出され、全身の血管内皮細胞が障害されます。危険因子として、初産婦、高齢妊娠、多胎妊娠、肥満、糖尿病、腎疾患、自己免疫疾患、妊娠高血圧症候群の既往や家族歴などが挙げられます。
病態生理
妊娠高血圧症候群の本質は全身の血管内皮細胞障害です。胎盤からの血管収縮物質により全身の血管が収縮し、高血圧が生じます。同時に血管透過性が亢進し、血管内から血管外へ水分が漏出して浮腫が生じ、血液が濃縮して血液凝固能が亢進します。腎臓では糸球体内皮細胞が障害され蛋白尿が出現し、重症化すると腎機能が低下します。肝臓では肝細胞障害により肝酵素が上昇し、HELLP症候群(溶血、肝酵素上昇、血小板減少)を引き起こすことがあります。脳血管攣縮により子癇(全身痙攣発作)が起こる可能性があり、母体の生命に直結する緊急事態となります。胎盤機能不全により、胎児は発育不全や胎児機能不全を起こすリスクが高まります。
症状・診断・治療
症状
軽症例では自覚症状に乏しく、健診で初めて高血圧や蛋白尿を指摘されることが多いです。症状が出現する場合は、頭痛、目がチカチカする(眼症状)、上腹部痛、悪心・嘔吐、急激な体重増加や浮腫の悪化などが見られます。これらの症状は重症化のサインであり、子癇発作や常位胎盤早期剥離の前兆である可能性があるため、緊急対応が必要です。重症化すると、意識障害、痙攣発作、呼吸困難、乏尿、視野障害などが出現します。
診断
診断は血圧測定と尿蛋白検査により行われます。血圧は収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上で高血圧と診断します。重症高血圧は収縮期血圧160mmHg以上または拡張期血圧110mmHg以上です。尿蛋白は300mg/日以上または尿蛋白/クレアチニン比0.3以上で陽性とします。血液検査では、肝機能(AST、ALT)、腎機能(クレアチニン、尿酸)、血小板数、凝固機能を評価します。胎児の状態評価には胎児心拍数モニタリング(NST)、超音波検査による推定体重や羊水量、臍帯血流測定などを行います。
治療
妊娠高血圧症候群の根本的治療は妊娠の終了、つまり分娩です。しかし、妊娠週数が早い場合は胎児の未熟性が問題となるため、母児の状態を慎重に評価しながら管理します。軽症例では安静と食事療法(減塩、カロリー制限)を基本とし、外来または入院で厳重に経過観察します。血圧が高い場合は降圧薬(メチルドパ、ヒドララジン、ラベタロールなど)を使用しますが、急激な降圧は胎盤血流を低下させるため注意が必要です。重症例や母児の状態が悪化した場合は、妊娠の終了を検討します。子癇発作の予防・治療には硫酸マグネシウムを投与します。分娩様式は母児の状態により決定され、緊急帝王切開となることもあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 組織灌流量減少リスク:血管収縮による臓器血流低下のリスク
- 不安:母体や胎児の健康、早産への不安
- 知識不足:疾患や安静の必要性、症状観察に関する知識不足
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、患者が疾患の重症度を理解し、安静や治療の必要性を認識しているかを評価します。自覚症状が乏しいため、疾患の深刻さを理解しにくく、安静が守られないことがあります。活動-運動パターンでは、安静度の遵守状況と、安静による身体的・精神的ストレスを評価します。長期臥床により筋力低下や深部静脈血栓症のリスクも考慮します。コーピング-ストレス耐性パターンでは、突然の入院や活動制限、胎児への不安など、多重なストレスへの対処能力を評価し、家族のサポート状況も確認します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸するニードでは、重症化時の肺水腫や呼吸困難の早期発見が重要です。胸部聴診や呼吸状態の観察を定期的に行います。食べる・飲むニードでは、減塩食の理解と実践、悪心・嘔吐による食事摂取困難への対応、適切な水分バランスの維持が必要です。安全なニードでは、子癇発作のリスクアセスメントと予防的環境整備(静かな環境、刺激の最小化、ベッド柵の使用)、転倒予防が重要です。硫酸マグネシウム投与時は中毒症状(呼吸抑制、腱反射消失)の観察も必須です。
看護計画・介入の内容
- 厳重なバイタルサイン管理:血圧測定(1日4回以上)、体重測定(毎日)、尿量・尿蛋白測定、浮腫の観察、自覚症状の確認(頭痛、視覚異常、上腹部痛など)
- 胎児の状態観察:胎動カウント指導、NST(1日1〜2回)、胎児発育の評価、羊水量の確認
- 子癇発作への備え:静かな環境の提供、急激な刺激の回避、緊急時の対応準備(酸素、吸引器、気道確保物品、硫酸マグネシウムの準備)、発作時の安全確保(側臥位、舌咬傷予防)
- 心理的支援:疾患や治療の説明、母児の状態に関する情報提供、不安の傾聴、家族との面会調整、必要に応じて医師との面談調整
よくある疑問・Q&A
Q: 妊娠高血圧症候群は予防できますか?
A: 完全な予防は困難ですが、リスクを減らすことは可能です。妊娠前からの適正体重の維持、バランスの良い食事、適度な運動が重要です。妊娠中は定期的な妊婦健診を必ず受け、早期発見に努めることが大切です。低用量アスピリンの予防投与がハイリスク妊婦に推奨される場合もあります。
Q: 安静にしていれば治りますか?
A: 安静は症状の悪化を防ぐために重要ですが、根本的な治療にはなりません。妊娠高血圧症候群の根本的治療は分娩(妊娠の終了)のみです。しかし、安静により血圧の上昇を抑え、胎児がより成熟するまで妊娠を継続できる可能性があります。
Q: なぜ頭痛や目がチカチカするのが危険なのですか?
A: これらの症状は脳血管の攣縮や脳浮腫を示唆し、子癇発作(全身痙攣)の前兆である可能性があります。子癇は母体の生命に関わる緊急事態であり、脳出血や意識障害を引き起こす危険があるため、すぐに医療スタッフに報告する必要があります。
Q: 出産後はすぐに治りますか?
A: 多くの場合、分娩後24〜48時間以内に症状は改善し始め、産後12週までには正常化します。ただし、産後も高血圧が持続することがあり、特に産後48時間は子癇発作のリスクが高いため注意が必要です。また、将来的に慢性高血圧や心血管疾患のリスクが高まるため、長期的なフォローアップが推奨されます。
Q: 次の妊娠でもまた発症しますか?
A: 妊娠高血圧症候群の既往がある場合、次回妊娠での再発率は約15〜25%と高くなります。特に前回が重症だった場合や早期発症だった場合はリスクが高まります。次回妊娠時は初期から厳重な管理が必要で、低用量アスピリンの予防投与が推奨されることがあります。
Q: 赤ちゃんへの影響はありますか?
A: 妊娠高血圧症候群では胎盤機能不全により、胎児発育不全や胎児機能不全のリスクが高まります。重症の場合は早産となることもあり、低出生体重児や新生児合併症のリスクがあります。適切な管理により、これらのリスクを最小限にすることが目標となります。
まとめ
妊娠高血圧症候群は全妊娠の約3〜7%に発症し、母児ともに重篤な合併症を引き起こす可能性のある重要な疾患です。全身の血管内皮細胞障害が本質であり、高血圧や蛋白尿だけでなく、多臓器に影響を及ぼします。
看護師の最も重要な役割は、重症化のサインを早期に発見することです。頭痛、視覚異常、上腹部痛などの症状は子癇発作の前兆である可能性があり、緊急対応が必要です。日々のバイタルサイン測定、自覚症状の確認、胎児心拍モニタリングを確実に実施し、異常の早期発見に努めましょう。
患者の多くは自覚症状が乏しく、突然の入院や活動制限に戸惑いや不安を感じています。疾患の重症度を理解してもらい、安静の必要性を納得して守ってもらうための患者教育が重要です。また、母児の安全への不安に対する心理的支援も看護の重要な役割となります。
実習では、子癇発作への備えを常に意識し、静かな環境の提供、急激な刺激の回避、緊急時対応の準備状況を確認しましょう。硫酸マグネシウム投与時は中毒症状の観察(呼吸抑制、腱反射消失)も重要な観察ポイントです。母児の安全を最優先に、チーム医療の一員として迅速かつ適切に行動できるよう心がけましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
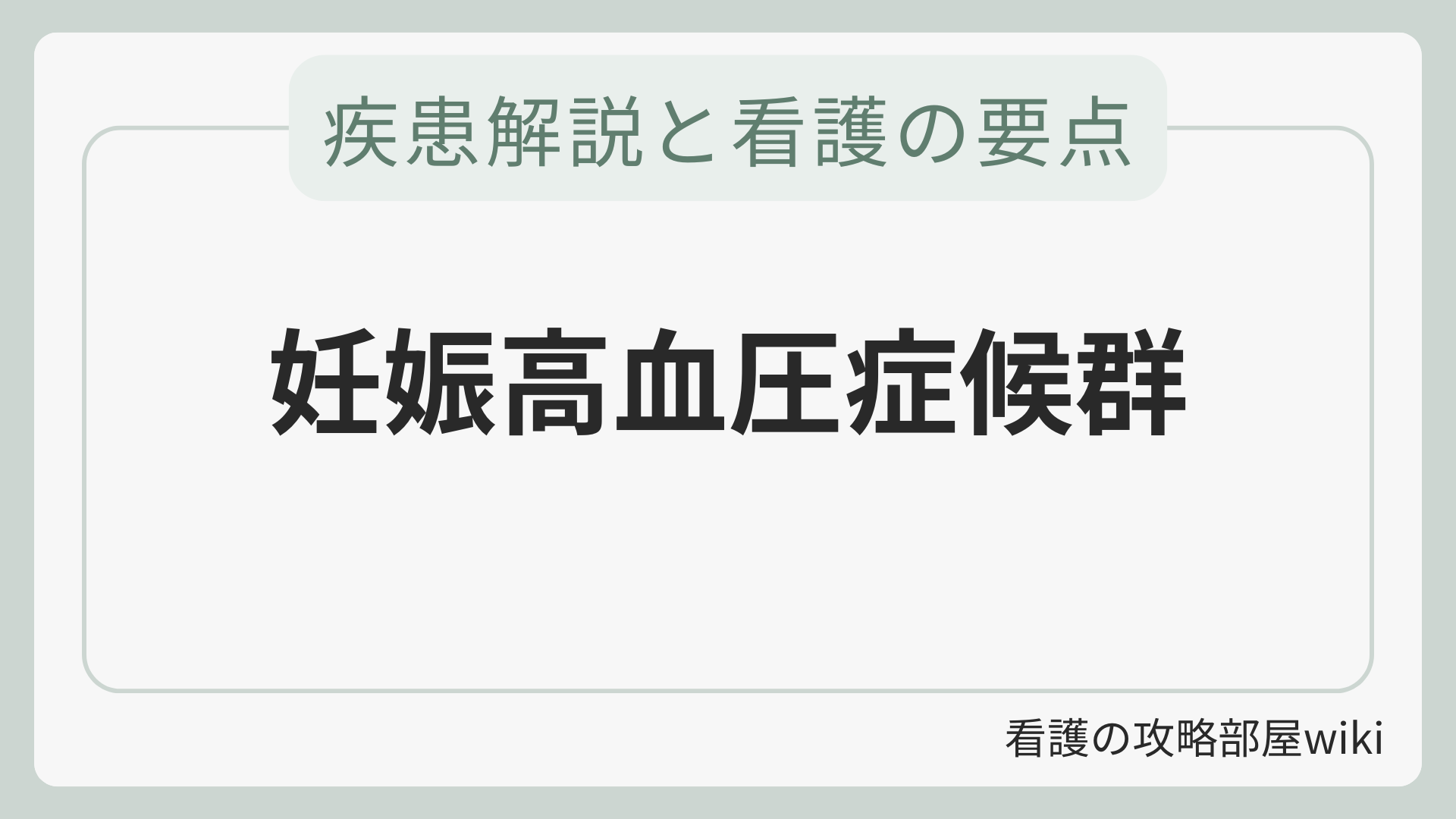
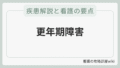
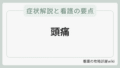
コメント