症状概要
定義
頭痛とは、頭部に感じる痛みや不快感の総称です。患者は「頭が痛い」「ズキズキする」「締め付けられる」「ガンガンする」「頭が重い」など様々な表現で訴えます。頭痛は非常に頻度の高い症状で、多くは一次性頭痛と呼ばれる機能性の頭痛ですが、中にはくも膜下出血や脳腫瘍などの重篤な疾患(二次性頭痛)が隠れていることもあります。看護師には、危険な頭痛を見逃さない観察力と迅速な対応が求められます。
疫学
頭痛は日本人の約3〜4人に1人が経験する非常に頻度の高い症状です。そのうち約90%以上は一次性頭痛(片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛)で、生命に関わることは少ないですが、QOLを大きく低下させます。特に片頭痛は20〜40代の女性に多く、約840万人の患者がいると推定されています。一方、二次性頭痛は約5〜10%と頻度は低いですが、くも膜下出血、脳腫瘍、髄膜炎など重篤な疾患が含まれ、見逃すと生命に関わります。
原因
頭痛は一次性頭痛と二次性頭痛に大きく分けられます。一次性頭痛は頭痛そのものが疾患であり、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛が代表的です。片頭痛は脳血管の拡張と三叉神経の炎症により、緊張型頭痛は頭頸部の筋肉の緊張により、群発頭痛は視床下部の異常により生じると考えられています。二次性頭痛は他の疾患が原因で起こる頭痛で、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、髄膜炎、脳炎、側頭動脈炎、緑内障発作、副鼻腔炎、高血圧性脳症、薬剤の副作用などが含まれます。
病態生理
片頭痛は、何らかの誘因により脳血管が拡張し、血管周囲の三叉神経が刺激されることで拍動性の痛みが生じます。セロトニンやCGRPなどの神経伝達物質が関与し、血管周囲に炎症が起こります。前兆を伴う場合は、大脳皮質拡延性抑制という現象により視覚異常などが生じます。緊張型頭痛は、精神的ストレスや不良姿勢により頭頸部の筋肉が持続的に収縮し、血流が低下することで痛みが生じます。くも膜下出血では、脳動脈瘤が破裂し、くも膜下腔に血液が流入することで激烈な頭痛と髄膜刺激症状が出現します。脳腫瘍では、頭蓋内圧亢進により頭痛、嘔吐、うっ血乳頭が生じます。
原因疾患・評価・対応
主な原因疾患
緊急対応が必要な危険な頭痛(レッドフラッグサイン)として、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、髄膜炎・脳炎、脳腫瘍、側頭動脈炎、急性緑内障発作、高血圧性脳症などがあります。一次性頭痛(機能性頭痛)として、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛が代表的です。片頭痛は拍動性で片側性のことが多く、悪心・嘔吐、光過敏、音過敏を伴います。緊張型頭痛は両側性で締め付けられるような鈍い痛みです。群発頭痛は片側の目の奥の激痛で、1〜2ヶ月間毎日同じ時刻に出現するのが特徴です。その他の二次性頭痛として、副鼻腔炎、薬剤性頭痛(鎮痛薬の過剰使用)、カフェイン離脱頭痛、二日酔いなどがあります。
評価とアセスメント
頭痛の評価で最も重要なのは危険な頭痛(レッドフラッグサイン)の鑑別です。まずバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数、体温、SpO2、意識レベル)を測定します。緊急性の高い危険なサインとして、突然発症の激しい頭痛(「バットで殴られたような」痛み)、今まで経験したことのない頭痛、50歳以降の初発頭痛、頭痛が日に日に悪化、発熱を伴う頭痛、神経学的症状を伴う頭痛(意識障害、麻痺、言語障害、痙攣)、悪心・嘔吐を伴う頭痛、体動で増悪する頭痛、項部硬直などがあれば緊急対応が必要です。頭痛の評価はOPQRSTを用いて系統的に行い、発症様式(突然か徐々にか)、部位(片側か両側か)、性状(拍動性か締め付けられるようか)、持続時間、随伴症状を詳細に確認します。
対応と治療
頭痛への対応は原因により異なりますが、危険な頭痛が疑われる場合は緊急対応が必要です。くも膜下出血が疑われる場合は、安静、血圧管理、頭部CT検査を緊急実施し、脳神経外科コンサルトを行います。髄膜炎が疑われる場合は、血液検査、髄液検査、頭部CTまたはMRIを実施し、抗菌薬投与を開始します。片頭痛の治療では、軽度なら鎮痛薬(NSAIDs)、中等度以上ではトリプタン製剤を使用します。予防薬として抗てんかん薬、β遮断薬、Ca拮抗薬なども使用されます。緊張型頭痛では、鎮痛薬、筋弛緩薬、ストレス管理、姿勢改善が有効です。群発頭痛の発作時には高濃度酸素吸入やトリプタン製剤を使用します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:血管拡張、筋緊張、頭蓋内圧亢進などに関連した頭部の疼痛
- 活動耐性低下:頭痛による日常生活動作の制限
- 不安:頭痛の原因や重症度に対する不安
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、頭痛の既往歴(種類、頻度、誘因、対処方法)、家族歴、内服薬(鎮痛薬の種類と頻度)を確認します。鎮痛薬の過剰使用は薬物乱用頭痛を引き起こすため、服薬状況の把握が重要です。活動-運動パターンでは、頭痛が日常生活にどの程度影響しているかを評価します。片頭痛では日常動作で痛みが増悪するため、仕事や家事ができなくなることが多く、QOLへの影響が大きいです。コーピング-ストレス耐性パターンでは、ストレスが頭痛の誘因や増悪因子となることが多いため、生活上のストレス状況と対処能力を評価します。緊張型頭痛は特にストレスと関連が深いです。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸するニードでは、群発頭痛の治療として高濃度酸素吸入が有効であり、酸素療法の実施と効果判定が重要です。また、重症頭痛では呼吸パターンの異常(Cheyne-Stokes呼吸など)が頭蓋内圧亢進を示唆することもあります。安全なニードでは、意識レベルの変化、神経学的症状の出現、転倒リスクを評価します。特に、くも膜下出血や脳出血では急激な意識レベル低下のリスクがあります。学習のニードでは、一次性頭痛の患者に対して、頭痛の種類、誘因、対処方法、予防策について教育します。頭痛日記をつけることで誘因の把握や治療効果の判定に役立ちます。
看護計画・介入の内容
- 頭痛の継続的評価:疼痛の程度・性状・部位・持続時間、発症様式(突然か徐々にか)、増悪・軽快因子の確認、バイタルサインの継続的モニタリング、神経学的症状の有無(意識レベル、瞳孔、運動麻痺、言語障害、痙攣)、髄膜刺激症状の有無(項部硬直、Kernig徴候)
- 疼痛緩和と安楽の提供:安静と休息の提供、環境調整(暗く静かな環境、適温)、処方された鎮痛薬の投与と効果判定、冷罨法(片頭痛)または温罨法(緊張型頭痛)、リラクセーション法の指導、群発頭痛では高濃度酸素吸入
- 誘因の回避と予防的介入:頭痛日記の記録指導、誘因となる因子の特定と回避(特定の食品、アルコール、睡眠不足、ストレス)、規則正しい生活リズムの維持、ストレス管理法の指導
よくある疑問・Q&A
Q: くも膜下出血の頭痛はどのような特徴がありますか?
A: くも膜下出血の頭痛は、突然発症の激烈な頭痛が最大の特徴で、患者は「バットで殴られたような」「今までで最悪の」と表現します。発症時刻を明確に言えることが多く、数秒から数分で最強になります。悪心・嘔吐、項部硬直、意識障害を伴うことが多く、見逃すと生命に関わるため、この特徴を持つ頭痛は必ず緊急対応が必要です。
Q: 片頭痛と緊張型頭痛の違いは何ですか?
A: 片頭痛は拍動性(ズキンズキン、ガンガン)で片側性のことが多く、中等度から高度の痛みで日常動作により増悪します。悪心・嘔吐、光過敏、音過敏を伴い、数時間から3日程度持続します。前兆(視覚異常など)を伴うこともあります。一方、緊張型頭痛は両側性で締め付けられるような、または圧迫されるような鈍い痛みです。軽度から中等度で、日常動作では増悪せず、悪心・嘔吐は通常ありません。30分から数日持続します。
Q: 頭痛に冷罨法と温罨法はどう使い分けますか?
A: 片頭痛では血管拡張が原因のため、冷罨法(額や首筋を冷やす)が有効です。血管を収縮させ痛みを軽減します。一方、緊張型頭痛では筋肉の緊張が原因のため、温罨法(首や肩を温める)が有効です。血流を改善し筋肉の緊張を和らげます。頭痛の種類が不明な場合や、患者が楽だと感じる方法を優先しましょう。
Q: 鎮痛薬を飲みすぎると頭痛がひどくなるというのは本当ですか?
A: はい、本当です。鎮痛薬を月に10〜15日以上、3ヶ月以上連用すると薬物乱用頭痛(薬剤の使用過多による頭痛)を引き起こすことがあります。この場合、鎮痛薬が効かなくなり、かえって頭痛が慢性化・悪化します。治療には原因薬剤の中止が必要ですが、離脱症状として一時的に頭痛が悪化するため、医師の指導のもとで行う必要があります。
Q: 片頭痛の誘因にはどのようなものがありますか?
A: 片頭痛の誘因は個人差がありますが、食品(チョコレート、チーズ、赤ワイン、人工甘味料)、生活習慣(睡眠不足または寝過ぎ、空腹、疲労)、環境因子(強い光、騒音、天候の変化、気圧の変化)、ホルモン変動(月経、排卵期)、ストレス(ストレス自体よりストレスからの解放時)などが知られています。頭痛日記をつけることで個人の誘因を特定できます。
Q: 項部硬直はどうやって確認しますか?
A: 項部硬直は髄膜刺激症状の一つで、仰臥位で患者の後頭部に手を当て、顎を胸につけるように頭部を前屈させようとしたとき、首が硬く抵抗があり前屈できない状態です。くも膜下出血や髄膜炎で陽性となります。確認時は患者に「力を抜いてください」と声をかけ、患者自身が抵抗していないことを確認します。Kernig徴候(股関節・膝関節を屈曲位から膝を伸展させようとすると抵抗がある)も併せて確認します。
まとめ
頭痛は非常に頻度の高い症状であり、多くは一次性頭痛(片頭痛、緊張型頭痛)で生命に関わることは少ないですが、中にはくも膜下出血や髄膜炎などの重篤な疾患が隠れていることもあります。看護師の最も重要な役割は、危険な頭痛(レッドフラッグサイン)を見逃さないことです。
特に、突然発症の激烈な頭痛、今まで経験したことのない頭痛、神経学的症状を伴う頭痛、項部硬直などは緊急対応が必要なサインであり、迅速にバイタルサイン測定と医師への報告を行う必要があります。
一次性頭痛の患者に対しては、疼痛緩和だけでなく、頭痛の種類を理解してもらい、誘因の回避や生活習慣の改善など、セルフマネジメント能力を高める支援が重要です。頭痛日記の記録は誘因の特定や治療効果の判定に有用です。
実習では、頭痛を訴える患者に遭遇した際、まず緊急性の評価を最優先に行い、OPQRST を用いた系統的な問診と、神経学的観察(意識レベル、瞳孔、運動麻痺、項部硬直)を確実に実施しましょう。また、片頭痛患者には暗く静かな環境、緊張型頭痛患者にはリラクセーションなど、頭痛の種類に応じた適切な看護介入を提供することが大切です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
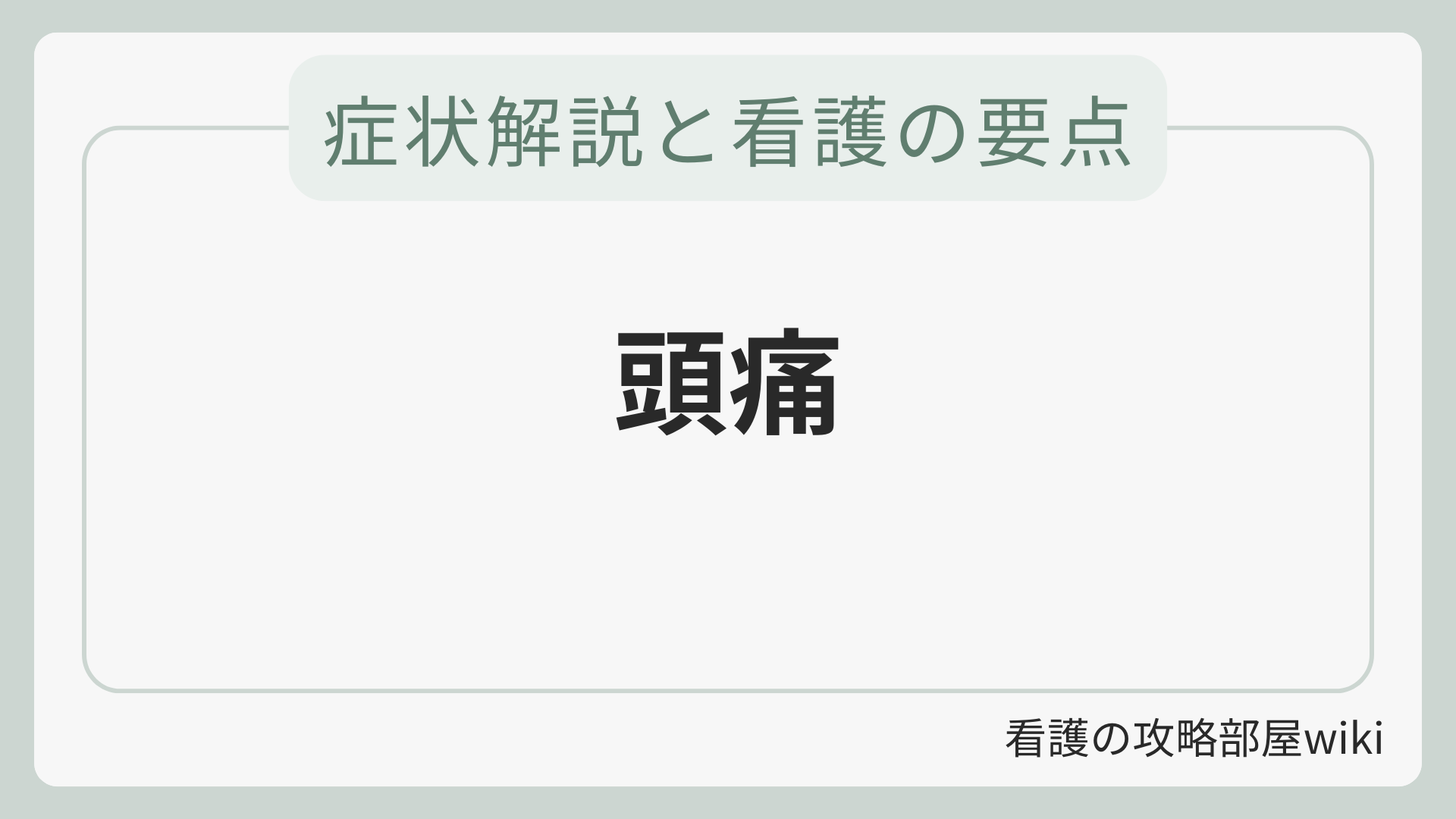
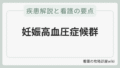
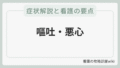
コメント