疾患概要
定義
前立腺肥大症(Benign Prostatic Hyperplasia:BPH)は、加齢に伴って前立腺が良性に肥大する疾患です。前立腺は男性特有の臓器で、膀胱の直下、尿道を取り囲むように位置しています。この前立腺が肥大することで尿道が圧迫され、排尿障害を引き起こします。「良性」という言葉が示すように、がん(悪性腫瘍)とは異なり、生命を直接脅かすものではありませんが、患者さんのQOL(生活の質)を大きく低下させる疾患です。
疫学
前立腺肥大症は中高年男性に非常に多い疾患で、加齢とともに発症率が上昇します。50歳代で約50%、60歳代で約60%、70歳代では約80%の男性に前立腺の肥大が認められるとされています。ただし、前立腺が肥大していても必ずしも症状が出るわけではなく、実際に治療が必要となるのはそのうちの一部です。日本では高齢化に伴い患者数が増加しており、今後もさらに増えることが予測されています。
原因
前立腺肥大症の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、加齢と男性ホルモン(アンドロゲン)が深く関与していることが分かっています。男性ホルモンの一種であるテストステロンが前立腺内でジヒドロテストステロン(DHT)に変換され、このDHTが前立腺細胞の増殖を促進すると考えられています。その他の危険因子としては、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などのメタボリックシンドロームの要素が挙げられます。遺伝的要因も関与している可能性があります。
病態生理
前立腺肥大症の病態は、大きく分けて「前立腺の肥大」と「それに伴う排尿障害」の2つの側面から理解する必要があります。
まず、加齢と男性ホルモンの影響により、前立腺の移行域(尿道周囲の部分)が主に肥大します。この肥大には結節性過形成という特徴があり、前立腺の内腺が大きくなって尿道を圧迫します。前立腺がんは主に外腺から発生するため、肥大症とは発生部位が異なるんですね。
前立腺が肥大して尿道を圧迫すると、機械的閉塞が起こります。これにより尿の通り道が狭くなり、尿が出にくくなります。さらに、この機械的な閉塞に加えて、動的閉塞も関与します。前立腺や膀胱頸部には平滑筋が豊富に存在し、これらが交感神経の刺激によって収縮すると、さらに尿道が狭くなるのです。
排尿障害が続くと、膀胱は尿を押し出すために強く収縮する必要が生じます。この状態が長期間続くと、膀胱壁が肥厚し(膀胱の筋肉が厚くなる)、さらに進行すると膀胱の収縮力が低下してしまいます。また、膀胱内に尿が残る残尿が増加し、膀胱容量の減少や過活動膀胱(膀胱が過敏になり、急に強い尿意を感じる状態)を引き起こします。
重症化すると、膀胱から腎臓への尿の逆流(膀胱尿管逆流)や、水腎症(腎臓に尿が溜まって腫れる状態)を引き起こし、最終的には腎機能障害に至る可能性もあります。
症状・診断・治療
症状
前立腺肥大症の症状は、大きく蓄尿症状、排尿症状、排尿後症状の3つに分類されます。
蓄尿症状には、頻尿(昼間8回以上、夜間1回以上の排尿)、夜間頻尿、尿意切迫感(急に強い尿意を感じ、我慢できない)などがあります。特に夜間頻尿は患者さんの睡眠を妨げ、QOLを大きく低下させる症状です。
排尿症状としては、尿勢低下(尿の勢いが弱い)、尿線途絶(排尿の途中で尿が途切れる)、排尿遅延(尿が出始めるまでに時間がかかる)、腹圧排尿(お腹に力を入れないと尿が出ない)などが見られます。
排尿後症状には、残尿感(排尿後もまだ尿が残っている感じがする)、排尿後尿滴下(排尿後にポタポタと尿が漏れる)があります。
重症化すると、尿閉(まったく尿が出なくなる)や溢流性尿失禁(膀胱に尿が溜まりすぎて少しずつ漏れてしまう)、血尿、尿路感染症、膀胱結石などの合併症を引き起こすこともあります。
診断
診断は問診、身体診察、各種検査を組み合わせて行われます。
問診では国際前立腺症状スコア(IPSS)という質問票を用いて、症状の程度を客観的に評価します。0〜7点が軽症、8〜19点が中等症、20〜35点が重症と判定されます。
身体診察では直腸診が重要です。肛門から指を入れて前立腺を触診し、大きさ、硬さ、表面の性状を確認します。前立腺肥大症では前立腺が弾性軟に腫大し、表面は平滑です。
検査としては、尿検査で血尿や尿路感染の有無を確認し、血液検査では腎機能(BUN、クレアチニン)とPSA(前立腺特異抗原)を測定します。PSAは前立腺がんのスクリーニングに用いられる腫瘍マーカーで、前立腺肥大症でも上昇することがありますが、急激な上昇や著しい高値の場合は前立腺がんを疑います。
尿流測定検査では、排尿の勢いや量をグラフで測定し、残尿測定は超音波検査で排尿後の膀胱内の尿量を確認します。経直腸的超音波検査では前立腺の大きさや形態を詳しく観察できます。
治療
治療は症状の程度と患者さんのQOLへの影響を考慮して選択されます。
軽症で日常生活への支障が少ない場合は、生活指導を中心とした経過観察を行います。水分摂取のタイミング調整(就寝前の水分制限)、アルコールやカフェインの制限、排尿習慣の改善などを指導します。
中等症以上では薬物療法が第一選択となります。主な薬剤には、α1遮断薬(交感神経を遮断して前立腺と膀胱頸部の平滑筋を弛緩させ、尿道を広げる)、5α還元酵素阻害薬(テストステロンからDHTへの変換を阻害し、前立腺を縮小させる)、PDE5阻害薬(血流を改善し、下部尿路の平滑筋を弛緩させる)などがあります。過活動膀胱の症状が強い場合は、抗コリン薬やβ3作動薬も併用されます。
薬物療法で効果が不十分な場合や、尿閉を繰り返す、腎機能障害がある、膀胱結石を伴うなどの場合は手術療法が検討されます。現在の標準術式は経尿道的前立腺切除術(TUR-P)で、尿道から内視鏡を挿入し、肥大した前立腺組織を切除します。近年では、レーザーを用いた低侵襲手術も増えています。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 排尿障害(尿閉、頻尿、残尿感)
- 睡眠パターン混乱(夜間頻尿による)
- 活動耐性低下(頻尿による外出制限)
- 不安(症状の進行、がんへの不安)
- 知識不足(疾患や治療に関する理解不足)
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
患者さんが自身の症状をどのように認識し、どの程度生活に支障をきたしているかをアセスメントします。「年だから仕方ない」と諦めて医療機関を受診していない場合や、前立腺がんへの不安を抱えている場合もあります。疾患に対する正しい理解を促し、適切な治療を受けることの重要性を伝えましょう。
排泄パターン
最も重要なアセスメント領域です。排尿回数(昼間・夜間)、1回排尿量、尿の性状、残尿感の有無、尿意切迫感の頻度、排尿時の痛みなどを詳細に聴取します。排尿日誌をつけてもらうことで、客観的なデータが得られます。また、便秘は排尿障害を悪化させるため、排便状況も確認が必要です。
睡眠-休息パターン
夜間頻尿により睡眠が分断されることで、日中の眠気や疲労感、集中力低下が生じます。何回起きるか、睡眠の質はどうか、日中の生活への影響を評価し、必要に応じて就寝前の水分制限や内服時間の調整を検討します。
活動-運動パターン
頻尿のためにトイレの場所を常に気にして外出を控えたり、社会活動への参加を制限したりしていないか確認します。これは患者さんの社会的孤立やQOL低下につながるため、適切な治療により活動範囲を広げられることを伝えましょう。
認知-知覚パターン
疾患や治療に関する理解度を確認します。特に薬物療法では効果が出るまでに時間がかかること、継続が重要であることを理解してもらう必要があります。また、尿閉や血尿などの緊急時の対応についても説明します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に排泄する
前立腺肥大症の中心的なニードです。排尿パターンの観察、残尿測定、尿閉の早期発見が重要です。排尿時の姿勢の工夫(前かがみになる、温座浴など)や、リラックスできる環境を整えることも効果的です。カテーテル留置が必要な場合は、適切な管理と感染予防が必要です。
正常に飲食する
水分摂取のタイミングと量の調整が重要です。脱水を避けつつ、夜間頻尿を軽減するために就寝2〜3時間前からの水分制限を指導します。アルコールやカフェインは利尿作用があるため、摂取時間や量に注意が必要です。
睡眠と休息をとる
夜間頻尿による睡眠障害に対して、就寝前の排尿習慣、適切な室温と照明(夜間トイレに行く際の転倒予防)、睡眠薬の必要性などを検討します。日中の過度な水分摂取を避け、夕方以降の水分量を調整することで、夜間の尿量を減らす工夫も有効です。
身体を清潔に保ち、身だしなみを整える
尿漏れがある場合は、皮膚の清潔保持と尿臭への対応が必要です。適切な尿パッドの使用方法を指導し、皮膚トラブルを予防します。心理的な羞恥心にも配慮しながら、具体的なケア方法を提案しましょう。
娯楽をもつ
頻尿により外出や趣味活動を制限していないか確認します。適切な治療により症状が改善できること、外出時の工夫(トイレマップの活用、尿パッドの使用など)を伝え、社会生活の維持を支援します。
看護計画・介入の内容
- 排尿パターンの観察と記録:排尿日誌をつけてもらい、排尿回数、時間、量、残尿感などを客観的に評価します。入院中は尿量測定と残尿測定を定期的に実施します。
- 尿閉の早期発見:下腹部の膨満感、疼痛、不穏などの尿閉のサインを見逃さないようにします。特に手術後や新たな薬剤開始後は注意が必要です。
- 水分摂取の指導:1日1500〜2000mlを目安に、日中にこまめに摂取し、夜間は控えるよう指導します。脱水にならないよう注意しながら、夜間頻尿の軽減を図ります。
- 排尿環境の整備:トイレまでの動線を確保し、夜間の転倒を防ぐために足元灯を設置します。病室では尿器やポータブルトイレの配置も検討します。
- 薬物療法の管理と副作用観察:α1遮断薬では起立性低血圧やめまいに注意し、ゆっくり立ち上がるよう指導します。5α還元酵素阻害薬は効果が出るまで数ヶ月かかることを説明し、継続を促します。
- 生活指導:便秘の予防(排尿障害を悪化させるため)、長時間の座位を避ける、身体を冷やさない、適度な運動を継続するなどを指導します。
- 心理的サポート:排尿障害による羞恥心や不安、がんへの恐怖などに共感的に対応します。同じ悩みを持つ患者会の情報提供も有効です。
- 術後管理(TUR-P後):尿道カテーテル管理、血尿の観察、膀胱洗浄、尿閉の予防、感染予防などを行います。退院後も数週間は血尿が続く可能性があることを説明します。
よくある疑問・Q&A
Q: 前立腺肥大症と前立腺がんの違いは何ですか?
A: 前立腺肥大症は良性疾患で、主に前立腺の移行域(内腺)が肥大します。一方、前立腺がんは悪性腫瘍で、主に外腺から発生します。前立腺肥大症自体ががんに変化することはありませんが、両方を併発することはあります。PSA値が高い場合や直腸診で硬い結節を触れる場合は、がんを疑って精密検査(生検)が必要になります。どちらも中高年男性に多い疾患なので、鑑別診断が重要なんですね。
Q: 患者さんから「手術すると性機能に影響しますか?」と聞かれたらどう答えたらよいですか?
A: これは患者さんが最も心配される質問の一つです。TUR-Pでは勃起機能は通常保たれますが、逆行性射精(精液が尿道から出ずに膀胱に逆流する現象)が70〜90%の確率で起こります。性的快感は保たれますが、精液が出ないため、妊娠を希望する場合は問題となります。このような情報は、患者さんのプライバシーに配慮しながら、医師と連携して適切なタイミングで伝える必要があります。看護師として、患者さんの不安を受け止め、医師への質問をサポートする姿勢が大切です。
Q: 夜間頻尿で何度も起きる患者さんへの看護で、特に注意すべき点は何ですか?
A: 最も注意すべきは転倒・転落のリスクです。高齢者は夜間に急いでトイレに行こうとして転倒しやすく、骨折などの重大な事故につながります。ベッド周囲の環境整備(動線の確保、足元灯の設置、滑り止めマットの使用)や、ナースコールの適切な使用を促すことが重要です。また、睡眠不足は日中の活動性低下や転倒リスクをさらに高めるため、夜間の排尿回数を減らす工夫(就寝前の水分制限、下肢の挙上による浮腫の軽減など)も効果的です。患者さんの安全を守りながら、QOLの改善を目指しましょう。
Q: 尿閉を起こした場合、すぐにカテーテルを挿入すべきですか?
A: 尿閉は緊急対応が必要な状態です。膀胱が過伸展すると膀胱機能が損なわれる可能性があるため、速やかに医師に報告し、指示を仰ぎます。通常は尿道カテーテルを挿入して尿を排出しますが、前立腺肥大が高度な場合はカテーテル挿入が困難なこともあります。その場合は恥骨上膀胱穿刺や膀胱瘻造設が必要になることもあります。カテーテル挿入時は無理に挿入せず、抵抗があれば医師に交代してもらいましょう。挿入後は急激な尿排出による血圧低下や血尿に注意が必要です。
まとめ
前立腺肥大症は加齢に伴う良性疾患であり、生命を脅かすものではありませんが、患者さんのQOLを大きく低下させる疾患です。病態の本質は、前立腺の肥大による尿道の圧迫と、それに伴う膀胱機能の変化にあります。
看護の要点は、排尿パターンの詳細な観察、尿閉の早期発見、転倒予防、そして心理的サポートです。特に夜間頻尿は患者さんの睡眠を妨げ、転倒のリスクを高めるため、生活指導と環境整備が重要になります。
治療は薬物療法が第一選択であり、効果が出るまでに時間がかかることや継続の重要性を患者さんに理解してもらう必要があります。手術療法が必要な場合は、術後の合併症(血尿、尿失禁、逆行性射精など)について事前に十分な説明を行い、患者さんの不安を軽減することが大切です。
実習では、患者さんの羞恥心に配慮しながら、排尿状況を詳しく聴取すること、そして生活への影響を多角的にアセスメントすることを意識しましょう。前立腺肥大症の患者さんは、症状を「年のせい」と諦めていたり、がんへの不安を抱えていたりすることも多いため、傾聴の姿勢を大切にしてください。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
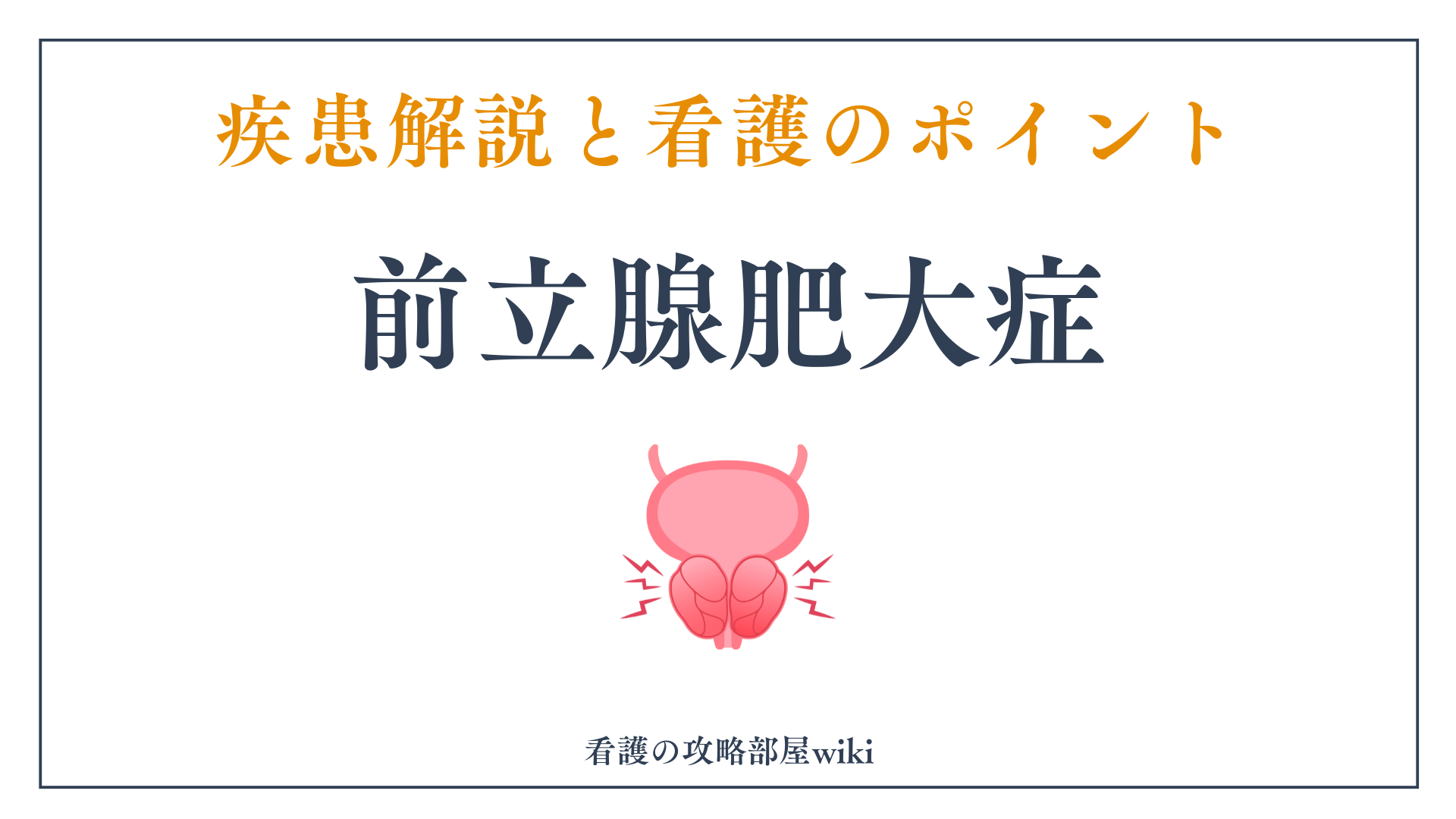
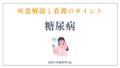
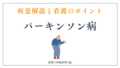
コメント