疾患概要
定義
PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)は、生命の危険を感じるような強烈なトラウマ体験の後に生じる精神的な後遺症です。トラウマ体験の再体験症状、回避症状、認知と気分の陰性変化、覚醒と反応性の変化を主症状とし、1ヶ月以上持続して日常生活に著しい支障をきたします。単なる「心の傷」ではなく、脳の機能的・構造的変化を伴う疾患であり、適切な治療により回復が期待できる病気です。
疫学
PTSDの生涯有病率は約3-4%ですが、トラウマ体験者では約10-30%に発症します。女性の発症率は男性の約2倍で、特に性的暴力、家庭内暴力の被害者で高率です。発症リスクの高いトラウマとして、戦争体験、性的暴力、重大事故、自然災害、犯罪被害、幼少期の虐待などがあります。日本では東日本大震災後にPTSD患者が増加し、自然災害によるトラウマの影響が注目されています。併存疾患が多く、約80%でうつ病、不安障害、物質使用障害を併発します。自殺リスクも高く、一般人口の約6倍とされています。
原因
PTSDの発症にはトラウマ体験が必須ですが、すべての人が発症するわけではありません。危険因子として女性、若年、既往の精神疾患、社会的支援の不足、追加的トラウマ、遺伝的素因があります。保護因子として強固な社会的支援、高い教育レベル、良好な対処能力、楽観的性格、宗教的信念などがあります。神経生物学的要因では視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)の異常、ノルアドレナリン系の過活動、セロトニン系の機能低下が関与します。心理学的要因では認知の歪み、学習性無力感、解離が病態形成に関与します。
病態生理
PTSDでは恐怖記憶の過剰固定と消去学習の障害が中核となります。扁桃体の過活動により恐怖反応が亢進し、海馬の機能低下により記憶の適切な処理ができなくなります。前頭前野の機能低下により恐怖反応の制御が困難となり、視床での感覚情報処理に異常が生じます。HPA軸の調節異常によりコルチゾール分泌パターンが変化し、ノルアドレナリン系の過活動により過覚醒症状が出現します。解離症状は心理的防衛機制として働きますが、適応的な情報処理を阻害します。神経画像研究では扁桃体の活動亢進、海馬容積の減少、前頭前野の活動低下が認められています。
症状・診断・治療
症状
再体験症状では侵入的記憶(フラッシュバック)、悪夢、身体反応(動悸、発汗)、心理的苦痛がトラウマ想起により出現します。回避症状ではトラウマ関連の思考・感情の回避、場所・人・活動の回避が認められます。認知と気分の陰性変化では記憶の欠損、自己・他者・世界に対する否定的信念、持続的な陰性感情、興味の著明な減退、離人感・現実感消失、他者からの疎外感が出現します。覚醒と反応性の変化では易怒性・攻撃行動、無謀・自己破壊的行動、過度の警戒心、過剰な驚愕反応、集中困難、睡眠障害が認められます。解離症状として離人感、現実感消失、時間感覚の歪み、記憶の断片化が生じることもあります。
診断
診断はDSM-5の診断基準に基づいて行われます。トラウマ体験の存在、4つの症状群(再体験、回避、認知・気分の陰性変化、覚醒・反応性の変化)からの症状、1ヶ月以上の症状持続、機能的障害が診断要件です。評価尺度としてCAPS-5(臨床医面接式PTSD尺度)、PCL-5(PTSD症状チェックリスト)、IES-R(改訂出来事インパクト尺度)が用いられます。鑑別診断では急性ストレス障害、適応障害、うつ病、不安障害、物質使用障害、境界性人格障害などを除外します。複雑性PTSDでは対人関係の困難、感情調節の問題、自己概念の障害が追加され、長期間の反復的トラウマで生じやすいとされています。
治療
心理療法が第一選択で、トラウマ焦点化認知行動療法とEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)が最も効果的です。PE(持続エクスポージャー療法)ではトラウマ記憶への段階的曝露により恐怖反応の消去を図ります。CPT(認知処理療法)ではトラウマ関連の認知の歪みを修正します。薬物療法ではSSRI(セルトラリン、パロキセチン)が第一選択で、SNRI(ベンラファキシン)も有効です。プラゾシンは悪夢に対して効果があります。複合的治療として心理療法と薬物療法の併用、集団療法、家族療法も考慮されます。身体的アプローチとしてヨガ、太極拳、ボディワークも補助的に用いられます。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 心的外傷後症候群:トラウマ体験に関連した持続的な苦痛症状
- 非効果的対処:トラウマ反応に対する不適応的対処行動
- 社会的孤立:回避症状と対人不信による社会的関係の断絶
ゴードン機能的健康パターン
認知・知覚パターンでは再体験症状の頻度と強度、解離症状の有無、記憶の連続性、現実検討能力を詳細にアセスメントします。トリガー(症状誘発要因)の特定と回避パターンの把握が重要です。対処・ストレス耐性パターンでは従来の対処方法、社会的支援システム、危険行動(自傷、物質使用、無謀行為)、自殺リスクを継続的に評価します。睡眠・休息パターンでは悪夢、中途覚醒、過覚醒による睡眠障害の程度と日常生活への影響を把握します。
ヘンダーソン14基本的ニード
安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは自傷・自殺リスクの評価と安全確保が最優先となります。トリガー要因の除去と安全な環境の提供が重要です。コミュニケーションをとるでは対人不信や回避により生じるコミュニケーション困難を評価し、信頼関係構築を支援します。眠る・休むでは悪夢や過覚醒による睡眠障害を評価し、良質な睡眠確保を支援します。働くこと、達成感を得るではトラウマ症状による職業機能への影響を評価し、段階的な社会復帰を支援します。
看護計画・介入の内容
- 安全確保・危機管理:自殺・自傷リスクの継続的評価、トリガー要因の特定と除去、安全で支持的な環境の提供、危険行動の予防、24時間の見守り体制確立
- 症状管理・対処支援:再体験症状への対処法指導(グラウンディング技法、呼吸法)、解離症状への対応、フラッシュバック時の安全確保、症状記録による自己観察支援
- 治療的関係構築:信頼関係の段階的構築、ペースを尊重した関わり、トラウマインフォームドケアの実践、エンパワメントの支援、治療動機の維持・向上
よくある疑問・Q&A
Q: PTSDは治る病気ですか?トラウマの記憶は消えるのでしょうか?
A: PTSDは適切な治療により大幅な改善が期待できる疾患です。約70-80%の患者さんで症状の著明な改善が認められ、日常生活に支障のない状態まで回復可能です。ただし、トラウマの記憶自体が完全に消えるわけではありません。治療の目標は記憶を「消す」ことではなく、記憶に伴う苦痛を軽減し、日常生活に支障をきたさない程度にコントロールできるようになることです。多くの方が治療により「思い出しても動揺しない」「普通の記憶として統合される」状態まで改善しています。
Q: フラッシュバックが起きた時はどう対処すればよいですか?
A: フラッシュバック時はグラウンディング技法が効果的です。5-4-3-2-1法では周囲にある「5つの見えるもの、4つの触れるもの、3つの聞こえるもの、2つの匂うもの、1つの味わうもの」を順番に意識し、現在に意識を戻します。呼吸法では鼻から4秒で吸い、7秒止めて、口から8秒で吐く腹式呼吸を繰り返します。身体感覚では足裏の感覚、椅子に座っている感覚など「今ここ」の身体感覚に注意を向けます。安全な場所への移動、信頼できる人への連絡も有効です。事前準備として対処法カードを携帯し、安全な場所を確認しておくことが重要です。
Q: 家族や周囲の人はどのように接すればよいでしょうか?
A: トラウマインフォームドケアの視点が重要です。基本原則として、①安全性の確保(物理的・心理的安全)、②信頼関係の構築(一貫性、透明性)、③選択と協働(本人の選択を尊重)、④文化的配慮(価値観の尊重)を心がけます。避けるべき対応は「忘れなさい」「頑張って」「もう過去のこと」などの minimizing(軽視)や、詳細を聞き出そうとする行為です。適切な対応では「つらかったですね」「あなたは悪くない」「一緒にいます」と共感と支持を示し、本人のペースを尊重します。専門的治療への橋渡し役となり、家族自身のケア(カウンセリング、家族会)も重要です。
Q: 薬だけでは治らないのでしょうか?心理療法は必ず必要ですか?
A: 薬物療法だけでは根本的な改善は困難で、心理療法との併用が最も効果的です。薬物療法は症状の軽減(不安、うつ、睡眠障害)に有効ですが、トラウマ記憶の適切な処理には心理療法が必要です。トラウマ焦点化認知行動療法やEMDRにより、恐怖記憶の適切な統合と認知の歪みの修正を行います。ただし、重篤な症状や解離が強い場合は、まず薬物療法で症状を安定化させてから心理療法を開始します。段階的なアプローチとして、①安全化・安定化、②トラウマ処理、③統合・再生、の順で治療を進めます。患者さんの準備状況と治療意欲を考慮して、適切なタイミングで心理療法を導入することが重要です。
まとめ
PTSDは深刻なトラウマ体験後に生じる精神的後遺症として、患者さんの人生に深刻な影響を与える疾患です。しかし、トラウマインフォームドケアの理念に基づく適切な理解と治療により、回復と成長が可能な疾患でもあります。
看護の要点は安全確保と信頼関係の構築です。PTSD患者さんは基本的な安全感が損なわれているため、物理的・心理的安全の確保が治療の前提となります。再トラウマ化を防ぐため、患者さんのペースを尊重し、選択権を保障することが重要です。
症状管理では、フラッシュバックや解離症状への適切な対応により、患者さんが症状に圧倒されることなく日常生活を維持できるよう支援します。グラウンディング技法や呼吸法などの具体的な対処スキルの指導により、患者さんの自己効力感を高めることができます。
治療的関係では、無条件の受容と共感的理解により、患者さんが安心して体験を語れる環境を提供します。再体験症状は病気の症状であり、患者さんの「弱さ」ではないことを理解し、非批判的な態度で関わることが大切です。
治療支援では、心理療法の重要性を説明し、治療への動機づけを行います。治療過程では一時的に症状が悪化することもあるため、治療継続への支援と希望の維持が重要な役割となります。
社会復帰支援では、トラウマ症状による職業・社会機能の低下を考慮し、段階的なアプローチで社会復帰を促進します。ピアサポートや自助グループの活用により、孤立感の軽減と相互支援を促進することも効果的です。
実習では患者さんのトラウマ体験を詳細に聞き出そうとしないことが重要です。症状や現在の困りごとに焦点を当て、患者さんの強さや回復力(レジリエンス)に注目したケアを提供しましょう。PTSDは回復可能な疾患であり、多くの方がポストトラウマティック成長(トラウマ後の成長)を体験しています。希望を持って治療に取り組めるよう、患者さんとその家族を支援し、新しい人生の再構築に向けて包括的なケアを提供していきましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
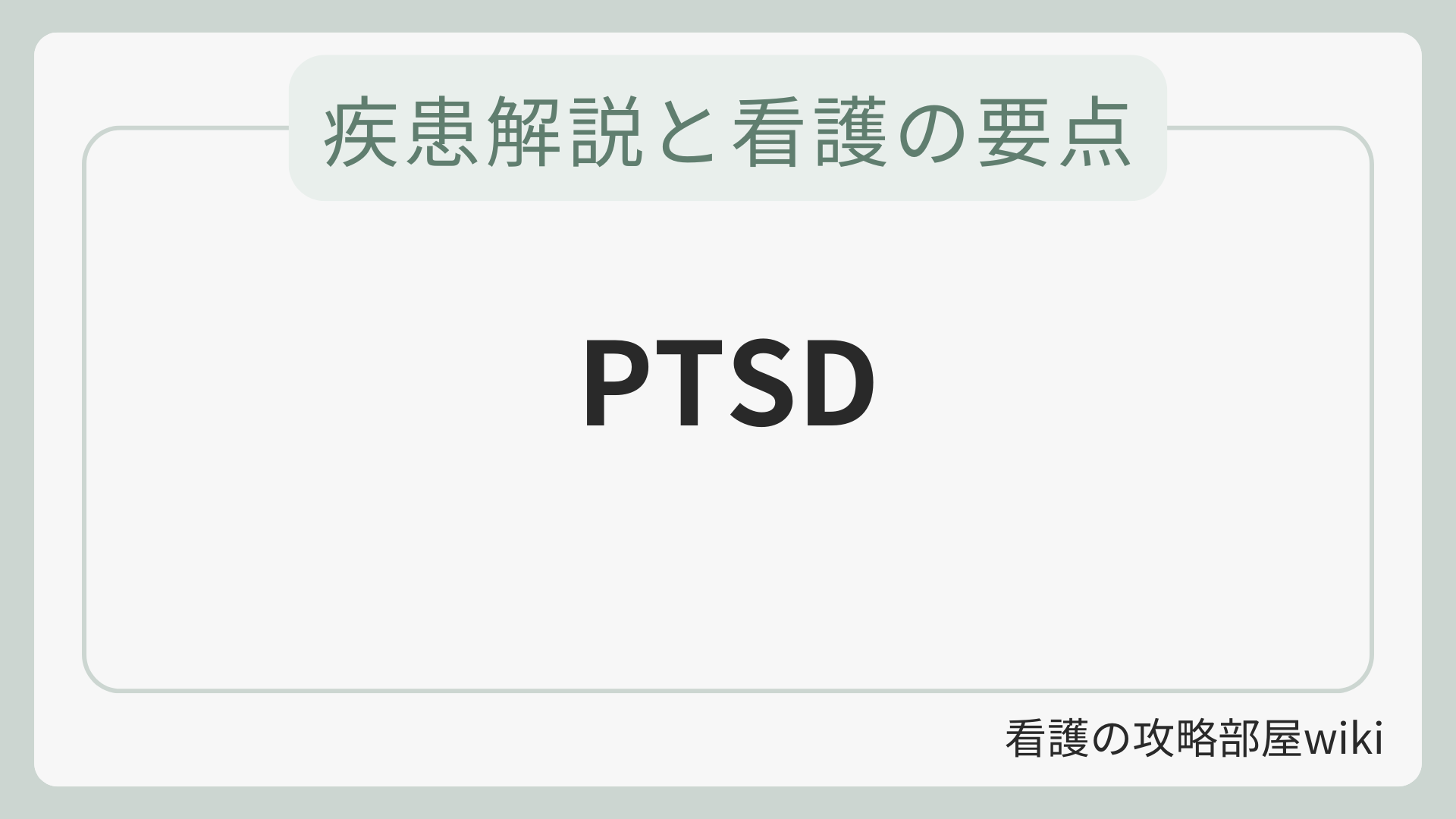
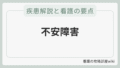
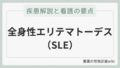
コメント