疾患概要
定義
中耳炎は中耳腔(鼓膜の奥の空間)に炎症が生じる疾患の総称です。急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎に大別され、それぞれ病態や治療法が異なります。急性中耳炎は細菌やウイルス感染により急激に発症し、滲出性中耳炎は耳管機能不全により中耳腔に滲出液が貯留する病態、慢性中耳炎は鼓膜穿孔や耳小骨の破壊を伴う慢性的な炎症状態を指します。
疫学
中耳炎は小児に最も多い疾患の一つで、特に2歳までに約80%の小児が少なくとも1回は急性中耳炎に罹患します。年間受診患者数は約240万人で、そのうち約70%が6歳未満の小児です。男児にやや多く、秋から冬にかけて上気道感染症の流行に伴い発症頻度が増加します。成人では慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎が問題となることが多く、難聴の重要な原因疾患となっています。
原因
急性中耳炎の主な原因菌は肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリスで、上気道感染症に続発して発症することが多いです。滲出性中耳炎は耳管機能不全が主因で、アデノイド肥大、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などが背景にあります。小児では耳管が成人に比べて短く、太く、水平に近いため感染が起こりやすくなっています。その他の要因として集団保育、受動喫煙、人工栄養、免疫不全などが挙げられます。
病態生理
中耳炎の発症には耳管機能が重要な役割を果たします。耳管は中耳腔と鼻咽腔をつなぐ管で、中耳腔の換気と排液を担っています。上気道感染により耳管粘膜が腫脹すると耳管機能が低下し、中耳腔の陰圧化が生じます。急性中耳炎では細菌が耳管を通って中耳腔に侵入し、炎症により膿性分泌物が産生されます。滲出性中耳炎では換気不良により中耳腔に滲出液が貯留し、難聴や耳閉感を引き起こします。炎症が持続すると鼓膜穿孔や耳小骨の破壊が生じ、慢性中耳炎に移行する可能性があります。
症状・診断・治療
症状
急性中耳炎では突然の激しい耳痛、発熱、耳閉感が特徴的です。乳幼児では耳痛を訴えることができないため、不機嫌、夜泣き、耳を触る、発熱などが主な症状となります。鼓膜穿孔が生じると耳痛は軽減しますが、耳漏(耳だれ)が出現します。滲出性中耳炎は無症状のことも多く、難聴、耳閉感、耳鳴りが主症状で、小児では呼びかけに反応が悪い、テレビの音を大きくするなどの行動変化で発見されることがあります。慢性中耳炎では持続性の耳漏、難聴、時として悪臭を伴います。
診断
診断は鼓膜所見と症状により行われます。耳鏡検査では急性中耳炎で鼓膜の発赤、腫脹、膨隆を認め、滲出性中耳炎では鼓膜の陥凹、滲出液による液面形成、鼓膜の色調変化を観察します。ティンパノメトリーは鼓膜の可動性を評価する検査で、滲出性中耳炎の診断に有用です。聴力検査では伝音難聴の程度を評価し、治療効果の判定にも用いられます。CT検査は慢性中耳炎における耳小骨の状態や真珠腫の診断に有用です。培養検査は耳漏がある場合に起炎菌の同定と薬剤感受性の確認のために実施されます。
治療
急性中耳炎の治療は重症度により決定されます。軽症例では症状観察を行い、中等症以上では抗菌薬治療を開始します。第一選択薬はアモキシシリンで、ペニシリンアレルギーがある場合はマクロライド系やセフェム系抗菌薬を使用します。解熱鎮痛薬による対症療法も併用します。滲出性中耳炎では保存的治療として鼻処置、去痰薬、抗アレルギー薬を使用し、3ヶ月以上改善しない場合は鼓膜切開や鼓膜チューブ留置術を考慮します。慢性中耳炎では鼓室形成術により鼓膜や耳小骨の再建を行い、聴力改善を図ります。真珠腫性中耳炎では手術による真珠腫摘出が必要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:中耳腔の炎症と圧迫に関連した耳痛
- 感覚知覚変調(聴覚):滲出液貯留や鼓膜損傷に関連した難聴
- 感染リスク状態:中耳炎の再発や合併症発症の危険性
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは患者・家族の中耳炎に対する理解度と治療への取り組み姿勢を評価します。特に小児では保護者の疾患理解と服薬管理能力、受診継続の意識が治療成果に大きく影響します。認知・知覚パターンでは聴力低下の程度と日常生活への影響を詳細にアセスメントします。小児では言語発達への影響、学習への支障、コミュニケーション能力の変化を観察します。活動・運動パターンでは耳痛や聴力低下による活動制限の程度を評価し、特に学童では学校生活への影響を把握します。
ヘンダーソン14基本的ニード
コミュニケーションをとるでは聴力低下による意思疎通の困難さを評価し、効果的なコミュニケーション方法を検討します。小児では言語習得への影響を継続的に観察し、必要に応じて言語聴覚士との連携を図ります。学習するでは難聴による学習への影響を評価し、教育現場との連携により適切な学習環境の整備を支援します。遊び、レクリエーション活動に参加するでは聴力低下による社会参加への影響を把握し、年齢に応じた遊びや活動への参加を支援します。
看護計画・介入の内容
- 疼痛管理:適切な鎮痛薬の使用指導、温罨法による疼痛緩和、安楽な体位の指導(患側を上にした側臥位)、疼痛の客観的評価(小児では行動観察による疼痛スケール使用)
- 服薬管理・指導:抗菌薬の正しい服薬方法と完遂の重要性説明、副作用の観察と対処法、服薬カレンダーや服薬確認表の活用、薬剤の保管方法指導
- 合併症予防・早期発見:症状悪化の兆候説明(耳痛増強、発熱、耳漏の性状変化)、定期受診の重要性説明、家庭での観察ポイント指導、緊急受診が必要な症状の説明
よくある疑問・Q&A
Q: 中耳炎は繰り返しやすいのでしょうか?
A: はい、特に小児では反復性中耳炎が起こりやすい傾向があります。6ヶ月間に3回以上、または1年間に4回以上の急性中耳炎を繰り返す場合を反復性中耳炎といいます。小児の耳管は成人に比べて短く太いため細菌が侵入しやすく、免疫機能も発達途中のため感染を起こしやすいのが原因です。予防策として手洗い・うがいの徹底、集団感染の回避、受動喫煙の防止、適切な鼻かみの方法習得などが重要です。
Q: プールに入ったり、お風呂に入ったりしても大丈夫ですか?
A: 鼓膜に穿孔がなければ、プールや入浴は基本的に問題ありません。中耳炎は中耳腔の感染であり、外から水が入ることで悪化することはありません。ただし、鼓膜穿孔がある場合や耳漏がある場合は、水が中耳腔に入る可能性があるため避ける必要があります。また、急性中耳炎の急性期で全身状態が悪い時期は、体力消耗を避けるため入浴を控えめにすることをお勧めします。
Q: 抗菌薬はどのくらいの期間飲む必要がありますか?
A: 急性中耳炎では一般的に5-7日間の抗菌薬治療が行われます。症状が改善しても処方された薬は最後まで服用することが重要です。途中で服薬を中止すると、細菌が完全に除菌されず再燃したり、薬剤耐性菌が出現する可能性があります。症状が改善しない場合や悪化する場合は、薬剤変更や治療期間の延長が必要になることもあるため、医師の指示に従って継続受診することが大切です。
Q: 難聴は治りますか?言葉の発達に影響はありませんか?
A: 急性中耳炎や滲出性中耳炎による難聴は多くの場合可逆性で、適切な治療により聴力は回復します。ただし、慢性中耳炎で鼓膜や耳小骨に不可逆的な変化が生じた場合は、永続的な難聴が残ることがあります。小児の場合、聴力低下が長期間続くと言語発達に影響を与える可能性があるため、早期診断・早期治療が重要です。定期的な聴力検査により聴力の回復を確認し、必要に応じて言語聴覚士による評価や指導を受けることをお勧めします。
まとめ
中耳炎は小児に最も多い感染症の一つであり、適切な診断と治療により良好な予後が期待できる疾患です。病態の中心は耳管機能不全と中耳腔の感染・炎症であり、年齢により症状の現れ方や治療方針が異なることが特徴です。
看護の要点は年齢に応じた症状観察と家族への教育・支援です。特に乳幼児では言葉で症状を訴えることができないため、行動変化や非言語的サインの観察が重要となります。疼痛管理では客観的な評価方法を用いて適切な鎮痛を図り、服薬管理では抗菌薬の完遂の重要性を家族に十分説明することが治療成功の鍵となります。
また、聴力への影響を考慮した継続的なフォローアップも重要な看護の視点です。特に小児では言語発達への影響を早期に発見し、適切な支援につなげることが将来の学習能力や社会適応に大きく影響します。
実習では患者さんの年齢と発達段階に応じたアプローチを心がけましょう。小児の場合は保護者との信頼関係の構築が治療継続の基盤となります。また、予防教育も重要で、手洗い・うがいの習慣化、適切な鼻かみの方法、受動喫煙の防止など、再発予防のための生活指導を通じて患者・家族の自己管理能力向上を支援することが、長期的な健康維持につながります。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
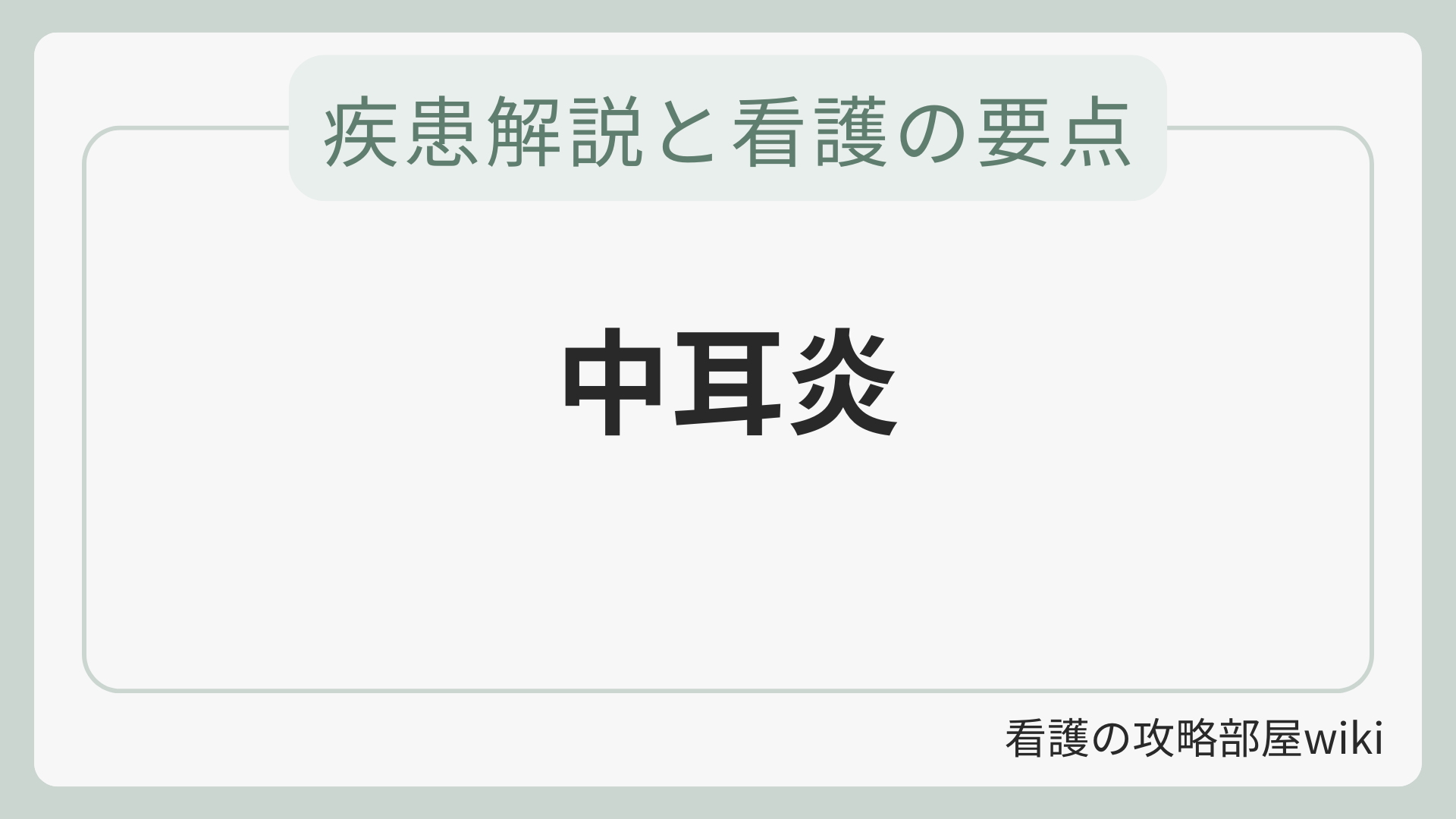
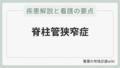
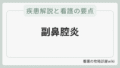
コメント