疾患概要
定義
脊柱管狭窄症は、加齢に伴う椎間板の変性、黄色靱帯の肥厚、椎間関節の変形などにより脊柱管が狭小化し、脊髄や神経根が圧迫されることで症状が生じる疾患です。最も頻度が高いのは腰部脊柱管狭窄症で、腰痛や下肢の痛み・痺れ、特徴的な間欠跛行を呈します。脊柱管の解剖学的狭窄があっても必ずしも症状を呈するとは限らず、症状の有無により治療方針が決定されます。
疫学
日本では約365万人が脊柱管狭窄症を患っているとされ、60歳以上の高齢者に多く発症します。男女差はあまりなく、年齢とともに有病率が増加し、70歳以上では約10-15%に認められます。高齢化社会の進展により患者数は増加傾向にあり、要介護状態の原因疾患としても重要な位置を占めています。発症部位は腰椎が最多で、次いで頸椎、胸椎の順となっています。
原因
主要な原因は加齢による脊椎の変性変化です。椎間板の変性により椎間腔が狭小化し、黄色靱帯が肥厚・内側に突出します。椎間関節の変形性変化により骨棘が形成され、脊柱管内腔が狭小化します。先天的に脊柱管が狭い場合(先天性脊柱管狭窄症)は、軽度の変性変化でも症状が出現しやすくなります。その他の原因として、腰椎すべり症、腰椎の不安定性、過去の手術による影響などがあります。危険因子には重労働、長時間の立位作業、肥満、喫煙などが挙げられます。
病態生理
脊柱管狭窄症では静的圧迫と動的圧迫が組み合わさって症状が生じます。立位や歩行時には腰椎が伸展し、既に狭小化した脊柱管がさらに狭くなり、神経組織への圧迫が増強されます。これにより神経根の血流障害が生じ、虚血性の痛みや痺れが出現します。前屈位では脊柱管が拡大するため症状が軽減し、これが間欠跛行の病態的基盤となります。馬尾神経や神経根の圧迫により、感覚障害、運動障害、膀胱直腸障害などの多彩な神経症状が生じる可能性があります。
症状・診断・治療
症状
最も特徴的な症状は神経性間欠跛行です。歩行開始時は問題ありませんが、一定距離(数百メートル程度)歩行すると下肢の痛みや痺れ、脱力感が出現し、座って休息すると症状が改善します。前屈位での症状軽減も特徴的で、ショッピングカートを押して歩く、自転車に乗るなどの前屈姿勢では症状が出にくくなります。腰痛は必発ではなく、下肢症状の方が主体となることが多いです。進行すると安静時にも下肢痛や痺れが持続し、膀胱直腸障害(排尿困難、便失禁)や下肢筋力低下が生じることもあります。
診断
診断は臨床症状と画像所見の総合的な評価により行われます。問診では間欠跛行の歩行距離、症状の性質、前屈位での症状軽減の有無を詳細に聴取します。理学所見では下肢筋力テスト、腱反射、知覚検査を行い、SLRテストは通常陰性です。画像診断ではMRIが第一選択で、脊柱管の狭窄程度、神経組織の圧迫状況を詳細に評価できます。CTミエログラフィーは骨性狭窄の評価に有用です。歩行負荷試験では症状誘発前後での神経症状の変化を客観的に評価できます。
治療
軽症例では保存的治療が基本となります。薬物療法ではプロスタグランジンE1製剤(リマプロストなど)が第一選択で、血流改善により間欠跛行の改善が期待できます。神経障害性疼痛に対してはプレガバリンやミロガバリンが使用されます。理学療法では脊柱管を拡大する前屈位での運動療法が中心となります。神経ブロック療法(硬膜外ブロック、神経根ブロック)は保存的治療抵抗例に考慮されます。手術適応は歩行距離が著しく短縮した場合、膀胱直腸障害がある場合、保存的治療で改善しない場合です。手術法には椎弓切除術、棘突起縦割式椎弓切除術などがあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 身体可動性障害:脊柱管狭窄による歩行能力の制限
- 活動耐性低下:間欠跛行に関連した活動制限と体力低下
- 転倒リスク状態:歩行時の下肢脱力と歩行不安定に関連した転倒の危険性
ゴードン機能的健康パターン
活動・運動パターンでは間欠跛行の詳細な評価が最も重要です。歩行可能距離、症状出現までの時間、休息による回復時間、前屈位での症状軽減効果を具体的に把握します。歩行補助具の使用状況や外出頻度の変化も重要な情報です。認知・知覚パターンでは下肢の痛みや痺れの部位、性質、程度を詳細にアセスメントし、疼痛が日常生活に与える影響を評価します。役割・関係パターンでは歩行能力の低下による社会活動への参加状況や家族関係への影響を把握し、孤立化の予防に注意を払います。
ヘンダーソン14基本的ニード
身体の位置を動かし、望ましい肢位を保持するでは、症状軽減のための適切な姿勢(前屈位)の指導と、安全な歩行方法の習得を支援します。歩行補助具(杖、歩行器、ショッピングカート)の適切な選択と使用方法の指導も重要です。遊び、レクリエーション活動に参加するでは歩行能力の低下による外出機会の減少や趣味活動への影響を評価し、QOL維持のための代替手段を検討します。正常に排泄するでは膀胱直腸障害の有無を継続的に観察し、排尿パターンの変化や便失禁の兆候を早期発見します。
看護計画・介入の内容
- 歩行能力の維持・改善:前屈位歩行の指導、適切な歩行補助具の選択と使用法指導、段階的な歩行訓練の実施、間欠跛行に対応した外出計画の立案
- 安全な生活環境の整備:転倒予防対策(手すりの設置、段差の解消、適切な照明)、緊急時対応方法の指導、家族への協力依頼
- 活動量維持と体力低下予防:症状に配慮した運動療法の指導、水中歩行や自転車運動の推奨、社会参加機会の維持支援、外出時の休憩場所の確保
よくある疑問・Q&A
Q: 脊柱管狭窄症は自然に治ることはありますか?
A: 脊柱管狭窄症は構造的な問題であるため、狭窄した脊柱管が自然に拡大することはありません。しかし、症状は必ずしも進行するとは限らず、適切な保存的治療により症状の改善や進行の抑制は可能です。血流改善薬や理学療法により間欠跛行の症状が軽減することも多く、手術を受けなくても日常生活に支障のない状態を維持できる患者さんも少なくありません。
Q: どのような歩き方をすれば症状が楽になりますか?
A: 前屈位での歩行が最も効果的です。具体的にはショッピングカートを押して歩く、杖をついて少し前かがみになる、手押し車(シルバーカー)を使用するなどの方法があります。階段昇降では上りの方が楽で、坂道では下りの方がつらくなる傾向があります。自転車は前屈位を保てるため、歩行よりも楽に移動できることが多いです。歩行時は無理をせず、症状が出現したら早めに休息を取ることが大切です。
Q: 手術を受ければ完全に治りますか?
A: 手術により脊柱管の狭窄は改善されますが、完全に元通りになるわけではありません。間欠跛行の改善率は約80-90%と高いですが、長期間の神経圧迫により生じた神経障害は完全には回復しないことがあります。また、加齢による変性は他の部位でも進行するため、将来的に隣接部位に狭窄が生じる可能性もあります。手術のメリットとリスクを十分に検討し、患者さんの症状の程度と生活への影響を総合的に判断して決定されます。
Q: 日常生活で気をつけることはありますか?
A: 無理な歩行を避け、症状に応じて歩行距離を調整することが重要です。外出時は休憩できる場所を事前に確認し、歩行補助具を適切に使用します。体重管理も腰椎への負担軽減のために大切です。前屈位を保てる運動(水中歩行、自転車、体操など)は症状の改善に効果的です。一方、腰を反らす動作や長時間の立位は症状を悪化させるため避けましょう。転倒予防のため、家の中の段差の解消や手すりの設置も重要です。
まとめ
脊柱管狭窄症は高齢者に多く発症する変性疾患であり、特徴的な間欠跛行により患者さんの活動範囲や生活の質に大きな影響を与えます。病態の本質は加齢による脊柱管の狭小化と神経組織の圧迫であり、前屈位での症状軽減という特徴的な所見が診断の重要な手がかりとなります。
看護の要点は歩行能力の維持と安全確保です。間欠跛行の程度を正確にアセスメントし、患者さんの症状に応じた個別的な歩行指導を行うことが重要です。前屈位歩行の指導や適切な歩行補助具の選択により、症状の軽減と歩行距離の延長が期待できます。
また、歩行能力の低下による社会的孤立の予防も重要な看護の視点です。外出機会の減少は体力低下や抑うつ状態を招きやすく、患者さんのQOL維持のためには積極的な社会参加の支援が必要です。症状に配慮した外出計画の立案や、水中歩行や自転車などの代替的な運動方法の提案により、活動的な生活の継続を支援します。
実習では患者さんの歩行パターンの観察と転倒リスクの評価に特に注意を払いましょう。間欠跛行の症状は個人差が大きく、患者さん自身の症状の訴えを丁寧に聞き取ることが適切な看護介入につながります。また、家族への指導も重要で、患者さんの症状への理解と適切な支援方法について説明し、安全で快適な在宅生活の継続を支援することが大切です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
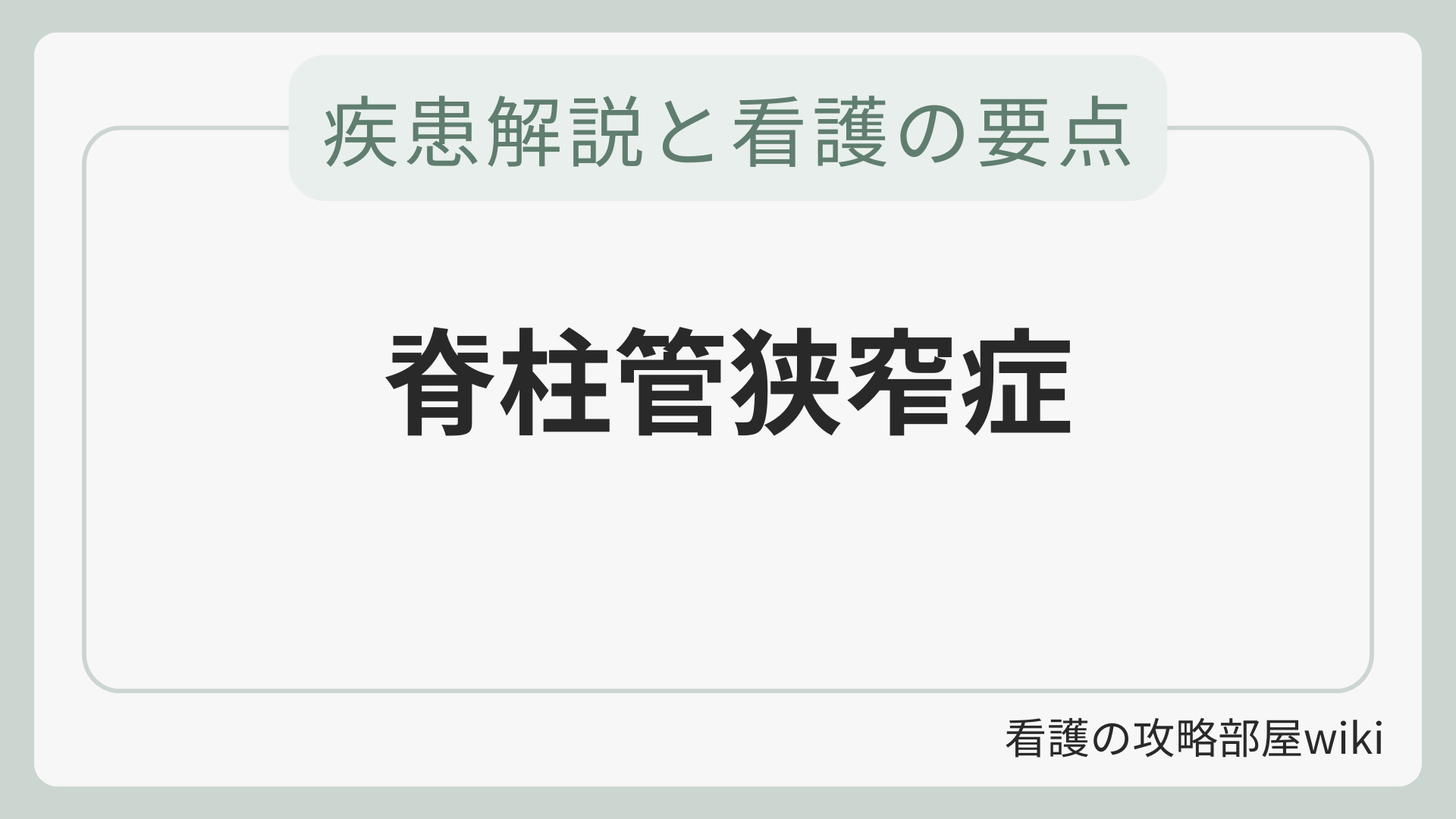
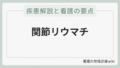
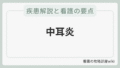
コメント