病態の概要
定義
難聴とは、音を感知する能力が低下した状態のことですね。聴力レベルが正常範囲を超えて悪化し、日常生活でのコミュニケーションに支障をきたす状態を指します。世界保健機関(WHO)では、良聴耳の平均聴力レベルが26dB以上の場合を難聴と定義しており、程度により軽度(26-40dB)、中等度(41-60dB)、高度(61-80dB)、重度(81dB以上)に分類されます。
原因
難聴の原因は、障害される部位によって大きく3つのタイプに分類されます。
伝音難聴の原因としては、外耳道の閉塞(耳垢栓塞、異物)、鼓膜穿孔、中耳炎(急性・慢性)、耳硬化症、先天性外耳道閉鎖などがあります。これらは音の伝達経路に問題が生じることで起こりますね。
感音難聴の原因には、加齢性難聴(老人性難聴)、騒音性難聴、突発性難聴、メニエール病、聴神経腫瘍、薬剤性難聴(アミノグリコシド系抗生物質、利尿薬など)、先天性難聴、髄膜炎後遺症などがあります。
混合性難聴は、伝音難聴と感音難聴が同時に存在する状態で、慢性中耳炎に加齢性変化が加わった場合などに見られます。
病態生理
正常な状態
正常な聴覚では、音波が外耳道を通って鼓膜を振動させ、中耳の耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)がその振動を増幅して内耳に伝えます。内耳の蝸牛では、有毛細胞が機械的振動を電気信号に変換し、聴神経を通って脳幹、視床を経て大脳皮質の聴覚野に達することで音として認識されるのです。
この過程で重要なのは、外耳から中耳での音の伝達と増幅、そして内耳での音の電気信号への変換ですね。
異常が起こる過程
伝音難聴では、外耳から中耳までの音の伝達経路に障害が生じます。鼓膜穿孔では振動の効率が低下し、中耳炎では炎症により耳小骨の動きが制限されます。音の増幅機能が低下するため、すべての周波数で均等に聴力が低下するのが特徴です。
感音難聴では、内耳の有毛細胞や聴神経の障害により起こります。加齢性難聴では、まず高音域の有毛細胞から徐々に変性し、「蝸牛基底回転から頂回転へ」と進行します。騒音性難聴では、過度の音刺激により有毛細胞が機械的に損傷されます。
薬剤性難聴では、アミノグリコシド系抗生物質などが内耳に蓄積し、有毛細胞を直接的に障害します。一度損傷された有毛細胞は再生しないため、感音難聴は基本的に不可逆的な変化となります。
突発性難聴では、ウイルス感染や血管障害により急激に内耳機能が低下し、多くの場合一側性に発症します。
症状
現れる症状とその理由
難聴の症状は、障害される部位や程度により異なった特徴を示します。
伝音難聴では、全周波数にわたって均等な聴力低下が起こります。患者さんは「音が小さく聞こえる」「テレビの音量を上げてしまう」といった症状を訴えますが、音の歪みは少ないため、大きな声で話せば比較的よく聞こえるのが特徴ですね。
感音難聴では、特に高音域の聴力低下が著明になります。これは「サ行」「タ行」「カ行」などの子音が聞き取りにくくなることを意味し、「聞こえるけれど何を言っているかわからない」という症状として現れます。また、補充現象と呼ばれる現象により、小さな音は聞こえないのに大きな音は異常にうるさく感じることがあります。
加齢性難聴では、段階的に症状が進行します。初期は高音域の軽度低下から始まり、徐々に会話音域にも影響が及びます。特に騒音下での聞き取りが困難になり、複数人での会話についていけないという症状が特徴的です。
突発性難聴では、多くの場合一側性の急激な聴力低下とともに、耳鳴りやめまい、耳閉感を伴います。
これらの聴覚症状により、二次的にコミュニケーション障害、社会的孤立、うつ状態などの心理社会的な問題が生じることも重要な症状の一つです。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
・コミュニケーション障害
・社会的孤立
・転倒リスク状態
・セルフケア不足
・活動耐性低下
・不安
・うつリスク状態
ゴードンのポイント
コミュニケーションパターンが最も重要で、患者さんの聞こえの程度、コミュニケーション方法の確認が必要です。筆談、手話、読唇術の習得度、補聴器の使用状況などを詳細にアセスメントします。
役割-関係パターンでは、家族や社会との関係性の変化を評価します。難聴により社会参加が制限され、家族内での役割変化や孤立感が生じていないかを確認することが重要ですね。
自己知覚-自己概念パターンでは、聴力低下による自信の喪失や劣等感、「聞こえない」ことへの恥ずかしさなどの心理的影響をアセスメントします。
ヘンダーソンのポイント
他者とのコミュニケーションが最も重要で、患者さんに適したコミュニケーション方法の確立と、相手に応じた関わり方の調整が必要です。
学習、発見、好奇心の充足では、難聴に関する正しい知識の提供、補聴器の適切な使用方法、コミュニケーション技術の習得支援が重要となります。
遊びや様々な形の娯楽では、聴覚に頼らない娯楽の提案や、聴覚障害者のコミュニティへの参加支援も考慮する必要がありますね。
看護計画・介入の内容
・効果的なコミュニケーション方法の確立
・筆談用具の準備と活用
・視覚的情報提供の充実
・補聴器の適切な使用と管理支援
・環境調整(騒音の軽減、照明の確保)
・家族への説明とコミュニケーション指導
・社会資源の情報提供
・心理的支援とカウンセリング
・転倒予防対策(めまいを伴う場合)
・定期的な聴力検査の勧奨
よくある疑問・Q&A
Q: 補聴器をつければ正常に聞こえるようになりますか?
A: 補聴器は音を大きくする装置であり、完全に正常な聴力を回復させるものではありません。特に感音難聴では、音の歪みや明瞭度の問題があるため、補聴器を装用しても「聞こえるが理解しにくい」状態が続くことがあります。しかし、適切に調整された補聴器は確実にコミュニケーション能力を向上させますね。
Q: 難聴は遺伝しますか?
A: 難聴には遺伝性のものと非遺伝性のものがあります。先天性難聴の約半数は遺伝的要因によるものですが、加齢性難聴や騒音性難聴などの後天性難聴は基本的に遺伝しません。ただし、加齢性難聴には遺伝的素因も関与するとされており、家族歴がある場合は早期からの予防が重要です。
Q: 難聴の患者さんとの会話で気をつけることはありますか?
A: 正面から話しかけ、口の動きが見えるようにすることが基本です。大声で話すよりも、はっきりとした発音でゆっくり話す方が効果的ですね。また、重要な内容は筆談を併用し、身振りや表情も活用して意思疎通を図りましょう。相手が聞き返したときは、同じ言葉を繰り返すのではなく、違う表現で伝え直すことも大切です。
Q: 一側性難聴の場合、日常生活でどんな困難がありますか?
A: 一側性難聴では、音源の方向がわからないため、車の接近音に気づかないなどの安全上の問題があります。また、騒音下での聞き取りが特に困難になり、会議や講演などで聞こえる側に座る必要があります。階段や段差でのバランス感覚にも影響することがあるため、転倒予防にも注意が必要ですね。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
看護過程の個別サポート
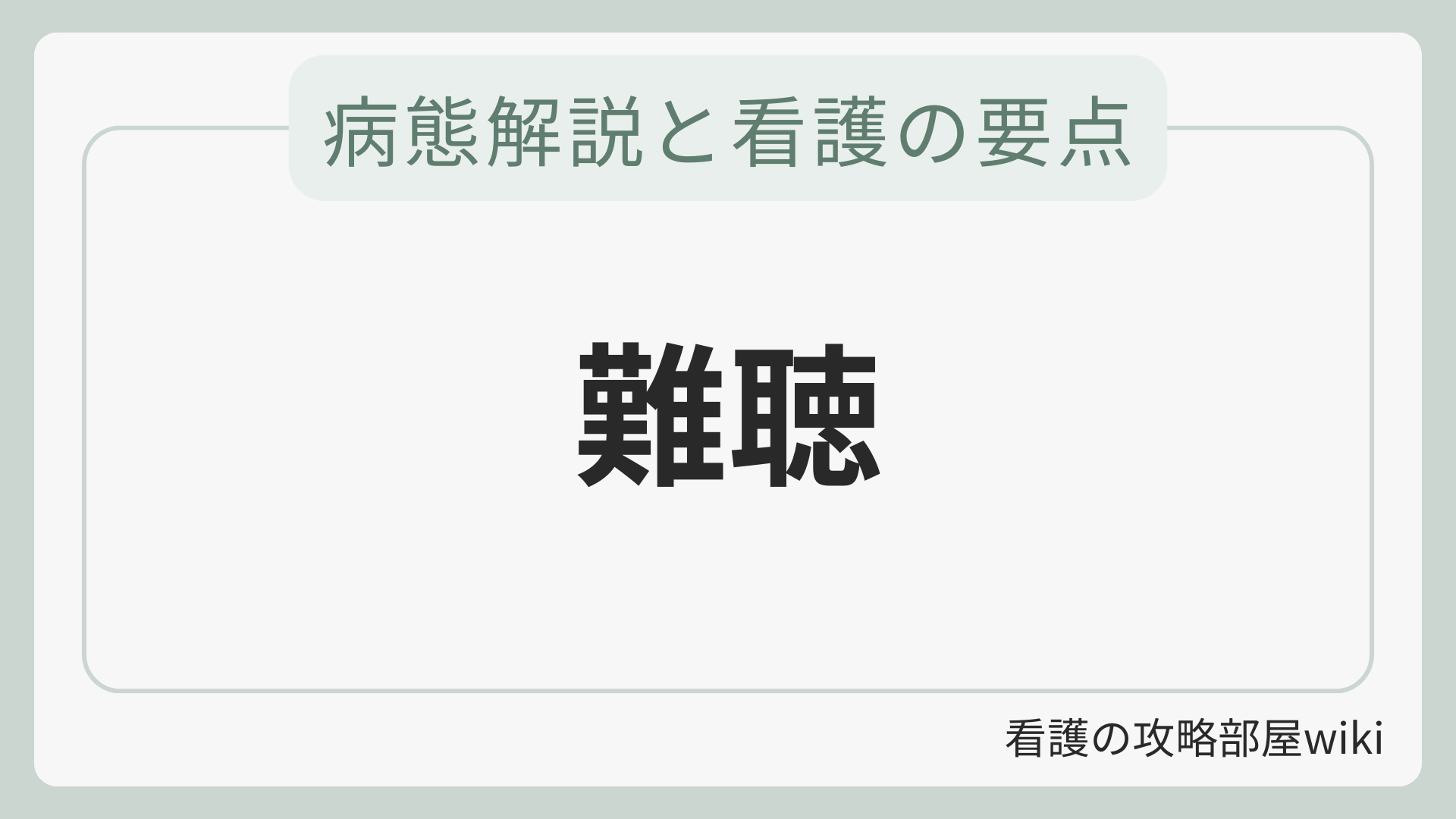
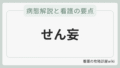
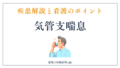
コメント