疾患概要
定義
結膜炎は、眼球表面とまぶたの内側を覆う薄い粘膜である結膜に炎症が生じる疾患です。原因により感染性結膜炎(細菌性、ウイルス性、真菌性)と非感染性結膜炎(アレルギー性、刺激性、ドライアイ関連など)に大別されます。最も頻度が高い眼科疾患の一つで、軽症から重症まで様々な程度があり、一部は強い感染力を持つため適切な診断と治療、感染対策が重要です。
疫学
結膜炎は年齢を問わず最も多い眼疾患で、眼科外来受診者の約30-40%を占めます。感染性結膜炎は秋から春にかけて多く、特に小児の集団発生が問題となります。ウイルス性結膜炎では流行性角結膜炎(アデノウイルス8型)、咽頭結膜熱(アデノウイルス3型)が代表的で、保育園や学校での集団感染がしばしば発生します。アレルギー性結膜炎は春から夏にかけてスギ花粉症に伴うものが多く、近年患者数が増加傾向にあります。細菌性結膜炎は年間を通じて発症し、特に高齢者や免疫力の低下した患者に多く見られます。
原因
ウイルス性結膜炎の原因として、アデノウイルス(最多)、エンテロウイルス、ヘルペスウイルスなどがあります。細菌性結膜炎では黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が主な原因菌です。アレルギー性結膜炎はスギ花粉、ヒノキ花粉、ダニ、ハウスダストなどのアレルゲンによる即時型過敏反応が原因です。刺激性結膜炎は化学物質、煙、風、紫外線などの物理的・化学的刺激により生じます。コンタクトレンズ関連結膜炎は不適切なレンズケアや長時間装用により発症します。
病態生理
結膜炎の病態は原因により異なります。感染性結膜炎では病原体の侵入により炎症反応が惹起され、血管透過性亢進により結膜の充血、浮腫、分泌物産生が生じます。ウイルス性では漿液性分泌物、細菌性では膿性分泌物が特徴的です。アレルギー性結膜炎ではⅠ型アレルギー反応により肥満細胞からヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、血管拡張、血管透過性亢進、知覚神経刺激による掻痒感が生じます。慢性結膜炎では持続的な刺激により結膜の肥厚、乳頭増殖、瘢痕形成が進行することがあります。
症状・診断・治療
症状
共通症状として結膜充血、異物感、流涙、眼脂(めやに)があります。ウイルス性結膜炎では水様性の眼脂、細菌性結膜炎では膿性の眼脂が特徴的です。アレルギー性結膜炎では強い掻痒感と水様性分泌物、くしゃみ、鼻汁などの鼻症状を伴うことが多いです。流行性角結膜炎では結膜の著明な充血・浮腫、眼瞼腫脹、耳前リンパ節腫脹を認め、角膜に点状表層角膜症や角膜上皮下混濁が生じると視力低下をきたします。急性出血性結膜炎では特徴的な結膜下出血を認めます。重症例では偽膜形成や角膜合併症を生じることがあります。
診断
診断は臨床症状と眼所見により行われます。細隙灯顕微鏡検査により結膜の充血程度、分泌物の性状、角膜の状態を詳細に観察します。細菌培養検査は重症例や治療抵抗例に実施し、起炎菌の同定と薬剤感受性を確認します。ウイルス抗原検査(迅速診断キット)によりアデノウイルスの検出が可能で、約15分で結果が得られます。アレルギー検査では血清特異的IgE抗体価の測定や皮膚反応テストにより原因アレルゲンを特定します。涙液分泌能検査(シルマーテスト)はドライアイの鑑別に有用です。細胞診では好酸球の増多によりアレルギー性結膜炎の診断に役立ちます。
治療
ウイルス性結膜炎は対症療法が基本で、人工涙液による洗眼、冷罨法、必要に応じて抗炎症薬(ステロイド点眼薬)を使用します。二次感染予防に抗菌薬点眼を併用することもあります。細菌性結膜炎では抗菌薬点眼が第一選択で、ニューキノロン系(レボフロキサシン、モキシフロキサシン)やアミノグリコシド系が使用されます。アレルギー性結膜炎では抗ヒスタミン薬点眼、肥満細胞安定薬点眼を使用し、重症例ではステロイド点眼薬や免疫抑制薬点眼(タクロリムス)も考慮されます。アレルゲン回避も重要な治療の一環です。人工涙液による洗眼は全ての病型で症状軽減に有効です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:結膜炎症に関連した眼痛・異物感・掻痒感
- 感染拡大リスク:感染性結膜炎の接触感染による感染拡大の危険性
- セルフケア不足:眼症状による日常生活動作の困難
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは患者・家族の結膜炎に対する理解度と感染予防に対する意識を評価します。特に感染性結膜炎では手指衛生の実践状況、タオルや枕カバーの共用回避、適切な点眼方法の習得が重要です。認知・知覚パターンでは眼症状(充血、異物感、掻痒感、視力への影響)の程度と日常生活への影響を詳細にアセスメントします。活動・運動パターンでは眼症状による外出や作業への制限、特に感染性結膜炎での学校・職場復帰時期について評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
清潔で健康な皮膚を維持し、衣服で身体を守るでは適切な眼部清拭方法と清潔保持を指導し、眼脂除去の適切な方法を習得させます。安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは感染拡散防止のための環境整備と家族への感染予防教育を行います。学習するでは疾患の理解促進、適切な点眼方法、症状悪化時の受診基準について指導します。働くこと、達成感を得るでは復職・復学時期の判断と職場・学校での感染予防対策について支援します。
看護計画・介入の内容
- 症状管理・緩和:適切な点眼方法の指導、冷罨法による症状軽減、眼脂除去の正しい方法指導、掻痒感に対する対処法(冷却、点眼)、人工涙液による洗眼指導
- 感染管理・予防:手指衛生の徹底指導、タオル・枕カバー・化粧品の個人使用徹底、適切なマスク着用、眼を触らない習慣の指導、家族・接触者への予防教育
- 治療継続・合併症予防:処方薬の正しい使用方法と期間の説明、症状改善後も治療完遂の重要性、角膜合併症の兆候説明、定期受診の必要性、復職・復学時期の判断基準説明
よくある疑問・Q&A
Q: 結膜炎はうつりますか?いつまで注意が必要ですか?
A: ウイルス性結膜炎と細菌性結膜炎は感染力があり、特にアデノウイルス結膜炎は非常に強い感染力を持ちます。感染期間はウイルス性で発症から約2週間、細菌性では抗菌薬治療開始から24-48時間で感染性がなくなります。アレルギー性結膜炎は感染しません。手指衛生の徹底、タオルや枕カバーの共用回避、眼を触った手で他の部位を触らないことが重要です。学校保健安全法では、ウイルス性結膜炎は医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止となります。
Q: 目薬はどのように使えばよいですか?コンタクトレンズは使用できますか?
A: 点眼前に必ず手を洗い、下まぶたを軽く引いて1滴点眼し、点眼後は軽く眼を閉じて1-2分間まばたきを控えます。複数の点眼薬を使用する場合は5分以上間隔をあけてください。点眼容器の先端が眼に触れないよう注意し、他人との共用は絶対に避けてください。コンタクトレンズは結膜炎治癒まで装用を中止し、特に感染性結膜炎では使用していたレンズとケースは廃棄することをお勧めします。
Q: 症状が改善したら治療をやめても大丈夫ですか?
A: 症状が改善しても処方された期間は治療を継続することが重要です。特に細菌性結膜炎では症状改善後も菌が残存している可能性があり、早期中止により再燃や薬剤耐性菌の出現リスクがあります。ウイルス性結膜炎では角膜合併症の予防のため、アレルギー性結膜炎では再燃防止のため、医師の指示に従って治療を完遂してください。症状が悪化した場合や新たな症状が出現した場合は早期に受診してください。
Q: アレルギー性結膜炎の予防法はありますか?
A: アレルゲン回避が最も重要な予防法です。花粉症の場合は花粉情報をチェックし、外出時はメガネやゴーグル、マスクを着用し、帰宅時は衣服や髪についた花粉を払い落とします。室内では空気清浄機の使用、こまめな掃除でダニやホコリを除去します。予防的治療として花粉飛散時期の2週間前から抗アレルギー薬の点眼を開始することで症状軽減が期待できます。規則正しい生活、十分な睡眠、ストレス管理により免疫機能を整えることも重要です。
まとめ
結膜炎は最も身近な眼疾患として、適切な診断と治療により速やかに改善が期待できる疾患です。しかし、原因により治療法や感染対策が大きく異なるため、正確な鑑別診断と個別的なアプローチが重要となります。
看護の要点は適切な症状管理と感染拡散防止です。特に感染性結膜炎では手指衛生の徹底と接触感染予防が地域の感染拡大防止に直結するため、患者・家族への教育指導が極めて重要となります。正しい点眼方法の指導は治療効果を最大化し、早期治癒につながります。
症状緩和では薬物療法に加えて、冷罨法や人工涙液による洗眼など、非薬物的アプローチも効果的です。患者さんの症状の程度と生活スタイルに応じて、実践可能な方法を提案することが大切です。
アレルギー性結膜炎では再発予防のためのアレルゲン回避と予防的治療の指導が重要で、患者さんが自己管理能力を向上させることで症状の軽減と生活の質の向上が期待できます。
合併症予防では特にウイルス性結膜炎における角膜合併症の早期発見が重要です。症状悪化の兆候や受診基準を明確に説明し、適切なタイミングでの医療機関受診を促すことが視機能保持につながります。
実習では患者さんの症状の詳細な観察と生活への影響の評価を重視しましょう。結膜炎は一見軽微な疾患に見えても、患者さんにとっては日常生活に大きな支障をきたす場合があります。共感的な態度で患者さんの不快症状に寄り添い、個別性のある看護介入を提供することで、患者さんの早期回復と再発防止に貢献していきましょう。また、感染管理の実践を通じて地域の健康維持にも貢献することが、看護職としての重要な役割です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
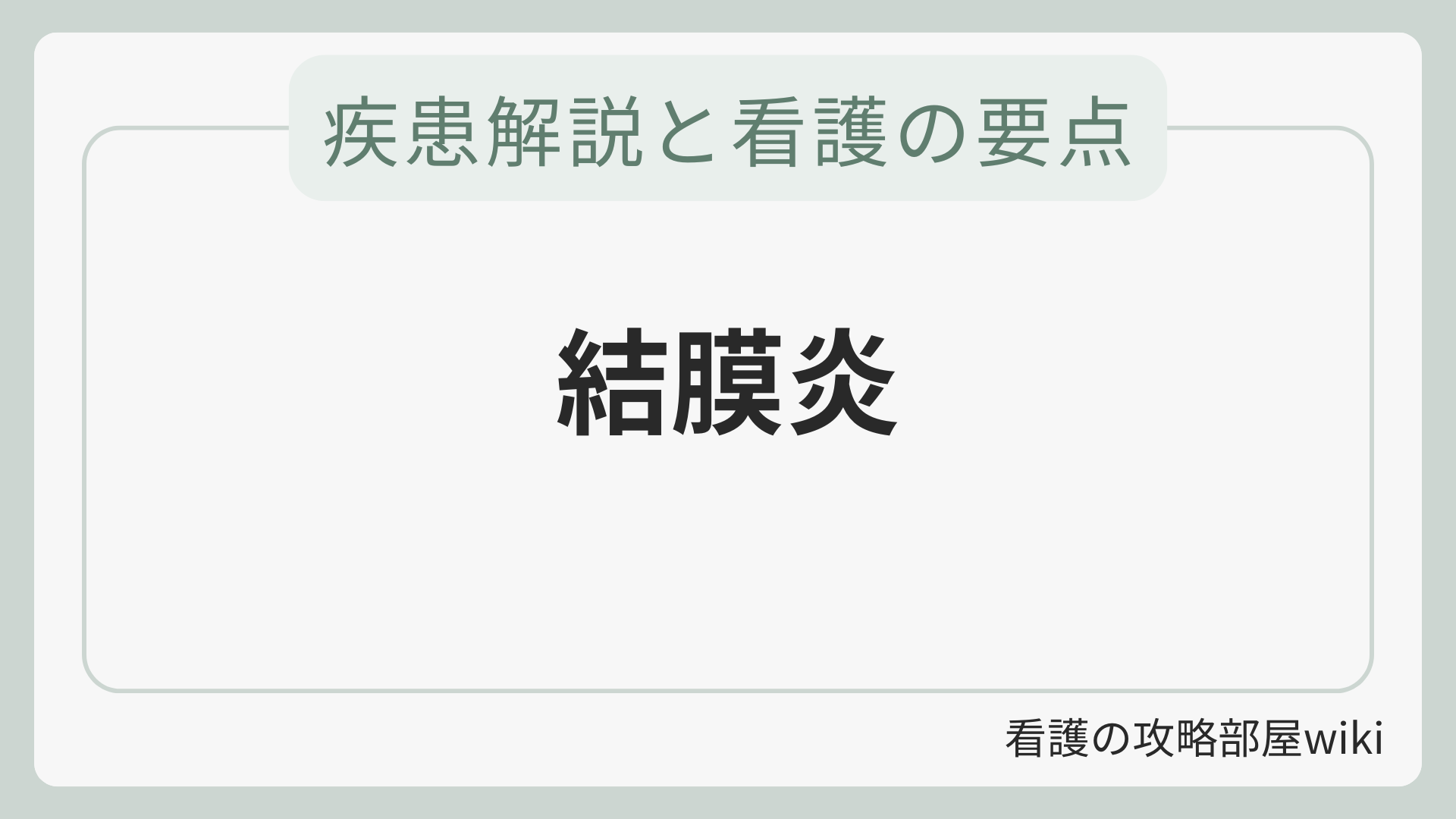
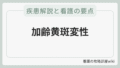
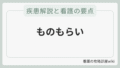
コメント