疾患概要
定義
ものもらいは、まぶた(眼瞼)に生じる炎症性疾患の総称で、医学的には麦粒腫と霰粒腫に分類されます。麦粒腫は眼瞼の脂腺や汗腺の急性化膿性炎症で、外麦粒腫(まつ毛の毛根部感染)と内麦粒腫(マイボーム腺感染)があります。霰粒腫はマイボーム腺の慢性炎症による無菌性の肉芽腫性病変です。「ものもらい」「めばちこ」「めんぼ」など地域により様々な呼び方があり、眼科外来で最も頻繁に遭遇する疾患の一つです。
疫学
ものもらいは年齢を問わず誰でも発症する可能性があり、特に20-40歳代に多く見られます。麦粒腫は急性発症で数日から1週間程度で軽快することが多く、霰粒腫は慢性経過をたどり数週間から数ヶ月持続することがあります。小児では外麦粒腫が多く、成人では内麦粒腫や霰粒腫の頻度が高くなります。眼瞼の不衛生、過労、ストレス、免疫力低下、アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎などがある場合に発症しやすく、反復することもあります。季節性はありませんが、乾燥する冬季にやや多い傾向があります。
原因
麦粒腫の原因菌は黄色ブドウ球菌が最多で、表皮ブドウ球菌、プロピオニバクテリウム・アクネスなども関与します。これらの常在菌が眼瞼の腺組織に侵入して化膿性炎症を引き起こします。霰粒腫は感染ではなく、マイボーム腺の分泌物が詰まることで生じる無菌性炎症です。誘因として眼瞼の不潔、目をこする習慣、化粧品による刺激、コンタクトレンズの不適切な使用、ドライアイ、アトピー性皮膚炎、ホルモンバランスの変化(妊娠、月経など)、過労、ストレス、免疫力低下などが挙げられます。
病態生理
外麦粒腫ではまつ毛の毛根部にあるモル腺やツァイス腺に細菌感染が生じ、内麦粒腫では眼瞼結膜側のマイボーム腺に感染が生じます。感染により急性炎症反応が惹起され、血管透過性亢進、白血球浸潤、膿瘍形成が起こります。霰粒腫ではマイボーム腺の分泌管が詰まり、分泌物が貯留して腺房が拡張します。貯留した脂質に対する異物反応として慢性肉芽腫性炎症が生じ、類上皮細胞、巨細胞、リンパ球の浸潤を認めます。二次感染が生じると急性炎症症状が出現し、感染性霰粒腫となります。
症状・診断・治療
症状
麦粒腫では局所の発赤、腫脹、疼痛、熱感が特徴的で、圧痛を伴う硬結を触知します。外麦粒腫では眼瞼縁(まつ毛の根元)、内麦粒腫では眼瞼結膜面に炎症を認めます。進行すると膿瘍を形成し、自然排膿することがあります。霰粒腫では無痛性の硬結が特徴で、眼瞼に可動性のある硬いしこりを触知します。炎症症状は軽微ですが、大きくなると眼瞼下垂や異物感を生じることがあります。感染性霰粒腫では急性炎症症状が加わり、発赤、腫脹、疼痛が出現します。いずれも片眼性に発症することが多く、両眼同時発症は稀です。
診断
診断は臨床症状と眼瞼所見により行われます。麦粒腫では急性炎症所見(発赤、腫脹、疼痛、熱感)と圧痛を伴う硬結の存在により診断します。霰粒腫では無痛性で可動性のある硬結の存在が診断の決め手となります。鑑別診断として眼瞼腫瘍(脂腺癌、基底細胞癌など)、眼瞼膿瘍、蜂窩織炎などがあります。細菌培養検査は重症例や治療抵抗例に実施し、起炎菌の同定と薬剤感受性を確認します。病理組織検査は悪性腫瘍との鑑別が必要な場合や、反復する霰粒腫で実施されることがあります。
治療
麦粒腫では抗菌薬治療が基本で、軽症例では抗菌薬点眼(フルオロキノロン系、クロラムフェニコール)、中等症以上では抗菌薬内服(セフェム系、マクロライド系)を併用します。温罨法により血行促進と排膿促進を図り、切開排膿が必要な場合もあります。霰粒腫では温罨法と眼瞼マッサージが基本治療で、ステロイド局所注射(トリアムシノロン)や摘出術が考慮されます。感染性霰粒腫では抗菌薬治療を併用します。予防として眼瞼の清潔保持、目をこすらない、適切な化粧品使用、コンタクトレンズの適切なケアが重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:眼瞼の炎症に関連した局所疼痛
- 感染リスク状態:眼瞼の細菌感染による周囲組織への感染拡大の危険性
- ボディイメージの混乱:眼瞼腫脹による外見の変化への困惑
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは患者の眼瞼衛生に対する認識と実践状況を評価します。手洗い習慣、目をこする頻度、化粧品の使用方法、コンタクトレンズのケア状況を詳細に把握し、再発予防のための生活習慣改善点を特定します。認知・知覚パターンでは疼痛の程度と性質、異物感の有無、視力への影響を評価します。自己概念・自己認識パターンでは眼瞼腫脹による外見の変化が自己イメージや社会活動に与える影響を把握し、心理的サポートの必要性を評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
清潔で健康な皮膚を維持し、衣服で身体を守るでは眼瞼の適切な清拭方法と清潔保持を指導し、化粧品使用時の注意点を説明します。安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは手指衛生の徹底と眼部への接触感染予防を指導します。身だしなみを整えるでは眼瞼腫脹時の化粧方法や外出時の対処法について支援し、社会生活への影響を最小限に抑えます。
看護計画・介入の内容
- 症状管理・疼痛緩和:適切な温罨法の指導(清潔なタオルで10-15分間、1日3-4回)、鎮痛薬の適切な使用、冷罨法による腫脹軽減、眼瞼マッサージ法の指導(霰粒腫の場合)
- 治療継続・薬物管理:抗菌薬点眼・内服の正しい使用方法、治療期間の遵守、副作用の観察と対処法、症状改善後も処方期間完遂の重要性説明
- 予防教育・生活指導:手指衛生の徹底、目をこすらない習慣づけ、適切な化粧品選択と使用法、コンタクトレンズの正しいケア方法、眼瞼清拭の適切な方法、再発予防のための生活習慣改善
よくある疑問・Q&A
Q: ものもらいはうつりますか?人にうつさないようにするにはどうすればよいですか?
A: 麦粒腫は基本的に他人にうつりません。原因菌は皮膚の常在菌で、健康な人では感染力は弱く、直接的な感染の心配はほとんどありません。ただし、手指衛生を徹底し、タオルや化粧品の共用は避けてください。霰粒腫は感染症ではないため全く感染しません。念のため、目を触った後は手を洗い、患部を触らないよう注意することで、家族への感染リスクをさらに軽減できます。普通の社会生活は問題なく継続できます。
Q: 温めるのと冷やすの、どちらが良いのでしょうか?
A: 急性期の痛みや腫れが強い時は冷罨法、慢性期や膿を出したい時は温罨法が効果的です。麦粒腫の初期で痛みが強い場合は冷やすことで炎症を抑制し、痛みを軽減できます。症状が安定してきたら温罨法に切り替え、血行促進により自然排膿を促進します。霰粒腫では温罨法が基本で、1日3-4回、清潔なタオルで10-15分間温めることで分泌物の排出を促進し、症状改善につながります。熱すぎると火傷の危険があるため、適温での実施が重要です。
Q: 市販の目薬を使っても大丈夫ですか?病院に行く必要がありますか?
A: 軽症の場合は抗菌作用のある市販点眼薬で改善することもありますが、数日で改善しない場合や症状が悪化する場合は受診をお勧めします。特に発熱、眼瞼全体の腫脹、視力低下、強い痛みがある場合は早期受診が必要です。霰粒腫では点眼薬だけでは改善しにくく、専門的な治療が必要になることが多いです。反復する場合や大きなしこりがある場合も、悪性腫瘍との鑑別のため眼科受診をお勧めします。
Q: 化粧はしても大丈夫ですか?コンタクトレンズは使用できますか?
A: 症状が軽微で痛みがなければ軽い化粧は可能ですが、患部への直接的な刺激は避けてください。アイメイクは控えめにし、クレンジングは優しく行います。コンタクトレンズは炎症が完全に治癒するまで装用を中止することをお勧めします。特に内麦粒腫や感染性霰粒腫では、レンズが感染を悪化させたり、逆に感染したりする可能性があります。治療期間中は眼鏡を使用し、治癒後にコンタクトレンズを再開してください。新しいレンズとケースの使用をお勧めします。
まとめ
ものもらいは身近で頻度の高い眼瞼疾患として、適切な診断と治療により比較的短期間での治癒が期待できる疾患です。麦粒腫と霰粒腫の鑑別は治療方針に直結するため、症状の特徴を正確に把握することが重要となります。
看護の要点は適切な症状管理と再発予防のための生活指導です。特に温罨法の正しい実施方法は症状改善に直結する重要な看護介入であり、患者さんが安全かつ効果的に実施できるよう具体的な指導が必要です。
薬物療法の継続支援では、症状改善後も処方された期間は治療を完遂することの重要性を説明し、再発や耐性菌出現の予防を図ります。また、適切な点眼方法の指導により治療効果を最大化することができます。
予防教育は再発防止の観点から極めて重要です。手指衛生の徹底、眼瞼の清潔保持、目をこすらない習慣の確立により、多くの症例で再発を予防できます。特に化粧品やコンタクトレンズ使用者には、適切な使用方法とケア方法の指導が必要です。
心理的支援では、眼瞼腫脹による外見の変化に対する患者さんの不安や困惑に共感的に対応し、短期間で改善する疾患であることを説明して安心感を提供することが大切です。
実習では患者さんの症状の詳細な観察と生活習慣の評価を重視しましょう。ものもらいは軽微な疾患と思われがちですが、患者さんにとっては痛みや外見の変化により日常生活に支障をきたす場合があります。共感的な態度で患者さんの症状に寄り添い、個別性のある看護介入を提供することで、患者さんの早期回復と再発防止に貢献していきましょう。また、正しい知識の提供により、患者さんが安心して治療に取り組めるよう支援することが看護の重要な役割です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
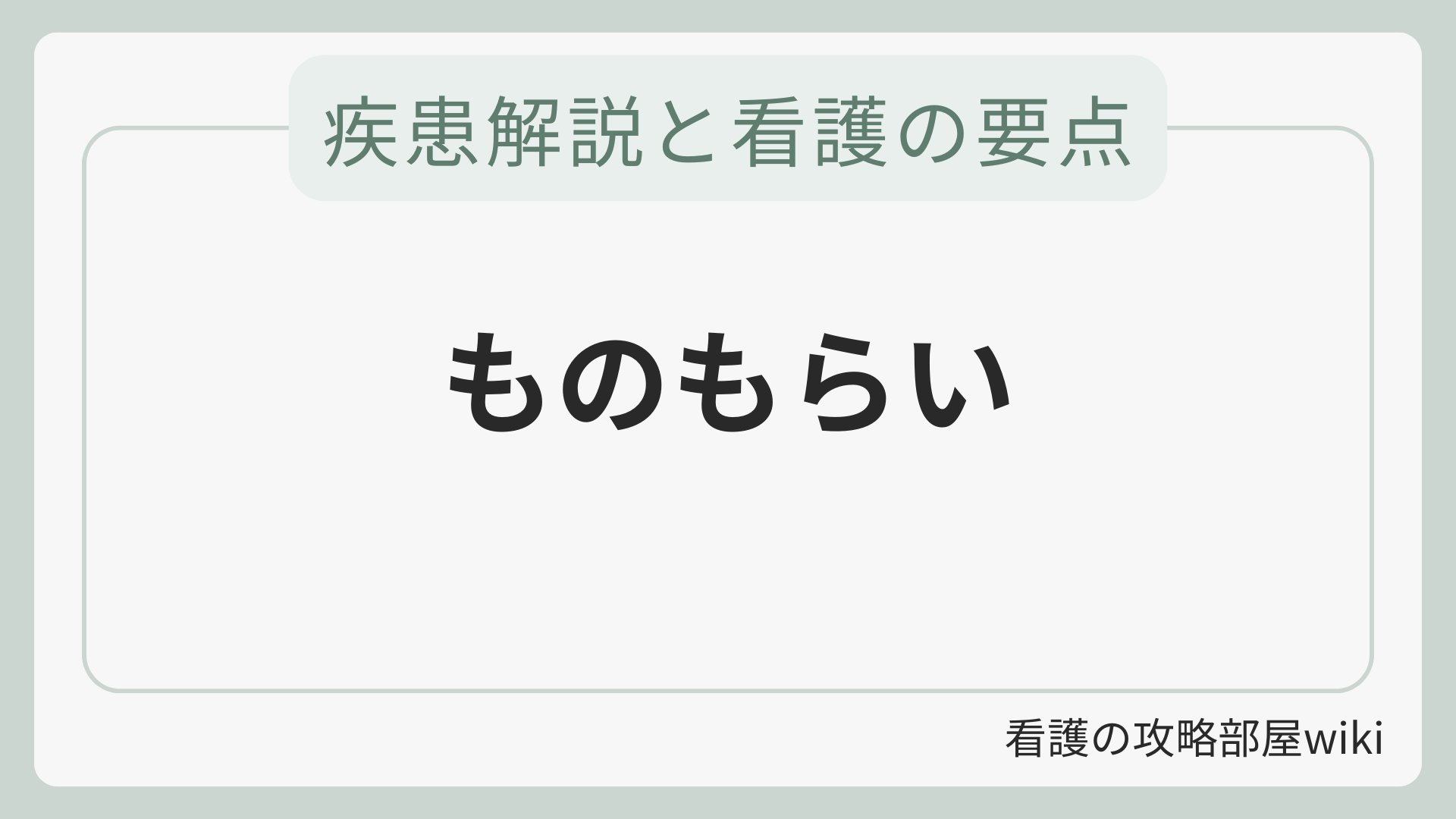
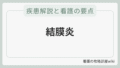
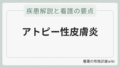
コメント