疾患概要
定義
双極性障害(bipolar disorder)は、躁病エピソードまたは軽躁病エピソードとうつ病エピソードを繰り返す慢性の精神疾患です。以前は「躁うつ病」と呼ばれていました。双極Ⅰ型障害では躁病エピソードが必須で、双極Ⅱ型障害では軽躁病エピソードとうつ病エピソードの組み合わせを特徴とします。気分の極端な変動により日常生活や社会機能に著しい障害をきたしますが、適切な治療により症状の安定化と社会復帰が可能な疾患です。
疫学
双極性障害の生涯有病率は約1-2%で、日本では約100万人が罹患していると推定されます。双極Ⅰ型障害の有病率は約0.4-1.6%、双極Ⅱ型障害は約0.3-4.8%とされています。発症年齢は10歳代後半から20歳代前半で、うつ病より早期に発症する傾向があります。男女差はほとんどないとされていますが、双極Ⅱ型障害では女性にやや多い傾向があります。家族歴がある場合の発症リスクは一般人口の10-20倍と高く、遺伝的要因の関与が強く示唆されています。初回エピソードはうつ病エピソードから始まることが多く、診断までに平均10年程度を要することが問題となっています。
原因
双極性障害の原因は多因子性で、遺伝的要因、生物学的要因、心理社会的要因が複合的に関与します。遺伝的要因では複数の遺伝子が関与し、一卵性双生児の一致率は約80%と高値を示します。生物学的要因では神経伝達物質(ドパミン、ノルアドレナリン、セロトニン)の機能異常、概日リズムの障害、視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)の異常が関与します。心理社会的要因では重大なライフイベント、慢性ストレス、薬物使用、睡眠リズムの乱れが気分エピソードの誘因となります。
病態生理
双極性障害の病態生理は完全には解明されていませんが、神経伝達物質系の異常が中核となります。躁病エピソードではドパミン系の過活動により興奮、多幸感、誇大感が生じ、ノルアドレナリン系の亢進により活動性増加、睡眠欲求減少が出現します。うつ病エピソードではセロトニン系の機能低下により抑うつ気分、興味の喪失が生じます。概日リズムの障害により睡眠覚醒周期が乱れ、気分エピソードの引き金となります。脳画像研究では前頭前野、海馬、扁桃体の構造・機能異常が報告され、気分調節や認知機能の障害に関与するとされています。
症状・診断・治療
症状
躁病エピソードでは気分の異常な高揚または易怒性が1週間以上持続し、誇大感、睡眠欲求の減少(3時間以下でも元気)、多弁、観念奔逸(考えが次々と浮かぶ)、注意転導性、活動性増加、快楽的活動への過度の参加(浪費、性的逸脱行為)が出現します。軽躁病エピソードは躁病と同様の症状が4日間以上持続しますが、入院を要するほど重篤ではない状態です。うつ病エピソードでは抑うつ気分、興味・関心の喪失、思考制止、精神運動制止または焦燥、希死念慮などが2週間以上持続します。混合エピソードでは躁病症状とうつ病症状が同時に出現し、急速交代型では年4回以上の気分エピソードを繰り返します。
診断
診断はDSM-5やICD-11の診断基準に基づいて行われます。双極Ⅰ型障害では1回以上の躁病エピソードがあれば診断され、双極Ⅱ型障害では1回以上の軽躁病エピソードと1回以上のうつ病エピソードが必要です。気分症状評価尺度としてYMRS(ヤング躁病評価尺度)、MADRS(モンゴメリー・アスベルグうつ病評価尺度)が用いられます。鑑別診断では統合失調症、物質使用障害、器質性精神障害、人格障害などを除外します。うつ病との鑑別は重要で、家族歴、発症年齢、エピソードの特徴、治療反応などを総合的に評価します。MDQ(Mood Disorder Questionnaire)などのスクリーニング尺度も有用です。
治療
治療は気分安定薬による薬物療法が中核となります。リチウムは躁病・うつ病の両方に効果があり、自殺予防効果も確立されています。抗てんかん薬ではバルプロ酸、カルバマゼピン、ラモトリギンが使用されます。非定型抗精神病薬(オランザピン、クエチアピン、アリピプラゾールなど)も躁病エピソードに有効です。急性期治療では躁病に対してリチウム、バルプロ酸、非定型抗精神病薬を、うつ病に対してクエチアピン、ラモトリギンを使用します。維持療法では再発予防のため長期間の気分安定薬投与を行います。心理社会的治療として心理教育、認知行動療法、対人関係・社会リズム療法、家族療法が有効です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 思考過程の変調:躁病エピソードにおける判断力低下と衝動的行動
- 自傷・他害リスク状態:躁病時の攻撃性とうつ病時の自殺念慮
- 社会的相互作用の障害:気分の極端な変動による対人関係の困難
ゴードン機能的健康パターン
認知・知覚パターンでは気分エピソードによる認知機能の変化を評価します。躁病時の判断力低下、集中力散漫、現実検討能力の低下、うつ病時の思考制止、集中困難、決断困難を詳細にアセスメントします。睡眠・休息パターンでは睡眠パターンの変化が気分エピソードの前兆や誘因となるため継続的に評価します。活動・運動パターンでは躁病時の過活動とうつ病時の活動性低下の程度を把握し、対処・ストレス耐性パターンでは気分変動への対処能力と病識の程度を評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
眠る・休むでは規則正しい睡眠リズムの維持が気分安定化に重要であり、睡眠パターンの変化を早期に発見し対応します。安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは躁病時の衝動的行動や危険行動、うつ病時の自殺リスクを評価し安全確保を図ります。働くこと、達成感を得るでは気分変動が職業機能に与える影響を評価し、段階的な社会復帰を支援します。
看護計画・介入の内容
- 気分変動の観察・記録:日々の気分変動のモニタリング、前兆症状の早期発見、気分チャートの活用、睡眠パターンの記録、服薬状況の確認
- 安全管理・危機介入:躁病時の衝動的行動の予防、環境調整(刺激の軽減)、うつ病時の自殺リスク評価、危険物の管理、24時間の見守り体制
- 治療継続・服薬支援:気分安定薬の重要性説明、副作用の観察と対処、血中濃度モニタリングの必要性説明、服薬自己管理能力の向上、定期受診の動機づけ
よくある疑問・Q&A
Q: 双極性障害は治る病気ですか?普通の生活を送ることはできますか?
A: 双極性障害は慢性疾患ですが、適切な治療により症状の安定化と充実した社会生活は十分可能です。約70-80%の患者さんで気分安定薬により再発予防が可能で、多くの方が働いたり家庭を持ったりしています。重要なのは継続的な治療と生活リズムの管理です。早期発見・早期治療により予後は格段に改善し、心理教育により自己管理能力を身につけることで、気分エピソードの頻度や重症度を大幅に減らすことができます。完治は困難ですが、寛解状態を長期間維持している方も多くいます。
Q: 気分安定薬は一生飲み続けなければならないのでしょうか?
A: 双極性障害では再発率が非常に高い(治療中断後1年以内に約50%が再発)ため、長期間の維持療法が重要です。多くの場合、数年から一生涯の服薬が必要になります。ただし、長期間安定している場合や軽症例では、医師と慎重に相談しながら減薬を検討することもあります。自己判断での中断は極めて危険で、重篤な躁病やうつ病エピソードの再発リスクが高まります。薬物療法は「松葉杖」のようなもので、生活の質を保つために必要な治療と考えてください。副作用が心配な場合は薬剤変更により改善できることも多いです。
Q: 躁状態の時は調子が良いと感じます。なぜ治療が必要なのでしょうか?
A: 躁状態では確かに気分が良く、エネルギッシュに感じられますが、実際には判断力が著しく低下しており、様々な問題を引き起こします。経済的損失(浪費、投資の失敗)、人間関係の悪化(攻撃的言動、不適切な行動)、社会的信用の失墜(職場でのトラブル)、法的問題(交通違反、暴行)などのリスクがあります。また、躁状態の後には必ずうつ状態が訪れ、躁状態での行動を激しく後悔することになります。予防的治療により、これらの問題を避けながら安定した生活を送ることができます。軽躁状態を適度に保つことは可能ですが、完全な躁状態は危険です。
Q: 家族はどのように接すればよいでしょうか?気分の変動にどう対応すればよいですか?
A: 家族の理解と適切な関わりは治療成功の鍵となります。躁状態では①刺激を避ける(静かな環境、人数制限)、②論争を避ける(正論で説得しようとしない)、③危険な行動を止める(車の運転、大きな買い物の阻止)、④医療機関との連携が重要です。うつ状態では①批判せず支える、②小さな改善を評価する、③自殺の危険を見逃さない、④専門的治療を促すことが大切です。家族自身のケアも重要で、家族会への参加やカウンセリングにより支援を受けてください。境界設定(許容できない行動への明確な対応)も必要で、愛情と毅然とした態度のバランスが重要です。
まとめ
双極性障害は気分の極端な変動を特徴とする慢性精神疾患として、患者さんとその家族の生活に大きな影響を与えます。しかし、適切な治療と管理により症状の安定化と充実した社会生活は十分に可能な疾患です。
看護の要点は気分変動の継続的観察と安全管理です。躁病エピソードでは判断力低下による危険行動、うつ病エピソードでは自殺リスクが最重要課題となります。気分チャートの活用により、患者さん自身が気分変動のパターンを理解し、早期警告サインを認識できるよう支援することが重要です。
薬物療法の支援では、気分安定薬の重要性と長期間の服薬継続の必要性について患者・家族に十分説明し、治療アドヒアランスの向上を図ります。血中濃度モニタリングや副作用管理も重要な看護の役割です。
生活リズムの管理は気分安定化の基盤であり、特に睡眠リズムの維持は気分エピソード予防に極めて重要です。ストレス管理、規則正しい生活、適度な運動などの生活指導を通じて、患者さんの自己管理能力向上を支援します。
心理教育では、疾患の理解促進、服薬の重要性、再発の兆候、対処方法について具体的に指導し、患者さんが疾患とうまく付き合っていけるよう支援します。家族教育も同様に重要で、適切な関わり方と支援方法について指導します。
社会復帰支援では、気分変動による職業機能への影響を考慮し、段階的なアプローチで社会復帰を促進します。障害者支援制度の活用やピアサポートの紹介により、包括的な支援体制を構築することが大切です。
実習では患者さんの個別性を重視し、気分エピソードの特徴や経過を詳細にアセスメントすることが重要です。双極性障害は波のある疾患ですが、適切な治療により多くの方が安定した生活を送っています。希望を持って治療に取り組めるよう、患者さんとその家族を支援し、その人らしい充実した人生の実現に向けて包括的なケアを提供していきましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
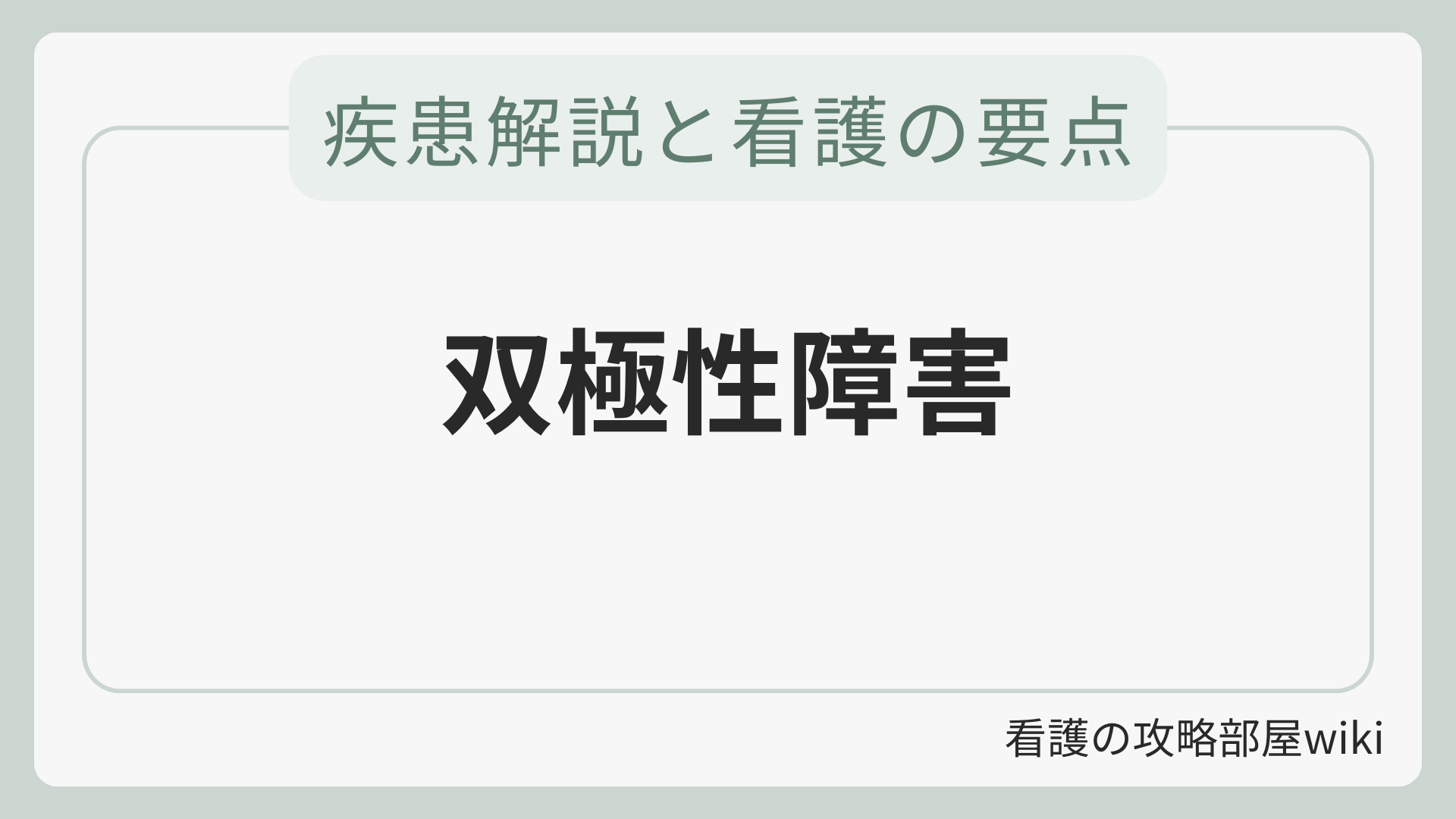
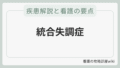
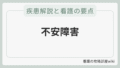
コメント