疾患概要
定義
統合失調症(schizophrenia)は、思考、感情、行動の統合性が失われる慢性の精神疾患です。幻覚、妄想などの陽性症状と、意欲低下、感情の平板化などの陰性症状を主とし、認知機能障害も伴います。青年期から成人早期に発症することが多く、慢性の経過をたどりますが、適切な治療により症状の安定化と社会復帰が可能な疾患です。病名は「精神の分裂」を意味するものではなく、心の様々な機能がまとまりにくくなる状態を表しています。
疫学
統合失調症の生涯有病率は約1%で、世界共通の疾患です。日本では約80万人が罹患していると推定されます。発症年齢は男性で20歳前後、女性で20歳代後半にピークがあり、男性の方がやや早期発症の傾向があります。有病率に男女差はないとされていますが、経過や症状に性差が認められます。遺伝的要因が関与し、一般人口の発症リスクを1%とすると、両親のうち一方が統合失調症の場合約10%、一卵性双生児では約50%の発症率となります。都市部での発症率がやや高く、移民や社会経済的地位の低い集団での有病率が高いことが知られています。
原因
統合失調症の原因は完全には解明されていませんが、多因子性の疾患とされています。生物学的要因では遺伝的素因、神経発達異常、ドパミン系の機能異常が関与します。心理社会的要因ではストレス、薬物使用(大麻、覚醒剤)、社会的孤立、移住などが発症の誘因となります。神経発達仮説では胎児期から青年期にかけての脳発達過程での異常が病態の基盤にあるとされ、ドパミン仮説では中脳辺縁系のドパミン過活動が陽性症状を、中脳皮質系のドパミン低下が陰性症状を引き起こすとされています。
病態生理
統合失調症の病態生理はドパミン仮説が中心的理論です。中脳辺縁系(側坐核、扁桃体)でのドパミン過活動により陽性症状(幻覚、妄想)が生じ、中脳皮質系(前頭前野)でのドパミン低下により陰性症状(意欲低下、感情の平板化)と認知機能障害が出現します。NMDA受容体仮説では、NMDA型グルタミン酸受容体の機能低下により、ドパミン系の調節異常が生じるとされています。神経病理学的変化として脳室拡大、海馬萎縮、前頭前野の血流低下、白質の異常などが認められ、認知機能障害の基盤となっています。
症状・診断・治療
症状
症状は陽性症状、陰性症状、認知機能障害に分類されます。陽性症状では幻聴(命令幻聴、評価幻聴、対話幻聴)、幻視、被害妄想、関係妄想、誇大妄想、思考奪取・注入・伝播、作為体験などが出現します。陰性症状では意欲・自発性の低下、感情の平板化、社会的引きこもり、快感消失、会話の貧困が認められます。認知機能障害では注意・集中力の低下、記憶力低下、実行機能障害、社会認知の障害が生じます。解体症状として思考の解体、行動の解体、カタトニア症状も認められることがあります。
診断
診断はDSM-5やICD-11の診断基準に基づいて行われます。5つの主要症状(妄想、幻覚、解体した思考、著しく解体したまたは異常な運動行動、陰性症状)のうち2つ以上が1ヶ月以上持続し、そのうち少なくとも1つは妄想、幻覚、解体した思考のいずれかである必要があります。社会的・職業的機能の著しい低下が6ヶ月以上継続することも診断要件です。鑑別診断では物質使用障害、器質性精神障害、双極性障害、うつ病の精神病性特徴、妄想性障害などを除外する必要があります。症状評価尺度としてPANSS(陽性・陰性症状評価尺度)、BPRS(簡易精神症状評価尺度)が用いられます。
治療
治療は抗精神病薬による薬物療法が中核となります。第一世代抗精神病薬(定型抗精神病薬)は主にドパミンD2受容体を遮断し、第二世代抗精神病薬(非定型抗精神病薬)はドパミンとセロトニン受容体に作用します。非定型抗精神病薬は陰性症状に対する効果と錐体外路副作用の軽減が期待できます。維持治療では再発予防のため長期間の服薬が必要で、LAI(長時間作用型注射薬)により服薬アドヒアランスの向上を図ります。心理社会的治療として社会技能訓練(SST)、認知行動療法、心理教育、就労支援、家族支援を組み合わせて行います。包括的地域精神保健により在宅生活の支援を行います。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 思考過程の変調:妄想・幻覚による現実検討能力の低下
- 社会的相互作用の障害:陰性症状による対人関係の困難
- 服薬遵守困難:病識の欠如と副作用に関連した治療中断リスク
ゴードン機能的健康パターン
認知・知覚パターンでは幻覚・妄想の内容と程度、現実検討能力、病識の有無を詳細にアセスメントします。命令幻聴の有無は特に重要で、自殺や他害のリスクに直結します。役割・関係パターンでは対人関係能力、社会的機能の低下程度、家族関係の状況を評価します。価値・信念パターンでは妄想内容が宗教的・哲学的信念とどのように関連しているかを把握し、対処・ストレス耐性パターンでは症状に対する対処能力、ストレス要因、支援システムを評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
コミュニケーションをとるでは思考の解体による意思疎通の困難さを評価し、効果的なコミュニケーション方法を検討します。学習するでは認知機能障害が学習能力に与える影響を評価し、疾患や治療に関する理解度を把握します。働くこと、達成感を得るでは職業機能の低下程度を評価し、段階的な社会復帰の可能性を検討します。遊び、レクリエーション活動に参加するでは興味・関心の変化、活動参加能力を評価し、生活の質向上を支援します。
看護計画・介入の内容
- 症状管理・現実見当識支援:幻覚・妄想への対応(否定せず、現実を提示)、安全で構造化された環境の提供、現実見当識の維持・改善、認知機能障害への配慮(情報提示の工夫)
- 服薬管理・治療継続支援:服薬の重要性と効果の説明、副作用の観察と対処、服薬自己管理能力の向上、LAI導入時の支援、定期受診の動機づけ
- 社会復帰・機能改善支援:段階的な活動拡大、社会技能訓練への参加促進、日常生活技能の維持・向上、就労・就学支援、家族関係の調整、地域資源の活用
よくある疑問・Q&A
Q: 統合失調症は治る病気ですか?普通の生活を送ることはできますか?
A: 統合失調症は慢性疾患ですが、適切な治療により症状の安定化と社会復帰は十分可能です。約25%の患者さんはほぼ完全に回復し、約50%は社会復帰が可能な状態まで改善します。重要なのは継続的な治療と心理社会的支援です。薬物療法により症状をコントロールしながら、社会技能訓練や就労支援を受けることで、働いたり家庭を持ったりする普通の生活を送っている方も多くいます。早期発見・早期治療が予後改善に重要で、現在の治療法は以前より格段に進歩しています。
Q: 薬を一生飲み続けなければならないのでしょうか?副作用が心配です
A: 統合失調症では再発予防のため長期間の服薬が重要ですが、必ずしも一生というわけではありません。症状が安定している場合は、医師と相談しながら慎重な減薬を検討することもあります。ただし、自己判断での中断は再発リスクが高いため危険です。副作用については、現在の薬物は以前より副作用が少なくなっており、錐体外路症状、体重増加、糖尿病などに注意しながら、個々の患者さんに最適な薬剤を選択します。LAI(注射薬)により服薬負担を軽減することも可能です。副作用が出現した場合は薬剤変更により改善できることも多いです。
Q: 家族はどのように接すればよいでしょうか?症状への対応方法を教えてください
A: 家族の理解と適切な関わりは回復に重要です。基本原則として、①批判的にならない、②過度に刺激しない、③患者さんのペースを尊重することが大切です。妄想や幻覚に対しては否定も肯定もせず、「そう感じるのですね」と受け止め、現実を穏やかに提示します。激しく否定したり論破しようとすると関係が悪化します。陰性症状(意欲低下)に対しては、「怠けている」と誤解せず、病気の症状として理解し、小さな改善を評価します。家族教育プログラムへの参加により、疾患の理解と対応方法を学ぶことができます。
Q: 社会復帰はできますか?どのような支援がありますか?
A: 統合失調症の方への社会復帰支援は充実しており、多くの方が働いたり学んだりしています。段階的なアプローチとして、まず生活訓練施設で日常生活技能を身につけ、就労移行支援事業所で職業訓練を受け、就労継続支援事業所や一般企業での就労を目指します。障害者手帳の取得により、雇用促進、交通費割引、税制優遇などの支援を受けられます。地域活動支援センター、グループホーム、訪問看護などの地域資源も利用できます。社会技能訓練(SST)により対人関係技能を向上させ、ピアサポート(同じ病気を持つ仲間の支援)も効果的です。個々の能力と希望に応じた支援を受けることで、充実した社会生活を送ることができます。
まとめ
統合失調症は思考、感情、行動の統合性が失われる慢性精神疾患として、患者さんとその家族の人生に大きな影響を与えます。しかし、現在の治療法の進歩により、症状の安定化と社会復帰は十分に可能な疾患となっています。
看護の要点は症状に対する適切な理解と対応、治療継続への支援、社会復帰の促進です。幻覚・妄想への対応では、患者さんの体験を否定せず受け止めながら、現実見当識を支援することが重要です。陰性症状に対しては、「怠け」ではなく病気の症状として理解し、患者さんのペースを尊重した関わりが必要です。
服薬管理は統合失調症治療の根幹であり、病識の向上と服薬アドヒアランスの改善が重要な看護目標となります。副作用への適切な対応と、LAIなどの選択肢についても患者さんと一緒に検討することが大切です。
心理社会的支援では、社会技能訓練、認知機能リハビリテーション、就労支援など、包括的なアプローチにより患者さんの社会復帰を促進します。ストレングスモデルの視点から、患者さんの持つ力や可能性に焦点を当てた支援を行うことが重要です。
家族支援も不可欠な要素です。家族の負担軽減と疾患理解の促進により、患者さんにとって支援的な環境を整備することが回復に大きく寄与します。
実習では患者さんの個別性と尊厳を重視し、偏見を持たずに関わることが重要です。統合失調症は特別な病気ではなく、適切な治療と支援により多くの方が充実した人生を送っています。希望を持って治療に取り組めるよう、患者さんとその家族を支援し、その人らしい生活の実現に向けて包括的なケアを提供していきましょう。統合失調症の方々が地域で安心して暮らせる社会の実現に向けて、看護職の果たす役割は極めて重要です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
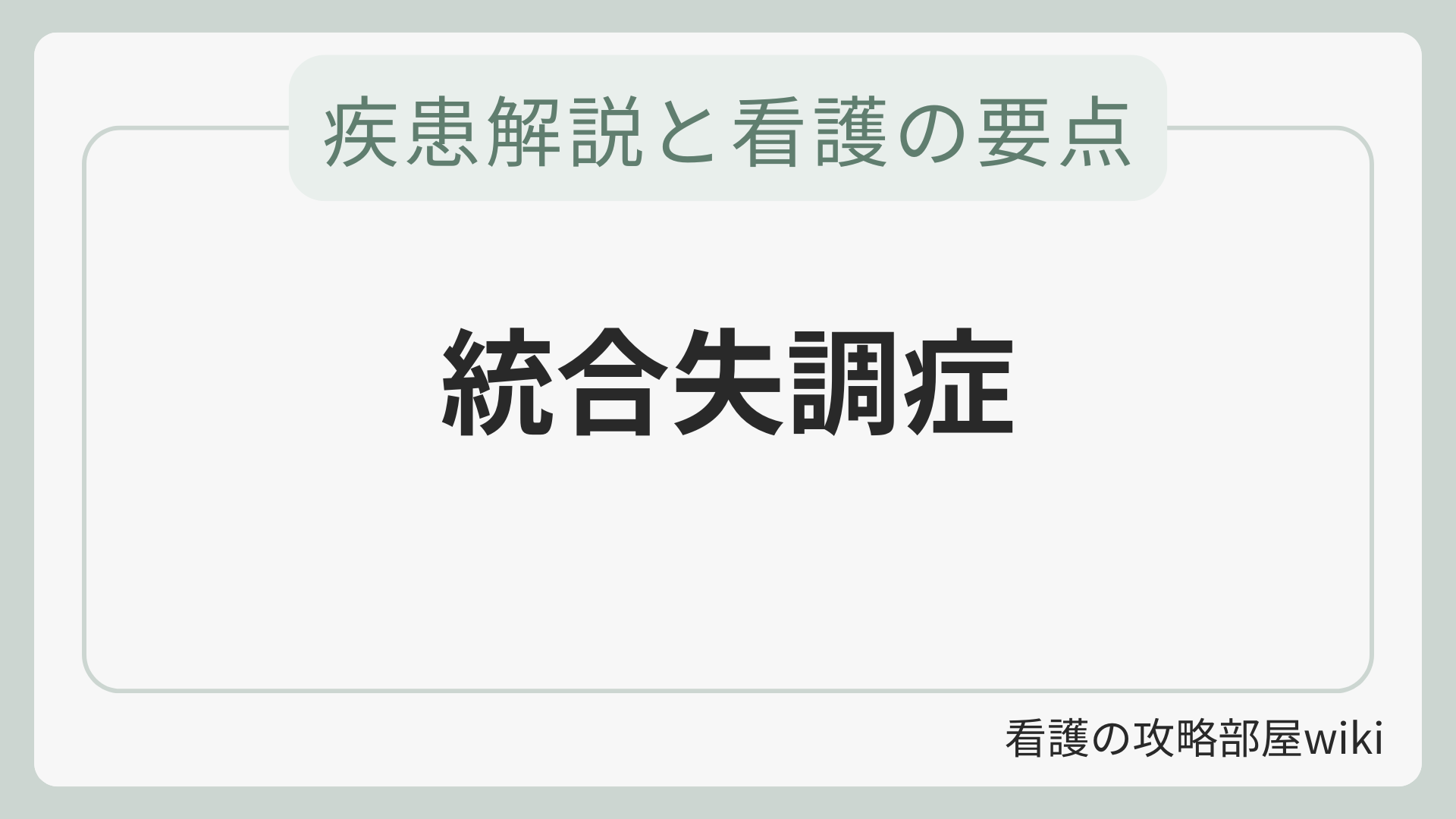
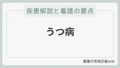
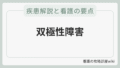
コメント