本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
A氏、60歳、女性、身長158cm、体重52kg。家族構成は夫(62歳・会社員)と長女(32歳・既婚で別居)の3人家族で、キーパーソンは夫である。職業は事務職であったが、現在は休職中である。性格は真面目で几帳面、周囲への気遣いが強く、自分の感情を表に出すことが苦手なタイプである。感染症はなく、アレルギーも特に認められない。認知力は保たれており、見当識や記憶力に問題はない。
病名
うつ病(中等度うつ病エピソード)
既往歴と治療状況
既往歴として5年前に甲状腺機能低下症の診断を受け、レボチロキシンナトリウムによる治療を継続している。3年前には不眠症状に対して睡眠薬の処方を受けていたが、当時は精神科受診には至らなかった。今回、約6か月前から抑うつ気分や意欲低下が出現し、心療内科での外来治療を開始したが、症状の改善が乏しく、自殺念慮の出現もみられたため、精神科病棟への入院となった。
入院から現在までの情報
入院は9月24日で、入院時は表情が乏しく、声も小さく、視線を合わせることが少なかった。日中もベッド上で過ごすことが多く、食事や入浴などの日常生活動作にも意欲が低下していた。入院後は抗うつ薬の調整と休息を中心とした治療が開始され、看護師による傾聴や支持的な関わりが継続的に行われた。入院1週間後頃から徐々に表情に変化がみられ始め、看護師との会話時に軽く笑顔を見せることもあった。入院2週間目には日中の離床時間が増加し、病棟内の散歩やデイルームでの活動にも参加するようになった。現在は自殺念慮は消失し、抑うつ気分はやや軽減しているが、依然として意欲の低下や集中力の減退が残存している。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは体温36.4℃、血圧118/72mmHg、脈拍76回/分・整、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)であった。現在のバイタルサインは体温36.6℃、血圧114/68mmHg、脈拍72回/分・整、呼吸数14回/分、SpO2 98%(室内気)であり、安定している。
食事と嚥下状態
入院前は食欲不振があり、1日2食程度で摂取量も少なかった。体重は2か月で約4kg減少していた。現在は病院食(常食・1800kcal)を提供されており、摂取量は7割程度まで回復している。嚥下状態に問題はなく、むせや咳き込みもみられない。喫煙歴はなく、飲酒は以前は晩酌程度であったが、半年前から飲酒はしていない。
排泄
入院前は便秘傾向があり、3~4日に1回の排便であった。現在も便秘傾向は続いており、2~3日に1回の排便で、硬便である。必要時に酸化マグネシウムを使用している。排尿は日中5~6回、夜間1回程度で、自立している。尿失禁や残尿感などの訴えはない。
睡眠
入院前は入眠困難と中途覚醒が著明で、睡眠時間は3~4時間程度であった。日中の倦怠感も強かった。現在は睡眠薬の調整により、入眠はスムーズになり、睡眠時間は6時間程度確保できるようになった。しかし、依然として中途覚醒が1~2回あり、熟眠感は乏しい状態である。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼があるが、眼鏡使用で日常生活に支障はない。聴力も正常で補聴器の使用はない。知覚に異常は認められず、痛みや痺れなどの訴えもない。コミュニケーションは日本語で可能であるが、声が小さく、話す内容も簡潔で、自発的な発言は少ない。看護師からの問いかけには応答するが、会話を続けることに疲労を感じやすい様子がみられる。信仰は特にない。
動作状況
歩行は自立しており、杖や歩行器の使用はない。移乗や排泄、入浴、衣類の着脱もすべて自立している。しかし、動作が緩慢で、一つ一つの動作に時間がかかる傾向がある。転倒歴はないが、注意力や集中力の低下があるため、転倒リスクには留意が必要である。
内服中の薬
- エスシタロプラムシュウ酸塩 10mg 1日1回 朝食後
- ミルタザピン 15mg 1日1回 就寝前
- クエチアピンフマル酸塩 25mg 1日1回 就寝前(不眠時)
- レボチロキシンナトリウム 50μg 1日1回 朝食後
- 酸化マグネシウム 500mg 1日2回 朝夕食後(便秘時)
検査データ
| 項目 | 入院時(9月24日) | 現在(10月10日) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 6,200/μL | 6,500/μL | 3,500~9,000 |
| RBC | 420万/μL | 430万/μL | 380~500万 |
| Hb | 12.8g/dL | 13.1g/dL | 11.5~15.0 |
| Ht | 38.5% | 39.2% | 35~45 |
| Plt | 25.0万/μL | 24.8万/μL | 13~37万 |
| TP | 7.0g/dL | 7.2g/dL | 6.5~8.0 |
| Alb | 4.0g/dL | 4.2g/dL | 3.8~5.2 |
| AST | 22IU/L | 20IU/L | 10~40 |
| ALT | 18IU/L | 16IU/L | 5~40 |
| BUN | 15mg/dL | 14mg/dL | 8~20 |
| Cr | 0.7mg/dL | 0.7mg/dL | 0.5~1.0 |
| Na | 140mEq/L | 141mEq/L | 135~145 |
| K | 4.1mEq/L | 4.0mEq/L | 3.5~5.0 |
| Cl | 102mEq/L | 103mEq/L | 98~108 |
| TSH | 2.8μU/mL | 2.5μU/mL | 0.5~5.0 |
| FT4 | 1.1ng/dL | 1.2ng/dL | 0.9~1.7 |
服薬は看護師管理で実施されており、確実な内服が確保されている。
今後の治療方針と医師の指示
今後は抗うつ薬の効果を評価しながら、必要に応じて薬剤の調整を行う方針である。精神療法として、認知行動療法を導入し、否定的な思考パターンの修正を図る予定である。また、作業療法への参加を通じて、日中の活動量を増やし、生活リズムの確立を目指す。退院に向けては、外泊訓練を実施し、自宅での生活に段階的に移行していく計画である。医師からは無理な活動を避け、十分な休息を取りながら、できることから少しずつ取り組むようにとの指示がある。
本人と家族の想いと言動
A氏は「自分は何もできない人間だと思う。家族に迷惑ばかりかけて申し訳ない」と自責的な発言が多く、自己評価が著しく低下している。また「以前のように仕事ができるか不安だ。このまま良くならないのではないか」と将来への不安も強い。一方で「少しずつだけど、前よりは気持ちが楽になってきた気がする」とも話しており、わずかながら改善の実感も得られている。
夫は「妻がこんなに苦しんでいるのに、何もしてあげられなかった。もっと早く気づいてあげるべきだった」と後悔の念を抱いている。また「家に帰ってきたときに、また同じようになってしまわないか心配だ。どうサポートすればいいのか教えてほしい」と退院後の生活への不安を表出している。長女は週1回程度面会に訪れており、「母が元気になって、また一緒に買い物に行けるようになったらいいな」と話している。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏がうつ病という疾患をどのように認識し、どのような健康管理行動をとってきたか、また今後の治療への姿勢を評価することが重要です。疾患の受容や治療への協力度は、回復過程に大きく影響します。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患発症前の健康管理行動
A氏は5年前に甲状腺機能低下症と診断され、レボチロキシンナトリウムによる治療を継続してきました。また3年前には不眠症状に対して睡眠薬の処方を受けていますが、当時は精神科受診には至りませんでした。この経過を踏まえると、身体的な不調に対しては医療機関を受診し、処方された薬を継続する健康管理行動がとれていたことが読み取れます。一方で、精神的な症状については受診のハードルが高かったことも考えられ、その点を踏まえてアセスメントを進めるとよいでしょう。
疾患に対する認識と受け止め方
「自分は何もできない人間だと思う」「以前のように仕事ができるか不安だ」「このまま良くならないのではないか」というA氏の発言からは、自己評価の著しい低下と、将来への強い悲観的な見通しが読み取れます。これはうつ病の症状そのものでもありますが、疾患についての理解が十分でない可能性も考慮する必要があります。疾患の理解度や治療への期待感をアセスメントし、どのような情報提供や支援が必要かを考えることが重要です。
治療への姿勢と服薬管理
約6か月前から心療内科で外来治療を開始していたものの症状の改善が乏しく、自殺念慮の出現により入院に至ったという経過があります。外来での治療が奏効しなかった要因として、服薬アドヒアランスの問題や生活環境の影響なども考えられます。入院後は看護師管理のもとで確実な内服が確保されており、抗うつ薬の効果が適切に評価できる状況にあることを踏まえて記述するとよいでしょう。
既往歴とリスク因子
甲状腺機能低下症の既往があり、現在も治療継続中です。甲状腺機能の異常はうつ症状を引き起こすことがあるため、入院時および現在のTSH、FT4の値が基準値内であることは重要な情報です。また喫煙歴はなく、飲酒も半年前から中止していることから、これらのリスク因子は現在ありません。アレルギーや感染症もないため、治療上の制約は少ない状態といえます。
症状の改善に対する認識
「少しずつだけど、前よりは気持ちが楽になってきた気がする」という発言は、わずかながらも改善を実感できていることを示しています。この認識は治療継続への動機づけとなる重要な要素です。本人が感じている変化を丁寧に確認し、それを支持していくことで、治療への積極性を引き出すことができる可能性があります。
アセスメントの視点
A氏は身体疾患に対しては適切な受診行動と服薬管理ができていましたが、精神症状への対処が遅れた経緯があります。現在は入院治療により確実な服薬管理がなされ、症状も徐々に改善してきています。しかし自責感や将来への不安が強く、疾患の理解や治療への期待感については十分に確認する必要があります。夫も「どうサポートすればいいのか教えてほしい」と述べており、家族を含めた疾患理解の促進と退院後の健康管理体制の確立が課題となることを意識してアセスメントするとよいでしょう。
ケアの方向性
うつ病の病態、治療、予後について本人と家族が理解できるよう、段階的な情報提供を行う必要があります。また本人が感じている症状の改善を共有し、治療継続への動機づけを支援することが重要です。退院後の服薬管理や生活リズムの維持について、具体的な方法を本人・家族とともに検討し、継続的な健康管理ができる体制を整えていくことが求められます。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、A氏の食事摂取状況と体重の変化、栄養状態を評価することが重要です。うつ病による食欲不振は身体的な健康にも影響を与えるため、栄養状態の回復と維持が治療の基盤となります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
入院前の食事摂取状況と体重変化
入院前のA氏は食欲不振があり、1日2食程度で摂取量も少なく、2か月で約4kg減少していました。身長158cm、現在の体重52kgからBMIを計算すると約20.8となり、標準範囲内ではありますが、短期間での体重減少は栄養状態の悪化と疾患の影響を示す重要なサインです。うつ病では食欲低下や食事への関心の喪失が典型的な症状として現れることを踏まえ、体重変化の経過を詳しく記述するとよいでしょう。
現在の食事摂取状況
現在は病院食(常食・1800kcal)が提供されており、摂取量は7割程度まで回復しています。入院前と比較すると改善傾向にありますが、まだ十分な摂取量とは言えない状態です。7割という摂取量が具体的に何kcal程度になるのか、また本人の活動量や必要栄養量に対して適切かどうかを検討することが重要です。食欲の回復は全体的な症状改善の指標の一つとなるため、継続的な評価が必要です。
嚥下機能と消化器症状
嚥下状態に問題はなく、むせや咳き込みもみられません。また嘔吐や吐気の訴えもないため、物理的に食事摂取を妨げる要因はないと考えられます。しかし、うつ病による意欲低下や倦怠感が食事摂取に影響している可能性があります。嚥下機能は保たれているものの、食事への関心や意欲の面でのアセスメントが必要となることを意識して記述するとよいでしょう。
栄養状態を示す血液データ
血液データを見ると、TP 7.2g/dL(基準6.5-8.0)、Alb 4.2g/dL(基準3.8-5.2)といずれも基準値内であり、タンパク質栄養状態は良好です。また電解質であるNa 141mEq/L、K 4.0mEq/Lも基準値内で、脱水などの問題も認められません。RBC 430万/μL、Hb 13.1g/dL、Ht 39.2%と貧血もなく、現時点での栄養状態は比較的維持されていると評価できます。ただし今後も食事摂取量が十分でない状態が続けば、栄養状態の悪化リスクがあることを考慮する必要があります。
皮膚の状態と水分代謝
事例には明確な記載はありませんが、ADLが自立しており、活動量も徐々に増えていることから、褥瘡のリスクは低いと考えられます。また浮腫などの記載もないため、水分代謝にも大きな問題はないと推測されます。しかし、意欲低下により入浴や清潔ケアへの関心が低下している可能性もあるため、皮膚の状態については継続的な観察が必要です。
アセスメントの視点
A氏は入院前に食欲不振と体重減少がみられましたが、入院後は食事摂取量が7割程度まで回復し、血液データ上も栄養状態は維持されています。嚥下機能に問題はなく、身体的に食事摂取を妨げる要因はありませんが、うつ病による意欲低下が食欲に影響していると考えられます。今後、精神症状の改善に伴い食欲も回復していくことが期待されますが、体重の推移や摂取量の変化を継続的にモニタリングし、必要栄養量が確保できているかを評価していくことが重要です。
ケアの方向性
食事摂取量と体重を定期的に評価し、栄養状態の維持・改善を図ることが必要です。食事環境の調整や、本人の嗜好を取り入れた食事内容の工夫、食事時間の柔軟な対応など、食欲を促進するケアを検討するとよいでしょう。また、食事が摂れたことを肯定的にフィードバックし、小さな改善を本人と共有することで、セルフケアへの意欲を高めることができます。退院後の食事管理についても、本人と家族が無理なく継続できる方法を一緒に考えていく必要があります。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
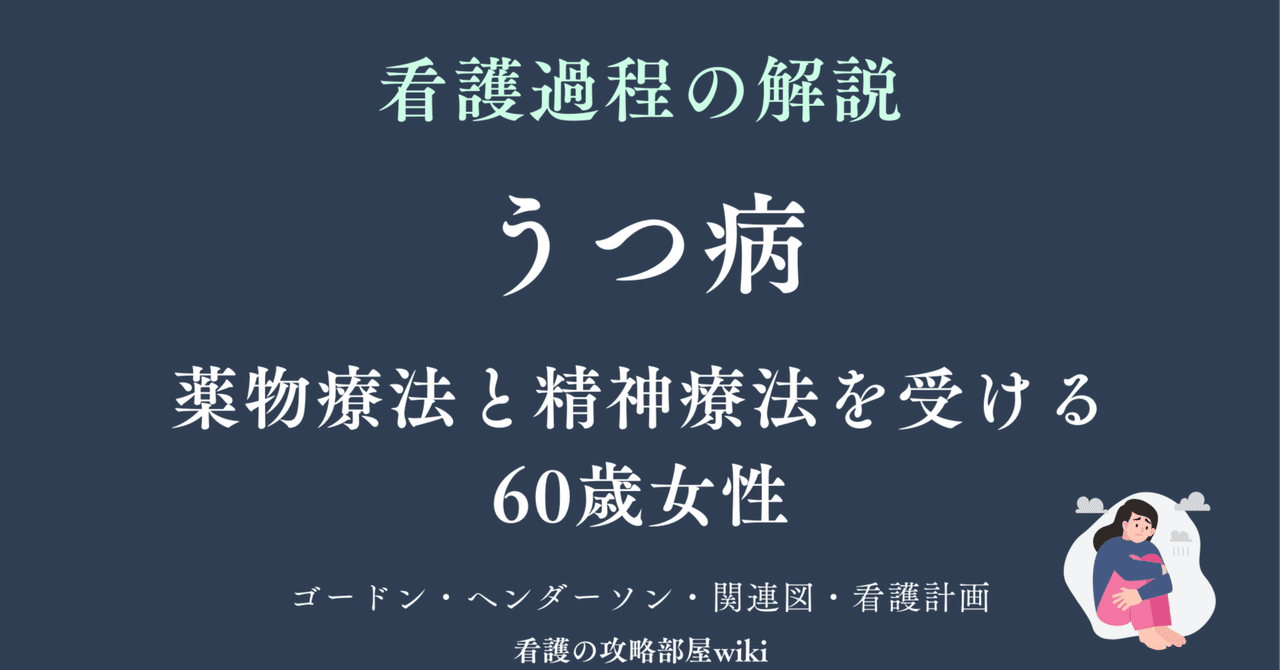
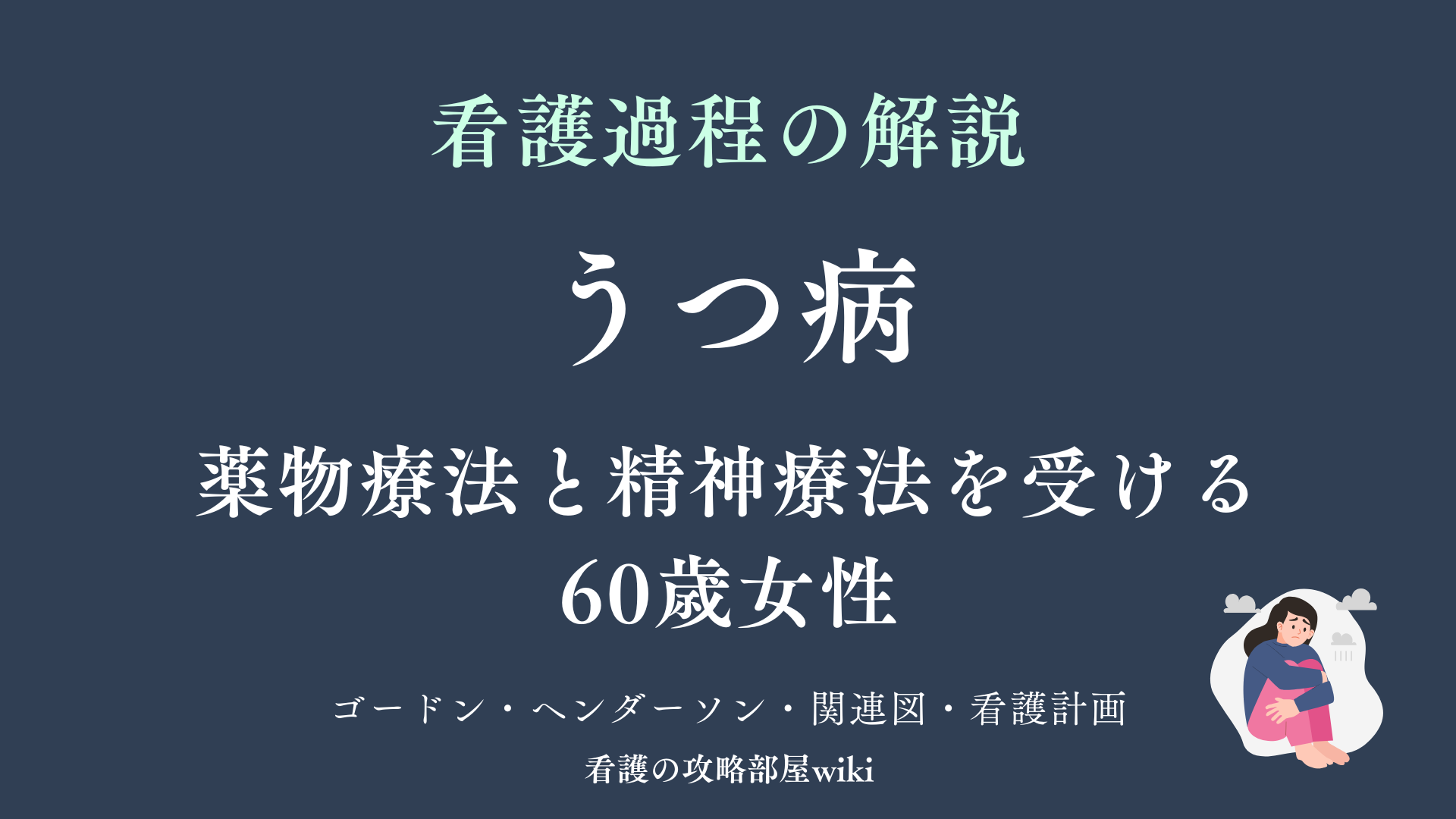


コメント