疾患概要
定義
膵炎とは、膵臓が自身の消化酵素によって自己消化され、炎症を起こす疾患です。急性膵炎と慢性膵炎に大きく分けられます。急性膵炎は突然発症し、適切な治療により膵臓の機能が回復する可能性がある一方、慢性膵炎は長期にわたる炎症により膵臓の組織が不可逆的に破壊され、内分泌・外分泌機能が徐々に低下していく疾患です。
疫学
急性膵炎は日本国内で年間約6万人が発症するとされ、男女比は約2:1で男性にやや多い傾向があります。発症年齢のピークは50〜60歳代です。一方、慢性膵炎の年間発症率は人口10万人あたり約5〜10人程度で、男性が女性の約4〜5倍と圧倒的に多く、40〜60歳代の男性に好発します。これは後述するアルコール性膵炎が多いことと関連しています。
原因
急性膵炎の主な原因
急性膵炎の原因として最も多いのはアルコールと胆石で、両者で全体の約70〜80%を占めます。アルコールは男性に多く、胆石は女性に多い傾向があります。その他、高脂血症、薬剤性、外傷、ERCP後、自己免疫性などがあり、約10〜20%は原因不明の特発性膵炎です。
慢性膵炎の主な原因
慢性膵炎ではアルコールが原因の約60〜70%を占めます。長期間の大量飲酒により膵臓に持続的なダメージが加わることで発症します。その他、特発性、遺伝性、自己免疫性などがあります。
病態生理
膵炎の発症メカニズムは、本来十二指腸内で活性化されるべき膵臓の消化酵素が、膵臓内で早期に活性化してしまうことから始まります。
正常な状態では、膵臓から分泌される消化酵素は不活性型で分泌され、十二指腸で腸液に含まれるエンテロキナーゼなどの働きによって初めて活性化されます。しかし、何らかの原因で膵管内圧が上昇したり、膵液の流出が障害されたりすると、膵臓内で消化酵素が活性化してしまいます。
活性化した膵酵素、特にトリプシンは膵臓自身の組織を消化し始め、これが炎症の引き金となります。この自己消化により、膵臓の細胞は破壊され、炎症性サイトカインが放出されます。炎症が広がると、膵臓だけでなく周囲の組織にも影響が及び、さらに血管の透過性が亢進して浮腫が生じます。
重症化すると、炎症物質が全身に広がり、SIRS(全身性炎症反応症候群)を引き起こし、多臓器不全に至ることもあります。また、膵臓の壊死が進むと、感染を合併して敗血症性ショックとなるリスクも高まります。
慢性膵炎では、繰り返される炎症により膵臓の組織が線維化し、正常な膵組織が失われていきます。その結果、外分泌機能障害により消化酵素の分泌が低下して消化吸収障害が起こり、内分泌機能障害によりインスリン分泌が低下して糖尿病を発症します。
症状・診断・治療
症状
急性膵炎の症状
急性膵炎の最も特徴的な症状は激しい上腹部痛です。痛みは突然始まり、持続的で、背中に放散することが多いのが特徴です。患者さんは「背中を丸めると楽になる」「前かがみになると痛みが和らぐ」と訴えることがあります。これを膵炎の前傾位といいます。
痛みに加えて、悪心・嘔吐が高頻度でみられます。食事摂取により症状が増悪するため、患者さんは食事を避けるようになります。重症例では発熱、頻脈、血圧低下、ショック症状が出現し、腹膜刺激症状として筋性防御がみられることもあります。
慢性膵炎の症状
慢性膵炎では、腹痛が主症状ですが、急性膵炎ほど激烈ではなく、鈍痛が持続することが多いです。膵機能が低下すると、消化吸収障害により脂肪便(便が白っぽく、油が浮く)や体重減少が出現します。また、糖尿病を合併すると、口渇、多飲、多尿などの症状も加わります。
診断
急性膵炎の診断基準
急性膵炎の診断には、以下の3項目のうち2項目以上を満たす必要があります。
- 上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある
- 血中または尿中に膵酵素の上昇がある(血清アミラーゼまたはリパーゼが基準値の3倍以上)
- 画像検査で膵臓に急性膵炎に特徴的な異常所見がある
検査項目
血液検査では、血清アミラーゼとリパーゼの上昇が重要です。特にリパーゼは膵特異性が高く、診断価値が高いとされています。また、白血球増多、CRP上昇などの炎症所見、重症例では腎機能障害、肝機能障害、低カルシウム血症、高血糖などがみられます。
画像検査では、造影CTが最も有用で、膵臓の腫大、周囲の脂肪織の炎症、腹水の有無、壊死の範囲などを評価できます。超音波検査やMRIも補助的に用いられます。
慢性膵炎の診断
慢性膵炎では、画像検査で膵石、膵管の不整拡張、膵の萎縮などの特徴的な所見がみられます。また、膵外分泌機能検査として、便中エラスターゼやBTパバ試験などが行われることもあります。
治療
急性膵炎の治療
急性膵炎の治療の基本は保存的治療です。膵臓を安静に保つため、絶飲食とし、輸液による水分・電解質の補正を行います。痛みのコントロールには鎮痛薬を使用し、必要に応じて蛋白分解酵素阻害薬や抗菌薬を投与します。
重症例では、集中治療室での全身管理が必要となり、呼吸管理、循環管理、腎代替療法などが行われます。感染性壊死が疑われる場合は、ドレナージや外科的治療が検討されます。
慢性膵炎の治療
慢性膵炎では、まず禁酒が絶対的に重要です。痛みに対しては鎮痛薬を使用し、膵酵素補充療法により消化吸収を改善します。糖尿病を合併している場合は、血糖コントロールが必要です。膵石による膵管閉塞がある場合は、内視鏡的治療や外科的治療が行われることもあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛
- 体液量不足
- 栄養摂取消費バランス異常
- 感染リスク状態
- 不安
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターン
膵炎患者さんは絶飲食となるため、栄養状態の悪化が懸念されます。急性期は輸液管理が中心となりますが、炎症が落ち着けば経口摂取を再開します。その際、低脂肪で消化のよい食事から開始し、症状の再燃に注意しながら段階的に食事内容を調整していく必要があります。慢性膵炎では、脂肪便の有無、体重変化、血糖値の推移を継続的にモニタリングすることが重要です。
活動・運動パターン
急性膵炎の急性期は安静が必要ですが、長期臥床による廃用症候群を予防するため、症状が安定したら早期離床を促します。慢性膵炎では、日常生活活動が制限されることは少ないですが、疲労感や栄養状態の低下により活動耐性が低下している場合があるため、個別に評価します。
認知・知覚パターン
膵炎における激しい腹痛は、患者さんのQOLを著しく低下させます。痛みの部位、性質、程度、増悪・軽減因子を詳細にアセスメントし、適切な鎮痛管理を行います。また、疾患や治療についての理解度を確認し、不安軽減のための情報提供や心理的サポートも重要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に飲食する
急性膵炎では絶飲食が基本となるため、このニードは満たされません。口渇感や空腹感を訴える患者さんに対しては、含嗽で口腔内を潤したり、氷片を与えたりして不快感を軽減します。経口摂取再開時は、膵臓への刺激を最小限にするため、低脂肪・高炭水化物・高蛋白の食事を少量から開始します。
身体の清潔を保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
急性期は安静が必要なため、清潔ケアは看護師の援助が必要です。発熱や発汗により不快感が増すため、清拭や寝衣交換をこまめに行います。また、輸液や持続的な安静により皮膚トラブルのリスクが高まるため、褥瘡予防のケアも重要です。
自分の感情、欲求、恐怖、あるいは気分を表現してコミュニケーションをとる
膵炎は激しい痛みを伴い、絶飲食や長期入院により患者さんは大きなストレスを感じます。痛みの訴えを傾聴し、不安や恐怖を表出できる環境を整えることが大切です。また、禁酒が必要な患者さんには、アルコール依存への介入や心理的サポートが必要になることもあります。
看護計画・介入の内容
- 疼痛コントロール: 鎮痛薬の確実な投与、痛みの評価(ペインスケールの使用)、安楽な体位の工夫(前傾位など)、温罨法や冷罨法の適用
- 輸液管理: 輸液量と速度の確実な管理、電解質バランスのモニタリング、尿量測定による水分出納の把握
- バイタルサインの監視: 発熱、頻脈、血圧低下などショック徴候の早期発見、呼吸状態の観察
- 腹部症状の観察: 腹痛の程度と部位、腹部膨満、腸蠕動音、悪心・嘔吐の有無と程度
- 検査データの確認: アミラーゼ・リパーゼ値、炎症反応、肝機能、腎機能、血糖値の推移を継続的に確認
- 感染予防: 壊死性膵炎では感染リスクが高いため、発熱や炎症反応の変化に注意し、清潔操作を徹底
- 栄養管理: 経口摂取再開時は医師の指示に従い、低脂肪食から段階的に進める。食後の腹痛や悪心の有無を確認
- 禁酒指導: アルコール性膵炎では禁酒が絶対的に必要であることを説明し、必要に応じて専門的な介入を検討
- 患者・家族教育: 疾患の理解促進、再発予防のための生活指導、退院後の食事管理や定期受診の重要性について説明
よくある疑問・Q&A
Q: 膵炎の患者さんはなぜ絶飲食にする必要があるのですか?
A: 膵臓は食事を摂ることで消化酵素を分泌します。膵炎では膵臓内で消化酵素が活性化してしまい、自己消化が起こっている状態です。食事を摂ると膵臓がさらに刺激され、酵素分泌が促進されて炎症が悪化してしまいます。そのため、膵臓を安静に保つために絶飲食とし、輸液で栄養や水分を補給するのです。炎症が落ち着いてきたら、段階的に経口摂取を再開していきます。
Q: 前かがみの体位をとると痛みが楽になるのはなぜですか?
A: 膵炎の炎症により膵臓が腫大すると、後腹膜にある神経叢が圧迫されて激しい痛みが生じます。前かがみの体位をとることで、腫大した膵臓と後腹膜の間にスペースができ、神経への圧迫が軽減されるため、痛みが和らぐのです。これを膵炎の前傾位といい、患者さんが自然とこの姿勢をとることが多いです。看護師は患者さんが楽な体位を保てるよう、クッションやベッドの角度調整などで援助します。
Q: 急性膵炎と慢性膵炎の違いは何ですか?
A: 急性膵炎は突然発症し、適切な治療を行えば膵臓の機能が回復する可能性がある疾患です。一方、慢性膵炎は長期にわたる炎症により膵臓の組織が不可逆的に破壊され、線維化が進行する疾患です。急性膵炎は激烈な腹痛で発症し、重症化すると命に関わりますが、多くは保存的治療で改善します。慢性膵炎は比較的緩やかに進行し、膵機能が徐々に低下して消化吸収障害や糖尿病を引き起こします。治療目標も異なり、急性膵炎では炎症の鎮静化が、慢性膵炎では症状緩和と合併症予防が中心となります。
Q: 膵炎の患者さんに禁酒指導をする際のポイントは何ですか?
A: アルコール性膵炎では、禁酒が治療の最も重要な柱です。しかし、単に「お酒をやめてください」と伝えるだけでは不十分です。まず、患者さんの飲酒歴や飲酒に対する認識を丁寧に聴取し、アルコールが膵炎の原因であることへの理解度を確認します。その上で、継続的な飲酒が膵炎の再発や慢性化、さらには膵がんのリスクを高めることを具体的に説明します。アルコール依存が疑われる場合は、患者さん一人では禁酒継続が困難なことも多いため、専門医療機関への紹介や、家族を含めた支援体制の構築が必要です。退院後も外来でフォローし、禁酒継続を支援していく姿勢が大切です。
まとめ
膵炎は、膵臓が自身の消化酵素によって自己消化される疾患で、急性膵炎と慢性膵炎に分けられます。急性膵炎の原因で最も多いのはアルコールと胆石で、激しい上腹部痛と背部痛が特徴的な症状です。病態の本質は膵酵素の膵臓内での早期活性化であり、これにより自己消化と炎症が引き起こされます。
看護のポイントは、疼痛コントロール、輸液管理、バイタルサインの監視です。急性期は絶飲食として膵臓を安静に保ち、重症化の兆候を早期に発見することが重要です。また、アルコール性膵炎では禁酒指導が治療の要となります。
慢性膵炎では、繰り返す炎症により膵機能が徐々に低下し、消化吸収障害や糖尿病を合併します。そのため、栄養管理や血糖コントロールも看護の重要な役割です。
実習では、患者さんの痛みの訴えを丁寧に傾聴し、苦痛を最小限にするケアを心がけてください。また、検査データの推移を継続的に確認し、病態の変化を的確に捉える力を養いましょう。膵炎は重症化すると多臓器不全に至る可能性もあるため、全身状態の観察と早期対応が求められます。患者さんの不安に寄り添いながら、根拠に基づいた看護を実践していきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
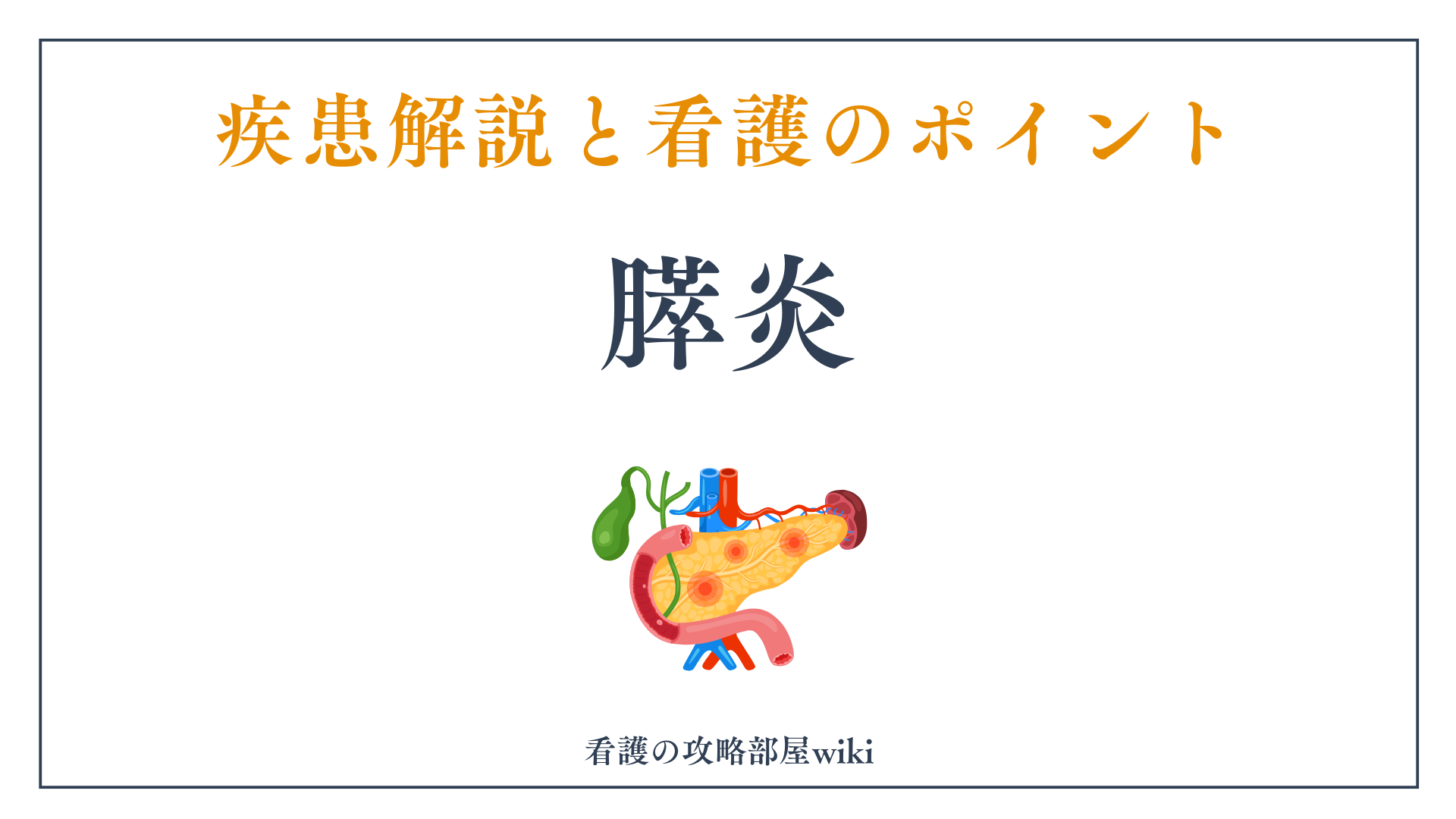

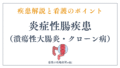
コメント