疾患概要
定義
骨粗鬆症は、骨量の減少と骨組織の微細構造の劣化により、骨の強度が低下して骨折しやすくなる疾患です。WHO(世界保健機関)の診断基準では、若年成人の平均骨密度と比較して-2.5SD以下の場合に骨粗鬆症と診断されます。単なる加齢現象ではなく、適切な予防と治療が必要な疾患として位置づけられています。
疫学
日本では約1,300万人が骨粗鬆症患者と推定され、特に閉経後女性に多く発症します。男女比は約1:4で女性が圧倒的に多く、50歳以上の女性では約20%、70歳以上では約40%が骨粗鬆症に罹患しています。高齢化社会の進展により患者数は増加傾向にあり、骨粗鬆症性骨折は年間約160万件発生し、医療費は約1兆円に達しています。
原因
骨粗鬆症の原因は原発性と続発性に大別されます。原発性骨粗鬆症は閉経や加齢が主因で、全体の約95%を占めます。閉経後は女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少により骨吸収が促進され、男性でも加齢によりテストステロンが減少して骨形成が低下します。続発性骨粗鬆症は特定の疾患(甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症、関節リウマチなど)や薬剤(ステロイド、抗てんかん薬など)が原因となります。その他の危険因子には遺伝、低体重、喫煙、過度の飲酒、運動不足、カルシウム・ビタミンD不足などがあります。
病態生理
骨は常に骨吸収(古い骨を溶かす)と骨形成(新しい骨を作る)を繰り返しており、この骨代謝回転により健康な骨が維持されています。骨粗鬆症では、破骨細胞による骨吸収が骨芽細胞による骨形成を上回ることで骨量が減少します。特にエストロゲン欠乏により破骨細胞の活性が亢進し、骨梁の菲薄化や連続性の断裂が生じます。これにより骨密度の低下だけでなく、骨質の劣化も起こり、骨の脆弱性が増大して軽微な外力でも骨折が生じやすくなります。
症状・診断・治療
症状
骨粗鬆症は「サイレント・ディジーズ(静かなる疾患)」と呼ばれ、初期は無症状で経過することが特徴です。症状が現れるのは骨折が生じてからで、腰背部痛が最も多い訴えです。椎体圧迫骨折により身長の短縮や円背(亀背)が進行し、日常生活動作に支障をきたします。進行すると軽微な転倒でも大腿骨近位部骨折や前腕骨遠位端骨折(コーレス骨折)などが生じ、寝たきりの原因となることがあります。慢性疼痛により活動量が減少し、筋力低下や関節可動域制限も併発します。
診断
診断はDEXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)による骨密度測定が基準となります。腰椎と大腿骨近位部の測定が一般的で、YAM(若年成人平均値)の80%以上が正常、70-80%が骨量減少、70%未満が骨粗鬆症の疑いとされます。骨代謝マーカーでは骨吸収マーカー(尿中NTx、血清TRACP-5b)と骨形成マーカー(血清BAP、オステオカルシン)により骨代謝の状態を評価します。画像診断では脊椎X線写真で椎体の変形や骨梁の粗造化を確認し、CT・MRIでは骨折の有無や程度を詳細に評価できます。
治療
治療の目標は骨折予防です。薬物療法では骨吸収抑制薬(ビスホスホネート系薬剤、デノスマブ、SERMs)、骨形成促進薬(テリパラチド、アバロパラチド)、デュアルアクション薬(ロモソズマブ)が使用されます。ビスホスホネート系薬剤は第一選択薬として広く使用されており、週1回または月1回の服薬で効果を示します。非薬物療法では適度な運動(荷重運動、筋力訓練)、転倒予防、禁煙・節酒が重要です。栄養療法ではカルシウム(700-800mg/日)とビタミンD(800-1000IU/日)の充足が基本となります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 外傷リスク状態:骨脆弱性と転倒リスクに関連した骨折の危険性
- 急性疼痛/慢性疼痛:骨折や椎体変形に関連した疼痛
- 身体可動性障害:疼痛と骨折リスクに関連した活動制限
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは患者の骨粗鬆症に対する理解度と治療への取り組み姿勢を評価します。服薬アドヒアランスは治療効果に直結するため、薬剤の効果・副作用への理解度や服薬方法の習得状況を詳細にアセスメントします。活動・運動パターンでは転倒リスクの評価が重要で、歩行状態、バランス機能、筋力、既往の転倒歴、使用中の薬剤(睡眠薬、血圧薬など)を総合的に判断します。栄養・代謝パターンではカルシウムやビタミンDの摂取状況、体重変化、食事摂取量を評価し、骨代謝に影響する栄養状態を把握します。
ヘンダーソン14基本的ニード
安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは、家庭内の転倒リスク要因(段差、滑りやすい床材、照明不足、手すりの欠如)を具体的に評価し、安全な生活環境の整備を支援します。身体の位置を動かし、望ましい肢位を保持するでは、骨折リスクを考慮した安全な動作方法や体位変換の指導を行います。食べる・飲むでは骨の健康に必要な栄養素の適切な摂取を支援し、カルシウム豊富な食品の選択方法や調理法を指導します。
看護計画・介入の内容
- 転倒・骨折予防対策:歩行補助具の適切な使用指導、住環境の安全性評価と改善提案、適切な履物の選択指導、段階的な運動療法の実施
- 服薬管理・指導:ビスホスホネート系薬剤の正しい服薬方法(起床時空腹時服用、30分間の起立保持)、副作用の観察と対処法、服薬カレンダーの活用
- 生活習慣の改善支援:骨に良い食事指導(カルシウム、ビタミンD、ビタミンKの摂取)、適度な日光浴の推奨、禁煙・節酒指導、継続可能な運動プログラムの提案
よくある疑問・Q&A
Q: 骨粗鬆症の薬は一生飲み続けなければいけませんか?
A: 必ずしも一生服薬が必要というわけではありません。ビスホスホネート系薬剤は3-5年間の投与で骨折リスクの大幅な軽減効果が得られ、その後は「休薬期間」を設けることもあります。ただし、休薬の判断は骨密度の推移や骨折リスクを総合的に評価して医師が決定します。定期的な骨密度測定と医師との相談により、個々の患者さんに最適な治療計画を立てることが大切です。
Q: カルシウムをたくさん摂れば骨は丈夫になりますか?
A: カルシウムの摂取は重要ですが、単独では効果は限定的です。カルシウムの吸収にはビタミンDが必要で、さらに骨にカルシウムを定着させるには適度な運動(特に荷重運動)が不可欠です。また、過剰なカルシウム摂取は結石形成や他のミネラルの吸収阻害を招く可能性があります。バランスの取れた食事と適切な運動、必要に応じた薬物療法の組み合わせが最も効果的です。
Q: 骨粗鬆症でも運動をして大丈夫ですか?
A: はい、適切な運動は骨密度の維持・改善に効果的です。推奨される運動は荷重運動(ウォーキング、階段昇降、軽いジャンプ)と筋力訓練です。ただし、転倒リスクの高い運動は避け、体の柔軟性を高めるストレッチも併用します。運動開始前には医師や理学療法士と相談し、個人の骨密度や身体機能に応じた安全で効果的な運動プログラムを作成することが重要です。
Q: 骨折したらもう治らないのでしょうか?
A: 骨折は適切な治療によりほとんどの場合治癒します。高齢者でも骨の修復能力は保たれており、特に手術技術の進歩により早期離床・早期社会復帰が可能となっています。重要なのは骨折後の二次骨折予防で、骨粗鬆症の治療を継続し、転倒予防対策を徹底することで、その後の骨折リスクを大幅に軽減できます。骨折を機に生活習慣を見直し、より積極的な治療を開始することが大切です。
まとめ
骨粗鬆症は高齢社会における重要な健康課題であり、単なる加齢現象ではなく治療可能な疾患です。最大の特徴は症状がないまま進行することで、骨折が起こって初めて診断されることが多いのが現状です。
看護の要点は予防的アプローチと骨折リスクの最小化です。特に閉経後女性や高齢者に対しては、骨密度測定の推奨と生活習慣の改善指導を積極的に行うことが重要です。転倒予防対策は骨折予防の根幹であり、住環境の評価から歩行能力の維持まで包括的な支援が求められます。
薬物療法では服薬アドヒアランスの向上が治療成功の鍵となります。ビスホスホネート系薬剤の特殊な服薬方法や副作用について十分な説明を行い、患者さんが安心して継続できる環境を整えることが大切です。
実習では患者さんのQOL向上を念頭に置いたケアを心がけましょう。骨粗鬆症は長期間の治療が必要な疾患ですが、適切な管理により活動的な生活の維持が可能です。患者さんの不安に共感しつつ、前向きに治療に取り組めるよう励まし、自己管理能力の向上を支援することが、患者さんの将来の健康維持につながります。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
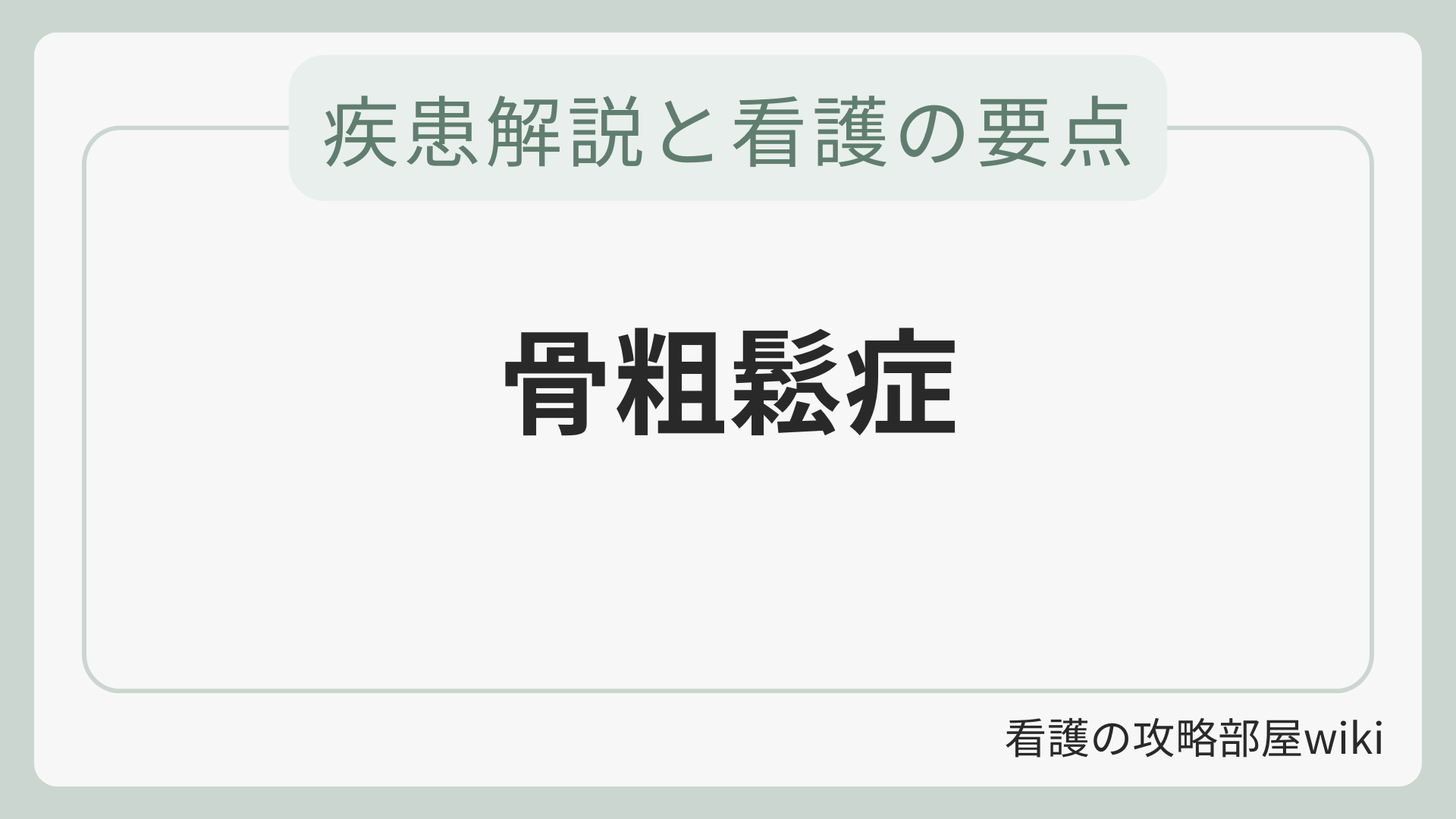
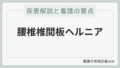
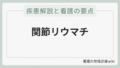
コメント