疾患概要
定義
胃がんとは、胃の粘膜から発生する悪性腫瘍です。胃は、噴門部、胃底部、胃体部、幽門部に分けられ、胃体部と幽門部に最も多く発生します。組織型により、分化型(腸型)と未分化型(びまん型)に大別され、進行形態や転移様式が異なります。早期胃がんは粘膜または粘膜下層にとどまるもので、進行胃がんは固有筋層以深に浸潤したものを指します。
疫学
胃がんは、日本において肺がん、大腸がんに次いで罹患者数が多いがんです。年間約13万人が胃がんと診断され、死亡者数は年間約4万人で、がんによる死亡原因の第3位となっています。男女比は約2:1で男性に多く、発症年齢のピークは60〜70歳代です。
かつて日本は世界で最も胃がんの多い国でしたが、ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療の普及や食生活の改善により、罹患率・死亡率ともに減少傾向にあります。しかし、依然として日本人に多いがんであり、検診による早期発見が重要です。
原因
胃がんの発生には、複数の要因が関与しています。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染
最も重要な危険因子です。ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎が持続し、胃粘膜の萎縮が進行します。萎縮性胃炎から腸上皮化生を経て、胃がんが発生すると考えられています。胃がん患者さんの約80〜90%がピロリ菌に感染しています。ピロリ菌の除菌治療により、胃がんのリスクを約30〜40%減少させることができます。
食生活
塩分の多い食事、燻製食品、漬物などに含まれる塩分やニトロソアミンという物質が、胃がんのリスクを高めます。一方、野菜や果物に含まれるビタミンCやカロテンは、胃がんのリスクを下げる効果があります。
喫煙・飲酒
喫煙は胃がんのリスクを約1.5〜2倍高めます。過度の飲酒も危険因子となります。
遺伝因子
胃がん患者さんの約10%は家族集積性があり、血縁者に胃がんの患者さんがいる場合、リスクが2〜3倍高まります。また、遺伝性びまん性胃がんという稀な遺伝性疾患もあります。
病態生理
胃がんは、胃粘膜の上皮細胞から発生します。多くは、ピロリ菌感染による慢性胃炎から始まります。
ピロリ菌に感染すると、胃粘膜に持続的な炎症が起こります。炎症が長期間続くと、胃粘膜が萎縮し(萎縮性胃炎)、胃酸の分泌が低下します。さらに進行すると、胃の粘膜が腸の粘膜のような状態に変化します(腸上皮化生)。この状態から、異型上皮(前がん病変)を経て、胃がんが発生すると考えられています。
胃がんは、粘膜から発生し、徐々に深く浸潤していきます。がんの深達度により、早期胃がん(粘膜または粘膜下層)と進行胃がん(固有筋層以深)に分けられます。
胃がんの進行様式は、組織型により異なります。分化型胃がん(腸型)は、比較的ゆっくり進行し、粘膜内を広がって大きくなります。潰瘍を形成することが多く、出血の原因となります。一方、未分化型胃がん(びまん型、スキルス胃がん)は、粘膜下層を這うように広がり、胃壁全体が硬くなります。進行が速く、若年者にも多いのが特徴です。
がん細胞が胃壁を越えて周囲のリンパ節に転移すると、リンパ節転移となります。さらに進行すると、血流に乗ってがん細胞が全身に運ばれ、遠隔転移を起こします。胃がんの遠隔転移で多いのは、肝臓、肺、骨、腹膜です。特に腹膜播種(腹膜に無数の小さな転移巣ができる)は、胃がんに特徴的な転移形態で、予後が不良です。
胃がんが進行すると、胃の出口(幽門部)を狭窄させ、食物の通過障害を起こします。これを幽門狭窄といい、悪心、嘔吐、体重減少などの症状が出現します。また、腫瘍からの慢性的な出血により、貧血が進行します。
症状・診断・治療
症状
早期胃がん
早期の胃がんは、ほとんど自覚症状がありません。あっても、軽度の上腹部不快感、胃もたれ、食欲不振など、非特異的な症状です。これらは胃炎や胃潰瘍でもみられる症状であり、胃がんに特徴的なものではありません。そのため、症状だけで早期胃がんを発見することは困難で、検診が非常に重要です。
進行胃がん
進行すると、以下のような症状が出現します。
上腹部痛・不快感: 持続的な鈍痛や圧迫感がみられます。食後に増悪することもあります。
食欲不振・体重減少: 進行すると、食欲が著しく低下し、体重が減少します。がんによる代謝亢進も体重減少の原因となります。
悪心・嘔吐: 幽門狭窄により、食物が胃から十二指腸へ流れにくくなると、悪心や嘔吐が頻繁に起こります。
吐血・下血: 腫瘍からの出血により、吐血(コーヒー残渣様の嘔吐物)や下血(黒色便、タール便)がみられます。大量出血ではショック状態となることもあります。
貧血: 慢性的な出血により、鉄欠乏性貧血が進行し、動悸、息切れ、めまい、全身倦怠感などの症状が出現します。
腹部膨満感: 腹水や腹膜播種により、腹部膨満感が出現します。
嚥下困難: 噴門部のがんでは、食物が飲み込みにくくなることがあります。
診断
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
胃がんの確定診断に最も有用な検査です。口または鼻から内視鏡を挿入し、胃の内部を直接観察します。病変を発見したら、組織を採取して病理検査(生検)を行い、がんの確定診断をします。早期胃がんの発見にも優れており、胃がん検診として推奨されています。
上部消化管造影検査(バリウム検査)
バリウムを飲んでX線撮影を行い、胃の形態や粘膜の異常を評価します。検診で広く用いられていますが、異常が見つかった場合は、内視鏡検査で精密検査を行います。
CT検査・MRI検査
がんの進行度、周囲臓器への浸潤、リンパ節転移、遠隔転移の有無を評価します。治療方針の決定に重要です。
腫瘍マーカー
血液検査でCEA、CA19-9などの腫瘍マーカーを測定します。進行がんでは上昇することがありますが、早期がんでは上昇しないことも多く、診断のための検査としては限界があります。治療効果の判定や再発の早期発見に用いられます。
病期分類
胃がんは、TNM分類とStage分類により病期が決定されます。病期はI期からIV期まであり、数字が大きいほど進行しています。病期により治療方針と予後が大きく異なります。
治療
胃がんの治療は、手術、化学療法、放射線療法を組み合わせて行います。
内視鏡的治療
早期胃がんで、リンパ節転移のリスクが非常に低い場合、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)により、開腹せずに治療できます。胃カメラを使って、がん病巣を含む粘膜を切除します。体への負担が少なく、胃の機能を温存できる利点があります。
手術療法
胃がんの根治的治療の中心は手術です。がんの部位と進行度により、術式が選択されます。
幽門側胃切除術: 胃の下部(幽門側)にがんがある場合、胃の下部2/3程度を切除し、残った胃と十二指腸または空腸をつなぎます。最も多く行われる術式です。
噴門側胃切除術: 胃の上部(噴門側)にがんがある場合、胃の上部を切除し、残った胃と食道をつなぎます。
胃全摘術: がんが広範囲に及ぶ場合や、胃体部のがんの場合、胃を全て摘出し、食道と空腸を直接つなぎます。
近年、腹腔鏡下手術やロボット支援下手術が普及し、傷が小さく、術後の回復が早いという利点があります。
化学療法
進行がんや再発がん、遠隔転移がある場合に行われます。また、術後の再発予防(術後補助化学療法)としても用いられます。S-1、シスプラチン、オキサリプラチン、分子標的薬(トラスツズマブ、ラムシルマブなど)などが使用されます。
放射線療法
胃がんでは、放射線療法が単独で行われることは少なく、主に化学療法と併用されたり、骨転移による痛みの緩和など症状緩和目的で使用されたりします。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛
- 栄養摂取消費バランス異常
- 悪心
- 不安
- 活動耐性低下
- 感染リスク状態
- ボディイメージ混乱
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターン
胃がん患者さんは、腫瘍による症状や、がんに伴う代謝亢進により栄養状態が著しく悪化します。食欲不振、悪心、嘔吐、早期満腹感により食事摂取が困難になります。特に幽門狭窄がある場合、固形物の摂取が難しくなります。
術前は、栄養状態の改善が重要です。食事摂取量、体重、血清アルブミン値、ヘモグロビン値を評価し、必要に応じて高カロリー輸液や経腸栄養により栄養補給を行います。
術後は、胃の切除範囲により、さまざまな症状が出現します。ダンピング症候群、逆流性食道炎、吸収不良などが代表的です。食事内容や食べ方の工夫が必要となります。
排泄パターン
胃がんからの出血により、黒色便(タール便)がみられることがあります。便の色と性状を観察し、消化管出血の有無を評価します。
術後は、腸蠕動の回復を確認します。排ガス、排便の有無、腹部膨満の程度、腸蠕動音を観察します。
活動・運動パターン
貧血や栄養状態の悪化により、活動耐性が著しく低下します。術前の貧血や低栄養を改善し、手術に備えます。
術後は、早期離床が推奨されます。術後合併症の予防と回復促進のため、疼痛をコントロールしながら、段階的に活動を拡大します。
認知・知覚パターン
がんの診断は、患者さんに大きな心理的衝撃を与えます。「がん」という言葉への恐怖、治療への不安、死への恐怖など、さまざまな感情が生じます。また、術後の食生活の変化への不安も大きいです。患者さんの感情を傾聴し、心理的サポートを提供することが重要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に飲食する
胃がんの症状により、食事摂取が困難になります。少量頻回の食事、嗜好に合わせた食事内容の調整、食べやすい形態の工夫により、必要な栄養を確保します。幽門狭窄がある場合は、流動食や半消化態栄養剤を使用します。
術後は、食事の工夫が非常に重要です。ダンピング症候群を予防するため、少量頻回の食事、糖質を控える、食事中の水分を控える、食後は横になるなどの指導を行います。胃全摘術後は、食事量が減少するため、高カロリー・高タンパク質の食事を少量ずつ、1日5〜6回に分けて摂取するよう指導します。
正常に排泄する
黒色便(タール便)は、上部消化管出血の重要なサインです。便の色を観察し、消化管出血の有無を評価します。大量出血では、ショック症状を呈することもあるため、バイタルサインの監視も重要です。
術後は、腸蠕動の回復を促すため、早期離床と歩行を促します。
身体を動かし、望ましい肢位を保持する
術後の早期離床は、合併症予防と回復促進のために非常に重要です。鎮痛薬を適切に使用し、創部を保護しながら体位変換や歩行を支援します。
身体の清潔を保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
術後は、創部の観察とケアが重要です。創部の発赤、腫脹、浸出液、離開の有無を確認し、感染徴候の早期発見に努めます。ドレーンが留置されている場合は、挿入部の観察と清潔管理を徹底します。
自分の感情、欲求、恐怖、あるいは気分を表現してコミュニケーションをとる
がんの診断、手術、術後の食生活の変化など、患者さんは多くのストレスにさらされます。不安、恐怖、悲しみ、怒りなど、さまざまな感情を抱えています。これらの感情を表出できる環境を整え、傾聴する姿勢が大切です。
看護計画・介入の内容
- 術前オリエンテーション: 手術の流れ、術後の経過、ドレーンの説明、痛みのコントロール方法、早期離床の重要性などを説明し、不安を軽減する
- 栄養状態の評価: 食事摂取量、体重、血清アルブミン値、ヘモグロビン値を測定し、栄養状態を評価する。必要に応じて栄養補給を行う
- 貧血の評価: ヘモグロビン値、ヘマトクリット値を確認し、貧血の程度を評価する。必要に応じて輸血を検討する
- バイタルサインの監視: 体温、血圧、脈拍、呼吸数を定期的に測定し、術後合併症や消化管出血の早期発見に努める
- 疼痛コントロール: 痛みの部位、程度をペインスケールで評価し、鎮痛薬を確実に投与する。患者自己調節鎮痛法(PCA)の使用方法を指導する
- 腸蠕動の観察: 術後、排ガス、排便の有無、腹部膨満の程度、腸蠕動音を継続的に観察する
- 創部・ドレーンの管理: 創部の発赤、腫脹、浸出液、感染徴候を観察する。ドレーンの排液量、性状、色を観察し、記録する。吻合部からの縫合不全の徴候に注意する
- 悪心・嘔吐の管理: 制吐薬を適切に使用し、悪心・嘔吐を軽減する。嘔吐物の量、性状、色を観察する
- 早期離床の促進: 術後の早期離床の重要性を説明し、患者さんのペースに合わせて歩行を支援する。深呼吸や咳嗽の指導も行い、呼吸器合併症を予防する
- 経口摂取の再開支援: 医師の指示に従い、水分摂取から開始し、段階的に食事を進める。摂取後の腹部症状や悪心を観察する
- ダンピング症候群の予防指導: 少量頻回の食事、糖質を控える、食事中の水分を控える、食後は横になるなどの具体的な方法を指導する
- 食事指導: 術後の食事の工夫について、栄養士と連携して具体的に指導する。高カロリー・高タンパク質、少量頻回、よく噛むなどのポイントを説明する
- 体重管理: 退院後も定期的に体重を測定し、極端な体重減少がないか確認するよう指導する
- 心理的サポート: 不安や恐怖を傾聴し、患者さんの尊厳を守る。術後の生活への不安に対しては、具体的な対処方法を提示する
- 患者・家族教育: 疾患の理解促進、術後の生活管理、食事の工夫、症状出現時の対応、定期受診の重要性について説明する
よくある疑問・Q&A
Q: ダンピング症候群とは何ですか? なぜ起こるのですか?
A: ダンピング症候群とは、胃の切除後に起こる特有の症状です。早期ダンピング症候群と後期ダンピング症候群の2種類があります。早期ダンピング症候群は、食後15〜30分以内に、動悸、発汗、めまい、脱力感、腹痛、下痢などの症状が出現します。これは、胃が小さくなったり、なくなったりすることで、食べ物が急速に小腸に流れ込むため起こります。小腸に高濃度の食物が一気に入ると、水分が腸管内に移動し、循環血液量が減少して症状が出るのです。後期ダンピング症候群は、食後2〜3時間後に、冷汗、脱力感、めまい、動悸などの症状が出現します。これは、糖質が急速に吸収されて血糖値が急上昇し、その後インスリンが過剰に分泌されて低血糖になるために起こります。予防には、少量頻回の食事、糖質を控える、食事中の水分を控える、食後は横になるなどの工夫が有効です。
Q: 胃を全部取ってしまっても、食事はできるのですか?
A: 胃全摘術後も、食事を摂ることは可能です。ただし、胃がない状態では、食べ物を一時的に貯めておく場所がなくなり、消化機能も低下するため、食事の工夫が必要です。少量頻回の食事が基本で、1日5〜6回に分けて食べます。1回の食事量は、手術前の半分程度になります。また、よく噛んで、ゆっくり食べることが大切です。高カロリー・高タンパク質の食事を心がけ、栄養補助食品も活用します。術後は、ビタミンB12や鉄の吸収が低下するため、サプリメントや注射による補充が必要になることもあります。多くの患者さんは、時間をかけて食事に慣れ、社会復帰しています。退院後も、栄養士による食事指導を受けながら、自分に合った食事方法を見つけていくことが大切です。
Q: ヘリコバクター・ピロリ菌を除菌すれば、胃がんは予防できるのですか?
A: ピロリ菌の除菌により、胃がんのリスクを約30〜40%減少させることができます。ピロリ菌は胃がんの最大の危険因子であり、除菌することで慢性胃炎の進行を止め、胃がんの発生を抑制できます。ただし、除菌しても胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。特に、萎縮性胃炎が進行している場合は、除菌後も胃がんが発生するリスクが残ります。そのため、除菌後も定期的な内視鏡検査による経過観察が必要です。ピロリ菌の感染検査は、胃内視鏡検査や血液検査、尿検査、便検査などで行えます。感染が判明した場合は、抗生物質と胃酸分泌抑制薬を1週間服用する除菌治療を受けることが推奨されます。
Q: 胃がんと胃潰瘍の症状の違いは何ですか?
A: 実は、症状だけで胃がんと胃潰瘍を区別することは非常に困難です。どちらも上腹部痛、食欲不振、悪心などの似た症状を呈します。胃潰瘍では、空腹時の痛みや、食後に痛みが軽減することが多いとされますが、胃がんでもこのような症状を示すことがあります。早期胃がんは特に症状が乏しく、胃炎や胃潰瘍と区別がつきません。そのため、症状だけで判断せず、必ず胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)を受けることが重要です。胃カメラでは、病変を直接観察し、組織を採取して病理検査を行うことで、確定診断ができます。「胃の調子が悪いけど、胃薬を飲んでいれば大丈夫」と自己判断せず、症状が続く場合は必ず医療機関を受診し、胃カメラを受けることをお勧めします。
Q: 胃がんの手術後、どのくらいで普通の生活に戻れますか?
A: 回復のスピードは、手術の方法、がんの進行度、患者さんの年齢や全身状態により異なります。腹腔鏡下手術の場合、開腹手術に比べて侵襲が少ないため、回復が早い傾向があります。一般的に、入院期間は10〜14日程度です。退院後は、徐々に日常生活に戻りますが、完全に回復するには2〜3ヶ月かかることもあります。特に、食事に慣れるまでに時間がかかります。軽い家事や散歩は退院後すぐに始められますが、重い物を持つ、激しい運動をするなどは、医師の許可が出るまで控えます。仕事復帰の時期は、仕事の内容により異なりますが、デスクワークであれば術後1〜2ヶ月程度、肉体労働であれば2〜3ヶ月以上が目安です。焦らず、自分のペースで回復を目指すことが大切です。定期的な外来受診で、体重や栄養状態をチェックしながら、生活を調整していきます。
まとめ
胃がんは、日本において依然として多いがんですが、ピロリ菌除菌治療の普及や検診による早期発見により、罹患率・死亡率ともに減少傾向にあります。最大の危険因子はヘリコバクター・ピロリ菌感染で、除菌により胃がんのリスクを約30〜40%減少させることができます。
早期胃がんはほとんど無症状であり、定期的な胃カメラ検査が早期発見の鍵となります。進行すると、上腹部痛、食欲不振、体重減少、悪心、嘔吐、吐血、下血、貧血などの症状が出現します。
治療の中心は手術療法です。早期胃がんでは内視鏡的切除、進行がんでは胃の部分切除または全摘術が行われます。進行がんでは、化学療法も併用されます。
看護のポイントは、術前の栄養状態と貧血の改善、術後の疼痛コントロール、早期離床の促進、腸蠕動の回復の観察、創部とドレーンの管理です。特に重要なのは、術後の食事指導です。ダンピング症候群を予防するため、少量頻回の食事、糖質を控える、食事中の水分を控えるなどの具体的な方法を指導します。
胃全摘術後は、食事量が減少し、体重減少が続くことがあるため、高カロリー・高タンパク質の食事を1日5〜6回に分けて摂取するよう支援します。また、ビタミンB12や鉄の吸収障害に対する補充療法も必要です。
がんの診断を受けた患者さんの心理的ショックは大きく、不安や恐怖に寄り添うケアが重要です。特に、術後の食生活の変化に対する不安が強いため、具体的な対処方法を提示し、「食事の工夫により普通の生活ができる」という希望を持てるよう支援します。
実習では、患者さんの栄養状態と貧血の程度を評価し、術前から術後の回復過程における変化を観察する力を養いましょう。また、術後の腸蠕動の回復を評価し、早期離床を促進する看護介入の重要性を理解してください。さらに、ダンピング症候群などの術後特有の合併症について学び、予防のための食事指導ができるよう知識を深めましょう。
胃がんは、早期発見により良好な予後が期待できる疾患です。検診の重要性を患者さんや家族に伝え、ピロリ菌除菌の意義についても説明できるようにしておきましょう。患者さんが希望を持って治療に臨み、術後も質の高い生活を送れるよう、根拠に基づいた看護を実践していきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
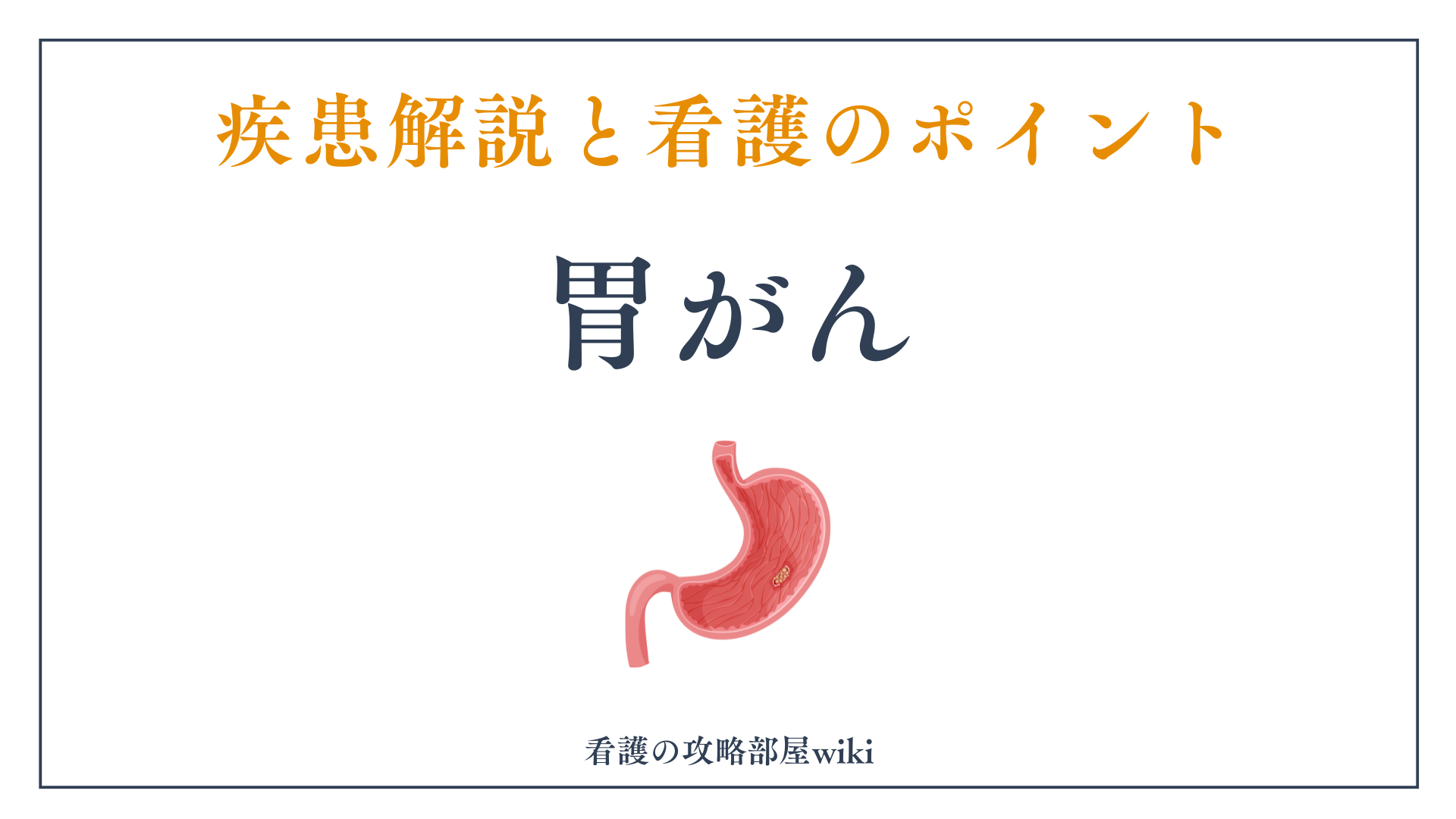


コメント