疾患概要
定義
乳がんは、乳腺組織に発生する悪性腫瘍です。大部分は乳管から発生する乳管がん(約90%)で、残りは小葉から発生する小葉がんです。がん細胞が乳管や小葉内にとどまっている状態を非浸潤がん、基底膜を破って周囲に広がった状態を浸潤がんと呼びます。浸潤がんはリンパ節や遠隔臓器に転移する可能性があります。
疫学
乳がんは日本人女性の約9人に1人が生涯で罹患する最も頻度の高いがんです。年間約9万人が新たに診断され、死亡者数は年間約1万4千人に上ります。40〜60代に最も多く発症しますが、近年は若年層での発症も増加傾向にあります。欧米と比較すると日本では40〜50代にピークがあり、比較的若い年齢での発症が特徴です。早期発見により予後は改善しており、5年相対生存率は約92%です。
原因
乳がんの発症には複数の危険因子が関与します。エストロゲン曝露期間の長期化が最も重要で、初経年齢が早い、閉経年齢が遅い、出産経験がない、初産年齢が高い、授乳経験がないなどが該当します。また、家族歴も重要で、特に第一度近親者(母、姉妹、娘)に乳がん患者がいる場合はリスクが2〜3倍になります。BRCA1/BRCA2遺伝子変異を持つ場合は生涯リスクが50〜80%と非常に高くなります。その他、肥満、飲酒、運動不足なども危険因子として知られています。
病態生理
乳がんは乳管や小葉の上皮細胞の遺伝子変異により発生します。初期段階では乳管内や小葉内にとどまっていますが、進行すると基底膜を破って浸潤し、血管やリンパ管に侵入します。リンパ行性転移では腋窩リンパ節に最初に転移することが多く、さらに進行すると鎖骨上リンパ節や対側のリンパ節にも広がります。血行性転移では骨、肺、肝臓、脳などに転移しやすい特徴があります。乳がんはホルモン受容体の有無により性質が異なり、エストロゲン受容体陽性がんは内分泌療法が有効ですが、トリプルネガティブ乳がんは治療選択肢が限られます。
症状・診断・治療
症状
初期の乳がんは多くの場合無症状で、検診や自己触診で発見されることが多いです。最も多い症状は乳房のしこりで、硬く、境界不明瞭で、動きにくいのが特徴です。その他、乳頭からの血性分泌物、乳房の皮膚の変化(えくぼ症状、オレンジピール様皮膚)、乳頭の陥没や変形、腋窩リンパ節の腫大などが見られます。進行すると乳房の疼痛や潰瘍形成、遠隔転移による症状(骨痛、呼吸困難、黄疸など)が出現します。
診断
診断には画像検査と病理検査を組み合わせます。スクリーニングにはマンモグラフィが標準的に用いられ、微細石灰化や腫瘤像を検出します。超音波検査は高濃度乳房や若年者に有用で、腫瘤の性状評価に優れています。MRI検査は病変の広がりや多発病変の評価に用いられます。確定診断には針生検(細胞診または組織診)が必須で、がんの組織型、悪性度、ホルモン受容体(ER、PgR)、HER2、Ki-67などを評価します。これらの情報はサブタイプ分類と治療方針の決定に重要です。
治療
乳がん治療は集学的治療が基本で、手術、放射線療法、薬物療法を組み合わせます。手術には乳房温存療法と乳房全切除術があり、温存療法の場合は術後に放射線療法を行います。センチネルリンパ節生検により不要な腋窩リンパ節郭清を避け、リンパ浮腫のリスクを減らします。薬物療法はサブタイプにより異なり、ホルモン受容体陽性では内分泌療法(タモキシフェン、アロマターゼ阻害薬)、HER2陽性では抗HER2療法(トラスツズマブなど)、再発リスクが高い場合は化学療法を行います。乳房再建は一次再建(がん切除と同時)または二次再建(術後一定期間後)が可能です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- ボディイメージ混乱:乳房切除や脱毛によるボディイメージの変化
- 不安:がん診断、治療、再発、死への不安
- 活動耐性低下:化学療法や放射線療法による倦怠感
ゴードン機能的健康パターン
自己知覚-自己概念パターンでは、乳房喪失や外見の変化が女性としてのアイデンティティに与える影響を評価します。患者の多くは深い悲しみや喪失感を経験するため、十分な心理的サポートが必要です。コーピング-ストレス耐性パターンでは、がん診断による心理的ストレスへの対処能力を評価し、家族や友人のサポート状況、過去の危機的状況への対処方法などを確認します。役割-関係パターンでは、治療が仕事や家庭内役割に与える影響を評価し、必要に応じて社会的サポートの調整を行います。
ヘンダーソン14基本的ニード
清潔と皮膚の統合性を保つニードでは、術後の創部管理、ドレーン管理、放射線療法による皮膚炎のケアが重要です。患側上肢の清潔保持の方法やリンパ浮腫予防のための注意点を指導します。安全なニードでは、化学療法による骨髄抑制時の感染予防、転倒予防、リンパ浮腫予防のための患側上肢の保護について指導します。学習のニードでは、疾患や治療に関する正確な情報提供、自己管理方法の指導、リハビリテーションの実施方法などを教育します。
看護計画・介入の内容
- 心理的支援:がん告知後の心理的ケア、ボディイメージの変化への支援、ピアサポートグループの紹介、必要に応じて精神科やカウンセラーへの橋渡し
- 術後管理:創部・ドレーン管理、疼痛管理、患側上肢のリハビリテーション指導、リンパ浮腫予防のための生活指導
- 化学療法の副作用管理:悪心・嘔吐対策、骨髄抑制時の感染予防指導、脱毛への対処(ウィッグや帽子の情報提供)、倦怠感への対応
よくある疑問・Q&A
Q: 乳房を切除すると女性ホルモンが出なくなりますか?
A: いいえ、女性ホルモンは主に卵巣から分泌されるため、乳房切除によってホルモン分泌が減少することはありません。ただし、治療の一環として内分泌療法を行う場合は、薬剤によってホルモンの働きを抑えることがあります。
Q: 手術後、どのくらいで日常生活に戻れますか?
A: 乳房温存療法では術後3〜5日程度、乳房全切除術では5〜7日程度で退院できることが多いです。軽い家事は退院後すぐに可能ですが、重いものを持つなどの動作は術後2〜3週間は避けます。患側上肢のリハビリテーションを段階的に進めることで、徐々に日常生活に戻ることができます。
Q: リンパ浮腫は必ず起こりますか?
A: いいえ、必ずしも起こるわけではありません。センチネルリンパ節生検のみの場合、リンパ浮腫の発生率は5%以下と低いです。腋窩リンパ節郭清を行った場合でも約20〜30%程度です。予防のために、患側上肢での採血や血圧測定を避ける、重いものを持たない、きつい衣服を避けるなどの注意が必要です。
Q: 化学療法で必ず髪が抜けますか?
A: 使用する抗がん剤の種類によって異なります。タキサン系やアントラサイクリン系の抗がん剤では高い確率で脱毛が起こりますが、一部の薬剤では脱毛が軽度または起こらないこともあります。脱毛は治療終了後、多くの場合2〜3ヶ月で再び生え始めます。
Q: 授乳経験がないと乳がんになりやすいのですか?
A: 授乳経験がないことは乳がんのリスク因子の一つですが、それだけで乳がんになるわけではありません。授乳により月経が止まる期間が長くなり、生涯のエストロゲン曝露期間が短くなることで、わずかにリスクが低下すると考えられています。
Q: 遺伝性乳がんはどのくらいの割合ですか?
A: 乳がん全体の約5〜10%が遺伝性で、そのうち最も多いのがBRCA1/BRCA2遺伝子変異によるものです。家族歴が強い場合や若年発症の場合は、遺伝カウンセリングや遺伝子検査を検討することがあります。
まとめ
乳がんは日本人女性の約9人に1人が罹患する最も頻度の高いがんですが、早期発見により予後は良好で、5年生存率は約92%です。看護師は早期発見の重要性を啓発し、検診受診や自己触診の方法を指導する役割を担います。
患者の多くはボディイメージの変化や女性性の喪失に深い悲しみを感じるため、心理的支援が非常に重要です。治療選択においても、乳房温存や再建など、患者の価値観や希望を尊重した意思決定支援が求められます。
治療は集学的治療が基本となり、手術、放射線療法、薬物療法を長期間継続することが多いため、副作用管理や生活の質の維持が重要な看護目標となります。特にリンパ浮腫予防、化学療法の副作用対策、患側上肢のリハビリテーションは実践的な看護技術として習得が必要です。
実習では、患者の個別性を重視したケアを心がけ、特にがん告知後の心理的サポートやボディイメージの変化への支援に注目しましょう。また、家族への支援も忘れずに、患者を取り巻く環境全体をアセスメントすることが、包括的な看護につながります。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
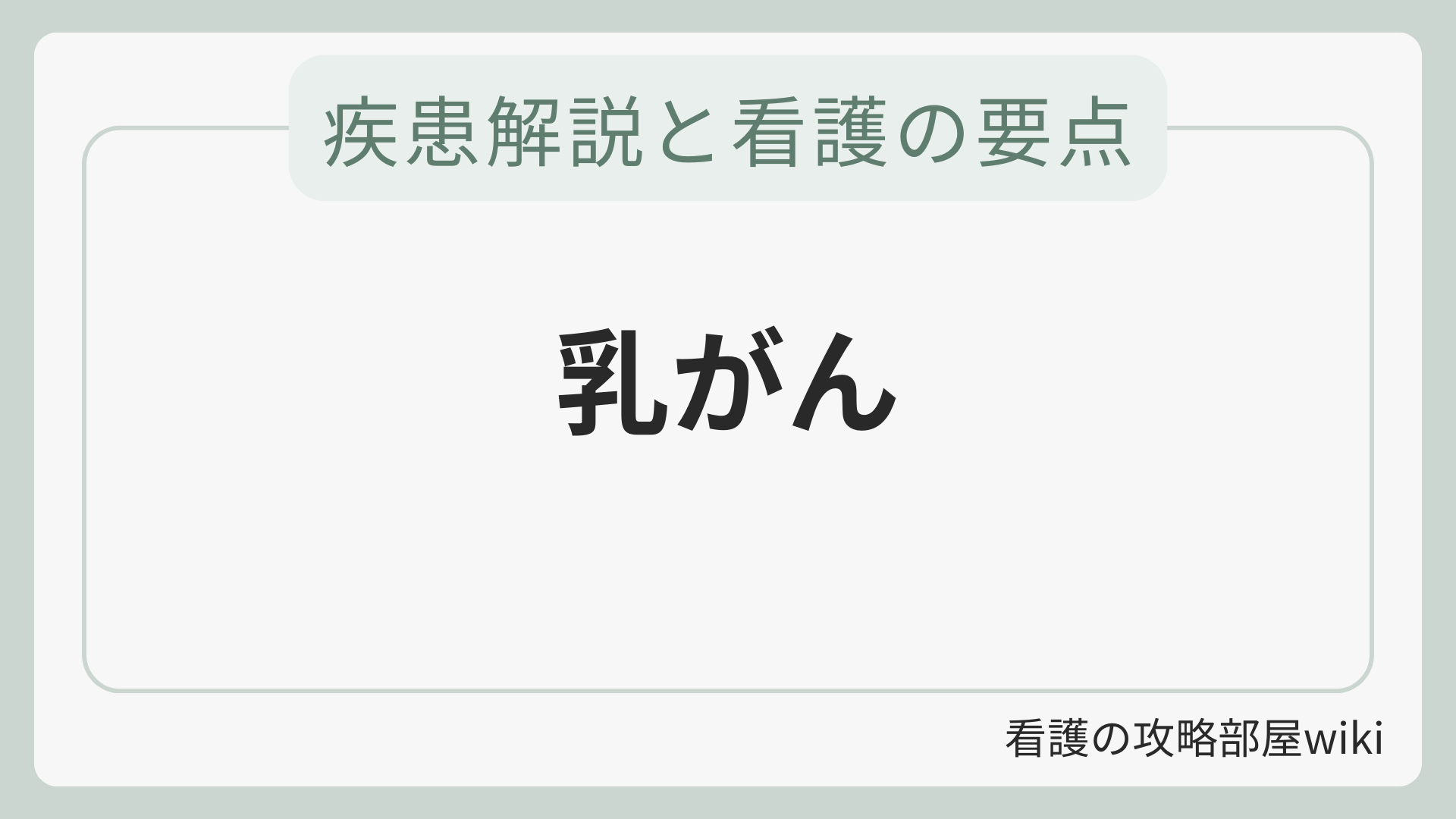
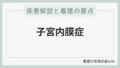
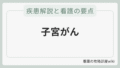
コメント