本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
今回の事例
基本情報
A氏は85歳の女性で、身長148cm、体重42kg(BMI 19.2)である。5年前に夫を亡くし、現在はマンション3階に独居している。長女(54歳)と次男(50歳)が近隣市に在住しており、キーパーソンは週2回の訪問をしている長女である。A氏は元会社員で、定年後は趣味の茶道を活かして自宅で教室を開いており、教授資格を保持している。温厚な性格ながら自己主張が強く、医療者の助言を受け入れにくい面がある。また、仏教信仰があり入院前は週1回の読経会に参加していた。感染症の既往やアレルギー歴は特になく、認知力は良好である。入院時のMMSEは28/30点で、計算と遅延再生で各1点の減点があったものの、日常生活に支障をきたすような認知機能の低下は認められていない。
病名
右大腿骨転子部骨折 術式:γネイル固定術
既往歴と治療状況
A氏は70歳時に骨粗鬆症と診断され(T値 -3.2)、現在アレンドロン酸、カルシウム製剤、活性型ビタミンD3製剤を内服中である。68歳時より高血圧症に対してアムロジピン5mg/日の内服を開始し、72歳からは高脂血症に対してロスバスタチン2.5mg/日の内服を継続している。また、両側変形性膝関節症を有しており、これまで転倒のリスク要因となっていた。
入院から現在までの情報
A氏は3週間前、自宅マンションの玄関で転倒し、右大腿部痛を自覚した。訪問中の長女により救急搬送され、X線検査で右大腿骨転子部骨折と診断された。全身状態が良好であったため、同日緊急でγネイル固定術が施行された。術後経過は概ね良好で、術後1週間目からベッド上での関節可動域訓練とレッグリフト、2週間目には平行棒内歩行訓練を開始した。現在は歩行器を使用して15m程度の歩行が可能である。疼痛は安静時NRS 1/10、運動時3/10と管理できているが、夜間の不眠と軽度の不安症状が出現している。検査所見では軽度の貧血(Hb 11.2g/dL)と低アルブミン血症(Alb 3.5g/dL)を認めているが、その他の検査値は概ね正常範囲内である。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは血圧142/84mmHg、脈拍78回/分、体温36.8℃、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)であった。現在のバイタルサインは安定しており、血圧132/78mmHg、脈拍68回/分、体温36.5℃、呼吸数14回/分、SpO2 97%(室内気)を維持している。
食事と嚥下状態
入院前は一日3食を自力で摂取し、栄養バランスにも気を配っていた。嚥下機能は良好で、食事にかかる時間は1食あたり20~30分程度であり、水分摂取量は1日1500ml程度を意識的に摂取していた。喫煙歴・飲酒歴はない。
現在は食事を自力摂取できているが、疲労のため15分程度で休憩が必要となっている。嚥下機能に問題なく、常食を摂取している。水分摂取は1日1200~1400mlで、定時の声掛けと記録表を使用して管理されている。喫煙・飲酒は入院前同様にない。
排泄
入院前は排尿排便ともに自立しており、排尿は1日6~7回、排便は規則的に1日1回朝食後にトイレで行われていた。必要時に市販の酸化マグネシウムを服用することはあったが、常用はしていなかった。
現在はポータブルトイレを使用して自立しており、排尿は1日6~7回、排便は1日1回と入院前と同様の回数を維持している。立ち上がりには手すりを使用し、必要時に軽介助を要する。夜間は1~2回の排尿がある。便秘予防のため、看護師の管理下で酸化マグネシウム330mg錠を1日1回朝食後に内服しており、便性状はブリストルスケール4型で概ね良好である。
睡眠
入院前は就寝時間が21時頃で起床は6時頃と規則正しい生活を送っており、日中の活動性も保たれていた。夜間は良眠でき、入眠剤等の使用はなかった。
現在は21時頃には床につくものの、術後の環境の変化や不安感から入眠までに1時間程度かかることがある。また、夜間の排尿や疼痛により1~2回の中途覚醒がみられ、再入眠に時間を要している。起床時間は6時頃と入院前と変わらないが、睡眠の質の低下を訴えている。医師と相談の上、不眠時の頓用薬としてゾルピデム5mgが処方されているが、本人の希望で内服は最小限にとどめられている。日中は午後2時頃から1時間程度の臥床休息を取っている。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼があり、読書時と茶道の際には近用眼鏡を使用している。聴力は左右ともに軽度低下があるものの、通常の会話に支障はない。知覚は年齢相応で、術側の右下肢に術後の創部痛以外の異常感覚はない。
コミュニケーションは良好で、会話の理解力も保たれている。元会社員としての経験もあり、論理的な思考と表現が可能である。温厚な性格だが、自己主張が強く、医療者の助言を受け入れにくい面がある。
仏教信仰があり、入院前は週1回の読経会に参加していた。入院中も仏壇の写真を枕元に置き、毎朝読経の時間を設けている。信仰は精神的な支えとなっており、回復への意欲にもつながっている。
動作状況
入院前は変形性膝関節症による長距離歩行時の膝の疲労感はあったものの、屋内外の移動は自立していた。変形性膝関節症による膝折れで2回の転倒歴があったが、大きな怪我には至らなかった。
現在は歩行器を使用して15m程度の歩行が可能であるが、立ち上がり動作では手すりと軽介助を要する。ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗時には手すりを使用し、必要時は軽介助を受けている。排泄動作はポータブルトイレを使用して概ね自立しているものの、立ち上がり時の安全確保のため見守りが必要な場合がある。入浴は週2回実施しており、浴室への移動は車椅子を使用し、洗体時には介助を要する。更衣動作については、上衣の着脱は自立しているが、下衣の着脱は疼痛と可動域制限により軽介助を必要としている。今回の骨折を機に、リハビリテーションを通じて転倒予防への意識が高まっている。
内服中の薬
定期内服薬
- アレンドロン酸錠35mg 1錠 週1回 起床時 空腹時
- 沈降炭酸カルシウム錠500mg 3錠 毎食後
- アルファカルシドール錠1.0μg 1錠 朝食後
- アムロジピン錠5mg 1錠 朝食後
- ロスバスタチン錠2.5mg 1錠 夕食後
- 酸化マグネシウム錠330mg 1錠 朝食後
頓用薬
- ゾルピデム錠5mg 1錠 不眠時
入院前は自己管理で、曜日別の薬箱を使用し確実に内服できていた。入院後は安静度の制限や術後の疼痛管理の必要性から、現在は看護師管理とされている。今後、退院に向けて自己管理への移行が検討されている。
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 現在(術後3週間) |
|---|---|---|---|
| WBC | 4,000-9,000/μL | 7,800 | 6,500 |
| RBC | 380-500万/μL | 355 | 348 |
| Hb | 11.5-15.0g/dL | 11.5 | 11.2 |
| Ht | 35-45% | 34.8 | 34.2 |
| Plt | 15-35万/μL | 22.5 | 23.1 |
| TP | 6.5-8.2g/dL | 6.8 | 6.5 |
| Alb | 3.8-5.2g/dL | 3.8 | 3.5 |
| AST | 10-35U/L | 28 | 25 |
| ALT | 5-40U/L | 32 | 28 |
| BUN | 8-20mg/dL | 18 | 16 |
| Cr | 0.4-1.1mg/dL | 0.8 | 0.7 |
| Na | 135-145mEq/L | 140 | 138 |
| K | 3.5-5.0mEq/L | 4.2 | 4.0 |
| Cl | 98-108mEq/L | 102 | 101 |
| CRP | 0.3以下mg/dL | 0.8 | 0.4 |
軽度の貧血と低アルブミン血症が認められており、骨癒合促進とリハビリテーション継続のための栄養管理が重要である。
今後の治療方針と医師の指示
骨折部の確実な癒合と基本的ADLの自立を目標に治療が継続される。骨密度検査でのT値の低下(-3.2)を受けて、骨粗鬆症に対する投薬内容の見直しが検討中である。リハビリテーションは現在の進捗状況を考慮し、歩行器歩行の距離延長と応用動作の練習を進めるとともに、両側の変形性膝関節症による膝折れのリスクも考慮し、下肢筋力強化を継続する。
医師からの指示として、1日2単位の理学療法を継続し、平行棒内歩行から歩行器歩行への移行を進め、最終的には杖歩行の獲得を目指すこととなっている。病棟内の活動は歩行器使用を許可されているが、夜間のトイレ歩行は転倒リスクを考慮し、ポータブルトイレを使用することとなっている。創部は感染徴候なく経過しているため消毒は不要とされ、シャワー浴が許可されている。また、骨癒合促進のため、タンパク質とカルシウムを意識した食事摂取が指導されている。退院時期については、骨癒合の状態とADLの自立度を評価しながら、4週間後を目途に検討されることとなっている。
退院後は2週間毎の外来診察とリハビリテーション外来(週2回)が予定されている。また、骨粗鬆症に対する投薬内容の調整と、再骨折予防のための生活指導が行われる方針である。
本人と家族の想いと言動
A氏は3ヶ月以内の杖歩行自立と茶道教室再開を強く希望している。茶道の教授資格を持っており、「早く教室に戻りたい。生徒たちが待っているから」と、リハビリテーションにも意欲的に取り組んでいる。一方で、夜間の不眠や軽度の不安症状が出現しており、「このまま元通りの生活に戻れるだろうか」という不安も抱えている。医療者の助言に対しては自己主張が強く受け入れにくい面があり、「今までも自分のやり方でやってきた」と話すことがある。
長女は週2回の面会時に、A氏の回復を気遣いながらも、「早く元の生活に戻りたがっているけれど、無理をさせたくない」と心配している。次男とともに、安全な在宅復帰と転倒予防策の確立を最優先に考えており、「もう一度転んでしまったら大変」と不安を表出している。特に長女は、仕事と介護の両立に対する不安も語っており、「できるだけ母の希望に沿いたいが、私たちにできるサポートには限界がある」と話している。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏が自身の健康状態や骨折をどのように認識し、これまでどのような健康管理を行ってきたか、そして今後の回復に向けてどのような姿勢を持っているかを評価することが重要です。特に、医療者の助言を受け入れにくい面がある点や、強い回復意欲を持っている点など、A氏の個別性を踏まえたアセスメントが求められます。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
骨折と既往歴に対する本人の認識
A氏は右大腿骨転子部骨折という重大な外傷を経験していますが、「早く教室に戻りたい。生徒たちが待っているから」と述べており、茶道教室の再開という明確な目標を持っています。この発言からは、骨折が一時的なものであり、回復すれば元の生活に戻れるという前向きな認識が読み取れます。一方で、「このまま元通りの生活に戻れるだろうか」という不安も表出しており、回復への意欲と不安が混在している状態を踏まえて記述するとよいでしょう。
また、A氏は骨粗鬆症、高血圧症、高脂血症、両側変形性膝関節症という複数の慢性疾患を抱えていますが、これらの疾患が今回の骨折リスクにどのように関連していたか、本人がどの程度理解しているかという視点でアセスメントすることが重要です。特に変形性膝関節症による膝折れで過去に2回の転倒歴があることから、転倒リスクについての認識がどの程度あったかを考えるとよいでしょう。
これまでの健康管理行動
A氏は入院前、定期内服薬を曜日別の薬箱を使用して確実に内服できていました。これは慢性疾患に対する自己管理能力が高いことを示しており、退院後の服薬管理における強みとなる情報です。また、食事についても栄養バランスに気を配り、水分摂取量も1日1500ml程度を意識的に摂取していたことから、健康に対する意識が高い方であることがわかります。これらの健康管理行動を踏まえて、A氏の健康管理能力をどのように評価するか考えるとよいでしょう。
一方で、変形性膝関節症による転倒リスクがありながら、具体的な転倒予防策を講じていた様子は記載されていません。今回の骨折を機に、リハビリテーションを通じて転倒予防への意識が高まっているという記載がありますので、この変化に着目して記述することが大切です。
医療者の助言に対する姿勢
A氏は温厚な性格ながら自己主張が強く、医療者の助言を受け入れにくい面があります。「今までも自分のやり方でやってきた」という発言は、A氏がこれまでの自分の健康管理方法に自信を持っていることを示していますが、同時に新しい情報や助言を取り入れることへの抵抗感も表れています。この特性は、退院後の生活指導や再発予防のための行動変容を促す際に、どのようなアプローチが適切かを考える上で重要な情報となります。看護師がどのように関わればA氏の自己決定を尊重しながら、必要な健康管理行動を促すことができるか、という視点でアセスメントするとよいでしょう。
家族の健康管理への関与
長女は週2回訪問しており、今回の骨折時も救急搬送を手配するなど、適切な対応ができています。また、「無理をさせたくない」「もう一度転んでしまったら大変」という発言からは、家族が転倒予防の重要性を認識していることがわかります。一方で、長女は「仕事と介護の両立に対する不安」や「できるだけ母の希望に沿いたいが、私たちにできるサポートには限界がある」と述べており、家族の支援能力や限界についても考慮する必要があります。家族のサポート体制を踏まえて、どのような退院支援が必要かという視点を持つことが重要です。
アセスメントの視点
A氏の健康知覚-健康管理パターンをアセスメントする際は、高い自己管理能力と強い回復意欲という強みと、医療者の助言を受け入れにくいという特性のバランスを考えることが大切です。また、骨粗鬆症や変形性膝関節症といった既往歴が今回の骨折にどのように関連していたか、そしてそれをA氏と家族がどの程度理解しているかという視点も重要です。さらに、3ヶ月以内の茶道教室再開という目標が現実的かどうか、そのギャップをどのように埋めていくかという点も考慮するとよいでしょう。
ケアの方向性
A氏の自己決定を尊重しながら、骨折の原因となった転倒リスク因子についての理解を深める支援が必要です。特に骨粗鬆症と変形性膝関節症の管理の重要性、再骨折予防のための生活環境の見直しについて、A氏が納得して受け入れられるような教育的アプローチを検討することが大切です。また、家族の支援能力と限界を考慮した退院計画を立案し、必要に応じて社会資源の活用についても検討する必要があります。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、A氏の栄養状態が骨折の治癒やリハビリテーションの進行に十分であるかを評価することが重要です。特に軽度の貧血と低アルブミン血症が認められており、高齢者の骨折後という状況を考慮した栄養管理の必要性を検討する必要があります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
身体計測値と栄養状態の評価
A氏の身長は148cm、体重は42kg、BMIは19.2です。BMI 19.2は基準範囲内ではありますが、高齢者における適正BMIは若年者よりやや高めが望ましいとされていることを踏まえて考えるとよいでしょう。85歳という年齢や骨折後のリハビリテーション期であることを考慮すると、現在の体重が十分であるか、それとも増加が必要かという視点でアセスメントすることが重要です。
また、検査データでは入院時Hb 11.5g/dL、術後3週間でHb 11.2g/dLと軽度の貧血が持続しています。Alb値も入院時3.8g/dLから術後3週間で3.5g/dLへと低下しており、基準値の下限を下回っています。これらの数値は、栄養状態がやや低下傾向にあることを示唆しており、骨癒合やリハビリテーションの進行に影響を与える可能性があることを踏まえて記述するとよいでしょう。
食事摂取状況と嚥下機能
入院前のA氏は一日3食を自力で摂取し、栄養バランスにも気を配っていました。嚥下機能は良好で、1食あたり20〜30分程度で食事を終えることができていました。これらの情報は、A氏が食事に関して自立しており、適切な食習慣を持っていたことを示しています。
現在は常食を摂取できていますが、疲労のため15分程度で休憩が必要となっています。これは術後の体力低下や活動量の減少によるものと考えられますが、食事時間の短縮が摂取量の減少につながっていないか、という視点で観察することが大切です。嚥下機能に問題はないものの、疲労による食事摂取量の低下がAlb値の低下に関連している可能性も考慮するとよいでしょう。
水分摂取と管理
入院前は1日1500ml程度の水分を意識的に摂取していましたが、現在は1日1200〜1400mlとやや減少しています。定時の声掛けと記録表を使用して管理されているという情報から、A氏自身の水分摂取への意識が入院前より低下している可能性や、トイレ歩行の負担から水分摂取を控えている可能性も考えられます。高齢者は脱水のリスクが高く、また便秘予防の観点からも適切な水分摂取は重要ですので、この点に着目して記述するとよいでしょう。
骨折治癒と栄養の関係
医師からはタンパク質とカルシウムを意識した食事摂取が指導されています。A氏は骨粗鬆症(T値-3.2)があり、アレンドロン酸、カルシウム製剤、活性型ビタミンD3製剤を内服していますが、骨折の治癒には薬物療法だけでなく、食事からの栄養摂取も重要です。特にタンパク質は創傷治癒や筋力維持に不可欠であり、低アルブミン血症の改善にも必要です。カルシウムとビタミンDは骨形成に直接関与しますので、これらの栄養素の摂取状況を踏まえて記述することが大切です。
アセスメントの視点
A氏の栄養-代謝パターンをアセスメントする際は、入院前の良好な食習慣という強みと、現在の軽度貧血・低アルブミン血症という課題のバランスを考えることが重要です。また、85歳という年齢、骨折後のリハビリテーション期、骨粗鬆症という背景を踏まえて、どの程度の栄養摂取が必要かという視点を持つことが大切です。さらに、疲労による食事時間の短縮や水分摂取量の減少が、栄養状態にどのような影響を与えているかという点も考慮するとよいでしょう。
ケアの方向性
骨癒合とリハビリテーションの進行を支えるために、タンパク質とカルシウムを十分に含む食事内容の検討が必要です。疲労による食事摂取への影響を軽減するため、食事時間の調整や休憩の取り方を工夫することも重要です。また、水分摂取量の維持・改善に向けて、A氏の水分摂取への意識を高める支援や、トイレ歩行の負担を軽減する環境調整を検討する必要があります。貧血や低アルブミン血症の改善に向けて、栄養士と連携した食事指導や、必要に応じた栄養補助食品の活用も考慮するとよいでしょう。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
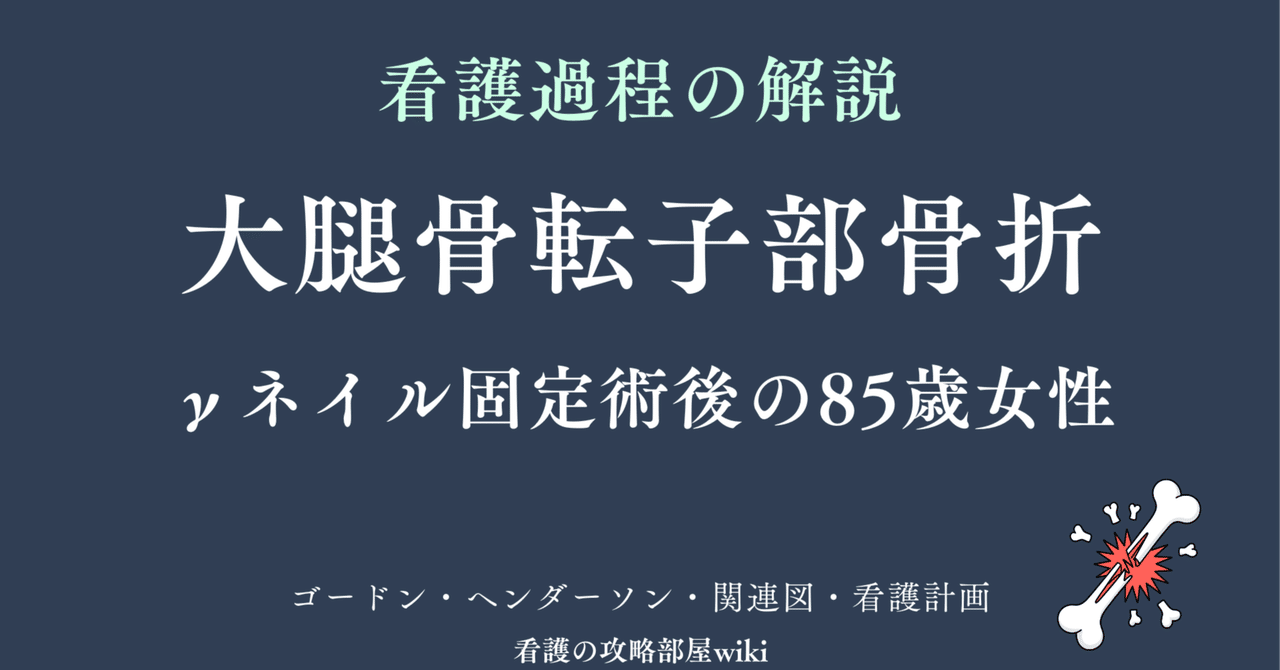
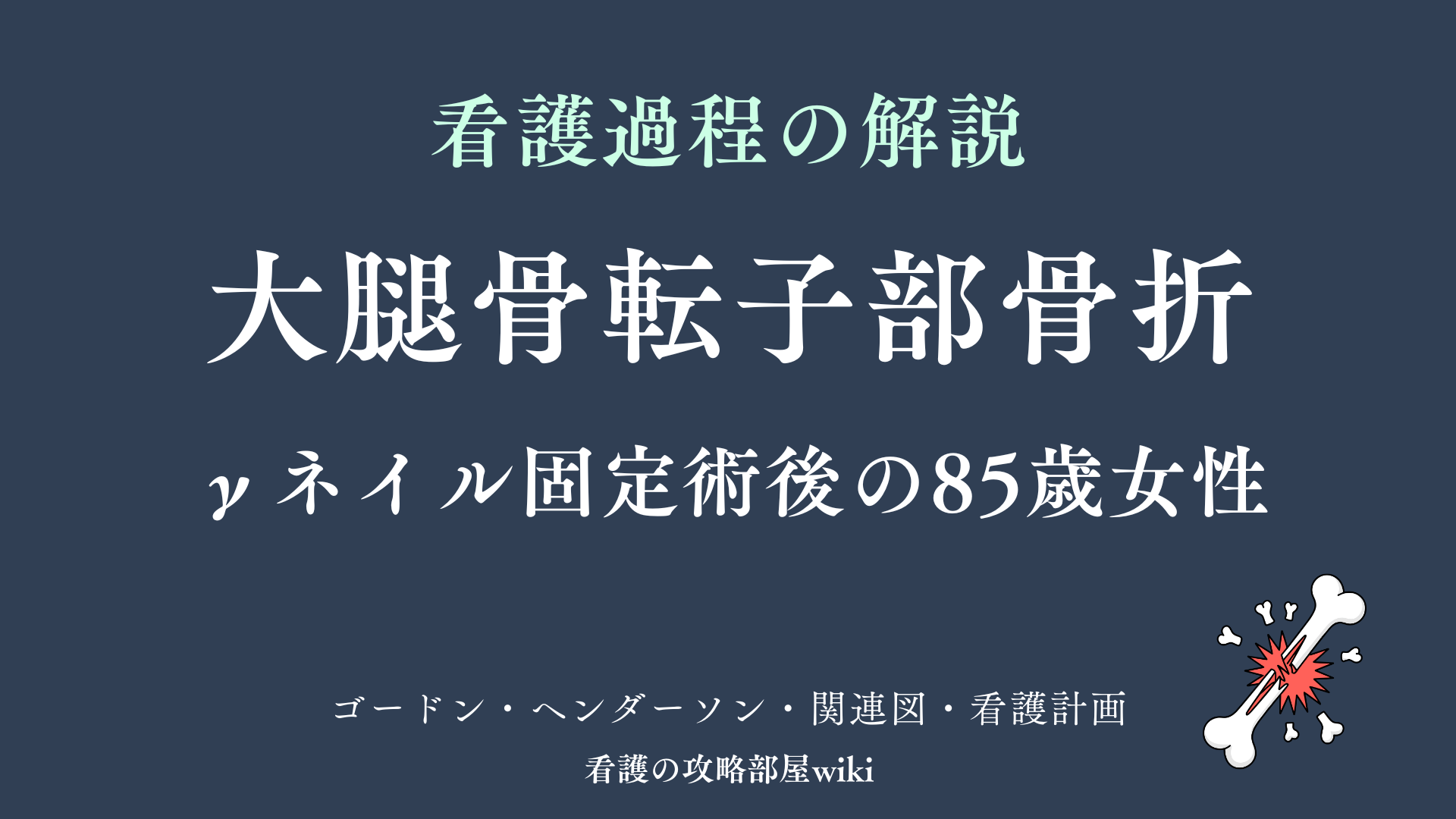


コメント