概要
母性・周産期外来とは、妊娠期から出産までの女性とその胎児を対象とした外来診療部門です。正常な妊娠経過の管理から、ハイリスク妊娠の専門的ケアまで幅広く対応し、安全な出産に向けたサポートを提供しています。なお、周産期とは妊娠22週から出生後7日未満までの期間を指します。
外来での観察において重要な基礎知識として、妊娠中の母体は著しい生理的変化を経験することを理解しておく必要があります。循環器系では心拍出量が40-50%増加し、これにより血圧や脈拍数の変動が起こります。呼吸器系では横隔膜の挙上により呼吸困難感が生じやすく、泌尿器系では腎機能の変化により蛋白尿や浮腫が出現することがあります。また、妊娠ホルモンの影響で悪心・嘔吐や情緒の変化も観察されます。
現在、日本では約15-20%がハイリスク妊娠に該当し、35歳以上の高齢出産の増加により妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスクが高まっています。外来では、これらの正常な生理的変化と病的変化の鑑別が重要な観察ポイントとなります。特に周産期(妊娠22週から出生後7日未満)は母児ともに最も注意深い観察が必要な時期であり、短時間の外来診察でも見逃してはいけない異常の早期発見が求められます。
症状・診断・治療
身体変化・症状
母性・周産期外来で遭遇する身体変化や症状は妊娠週数や合併症によって様々です。妊娠初期(~15週)では、悪心・嘔吐(つわり)が最も多く、重症妊娠悪阻では脱水や電解質異常を呈します。妊娠中期(16~27週)では、比較的安定していますが、貧血や便秘などの症状が現れやすくなります。妊娠後期(28週~)では、子宮の増大による胃部圧迫感、息切れ、下肢浮腫、腰痛などが頻発します。危険な症状として、頭痛・視野障害・上腹部痛(妊娠高血圧症候群)、性器出血(前置胎盤、常位胎盤早期剥離)、持続する腹痛・子宮収縮(切迫早産)などがあり、これらは緊急対応が必要です。
アセスメント・評価
母性・周産期外来でのアセスメントは、詳細な問診、身体診察、各種検査により行われます。初診時には、月経歴、妊娠歴、既往歴、家族歴、服薬歴を詳細に聴取し、妊娠週数の確定を行います。定期健診では、体重測定、血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、子宮底長測定、腹囲測定、胎児心音聴取を実施します。超音波検査は胎児の発育評価、胎盤位置の確認、羊水量の評価に不可欠です。血液検査では、血算、生化学検査、血糖値、感染症スクリーニング(HBs抗原、HCV抗体、梅毒、HIV、HTLV-1など)を行います。妊娠中期には胎児染色体異常スクリーニング、妊娠後期にはGBS培養検査も重要な診断項目となります。
ケア・管理
母性・周産期外来でのケアは、正常妊娠の管理と異常妊娠への対応に大別されます。正常妊娠では、適切な体重管理指導、栄養指導、生活指導が中心となります。妊娠高血圧症候群では、降圧薬(メチルドパ、ラベタロールなど)の投与と厳重な母児監視を行います。妊娠糖尿病では、食事療法を基本とし、必要に応じてインスリン療法を導入します。切迫早産では、子宮収縮抑制剤(リトドリン、ニフェジピンなど)の投与と安静指導を行います。鉄欠乏性貧血では、鉄剤の経口投与を行い、重症例では鉄剤の静脈内投与も検討します。いずれの場合も、母児の安全を最優先とし、必要に応じて高次医療機関への紹介を迅速に判断することが重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
・妊娠に関連した悪心・嘔吐
・妊娠による身体変化に関連した不安
・初回妊娠に関連した知識不足
・妊娠高血圧症候群に関連した体液量過多
・妊娠糖尿病に関連した血糖値上昇リスク状態
・切迫早産に関連した活動制限
・経済的問題に関連した治療継続困難
・家族のサポート不足に関連した育児不安
・妊娠による体型変化に関連した自己概念の混乱
・分娩への恐怖に関連した不安
ゴードンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、妊娠という正常な生理的過程に対する理解度と、健康管理行動の実践状況を詳細にアセスメントします。多くの初産婦は妊娠に関する知識が不足しており、インターネットの情報に振り回されることも多いため、正確な情報提供と不安の軽減が重要です。また、喫煙や飲酒などの有害な生活習慣がある場合は、胎児への影響を説明し、行動変容を支援します。
活動-運動パターンでは、妊娠週数の進行に伴う身体的制約と日常生活動作への影響をアセスメントします。妊娠後期には腰痛や下肢浮腫により歩行困難となる場合があり、安全な日常生活の維持のための指導が必要です。切迫早産などで安静が必要な場合は、廃用症候群の予防と精神的ストレスの軽減を図ります。
認知-知覚パターンでは、妊娠による感覚の変化や学習ニーズをアセスメントします。妊娠中は集中力の低下や物忘れが増加することがあり、重要な情報は繰り返し確認することが大切です。また、胎動の感じ方や異常の早期発見方法について十分な教育を行います。
ヘンダーソンのポイント
呼吸のニードでは、妊娠後期の横隔膜挙上による呼吸困難感をアセスメントします。特に多胎妊娠や羊水過多症では呼吸困難が顕著となるため、適切な体位の指導(セミファーラー位など)と、必要に応じて酸素療法を検討します。
飲食のニードでは、妊娠初期のつわりによる摂食困難から妊娠後期の胃部圧迫感まで、妊娠週数に応じた栄養摂取の問題をアセスメントします。適切な体重増加(BMIに応じて7-12kg)を目標とし、栄養バランスの取れた食事指導を行います。妊娠糖尿病の場合は、血糖コントロールを考慮した食事療法が必要です。
排泄のニードでは、妊娠による便秘の増加と、妊娠後期の頻尿をアセスメントします。便秘に対しては食物繊維の摂取と適度な運動を勧め、必要に応じて下剤を処方します。頻尿については正常な生理的変化であることを説明し、尿路感染症の早期発見のための観察ポイントを指導します。
外来での観察の注意点
外来では限られた時間の中で効率的かつ的確な観察が求められるため、優先順位を明確にした観察が重要です。まず受付時から患者の歩行状態、表情、呼吸状態を観察し、全体的な印象をつかみます。特に妊娠後期では、顔面や手指の浮腫の程度を素早く確認することが大切です。
前回受診時との比較観察は外来の特徴的な観察ポイントです。体重増加のペース(週500g以上は要注意)、血圧の変動パターン、尿蛋白の推移を必ずチェックし、急激な変化がないか確認します。患者の自己申告による症状については、具体的な質問で詳細を確認することが重要です。「調子はいかがですか?」ではなく、「頭痛はありませんか?」「むくみはいつから?」「胎動は昨日何回感じましたか?」といった具体的な質問を行います。
緊急度の判断は外来看護師の重要な役割です。血圧140/90mmHg以上、蛋白尿2+以上、急激な体重増加、持続する頭痛や上腹部痛、性器出血、破水感、規則的な子宮収縮などは即座に医師に報告が必要な所見です。また、患者の不安や心配事も軽視せず、「いつもと違う感じ」という訴えには特に注意を払います。
家族からの情報収集も外来では重要です。特に初産婦の場合、夫や母親からの情報が診断の手がかりとなることがあります。家庭での様子、食事摂取状況、睡眠状態、精神状態の変化など、患者が気づいていない変化を家族が観察していることがあります。
看護計画・介入の内容
・妊娠週数に応じた身体変化の説明と不安軽減のための情報提供
・定期健診の重要性と検査結果の説明による治療継続への動機づけ
・適切な体重管理のための栄養指導と食事療法の支援
・妊娠高血圧症候群の早期発見のための自己血圧測定指導
・胎動カウントの方法と異常時の対応についての教育
・切迫早産予防のための生活指導と症状出現時の対応方法の指導
・分娩準備教育と育児準備のための情報提供
・家族を含めたサポート体制の構築と連携強化
・経済的問題に対する社会資源の活用支援
・精神的サポートとカウンセリングの提供
よくある疑問・Q&A
Q: 妊娠中の体重増加はどの程度が適切ですか? A: BMIによって推奨される体重増加量が異なります。やせ型(BMI18.5未満)の方は9-12kg、普通体型(BMI18.5-25.0未満)の方は7-12kg、肥満(BMI25.0以上)の方は個別に判断しますが5kg程度を目安とします。急激な体重増加は妊娠高血圧症候群のリスクを高めるため、週1kg以上の増加がある場合は注意が必要ですね。
Q: つわりがひどくて何も食べられません。赤ちゃんは大丈夫でしょうか? A: 妊娠初期の胎児は小さく、母体の蓄積された栄養で十分成長できます。ただし、1週間で体重が5%以上減少したり、尿中ケトン体が陽性になったりする場合は重症妊娠悪阻の可能性があるため、点滴治療が必要になることがあります。水分摂取を心がけ、食べられるものを少量ずつでも摂取することが大切です。
Q: 妊娠中に市販薬を飲んでも大丈夫ですか? A: 妊娠中の薬物使用は慎重に判断する必要があります。特に妊娠初期(4-10週)は器官形成期のため、薬物の影響を受けやすい時期です。市販薬であっても必ず医師に相談してから服用してください。アセトアミノフェンは比較的安全とされていますが、アスピリンやイブプロフェンなどのNSAIDsは避けるべき薬剤です。
Q: 胎動を感じなくなったらどうすればいいですか? A: 妊娠20週頃から感じ始める胎動は、胎児の健康状態を知る重要な指標です。12時間以上胎動を感じない場合や、いつもより明らかに胎動が少ない場合は、すぐに医療機関を受診してください。胎動カウント(10回の胎動を感じるまでの時間を測定)を日常的に行い、異常の早期発見に努めることが大切です。
Q: 妊娠高血圧症候群と診断されました。どんな症状に注意すべきですか? A: 妊娠高血圧症候群では、頭痛、視野のかすみやちらつき、上腹部痛、急激な体重増加、手足の強いむくみなどの症状に注意が必要です。これらの症状は子癇(けいれん発作)の前兆症状の可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください。日常的な血圧測定と体重測定、適度な安静と塩分制限が重要な管理方法となります。
関連事例・症例へのリンク
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
看護過程の個別サポート
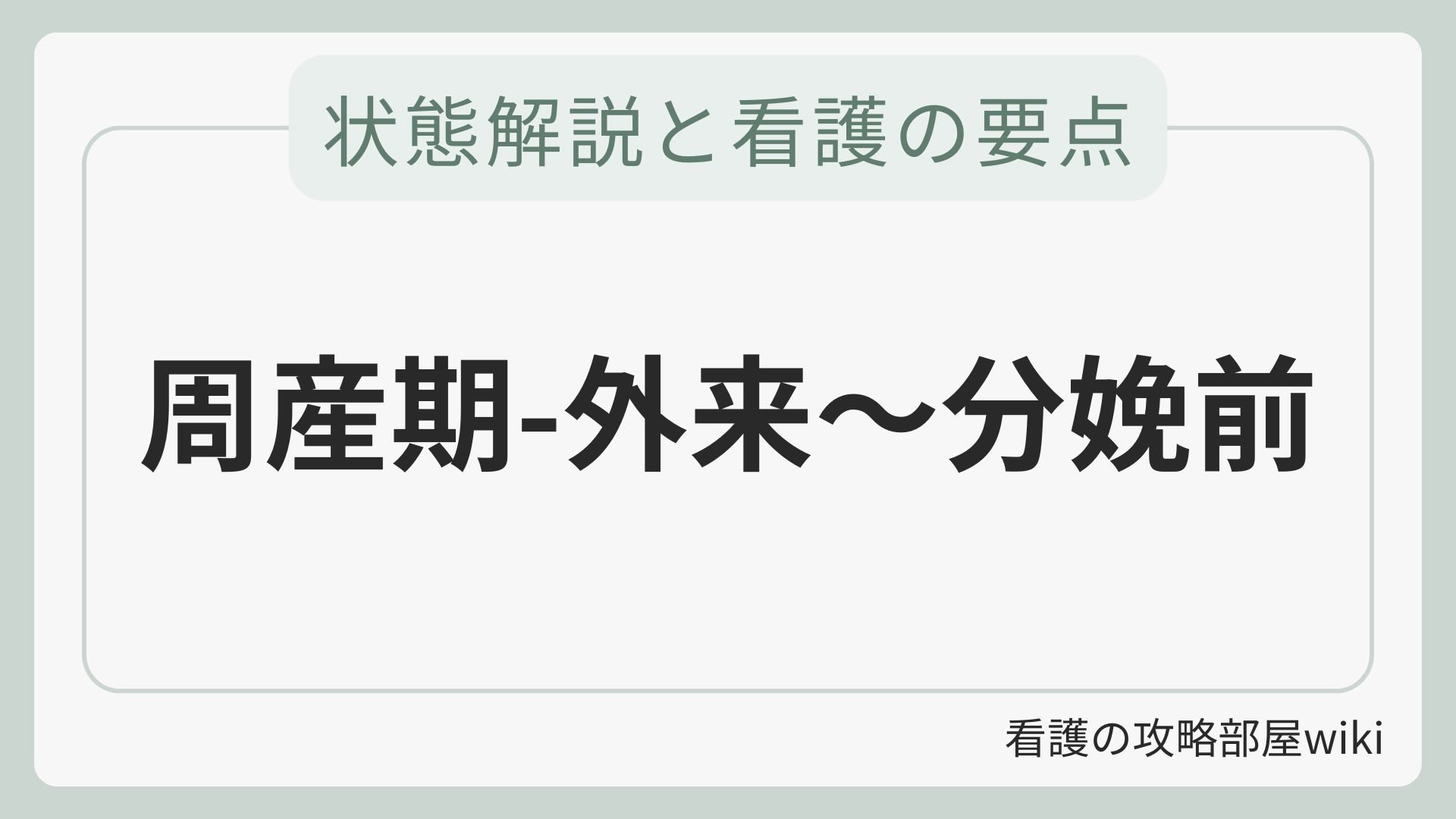
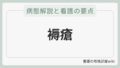
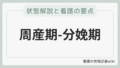
コメント