症状概要
定義
下痢とは、便の水分量が増加し、軟便または水様便が1日3回以上排泄される状態です。便秘とは、排便回数が週3回未満、または排便困難、残便感、硬便などの症状がある状態を指します。両者は排便パターンの異常を示す症状で、消化器疾患だけでなく、全身疾患、薬剤、生活習慣など多様な原因により生じます。急性の下痢や便秘は緊急性の判断が重要であり、慢性化した場合はQOLに大きな影響を与えます。
疫学
下痢は非常に頻度の高い症状で、成人の約20〜30%が年に1回以上の急性下痢を経験します。感染性胃腸炎が最も多い原因です。一方、便秘は日本人の約10〜20%が悩んでおり、特に女性と高齢者に多く見られます。女性では約20〜30%、高齢者では約30〜40%が便秘を自覚しています。慢性便秘は加齢とともに増加し、生活の質を著しく低下させます。また、過敏性腸症候群(IBS)では下痢型、便秘型、混合型があり、若年〜中年層に多く見られます。
原因
下痢の原因は、急性では感染性腸炎(ウイルス、細菌、寄生虫)、食中毒、薬剤性(抗菌薬など)が多く、慢性では炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)、過敏性腸症候群、吸収不良症候群、甲状腺機能亢進症、糖尿病性腸症などがあります。便秘の原因は、機能性便秘(弛緩性、痙攣性、直腸性)が最も多く、その他に器質性便秘(大腸がん、腸閉塞、直腸肛門疾患)、症候性便秘(糖尿病、甲状腺機能低下症、パーキンソン病)、薬剤性(麻薬、抗コリン薬、抗うつ薬)があります。生活習慣(食物繊維不足、水分不足、運動不足)も大きな要因です。
病態生理
下痢のメカニズムは、浸透圧性下痢(吸収されない物質により腸管内に水分が保持される)、分泌性下痢(腸管からの水分・電解質分泌が亢進する)、滲出性下痢(炎症により血液・粘液・膿が漏出する)、運動亢進性下痢(腸管の蠕動が亢進し通過時間が短縮する)に分類されます。下痢により脱水、電解質異常(低ナトリウム血症、低カリウム血症)、代謝性アシドーシスを引き起こします。便秘のメカニズムは、大腸の蠕動運動低下により便の通過時間が延長し、水分が過度に吸収されて便が硬くなります。長期化すると宿便が形成され、腸閉塞や糞便性イレウスのリスクが高まります。また、いきみによる痔核や直腸脱、憩室形成なども合併します。
原因疾患・評価・対応
主な原因疾患
下痢の原因疾患として、急性期では感染性腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、サルモネラ、カンピロバクター、O157など)、食中毒、薬剤性腸炎(抗菌薬関連下痢、偽膜性腸炎)があります。慢性期では炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)、過敏性腸症候群、大腸がん、慢性膵炎、吸収不良症候群、甲状腺機能亢進症、糖尿病性腸症などが挙げられます。便秘の原因疾患として、機能性便秘(弛緩性、痙攣性、直腸性)が最も多く、器質性便秘では大腸がん、腸閉塞、巨大結腸症、直腸瘤、肛門狭窄などがあります。症候性便秘では糖尿病、甲状腺機能低下症、低カリウム血症、高カルシウム血症、パーキンソン病、脊髄損傷などが原因となります。
評価とアセスメント
下痢の評価では、まずバイタルサイン測定により脱水とショックの評価を行います。緊急性の高い危険なサインとして、血圧低下、頻脈、意識障害、高熱(38.5℃以上)、激しい腹痛、血便、大量の水様便、高齢者や小児の急性下痢があります。便の性状(水様、泥状、血性、粘液性、脂肪便)、回数、量、色、臭いを詳細に観察します。随伴症状として腹痛、発熱、悪心・嘔吐、テネスムス(しぶり腹)を確認します。発症時期、食事歴、海外渡航歴、薬剤使用歴、周囲の発症状況も重要です。便秘の評価では、排便回数、便の性状(Bristol便形状スケール)、排便困難感、残便感、腹部膨満感、腹痛を確認します。警告症状(50歳以上の初発、体重減少、血便、貧血、腹部腫瘤)がある場合は器質的疾患を疑い精査が必要です。
対応と治療
下痢の対応は、軽症では経口補水液による水分・電解質補給と消化の良い食事が基本です。中等度以上では静脈輸液により脱水を補正します。整腸薬(プロバイオティクス)、止痢薬(ロペラミド)を使用しますが、感染性腸炎で発熱や血便がある場合は止痢薬は原則禁忌です。細菌性腸炎では抗菌薬を使用することもあります。炎症性腸疾患では5-ASA製剤やステロイド、免疫抑制薬などを使用します。便秘の対応は、まず生活習慣の改善(食物繊維摂取、水分摂取、運動、排便習慣の確立)を指導します。薬物療法では、浸透圧性下剤(酸化マグネシウム、ラクツロース)、刺激性下剤(センナ、ビサコジル)、上皮機能変容薬(ルビプロストン、リナクロチド)などを使用します。宿便がある場合は浣腸や摘便が必要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 体液量不足(下痢):頻回の水様便による体液・電解質喪失
- 排便パターン変調:下痢または便秘による正常な排便パターンの障害
- 皮膚統合性障害リスク(下痢):頻回の排便による肛門周囲皮膚の損傷リスク
ゴードン機能的健康パターン
栄養-代謝パターンでは、食事内容、水分摂取量、体重変化を評価します。下痢では脱水徴候(口渇、皮膚ツルゴール低下、尿量減少)を確認し、便秘では食物繊維や水分の摂取不足がないか評価します。排泄パターンが最も重要で、排便回数、便の性状・量・色・臭い、排便時の症状(腹痛、テネスムス、残便感、いきみ)、排便パターンの変化を詳細に評価します。下痢では便失禁のリスクも考慮します。活動-運動パターンでは、便秘では運動不足が原因となることが多く、日常の活動量を評価します。下痢では頻回のトイレのため活動が制限され、外出が困難になることもあります。役割-関係パターンでは、慢性的な下痢や便秘が仕事や社会生活に与える影響を評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に排泄するニードが最も直接的に障害されています。下痢では頻回の排便によるQOL低下と脱水のリスク、便秘では排便困難による苦痛と合併症のリスクがあります。排便パターンの観察と適切な介入が中心となります。食べる・飲むニードでは、下痢時の水分・電解質補給、便秘時の食物繊維と水分摂取の促進が重要です。下痢では消化の良い食事への変更、便秘では食事内容の見直しが必要です。清潔と皮膚の統合性を保つニードでは、下痢による肛門周囲皮膚の損傷(スキントラブル)の予防と対処が重要です。温水洗浄、保湿剤・保護剤の使用、頻繁なおむつ交換などを行います。
看護計画・介入の内容
- 排便状態の継続的評価:排便回数・時刻の記録、便の性状・量・色・臭いの観察と記録(Bristol便形状スケール使用)、随伴症状の確認(腹痛、腹部膨満感、悪心・嘔吐)、バイタルサインの測定、脱水徴候の観察(下痢時)、腹部聴診による腸蠕動音の確認
- 水分・電解質バランスの管理:輸液管理と水分出納バランスの評価、経口補水液の提供と摂取量の記録、尿量測定、電解質データの確認、脱水改善の評価
- スキンケアと快適性の提供:肛門周囲の皮膚観察と保護(下痢時)、温水洗浄後の水気の押さえ拭き、保護クリームやオムツの使用、便失禁時の速やかな対応とケア、トイレ環境の整備(プライバシー保護、アクセスしやすい配置)
よくある疑問・Q&A
Q: 下痢のときに止痢薬を使ってはいけない場合はありますか?
A: はい、感染性腸炎で発熱や血便がある場合は止痢薬の使用は原則禁忌です。下痢は病原体や毒素を体外に排出する防御反応であり、止痢薬で無理に止めると病原体が腸内に停滞し、症状が長引いたり重症化したりする可能性があります。特に細菌性腸炎(O157など)では溶血性尿毒症症候群(HUS)のリスクが高まります。
Q: Bristol便形状スケールとは何ですか?
A: Bristol便形状スケールは便の性状を客観的に評価するための7段階の分類です。タイプ1(硬いコロコロ便)とタイプ2(硬い塊状便)は便秘を示し、タイプ3(ひび割れのあるソーセージ状)とタイプ4(滑らかなソーセージ状)が正常便、タイプ5(柔らかい半固形便)からタイプ7(完全な水様便)は下痢を示します。看護記録での客観的な便性状の記載に有用です。
Q: 高齢者の便秘で特に注意すべきことは?
A: 高齢者の便秘では、宿便による腸閉塞や糞便性イレウスのリスクが高いため注意が必要です。また、いきみによる脳血管障害や心筋梗塞の誘発、直腸脱や痔核の悪化も起こりやすいです。さらに、薬剤性便秘(麻薬、抗コリン薬、抗うつ薬など)の頻度が高く、複数の疾患を持つことが多いため、総合的な評価が必要です。
Q: 浣腸と摘便はどのように使い分けますか?
A: 一般的に、まず浣腸を試み、それでも排便がない場合や直腸に硬い便塊が触知される場合に摘便を行います。浣腸は腸粘膜を刺激して蠕動を促し、便を軟化させます。摘便は直腸内の硬い便を用手的に除去する方法です。ただし、直腸肛門部の手術後、重度の痔核、心疾患、脳血管障害の急性期などでは慎重に適応を判断します。摘便は迷走神経反射により徐脈や血圧低下を起こす可能性があるため、バイタルサイン監視下で実施します。
Q: 下痢のときの食事はどうすればよいですか?
A: 下痢の急性期は消化の良い食品を少量ずつ摂取します。おかゆ、うどん、白身魚、バナナ、りんごのすりおろし、トーストなどが適しています。避けるべき食品は、脂っこいもの、香辛料、カフェイン、アルコール、乳製品(乳糖不耐症がある場合)、食物繊維の多いもの(急性期)です。水分補給は重要ですが、冷たすぎる飲み物は腸を刺激するため、常温または温かい飲み物が望ましいです。
Q: 便秘予防のための生活習慣で最も重要なことは?
A: 便秘予防には複数の要素が重要ですが、特に規則正しい排便習慣の確立が基本です。毎朝同じ時刻にトイレに行く習慣をつけ、便意を我慢しないことが大切です。その上で、食物繊維の摂取(1日20〜25g目標)、十分な水分摂取(1日1.5〜2L)、適度な運動(ウォーキングなど)、腹部マッサージなども有効です。また、朝食後は胃結腸反射により便意が起こりやすいため、朝食をしっかり摂ることも重要です。
まとめ
下痢・便秘は非常に頻度の高い排便異常の症状であり、QOLに大きな影響を与えます。下痢では脱水と電解質異常が生命に関わることもあるため、特に高齢者や小児では迅速な評価と対応が必要です。便秘では器質的疾患の鑑別が重要であり、警告症状(血便、体重減少、50歳以上の初発)がある場合は精査が必須です。
看護師の重要な役割は、便の性状を正確に観察・記録し、異常の早期発見と適切な対応につなげることです。Bristol便形状スケールを活用し、客観的な評価を行いましょう。下痢では脱水徴候の継続的観察と水分・電解質補給、肛門周囲のスキンケアが重要です。便秘では生活習慣の改善指導と排便パターンの確立支援が中心となります。
また、排便は非常にプライベートな問題であり、患者は羞恥心や抵抗感を持ちやすいため、プライバシーに配慮した丁寧な対応と共感的な態度が大切です。排便コントロールは患者の自尊心やQOLに直結するため、患者の苦痛を理解し、尊厳を守る看護を提供しましょう。
実習では、排便状態の観察を通じて、患者の全身状態や疾患の経過を把握する力を養うことが重要です。便の観察は基本的かつ重要な看護技術であり、詳細で正確な観察・記録を心がけましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
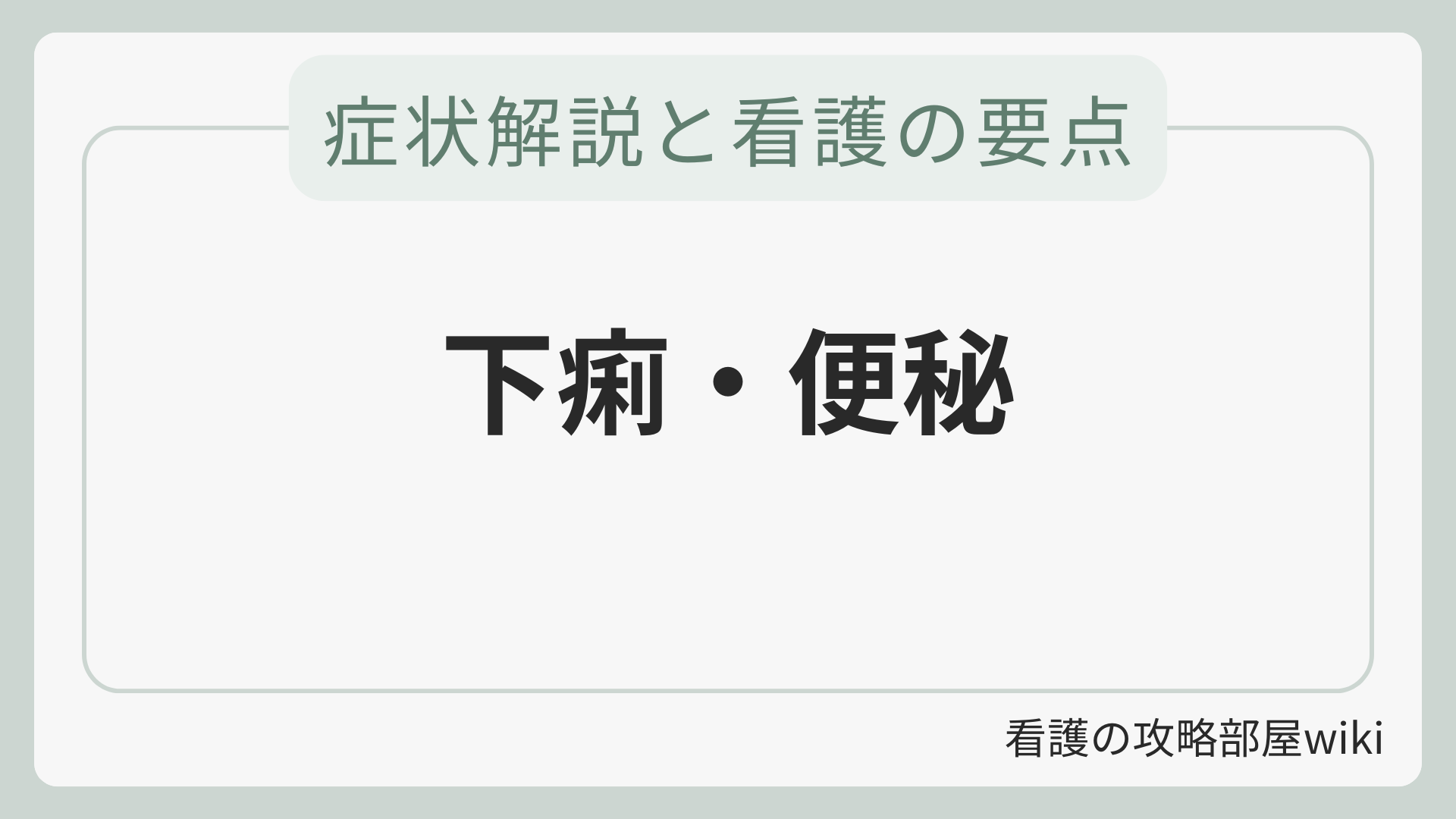
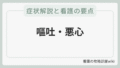
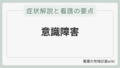
コメント