1. はじめに
消化管出血は看護師が救急外来や内科病棟で頻繁に遭遇する重要な病態です。軽微な出血から生命に関わる大量出血まで幅広く、迅速で適切な判断と対応が患者さんの予後を大きく左右します。上部消化管出血と下部消化管出血では原因や症状が異なるため、それぞれの特徴を理解し、出血部位の推定と重症度評価を的確に行うことが重要です。実習では吐血や下血などの症状を呈する患者さんに出会う機会が多い病態です。
この記事で学べること
- 上部・下部消化管出血の病態生理と症状の違い
- 出血量評価と重症度判定の具体的方法
- 出血性ショックへの進行過程と観察ポイント
- 原因疾患別の特徴と治療アプローチの理解
- 緊急時の看護介入と安全管理のポイント
2. 病態の基本情報
定義
消化管出血とは、食道から肛門までの消化管のいずれかの部位からの出血で、トライツ靭帯(十二指腸空腸移行部)を境に上部消化管出血(食道・胃・十二指腸)と下部消化管出血(小腸・大腸・直腸・肛門)に分類されます。
疫学
日本では年間約8万人が消化管出血で入院治療を受けており、そのうち約70%が上部消化管出血、約30%が下部消化管出血とされています。上部消化管出血の死亡率は約5-10%、下部消化管出血は約2-5%で、高齢者や併存疾患を有する患者では死亡率が高くなります。救急外来受診者の約3-5%が消化管出血関連であり、そのうち約20-30%が輸血を必要とする中等度以上の出血です。
分類・病型
解剖学的分類では上部消化管出血(食道静脈瘤破裂、胃・十二指腸潰瘍、マロリー・ワイス症候群など)と下部消化管出血(大腸憩室出血、虚血性腸炎、大腸癌、痔核など)に分けられます。出血量による分類では大量出血(24時間で1000ml以上または循環動態に影響)、中等量出血(500-1000ml)、少量出血(500ml未満)に分類されます。また、出血の持続性により活動性出血(現在進行中)、最近の出血(24時間以内に止血)、陳旧性出血(それ以前の出血)に分けられ、治療の緊急度が異なります。発症様式では急性出血(突然発症、症状明瞭)と慢性出血(緩徐進行、鉄欠乏性貧血で発見)があります。
3. 病態生理
基本メカニズム
消化管出血を理解するために、消化管を「水道管システム」に例えて考えてみましょう。正常な消化管は丈夫な配管(粘膜)で保護されていますが、潰瘍は配管に穴が開いた状態、静脈瘤破裂は水圧に耐えきれず配管が破裂した状態です。出血部位により血液の「流れ方」が異なり、上部では胃酸により血液が変性して「コーヒー残渣様」となり、下部では新鮮血として排出されます。出血量が多いと「配管内の水圧」(循環血液量)が低下し、全身への「水の供給」(組織灌流)が不足します。
進行過程
消化管出血は初期出血期→代償期→ショック期→多臓器不全期の段階で進行します。初期出血期では少量の出血のため症状は軽微で、患者さんは「便の色が変わった」「気分が悪い」程度の訴えです。代償期では出血量増加に対し心拍数増加、末梢血管収縮により血圧を維持しようとしますが、起立性低血圧や頻脈が現れます。ショック期では代償機能の限界を超え、明らかな血圧低下、頻脈、冷汗、意識レベル低下が出現します。多臓器不全期では循環不全により腎不全、肝不全、呼吸不全などを併発し、予後不良となります。
病型別の違い
- 上部消化管出血: 吐血(血性嘔吐)、黒色便(タール便)、胃内容物逆流によるコーヒー残渣様嘔吐
- 下部消化管出血: 血便(鮮血便、暗赤色便)、粘血便、出血量に応じた便性状の変化
- 大量出血: 急激な循環動態悪化、ショック症状、24時間以内に輸血必要
- 慢性出血: 緩徐な貧血進行、易疲労感、動悸、息切れ、鉄欠乏症状
合併症・併発する病態
急性大量出血では出血性ショックによる多臓器不全が最も重要な合併症です。腎血流減少による急性腎障害、脳血流減少による意識障害、心筋虚血による心不全や不整脈が生じます。慢性出血では鉄欠乏性貧血により易疲労感、動悸、息切れが現れ、重篤な場合は心不全を併発します。また、大量輸血により輸血関連急性肺障害や電解質異常、凝固障害などの輸血合併症も重要です。上部消化管出血では誤嚥性肺炎のリスクも高くなります。
看護に活かすポイント
なぜ便や嘔吐物の性状観察が重要なのでしょうか。血液の消化管内滞留時間により性状が変化するため、出血部位の推定が可能だからです。上部出血では胃酸により血液が変性し黒色便となり、下部出血では消化されずに鮮血便として排出されます。ただし、上部の大量出血では腸管通過時間が短縮し鮮血便となることもあり、出血量と緊急度の判定にも重要な情報となります。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
初期では患者さんから「便の色が黒くなった」「トイレットペーパーに血がついた」「なんとなく気分が悪い」といった軽微な訴えが聞かれます。上部消化管出血では「コーヒーのような物を吐いた」「口の中が血の味がする」「胸やけがひどい」、下部消化管出血では「赤い血が混じった便が出た」「下腹部が痛い」「排便回数が増えた」といった特徴的な訴えがあります。出血量が増加すると「立ちくらみがする」「冷や汗が出る」「動悸がする」「息切れがする」といった循環不全の症状を訴え、重篤になると「意識がもうろうとする」「話すのもしんどい」といった状態になります。
主要な検査・診断
血液検査ではヘモグロビン値(正常男性13-17g/dL、女性11-15g/dL)の低下程度で出血量を評価しますが、急性出血では初期は正常のことが多く、ヘマトクリット値(正常男性40-50%、女性35-45%)の方が敏感な指標です。血小板数(正常15-40万/μL)、PT・APTTにより凝固能を評価し、BUN/クレアチニン比(正常10:1)の上昇は上部消化管出血を示唆します。便潜血反応は慢性出血の検出に有用です。内視鏡検査は出血部位の確定と治療を兼ねた最も重要な検査で、緊急内視鏡(6時間以内)の適応判断が重要です。CT検査では活動性出血や腹腔内出血の評価を行います。
治療の基本
急性期治療では循環動態の安定化が最優先で、大口径静脈路確保(18G以上)による迅速輸液、必要に応じた輸血療法(ヘモグロビン7-8g/dL以下で輸血検討)を行います。薬物療法として上部消化管出血ではプロトンポンプ阻害薬(PPI)の大量投与、食道静脈瘤出血ではバソプレシンやソマトスタチンによる内臓血流減少を図ります。内視鏡的治療では止血クリップ、電気凝固、硬化療法などにより直接止血を行い、内視鏡的止血成功率は約90%です。外科的治療は内視鏡止血困難例や再出血例に対して実施され、血管内治療(動脈塞栓術)も選択肢の一つです。
5. 看護のポイント
主な看護診断
- 体液量不足
- 組織灌流量減少
- 不安
- 知識不足
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
活動・運動パターンが最も重要な観察対象です。循環動態の評価として血圧・脈拍・心電図を継続的に監視し、収縮期血圧90mmHg未満または平常時より30mmHg以上の低下、脈拍100回/分以上は出血性ショックのサインとして緊急対応が必要です。起立性低血圧の評価(臥位から座位で収縮期血圧20mmHg以上低下)も重要な指標です。排泄パターンでは便や嘔吐物の性状・量・回数を詳細に観察し、写真撮影による客観的記録も有効です。時間尿量30ml/時未満は循環不全のサインとして注意が必要です。栄養・代謝パターンでは皮膚色(蒼白、冷汗)、毛細血管再充満時間(正常2秒以内)、体重変化を観察し、認知・知覚パターンでは意識レベルや見当識の変化を通じて脳血流の状態を評価します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
循環の基本的欲求に対しては、大口径静脈路の確保と維持、輸液・輸血の確実な実施により循環血液量の回復を図ります。下肢挙上位(15-20度)による静脈還流促進も有効で、ショック体位は呼吸困難を増悪させる可能性があるため注意が必要です。安全の基本的欲求では出血による意識レベル低下に伴う転倒・転落防止、誤嚥予防対策を徹底し、ベッドサイドでの24時間観察体制を整えます。排泄の基本的欲求に対しては、排便・嘔吐時の安全確保、便器やポータブルトイレの使用による転倒防止、排泄物の正確な観察と記録を行います。水分・電解質平衡の基本的欲求では医師の指示に基づく適切な輸液管理、電解質バランスの監視、必要に応じた制酸剤や止血剤の投与を実施します。
病態に応じた具体的な看護介入
最優先は出血量と循環動態の継続的評価です。バイタルサイン測定(15-30分毎)、尿量測定(時間毎)、便・嘔吐物の性状観察を継続し、出血量評価スケール(少量・中等量・大量)による客観的評価を行います。第二に迅速な輸液・輸血療法の準備と実施で、大口径静脈路(18G以上)の確保、クロスマッチ用血液採取、輸血の準備と実施、輸血副反応の監視を行います。第三に出血源の安静保持として、絶飲食による消化管の安静、体動制限による血圧変動の最小化、ストレス軽減による再出血予防を図ります。第四に誤嚥予防対策として、嘔吐時の体位管理(側臥位、前傾位)、口腔内吸引の準備、気道確保の準備を行います。第五に心理的支援として、突然の出血に対する不安軽減、検査・治療に関する分かりやすい説明、家族への状況説明と精神的サポートを提供します。
予防・悪化防止のポイント
再出血の予防が最も重要で、内服薬の確実な服用(PPI、粘膜保護剤)、生活指導(禁煙・節酒、規則正しい食事、ストレス管理)を徹底します。NSAIDsや抗凝固薬など出血リスクを高める薬剤の適切な管理も重要です。慢性疾患(肝硬変、腎不全など)の管理により基礎疾患の悪化を防ぎ、定期的な内視鏡検査により早期発見・早期治療を図ります。また、便潜血反応検査による慢性出血のスクリーニング、貧血症状の自己観察指導により、早期受診を促します。
6. よくある質問・Q&A
Q:便や嘔吐物の観察で出血部位をどのように判断すればよいですか?
A: 最も重要なのは血液の性状です。上部消化管出血では胃酸により血液が変性するため、嘔吐物は「コーヒー残渣様」(黒褐色でざらざらした感じ)、便は「タール便」(黒色で粘稠、特有の臭い)となります。下部消化管出血では血液が消化されないため「鮮血便」(明るい赤色)や「暗赤色便」として排出されます。ただし、上部の大量出血では腸管通過時間短縮により鮮血便となることもあるため、出血量と緊急度も併せて評価することが重要です。
Q:出血性ショックの早期サインを見逃さないための観察ポイントは?
A: 血圧低下は代償機能により遅れて現れるため、早期サインの観察が重要です。心拍数100回/分以上の頻脈、起立性低血圧(座位で収縮期血圧20mmHg以上低下)、皮膚の冷感・蒼白、毛細血管再充満時間延長(2秒以上)、尿量減少(30ml/時未満)が重要な指標です。また、患者さんの「のどが渇く」「立ちくらみがする」「冷汗が出る」といった主観的症状も見逃してはいけません。これらの変化を総合的に評価し、早期の医師報告につなげます。
Q:内視鏡検査前後の看護で注意すべきポイントを教えてください
A: 検査前は絶飲食の確認(上部内視鏡は6-8時間前から)、義歯の除去、同意書の確認、前投薬の実施を行います。循環動態が不安定な場合は検査室でのモニタリング体制を整えます。検査中は体位保持(左側臥位)、バイタルサイン監視、気道確保の準備を行います。検査後は咽頭麻酔が効いている間の誤嚥予防、止血処置後の安静保持、再出血徴候の監視が重要です。また、組織採取を行った場合は感染徴候の観察も必要です。
Q:輸血療法実施時の観察ポイントと副反応対応を教えてください
A: 輸血前は患者確認(氏名、血液型)、クロスマッチ確認、ベースラインのバイタルサイン測定を確実に行います。輸血開始後15分間は最も副反応が起こりやすいため、5分後、15分後にバイタルサイン測定を行い、発熱、悪寒、皮疹、呼吸困難などの症状を観察します。副反応出現時は直ちに輸血を中止し、ルートは確保したまま生理食塩水に変更、医師報告を行います。重篤な場合は気道確保、酸素投与、昇圧剤投与の準備を行い、輸血バッグと患者血液を検査室に提出します。
7. まとめ
消化管出血は軽微なものから生命に関わる重篤なものまで幅広く、迅速で的確な判断が患者さんの予後を決定します。上部・下部消化管出血の特徴を理解し、出血量評価と重症度判定を適切に行うことで、早期の治療介入につなげることができます。継続的な観察と根拠に基づく看護介入により、患者さんの安全確保と回復支援を図ります。
覚えるべき数値
- 出血性ショック:収縮期血圧90mmHg未満または30mmHg以上低下
- 頻脈:100回/分以上(代償性)
- 尿量減少:30ml/時未満
- 輸血検討基準:ヘモグロビン7-8g/dL以下
- 起立性低血圧:座位で収縮期血圧20mmHg以上低下
- 毛細血管再充満時間:正常2秒以内
実習・現場で活用できるポイント
便や嘔吐物の性状観察により出血部位を推定し、出血量評価により緊急度を判定する力を養います。「なぜタール便なのか」「なぜ鮮血便なのか」を病態生理と関連付けて理解し、根拠に基づいた観察を実践してください。循環動態の変化を早期に察知し、迅速な報告と対応につなげることが重要です。消化管出血の看護経験は、循環管理や救急看護の基礎となる貴重な学習機会であり、将来様々な分野で活用できる知識と技術を身につけることができます。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
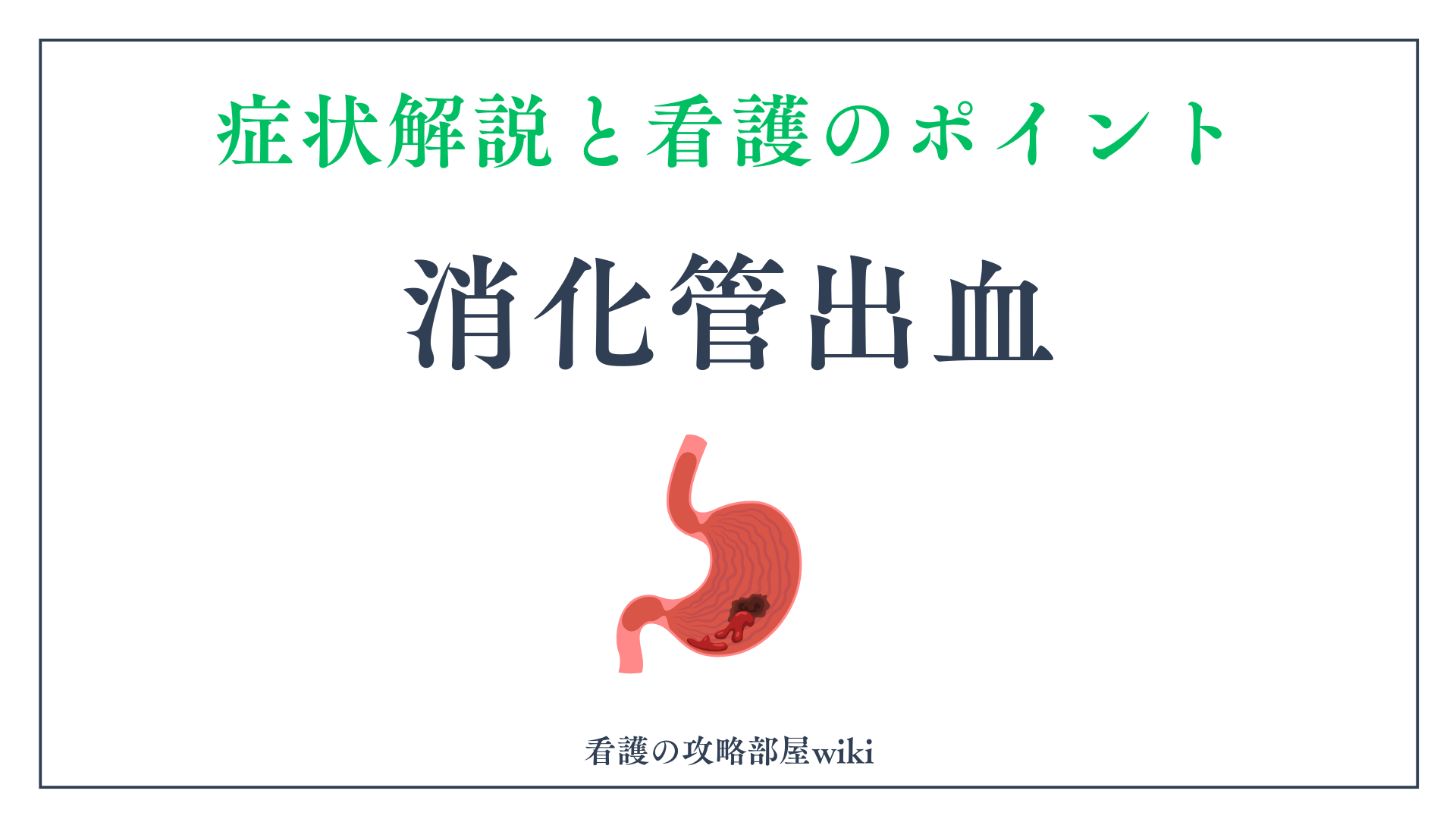
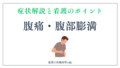
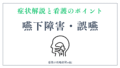
コメント