1. はじめに
血糖値の異常は糖尿病患者さんだけでなく、様々な疾患や治療により引き起こされる重要な病態です。看護学生の皆さんが実習で血糖異常の患者さんと関わる際、「なぜこの症状が現れるのか?」「どのタイミングで介入すべきか?」を病態生理に基づいて理解することが重要です。特に低血糖は生命に関わる緊急事態となることがあり、迅速で適切な判断と対応が求められます。血糖管理は単なる数値のコントロールではなく、患者さんの安全と生活の質に直結する重要なケアです。
この記事で学べること:
- 高血糖・低血糖の発症メカニズムと身体への影響
- 糖尿病性ケトアシドーシスと高浸透圧高血糖症候群の違い
- 血糖自己測定の意義と正確な測定方法
- 症状の早期発見と段階的な対応方法
- インスリン療法と経口血糖降下薬の安全管理
2. 疾患の基本情報
定義
高血糖は血糖値が正常範囲を超えて上昇した状態(一般的に180mg/dl以上)、低血糖は血糖値が異常に低下した状態(一般的に70mg/dl未満)で、いずれも適切な対応が必要な病態
疫学
日本の糖尿病患者数は約1000万人に達し、糖尿病予備群を含めると約2000万人が血糖異常を有しています。入院患者の約20-30%に何らかの血糖異常が認められ、手術や感染症により血糖値が変動しやすくなります。低血糖による救急搬送は年間約1万件発生し、特に高齢者では重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。また、入院中の血糖管理不良により感染症リスクが2-3倍、創傷治癒遅延のリスクが1.5-2倍に増加することが報告されています。
分類・病型
高血糖は軽度(180-250mg/dl)、中等度(250-400mg/dl)、重度(400mg/dl以上)に分類され、それぞれ症状の程度と緊急度が異なります。急性合併症では糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)と高浸透圧高血糖症候群(HHS)があり、DKAは主に1型糖尿病で、HHSは主に2型糖尿病で発症します。
低血糖は軽症(50-69mg/dl)、中等症(40-49mg/dl)、重症(40mg/dl未満)に分類されます。症状の有無により症候性低血糖と無症候性低血糖に分けられ、無症候性低血糖は低血糖無自覚症の患者さんに見られる危険な状態です。原因別では薬剤性、肝疾患、内分泌疾患、腫瘍性などがあり、薬剤性が最も頻度が高く、特にインスリンとスルホニル尿素薬によるものが多くなります。
3. 病態生理
基本メカニズム
血糖値は膵臓のランゲルハンス島で産生されるインスリンとグルカゴンにより調節されています。これは室温を一定に保つエアコンのようなシステムで、インスリンが「冷房(血糖降下)」、グルカゴンが「暖房(血糖上昇)」の役割を果たします。食事により血糖値が上昇するとインスリンが分泌され、筋肉や脂肪組織へのブドウ糖取り込みを促進し、肝臓でのグリコーゲン合成を促進します。
高血糖状態では、まるで水道の蛇口が壊れて水が流れ続けるように、ブドウ糖が細胞内に取り込まれず血液中に蓄積します。細胞はエネルギー不足となり、代償的に脂肪やタンパク質を分解してエネルギーを得ようとします。この過程で産生されるケトン体が蓄積すると、血液が酸性に傾きケトアシドーシスを引き起こします。
低血糖状態では、脳が「エネルギー不足の警報」を発し、交感神経系が活性化されます。アドレナリンやグルカゴンが分泌され、肝臓でのグリコーゲン分解や糖新生を促進して血糖値を上昇させようとします。しかし、これらの代償機能が追いつかないと、脳の機能低下により意識障害や痙攣が生じます。
進行過程
高血糖の進行は段階的に起こります。初期段階では軽度の口渇、多尿から始まり、患者さんは「最近よく水を飲む」「トイレの回数が増えた」と感じます。代償期には体重減少、倦怠感が現れ、「食べているのに痩せる」「疲れやすい」といった症状が出現します。非代償期に入ると脱水が進行し、意識レベルの低下、呼吸の変化(クスマウル呼吸)が生じ、最終的には昏睡状態となります。
低血糖の進行はより急激です。初期には交感神経刺激症状として発汗、動悸、手指振戦が現れ、患者さんは「急に汗が出てきた」「胸がドキドキする」と訴えます。進行すると中枢神経症状として集中力低下、異常行動、錯乱が生じ、「頭がぼんやりする」「いつもと違う行動をする」といった変化が見られます。最終段階では痙攣、昏睡に至り、適切な治療を行わないと不可逆的な脳障害や死に至る可能性があります。
病型別の違い
糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)は主に1型糖尿病やインスリン不足により発症し、血糖値上昇、ケトン体産生、代謝性アシドーシスの3つが特徴です。患者さんからは「お腹が痛い」「吐き気がする」「息苦しい」といった訴えが聞かれ、呼気からケトン臭(甘酸っぱいにおい)がします。
高浸透圧高血糖症候群(HHS)は主に2型糖尿病の高齢者に発症し、著明な高血糖(600mg/dl以上)と脱水が特徴で、ケトン体の産生は軽微です。意識障害が主症状で、「ぼんやりしている」「反応が鈍い」といった変化が徐々に進行します。
薬剤性低血糖では、インスリンによるものは作用時間により症状の持続時間が異なり、速効型では1-2時間、持効型では12-24時間持続する可能性があります。スルホニル尿素薬による低血糖は遷延性で、初回治療で改善しても再び低血糖を起こすことがあります。
合併症・併発する病態
高血糖による急性合併症として、感染症リスクの増加、創傷治癒遅延、血管内脱水による血栓形成があります。慢性的な高血糖は血管障害を引き起こし、網膜症、腎症、神経障害などの細小血管症と、冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患などの大血管症を発症します。
低血糖による合併症では、交通事故や転倒による外傷、不整脈、心筋梗塞、脳血管障害があります。特に高齢者では低血糖により認知機能が低下し、回復に時間を要することがあります。頻回の低血糖は低血糖無自覚症を引き起こし、危険な低血糖の早期発見が困難になります。
看護に活かすポイント
なぜ低血糖の患者さんには「とりあえず様子を見る」ではいけないのでしょうか?脳は血糖値が50mg/dl以下になると機能障害を起こし始め、30mg/dl以下では不可逆的な脳障害のリスクが急激に高まります。脳細胞はブドウ糖以外のエネルギー源をほとんど利用できないため、低血糖状態の持続は「脳の窒息状態」と同じです。このメカニズムを理解することで、低血糖症状を認めた際の迅速な対応の重要性を患者さんや家族に説明でき、適切な血糖管理への協力を得ることができます。
4. 症状・診断・治療
代表的な症状
高血糖では初期症状として「のどが渇く」「水をたくさん飲む」「尿の回数や量が多い」といった三大症状が現れます。進行すると「体重が減る」「疲れやすい」「集中できない」「傷が治りにくい」という訴えが聞かれます。重症化すると「お腹が痛い」「吐き気がする」「息が荒い」といった症状が出現し、DKAでは特徴的な「甘酸っぱい口臭」があります。
低血糖では段階的に症状が現れます。軽症では自律神経症状として「急に汗が出る」「手が震える」「動悸がする」「お腹が空く」という訴えがあります。中等症になると中枢神経症状として「頭がぼんやりする」「集中できない」「いつもと違う行動をとる」「怒りっぽくなる」といった変化が見られます。重症では「意識がもうろうとする」「痙攣する」「反応しない」といった危険な状態となります。
患者さんの中には「いつものことだから」と症状を軽視する方もいますが、特に高齢者では典型的な症状が現れにくく、「なんとなく調子が悪い」「食欲がない」といった非特異的な症状のみの場合があるため注意深い観察が必要です。
主要な検査・診断
血糖自己測定(SMBG)は最も迅速で重要な検査です。指先から採血し、血糖測定器で測定します。正常値は空腹時70-109mg/dl、食後2時間140mg/dl未満です。測定時は手指の清拭、十分な血液量の確保、測定器の校正確認が重要で、誤差を最小限にするため同じ部位の連続使用は避けます。
HbA1cは過去1-2ヶ月の平均血糖値を反映し、糖尿病の診断と血糖管理の評価に用います。正常値は6.2%未満、糖尿病では7.0%未満を目標とします。ただし、急性期の血糖変動は反映されないため、日々の血糖管理には血糖測定が必要です。
血液ガス分析はDKAやHHSの診断に重要で、pH、重炭酸イオン、anion gapを評価します。DKAではpH 7.3未満、HCO3- 15mEq/L未満、anion gap 10mEq/L以上となります。尿ケトン体測定では、試験紙により簡便に測定でき、DKAの診断と治療効果判定に用います。
治療の基本
高血糖治療では原因に応じた対応が重要です。軽度から中等度の高血糖では、インスリンの追加投与、食事調整、水分補給を行います。DKAでは大量輸液による脱水補正、持続インスリン投与によるケトン体の是正、電解質(特にカリウム)の補正を行います。HHSでは緩徐な血糖降下と脱水補正が重要で、急激な血糖低下は脳浮腫のリスクがあります。
低血糖治療は血糖値と意識レベルに応じて段階的に行います。意識清明で軽症の場合は、ブドウ糖10-20g(砂糖なら20-40g)の経口摂取により15分以内に改善します。中等症以上や経口摂取困難な場合は、50%ブドウ糖液20-40mlの静脈内投与を行います。グルカゴン1mgの筋肉内投与も有効ですが、肝グリコーゲンが枯渇している場合は効果が限定的です。
治療後は血糖値の再確認が重要で、低血糖では15分後、30分後、1時間後の血糖測定により改善と再発の有無を確認します。スルホニル尿素薬による低血糖では作用時間が長いため、24-48時間の観察が必要です。
5. 看護のポイント
主な看護診断
- 血糖値不安定リスク状態
- 体液量不足
- 栄養摂取消費バランス異常
- 急性錯乱リスク状態
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚・健康管理パターンでは、血糖値の変動と症状の関連性を系統的に観察します。「いつもと比べて体調に変化はありませんか?」「のどの渇きや尿の回数に変化はありませんか?」と確認し、血糖測定値と症状を関連づけて評価します。自覚症状の変化を見逃さないよう、「いつもなら気づく低血糖の症状を感じにくくなっていませんか?」と低血糖無自覚症の可能性も評価します。薬物療法の理解度と実行状況についても「お薬は決められた時間に服用できていますか?」「インスリン注射の手技で困っていることはありませんか?」と確認します。
栄養・代謝パターンでは、食事摂取量と血糖値の関係を詳細に観察します。「食事の量や時間はいつも通りですか?」「食欲に変化はありませんか?」と確認し、摂取カロリーと血糖値の変動を関連づけます。体重変化も重要な指標で、「最近体重に変化はありませんか?」と定期的に確認し、異常な体重減少は高血糖の悪化を示唆します。水分バランスでは、「一日にどのくらい水分を摂取していますか?」「尿の色や量に変化はありませんか?」と聴取し、脱水の程度を評価します。
活動・運動パターンでは、運動と血糖値の関係を観察します。「運動をした後に体調の変化を感じることはありませんか?」「活動量の変化はありませんか?」と確認し、運動による血糖変動のパターンを把握します。倦怠感や易疲労性についても「以前より疲れやすくなったと感じますか?」「日常の活動で息切れや動悸はありませんか?」と評価し、高血糖による影響を確認します。
認知・知覚パターンでは、血糖変動による認知機能への影響を評価します。「集中力や記憶力に変化はありませんか?」「いつもと違う行動をとっていると言われたことはありませんか?」と確認し、特に低血糖による中枢神経症状の早期発見に努めます。血糖管理に対する理解度も重要で、「血糖値の目標値や測定方法について理解されていますか?」と教育ニーズを評価します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常に呼吸する欲求に対しては、高血糖による代謝性アシドーシスの早期発見と対応を行います。「息苦しさや呼吸の変化はありませんか?」と確認し、クスマウル呼吸(深大呼吸)の有無を観察します。DKAでは「息が荒くなったり、呼吸が深くなったりしていませんか?」と特徴的な呼吸パターンの変化を注意深く観察し、早期の医学的介入につなげます。
適切に飲食する欲求では、血糖管理と栄養バランスの両立を支援します。「お食事の内容や量について一緒に考えてみませんか?」と提案し、個別性を重視した食事指導を行います。低血糖時の補食についても「低血糖の時にすぐに摂取できる食品を準備しておきましょう」と具体的な準備を支援し、適切な対応方法を指導します。
学習する欲求では、血糖自己管理能力の向上を支援します。「血糖測定の手技を一緒に確認してみませんか?」と提案し、正確な測定方法を指導します。また、「どのような時に血糖値が変動しやすいか、ご自身のパターンを見つけてみましょう」と個別の血糖変動パターンの理解を促し、予防的な対応ができるよう支援します。
具体的な看護介入
血糖モニタリングでは定期的かつ適切なタイミングでの測定を支援します。「食前、食後、就寝前の血糖測定を一緒に行いましょう」と説明し、測定の意義と方法を指導します。測定時は「手をきれいに洗ってから測定しますね」「十分な血液量が必要です」と手技のポイントを説明し、正確な測定を支援します。異常値を認めた場合は「血糖値が高めですね。症状はいかがですか?」と症状の確認を行い、必要に応じて医師への報告を行います。
症状の早期発見では、患者さんと家族への教育を重視します。「高血糖の症状として、のどの渇き、多尿、体重減少があります」「低血糖の症状として、発汗、動悸、手の震えがあります」と具体的な症状を説明し、「このような症状を感じたらすぐに血糖測定を行ってください」と対応方法を指導します。特に夜間の低血糖について「夜中に悪夢を見る、寝汗をかく、朝の頭痛なども低血糖の症状の可能性があります」と説明し、見落としやすい症状についても注意を促します。
薬物療法の支援では、安全で効果的な薬物使用を支援します。インスリン療法では「注射部位のローテーション」「保存方法の確認」「投与手技の習得」を段階的に指導し、「痛みを軽減する注射方法」「適切な針の選択」についても助言します。経口血糖降下薬では「食事との関係」「副作用の観察」「他の薬剤との相互作用」について説明し、安全な服薬を支援します。
緊急時対応では、迅速で適切な初期対応を行います。低血糖症状を認めた場合は「まず血糖測定を行い、70mg/dl未満であれば速やかにブドウ糖を摂取します」と説明し、実際の手順を指導します。意識レベルの低下を認めた場合は「無理に経口摂取させず、すぐに医療者を呼んでください」と注意点を強調し、安全な対応方法を指導します。
予防・悪化防止のポイント
生活習慣の調整では、規則正しい食事と運動習慣の確立を支援します。「食事の時間を一定にすることで、血糖値の変動を小さくできます」と説明し、個々のライフスタイルに合わせた食事パターンを一緒に検討します。運動については「食後1-2時間後の軽い運動が血糖値の改善に効果的です」と具体的なタイミングと強度を指導し、低血糖のリスクについても「運動前後の血糖測定の重要性」を説明します。
ストレス管理では、心理的・身体的ストレスが血糖値に与える影響について説明します。「風邪や発熱時は血糖値が上昇しやすくなります」「ストレスや睡眠不足も血糖値に影響します」と関連性を説明し、「体調不良時はより頻回な血糖測定が必要です」と指導します。また、「血糖管理に対する不安や心配があれば、いつでもご相談ください」と心理的サポートの重要性も伝えます。
6. よくある質問・Q&A
Q:患者さんが「血糖値が少し高いくらいなら大丈夫」と言われています。どう説明すべきでしょうか?
A: 血糖値の軽度上昇でも継続すると重大な合併症につながることを、具体的で理解しやすい例を用いて説明します。「血糖値が高い状態は、血液がドロドロになって血管を傷つけている状態です」と視覚的にイメージしやすい表現を使い、「短期間では症状を感じなくても、長期間続くと目や腎臓、神経に障害が起こる可能性があります」と将来のリスクを説明します。具体的には「HbA1c 1%の改善により、糖尿病性網膜症は21%、腎症は33%、神経障害は60%リスクが減少します」と数値を示して改善の意義を伝えます。また、「今は症状がなくても、血管や臓器への影響は既に始まっている可能性があります」と現在の状況の重要性を説明し、「適切な管理により合併症は予防できます」と希望を持てるメッセージを伝えます。患者さんの生活背景を理解し、「実現可能な小さな目標から始めて、段階的に改善していきましょう」と個別性を重視したアプローチを提案します。
Q:夜勤中に糖尿病患者さんが「なんだかいつもと違う」と訴えています。どう対応すべきでしょうか?
A: 「いつもと違う」という訴えは重要なサインで、特に糖尿病患者さんでは血糖異常を疑って迅速に対応する必要があります。まず「どのような感じで違いますか?」と具体的な症状を聴取し、同時に血糖測定を速やかに実施します。低血糖の可能性を考慮し、「発汗、動悸、手の震え、空腹感はありませんか?」と自律神経症状を確認し、「頭がぼんやりする、集中できない、いつもと違う行動をとりたくなる」といった中枢神経症状の有無も評価します。バイタルサインを測定し、意識レベル、皮膚の状態、口臭の確認を行います。血糖値が70mg/dl未満の場合は直ちに低血糖への対応を開始し、「ブドウ糖やジュースを摂取していただきます」と説明して適切な補給を行います。180mg/dl以上の高血糖の場合は脱水の評価と医師への報告を行います。「夜間は低血糖を起こしやすい時間帯です」と説明し、対応後も15分、30分、1時間後の血糖再測定により改善を確認します。患者さんには「症状を感じたらすぐに教えてください」と伝え、継続的な観察の重要性を説明します。
Q:認知症を併発している糖尿病患者さんの血糖管理で注意すべき点は何ですか?
A: 認知症を併発した糖尿病患者さんでは、低血糖無自覚症のリスクが高く、症状の訴えが困難なため、より注意深い観察と個別的なアプローチが必要です。「いつもと様子が違う」「落ち着きがない」「攻撃的になる」といった行動変化が血糖異常の唯一のサインとなることがあるため、「普段の様子と比べて変化はありませんか?」と日常の行動パターンを把握し、わずかな変化も見逃さないよう注意深く観察します。血糖管理では「より緩やかな目標設定」が重要で、厳格な血糖管理よりも低血糖の回避を優先し、HbA1c 7.5-8.5%程度を目標とします。食事管理では「食事拒否や過食の有無」「食事時間の認識」「嚥下機能の評価」を行い、栄養状態の維持と血糖変動の最小化を図ります。薬物療法では「低血糖リスクの低い薬剤選択」「シンプルな投薬スケジュール」を心がけ、家族や介護者への教育も重要です。「血糖測定や薬物管理を誰が行うか」「緊急時の対応方法」について事前に調整し、多職種での連携により安全な血糖管理を実現します。また、「認知症の進行により血糖管理能力が低下する可能性」を説明し、定期的な評価と管理方法の見直しを行います。
Q:インスリン注射を拒否する患者さんにどうアプローチすれば良いですか?
A: インスリン注射への拒否には様々な理由があるため、まず患者さんの不安や懸念を丁寧に聴取することが重要です。「インスリン注射について、どのような心配がありますか?」と開かれた質問で患者さんの気持ちを確認します。よくある懸念として「痛みへの恐怖」「依存への不安」「手技への不安」「社会的偏見」があります。痛みについては「現在の針は非常に細く、ほとんど痛みを感じません」と実際に針を見せて説明し、可能であれば「まず看護師が代わりに注射して、慣れてから自己注射を覚えていきましょう」と段階的なアプローチを提案します。依存への不安には「インスリンは体内で作られるホルモンと同じもので、麻薬などの依存性薬物ではありません」「膵臓の機能を助ける治療です」と正しい情報を提供します。インスリンの必要性について「血糖値をコントロールすることで、将来の合併症を防ぐことができます」「適切な血糖管理により、より活動的な生活を送ることができます」と利益を具体的に説明し、「一緒に血糖管理の方法を学んでいきましょう」と協働的な関係を築きます。拒否が続く場合は、他の治療選択肢について医師と相談し、患者さんの価値観を尊重しながら最適な治療方針を検討します。
7. まとめ
血糖異常の看護では、迅速で正確な血糖評価と、患者さんの症状や生活背景に応じた個別的な対応が重要です。特に低血糖は生命に関わる緊急事態となる可能性があるため、早期発見と適切な初期対応が患者さんの安全に直結します。また、長期的な血糖管理は患者さんの自己管理能力に依存するため、継続的な教育と支援が欠かせません。
覚えるべき数値
- 正常血糖値:空腹時70-109mg/dl、食後2時間140mg/dl未満
- 低血糖:70mg/dl未満(重症40mg/dl未満)
- 高血糖:180mg/dl以上(重度400mg/dl以上)
- HbA1c目標値:糖尿病患者7.0%未満
- 低血糖治療:ブドウ糖10-20g経口、50%ブドウ糖液20-40ml静注
- DKA基準:pH 7.3未満、HCO3- 15mEq/L未満
実習・現場で活用できるポイント
血糖異常の患者さんとの関わりでは、数値だけでなく症状と患者さんの主観的な体験を総合的に評価してください。血糖測定は単なる数値の確認ではなく、患者さんの安全を守る重要な観察技術です。特に低血糖症状を見逃さないよう、「いつもと違う」という患者さんの訴えを大切にし、迅速な対応を心がけましょう。また、血糖管理は患者さんの生活全体に影響するため、食事、運動、薬物療法、ストレス管理を包括的に捉え、患者さんが無理なく継続できる個別的な管理方法を一緒に見つけていくことが重要です。ゴードンとヘンダーソンの理論を活用して多角的にアセスメントを行い、多職種と連携しながら患者さんの安全な血糖管理と生活の質向上を支援してください。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
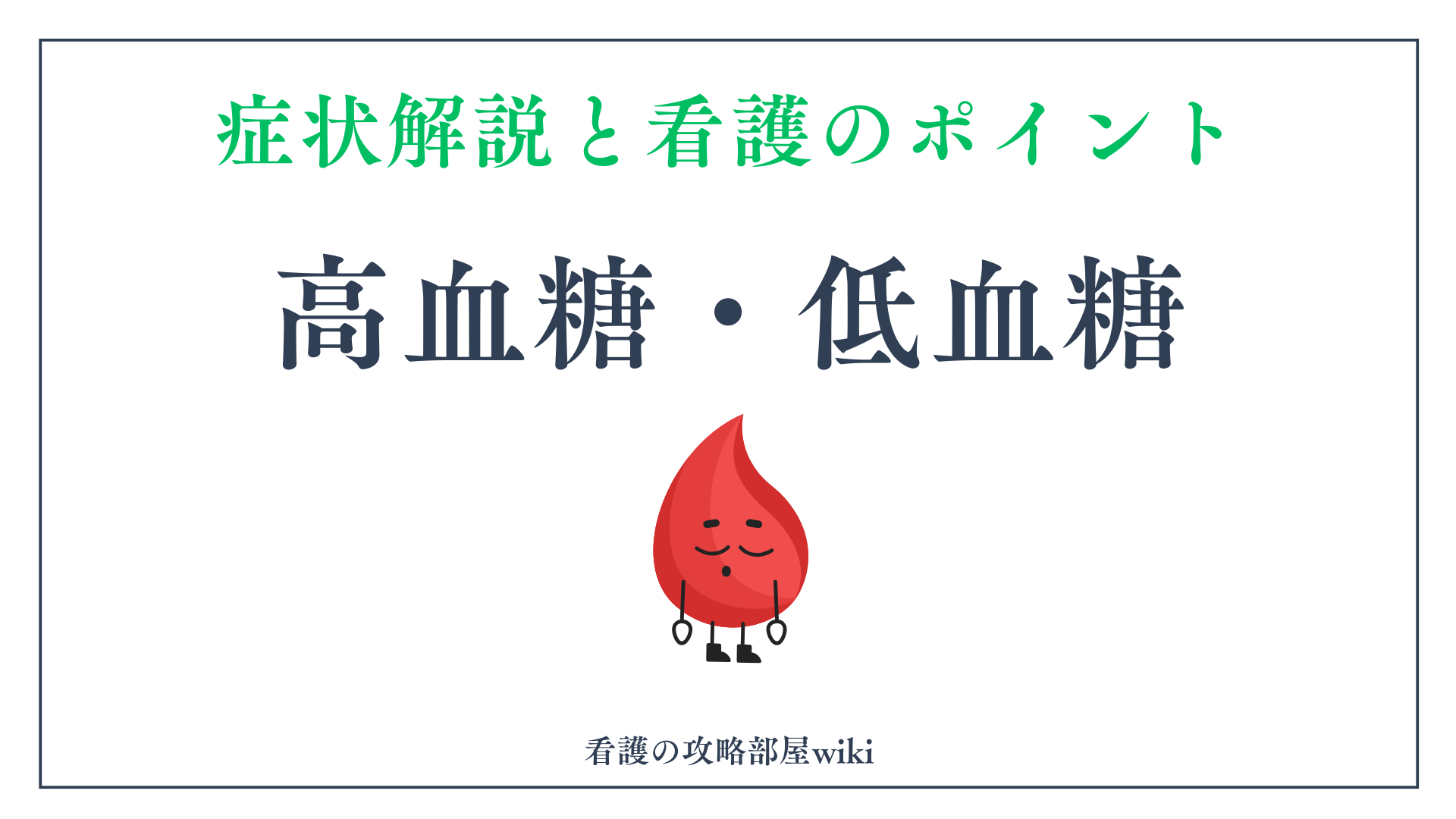


コメント