1. はじめに
「痰が絡んで苦しそう」「呼吸音がゴロゴロしている」といった患者さんの状態を目の当たりにしたとき、適切な気道内吸引により患者さんの呼吸を楽にしてあげることは、看護師として最も重要な技術の一つです。気道内吸引は、患者さんの生命に直結する呼吸を支援する基本的でありながら高度な看護技術です。
気道内吸引は単に分泌物を除去するだけではなく、患者さんの呼吸機能を改善し、肺炎などの合併症を予防し、快適性を向上させる包括的なケアです。口腔、鼻腔、気管内それぞれの吸引には異なる技術と注意点があり、患者さんの状態や気道の状況に応じた適切な判断と手技が求められます。
実習では様々な患者さんの吸引場面に遭遇し、その手技や観察ポイントに緊張することも多いでしょう。しかし、吸引の基本原理と安全な手技を習得することで、患者さんにとって安全で効果的なケアを提供できます。適切な技術により、患者さんの呼吸困難感を軽減し、安心感を提供することが可能になります。
この記事で学べること
- 口腔・鼻腔・気管内吸引の適応と実施判断の基準
- 安全で効果的な吸引手技の実際と注意点
- 吸引に伴う合併症の予防と早期発見のポイント
- 患者さんの個別性を考慮した吸引ケアの方法
- 無菌操作と感染予防を重視した実践技術
2. 気道内吸引の基本情報
定義
気道内吸引とは、自力で喀出できない気道内分泌物を陰圧を利用して除去し、気道の開通性を確保する看護技術です。
技術の意義と目的
気道内吸引の最大の目的は、効果的な換気を維持し、肺炎や無気肺などの呼吸器合併症を予防することです。分泌物の貯留により気道が閉塞すると、換気不全、ガス交換障害、感染リスクの増大が生じます。適切な吸引により、これらのリスクを軽減し、患者さんの呼吸機能を最適化できます。
患者さんにとって吸引は、呼吸困難感の軽減と快適性の向上をもたらします。特に意識障害や筋力低下により自力喀出が困難な患者さんにとって、吸引は生命維持に不可欠なケアとなります。看護師による適切な吸引技術により、患者さんは安全で効果的な呼吸支援を受けることができます。
実施頻度・タイミング
吸引の実施は患者さんの状態に応じて決定され、定時的な実施よりも必要時の実施が基本となります。呼吸音の異常、SpO₂の低下、咳嗽反射の減弱、痰の貯留音などが吸引の適応となります。一般的には2-4時間毎の評価を行い、必要に応じて実施します。
過度な吸引は気道粘膜の損傷や感染リスクを増大させるため、必要最小限の実施が原則です。患者さんの状態変化、体位変換後、理学療法後などに分泌物の移動が生じやすく、これらのタイミングでの評価が重要です。
3. 必要物品と準備
基本的な気道内吸引用品
気道内吸引には無菌操作を基本とした物品準備が必要です。吸引器、吸引瓶、吸引チューブ(各サイズ)、滅菌手袋、滅菌生理食塩水は必須物品です。吸引チューブは口腔用14-16Fr、鼻腔・気管内用10-14Frを準備し、患者さんの年齢や体格に応じて選択します。
モニタリング機器としてパルスオキシメーター、心電図モニターを使用し、吸引中の状態変化を監視します。アンビューバッグ、酸素マスクも準備し、吸引後の酸素化改善に備えます。記録用紙や観察チェック表も準備し、正確な記録管理を行います。
状況別対応用品
感染対策ではサージカルマスク、エプロン、アイシールドを標準装備とし、感染症疑いの場合はN95マスク、ガウンを追加します。気管内吸引では閉鎖式吸引システムを使用し、人工呼吸器回路の汚染を防ぎます。
緊急時対応として気管内挿管セット、蘇生用品を準備し、吸引に伴う急変に備えます。小児の場合は適切なサイズの吸引チューブ、小児用バッグマスクを準備し、年齢に応じた対応を行います。
物品準備のポイント
吸引圧の設定は成人80-120mmHg、小児60-100mmHg、新生児60-80mmHgを基準とし、患者さんの状態に応じて調整します。吸引チューブの選択では、気管チューブ内径の1/2以下のサイズを使用し、過度な陰圧による気道損傷を防ぎます。物品の配置は効率的な手技ができるよう工夫し、無菌操作の原則を遵守します。
4. 気道内吸引の実施手順
事前準備とアセスメント
吸引実施前に、患者さんの呼吸状態、SpO₂値、意識レベル、血行動態を詳細に評価します。呼吸音の聴診、痰の性状確認、咳嗽反射の有無を観察し、吸引の必要性と適切な方法を判断します。患者さんには処置の目的と手順を説明し、協力を得ながら不安の軽減を図ります。
吸引器の動作確認を行い、適切な吸引圧、吸引瓶の清潔性、チューブの通過性を確認します。前酸素化(FiO₂ 100%で1-2分間)を実施し、吸引による低酸素血症を予防します。
口腔内吸引の手順
清潔手袋を装着し、吸引チューブを滅菌生理食塩水で湿潤させます。口角から舌根部に向けてチューブを挿入し、吸引圧をかけながら回転させつつ引き抜きます。一回の吸引時間は10-15秒以内とし、患者さんの状態を観察しながら実施します。
鼻腔内吸引の手順
滅菌手袋を装着し、吸引チューブを滅菌生理食塩水で湿潤させます。鼻孔から下鼻道に沿って咽頭まで挿入し、分泌物を確認してから吸引を開始します。陰圧をかけながらゆっくりと回転させつつ引き抜き、一回の吸引時間は10-15秒以内とします。
気管内吸引の手順
厳格な無菌操作で滅菌手袋を装着し、滅菌された吸引チューブを準備します。気管チューブや気管切開チューブから挿入し、軽い抵抗を感じるまで挿入後1-2cm引き戻してから吸引を開始します。陰圧をかけながら回転させつつ10-15秒以内で引き抜き、必要に応じて複数回実施します。
実施中の観察ポイント
吸引中は患者さんのSpO₂値、心拍数、血圧、意識レベルを継続的に監視します。顔色の変化、不整脈の出現、血圧変動に注意を払い、異常時には直ちに吸引を中止します。分泌物の量、性状、色調も詳細に観察し、感染や出血の有無を評価します。
5. 特殊な状況での気道内吸引
人工呼吸器装着患者の吸引
人工呼吸器装着患者では閉鎖式吸引システムを使用し、回路の汚染と離脱を防ぎます。吸引前に100%酸素投与とSIGH機能を使用し、低酸素血症を予防します。PEEP設定値の維持に注意し、肺胞虚脱を防ぎます。吸引後は呼吸器設定の確認と肺音の再評価を行います。
意識障害患者の吸引
意識障害患者では咳嗽反射や嚥下反射の低下により、吸引時の誤嚥リスクが高くなります。側臥位での実施、口腔内の十分な観察、ゆっくりとした手技により安全性を確保します。瞳孔反応や意識レベルの変化にも注意を払い、頭蓋内圧亢進の兆候を見逃さないようにします。
小児の気道内吸引
小児では気道径が小さく、粘膜が脆弱なため、より慎重な手技が必要です。低い吸引圧(60-100mmHg)、細いチューブ(6-10Fr)、短時間(5-10秒)の吸引を心がけます。体位保持や固定には注意を払い、安全で効果的な吸引を実施します。
感染症患者の吸引
感染症患者の吸引では標準予防策に加えた感染対策が必要です。個人防護具の適切な装着、使い捨て器具の使用、適切な廃棄処理により、医療従事者と他患者への感染拡大を防ぎます。陰圧室での実施やエアロゾル対策も考慮します。
6. 気道内吸引中の観察とアセスメント
気道内吸引の効果判定では、吸引前後の呼吸状態の変化を詳細に評価することが重要です。有効な吸引の指標として、呼吸音の改善、SpO₂値の上昇、呼吸困難感の軽減、咳嗽の減少が挙げられます。これらの改善が見られれば、適切な吸引が実施できたと判断できます。
分泌物の性状評価も重要な観察項目です。正常な分泌物は透明から白色の粘液性で、量は少量です。異常所見として、黄色・緑色の膿性分泌物、血液混入、異臭、粘稠度の著明な増加などに注意します。これらは感染や炎症の進行を示唆する重要な所見です。
吸引に伴う合併症の早期発見も重要です。低酸素血症ではSpO₂低下、チアノーゼ、頻脈が見られ、気道損傷では血液混入、疼痛増強が生じます。迷走神経刺激による徐脈、血圧低下にも注意を払い、異常時には速やかに処置を中止し、医師に報告します。
患者さんの主観的な症状として、「息が楽になった」「胸がすっきりした」といった改善の訴えは重要な評価指標です。逆に、「苦しさが変わらない」「痛みが強い」などの訴えは、手技の見直しや他の原因の検索が必要なことを示唆します。
長期的な評価では、吸引頻度の変化、分泌物量の推移、呼吸機能の改善度を継続的に評価し、患者さんの全体的な呼吸状態の改善を図ります。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 非効率的気道クリアランス
- ガス交換障害
- 感染リスク状態
- 不安
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さんの吸引に対する理解度と受け入れ状況を評価します。吸引の必要性と効果について分かりやすく説明し、患者さんが協力的に処置を受けられるよう支援します。在宅での吸引が必要な場合は、家族への技術指導と安全管理について詳細な教育を行います。
活動-運動パターンでは、吸引前後の活動耐性の変化を評価します。効果的な吸引により呼吸状態が改善すれば、活動耐性の向上が期待できます。体位変換や早期離床が分泌物の移動と排出を促進するため、適切な活動計画を立案し、吸引との相乗効果を図ります。
睡眠-休息パターンでは、夜間の分泌物貯留と睡眠への影響を評価します。体位による分泌物の移動、睡眠中の呼吸状態を観察し、必要に応じて夜間の吸引実施を検討します。適切な体位管理により、夜間の分泌物貯留を軽減し、睡眠の質向上を図ります。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
呼吸の欲求に対しては、効果的な気道クリアランスの維持を最優先課題として位置づけます。患者さんの状態に応じた適切な吸引方法を選択し、継続的な効果評価と手技の調整を行います。分泌物の除去により気道の開通性を確保し、効率的な換気とガス交換を支援します。
苦痛の回避と除去では、吸引に伴う身体的・精神的苦痛の軽減を図ります。吸引時の不快感、恐怖感、痛みを最小限に抑えるため、適切な前処置、丁寧な説明、技術の向上に努めます。患者さんの表情や訴えに注意を払い、個別性を考慮した優しいケアを提供します。
安全の欲求に対しては、吸引に伴う合併症の予防と安全管理を徹底します。無菌操作の確実な実施、適切な吸引圧と時間の設定、継続的なモニタリングにより、安全で効果的な吸引を提供します。緊急時の対応体制も整備し、患者さんが安心して処置を受けられる環境を確保します。
具体的な看護介入
無菌操作と感染予防の徹底では、標準予防策を基本とした厳格な感染対策を実施します。適切な手洗い、個人防護具の使用、器具の無菌管理により、医療関連感染を防止します。使用済み器具の適切な処理と環境の清潔保持により、安全な医療環境を維持します。
個別性を考慮した吸引技術の提供では、患者さんの年齢、体格、病態、意識レベルに応じた最適な吸引方法を選択します。吸引圧、チューブサイズ、実施時間、体位を個別に調整し、最大の効果と最小の侵襲を実現します。
継続的な技術向上と教育により、最新のエビデンスに基づいた吸引技術を習得し、安全で効果的なケアを提供します。チーム内での技術統一、定期的な勉強会、事例検討を通じて、質の高い吸引ケアを実現します。
多職種との連携強化により、医師、呼吸療法士、理学療法士などとの情報共有を密にし、包括的な呼吸管理を実現します。吸引の効果評価、手技の改善、患者状態の変化について定期的にカンファレンスを行い、最適なケアプランを継続的に見直します。
8. よくある質問・Q&A
Q:吸引中にSpO₂が下がった場合、どのように対応すべきでしょうか?
A: SpO₂の低下は吸引による低酸素血症を示唆する重要な所見です。直ちに吸引を中止し、100%酸素投与やアンビューバッグによる換気支援を行ってください。前酸素化が不十分だった可能性も考えられるため、次回の吸引ではより長時間の前酸素化(2-3分間)を実施します。頻回の吸引や長時間の吸引も原因となるため、必要最小限の実施を心がけてください。
Q:気管内吸引でチューブがなかなか入らない場合の対処法を教えてください
A: チューブが入りにくい場合は、無理に挿入せず、一度引き抜いて再試行してください。チューブの向きや角度を調整し、ゆっくりと挿入することで改善する場合があります。気管チューブの位置異常や分泌物による閉塞も考えられるため、医師に相談して評価を受けてください。適切なサイズのチューブ使用も重要で、太すぎるチューブは挿入困難の原因となります。
Q:分泌物が粘稠で吸引しにくい場合はどうすればよいでしょうか?
A: 粘稠な分泌物には加湿療法や体位ドレナージが効果的です。ネブライザーや超音波ネブライザーによる気道加湿、適切な水分摂取により分泌物の粘稠度を改善できます。理学療法士による胸部理学療法も有効で、分泌物の移動と排出を促進します。吸引前の体位変換も分泌物を移動させ、吸引しやすくする効果があります。
Q:患者さんが吸引を嫌がる場合の対応方法を教えてください
A: 患者さんの吸引への抵抗は不安や恐怖、過去の不快な体験が原因であることが多いです。まず、吸引の必要性と効果を丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。「少し我慢していただければ、呼吸が楽になります」など、具体的な効果を伝えてください。前処置の充実、優しい手技、処置後の声かけにより、患者さんの不安を軽減し、協力を得られるよう努めてください。
9. まとめ
気道内吸引は患者さんの呼吸機能を直接支援する重要な看護技術です。適切な手技と継続的な評価により、効果的な気道クリアランスを実現し、患者さんの呼吸状態改善と快適性向上に大きく貢献できます。
覚えるべき重要数値・基準
- 吸引圧:成人80-120mmHg、小児60-100mmHg、新生児60-80mmHg
- 一回吸引時間:10-15秒以内(小児5-10秒)
- チューブサイズ:口腔用14-16Fr、鼻腔・気管内用10-14Fr
- 前酸素化:FiO₂ 100%で1-2分間
- 評価頻度:2-4時間毎の状態評価
- チューブ選択基準:気管チューブ内径の1/2以下
実習・現場で活用できるポイント
気道内吸引では「安全性と効果の両立」が最も重要です。無菌操作を確実に実施し、患者さんの状態を継続的に観察しながら、必要最小限の侵襲で最大の効果を得られる手技を心がけましょう。また、患者さんの不安や恐怖に共感し、丁寧な説明と優しいケアにより、協力的な関係を築くことが成功の鍵となります。多職種との連携により、包括的な呼吸管理を提供することを大切にしてください。つけることを目標とし、多職種連携の重要性も常に意識して患者ケアに取り組んでください。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
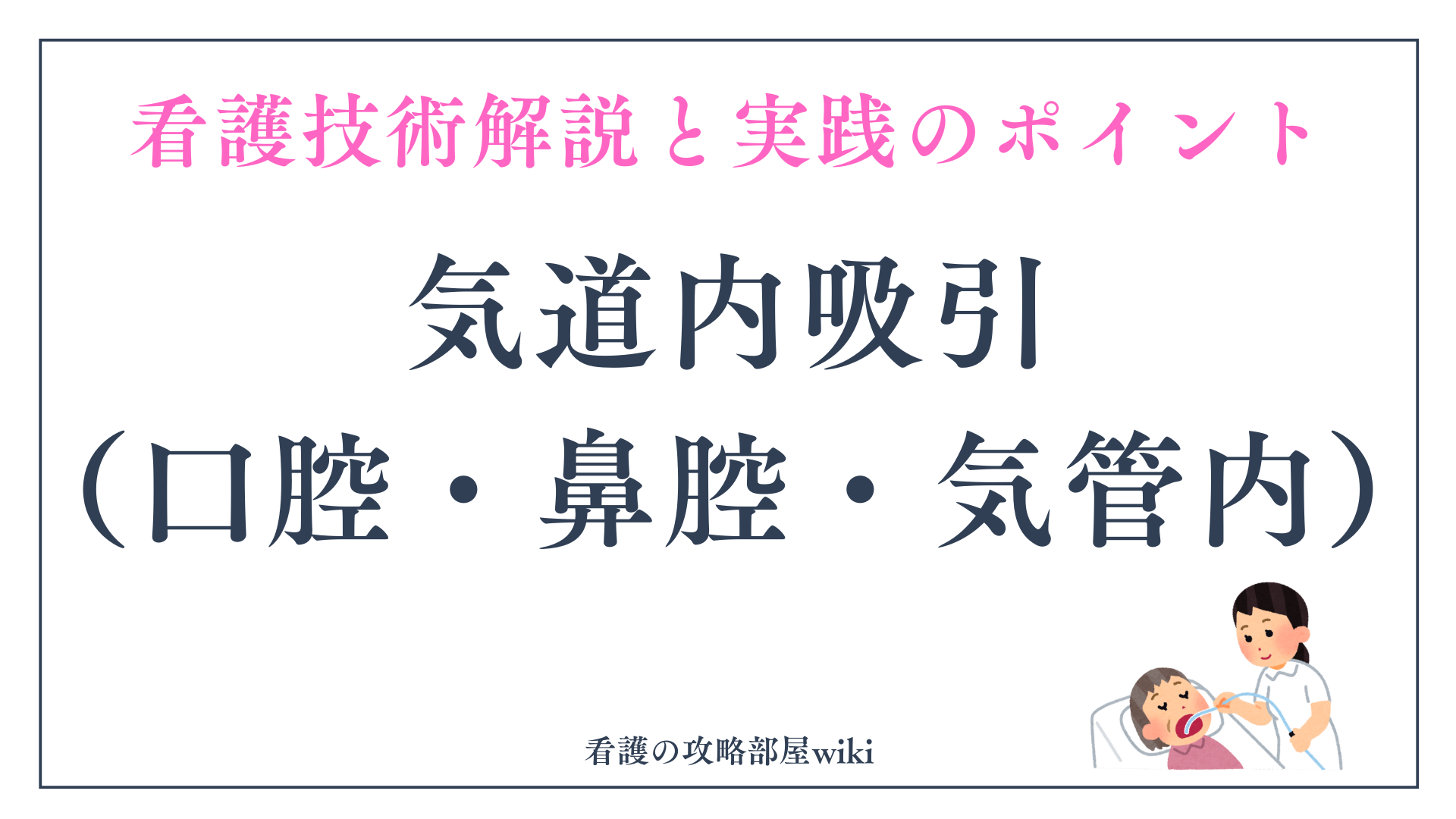

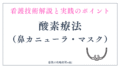
コメント