1. はじめに
「注射は痛いから嫌だ」「本当に正しい場所に打てているか心配」といった患者さんの声や、看護学生の不安をよく耳にします。筋肉注射は、薬物を筋肉内に投与することで確実で安定した薬効を得られる重要な治療技術です。
筋肉注射は皮下注射に比べて吸収が早く、静脈注射に比べて安全性が高いという特徴があります。ワクチン接種、抗生物質投与、鎮痛薬投与など、様々な場面で実施される基本的な看護技術でありながら、解剖学的知識と正確な手技が要求される専門性の高い技術でもあります。
実習では、患者さんの安全と安楽を最優先に考えながら、科学的根拠に基づいた正確な手技を身につけることが求められます。また、患者さんの不安を軽減し、信頼関係を築きながら実施することで、治療への協力を得ることも重要な要素となります。
この記事で学べること:
- 筋肉注射の適応と解剖学的基礎知識の理解
- 安全で確実な注射部位の選択と確認方法
- 正しい手技と注射針の選択・使用方法
- 患者の個別性に応じた実施方法と配慮事項
- 合併症の予防と早期発見・対応技術
2. 筋肉注射の基本情報
定義
筋肉注射とは、薬液を筋肉組織内に投与することにより、皮下注射より速やかで静脈注射より安全な薬物吸収を得る注射技術
技術の意義と目的
筋肉注射は筋肉組織の豊富な血管により、皮下注射に比べて2-3倍速い吸収が得られ、15-30分で効果が現れます。注射部位の筋肉量が十分であれば最大5mlまでの薬液投与が可能で、油性薬剤や懸濁液など、静脈内投与できない薬剤の投与にも適しています。
患者さんにとっては、確実で予測可能な薬効により症状の改善が期待でき、看護師にとっては、安全で効果的な薬物投与により患者さんの治療目標達成を支援できます。ワクチン接種では95%以上の確実な免疫獲得が可能となります。
実施頻度・タイミング
筋肉注射の実施は医師の指示に基づき、薬剤の種類と患者さんの状態に応じて決定されます。単回投与から1日数回の定期投与まで様々で、ワクチン接種では決められたスケジュールに従って実施します。疼痛管理では必要時投与も行われます。
3. 必要物品と準備
基本的な筋肉注射用品
注射器・注射針
- 注射器:1ml、2ml、5ml(投与量に応じて選択)
- 注射針:18-22G、25-38mm(部位と患者の体型に応じて選択)
- 薬液吸引用針:18-20G(薬液の粘度に応じて)
薬剤関連
- 処方薬剤(アンプル、バイアル)
- 溶解液(必要時)
- アルコール綿またはアルコールスワブ
安全・清潔用品
- 使い捨て手袋
- 手指消毒薬
- 注射部位消毒薬(アルコール系消毒薬)
- 絆創膏またはガーゼ
廃棄・安全管理用品
感染防止用品
- 針刺し事故防止用品(セーフティボックス)
- 感染性廃棄物容器
- 針リキャップ防止デバイス
緊急時対応用品
- 救急薬品(エピネフリン、抗ヒスタミン薬)
- 血圧計、パルスオキシメーター
- 酸素投与準備物品
物品準備のポイント
注射針の選択は患者さんの年齢、性別、BMI、注射部位を総合的に考慮します。成人男性の殿部では25mm以上、小児や痩せ型の患者では25mm以下が適当です。薬液の性状(水溶性、油性、懸濁液)に応じて針の太さも調整します。
4. 筋肉注射の実施手順
事前準備とアセスメント
環境整備では、プライバシーが保護できる静かな場所を選び、十分な照明と適切な室温を確保します。患者さんには注射の必要性、使用する薬剤、予想される効果と副作用について説明し、同意を得ます。
アセスメントでは、既往歴(薬物アレルギー、出血傾向)、バイタルサイン、注射部位の皮膚状態、筋肉の発達程度、可動域制限の有無を評価します。特に抗凝固薬服用中の患者では出血リスクを慎重に評価します。
基本手順
薬液の準備 6R(正しい患者、薬剤、用量、経路、時間、記録)を確実に確認します。アンプルの場合はネック部分を清拭後に折り、バイアルの場合はゴム栓を清拭してから薬液を吸引します。薬液吸引時は18-20Gの太い針を使用し、投与時には新しい針に交換します。
注射部位の選択と確認 三角筋:肩峰の下2-3横指、上腕骨外側で骨の上1/3の部分 中殿筋:左右の上前腸骨棘を結んだ線と正中線の交点から外側へ2-3cm 大腿四頭筋外側広筋:膝蓋骨上端から10-15cm上方の外側部
選択した部位の解剖学的ランドマークを触診で確認し、血管、神経の走行を避けることを確認します。
消毒と穿刺 注射部位をアルコール系消毒薬で中央から外側へ円を描くように消毒し、完全に乾燥させます。皮膚を非利き手で伸展させ、90度の角度で迅速に穿刺します。血管内誤挿入防止のため、軽く陰圧をかけて血液の逆流がないことを確認してから薬液を注入します。
注入と抜針 薬液は1ml/分程度の速度でゆっくりと注入し、患者さんの表情や訴えを観察します。注入後は10秒程度待機してから迅速に抜針し、注射部位を軽く圧迫します。強くマッサージすることは避け、必要に応じて絆創膏を貼付します。
実施中の観察ポイント
穿刺時は血液の逆流の有無を必ず確認し、注入中は疼痛の増強、腫脹、薬液の漏れがないか観察します。患者さんの顔色、呼吸状態、意識レベルの変化にも注意し、アナフィラキシー反応の早期発見に努めます。
5. 特殊な状況での筋肉注射
高齢者への配慮 皮膚の脆弱性と筋肉量の減少を考慮し、針は短め(25mm以下)を選択します。消毒後の乾燥時間を十分にとり、穿刺角度を85-90度で実施します。抗凝固薬服用者では圧迫時間を長くし、内出血の予防に努めます。
小児・乳幼児への配慮 2歳未満では大腿四頭筋外側広筋を第一選択とし、2歳以上では三角筋も使用可能です。針の長さは16-25mm、薬液量は年齢に応じて制限(乳児:0.5ml以下、幼児:1ml以下)します。保護者の協力を得て適切な体位保持を行います。
妊婦への配慮 妊娠期間を通じて筋肉注射は実施可能ですが、薬剤の妊娠への影響を事前に確認します。体位は側臥位を基本とし、仰臥位症候群を避けます。妊娠後期では腹部の圧迫を避ける体位での実施が重要です。
出血傾向のある患者への配慮 抗凝固薬服用中や血小板減少症の患者では、可能な限り細い針(23-25G)を使用し、注射後の圧迫を5-10分間継続します。注射部位の腫脹や内出血の観察を十分に行い、必要に応じて冷罨法を実施します。
6. 筋肉注射中の観察とアセスメント
即座の観察項目 穿刺時の血液逆流の有無、注入中の疼痛の程度、薬液の漏出、皮膚の変色や腫脹を観察します。患者さんの表情の変化、不快感の訴えも重要な指標となります。
アレルギー反応の観察 注射後15-30分間は呼吸困難、じんま疹、血圧低下、意識レベルの変化などのアナフィラキシー症状を観察します。軽微な反応でも見逃さず、バイタルサインの変化を継続的にモニタリングします。
局所反応の観察 注射後24-48時間は注射部位の発赤、腫脹、硬結、疼痛の程度を評価します。正常な炎症反応と異常な反応を区別し、感染徴候(熱感、波動、膿性分泌物)の早期発見に努めます。
全身反応の評価 薬剤固有の副作用症状の出現を観察し、効果の発現時期と程度を評価します。疼痛管理薬では疼痛スコアの変化、ワクチンでは発熱や倦怠感などの一般的な反応を観察します。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 急性疼痛(注射に関連した)
- 感染リスク状態
- 不安(注射手技に関連した)
- 皮膚統合性障害リスク状態
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚・健康管理パターンでは、患者さんの注射に対する理解度、過去の注射経験、薬物アレルギーの既往を詳しく評価します。筋肉注射の必要性に対する認識、治療への協力度、自己管理能力を観察し、適切な説明と支援を提供します。服薬歴や健康管理への取り組み姿勢も重要な評価項目となります。
認知・知覚パターンでは、疼痛に対する感受性、不安のレベル、注射に対する恐怖心の程度を評価します。過去の痛みの体験や注射に対するトラウマの有無、痛みの表現方法や対処法についても観察します。認知機能の程度に応じた説明方法の選択も必要です。
対処・ストレス耐性パターンでは、注射に対する不安やストレスへの対処方法、支援システムの有無を評価します。リラクゼーション技法の活用、家族の支援、過去の類似体験での対処法などを観察し、個別的な支援計画を立案します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
身体的安全の欲求に対しては、正確で安全な注射手技により、感染や神経損傷などの合併症を予防します。適切な注射部位の選択、無菌操作の徹底、針刺し事故の防止により、患者さんと看護師双方の安全を確保します。緊急時対応の準備を整え、万一の副作用反応にも迅速に対応できる体制を維持します。
痛みの回避の欲求では、患者さんの疼痛を最小限に抑えるための工夫を行います。適切な針の選択、迅速で確実な手技、注射前後の説明とコミュニケーション、必要に応じた表面麻酔の使用などにより、身体的・精神的苦痛を軽減します。
安心と信頼の欲求に対しては、十分な説明と同意の取得、患者さんの質問や不安への真摯な対応により、治療への信頼関係を築きます。プライバシーの保護、尊厳への配慮、専門的で確実な技術の提供により、患者さんが安心して治療を受けられる環境を整えます。
具体的な看護介入
事前の不安軽減対策が最も重要な介入となります。注射の必要性と効果について分かりやすく説明し、手技の流れを事前に伝えることで、患者さんの不安を軽減します。過去の注射体験について聞き取り、恐怖心がある場合は共感的に対応し、今回の注射では十分な配慮を行うことを伝えます。
正確で安全な手技の実施では、解剖学的知識に基づいた適切な部位選択、無菌操作の徹底、6Rの確実な実施により、安全で効果的な薬物投与を行います。患者さんの個別性(年齢、体型、筋肉量、皮膚状態)を考慮し、最適な器具選択と手技の調整を行います。
継続的な観察と合併症予防では、注射後の局所・全身反応を系統的に観察し、異常の早期発見と適切な対応を行います。患者さんには注射後の注意事項を説明し、異常があった場合の連絡方法を伝えます。記録の正確な記載により、次回注射時の参考情報として活用します。
8. よくある質問・Q&A
Q:注射針を刺した時に血液が逆流した場合はどうすればよいですか?
A: 直ちに針を抜いて注射を中止し、注射部位を清潔なガーゼで圧迫します。血管内に薬剤を投与することは危険な副作用を引き起こす可能性があるため、絶対に薬液を注入してはいけません。別の部位を選択して再度注射を実施します。逆流した血液量が多い場合や患者さんに異常がある場合は、医師に報告します。このような事態を避けるため、穿刺後は必ず吸引して血液逆流がないことを確認することが重要です。
Q:患者さんが「以前注射でアレルギーが出たことがある」と言われた場合はどうすればよいですか?
A: 詳しい状況を聞き取り、どのような薬剤で、どのような症状が出たのかを確認します。軽微な局所反応(発赤、腫脹)と全身のアレルギー反応(呼吸困難、血圧低下)では重要度が大きく異なります。今回使用予定の薬剤が同じものかどうか、医師がアレルギー歴を把握しているかを確認し、不明な点があれば必ず医師に報告してから実施します。アレルギー反応の既往がある場合は、救急薬品の準備と注射後の厳重な観察が必要です。
Q:筋肉注射の部位選択で迷った時はどうすればよいですか?
A: 患者さんの年齢と体型を第一に考慮します。成人では三角筋が第一選択ですが、筋肉量が少ない場合や上肢に可動域制限がある場合は中殿筋を選択します。2歳未満の小児では大腿四頭筋外側広筋が安全です。迷った場合は解剖学的ランドマークを触診で確認し、血管・神経の走行から十分離れていることを確認してから実施します。自信がない場合は先輩看護師や医師に相談することも重要です。
Q:注射後に患者さんが「すごく痛い」と訴える場合はどうすればよいですか?
A: まず痛みの性質と程度を詳しく聞き取ります。刺すような鋭い痛みは神経損傷の可能性、ズキズキする痛みは血管損傷や炎症の可能性があります。注射部位の観察を行い、異常な腫脹、発赤、硬結がないか確認します。痛みが持続する場合や増強する場合は医師に報告します。一般的な筋肉注射後の疼痛であれば、冷罨法や安静により軽減することを説明し、24-48時間で改善することを伝えます。ただし、異常な痛みや神経症状(しびれ、脱力)がある場合は緊急性が高いため、直ちに医師に報告します。
9. まとめ
筋肉注射は基本的な看護技術でありながら、正確な解剖学的知識と確実な手技が要求される専門性の高い技術です。患者さんの安全と安楽を最優先に考えながら、科学的根拠に基づいた実践を行うことが重要です。
覚えるべき重要数値・基準
- 針の長さ:25-38mm(部位と体型に応じて選択)
- 針の太さ:18-22G(薬液の性状に応じて選択)
- 注入速度:1ml/分程度でゆっくりと
- 最大投与量:筋肉量が十分であれば5mlまで
- 効果発現時間:15-30分
- 三角筋:肩峰下2-3横指
- 中殿筋:上前腸骨棘線から外側2-3cm
- 大腿四頭筋:膝蓋骨上端から10-15cm上方
- 穿刺角度:90度
- 観察期間:アレルギー反応は15-30分間、局所反応は24-48時間
実習・現場で活用できるポイント
実習では、患者さん一人ひとりの身体的特徴と心理状態を総合的にアセスメントし、個別性を重視した安全で効果的な注射技術を実践します。ゴードンの健康知覚・健康管理パターンとヘンダーソンの身体的安全の欲求を活用し、患者さんの安全確保と不安軽減に努めます。
解剖学的知識の確実な理解により、適切な注射部位を選択し、血管・神経損傷などの合併症を予防します。6R(正しい患者、薬剤、用量、経路、時間、記録)の確実な実施により、医療安全の確保に貢献します。
患者さんとのコミュニケーションでは、事前の十分な説明により信頼関係を築き、注射後の観察と適切な記録により、継続的な安全管理を実現していきましょう。常に謙虚な姿勢で学び続け、患者さんにとって最良のケアを提供することを心がけます。歩行介助は患者さんの自立と生活の質向上に直結する重要な技術として、継続的にスキルアップを図っていきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

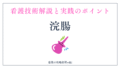

コメント