1. はじめに
導尿は、患者さんの排尿機能を援助し、生命を支える重要な看護技術です。「単にカテーテルを挿入するだけ」と思われがちですが、実は患者さんの尊厳を守りながら、感染予防と安全性を両立させる高度な技術なのです。
実習現場では、「恥ずかしくて嫌だ」「痛くないか心配」「いつまで管を入れておくのか」といった患者さんの切実な声を聞くことがあります。また、「こんな介護をしてもらって申し訳ない」という患者さんの遠慮や、家族の「本当に必要なのでしょうか」という疑問にも向き合う必要があります。
導尿には一時的導尿(間欠的導尿)と持続的導尿(留置カテーテル)があり、それぞれに明確な適応と目的があります。適切な導尿管理は、尿路感染症や腎機能障害の予防、患者の快適性向上に直結します。しかし、不適切な管理は重篤な合併症を招く危険性もあります。
看護師は、患者さんの羞恥心に配慮しながら、科学的根拠に基づいた安全で効果的な導尿ケアを提供する責任があります。また、可能な限り自然排尿への復帰を目指し、患者さんの自立支援に努めることも重要な役割です。
この記事で学べること
- 一時的導尿と持続的導尿の適応と選択基準
- 無菌操作による安全な導尿手技の習得方法
- 尿路感染症予防のための具体的な管理方法
- 患者の羞恥心への配慮と心理的ケア
- 合併症の早期発見とアセスメント技術
2. 導尿の基本情報
定義
導尿とは、カテーテルを尿道に挿入して膀胱内の尿を体外に排出させる看護技術である
導尿は、自然排尿が困難または不可能な患者に対して、膀胱内圧の軽減、尿路の機能評価、感染予防を目的として実施される侵襲的処置です。一時的導尿では処置後にカテーテルを抜去し、持続的導尿では一定期間カテーテルを留置して持続的な排尿管理を行います。
技術の意義と目的
導尿の最大の意義は、膀胱機能の代替と尿路系の保護です。尿閉や排尿困難により膀胱内圧が上昇すると、腎盂腎炎や腎機能低下を引き起こす危険があります。適切な導尿により、これらの合併症を予防できます。
患者さんにとっては、膀胱の不快感や痛みから解放され、「楽になった」「スッキリした」という安心感を得ることができます。特に術後や急性期の患者さんでは、排尿への不安が軽減されることで、治療に集中できるようになります。
看護師にとって導尿は、患者の全身状態を把握する重要な手がかりともなります。尿量、尿性状、排尿パターンの観察により、循環動態や腎機能、感染症の早期発見が可能になります。
実施頻度・タイミング
一時的導尿は必要時に実施し、通常1回の処置で完了します。術前の膀胱空虚化、尿閉時の緊急処置、残尿測定などが主な適応です。
持続的導尿では、カテーテル留置期間中は24時間持続的な排尿管理を行います。留置期間は最短必要期間に留め、7-14日での抜去を目標とすることが多く、長期留置が必要な場合は4-6週間ごとの交換が推奨されています。
導尿のタイミングは患者の状態により異なりますが、膀胱内尿量が300-400mlに達する前の実施が理想的です。過度の膀胱拡張は膀胱機能の低下や感染リスクの増加を招くため、適切なタイミングでの介入が重要です。
3. 必要物品と準備
基本的な導尿用品
カテーテル類
- 一時的導尿用カテーテル(14-16Fr):成人女性用、材質はシリコンまたはラテックス
- 持続導尿用バルーンカテーテル(14-18Fr):留置期間に応じたサイズ選択
- 小児用カテーテル(8-12Fr):年齢・体格に応じて選択
- 三方活栓付きカテーテル:膀胱洗浄が必要な場合
無菌器具類
- 滅菌手袋:術者用(適切なサイズ)
- 滅菌ガーゼ:陰部消毒・清拭用
- 滅菌綿球:細かい部分の消毒用
- 消毒用鑷子(ペアン鉗子):無菌操作用
- 滅菌トレイ:物品配置用
消毒・洗浄剤
- ポビドンヨード(イソジン):皮膚・粘膜消毒用
- 生理食塩水:洗浄・希釈用
- 滅菌蒸留水:バルーン膨張用(5-10ml)
- 潤滑剤(キシロカインゼリー):挿入時の摩擦軽減・局所麻酔効果
測定・観察器具
- 計量カップ:尿量測定用(目盛り付き)
- 蓄尿バッグ:持続導尿時の尿収集用
- pH試験紙:尿性状確認用
- 尿比重計:尿濃縮度測定用
持続導尿特有用品
固定・管理用品
- カテーテル固定用テープ:皮膚に優しい材質
- レッグバッグ:日中の尿収集用(500-750ml容量)
- ナイトバッグ:夜間用大容量バッグ(2000ml容量)
- カテーテルクランプ:流量調整用
交換・メンテナンス用品
- 膀胱洗浄用生理食塩水:結晶や血塊除去用
- カテーテルプラグ:一時的閉鎖用
- 採尿バッグ:尿検査検体採取用
状況別対応用品
感染対策用品
- 使い捨てエプロン:術者の衣服保護用
- フェイスシールドまたはゴーグル:飛沫防護用
- 手指消毒剤:手指衛生用
- 環境消毒剤:周辺環境の清潔保持用
緊急時対応用品
- 吸引器:分泌物除去用
- 酸素吸入器具:呼吸困難時対応用
- 血圧計:循環動態監視用
- 救急薬品:アナフィラキシー対応用
特殊状況対応用品
- 膀胱鏡:直視下でのカテーテル挿入用
- 尿道ブジー:尿道狭窄時の拡張用
- 恥骨上穿刺セット:経尿道的挿入困難時用
- 抗痙攣剤:膀胱痙攣時対応用
物品準備のポイント
物品選択では患者の個別性と安全性を最優先に考えます。高齢女性では尿道が短く挿入しやすい反面、尿道損傷のリスクがあるため、十分な潤滑剤の使用と愛護的操作が必要です。
カテーテルのサイズ選択は重要で、太すぎると尿道損傷、細すぎると排尿効果不十分となります。一般的に成人では14-16Frが標準ですが、血尿や膿尿がある場合は16-18Frの使用を検討します。
アレルギー歴の確認も必須で、ラテックスアレルギーの患者にはシリコン製カテーテルを選択し、ヨードアレルギーの患者には代替消毒剤を使用します。患者さんに「以前にゴム製品でかぶれたことはありますか」と確認することで、重篤なアレルギー反応を予防できます。
プライバシー保護の観点から、処置室の環境整備も重要です。十分なスペースの確保、適切な照明、カーテンやスクリーンによる遮蔽など、患者さんが安心して処置を受けられる環境を整えます。
4. 導尿の実施手順
事前準備とアセスメント
まず、医師の指示内容を正確に確認し、導尿の目的、種類、特別な注意事項を把握します。患者さんには「排尿のお手伝いをさせていただきますね」と説明し、インフォームドコンセントを得ます。羞恥心への配慮として「プライバシーをお守りしますので、ご安心ください」と声をかけます。
膀胱の状態評価として、下腹部の膨隆、叩打痛の有無、最終排尿時刻を確認します。エコー検査により膀胱内尿量を測定できる場合は、300ml以上で導尿の適応とすることが多いです。
全身状態の確認では、意識レベル、循環動態、体温、感染兆候の有無を評価します。発熱や白血球増多がある場合は、尿路感染症を疑い、より慎重な無菌操作が必要となります。
環境整備では、処置室の温度を22-26℃に調整し、十分な明るさを確保します。必要物品を手の届く範囲に配置し、無菌野を作成する準備を整えます。
一時的導尿の実施手順
1. 体位の調整 患者を仰臥位とし、両下肢を軽度屈曲させます。女性では截石位または膝立て位が標準的で、男性では仰臥位で陰茎を腹部方向に軽く牽引した位置とします。羞恥心に配慮し、必要最小限の露出に留めます。
2. 無菌操作の実施 手指消毒を徹底し、滅菌手袋を装着します。滅菌トレイに物品を配置し、無菌野を確保します。この段階で「清潔に処置を進めますので、少々お時間をいただきます」と説明します。
3. 陰部の消毒 女性では恥骨結合部から肛門方向へ、尿道口を中心として消毒します。大陰唇、小陰唇、尿道口の順で、外側から内側、清潔部から汚染部へ向かって消毒します。男性では亀頭部を露出させ、尿道口から外側へ円を描くように消毒します。
4. カテーテルの挿入 潤滑剤をカテーテル先端に十分量塗布します。女性では尿道口を確認し、4-6cm挿入します。男性では陰茎を軽く伸展させ、18-20cm挿入します。挿入時は「少し圧迫感がありますが、我慢してください」と声をかけます。
5. 尿の排出と観察 尿の流出を確認したら、自然流下により完全に排尿させます。この時、尿量、色調、混濁の有無を観察し、記録します。急激な大量排尿時は血圧低下に注意し、500ml以上の場合は一時的にクランプして段階的に排出することもあります。
6. カテーテルの抜去 排尿が完全に終了したことを確認し、ゆっくりとカテーテルを抜去します。抜去時も愛護的に行い、尿道損傷を防止します。
持続的導尿の実施手順
1. バルーンカテーテルの準備 バルーンの完全性を事前に確認します。滅菌蒸留水5-10mlでバルーンを膨張・収縮させ、リークがないことを確認します。バルーンに異常がある場合は、決して使用せず新しいものと交換します。
2. カテーテルの挿入 基本的な挿入手技は一時的導尿と同様ですが、尿の流出を確認後、さらに2-3cm深く挿入してからバルーンを膨張させます。これにより、バルーンが完全に膀胱内に位置することを確保します。
3. バルーンの膨張 滅菌蒸留水を用いてバルーンを膨張させます。通常5-10mlを注入しますが、患者の体格や膀胱の状態により調整します。膨張後は軽く牽引し、バルーンが膀胱頸部に位置することを確認します。
4. 固定と接続 カテーテルを大腿内側にテープで固定し、張力がかからないよう調整します。蓄尿バッグを接続し、膀胱より低い位置に設置します。バッグの容量と目盛りを確認し、正確な尿量測定が可能な状態にします。
実施中の観察ポイント
処置中は患者の表情、呼吸パターン、循環動態を継続的に観察します。疼痛の訴えがある場合は処置を一時中断し、原因を検索します。特に血尿の出現や強い疼痛は尿道損傷を示唆するため、直ちに医師に報告します。
挿入困難な場合は、無理に挿入せず医師に相談します。前立腺肥大症や尿道狭窄などの器質的病変がある可能性があり、専門的な処置が必要となることがあります。
バイタルサインの変動にも注意し、特に血圧低下や徐脈は迷走神経反射を示唆します。処置後は30分程度の経過観察を行い、患者の状態が安定していることを確認します。
5. 特殊な状況での導尿
小児患者への導尿
小児では解剖学的特徴と心理的配慮が重要です。尿道が短く細いため、8-12Frの細いカテーテルを選択し、挿入長は女児2-3cm、男児6-8cm程度とします。
恐怖心や不安が強いため、年齢に応じた説明を行います。「お腹の中の悪いおしっこを出してあげますね」「少しチクチクするけど、すぐに楽になりますよ」など、理解しやすい言葉で説明します。可能な限り両親の付き添いを許可し、安心できる環境を提供します。
処置中は体動による損傷を防ぐため、適切な体位保持が必要です。しかし、過度の抑制は避け、看護師が優しく支えることで安全性を確保します。
高齢患者への導尿
高齢者では認知機能の低下や身体機能の変化に配慮が必要です。認知症患者では処置の意味を理解できない場合があり、不穏や抵抗を示すことがあります。
尿道粘膜の菲薄化により損傷しやすいため、十分な潤滑剤の使用と愛護的操作が重要です。また、前立腺肥大症や骨盤底筋の緩みにより、挿入困難や尿失禁を併発することがあります。
薬剤の影響も考慮し、抗コリン薬や利尿薬の使用状況を確認します。これらの薬剤は膀胱機能に影響し、導尿後の自然排尿に影響することがあります。
脊髄損傷患者への導尿
脊髄損傷患者では神経因性膀胱により、膀胱機能が著しく障害されています。自律神経過反射のリスクがあるため、処置前に血圧測定を行い、異常値がある場合は医師に相談します。
間欠的自己導尿の指導が重要で、患者の残存機能を活かした自立支援を行います。上肢機能が保たれている患者では、清潔間欠導尿法の指導により、QOLの大幅な改善が期待できます。
膀胱洗浄が必要な場合があり、感染予防と結石形成予防のため定期的に実施します。洗浄液の温度は体温程度とし、強い圧力をかけないよう注意します。
術後患者への導尿
術後患者では麻酔の影響により、一時的に排尿機能が低下します。全身麻酔後6-8時間は特に注意深い観察が必要で、膀胱の過度な拡張を防ぐため適切なタイミングでの導尿を行います。
術式による特殊性も考慮し、婦人科手術後では膀胱損傷のリスク、泌尿器科手術後では血尿や血塊による閉塞のリスクがあります。
疼痛管理との関連では、強いオピオイド系鎮痛薬の使用により腸管運動低下や排尿困難が生じることがあります。薬剤の種類と投与量を確認し、必要に応じて医師と疼痛管理方法を検討します。
感染症患者への導尿
尿路感染症が疑われる患者では、より厳格な無菌操作が必要です。処置前に尿培養検体を採取し、適切な抗生剤治療の指標とします。
標準予防策を徹底し、処置後の手指衛生と環境消毒を確実に実施します。耐性菌感染の可能性がある場合は、接触予防策を併用し、専用の処置用具を使用します。
導尿後は感染兆候の監視を強化し、発熱、白血球増多、CRP上昇などの変化に注意します。特に菌血症への進展リスクがあるため、全身状態の慎重な観察が必要です。
6. 導尿中の観察とアセスメント
導尿中および導尿後の観察は、患者の安全確保と合併症の早期発見において極めて重要です。
尿の性状観察では、量、色調、混濁度、臭気が主要な項目となります。正常尿は淡黄色透明で特異臭はありません。血尿は尿路損傷や感染症を示唆し、膿尿(白濁尿)は細菌感染を疑います。
尿量の評価も重要で、成人では時間尿量0.5-1ml/kg/時が正常範囲です。乏尿(400ml/日未満)は腎機能低下や脱水を、多尿(3000ml/日以上)は糖尿病や腎疾患を示唆します。導尿後の初回自然排尿量や残尿量は、膀胱機能の回復度を評価する重要な指標です。
尿のpHと比重も有用な情報です。正常なpHは4.5-8.0で、アルカリ性に傾くと細菌感染を疑います。比重は1.010-1.025が正常で、低比重は腎濃縮能低下、高比重は脱水や糖尿を示唆します。
カテーテル周囲の観察では、挿入部位の発赤、腫脹、分泌物の有無を確認します。尿道口からの膿性分泌物は尿道炎を、カテーテル周囲の出血は機械的損傷を示唆します。
膀胱の状態評価では、導尿前後の腹部膨満の変化を観察します。導尿後も下腹部の膨隆が持続する場合は、不完全排尿や膀胱痙攣を疑います。
全身症状の観察では、発熱パターンが重要です。導尿後6-12時間以内の発熱は細菌の血中移行による菌血症を示唆し、持続的な微熱は慢性感染症を疑います。
循環動態の変化にも注意が必要で、急激な大量排尿後の血圧低下は循環血液量減少を示します。特に高齢者や心疾患患者では、心不全の増悪や不整脈のリスクがあります。
疼痛の評価では、部位、性質、程度を詳しく聴取します。腰背部痛は腎盂腎炎を、下腹部の持続痛は膀胱炎を、会陰部の鋭痛は尿道損傷を示唆することがあります。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 排尿パターン障害
- 感染リスク状態
- 急性疼痛
- セルフケア不足:トイレ行動
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
排泄パターンでは、導尿が患者の正常な排泄機能に与える影響を包括的に評価します。導尿前の排尿習慣、頻度、量、困難感を詳しく聴取し、導尿の必要性と期間を適切に判断します。持続導尿中は尿量の時間的変動を観察し、日内リズムや体位変換による影響を評価します。また、導尿終了後の自然排尿の回復過程を段階的に評価し、膀胱訓練の必要性を検討します。
活動・運動パターンでは、導尿が患者の活動性や移動能力に与える制限を最小限に抑える工夫を行います。持続導尿中の患者でも、レッグバッグの使用により歩行や車椅子移動が可能になります。転倒リスクを考慮し、カテーテルやバッグの固定方法を工夫し、患者が安全に活動できる環境を整えます。
自己概念・自己知覚パターンでは、導尿による患者の尊厳への影響を重視します。特に若年者や社会復帰を目指す患者では、導尿に対する羞恥心や無力感が強く、心理的支援が重要になります。患者の価値観や生活観を理解し、可能な限り患者らしさを維持できるよう援助します。
性・生殖パターンでは、導尿が性機能や生殖機能に与える影響について、適切な情報提供を行います。特に若年患者では将来への不安が強く、医師と連携して正確な情報を提供し、希望を失わせない支援を行います。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常な排泄をする欲求への援助では、導尿を単なる代替手段ではなく、膀胱機能回復への過程として位置づけます。可能な限り生理的な排尿パターンに近づけるよう、膀胱訓練や間欠的クランプなどの技法を用いて膀胱機能の回復を促進します。患者には「膀胱の筋肉を休ませて、回復を待っています」と説明し、治療の意味を理解してもらいます。
清潔に関する欲求では、導尿に伴う感染リスクを最小限に抑制しながら、患者の快適性を確保します。陰部の清潔保持、カテーテル挿入部のケア、尿臭の管理などを通じて、患者が清潔感を維持できるよう支援します。また、患者自身ができる清潔ケアを指導し、自立への意欲を高めます。
安全な環境で生活する欲求では、導尿に伴う合併症の予防と早期発見に努めます。感染予防策の徹底、カテーテル関連事故の防止、適切な観察とアセスメントにより、患者が安心して治療を受けられる環境を提供します。
愛され愛する欲求では、導尿による人間関係への影響を考慮します。家族や恋人との関係において、導尿が負担感や遠慮を生じさせないよう、適切な説明と支援を行います。
具体的な看護介入
最優先の介入は感染予防です。無菌的操作の徹底、適切な手指衛生、カテーテルケアの実施により、尿路感染症の発生を防ぎます。特に持続導尿では、閉鎖式システムの維持が重要で、不必要な開放は避け、採尿や洗浄時も無菌的手技を厳守します。
早期抜去への取り組みも重要な介入です。導尿の継続理由を毎日評価し、医師と連携して抜去時期を検討します。「今日は膀胱の調子はいかがですか」と患者に声をかけ、自覚症状の変化を把握します。膀胱訓練では段階的なクランプを行い、2-4時間ごとの間欠的開放から開始して膀胱機能の回復を促進します。
患者・家族への教育では、導尿の意義と管理方法について理解を深めてもらいます。感染予防の重要性、異常症状の早期発見方法、カテーテル管理の基本について段階的に指導します。在宅での自己管理が必要な場合は、清潔操作の技術習得と緊急時の対応方法を重点的に指導します。
心理的支援では、患者の羞恥心や不安に寄り添い、尊厳を保持できるよう配慮します。処置時は必要最小限の露出に留め、「プライバシーをお守りしますので、安心してくださいね」と声をかけます。また、導尿が一時的な処置であることを説明し、回復への希望を持続できるよう支援します。
多職種連携では、医師、理学療法士、作業療法士、薬剤師と連携して包括的なケアを提供します。特に神経疾患による排尿障害では、リハビリテーションとの連携により、残存機能を活かした自立支援を行います。泌尿器科専門医との連携では、膀胱機能検査や薬物療法の必要性について相談し、最適な治療方針を検討します。
8. よくある質問・Q&A
Q:カテーテル挿入時に抵抗があり、なかなか入らない場合はどうすればよいでしょうか?
A: まず無理な力を加えることは絶対に避けます。男性では前立腺肥大症による抵抗、女性では尿道口の同定困難が主な原因です。潤滑剤を追加し、挿入角度を調整してみます。男性では陰茎をより頭側に牽引し、尿道の生理的彎曲に沿って挿入します。それでも困難な場合は処置を中止し、医師に報告します。尿道損傷のリスクがあるため、専門医による処置が必要になることがあります。
Q:導尿後に血尿が出現した場合、どの程度まで様子を見てよいでしょうか?
A: 軽度の血尿(薄いピンク色程度)は、カテーテル挿入による機械的刺激で起こることがあり、30分-1時間程度で改善することが多いです。しかし、鮮血色の血尿や血塊を伴う血尿、持続的な出血がある場合は直ちに医師に報告します。患者さんには「少し血が混じることがありますが、様子を見させていただきますね」と説明し、不安を軽減します。血尿が持続する場合は、尿道損傷や膀胱損傷の可能性があり、緊急処置が必要です。
Q:持続導尿中の患者で、尿量が急に減少した場合の対応は?
A: まずカテーテルの閉塞を疑います。屈曲や血塊、結晶による閉塞が主な原因です。カテーテルの走行を確認し、屈曲があれば解除します。それでも改善しない場合は、20-30mlの生理食塩水で軽く洗浄を試みます。洗浄に抵抗がある場合は無理をせず、医師に相談します。また、脱水による尿量減少も考慮し、水分摂取量、バイタルサイン、皮膚の弾力性を確認します。腎機能低下の可能性もあるため、血液検査の必要性についても医師と相談します。
Q:在宅で間欠的自己導尿を行う患者への指導のポイントは?
A: 清潔操作の重要性を理解してもらうことから始めます。完全な無菌操作は困難ですが、手指衛生とカテーテルの清潔保持は必須です。実際の手技では、鏡を使った尿道口の確認方法、適切な挿入角度、挿入困難時の対応を段階的に指導します。カテーテルの消毒・保管方法、再使用の限界についても説明します。緊急時には「すぐに病院に連絡してください」と、24時間対応の連絡先を提供します。家族にも基本的な知識を共有し、患者を支える体制を整えます。
9. まとめ
導尿は、患者さんの生命を支え、苦痛を軽減する重要な看護技術です。単に技術的な手技の習得だけでなく、患者さんの尊厳を守り、心理的ケアを提供しながら、安全で効果的な処置を実施することが求められます。
一時的導尿と持続的導尿それぞれの特徴を理解し、患者さんの状態や病期に応じた適切な選択と管理を行うことが重要です。感染予防を最優先としながら、可能な限り早期の自然排尿回復を目指し、患者さんの自立支援に努めることが看護師の重要な役割です。
実習現場では、患者さんの羞恥心や不安に寄り添い、信頼関係を築きながらケアを提供することが大切です。また、家族への適切な説明と支援により、患者さんを取り巻く環境全体で治療を支えることができます。
覚えるべき重要数値・基準
- カテーテルサイズ:成人14-16Fr、小児8-12Fr
- 挿入長:女性4-6cm、男性18-20cm、女児2-3cm、男児6-8cm
- バルーン容量:5-10ml(滅菌蒸留水)
- 正常尿量:0.5-1ml/kg/時(成人)
- 膀胱容量:通常300-400mlで排尿欲求
- 残尿量:50ml以下が正常
- カテーテル交換間隔:4-6週間
- 尿pH:正常4.5-8.0
- 尿比重:正常1.010-1.025
- 処置後観察時間:30分以上
実習・現場で活用できるポイント
無菌操作を確実に実施し、感染予防を最優先に考えながら処置を行いましょう。患者さんの個別性を重視し、年齢、性別、疾患、心理状態に応じた柔軟な対応が重要です。
処置中は患者さんの表情や反応を注意深く観察し、疼痛や不快感に敏感に対応してください。また、羞恥心への配慮を忘れず、プライバシーの保護と尊厳の維持に努めることが大切です。
導尿後の観察とアセスメントを丁寧に行い、合併症の早期発見に努めましょう。特に感染兆候や尿路損傷の症状には注意を払い、異常を認めた場合は迅速に医師に報告することが重要です。
多職種との連携を積極的に図り、患者さんにとって最適なケアプランを立案し、早期の機能回復と自立支援を目指しましょう。心がけます。歩行介助は患者さんの自立と生活の質向上に直結する重要な技術として、継続的にスキルアップを図っていきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。


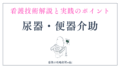
コメント