1. はじめに
車椅子移乗は、患者さんの自立支援と安全確保を両立させる重要な看護技術です。「単に車椅子に移すだけ」と思われがちですが、実は患者さんの残存機能を最大限に活用し、尊厳を保ちながら安全な移動を実現する高度な技術なのです。
実習現場では、「立てない」「怖い」「迷惑をかけて申し訳ない」といった患者さんの不安や遠慮の声を聞くことがあります。また、「一人でできるようになりたい」「家族に負担をかけたくない」という患者さんの切実な思いに触れることもあるでしょう。
車椅子移乗は、患者さんにとって自立への第一歩となることが多く、「自分で動けた」という成功体験は大きな励みとなります。適切な移乗技術により、患者さんは安全に移動でき、社会参加や生活の質の向上を図ることができます。
看護師にとって車椅子移乗は、患者さんの機能評価、転倒予防、自立支援を統合した重要な援助技術です。また、患者さんとの密接なコミュニケーションを通じて信頼関係を深め、リハビリテーションへの意欲を高める機会でもあります。
この記事で学べること
- 安全で効率的な車椅子移乗の基本技術
- 患者の状態別移乗方法の選択と実施
- 転倒・外傷予防のための安全管理
- 患者の残存機能を活かした自立支援技術
- 腰痛予防を含めた看護師の身体保護方法
2. 車椅子移乗の基本情報
定義
車椅子移乗とは、患者をベッドから車椅子へ、または車椅子からベッドへ安全に移動させる看護技術である
車椅子移乗は、患者の身体機能と移動能力に応じて、全介助、一部介助、見守りのレベルで実施される援助技術です。患者の自立度と安全性を両立させながら、日常生活活動の拡大と社会参加を促進することを目的とします。
技術の意義と目的
車椅子移乗の最大の意義は、患者の生活圏の拡大です。ベッドサイドから病室内、病棟内、さらには院外へと活動範囲が広がることで、患者さんの心理的・社会的な健康状態も大きく改善されます。
患者さんにとっては、「車椅子に乗れた」という達成感が自信につながり、「また外に出てみたい」「リハビリを頑張ろう」という意欲の向上をもたらします。家族にとっても、患者の移動能力の回復は大きな安心と希望を与えます。
看護師にとって車椅子移乗は、患者の身体機能評価と安全管理を同時に行う重要な機会です。移乗動作を通じて、筋力、バランス能力、認知機能、協調性などを包括的に評価し、今後のケアプランに反映させることができます。
実施頻度・タイミング
移乗の頻度は患者の状態と治療方針により異なりますが、1日2-3回が一般的です。離床時間は段階的に延長し、初期は30分-1時間から開始して、患者の耐性に応じて調整します。
最適なタイミングは患者の体調が良好な時間帯で、通常は午前中が適しています。食後すぐは避け、食事前1時間または食後2時間後の実施が推奨されます。バイタルサインが安定し、疼痛が軽微な時を選ぶことが重要です。
リハビリテーション計画との連携では、理学療法士の訓練前後の移乗により、治療効果を最大化できます。また、面会時間に合わせて実施することで、家族との交流を促進し、患者の心理的安定を図ることができます。
3. 必要物品と準備
基本的な車椅子移乗用品
車椅子本体
- 標準型車椅子:自操用・介助用(座面幅38-42cm)
- ティルト・リクライニング車椅子:重度障害者用
- 軽量車椅子:在宅用・外出用
- 電動車椅子:上肢機能障害者用
安全器具類
- 車椅子ベルト:体幹固定・転落防止用
- フットサポート:下肢支持・安全確保用
- アームサポート:上肢支持・立ち上がり補助用
- ブレーキ:駐車時の安全確保用
- 移乗ボード:滑らせて移動する補助具
クッション・パッド類
- シートクッション:褥瘡予防・快適性向上用
- 背当てクッション:体幹支持・姿勢保持用
- ヘッドサポート:頭部支持用(必要時)
- 側面パッド:体幹側方支持用
移乗補助用品
リフト・スタンディングマシン
- 全介助リフト:寝たきり患者用
- スタンディングリフト:立位保持困難患者用
- 移乗用リフト:ベッド⇔車椅子専用
- 移乗ベルト(ゲイトベルト):腰部支持・介助者の負担軽減
滑り用具
- スライディングボード:摩擦軽減移乗用
- スライディングマット:体位変換・移乗補助用
- ターンテーブル:方向転換補助用
環境整備用品
安全管理用品
- 床頭台:移乗時の障害物移動用
- ベッドサイドテーブル:物品整理用
- ナースコール:緊急時連絡用
- 履物:滑り止め付きスリッパまたはシューズ
感染対策用品
- 手指消毒剤:移乗前後の手指衛生用
- 車椅子用消毒剤:使用後の清拭用
- 使い捨て手袋:必要に応じて使用
- マスク:感染症患者対応用
観察・記録用品
- 血圧計:移乗前後のバイタル測定用
- パルスオキシメーター:酸素飽和度モニタリング用
- ストップウォッチ:移乗時間・離床時間測定用
- 体重計:定期的な体重測定用
状況別対応用品
麻痺患者用品
- 片麻痺用車椅子:健側操作対応型
- 足こぎ車椅子:下肢機能活用型
- 電動車椅子:重度上肢麻痺用
- 補装具:下肢装具・体幹装具
高齢者用品
- 認知症対応車椅子:立ち上がり防止機能付き
- 車椅子用テーブル:食事・活動支援用
- 車椅子用レインコート:外出時の雨天対応
- 保温用毛布:体温調節用
小児用品
- 小児用車椅子:体格に応じたサイズ
- 車椅子用玩具:移動時の気分転換用
- 安全ベルト:体動による転落防止用
- 付添い用補助席:保護者同乗用
物品準備のポイント
車椅子の選択では患者の身体的特徴を最優先に考慮します。座面の高さはベッドと同じ高さに調整し、座面幅は患者の臀部幅に左右2-3cmの余裕を持たせます。背もたれの高さは患者の体幹機能に応じて調整し、支持が必要な部位をカバーできるようにします。
患者の機能レベルに応じた補助具の選択も重要です。全介助が必要な患者には移乗用リフトやスライディングボードを、一部介助の患者には移乗ベルトや手すりを準備します。自立度の高い患者では、最小限の補助具に留めて自立を促進します。
安全性の確保では、ブレーキの動作確認、フットサポートの固定状況、ベルト類の破損の有無を事前にチェックします。患者さんに「安全を確認してから移乗しますね」と説明し、安心感を提供します。
環境の個別性も考慮し、ベッドサイドのスペース、床面の状況、照明の明るさなどを確認します。転倒リスクの高い患者では、より広いスペースを確保し、必要に応じて2人介助の準備を行います。
4. 車椅子移乗の実施手順
事前準備とアセスメント
患者の全身状態を詳しく評価します。バイタルサイン、意識レベル、疼痛の程度、前日の離床状況を確認し、移乗の適応を判断します。特に起立性低血圧のリスクがある患者では、血圧測定を移乗前後に実施します。
身体機能の評価では、筋力、関節可動域、バランス能力、協調性を確認します。「今日の体調はいかがですか」「立ち上がる時に痛いところはありませんか」と患者さんに声をかけ、主観的な訴えも重視します。
認知機能と理解力も重要な評価項目です。指示の理解度、記憶力、判断力を確認し、転倒リスクを総合的に判断します。認知症患者では、なじみのある職員が移乗を担当することで、不安を軽減できます。
患者さんには移乗の目的と手順を説明し、「車椅子でお散歩に行きましょうか」「リハビリ室まで一緒に行きますね」など、前向きな表現で動機づけを行います。
ベッドから車椅子への移乗手順
1. 環境整備と車椅子の配置 車椅子をベッドに30-45度の角度で近づけ、ブレーキを確実にかけます。フットサポートを上げるまたは取り外し、アームサポートも取り外し可能なものは外します。ベッドの高さを車椅子の座面と同じ高さに調整します。
2. 患者の準備と体位調整 患者をベッド端に座らせ、両足を床につけた状態で安定させます。患者さんの健側を車椅子側に向け、移乗しやすい体位とします。「足の感覚はいかがですか」「めまいはありませんか」と確認しながら、ゆっくりと進めます。
3. 立ち上がり動作の介助 患者の腰部に移乗ベルトを装着し、看護師は患者の正面または健側に立ちます。患者には「私の肩に手を置いてください」と指示し、協力動作を促します。「一、二、三」の掛け声で同時に立ち上がり、患者のペースに合わせてゆっくりと動作します。
4. 方向転換と着座 立位が安定したら、患者の腰を支持しながら車椅子の方向へ小刻みに方向転換します。患者が車椅子の座面を膝の後ろで感じることを確認してから、「ゆっくり座ってください」と指示し、ゆっくりと着座させます。
5. 姿勢調整と安全確認 座位が安定したら、背中をしっかり背もたれにつけ、足をフットサポートに乗せます。必要に応じて車椅子ベルトを装着し、姿勢の安定性を確認します。クッションの位置を調整し、患者が「楽な姿勢になりましたか」と確認します。
車椅子からベッドへの移乗手順
1. 車椅子の位置調整 車椅子をベッドに近づけ、移乗しやすい角度に調整します。ブレーキをかけ、フットサポートを上げ、必要に応じてアームサポートを取り外します。
2. 立ち上がり準備 車椅子ベルトを外し、患者を座面の前方に移動させます。両足を床にしっかりつけ、立ち上がりの準備を整えます。「お疲れ様でした。ベッドに戻りましょうね」と声をかけ、患者をねぎらいます。
3. 立ち上がりとベッドへの移動 ベッドから車椅子への移乗と同様の手順で、協力動作により立ち上がりを行います。ベッドの方向へ方向転換し、ベッド端にゆっくりと着座させます。
4. ベッド上での体位調整 ベッド上で患者の姿勢を整え、必要に応じて臥床姿勢へ移行します。移乗後の疲労度を確認し、「お疲れ様でした。しばらく休んでくださいね」と声をかけます。
実施中の観察ポイント
移乗中は患者の表情、呼吸状態、皮膚色を継続的に観察します。冷汗、蒼白、呼吸困難の出現は起立性低血圧や心負荷を示唆するため、直ちに移乗を中止し、安全な体位で休息させます。
疼痛の評価も重要で、「痛いところはありませんか」「我慢しないで教えてくださいね」と声をかけ続けます。特に骨折術後や関節疾患の患者では、無理な動作により損傷を拡大するリスクがあります。
転倒の前兆として、ふらつき、膝折れ、意識朦朧に注意します。これらの兆候があれば、無理に継続せず、最寄りの安全な場所(ベッドまたは車椅子)への移動を優先します。
患者の協力度と理解度も観察し、指示が伝わっているか、適切に協力動作ができているかを確認します。理解が困難な場合は、より簡単な指示に変更したり、身体的ガイドを多用したりして対応します。
5. 特殊な状況での車椅子移乗
片麻痺患者への移乗
片麻痺患者では健側の機能を最大限活用した移乗技術が重要です。車椅子は必ず健側に配置し、患者が健側の手足を使って移乗できるよう支援します。
立ち上がり時は健側下肢に重心をかけ、健側上肢で支持物(ベッド柵や車椅子アームサポート)を把持するよう指導します。看護師は患側を支持し、転倒を防止します。「健康な方の足に力を入れて立ってください」「健康な方の手でしっかり支えてくださいね」と具体的に指示します。
失語症を伴う場合は、言語による指示だけでなく、ジェスチャーや身体的ガイドを併用します。患者の理解を確認するため、「うなずいてください」「手を握ってください」などの簡単な動作で意思疎通を図ります。
認知症患者への移乗
認知症患者では不安の軽減と安心感の提供が最も重要です。なじみのある職員が一貫してケアにあたり、ゆっくりとした動作と優しい口調で接します。
「お散歩に行きましょう」「お食事の時間ですよ」など、患者が理解しやすく、ポジティブな表現を使用します。無理強いは避け、患者のペースに合わせて時間をかけて移乗を行います。
見当識障害がある場合は、「今から車椅子に乗って、食堂に向かいます」「私が一緒にいますので安心してください」と、現在の状況を繰り返し説明します。混乱が強い時は、いったん移乗を中止し、落ち着いてから再度試みます。
脊髄損傷患者への移乗
脊髄損傷患者では残存機能のレベルに応じた移乗方法を選択します。頸髄損傷では全介助が必要で、移乗用リフトの使用を検討します。胸腰髄損傷では上肢機能を活かしたプッシュアップ移乗やスライディングボード移乗が可能です。
起立性低血圧のリスクが高いため、移乗前後の血圧測定を必須とし、段階的な体位変換を行います。長期臥床後の初回移乗では、腹帯の装着や弾性ストッキングの着用により血圧低下を予防します。
自律神経過反射の既往がある患者では、移乗時の刺激により血圧が急上昇するリスクがあります。頭痛、発汗、徐脈などの症状に注意し、異常があれば直ちに移乗を中止して医師に報告します。
高齢患者への移乗
高齢患者では筋力低下とバランス能力の低下により、転倒リスクが高くなります。ゆっくりとした動作で、患者が各段階で安定するまで待つことが重要です。
骨粗鬆症による骨折リスクを考慮し、愛護的な操作を心がけます。特に大腿骨頸部骨折や脊椎圧迫骨折の既往がある患者では、無理な体位変換は避けます。
多剤服用によるふらつきや眠気の影響も考慮し、移乗前に服薬状況を確認します。降圧薬や睡眠薬の服用後は、より慎重な移乗を行います。
小児患者への移乗
小児では恐怖心や不安への配慮が重要です。年齢に応じた説明を行い、「車椅子でお散歩に行こうね」「ママに会いに行こうか」など、楽しい活動として動機づけます。
体重が軽いため、看護師1人でも移乗は可能ですが、予期しない体動により転落するリスクがあります。安全ベルトの使用や2人介助を検討し、安全を確保します。
成長発達段階を考慮し、可能な範囲で自立を促進します。学童期以降では、移乗の意味を説明し、協力動作を教育することで、将来の自立につなげます。
術後患者への移乗
術後患者では創部の保護と疼痛管理を重視します。移乗前に疼痛の程度を確認し、必要に応じて鎮痛薬の投与を検討します。創部に負荷がかからない体位での移乗を心がけます。
全身麻酔後は意識レベルと運動機能の回復を確認してから移乗を行います。ふらつきや協調性の低下がある場合は、移乗を延期するか、より安全な方法を選択します。
ドレーンやカテーテル類が留置されている場合は、屈曲や引っ張りによる事故を防ぐため、十分な長さを確保し、移乗中も位置を確認し続けます。
6. 車椅子移乗中の観察とアセスメント
車椅子移乗中の観察は、患者の安全確保と身体機能の評価において極めて重要です。
循環動態の観察では、血圧、脈拍、呼吸数の変化を注意深く監視します。起立性低血圧は高齢者や長期臥床患者で頻発し、立位で収縮期血圧20mmHg以上または拡張期血圧10mmHg以上の低下があれば診断されます。
症状としては、立ち上がり時のめまい、ふらつき、冷汗、悪心が典型的で、重症例では失神に至ることもあります。このような症状を認めた場合は、直ちに移乗を中止し、臥床または座位で安静を保ちます。
呼吸状態の評価では、移乗前後の呼吸数、呼吸パターン、酸素飽和度を比較します。呼吸困難やチアノーゼの出現は心肺機能の低下を示唆し、移乗の適応を再検討する必要があります。
筋骨格系の観察では、筋力、関節可動域、バランス能力を動的に評価できます。立ち上がり時の膝折れは大腿四頭筋力の低下を、体幹の動揺はバランス機能の低下を示します。
疼痛の評価では、部位、性質、程度を詳しく聴取します。腰背部痛は不適切な体位や過度の負荷を、関節痛は関節疾患の増悪を示唆することがあります。NRS(Numerical Rating Scale)を用いて疼痛を定量化し、移乗方法の調整に活用します。
認知機能の観察では、指示の理解度、記憶力、判断力、注意力を評価します。移乗中の協力度や安全への配慮は、認知機能の重要な指標となります。
心理状態の評価では、不安、恐怖、抑うつなどの感情面の変化を観察します。「怖い」「落ちそう」という訴えは、身体機能の問題だけでなく、心理的要因も考慮する必要があります。
自立度の評価では、FIM(Functional Independence Measure)やBarthel Indexなどの評価尺度を参考に、移乗動作における自立度を客観的に評価します。これにより、適切な介助レベルの設定と目標設定が可能になります。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 身体可動性障害
- 転倒リスク状態
- 活動耐性低下
- セルフケア不足:移動
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
活動・運動パターンでは、車椅子移乗が患者の全体的な活動能力に与える影響を包括的に評価します。移乗能力の向上は、ADL(日常生活動作)全体の改善につながるため、段階的な目標設定を行います。初期は全介助から始まり、一部介助、見守り、自立へと進行する過程を詳細に記録し、患者や家族と共有します。
健康知覚・健康管理パターンでは、患者が自身の身体機能と移乗能力の変化をどのように認識しているかを評価します。「前より楽に立てるようになった」「まだふらつくけれど、少しずつ良くなっている」など、患者の主観的な改善感覚は、リハビリテーションへの動機づけに重要な意味を持ちます。
自己概念・自己知覚パターンでは、移乗能力の変化が患者の自己効力感や自尊心に与える影響を注意深く観察します。移乗が困難になったことで「迷惑をかけている」「情けない」という感情を抱く患者には、段階的な改善の可能性と、現在の努力の価値を伝えます。
役割・関係パターンでは、移乗能力が家族関係や社会参加に与える影響を評価します。車椅子での移動が可能になることで、面会時間の充実や院内散歩、リハビリテーション参加など、社会的な関わりが拡大します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常な姿勢を保持し、動く欲求への援助では、車椅子移乗を通じて患者の移動能力の最大化を図ります。患者の残存機能を活用し、可能な限り自立した移動を支援します。完全に自立できない場合でも、「健康な足でしっかり踏ん張ってください」「腕の力を使って立ち上がりましょう」など、患者が主体的に参加できる部分を強調します。
遊び、娯楽、学習の欲求では、車椅子移乗により活動範囲が拡大することで、これらの欲求の充足を支援します。病室内に留まっていた患者が、車椅子でデイルームや院内庭園に行けることで、他の患者との交流や自然との触れ合いが可能になります。
愛され愛する欲求では、車椅子移乗により家族や友人との面会がより充実したものになることを支援します。ベッドサイドだけでなく、面会室や屋外での時間を過ごすことで、より自然な関係性を維持できます。
生産的な仕事をする欲求では、移乗能力の回復が将来の社会復帰や職場復帰への第一歩となることを患者に伝え、希望を持ち続けられるよう支援します。作業療法との連携により、職業関連動作の獲得を目指します。
自己実現の欲求では、車椅子移乗の習得そのものが、患者にとって重要な達成目標となります。「今日は一人で立てた」「車椅子まで歩けた」という小さな成功体験を積み重ねることで、自己実現感を高めます。
具体的な看護介入
最優先の介入は安全確保です。転倒予防対策として、移乗前の環境整備、適切な人員配置、安全器具の使用を徹底します。リスクアセスメントを定期的に実施し、患者の状態変化に応じて介助方法を調整します。特に初回移乗では、2人介助を原則とし、患者の反応を慎重に観察します。
段階的な自立支援では、患者の能力に応じた目標設定と段階的な介助レベルの調整を行います。全介助から始まって、徐々に患者の参加度を高め、最終的には自立または最小限の介助での移乗を目指します。「今日は昨日より長く立っていられましたね」と具体的な改善点を指摘し、患者の意欲を向上させます。
疼痛管理では、移乗に伴う疼痛を最小限に抑えるため、鎮痛薬の適切な使用、温熱療法、マッサージなどを併用します。疼痛により移乗への恐怖心が生じている患者には、「痛みのコントロールをしながら、無理のない範囲で練習していきましょう」と説明し、安心感を提供します。
患者・家族教育では、退院後の生活を見据えた移乗技術の指導を行います。家族には安全な介助方法を段階的に指導し、実際の練習を重ねます。「ご家庭でも同じようにできるよう、一緒に練習しましょう」と声をかけ、家族の不安を軽減します。
多職種連携では、理学療法士、作業療法士、医師、ソーシャルワーカーと密接に連携し、包括的なリハビリテーション計画を立案します。定期的なカンファレンスで患者の進歩を共有し、一貫した目標に向けて支援します。
8. よくある質問・Q&A
Q:移乗中に患者がめまいを訴えた場合、どのように対応すればよいでしょうか?
A: 直ちに移乗を中止し、患者を最も近い安全な場所(ベッドまたは車椅子)に座らせます。血圧測定を行い、起立性低血圧の有無を確認します。収縮期血圧が20mmHg以上低下している場合は起立性低血圧と診断し、水分補給や下肢挙上を行います。症状が改善しない場合や意識レベルの低下がある場合は、直ちに医師に報告します。今後の移乗では、より緩徐な体位変換や弾性ストッキングの着用を検討します。
Q:認知症の患者さんが移乗を拒否する場合の対応方法は?
A: まず無理強いは避け、患者の感情を受け止めます。「嫌ですよね、でも少しだけお付き合いください」と共感的に接します。時間をおいて再度声かけを行ったり、患者の興味のある話題で気分転換を図ったりします。「お庭のお花を見に行きませんか」「ご家族が面会室でお待ちです」など、ポジティブな理由を提示することも効果的です。それでも拒否が続く場合は、その日の移乗は見送り、翌日に再挑戦します。患者の尊厳と自己決定権を尊重することが最も重要です。
Q:片麻痺の患者さんで、健側の筋力が弱い場合の移乗方法は?
A: 健側の筋力不足により通常の移乗が困難な場合は、補助具の活用を検討します。スタンディングリフトや移乗ベルトを使用し、患者の負担を軽減します。移乗前に健側の筋力強化訓練を理学療法士と連携して実施し、段階的に自立度を向上させます。また、スライディングボードを使用した座位移乗も選択肢の一つです。「健康な方の手足を使いながら、機械の力も借りて安全に移乗しましょう」と説明し、患者の理解を得ます。
Q:車椅子移乗後に患者さんが「疲れた」「もうベッドに戻りたい」と訴える場合はどうすればよいですか?
A: 患者の訴えを真摯に受け止め、疲労度を客観的に評価します。バイタルサイン、顔色、呼吸状態を確認し、必要に応じてベッドに戻します。ただし、軽度の疲労であれば「少し休憩してから、もう少しだけ座っていましょうか」と提案し、段階的に離床時間を延長します。患者には「最初は疲れるのが普通です。少しずつ慣れていきますよ」と励まし、小さな目標を設定します(今日は30分、明日は45分など)。疲労の原因が不明な場合は、医師に相談し、基礎疾患の影響がないか確認します。
9. まとめ
車椅子移乗は、患者さんの自立支援と生活の質向上を実現する重要な看護技術です。単に移動の援助を行うだけでなく、患者さんの身体機能の回復を促進し、社会参加への道筋を作る重要な役割を担っています。
安全性を最優先としながら、患者さんの残存機能を最大限活用し、段階的な自立支援を行うことが求められます。患者さん一人ひとりの状態や目標に応じた個別的なアプローチにより、効果的なリハビリテーションを提供できます。
実習現場では、患者さんの不安や恐怖心に寄り添いながら、「一緒に頑張りましょう」という励ましの気持ちを持って関わることが大切です。小さな成功体験の積み重ねが、患者さんの大きな自信と希望につながることを忘れずに、温かいケアを提供していきましょう。
覚えるべき重要数値・基準
- 車椅子配置角度:ベッドに対して30-45度
- 座面幅の余裕:臀部幅の左右2-3cm
- 起立性低血圧の基準:収縮期血圧20mmHg以上または拡張期血圧10mmHg以上の低下
- 初期離床時間:30分-1時間から開始
- 移乗前後の観察時間:最低15分間
- 2人介助の適応:初回移乗、転倒リスク高、認知症患者
- バイタルサイン測定タイミング:移乗前・移乗直後・15分後
- 疼痛評価:NRSで3以下を目標
- 車椅子点検項目:ブレーキ・フットサポート・アームサポート・タイヤの空気圧
実習・現場で活用できるポイント
安全確認を徹底し、移乗前の環境整備と物品準備を怠らないようにしましょう。患者さんの状態に応じた適切な介助レベルを選択し、無理のない範囲で自立を促進することが重要です。
移乗中は患者さんとのコミュニケーションを大切にし、不安を軽減する声かけを心がけてください。「大丈夫ですよ」「しっかり支えていますからね」などの安心感を与える言葉が、患者さんの協力と信頼を得ることにつながります。
観察とアセスメントを丁寧に行い、患者さんの身体機能の変化や改善点を見逃さないよう注意深く関わりましょう。小さな変化でも記録に残し、チーム全体で情報を共有することで、継続的な支援が可能になります。
多職種との連携を積極的に図り、理学療法士や作業療法士からの専門的なアドバイスを活用して、より効果的な移乗技術を習得していきましょう。人ひとりの患者さんから学ばせていただく謙虚な気持ちを持ち続けることで、信頼される看護師として成長できるでしょう。しながら実施することで、患者さんに信頼される看護師として成長できるでしょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

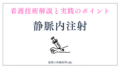
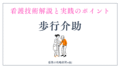
コメント