1. はじめに
実習で患者さんを受け持った時、「この方は褥瘡ができやすい状態だから、しっかり予防しましょうね」と指導者から言われた経験はありませんか?褥瘡は一度発生すると治癒に長期間を要し、患者さんのQOLを大きく左下させてしまう深刻な問題です。
褥瘡は「寝たきりだから仕方ない」という時代は終わり、現在では「予防可能な医療関連事故」として位置づけられています。つまり、適切な知識と技術があれば防げるものなのです。実際、褥瘡発生率を大幅に減少させている医療機関も数多く存在します。
看護師として最も基本的でありながら、最も重要な技術の一つが褥瘡予防・ケアです。患者さんの「痛い」「つらい」という訴えを未然に防ぎ、快適な療養生活を支援することは、看護の本質そのものと言えるでしょう。
実習では限られた時間の中で多くの技術を身につける必要がありますが、褥瘡予防・ケアは毎日のケアの中で自然に実践できる技術です。基本的な観察ポイントから専門的なケア技術まで、段階的に学んでいくことで、患者さんに安全で質の高いケアを提供できるようになります。
この記事で学べること
- 褥瘡発生のメカニズムと予防の重要性
- リスクアセスメントツールの活用方法
- 効果的な体位変換とポジショニング技術
- 褥瘡の観察・評価方法と記録のポイント
- 多職種連携による包括的なケアアプローチ
2. 褥瘡予防・ケアの基本情報
定義
褥瘡とは、骨突出部などの持続的な圧迫により、皮膚・皮下組織・筋肉が壊死に陥った状態
褥瘡は単純に「床ずれ」と呼ばれることもありますが、実際にはより複雑なメカニズムで発生します。持続的な圧迫だけでなく、ずれやせん断力、湿潤、摩擦などの外的要因と、栄養状態の悪化、循環障害、浮腫などの内的要因が複合的に作用して発生する創傷です。
技術の意義と目的
褥瘡予防・ケアは、患者さんの身体的苦痛を軽減し、感染リスクを回避することで生命の質を向上させます。患者さんにとっては、痛みや不快感から解放され、治療に集中できる環境が整います。また、早期離床や社会復帰への道筋を維持することができます。
看護師にとっては、予防的ケアを通じて患者さんとの信頼関係を深め、看護の専門性を発揮する重要な場面となります。さらに、褥瘡予防は医療費の削減にも大きく貢献し、医療の質向上につながる社会的意義も持っています。
実施頻度・タイミング
褥瘡予防は24時間継続的に行う必要があります。体位変換は基本的に2時間ごと、皮膚観察は毎日、リスクアセスメントは入院時および状態変化時に実施します。ケアの頻度は患者さんのリスクレベルに応じて調整し、高リスク患者では1-2時間ごとの観察が必要な場合もあります。
3. 必要物品と準備
基本的な褥瘡予防・ケア用品
体圧分散用具
- エアマットレス(静止型・交替型)
- ウレタンマットレス
- 体圧分散クッション
- ポジショニングクッション(大・中・小各サイズ)
- 円座(使用は原則禁止)
スキンケア用品
- 弱酸性石鹸またはpH調整スキンクレンザー
- 保湿剤(ローション、クリーム、オイル)
- 皮膚保護材(ドレッシング材、フィルム材)
- 清拭用タオル(柔らかい材質)
- 使い捨て手袋
観察・評価用品
- DESIGN-R評価用紙
- ブレーデンスケール評価表
- メジャー(創部測定用)
- カメラ(記録用、施設の規定に従って)
特殊状況対応用品
感染対策用品
- 滅菌手袋
- 滅菌生理食塩水
- 感染創用ドレッシング材
- ディスポーザブル器具
処置用品
- 各種創傷被覆材(ハイドロコロイド、ハイドロジェル、フォーム材など)
- 外用薬(軟膏、クリーム)
- 固定用テープ(低刺激性)
- 洗浄用シリンジ
物品準備のポイント
患者さんの身体状況、褥瘡の有無・程度、皮膚の状態に応じて物品を選択します。特に体圧分散用具は患者さんの体重や活動レベル、既存の褥瘡の状況を考慮して選定する必要があります。アレルギー歴や皮膚の敏感性についても事前に確認し、適切なスキンケア製品を準備することが重要です。
4. 褥瘡予防・ケアの実施手順
事前準備とアセスメント
まず、患者さんの全身状態を把握します。ブレーデンスケールを用いてリスクアセスメントを行い、合計点数が18点以下の場合は褥瘡発生リスクが高いと判断します。既存の褥瘡がある場合は、DESIGN-Rを用いて創の状態を評価し、適切なケア方法を決定します。
環境整備では、室温を22-24℃に調整し、プライバシーを確保します。患者さんには褥瘡予防の重要性とケア内容について説明し、協力を得ます。「今から体の向きを変えて、皮膚の状態を確認させていただきますね」などの声かけを行います。
基本手順
1. 全身皮膚観察 頭部から足先まで順序立てて観察します。特に骨突出部(後頭部、肩甲骨、肘、仙骨部、大転子部、膝、踵など)を重点的にチェックします。発赤の有無、指圧退色試験(発赤部を指で圧迫し、白くならない場合はステージ1の褥瘡を疑う)を実施します。
2. スキンケア 皮膚の清潔保持と保湿を行います。石鹸使用時はpH5.5-6.5の弱酸性製品を選択し、十分にすすぎます。清拭後は必ず保湿剤を塗布し、皮膚のバリア機能を維持します。
3. 体位変換とポジショニング 2時間ごとを基本とし、患者さんの状態に応じて調整します。体位変換時は30度側臥位を基本とし、真横向きは避けます。ポジショニングクッションを用いて、骨突出部の圧迫を回避し、身体の安定を図ります。
4. 体圧分散寝具の調整 エアマットレスの場合は、適正圧設定(一般的に患者の体重×0.4-0.6cmH2O)を確認します。マットレスに手のひらを入れて、2-3cm程度沈むのが適切な硬さです。
実施中の観察ポイント
体位変換時は患者さんの表情や訴えを観察し、痛みや不快感がないか確認します。皮膚観察では、発赤の範囲や色調の変化、皮膚温度、腫脹の有無をチェックします。また、患者さんの全身状態の変化(血圧、脈拍、呼吸状態)にも注意を払います。
5. 特殊な状況での褥瘡予防・ケア
手術後患者の褥瘡予防 手術中の長時間同一体位による圧迫で、術後に褥瘡が発生するリスクが高まります。手術部位や麻酔の影響で体位変換が制限される場合は、可能な範囲でのポジショニング変更と、1時間ごとの皮膚観察を実施します。特に手術台接触部位の観察を重点的に行います。
終末期患者の褥瘡ケア 終末期では根治的治療よりも症状緩和が優先されます。痛みを最小限に抑えながら、清潔保持と感染予防に重点を置きます。体位変換の頻度は患者さんの苦痛に応じて調整し、家族への説明と協力も重要になります。
ICU患者の集中的予防ケア 人工呼吸器装着中や循環動態が不安定な患者では、体位変換に制約があります。可能な範囲でのmicro-positioning(わずかな体位変更)や、除圧時間の延長(15分程度の完全除圧)を組み合わせて実施します。
認知症患者の褥瘡予防 認知機能の低下により自力での体位変換が困難で、ケアへの協力も得にくい場合があります。患者さんが安心できるよう声かけを工夫し、家族の協力を得ながらケアを継続します。転倒・転落防止も同時に考慮する必要があります。
6. 褥瘡予防・ケア中の観察とアセスメント
皮膚観察では、発赤の出現と消失時間を記録します。正常な反応性充血は体位変換後30分以内に消失しますが、それ以上持続する場合は組織損傷を疑います。皮膚の色調変化では、暗赤色や紫色への変化は深部組織損傷の可能性を示します。
創部の観察では、大きさ(縦×横×深さ)、滲出液の性状と量、臭気の有無、周囲皮膚の状態を詳細に記録します。滲出液が増加したり、悪臭が出現した場合は感染を疑い、医師への報告を行います。
全身状態の変化も重要な観察項目です。栄養状態の悪化(アルブミン値2.5g/dL以下、BMI18.5未満)は褥瘡の治癒を遅延させます。また、浮腫の出現や循環状態の悪化は新たな褥瘡発生のリスクを高めます。
患者さんの主観的訴えにも注意を払います。「ここが痛い」「しびれる」「違和感がある」といった訴えは、深部組織損傷の早期発見につながる重要な情報です。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 皮膚統合性障害リスク状態
- 皮膚統合性障害
- 急性疼痛
- 感染リスク状態
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
栄養・代謝パターンでは、褥瘡の発生と治癒に大きく影響する要素を重点的に観察します。患者さんの食事摂取状況、体重変化、血液検査データ(アルブミン、総蛋白、ヘモグロビン値)を継続的に評価し、栄養士と連携した栄養管理を実施します。脱水状態は皮膚の弾力性を低下させ、褥瘡のリスクを高めるため、水分摂取量と尿量のバランスも重要な観察項目です。
活動・運動パターンにおける観察では、患者さんの自力体動能力、筋力、関節可動域を評価します。長期臥床により筋萎縮や関節拘縮が進行すると、体位変換がより困難になり、褥瘡リスクが増大します。理学療法士と連携し、可能な範囲での関節可動域訓練や筋力維持訓練を計画的に実施することが重要です。
認知・知覚パターンでは、患者さんの意識レベル、感覚機能、痛みの認識能力を評価します。感覚麻痺がある部位では患者さん自身が異常を感知できないため、看護師による観察がより重要になります。また、認知機能の低下がある場合は、ケアへの協力方法を工夫し、患者さんが理解しやすい説明を心がけます。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常な呼吸に関連して、体位変換時は呼吸状態の変化に注意し、特に呼吸器疾患を持つ患者さんでは、呼吸を妨げない体位選択を行います。側臥位時は患側を下にしない、座位時は前傾姿勢を避けるなど、個別性を考慮したポジショニングを実施します。
適切な飲食については、褥瘡予防・治癒に必要な栄養素(蛋白質、ビタミンC、亜鉛など)の摂取を支援します。経口摂取困難な患者さんには、医師と相談の上、適切な栄養補給方法を検討し、管理栄養士と連携した栄養ケア計画を立案します。
身体の清潔と衣服の選択では、皮膚の清潔保持と適度な保湿を実施し、皮膚のバリア機能を維持します。衣服や寝具のしわは圧迫を増強するため、こまめに整える必要があります。また、通気性の良い素材を選択し、皮膚の乾燥と湿潤の適切なバランスを保ちます。
安全な環境の維持として、転倒・転落防止対策と褥瘡予防を両立させる環境整備を行います。ベッド周囲の整理整頓、適切な照明の確保、緊急時の対応体制の整備などを通じて、患者さんが安心してケアを受けられる環境を提供します。
具体的な看護介入
優先度1:包括的リスクアセスメントの実施 入院時および状態変化時に、ブレーデンスケールやその他のリスクアセスメントツールを用いて、褥瘡発生リスクを客観的に評価します。単に点数を算出するだけでなく、各項目の背景にある病態や生活状況を理解し、個別性のある予防計画を立案します。評価結果は多職種で共有し、チーム全体で一貫したケアを提供する体制を構築します。
優先度2:科学的根拠に基づく予防的ケアの実施 体位変換、スキンケア、体圧分散用具の使用などを、最新のガイドラインに基づいて実施します。特に体位変換では、30度側臥位の原則を守りつつ、患者さんの疾患や身体状況に応じた個別調整を行います。また、マッサージや円座の使用など、科学的根拠のない方法は避け、エビデンスに基づいたケアを提供します。
優先度3:患者・家族への教育とエンパワーメント 褥瘡予防の重要性と具体的な方法について、患者さんや家族に分かりやすく説明します。可能な範囲での自己管理方法を指導し、患者さんの主体性を尊重したケアを実施します。退院後の在宅ケアに向けて、家族への技術指導や地域連携の調整も重要な役割となります。
優先度4:多職種連携による包括的ケア 医師、管理栄養士、理学療法士、薬剤師などと連携し、褥瘡予防・ケアに関する専門的知識を統合したケアを提供します。定期的なカンファレンスを通じて情報共有を行い、ケア方針の統一を図ります。また、必要に応じて皮膚・排泄ケア認定看護師などの専門看護師への相談も積極的に活用します。
8. よくある質問・Q&A
Q:エアマットレスを使用していれば褥瘡はできませんか?
A: エアマットレスは体圧分散効果が高く褥瘡予防に有効ですが、それだけで完全に予防できるものではありません。適切な圧力設定、定期的な体位変換、スキンケアなどを組み合わせた総合的なケアが必要です。また、エアマットレスの種類や設定を患者さんの状態に合わせて選択することが重要で、過度に柔らかすぎると逆に沈み込みによる圧迫が生じる場合もあります。
Q:円座を使用してはいけないのはなぜですか?
A: 円座の使用は現在、褥瘡予防ガイドラインで推奨されていません。円座を使用すると、接触部分の圧力が集中し、血流が阻害されるリスクが高まります。また、円座の中央部分では組織が引き伸ばされ、せん断力が増加することで深部組織損傷を引き起こす可能性があります。仙骨部や尾骨部の圧迫を軽減したい場合は、適切なポジショニングクッションやエアマットレスを使用しましょう。
Q:発赤が出現したらマッサージをした方が良いですか?
A: 発赤部位へのマッサージは絶対に行ってはいけません。発赤は既に組織損傷が始まっているサインであり、マッサージによってさらに組織を損傷させてしまいます。発赤を発見した場合は、まず圧迫を完全に除去し、指圧退色試験を実施して褥瘡の進行度を評価します。その上で適切な体位変換とスキンケアを継続し、必要に応じて皮膚保護材の使用を検討しましょう。
Q:褥瘡ができやすい患者さんの特徴はありますか?
A: 褥瘡発生のリスクが高いのは、長期臥床患者、栄養状態不良、高齢者、意識レベル低下、皮膚の感覚低下、循環障害、糖尿病患者などです。また、手術侵襲や薬物療法(ステロイド使用など)も影響します。ただし、これらの要因があっても適切な予防ケアにより褥瘡発生を防ぐことは可能です。重要なのは、リスク要因を早期に把握し、個別性のある予防計画を立案・実施することです。
9. まとめ
褥瘡予防・ケアは看護師の基本的な技術でありながら、患者さんの生活の質を大きく左右する重要なケアです。単なる技術の習得だけでなく、患者さん一人ひとりの状態を総合的にアセスメントし、科学的根拠に基づいたケアを提供することが求められます。
実習や臨床現場では、「なぜこのケアが必要なのか」「どのような根拠があるのか」を常に考えながら実践することで、より質の高いケアが提供できるようになります。また、褥瘡予防は看護師だけでなく、多職種が連携して取り組む必要があるケアです。
覚えるべき重要数値・基準
- ブレーデンスケール:18点以下で褥瘡発生リスク高
- 体位変換頻度:基本2時間ごと、高リスク患者は1-2時間ごと
- 体位変換角度:30度側臥位を基本とする
- 指圧退色試験:30分以上発赤が持続すれば褥瘡を疑う
- 栄養状態:アルブミン2.5g/dL以下、BMI18.5未満は要注意
- エアマットレス適正圧:体重×0.4-0.6cmH2O
実習・現場で活用できるポイント
実習では、受け持ち患者さんのリスクアセスメントから始めて、個別性のあるケア計画を立案してみましょう。体位変換の際は必ず皮膚観察を行い、変化があれば記録に残し、指導者に報告します。また、なぜその体位を選択するのか、なぜその間隔で実施するのかを考えながら実践することで、根拠に基づいた看護を身につけることができます。
褥瘡予防・ケアを通じて、患者さんの「ありがとう、楽になりました」という言葉を聞けた時、看護師としての大きなやりがいを感じることでしょう。一人ひとりの患者さんに最適なケアを提供できる看護師を目指して、継続的に学習を重ねていきましょう。摂食支援を提供していきましょう。言語聴覚士や医師との連携を大切にし、専門的な評価や治療が必要な場合は積極的に相談することが重要です。常に観察しながら実施することで、患者さんに信頼される看護師として成長できるでしょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
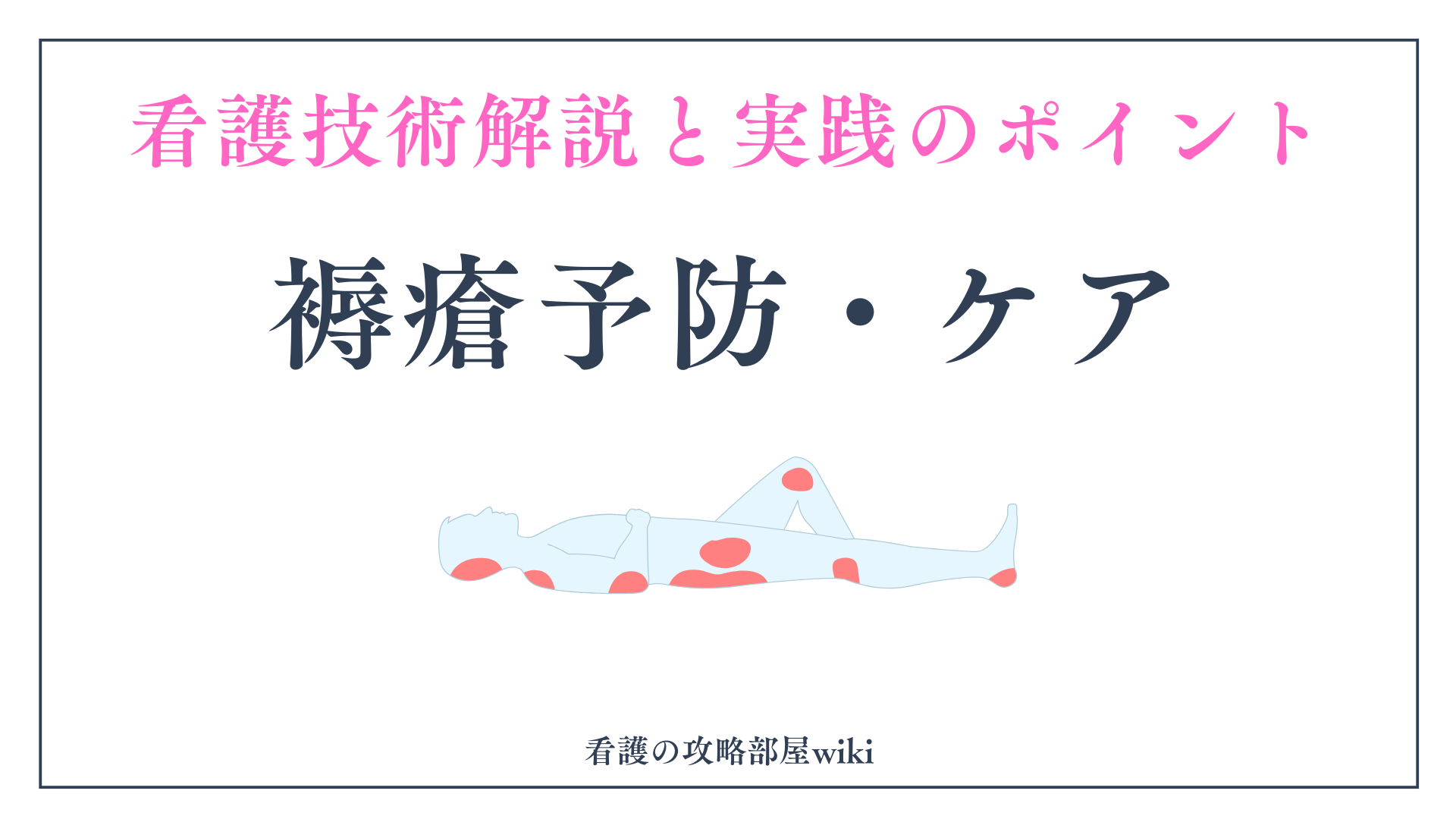


コメント