1. はじめに
嚥下評価・誤嚥予防は、患者さんの生命を守り、安全な摂食を支援するための極めて重要な看護技術です。誤嚥性肺炎は高齢者の死因上位を占める深刻な問題であり、適切な嚥下評価と予防策により多くの患者さんの生命と生活の質を守ることができます。
実習現場では「患者さんが『むせない』から大丈夫」「食べたがっているから食事を提供したい」という場面に遭遇することがありますが、嚥下機能の評価は複雑で専門的な知識と技術が必要です。見た目には問題がないように見えても、実際には嚥下機能が低下している「サイレント誤嚥」も存在し、客観的で系統的な評価が不可欠です。
この技術は単なる食事介助の前段階ではなく、患者さんの全身状態、意識レベル、呼吸状態、口腔機能など多面的な評価に基づいて安全な摂食方法を決定し、継続的にモニタリングする包括的なケアです。脳血管疾患、認知症、神経筋疾患、手術後、高齢による機能低下など、様々な原因による嚥下障害に対応する必要があります。
医療現場では内科、外科、神経内科、リハビリテーション科、耳鼻咽喉科など多くの診療科で必要とされ、急性期から回復期、慢性期、在宅まで全ての医療・介護現場で重要な技術となっています。
この記事で学べること
- 嚥下のメカニズムと嚥下障害の病態理解
- 系統的な嚥下評価の方法と判定基準
- 誤嚥リスクの早期発見と予防策
- ゴードンとヘンダーソンの理論に基づいた個別的なアセスメント
- 多職種連携による安全な摂食支援の実践方法
2. 嚥下評価・誤嚥予防の基本情報
定義
嚥下評価・誤嚥予防とは、患者の嚥下機能を客観的に評価し、誤嚥リスクを最小化しながら安全な摂食を支援する一連の看護援助技術
技術の意義と目的
患者さんにとって、安全な摂食は生命維持と生活の質の向上に直結します。「美味しく食べられる」「むせずに飲み込める」という基本的な機能が保たれることで、栄養状態の改善、感染症の予防、心理的な満足感が得られます。また、適切な評価により不必要な絶食を避け、可能な限り経口摂取を継続することで、患者さんの尊厳と生活の質を維持できます。
看護師にとっては、客観的で継続的な嚥下機能の評価により、誤嚥性肺炎などの重篤な合併症を予防し、患者さんの安全を確保できます。また、摂食状況の変化を早期に発見し、適切な医療チームとの連携や治療方針の検討につなげる重要な役割を果たします。
実施頻度・タイミング
入院時の初回評価では全患者に対してスクリーニング評価を実施し、リスクがある患者では詳細評価を行います。病状変化時(意識レベルの変化、新たな神経症状の出現、呼吸状態の悪化など)には必ず再評価が必要です。
定期的な評価として、高リスク患者では週1〜2回、中等度リスク患者では週1回、軽度リスク患者でも2週間に1回程度の評価を継続します。食事の前には毎回簡易評価を実施し、安全性を確認してから摂食を開始することが重要です。
3. 必要物品と準備
基本的な嚥下評価用品
評価用具として、パルスオキシメーター、聴診器、ペンライト、舌圧子、体温計、血圧計、時計(秒針付き)、評価表やチェックリストを準備します。
水分類では、常温の水3ml、5ml、10mlを正確に測れるシリンジやスプーン、とろみ剤、様々な粘度の液体(薄いとろみ、中間のとろみ、濃いとろみ)、ゼリー状食品を用意します。
観察用品として、口腔内観察用のミラー、ガーゼ、吸引器(口腔・鼻腔用)、酸素供給器具、緊急時対応用のバッグバルブマスクを準備します。
安全管理対応用品
緊急時対応用品として、救急カート、酸素、吸引器、気管内挿管セット、緊急薬剤を評価場所の近くに配置します。
モニタリング機器では、心電図モニター、血圧計、体温計、呼吸数計測用機器、意識レベル評価用のスケールを用意します。
感染対策用品として、手袋、マスク、エプロン、アルコール手指消毒剤、感染性廃棄物容器を準備します。
特殊状況対応用品
気管切開患者用として、気管カニューレ用吸引カテーテル、カフ圧計、スピーキングバルブ、緊急時用の予備カニューレを用意します。
認知症・意識障害患者用では、身体拘束具(安全な評価のため最小限使用)、口腔ケア用品、誤嚥時の体位変換用枕やクッションを準備します。
在宅評価用品として、簡易型パルスオキシメーター、家庭用血圧計、計量スプーン、とろみ剤、評価記録用紙を用意します。
物品準備のポイント
患者さんの基礎疾患、意識レベル、呼吸状態、既往歴、内服薬の影響、栄養状態を事前にアセスメントし、個別性に応じた物品選択を行います。特に抗コリン薬、向精神薬、筋弛緩薬などの内服は嚥下機能に影響するため、薬剤情報の確認も重要です。
4. 嚥下評価・誤嚥予防の実施手順
事前準備とアセスメント
環境整備として、静かで集中できる環境を作り、十分な照明を確保します。緊急時対応ができるよう、吸引器と酸素の準備を行い、他の医療スタッフにも評価実施を伝えておきます。
患者さんには「飲み込みの機能を確認させていただきます。安全にお食事をしていただくために大切な検査です」と説明し、協力を求めます。評価前2時間は絶食とし、口腔内を清潔にしておきます。
バイタルサイン測定では、特に体温37℃以上、SpO2 95%未満、呼吸数24回/分以上の場合は評価を延期し、医師に相談します。意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で評価し、JCS 10以上の場合は安全性を慎重に検討します。
基本手順
第1段階:ベッドサイドスクリーニング評価
まず全身状態の評価を行います。意識レベル、呼吸状態、循環動態、体位保持能力、認知機能を系統的に評価し、嚥下評価が安全に実施できる状態かを判断します。
口腔機能評価では、口唇の動き、舌の動き、咀嚼能力、唾液分泌の状態、口腔内の清潔度を観察します。舌の挙上が困難、口唇閉鎖が不完全、顔面の非対称などの異常所見は嚥下障害の重要な指標となります。
発声・構音機能では、「あー」「かー」「らー」の発声を求め、声質の変化(湿性嗄声)、構音の不明瞭さ、発声持続時間の短縮(15秒未満)を評価します。
第2段階:水飲みテスト
患者さんを30度以上のギャッチアップ位または座位にし、3mlの常温水から開始します。シリンジまたは小さなスプーンで口腔内に注入し、嚥下の様子を観察します。
評価項目として、嚥下までの時間(正常は3秒以内)、嚥下回数、むせの有無、呼吸の変化、声質の変化、SpO2の変化を記録します。むせが生じた場合や、SpO2が2%以上低下した場合は評価を中止し、十分な回復を確認してから次の段階に進みます。
3mlで問題がなければ、5ml、10mlと段階的に量を増やして評価します。各段階で5分間の経過観察を行い、遅発性の症状がないことを確認します。
第3段階:とろみ付き液体・ゼリーテスト
水飲みテストで問題があった場合は、とろみの程度を調整した液体で再評価します。薄いとろみ(150mPa・s)から開始し、必要に応じて中間とろみ(300mPa・s)、濃いとろみ(500mPa・s)と調整します。
ゼリーテストでは、プリン状のゼリー5mlから開始し、咀嚼を必要としない軟らかさで嚥下機能を評価します。口腔内でのまとまりやすさ、嚥下反射の誘発、残留感の有無を観察します。
実施中の観察ポイント
継続的にSpO2、呼吸パターン、心拍数をモニタリングし、SpO2 90%未満、呼吸数30回/分以上、頻脈などの異常があれば直ちに評価を中止します。
患者さんの表情、発汗、チアノーゼの有無、咳嗽反射の状態、声質の変化を細かく観察し、湿性嗄声、弱い咳嗽、呼吸困難感などの誤嚥を示唆する症状を見逃さないよう注意します。
評価後は30分間の経過観察を行い、遅発性の誤嚥症状(発熱、SpO2低下、湿性咳嗽)がないことを確認してから食事開始の判断を行います。
5. 特殊な状況での嚥下評価・誤嚥予防
脳血管疾患患者では、病巣の部位により嚥下障害の特徴が異なります。延髄梗塞では重篤な嚥下障害を呈することが多く、大脳皮質病変では認知機能の影響も考慮した評価が必要です。急性期では病状が変化しやすいため、日単位での再評価が重要です。
気管切開患者では、カフ上部の分泌物吸引を十分に行ってから評価を開始します。カフを膨らませたままでの評価は誤嚥リスクが高いため、医師の指示のもとでカフを一時的に収縮させて評価することがあります。スピーキングバルブの使用により、より生理的な嚥下が可能になる場合があります。
認知症患者では、理解力や協力度の評価が重要です。環境の変化や時間帯により嚥下機能が変動することがあるため、最も覚醒が良い時間帯での評価を心がけます。食事への意欲や集中力も嚥下安全性に大きく影響します。
高齢者では、複数の要因(薬剤、脱水、栄養不良、筋力低下)が複合的に嚥下機能に影響します。サイレント誤嚥の頻度が高いため、むせがなくても慎重な評価が必要です。日内変動や体調による変化も考慮した継続的な観察が重要です。
6. 嚥下評価中の観察とアセスメント
嚥下機能の客観的評価では、嚥下反射の潜時(正常1秒以内)、嚥下音の聴取、舌骨の挙上、喉頭の前上方移動を観察します。嚥下音が微弱、複数回嚥下が必要、嚥下後の湿性嗄声は異常所見として記録します。
呼吸状態の変化として、嚥下前後のSpO2変化(2%以上の低下)、呼吸パターンの変化、咳嗽の性状を詳細に観察します。弱い咳嗽や咳嗽反射の消失は重要な異常所見であり、気道保護機能の低下を示唆します。
口腔内の観察では、嚥下後の口腔内残留、唾液の性状と量、口腔乾燥の程度を評価します。粘稠な分泌物や著明な口腔乾燥は誤嚥リスクを高める要因となります。
全身状態の変化として、嚥下努力に伴う疲労感、血圧や心拍数の変動、発汗や顔面紅潮なども重要な観察項目です。これらの変化は嚥下機能の代償機転の破綻を示す可能性があります。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 誤嚥リスク状態(嚥下機能低下に関連した)
- 栄養摂取消費バランス異常:必要量以下(嚥下障害による摂食困難に関連した)
- 口腔粘膜障害リスク状態(唾液分泌減少、口腔清潔不良に関連した)
- 社会的孤立(摂食制限による食事の楽しみの喪失に関連した)
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚・健康管理パターンでは、患者さんや家族が嚥下障害のリスクと重要性をどの程度理解しているか、以前の摂食状況や嚥下に関する問題の既往、服薬状況と嚥下への影響を詳細に評価します。患者さんの病識や治療への協力度も重要な評価項目です。
栄養・代謝パターンでは、現在の栄養状態、体重変化、食事摂取量、嗜好の変化、口腔内の状態を系統的に評価します。BMI 18.5未満や体重減少率3%/月以上は栄養不良の指標となり、嚥下機能にも悪影響を与えます。血清アルブミン値、プレアルブミン値などの栄養指標も参考にします。
認知・知覚パターンでは、意識レベル、認知機能、注意力、理解力が嚥下の安全性に大きく影響します。見当識障害や注意力散漫は誤嚥リスクを高める重要な要因です。感覚機能(視覚、聴覚、味覚、嗅覚)の変化も食事への意欲と安全性に影響します。
活動・運動パターンでは、座位保持能力、頭部・頸部のコントロール、全身の筋力と耐久性を評価します。座位保持困難や頸部筋力低下は適切な摂食姿勢の維持を困難にし、誤嚥リスクを高めます。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
飲食に関する欲求では、患者さんの「食べたい」「飲みたい」という基本的な願いを尊重しながら、安全性を確保する方法を模索します。完全な絶食が必要な場合でも、口腔ケアや少量の氷片で口渇感を和らげるなど、可能な限り患者さんの欲求に応える工夫を行います。
正常な呼吸に関する欲求では、誤嚥による気道閉塞や肺炎のリスクから患者さんを守ります。適切な体位の保持、口腔・咽頭の清潔保持、呼吸状態の継続的な観察を通じて、安全な呼吸を維持します。
危険の回避に関する欲求では、誤嚥性肺炎、窒息、栄養失調などの重篤な合併症から患者さんを保護します。客観的で継続的な評価により、リスクの早期発見と適切な対応を行います。
学習に関する欲求では、患者さんや家族に対して嚥下障害の理解促進、安全な摂食方法の指導、家庭での継続ケアの教育を行います。退院後の生活を見据えた実践的な指導を通じて、患者さんの自立と家族の介護力向上を支援します。
具体的な看護介入
最優先として継続的なリスクアセスメントを実施します。毎食前の簡易評価、定期的な詳細評価、病状変化時の緊急評価を系統的に行い、嚥下機能の変化を見逃しません。評価結果は標準化された評価表を用いて記録し、多職種間で情報共有します。
次に個別性に応じた摂食支援計画を立案します。患者さんの嚥下機能、栄養状態、認知機能、生活歴、嗜好を総合的に考慮し、最も安全で実現可能な摂食方法を選択します。食事形態、とろみの程度、一回量、摂食ペース、環境設定を個別に調整します。
多職種連携による包括的ケアを推進します。医師、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、作業療法士との密接な連携により、医学的治療、機能訓練、栄養管理、薬剤調整を統合的に実施します。
緊急時対応体制を整備します。誤嚥や窒息が発生した場合の対応手順を明確にし、必要な器材と人員を迅速に確保できる体制を構築します。スタッフ全員が緊急時対応を理解し、適切に実践できるよう継続的な教育を行います。
8. よくある質問・Q&A
Q:患者さんが「むせていないから大丈夫」と言って評価を拒否する場合はどうすればよいですか?
A: まず「サイレント誤嚥」について丁寧に説明します。「むせは身体の防御反応ですが、この反応が弱くなると気づかないうちに誤嚥することがあります。これを防ぐために専門的な評価が必要です」と伝えます。過去の誤嚥性肺炎の事例や、早期発見により適切な対応ができた成功例を示し、評価の重要性を理解してもらいます。どうしても拒否される場合は、段階的なアプローチを提案し、まず口腔機能評価から開始することを提案します。
Q:水飲みテスト中にむせが生じた場合の対応は?
A: 直ちにテストを中止し、患者さんを前傾姿勢にして咳嗽を促します。背部叩打や胸部圧迫は避け、自然な咳嗽で喀出できるよう援助します。SpO2をモニタリングし、90%未満またはベースラインから5%以上の低下があれば酸素投与を検討します。完全に咳嗽が治まり、SpO2が回復するまで経過観察し、医師に報告します。その日の評価は中止し、翌日以降に再評価を行います。むせの程度や回復状況により、食事形態の調整や言語聴覚士への相談を検討します。
Q:認知症で協力が得られない患者さんの評価はどのように行いますか?
A: まず患者さんの覚醒状態が最も良い時間帯を見極めます。環境を整え、馴染みのある看護師が対応し、患者さんの理解レベルに合わせた簡潔な説明を行います。「のどを確認させてください」「お水を少し飲んでみましょう」など分かりやすい言葉を使用します。直接的な評価が困難な場合は、食事場面の観察評価を重視し、摂食時の様子、咳嗽の有無、食後の呼吸状態変化を継続的に観察します。家族から普段の摂食状況について詳しく情報収集することも重要です。
Q:気管切開患者の嚥下評価で注意すべきポイントは?
A: まずカフ圧を確認し、医師の指示に従ってカフの調整を行います。カフ上部吸引を十分に実施してから評価を開始します。気管カニューレの種類(有窓・無窓)やスピーキングバルブの有無により評価方法が異なるため、事前に確認します。評価中は連続的なSpO2モニタリングを行い、異常があれば直ちに中止します。嚥下後は必ずカフ上部の再吸引を行い、分泌物の性状を確認します。気管切開患者では唾液の嚥下も困難な場合があるため、段階的かつ慎重に評価を進めることが重要です。
9. まとめ
嚥下評価・誤嚥予防は患者さんの生命に直結する重要な看護技術であり、客観的で継続的な評価により安全な摂食支援を提供する専門的な技術です。多職種連携による包括的なアプローチが不可欠です。
覚えるべき重要数値・基準
- 評価前絶食時間:2時間以上
- 水飲みテスト開始量:3mlから段階的に増量
- 正常嚥下時間:3秒以内
- 発声持続時間:15秒以上(正常)
- SpO2低下の基準:2%以上の低下で要注意、90%未満で中止
- 評価中止基準:体温37℃以上、JCS 10以上
- 経過観察時間:評価後30分間の継続観察
- 栄養不良の指標:BMI 18.5未満、体重減少率3%/月以上
実習・現場で活用できるポイント
実習では事前の十分な準備と緊急時対応の確認が重要です。患者さんの安全を最優先に、無理な評価は避け、異常を認めた場合は直ちに指導者に報告しましょう。「むせがない=安全」ではないことを理解し、客観的な評価に基づいた判断を心がけます。ゴードンとヘンダーソンの理論を活用し、患者さんの全体像を捉えた個別的なアセスメントを実践します。多職種チームの一員として、継続的な観察と情報共有により、患者さんの安全で質の高い摂食支援を提供していきましょう。言語聴覚士や医師との連携を大切にし、専門的な評価や治療が必要な場合は積極的に相談することが重要です。常に観察しながら実施することで、患者さんに信頼される看護師として成長できるでしょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
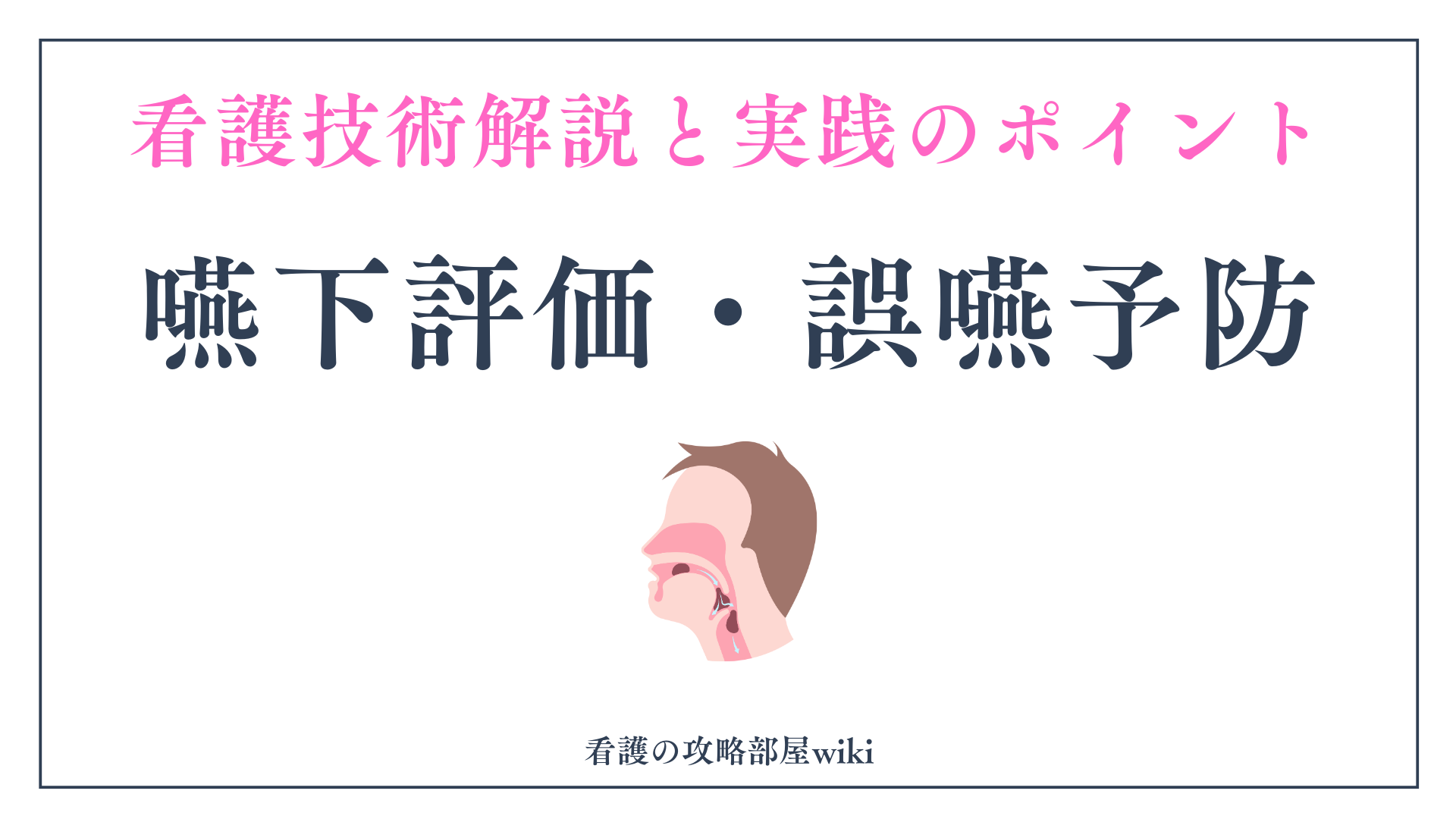
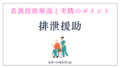
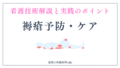
コメント