1. はじめに
感染予防対策は、患者さん、医療従事者、面会者すべての安全を守る看護の根幹となる技術です。「手洗いをして清潔にしていれば大丈夫でしょう?」と思われがちですが、実は科学的根拠に基づいた体系的なアプローチが必要な、高度に専門的な技術なのです。
病院は様々な病原体が存在し、免疫力の低下した患者さんが多い特殊な環境です。一つの感染対策の不備が、患者さんの生命に関わる院内感染を引き起こし、時には病院全体の機能停止につながることもあります。近年の新型コロナウイルス感染症の経験からも、感染予防の重要性は改めて認識されています。
実習では様々な感染症患者や易感染患者を受け持つ可能性があります。正しい感染予防技術を身につけることで、安心して患者ケアに専念でき、医療チームの一員として信頼される看護師を目指しましょう。
この記事で学べること
- 標準予防策の理論的根拠と実践技術の完全習得
- 感染経路別予防策の適応判断と正確な実施方法
- 個人防護具(PPE)の正しい着脱手順と選択基準
- 患者の個別性を考慮した感染管理アプローチ
- 多職種連携による包括的感染対策の実践方法
2. 感染予防対策の基本情報
定義
病原体の感染経路を遮断し、患者・医療従事者・面会者への感染拡大を防止するため、科学的根拠に基づいて実施する一連の予防技術
感染予防対策は単なる清潔保持ではありません。感染成立の3要素(感染源、感染経路、感受性宿主)を科学的に分析し、最も効果的で実行可能な予防策を選択・実施する専門的な看護実践です。
感染成立の条件と予防の原理
感染が成立するためには、①病原体(感染源)、②感染経路、③感受性のある宿主の3つの要素がすべて揃う必要があります。感染予防対策は、この3要素のいずれかを遮断することで感染を防ぐ仕組みです。
病原体については除菌・滅菌により数を減らし、感染経路については適切な予防策で遮断し、感受性宿主については免疫力向上や曝露量削減により防御します。この多重防御により、確実な感染予防を実現します。
標準予防策の基本概念
標準予防策(Standard Precautions)は、すべての患者の血液、体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜には感染性があるものとして取り扱うことを基本とします。感染症の診断に関係なく、すべての患者に適用する基本的な感染予防策です。
これは「すべての患者が潜在的に感染性を持つ可能性がある」という考え方に基づいており、未診断の感染症や無症候性キャリアからの感染を防ぐための重要な概念です。
3. 必要物品と準備
手指衛生用品
基本的手指衛生用品
- アルコール系手指消毒剤(70-80%エタノール)
- 抗菌石鹸(液体石鹸)
- ディスポーザブルタオル・ペーパータオル
- 爪ブラシ(滅菌済み)
- ハンドクリーム(保湿用)
- 手指消毒剤ディスペンサー
手指衛生のタイミング管理用品
- WHO手指衛生5つのタイミング掲示物
- 手指衛生実施記録用紙
- タイマー(手洗い時間管理用)
- 手指衛生チェックリスト
個人防護具(PPE)
基本的PPE
- ディスポーザブル手袋(ニトリル・ラテックスフリー推奨)
- サージカルマスク
- N95マスク(NIOSH認証品)
- アイプロテクション(ゴーグル・フェイスシールド)
- ガウン(撥水性・通気性)
- エプロン(ディスポーザブル・再使用可能)
特殊用途PPE
- 長袖ガウン(接触感染対策用)
- キャップ・ヘアカバー
- シューズカバー・長靴
- 防護服(全身カバータイプ)
- 専用靴(手術室・感染病棟用)
環境管理・消毒用品
消毒薬
- アルコール系消毒薬(環境表面用)
- 次亜塩素酸ナトリウム(0.02%-0.1%)
- 第4級アンモニウム塩系消毒薬
- 過酸化水素系消毒薬
- ポビドンヨード(皮膚消毒用)
清拭・清掃用品
- ディスポーザブルクロス
- マイクロファイバークロス
- 専用モップ・バケツ
- スプレーボトル(消毒薬用)
- 感染性廃棄物容器
- バイオハザード表示ラベル
物品選択の個別化要因
患者の免疫状態(好中球数、CD4陽性T細胞数など)、基礎疾患、治療内容(化学療法、免疫抑制薬使用など)、感染症の有無・種類に応じて、必要なPPEや消毒薬を選択します。
アレルギー歴(ラテックス、薬剤など)、皮膚疾患の有無、妊娠の可能性なども考慮し、患者・医療従事者双方にとって安全な物品を選択することが重要です。
4. 標準予防策の実践技術
手指衛生の技術
手指消毒の実施手順
アルコール系手指消毒剤を手のひらに3-5ml取り、15-30秒間をかけて手指全体にすり込みます。WHO推奨の6ステップ法に従い、①手のひら同士、②手の甲、③指間、④指先・爪、⑤親指、⑥手首まで確実に消毒します。
アルコール系消毒剤は70-80%エタノールが最も効果的で、15秒以内に大部分の病原体を不活化します。ただし、Clostridium difficileの芽胞やノロウイルスには効果が限定的なため、これらが疑われる場合は石鹸と流水での手洗いが必要です。
流水と石鹸による手洗い
目に見える汚れがある場合、血液・体液が付着した場合、芽胞形成菌が疑われる場合は、流水と石鹸による手洗いを実施します。40-60秒間かけて丁寧に洗浄し、特に爪の間、指間、手首まで確実に洗います。
水温は20-37℃が適切で、熱すぎる水は皮膚を傷つけ、冷たすぎる水は洗浄効果を低下させます。洗浄後はディスポーザブルタオルで水分を完全に除去し、手荒れ予防のため適宜ハンドクリームを使用します。
手指衛生の5つのタイミング
WHO推奨の手指衛生5つのタイミングを確実に実行します。①患者に触れる前、②清潔・無菌操作前、③体液曝露リスクの後、④患者に触れた後、⑤患者周辺環境に触れた後です。
これらのタイミングでの実施率は、80%以上を目標とし、継続的な監査により遵守率を向上させます。手指衛生の実施は感染予防の最も基本的で効果的な手段です。
個人防護具(PPE)の選択と着脱
PPE選択の判断基準
血液・体液との接触可能性、飛沫の発生可能性、エアロゾル発生手技の有無などに基づいてPPEを選択します。低リスク(日常的なケア)では手袋とエプロン、中リスク(採血、注射)では手袋、エプロン、マスク、高リスク(気管内吸引、エアロゾル発生手技)では全てのPPEを着用します。
感染症が確定している患者では、感染経路に応じた追加予防策としてのPPEを選択します。接触感染では長袖ガウンと手袋、飛沫感染ではサージカルマスクとアイプロテクション、空気感染ではN95マスクが必要です。
正しいPPE着用手順
着用順序は、①ガウン、②マスク、③アイプロテクション、④手袋の順で行います。ガウンは首元と腰部をしっかりと固定し、袖口が手袋に覆われるよう重ねます。マスクは鼻梁にフィットさせ、顎の下まで確実に覆います。
N95マスクを使用する場合は、着用前にフィットテストを実施し、個人の顔面に適合するサイズ・形状を選択します。着用後はシールチェックにより密着性を確認し、空気漏れがないことを確認します。
安全なPPE脱衣手順
脱衣は最も汚染のリスクが高い作業のため、慎重に行います。脱衣順序は、①手袋、②アイプロテクション、③ガウン、④マスクの順で、各段階で手指消毒を実施します。
汚染された外面に触れないよう、ガウンは内側を外に向けて脱ぎ、手袋は手首から裏返すように脱ぎます。使用済みPPEは感染性廃棄物として適切に廃棄し、再使用可能なものは適切な消毒処理を行います。
5. 感染経路別予防策
接触感染予防策
適応となる病原体と疾患
MRSA、VRE、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性アシネトバクター、Clostridium difficile、疥癬、ノロウイルス胃腸炎などが対象となります。これらは患者の皮膚や患者環境表面を介して伝播するため、接触による感染経路の遮断が重要です。
具体的な予防策
個室管理を基本とし、困難な場合は同一病原体感染患者とのコホート管理を行います。入室時には長袖ガウンと手袋を着用し、患者ケア終了後は病室内で脱衣・廃棄します。
専用または使い捨て器具の使用を徹底し、聴診器、血圧計、体温計などは患者専用とします。環境表面は0.02-0.1%次亜塩素酸ナトリウムまたはアルコール系消毒薬で1日2回以上清拭します。
飛沫感染予防策
適応となる病原体と疾患
インフルエンザウイルス、RSウイルス、マイコプラズマ、百日咳菌、ムンプス、風疹などが対象です。患者の咳、くしゃみ、会話により発生する飛沫(直径5μm以上)により感染します。
具体的な予防策
患者から1-2m以内でケアを行う際は、サージカルマスクとアイプロテクションを着用します。患者にもサージカルマスクを着用してもらい、咳エチケットを指導します。
個室管理が望ましく、困難な場合は同一病原体患者とのコホート管理または2m以上のベッド間隔を確保します。ドアは閉めておく必要はありませんが、患者の移動は最小限に留めます。
空気感染予防策
適応となる病原体と疾患
結核菌、麻疹ウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルスが主な対象です。これらは飛沫核(直径5μm未満)として長時間空気中に浮遊し、広範囲に拡散する可能性があります。
具体的な予防策
陰圧個室での管理が必須で、1時間に6-12回の空気交換率と2.5Pa以上の陰圧を維持します。入室時はN95マスクまたはそれ以上の防護性能を持つマスクを着用し、フィットテストに合格したものを使用します。
患者の移動は医学的に必要な場合のみとし、移動時は患者にサージカルマスクを着用させます。病室のドアは常に閉じた状態を保ち、入退室は最小限に留めます。
6. 特殊な感染管理
易感染患者の管理
防護的隔離(プロテクティブアイソレーション)
好中球数500/μL未満、造血幹細胞移植後、重篤な免疫不全状態の患者では、外部からの病原体侵入を防ぐ防護的隔離を実施します。陽圧個室での管理を基本とし、入室時は清潔なガウン、マスク、手袋を着用します。
面会者の制限、生花・生果物の持ち込み禁止、水道水の使用制限(煮沸済みまたはボトル水の使用)など、厳格な環境管理を行います。患者の免疫状態に応じて、予防策のレベルを調整します。
多剤耐性菌感染対策
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)
接触感染予防策を基本とし、個室隔離、専用器具の使用、環境清拭の強化を行います。MRSA保菌者では、他の患者への感染リスクと患者のQOLを考慮し、個別に隔離の必要性を判断します。
除菌治療(ムピロシン軟膏の鼻腔内塗布など)の適応は、易感染患者との接触リスクや外科手術予定などを考慮して決定します。除菌効果判定は治療終了1週間後から行い、3回連続陰性で除菌成功とみなします。
VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)
MRSA以上に厳格な接触感染予防策が必要です。腸内常在菌のため、便中に高濃度で排出され、環境汚染のリスクが高くなります。便失禁がある場合は、より頻繁な環境清拭と手指衛生の徹底が必要です。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 感染リスク状態
- 社会的孤立
- 不安
- 知識不足
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚-健康管理パターンでは、患者・家族の感染に対する知識レベル、予防行動の実践状況、隔離に対する理解度を評価します。文化的背景や宗教的信念が感染対策に与える影響も考慮する必要があります。
役割-関係パターンでは、隔離による社会的孤立感、家族関係への影響、医療スタッフとの関係性を観察します。面会制限が患者の精神状態に与える影響を評価し、適切な心理的支援を提供することが重要です。
対処-ストレス耐性パターンでは、隔離ストレスへの対処方法、不安や恐怖に対する反応、感染への心理的負担を評価します。患者の心理的適応を支援し、治療継続への意欲を維持する関わりが必要です。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
危険の回避や他者を傷つけないことの欲求に対しては、感染予防の重要性を理解し、主体的に予防行動をとれるよう支援します。患者自身が感染拡大防止に参加することで、治療に対する主体性も向上します。
他者とのコミュニケーションの欲求では、隔離による孤立感を軽減するため、面会制限下でも家族や友人との交流を維持できる方法(電話、ビデオ通話など)を提供します。医療スタッフとの適切なコミュニケーションにより、信頼関係を築くことも重要です。
学習の欲求に対しては、感染症や予防策について正確で理解しやすい情報を提供し、患者・家族の不安軽減と協力促進を図ります。退院後の生活での注意点も含めて、継続的な教育を実施します。
具体的な看護介入
感染拡大防止では、標準予防策の確実な実施と感染経路別予防策の適切な選択・実践を行います。患者の状態や治療内容の変化に応じて、感染リスクを再評価し、必要に応じて予防策を調整します。
心理的支援では、隔離による孤立感や不安に対して共感的な関わりを持ち、患者の気持ちを受け止めます。感染症に対する偏見や差別を防ぐため、正しい知識の提供と理解促進に努めます。
教育・指導では、患者・家族に感染症の特徴、感染経路、予防方法について分かりやすく説明します。退院後の生活での注意点、家族への感染予防策、定期的な検査の必要性などについても指導します。
8. よくある質問・Q&A
Q:N95マスクを着用していても息苦しく感じる場合、どう対処すべきですか?
A: まずフィットテストが適切に行われているかを確認しましょう。サイズが合わない場合は息苦しさが増します。適切なフィットが確認できている場合は、長時間着用による慣れの問題の可能性があります。必要に応じて短時間の休憩を取り、陰圧個室外で新鮮な空気を吸うことも大切です。ただし、空気感染予防策が必要な患者のケア中は、適切なマスク着用を継続する必要があります。医学的に着用困難な場合は産業医に相談しましょう。
Q:接触感染対策中の患者さんが「寂しい」と訴えられる場合、どのような心理的支援ができますか?
A: 隔離による孤立感は患者さんにとって大きなストレスです。まず患者さんの気持ちを受け止め、「寂しい気持ちはよく理解できます」と共感を示しましょう。ケア時間を少し長めに取って会話の機会を増やす、家族との電話やビデオ通話を支援する、可能な範囲で窓越しの面会を調整するなどの工夫ができます。また、隔離の意味と期間について説明し、「治療のために必要な期間限定の対策」であることを伝えて希望を持てるよう支援することも重要です。
Q:標準予防策と感染経路別予防策を同時に実施する場合、PPEの選択はどうすればよいですか?
A: より厳格な予防策に合わせてPPEを選択します。例えば、MRSAに感染した患者がインフルエンザを併発した場合、接触感染予防策(長袖ガウン、手袋)と飛沫感染予防策(サージカルマスク、アイプロテクション)の両方が必要になります。この場合、すべての必要なPPEを着用し、より厳格な管理方法(個室隔離、専用器具使用など)を適用します。複数の感染経路がある場合は感染管理看護師に相談することをお勧めします。
Q:患者さんが「手洗いしすぎて手が荒れる」と言われる場合、どうアドバイスすべきですか?
A: 手荒れは手指衛生の実施率低下につながるため、重要な問題です。アルコール系消毒剤は石鹸での手洗いより皮膚に優しいため、目に見える汚れがない場合はアルコール消毒を推奨します。手洗い後は必ず水分を完全に拭き取り、適宜ハンドクリームを使用するよう指導します。皮膚の状態が改善しない場合は皮膚科への相談も検討し、感染予防を継続しながら皮膚の健康も維持できるよう支援することが大切です。
9. まとめ
感染予防対策は、患者さんと医療従事者の安全を守る最も重要な看護技術の一つです。標準予防策を確実に実施し、患者の状況に応じて感染経路別予防策を適切に選択・実践することで、安全で質の高い医療を提供することができます。
覚えるべき重要数値
- 手指消毒時間:15-30秒間
- 石鹸での手洗い時間:40-60秒間
- アルコール濃度:70-80%エタノール
- 陰圧個室:2.5Pa以上の陰圧、6-12回/時間の空気交換
- 飛沫感染予防距離:患者から1-2m以内でマスク着用
実習・現場で活用できるポイント
実習では、受け持ち患者さんの感染リスクを適切にアセスメントし、根拠に基づいた予防策を選択することから始めましょう。「なぜこの予防策が必要なのか」「どの程度の期間継続するのか」を常に考えながら実践することで、科学的思考力が身につきます。
また、感染予防は個人の技術だけでなく、チーム全体での取り組みが重要です。他職種との連携、患者・家族への教育、環境管理など、包括的なアプローチを学ぶことで、感染管理のスペシャリストとしての基盤を築くことができます。に喜んでもらえる全身清拭を目指しましょう。で部分浴を位置づけて実施しましょう。じて、看護の専門性と人間性の両方を育んでいってください。能力の向上を目指してください。者さんの生活を支える看護師としての誇りを育んでいってください。きます。ましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
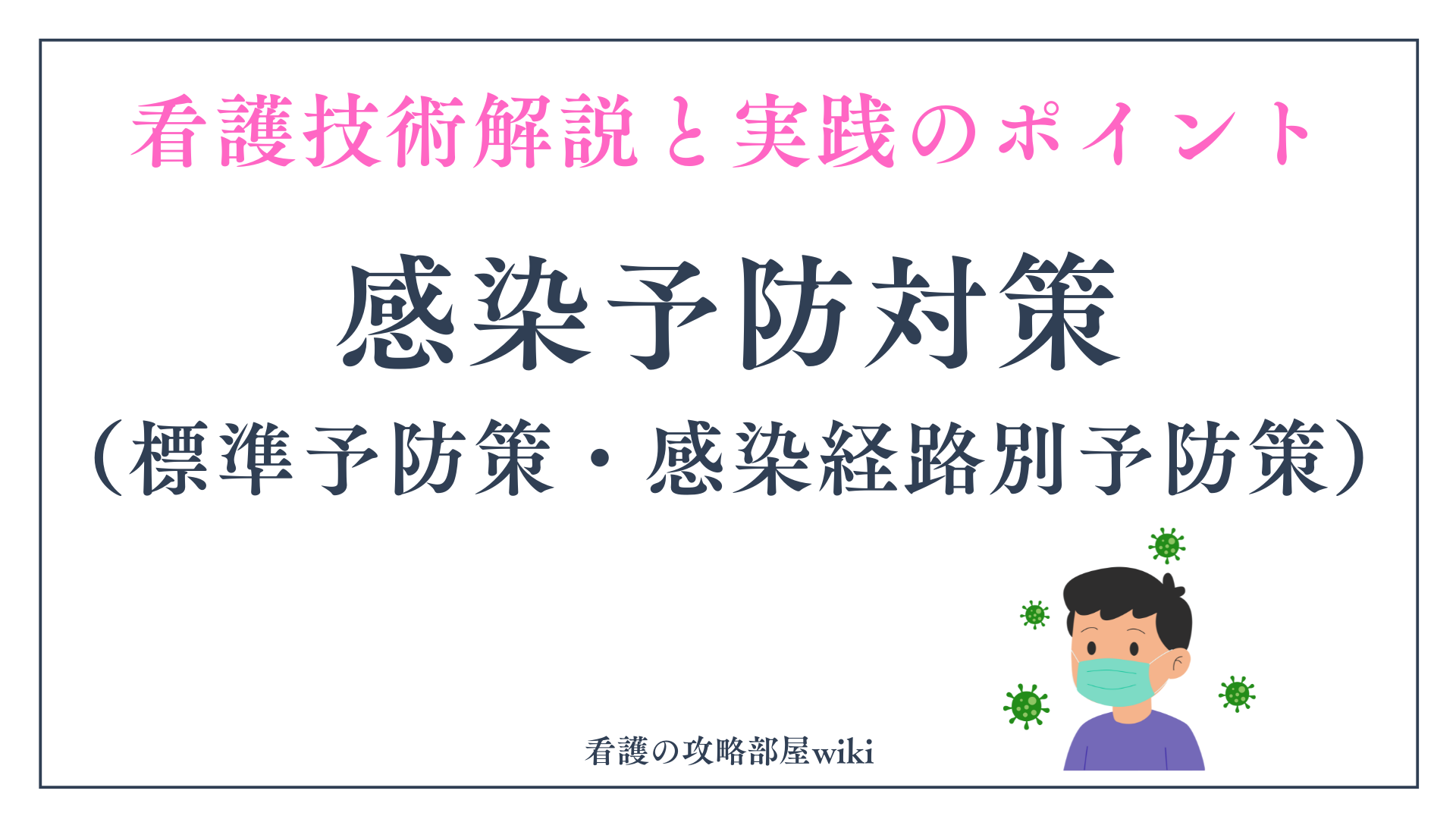


コメント