1. はじめに
転倒・転落予防対策は、患者さんの安全を守る最も重要な看護技術の一つです。「注意して歩けば大丈夫でしょう?」と思われがちですが、入院という特殊な環境下では、普段は転倒しない方でも様々な要因により転倒リスクが高まります。
病院での転倒・転落は、骨折や頭部外傷などの重大な二次損傷を引き起こし、患者さんの ADL低下、入院期間の延長、さらには生命に関わる事態にもなりかねません。また、転倒への恐怖から活動量が減少し、廃用症候群を招くことも少なくありません。
実習では様々な年齢・疾患の患者さんを受け持つため、それぞれの転倒リスクを適切にアセスメントし、個別性のある予防対策を実践できるスキルが必要です。科学的根拠に基づいた予防技術を身につけ、患者さんが安心して療養できる環境を提供しましょう。
この記事で学べること
- 転倒・転落のメカニズムとリスクファクターの包括的理解
- 科学的根拠に基づいたリスクアセスメントツールの活用方法
- 個別性を重視した多角的予防対策の立案と実践技術
- 転倒発生時の適切な対応と記録・報告の方法
- 患者・家族への教育と自立支援を重視した予防アプローチ
2. 転倒・転落予防の基本情報
定義
患者の身体機能・認知機能・環境要因・薬物要因などを総合的にアセスメントし、科学的根拠に基づいた個別的予防策を実施することで転倒・転落事故を防止する看護技術
転倒・転落予防は単に「気をつけて歩く」ことではありません。患者さんの多面的なリスク要因を分析し、環境調整、身体機能維持、認知的支援、薬物管理などを統合的に行う専門的な看護実践です。
転倒と転落の違い
転倒は立位または座位から、自分の意志に反して地面または床面に倒れることです。転落はベッドや車椅子など、ある一定の高さから下方に落下することを指します。病院では両者を合わせて「転倒・転落」として管理することが一般的です。
発生状況と影響
病院での転倒・転落は、ベッド周辺が約60%、廊下・病室内が約25%、トイレ・洗面所が約15%の割合で発生します。時間帯では夜間から早朝にかけてが最も多く、特に午前0時-6時の発生率が高くなります。
転倒により約20-30%の患者で何らかの外傷が生じ、そのうち5-15%で骨折などの重篤な傷害が発生します。高齢者では大腿骨近位部骨折のリスクが特に高く、これにより歩行能力の著しい低下や要介護状態への移行が懸念されます。
3. 必要物品と準備
リスクアセスメント用品
評価ツール・記録用品
- 転倒・転落リスクアセスメントシート
- Morse Fall Scale(モース転倒スケール)
- 転倒・転落アセスメントスコアシート
- 経時的記録用紙
- 血圧計・体温計(起立性低血圧評価用)
- ストップウォッチ(歩行評価用)
身体機能評価用品
- 歩行補助具(杖・歩行器・車椅子)
- 滑り止め付きスリッパ・靴下
- 筋力測定器(簡易式)
- バランス評価用マット
- 視力検査用品(必要時)
環境整備・安全対策用品
転倒予防環境整備用品
- 滑り止めマット(浴室・洗面所用)
- 床用滑り止めテープ
- ベッド用転落防止パッド
- 衝撃吸収マット(ベッド周囲用)
- 手すり(移動式・固定式)
- 段差解消スロープ
照明・視認性向上用品
- フットライト・ナイトライト
- 人感センサー付き照明
- 反射テープ(段差・角部用)
- カラーテープ(段差標識用)
- 蓄光テープ(暗闇での視認性向上)
警報・監視システム
離床センサー類
- ベッドサイドセンサー(マット式)
- ベッド内蔵型離床センサー
- 赤外線センサー
- ナースコール連動型センサー
- ウェアラブル型活動量計
警報・通知用品
- ナースコール(手引き型・無線型)
- 携帯型アラーム
- 見守りカメラシステム
- スマートフォン連携アプリ
- 緊急呼び出しペンダント
物品選択と個別化
患者さんの身体機能、認知機能、疾患の特徴、入院期間などを総合的に考慮して必要物品を選択します。過度な制限は患者さんの自立性を損なうため、必要最小限で最大効果を得られる物品を選択することが重要です。
認知機能が低下した患者さんでは、複雑な機器よりもシンプルで直感的に理解できる対策を優先します。一方、身体機能は保たれているが一時的にリスクが高まった患者さんでは、自己管理能力を活用した対策を中心に選択します。
4. 転倒・転落リスクアセスメント
包括的リスク評価
身体的要因の評価
筋力低下、バランス障害、歩行障害、視力・聴力障害、起立性低血圧、関節可動域制限などを系統的に評価します。Timed Up & Go Test(TUG)では、椅子から立ち上がり3メートル歩行して戻る時間を測定し、14秒以上で転倒リスクありと判定します。
片脚立位時間の測定では、目を開けた状態で15秒未満の場合、転倒リスクが高いとされます。また、Functional Reach Testでは前方リーチ距離が25cm未満で転倒リスクが高まります。
認知的要因の評価
見当識障害、記憶障害、判断力低下、病識の欠如、衝動性などを評価します。HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)やMMSE(Mini-Mental State Examination)を活用し、20点以下では転倒リスクが高まるとされます。
せん妄の有無も重要な評価項目です。CAM(Confusion Assessment Method)を用いてせん妄を評価し、陽性の場合は転倒リスクが著しく高まるため、より厳重な対策が必要になります。
薬物関連要因の評価
睡眠薬、抗不安薬、降圧薬、利尿薬、抗精神病薬、抗てんかん薬などの服用状況を詳細に確認します。4剤以上の薬物服用で転倒リスクが有意に上昇し、特にpsychotropic drugs(精神作用薬)の使用では注意が必要です。
薬物の副作用として、ふらつき、眠気、起立性低血圧、筋力低下、認知機能低下などが出現していないかを観察します。新規処方薬や用量変更後は、特に注意深い観察が必要です。
環境的要因の評価
照明の適切性、床面の状態、段差の有無、手すりの設置状況、履物の適切性、ベッドの高さ、障害物の配置などを詳細に評価します。病室とトイレ間の動線、夜間の照明状況、ナースコールの位置なども重要な評価項目です。
Morse Fall Scale の活用
国際的に広く使用されている転倒リスクアセスメントツールです。転倒歴、二次診断、歩行補助具、点滴治療、歩行状態、精神状態の6項目で評価し、25点以上で転倒リスクあり、45点以上で高リスクと判定します。
5. 個別的予防対策の実践
身体機能維持・向上対策
筋力・バランス訓練
理学療法士と連携し、患者さんの状態に応じた運動プログラムを実施します。ベッド上での等尺性筋力訓練、立位バランス訓練、歩行練習などを段階的に進めます。週3回以上、1回30分程度の運動が効果的とされています。
座位での足上げ運動、踵上げ運動、足首の背屈・底屈運動など、ベッドサイドで実施できる簡単な運動も有効です。患者さんが主体的に取り組めるよう、運動の意義を説明し、モチベーションを維持する支援が重要です。
歩行能力の評価と支援
歩行補助具の適切な選択と使用方法の指導を行います。杖では患者さんの身長に対して適切な長さに調整し、肘の屈曲角度を20-30度に保てる高さに設定します。歩行器では患者さんの歩幅に合わせて調整し、正しい使用方法を繰り返し指導します。
歩行時の観察では、歩行速度、歩幅、ふらつきの有無、疲労の程度を評価し、患者さんの能力に応じた活動レベルを設定します。過度な活動制限は廃用症候群を招くため、安全性と活動性のバランスを考慮した支援が必要です。
環境調整と安全対策
照明環境の最適化
夜間の転倒予防では適切な照明が不可欠です。ベッドからトイレまでの動線にフットライトを設置し、10ルクス以上の照度を確保します。人感センサー付き照明により、患者さんの動きに応じて自動的に点灯するシステムも効果的です。
日中でも病室内の照度が不十分な場所があるため、300ルクス以上の照度を確保し、影になりやすい箇所には補助照明を設置します。眩しさを避けながらも十分な明るさを提供することがポイントです。
床面・動線の安全確保
床面の水濡れは直ちに清拭し、滑り止めマットを適切に配置します。段差がある場所にはスロープを設置し、段差が解消できない場合は反射テープやカラーテープで視認性を高めます。
患者さんの動線上にある障害物(点滴スタンド、車椅子、ゴミ箱など)は適切に配置し直し、十分な通行幅を確保します。特に夜間のトイレ動線では、80cm以上の通行幅を確保することが推奨されます。
認知的支援と行動変容
見当識支援と環境の見える化
認知機能が低下した患者さんでは、時間・場所・状況の見当識を支援します。大きな文字で日付・時刻を表示し、病室の場所やトイレの位置を分かりやすく示します。馴染みのある物品を配置することで、安心感を提供します。
夜間のせん妄予防では、昼夜のリズムを保つため、日中は明るく、夜間は適度な暗さを維持します。不必要な刺激を避けながらも、必要時には迅速に対応できる環境を整えます。
患者・家族教育
転倒予防の重要性と具体的な方法について、患者さんと家族に分かりやすく説明します。「ちょっとそこまでなら大丈夫」という油断が転倒につながることを説明し、常に安全を意識した行動をとっていただけるよう支援します。
ナースコールの使い方、適切な履物の選択、夜間トイレ時の注意点などを具体的に指導します。また、転倒に対する過度な恐怖心も活動量低下を招くため、適切なリスク認識を持てるよう情報提供します。
6. 転倒発生時の対応
初期対応と安全確保
転倒を発見または転倒の報告を受けた場合、まず患者さんの意識状態と呼吸・循環状態を確認します。意識消失や呼吸困難がある場合は、直ちに医師に連絡し、必要に応じて心肺蘇生術を開始します。
患者さんが動かないよう声をかけ、頭部・頸部・脊椎の損傷を考慮して不用意な体位変換は避けます。出血がある場合は清潔なガーゼやタオルで圧迫止血を行い、骨折が疑われる場合は患部を固定します。
医学的評価と検査
医師による診察を受け、神経学的所見、整形外科的所見、外傷の有無を詳細に評価します。頭部外傷が疑われる場合はCT検査、骨折が疑われる場合はX線検査を実施し、内臓損傷の可能性も考慮します。
バイタルサインの測定と継続的な意識レベルの観察を行い、遅発性の症状出現に注意します。特に高齢者では軽微な外傷でも重篤な合併症を生じる可能性があるため、慎重な経過観察が必要です。
記録と報告
転倒の状況を詳細に記録し、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)に沿って客観的に記載します。転倒前後の患者の状態、環境要因、発見時の状況、実施した対応などを時系列で整理します。
インシデント・アクシデントレポートを速やかに作成し、関係部署への報告を行います。家族への連絡では、事実を正確に伝えるとともに、今後の対策についても説明し、理解を得ることが重要です。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 転倒・転落リスク状態
- 歩行障害
- 活動耐性低下
- 不安
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さんが自身の転倒リスクをどの程度認識しているか、予防行動をとる意欲があるかを評価します。過去の転倒体験や転倒に対する恐怖感も重要な情報です。
活動-運動パターンでは、日常生活動作の自立度、筋力・バランス能力、歩行状態、活動量の変化を詳細に観察します。疾患や治療による活動制限と、それに伴う身体機能の変化も評価の対象となります。
認知-知覚パターンでは、見当識、記憶力、判断力、病識の程度を評価し、転倒予防指導の理解度や実行可能性を判断します。疼痛や不快感が行動に与える影響も考慮します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
身体の動きや適正な姿勢の保持の欲求に対しては、患者さんの残存機能を最大限に活用し、安全な移動方法を習得できるよう支援します。転倒予防と活動性維持の両立を図り、患者さんの自立を促進することが重要です。
危険の回避や他者を傷つけないことの欲求では、転倒リスクの適切な認識と予防行動の実践を支援します。患者さん自身が安全を意識し、主体的に予防策に取り組めるよう動機づけを行います。
正常な睡眠と休息の欲求に対しては、夜間の転倒リスクを最小限に抑えながら、質の良い睡眠を提供できる環境を整備します。睡眠薬の使用による転倒リスク上昇と睡眠の質のバランスを考慮した支援が必要です。
具体的な看護介入
最優先事項は生命に関わるリスクの除去と緊急時の迅速な対応です。高リスク患者では定期的な巡視頻度を増やし、夜間は特に注意深い観察を行います。離床センサーやナースコールの適切な使用により、早期発見・早期対応を可能にします。
継続的な評価では、患者さんの状態変化に応じてリスクアセスメントを更新し、予防策を調整します。薬物変更、病状変化、身体機能の改善・悪化などに応じて、柔軟に対策を見直すことが重要です。
多職種との連携により、包括的な転倒予防対策を実施します。医師との薬物調整の相談、理学療法士との機能訓練計画の立案、薬剤師との服薬指導の連携などにより、より効果的な予防が可能になります。
8. よくある質問・Q&A
Q:認知症の患者さんが「トイレに行きたい」と言って立ち上がろうとしますが、転倒リスクが高い場合はどう対応すべきですか?
A: 患者さんの尊厳と安全の両方を考慮した対応が必要です。まず「トイレに行きたい」という気持ちを受け止め、「一緒に行きましょう」と声をかけます。可能であれば看護師が付き添ってトイレ誘導を行い、困難な場合はポータブルトイレの使用や、定時のトイレ誘導により排尿パターンを把握して予防的に対応します。身体拘束は最後の手段として、倫理委員会での検討を経て実施します。
Q:夜勤帯で転倒リスクの高い患者さんが複数いる場合、どのように優先順位をつけて対応すべきですか?
A: リスクアセスメントスコアと臨床判断を総合して優先順位を決定します。認知機能低下+せん妄の患者、新規処方薬開始直後の患者、転倒歴のある患者を最優先とし、巡視頻度を増やします。離床センサーの活用、ベッドサイドへの移動、同室者への協力依頼なども検討します。必要に応じて看護師長に相談し、適切な人員配置を求めることも重要です。
Q:患者さんが「大丈夫、一人でできる」と言って転倒予防対策を拒否される場合はどうすればよいですか?
A: まず患者さんの気持ちを理解し、自立したいという意欲を尊重する姿勢を示します。その上で、入院環境では普段とは異なるリスクがあることを具体例を交えて説明します。「○○さんなら普段は大丈夫だと思いますが、慣れない環境や治療の影響で、いつもより転びやすくなることがあります」と伝え、予防策を「一時的な安全確保」として提案します。完全な制限ではなく、段階的な自立支援プランを一緒に検討することも効果的です。
Q:転倒が発生してしまった場合、家族への説明で注意すべき点は何ですか?
A: まず患者さんの現在の状態と実施した治療について正確に報告します。転倒の状況は事実のみを客観的に伝え、推測や憶測は避けます。「申し訳ありませんでした」という謝罪よりも、「ご心配をおかけして」という共感の言葉を使います。今後の予防策について具体的に説明し、家族の協力もお願いします。責任の所在については医師や師長と相談してから回答し、一看護師の判断で発言しないことが重要です。
9. まとめ
転倒・転落予防対策は、患者さんの安全を守り、質の高い療養環境を提供するための重要な看護技術です。多角的なリスクアセスメントと個別性を重視した予防策の実践により、患者さんが安心して治療に専念できる環境を作ることができます。
覚えるべき評価基準
- Timed Up & Go Test:14秒以上で転倒リスクあり
- 片脚立位時間:15秒未満で転倒リスク高
- Morse Fall Scale:25点以上でリスクあり、45点以上で高リスク
- 夜間照明:動線上で10ルクス以上を確保
- 通行幅:80cm以上の確保が推奨
実習・現場で活用できるポイント
実習では、受け持ち患者さんの転倒リスクを系統的にアセスメントし、根拠に基づいた個別的な予防計画を立案することから始めましょう。「この患者さんにとって最も効果的な予防策は何か」「患者さんの尊厳を保ちながら安全を確保するにはどうすればよいか」を常に考えることが重要です。
また、転倒予防は看護師だけで行うものではありません。患者さんご本人、ご家族、多職種のチームメンバーとの連携により、より効果的な予防が可能になります。コミュニケーションスキルと協働する姿勢も重要な技術の一部として身につけましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
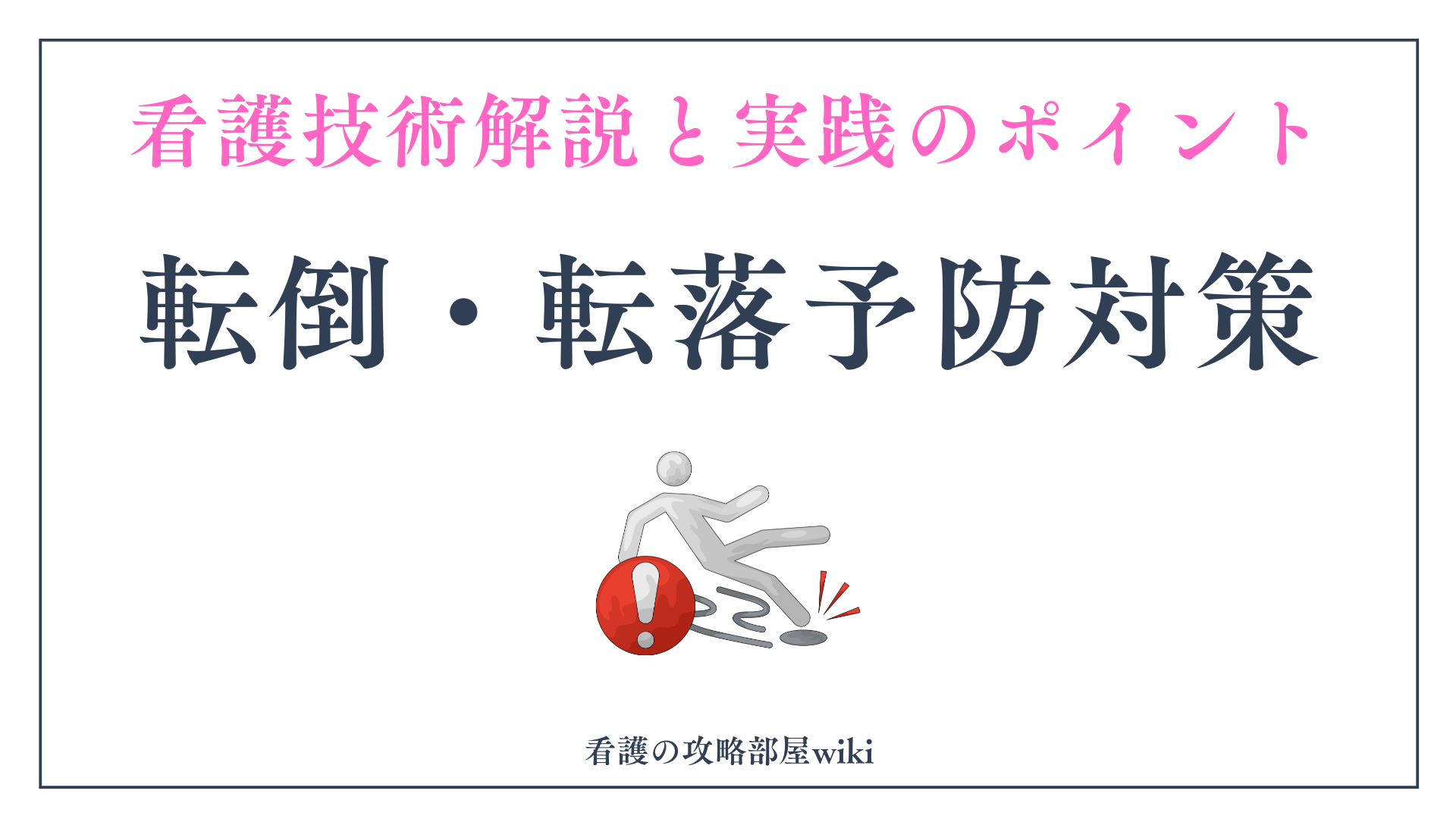
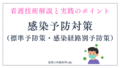
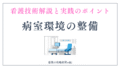
コメント