1. はじめに
「褥瘡はどうして起こるの?」「一度できてしまったら治らないの?」褥瘡は看護実習でも臨床現場でも頻繁に遭遇する重要な問題です。「褥瘡ができてしまったのは看護が悪いから」という思い込みや、「仕方がない」という諦めの気持ちを持つ看護学生も少なくありません。
患者さんや家族からも「寝ているだけなのになぜ傷ができるの?」「いつになったら治るの?」「痛そうで見ていられない」といった切実な声をよく聞きます。褥瘡は単なる皮膚の問題ではなく、患者さんの生活の質を大きく左下させ、時には生命にも関わる深刻な合併症です。
しかし、適切な知識と技術を持って系統的にアプローチすれば、褥瘡の多くは予防可能であり、発生してしまった褥瘡も治癒に導くことができます。現代の褥瘡ケアは、圧迫・ずれ・摩擦の除去、湿潤環境の維持、栄養管理、感染制御など多角的なアプローチにより、大幅に改善されています。
実習では褥瘡のある患者さんを受け持つ機会が多く、将来的には看護師として褥瘡予防から治療まで包括的な責任を担う重要な技術となります。
この記事で学べること
- 褥瘡の発生メカニズムと分類・評価方法
- 褥瘡の状態に応じた適切な処置技術と材料選択
- 圧迫除去とポジショニングの具体的方法
- 褥瘡予防のための包括的アプローチ
- ゴードンとヘンダーソンの理論に基づいた全人的ケア
2. 褥瘡処置の基本情報
定義
褥瘡処置とは、圧迫や摩擦・ずれにより生じた組織損傷(褥瘡)に対して、治癒促進・感染予防・疼痛軽減を目的として行う包括的な創傷管理技術
褥瘡処置は単なる創傷処置ではなく、褥瘡発生の根本原因である圧迫・ずれ・摩擦の除去、全身状態の改善、創傷治癒環境の最適化を総合的に行う高度な看護技術です。予防的ケアから治療的介入まで幅広い知識と技術が求められます。
技術の意義と目的
褥瘡処置の最終目標は単なる創傷治癒ではなく、患者の生活の質の向上と尊厳の保持です。適切な褥瘡ケアにより、疼痛の軽減、感染の予防、入院期間の短縮、医療費の削減が可能になります。
患者にとっては、身体的苦痛の軽減だけでなく、外見上の問題や臭いによる心理的苦痛からも解放され、より快適な療養生活を送ることができます。看護師にとっては、予防的視点と治療的視点を統合した包括的ケアを実践する重要な機会となります。
実施頻度・タイミング
褥瘡処置の頻度は褥瘡の重症度、感染の有無、浸出液の量により決定されます。NPUAP分類ステージIでは処置は不要で圧迫除去が中心、ステージIIでは1日1回程度、ステージIII-IVでは1日1-2回が一般的です。感染がある場合は1日2-3回の処置が必要な場合もあります。体位変換は2時間毎を基本とし、患者の状態に応じて調整します。
3. 必要物品と準備
基本的な褥瘡処置用品
滅菌生理食塩水、滅菌ガーゼ(各種サイズ)、滅菌綿棒、医療用テープ、滅菌手袋、マスク、エプロンを準備します。褥瘡の洗浄には微温生理食塩水(32-37℃)を使用し、組織に優しい低圧洗浄を心がけます。
測定用具として滅菌定規、写真撮影用カメラ、褥瘡評価スケール(DESIGN-R、NPUAP分類表)を準備します。記録用紙と前回の評価結果も手元に用意し、経時的変化を把握できるようにします。
褥瘡専用ドレッシング材
褥瘡の状態に応じて、ハイドロコロイドドレッシング、ハイドロジェルドレッシング、ポリウレタンフォームドレッシング、アルギン酸ドレッシング、銀含有ドレッシングなどを選択します。
深い褥瘡には充填材(アルギン酸ファイバー、ハイドロファイバーなど)を準備し、ポケット形成がある場合は適切な充填と排液経路の確保を図ります。複数の材料を組み合わせる場合も多くあります。
体圧分散・ポジショニング用品
体圧分散マットレス、体位保持用クッション、ポジショニング枕、踵部保護用具、肘部保護用具を患者の状態に応じて準備します。マットレスは患者の体重と活動レベルに応じて選択します。
車椅子使用患者では車椅子用クッション、ベッド上では30度側臥位を維持するための三角クッション、踵部挙上用枕などを準備します。摩擦軽減のため、シルキーテックスやスライディングシートも有用です。
栄養・感染対策用品
褥瘡治癒には適切な栄養管理が不可欠です。血液検査データ確認のため、最新の検査結果(アルブミン、総蛋白、ヘモグロビン値)を準備します。栄養士との連携のため、栄養評価表も用意します。
感染徴候の評価のため、体温計、創部培養用検体採取容器、感染性廃棄物容器を準備します。多剤耐性菌のリスクがある場合は、追加の感染予防具も準備します。
疼痛管理用品
褥瘡処置時の疼痛軽減のため、局所麻酔剤(リドカインゼリーなど)、鎮痛剤、冷罨法用品を準備します。非薬物的疼痛緩和のため、音楽プレーヤーや患者の好む読み物も有効です。
処置中の患者の安楽確保のため、適切な体位保持用具、室温調整、プライバシー保護用品も忘れずに準備します。
4. 褥瘡処置の実施手順
事前準備とアセスメント
患者の全身状態、褥瘡の既往歴、現在の褥瘡の状態と処置内容を確認します。前回の褥瘡評価記録、写真、処置記録を参照し、治癒の進行度を把握します。栄養状態、循環状態、感染徴候の有無も総合的に評価します。
医師の処置指示内容、使用薬剤、ドレッシング材の種類と交換頻度を確認します。患者の疼痛レベルと前回処置時の反応、アレルギー歴も重要な確認事項です。
患者・家族への説明では、処置の目的、手順、予想される疼痛と対策、治癒の見通しについて丁寧に説明し、理解と協力を得ます。不安や疑問がある場合は十分に時間をかけて対応します。
NPUAP分類に基づく褥瘡評価
ステージIでは皮膚の発赤、熱感、硬結、疼痛を評価します。指圧により退色しない発赤が特徴的で、皮膚の色調変化、温度変化、硬さの変化を詳細に観察します。
ステージIIでは表皮・真皮の部分欠損を評価し、水疱、浅い潰瘍、擦り傷様の外観を呈します。創床は淡紅色から赤色で、スラフ(黄色組織)は認められません。
ステージIIIでは皮下組織までの全層欠損があり、脂肪組織が見える場合がありますが、骨・腱・筋肉は露出していません。アンダーマイニング(皮下の空洞)やポケット形成の有無も評価します。
ステージIVでは骨・腱・筋肉まで露出する全層欠損で、スラフやエスチャー(黒色壊死組織)が存在する場合があります。アンダーマイニングやポケット形成も頻繁に認められます。
DESIGN-Rによる詳細評価
DESIGN-Rスケールを用いて、深さ(Depth)、浸出液(Exudate)、サイズ(Size)、炎症・感染(Inflammation/Infection)、肉芽組織(Granulation tissue)、壊死組織(Necrotic tissue)、ポケット(Pocket)の7項目を各3-4段階で評価し、総合点により重症度を判定します。
各項目を客観的に評価し、前回評価との比較により治癒の進行度を判定します。評価結果は処置方針の決定と他職種との情報共有に活用します。
褥瘡洗浄と清拭
褥瘡洗浄は微温生理食塩水(32-37℃)を使用し、8-15cmの距離から低圧(4-15psi)で実施します。シリンジを使用する場合は19ゲージ針を装着し、適切な洗浄圧を確保します。
洗浄は褥瘡の中央から外側に向かって行い、壊死組織、スラフ、古い浸出液、細菌を除去します。健康な肉芽組織を損傷しないよう、愛護的に実施することが重要です。
ポケットがある場合は、滅菌綿棒や軟らかいカテーテルを使用して内部を洗浄しますが、無理な洗浄は避け、排液経路の確保を重視します。
壊死組織の除去(デブリードマン)
シャープデブリードマン(鋭的除去)は医師の指示のもとで実施し、滅菌はさみや鋭匙を使用して壊死組織を除去します。血管や神経の損傷リスクがあるため、解剖学的知識と確実な技術が必要です。
ケミカルデブリードマンでは、酵素軟膏(コラゲナーゼ軟膏など)やハイドロジェルを使用して壊死組織を軟化・除去します。作用時間と効果を考慮した適切な適用が重要です。
オートリティックデブリードマンでは、湿潤環境の維持により自己融解を促進し、自然な壊死組織除去を図ります。ハイドロコロイドドレッシングなどが有効です。
ドレッシング材の選択と適用
ステージIIの浅い褥瘡では、ハイドロコロイドドレッシングやポリウレタンフィルムドレッシングを選択し、湿潤環境を維持します。浸出液が少ない場合に適しています。
ステージIII-IVの深い褥瘡では、浸出液の量に応じてポリウレタンフォームドレッシング、アルギン酸ドレッシングを選択します。感染がある場合は銀含有ドレッシングの使用を検討します。
深い褥瘡やポケット形成がある場合は、一次ドレッシング(充填材)と二次ドレッシング(吸収・保護材)の組み合わせにより、適切な浸出液管理と湿潤環境の維持を図ります。
圧迫除去とポジショニング
褥瘡部位の完全免荷が治癒の絶対条件です。体位変換は2時間毎を基本とし、褥瘡部位に圧迫が加わらない体位を選択します。30度側臥位により仙骨部と大転子部の圧迫を回避します。
踵部褥瘡では踵部完全挙上を実施し、膝関節を軽度屈曲位に保持して腓腹筋の緊張を緩和します。肘部褥瘡では肘当ての使用と定期的な肢位変換を行います。
車椅子使用時は1時間毎のプッシュアップまたは15分毎の体重移動を指導し、座面の圧迫を定期的に除去します。車椅子用クッションの適切な選択も重要です。
5. 特殊な状況での褥瘡処置
終末期患者の褥瘡ケア
終末期では治癒よりも疼痛緩和と感染予防が優先されます。過度な処置は避け、患者の苦痛を最小限に抑える緩和的ケアを中心とします。ドレッシング交換頻度を減らし、長時間作用型のドレッシング材を選択します。
家族への説明では、褥瘡の意味と今後の見通し、ケアの方針について丁寧に説明し、理解と協力を得ます。QOLを重視した個別的なケア計画を立案し、多職種で共有します。
糖尿病患者の褥瘡ケア
糖尿病患者では血糖コントロールが褥瘡治癒に大きく影響します。HbA1c値、血糖値の推移を確認し、内分泌科との連携により血糖管理を最適化します。
易感染性と創傷治癒遅延のため、厳重な感染予防策と長期間の治療計画が必要です。足部褥瘡では免荷装具の使用やフットケアの専門的評価も検討します。
脊髄損傷患者の褥瘡ケア
脊髄損傷患者では感覚脱失により褥瘡の早期発見が困難なため、定期的な皮膚観察と予防的ケアが重要です。2時間毎の体位変換とプッシュアップ訓練の確実な実施が必要です。
長期的な自己管理能力の向上のため、患者・家族への褥瘡予防教育とスキンチェック技術の指導を段階的に実施します。社会復帰を見据えた実用的な技術習得を支援します。
高齢者の褥瘡ケア
高齢者では皮膚の脆弱性、治癒力の低下、基礎疾患の影響を考慮した褥瘡ケアが必要です。テープによる皮膚損傷を防ぐため、皮膚保護剤の使用や低刺激性テープの選択を行います。
認知症がある場合は、ドレッシングの無意識な除去を防ぐ工夫や、行動・心理症状への対応も含めた包括的ケアが必要です。家族の協力と理解も重要な要素となります。
小児の褥瘡ケア
小児では成人とは異なる解剖学的特徴と生理学的特徴を考慮した褥瘡ケアが必要です。皮膚が薄く、体表面積が相対的に大きいため、体温調節と水分バランスへの影響に注意が必要です。
年齢に応じた説明と心理的支援により、治療への協力を得ます。成長・発達への影響を最小限に抑えるため、活動制限を必要最小限に留める工夫が重要です。
6. 褥瘡処置中の観察とアセスメント
処置中は患者の疼痛レベルを継続的に評価し、処置による疼痛増強がないか確認します。特に壊死組織除去時は愛護的な手技を心がけ、必要に応じて処置を中断し、鎮痛対策を検討します。
褥瘡の治癒進行度を前回との比較で評価し、サイズの縮小、肉芽組織の増生、上皮化の進行を確認します。治癒が停滞している場合は、阻害要因の検索と処置方針の見直しを検討します。
感染徴候(発赤の拡大、腫脹、熱感、膿性分泌物、悪臭)の有無を詳細に観察し、全身の感染徴候(発熱、白血球増多)も合わせて評価します。早期発見により重篤化を防ぎます。
ドレッシング材の適合性を評価し、浸出液の吸収状況、固定状況、皮膚への刺激の有無を確認します。適切でない場合は材料の変更や固定方法の調整を検討します。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 皮膚統合性の障害
- 急性疼痛/慢性疼痛
- 感染リスク状態
- 活動耐性の低下
- 身体像の混乱
- 介護者の役割緊張
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚・健康管理パターンでは、患者・家族の褥瘡に対する理解度と予防意識、自己管理能力、治療への協力度を評価します。褥瘡予防の重要性を理解し、日常生活の中で予防策を実践できるよう支援することが重要です。喫煙や飲酒などの生活習慣も創傷治癒に影響するため、改善指導も必要です。
活動・運動パターンでは、患者の活動レベル、可動域制限、褥瘡による活動制限の程度を評価します。褥瘡の部位と重症度により、歩行、座位保持、体位変換の可否が決まります。安全な活動レベルを維持しながら、可能な限り自立性を保持することが生活の質の向上につながります。
栄養・代謝パターンでは、褥瘡治癒に必要な栄養素の摂取状況を詳細に評価します。蛋白質、ビタミンC、亜鉛、鉄分の充足度、アルブミン値(3.0g/dl以上)、BMI、食事摂取量の推移を確認し、栄養士と連携した栄養管理を実施します。脱水状態も創傷治癒を阻害するため、水分摂取量の評価も重要です。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常に動き、望ましい体位を保持する欲求では、褥瘡部位の圧迫除去と快適な体位保持の両立が重要になります。2時間毎の体位変換、30度側臥位の維持、踵部挙上などの技術的な介入と、患者が可能な範囲での自動運動や体位変換への参加を促進します。長期間の安静が必要な場合でも、関節拘縮や筋萎縮を防ぐための工夫が必要です。
身体の清潔を保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する欲求では、褥瘡周囲皮膚の清潔保持と保護が中心となります。過度な清拭による皮膚損傷を防ぎながら、感染予防に必要な清潔レベルを維持します。失禁による皮膚汚染の迅速な除去、適切なスキンケア製品の選択、摩擦軽減のための工夫が重要です。
苦痛を避け、それを表現し、解釈し、解決する欲求では、褥瘡に伴う疼痛の適切な評価と管理が最重要課題となります。安静時痛、体動時痛、処置時痛それぞれに対する対策を講じ、薬物療法と非薬物療法を組み合わせた包括的疼痛管理を実施します。患者が疼痛を適切に表現し、医療者と共有できる環境づくりも重要です。
具体的な看護介入
圧迫除去が最も重要な看護介入です。体圧分散マットレスの適切な選択、定期的な体位変換(2時間毎)、プッシュアップや体重移動の指導により、褥瘡部位の完全免荷を実現します。車椅子使用時は1時間毎の圧迫除去、歩行可能な患者では定期的な立位・歩行により血流改善を図ります。
栄養管理では、高蛋白・高カロリー食の提供、必要に応じた栄養補助食品の使用、水分摂取量の確保により創傷治癒に最適な栄養状態を維持します。栄養士と連携し、患者の嗜好や摂食能力を考慮した個別的な栄養計画を立案・実施します。
感染予防では、標準予防策の徹底、適切な創傷管理、早期感染徴候の発見により重篤化を防ぎます。無菌操作による処置、適切なドレッシング材の選択、環境の清潔保持を確実に実施し、院内感染の防止も図ります。
患者・家族教育では、褥瘡予防の重要性、スキンチェック方法、適切な体位変換技術、栄養管理の重要性について段階的に指導します。実際のケア場面での指導、視覚的教材の活用、繰り返し練習の機会提供により、確実な技術習得と意識向上を支援します。
8. よくある質問・Q&A
Q:エアマットレスを使っているのに褥瘡ができてしまいました。なぜでしょうか?
A: エアマットレスは褥瘡予防に有効ですが、万能ではありません。マットレスの設定が不適切(圧力設定が高すぎる、患者の体重に合わない)、体位変換の不備(同一部位への長時間圧迫)、ずれ・摩擦の影響(ベッドアップ角度が高すぎる、不適切な体位変換)が原因として考えられます。また、栄養状態の悪化、循環不全、皮膚の脆弱性などの内的要因も褥瘡発生に大きく影響します。エアマットレスの適切な使用に加えて、2時間毎の体位変換、栄養管理、スキンケアを包括的に実施することが重要です。マットレスの機種選択や設定について、医療機器メーカーや褥瘡対策チームに相談することをお勧めします。
Q:褥瘡の処置中に出血してしまった場合、どう対処すればよいですか?
A: 褥瘡処置中の出血は珍しいことではありませんが、適切な対応が必要です。まず出血の程度と原因を確認します。軽度の出血であれば、清潔なガーゼで圧迫止血し、数分間圧迫を継続します。肉芽組織からの軽微な出血は正常な反応の場合もありますが、動脈性出血や大量出血の場合は速やかに医師に報告してください。処置を一時中断し、バイタルサインの確認、出血量の把握を行います。出血が止まった後は、出血の原因(過度な機械的刺激、感染、血管新生)を検索し、今後の処置方法を見直します。抗凝固薬の使用歴、血小板数、凝固機能も確認が必要です。
Q:褥瘡が一向に良くならないのですが、どのような要因が考えられますか?
A: 褥瘡治癒の停滞には多くの要因が関与します。局所要因として、持続的な圧迫・摩擦(体位変換不備、不適切なマットレス)、感染(細菌感染、バイオフィルム形成)、不適切な湿潤環境(過乾燥、過湿潤)、血流不全が挙げられます。全身要因では、栄養不良(蛋白質不足、アルブミン低値)、貧血、糖尿病、循環器疾患、腎疾患、免疫不全、薬剤の影響(ステロイド、抗がん剤)があります。心理社会的要因として、疼痛によるストレス、治療への非協力、社会的支援不足も影響します。包括的な要因分析を行い、多職種チームで対策を検討することが重要です。必要に応じて形成外科や皮膚科への紹介も検討してください。
Q:在宅で褥瘡ケアを継続する場合、家族にはどのような指導が必要ですか?
A: 在宅での褥瘡ケア成功のカギは、家族の理解と技術習得です。まず褥瘡発生のメカニズムと予防の重要性について丁寧に説明し、体位変換の方法とタイミング(2時間毎)を実際に指導します。スキンチェックの方法では、発赤、腫脹、熱感、硬結の確認方法を具体的に教え、異常時の対応(連絡先、受診のタイミング)を明確にします。処置技術については、手指衛生、清潔操作、ドレッシング交換の方法を段階的に指導し、実際の処置を見学・実践してもらいます。栄養管理の重要性も説明し、高蛋白食の工夫や水分摂取について具体的にアドバイスします。定期的な訪問看護やかかりつけ医との連携体制を整備し、家族が孤立しないよう支援することも重要です。
9. まとめ
褥瘡処置は、圧迫除去、適切な創傷管理、全身状態の改善を総合的に行う高度な看護技術です。予防的視点と治療的視点を統合し、患者の個別性を重視したケアが求められます。
単なる創傷処置ではなく、患者の生活の質の向上と尊厳の保持を目指し、ゴードンの機能的健康パターンやヘンダーソンの基本的欲求の視点から包括的なアプローチを実践することが重要です。
覚えるべき重要数値・基準
- 体位変換頻度:2時間毎
- 洗浄液温度:32-37℃
- 洗浄圧力:4-15psi
- 洗浄距離:8-15cm
- 側臥位角度:30度
- 車椅子圧迫除去:1時間毎
- プッシュアップ頻度:15分毎
- アルブミン目標値:3.0g/dl以上
- ステージII処置頻度:1日1回
- ステージIII-IV処置頻度:1日1-2回
実習・現場で活用できるポイント
実習では褥瘡予防の重要性を理解し、体位変換やスキンケアなどの基本技術を確実に身につけましょう。褥瘡のある患者を受け持つ際は、NPUAP分類やDESIGN-Rによる客観的評価を実践し、治癒過程を科学的に理解することが重要です。
将来的には褥瘡対策チームの一員として、多職種と連携した包括的ケアを担うことになります。Evidence-Based Practiceに基づいた最新の褥瘡ケア技術を継続的に学習し、患者中心のケアを実践する看護師を目指しましょう。褥瘡は予防可能な医療関連有害事象であることを常に意識し、質の高い看護の提供に努めてください。さい。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

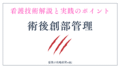
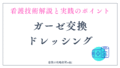
コメント