病態の概要
定義
発熱とは、体温調節中枢である視床下部の体温設定値が上昇し、通常よりも体温が高くなった状態のことですね。一般的に腋窩温で37℃以上、口腔温で37.5℃以上を発熱と定義します。単なる体温上昇ではなく、体が意図的に体温を上げている状態なのです。
原因
発熱の原因は大きく分けて感染性と非感染性に分類されます。感染性では細菌、ウイルス、真菌、寄生虫による感染が最も多く、特に細菌感染では高熱になりやすい傾向があります。非感染性では膠原病、悪性腫瘍、薬剤性、手術侵襲、脱水などがあります。臨床現場では感染症による発熱が圧倒的に多いため、まずは感染の可能性を考えることが重要でしょう。
病態生理
正常な状態
通常、私たちの体温は視床下部の体温調節中枢によって約36~37℃に維持されています。この中枢は体温設定値(セットポイント)を持ち、体温がこの設定値から外れると、発汗や血管拡張(体温を下げる)、震えや血管収縮(体温を上げる)などの反応を起こして体温を一定に保っているのです。
異常が起こる過程
発熱の引き金となるのは発熱性物質(パイロジェン)です。外因性パイロジェンとして細菌の内毒素や外毒素があり、これらが体内に侵入すると、白血球(特にマクロファージ)が刺激されます。すると白血球から内因性パイロジェン(インターロイキン-1、腫瘍壊死因子など)が放出され、これが血流に乗って視床下部に到達します。視床下部の体温調節中枢がこれらのサイトカインの影響を受けると、体温設定値が上昇し、体は新しい高い設定値に合わせて体温を上げようとするのです。
症状
現れる症状とその理由
発熱時の症状は、体温上昇期、持続期、下降期によって異なります。
体温上昇期では悪寒や震えが特徴的です。これは体温設定値が上がったのに、実際の体温がまだ低いため、体が体温を上げようとして起こる反応ですね。血管収縮により手足が冷たくなり、筋肉の震えによって熱産生を促進します。
持続期では体温が設定値に達するため、悪寒は収まり、皮膚は温かく乾燥します。この時期には頭痛、倦怠感、食欲不振、関節痛などが現れます。これらは発熱に伴う全身の代謝亢進や、炎症性サイトカインの全身への影響によるものです。
下降期では発汗が著明になります。体温設定値が正常に戻ったため、体は過剰な熱を放散しようとして血管拡張と発汗を起こすのです。この時期は脱水のリスクが高くなります。
また、発熱により代謝が亢進するため、体温1℃上昇につき約13%基礎代謝が増加し、心拍数も増加します。これにより酸素消費量や水分・電解質の需要が増大するのです。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
・体温調節障害
・脱水リスク状態
・感染リスク状態
・活動耐性低下
・栄養摂取不足
・睡眠パターン混乱
・不安
ゴードンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、患者の発熱に対する理解度と対処行動を評価することが重要です。解熱剤の適切な使用や、感染予防行動の実践状況を確認しましょう。栄養-代謝パターンでは、発熱による代謝亢進で水分・電解質バランスが崩れやすいため、摂取量と排泄量の観察、体重変化の監視が必要です。特に高齢者や小児では脱水が急速に進行する可能性があります。活動-運動パターンでは、発熱により活動耐性が低下するため、ADLの変化や倦怠感の程度を評価し、適切な安静度を設定することが大切でしょう。
ヘンダーソンのポイント
体温調節のニードが最も重要で、環境温度の調整、適切な寝具の選択、クーリングの実施などが必要です。水分・電解質バランスのニードでは、発熱による不感蒸泄の増加と発汗により水分喪失が増大するため、こまめな水分補給が欠かせません。栄養のニードでは、発熱により食欲が低下しがちですが、代謝亢進により栄養需要は増加しているため、消化の良い高カロリー食の提供を心がけましょう。休息・睡眠のニードでは、発熱による不快感で睡眠が妨げられやすいため、快適な環境づくりと症状緩和が重要です。
看護計画・介入の内容
・バイタルサインの定期的測定(体温、脈拍、血圧、呼吸)
・水分出納バランスの観察と記録
・適切な解熱対策の実施(クーリング、環境調整、薬物療法の補助)
・脱水症状の早期発見と対応
・感染源の除去と感染拡大防止策の実施
・栄養状態の維持・改善(水分・電解質補給、食事援助)
・快適な療養環境の提供
・患者・家族への教育指導(発熱時の対処法、受診のタイミング)
・原因疾患の治療への協力
・合併症予防のための観察と対応
よくある疑問・Q&A
Q: 発熱時に解熱剤はいつ使用すべきでしょうか?
A: 解熱剤の使用は体温の数値だけでなく、患者の全身状態を総合的に判断することが重要です。一般的に38.5℃以上で患者が辛そうな場合や、心疾患などで発熱による循環器への負担を避けたい場合に使用を検討します。ただし、発熱は感染に対する生体防御反応でもあるため、無理に下げる必要がない場合もあります。
Q: 悪寒がある時のケアのポイントは何ですか?
A: 悪寒は体温上昇期の症状で、体が体温を上げようとしている状態です。この時期は保温が重要で、毛布を追加したり、温かい飲み物を提供したりします。逆にクーリングは逆効果となるため避けましょう。悪寒が収まって体温が上昇してきたら、今度は放熱を促すケアに切り替えます。
Q: 発熱時の水分補給で注意すべき点は?
A: 発熱により水分喪失が増加するため、こまめな補給が必要です。ただし、一度に大量摂取すると嘔吐を誘発する可能性があるため、少量ずつ頻回に摂取することが大切です。また、発汗により電解質も失われるため、スポーツドリンクなど電解質を含む飲料も有効でしょう。
Q: 高齢者の発熱で特に注意すべきことは?
A: 高齢者は体温調節機能が低下しているため、重篤な感染症でも微熱程度しか出ないことがあります。また、脱水に陥りやすく、急速に状態が悪化する可能性があります。食欲不振や活動性の低下、意識レベルの変化なども発熱以外の重要な観察ポイントです。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
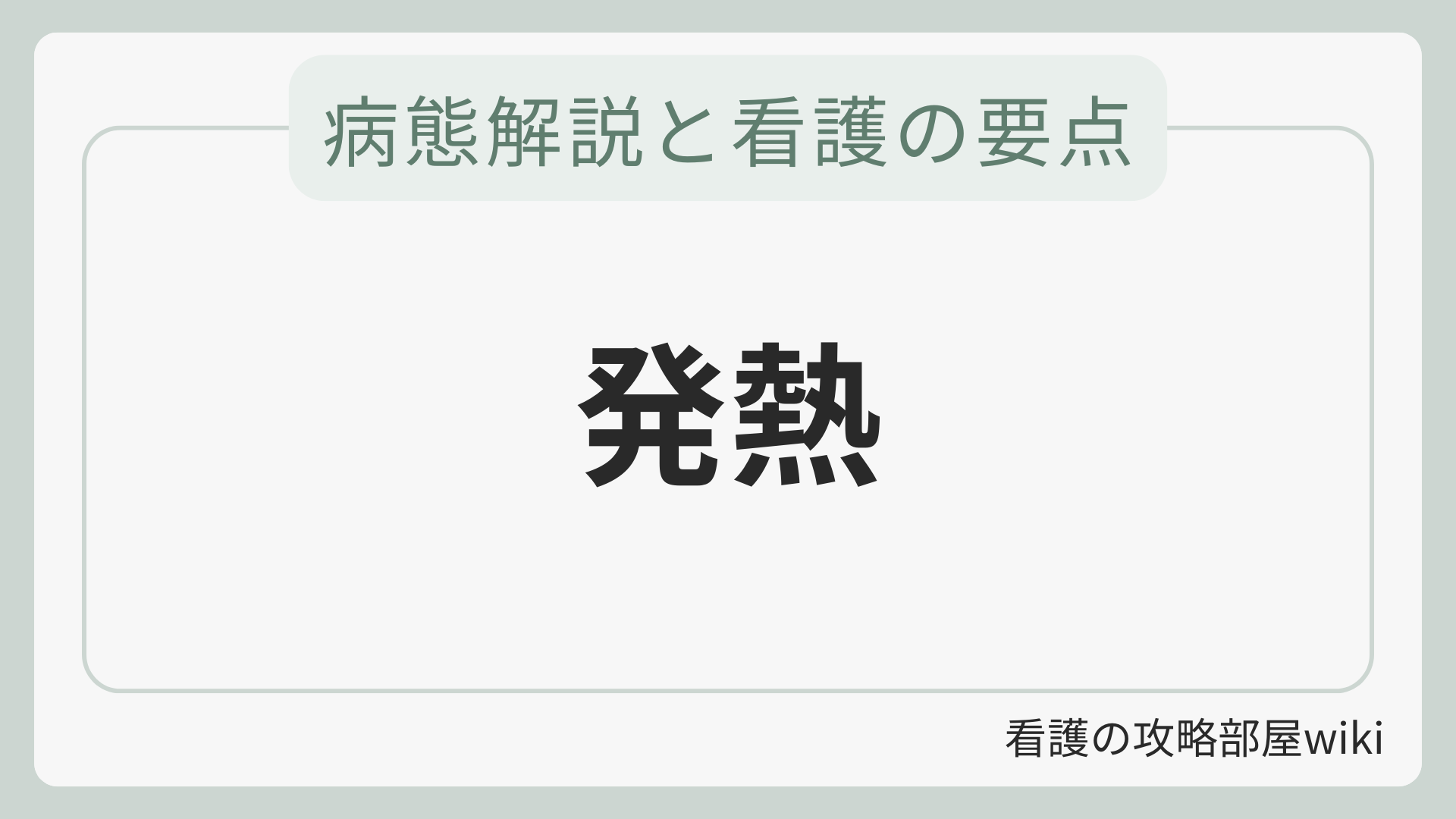
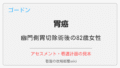
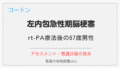
コメント