事例の要約
80代女性の幽門側胃切除術後の栄養管理に関する事例である。本事例は術後13日目に介入を開始した。
基本情報
A氏は82歳の女性で、身長152cm、体重は術前48kg、現在42kgである。家族構成は長男夫婦と同居しており、キーパーソンは長男である。職業は元小学校教員で現在は無職である。性格は几帳面で責任感が強く、他人に迷惑をかけることを嫌う傾向がある。感染症の既往はなく、薬物アレルギーも認めない。認知機能は正常で、MMSE28点と良好である。
病名
胃癌(T2N0M0 Stage IB)、幽門側胃切除術(Billroth I法再建)施行済み
既往歴と治療状況
高血圧症にて10年前よりアムロジピン5mgを内服中である。糖尿病や心疾患の既往はない。今回、健康診断での上部消化管内視鏡検査にて胃角部に2cm大の潰瘍性病変を認め、生検の結果胃癌と診断された。術前検査では遠隔転移や明らかなリンパ節転移は認めず、根治術の適応と判断され手術が施行された。
入院から現在までの情報
5月28日に入院し、5月30日に腹腔鏡下幽門側胃切除術が施行された。手術時間は3時間30分、出血量は少量であった。術後経過は良好で、術後3日目(6月2日)に飲水開始、術後5日目(6月4日)に流動食開始となった。術後7日目(6月6日)より3分粥を開始した。術後10日目頃からダンピング症候群様の症状(食後の動悸、冷汗、めまい)が出現し、栄養士による栄養指導を受けた。現在術後13日目(6月12日)で、3分粥を1日4回に分けて摂取しており、5分粥への移行を検討している段階である。
バイタルサイン
入院時は血圧138/82mmHg、脈拍78回/分・整、体温36.4℃、呼吸数18回/分、SpO2 98%(室内気)であった。現在は血圧125/75mmHg、脈拍68回/分・整、体温36.6℃、呼吸数16回/分、SpO2 99%(室内気)と安定している。
食事と嚥下状態
入院前は通常の和食中心の食事を1日3回摂取しており、嚥下機能に問題はなかった。喫煙歴はなく、飲酒も月に数回程度のビール1缶程度であった。現在は3分粥を1日4回に分けて摂取しており、1回量は茶碗3分の1程度と制限されている。嚥下機能は良好だが、食後30分程度の臥床を指導されている。ダンピング症候群対策として、少量頻回摂取と糖質制限を行っている。
排泄
入院前は1日1回の自然排便があり、便秘の既往はなかった。現在は術後の影響で2-3日に1回の排便となっており、必要時にセンノシド12mg頓用で調整している。排尿は1日6-7回と正常範囲内である。
睡眠
入院前は午後10時頃就寝、午前6時頃起床の規則正しい睡眠パターンであった。現在は入院環境の変化と手術後の不安により入眠困難を訴えることがあり、必要時にゾルピデム5mg頓用を使用している。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼鏡使用にて日常生活に支障なく、聴力も正常である。知覚異常は認めず、コミュニケーションも良好である。信仰は仏教徒である。
動作状況
歩行は自立しており、手術前と変わらず杖などの歩行補助具は不要である。移乗、排尿、排泄、入浴、衣類の着脱も自立している。転倒歴は過去5年間で認めていない。術後初期は腹痛により動作がやや緩慢になったが、現在は改善傾向にある。
内服中の薬
- アムロジピン5mg 1日1回朝食後
- センノシド12mg 頓用(便秘時)
- ゾルピデム5mg 頓用(不眠時)
- ファモチジン20mg 1日2回朝夕食後
看護師管理となっており、配薬時に服薬確認を行っている。本人の理解力は良好で、退院後は自己管理可能である。
検査データ
| 項目 | 入院時 | 最近(6月11日) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 6800 | 5200 | 3500-9000 |
| RBC | 420 | 380 | 380-500 |
| Hb | 12.8 | 10.2 | 11.5-15.0 |
| Ht | 38.5 | 31.2 | 35.0-45.0 |
| TP | 7.2 | 6.1 | 6.5-8.2 |
| Alb | 4.1 | 3.2 | 3.8-5.2 |
| T-Bil | 0.8 | 0.9 | 0.2-1.2 |
| AST | 24 | 28 | 10-35 |
| ALT | 18 | 22 | 5-40 |
| BUN | 18 | 22 | 8-22 |
| Cre | 0.7 | 0.8 | 0.4-1.1 |
| Na | 142 | 140 | 135-147 |
| K | 4.2 | 3.8 | 3.5-5.0 |
| CRP | 0.2 | 0.3 | <0.3 |
今後の治療方針と医師の指示
主治医からは術後の栄養状態改善が最優先課題とされており、段階的な食事形態のアップと摂取量の増加を図る方針である。退院は6月20日頃を予定(8日後程度)しており、外来での定期的なフォローアップを継続する。補助化学療法の適応はなく、経過観察となる。栄養士との連携により、退院後の食事指導の徹底が指示されている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「手術は成功したと聞いて安心しているが、食事が思うように食べられず体重が減ってしまって心配」と話している。また「家族に迷惑をかけたくないので、早く元の生活に戻りたい」との発言も聞かれる。長男は「母は昔から食事作りが得意で、食べることが楽しみだったので、今の状況は辛そうだ。家族としてできる限りサポートしたい」と述べており、退院後の食事管理について積極的に学習する姿勢を示している。
アセスメント
疾患の簡単な説明
A氏は胃角部に発生した2cm大の胃癌(T2N0M0 Stage IB)に対して腹腔鏡下幽門側胃切除術(Billroth I法再建)を施行された。胃癌は進行度が比較的早期であり、遠隔転移やリンパ節転移を認めない根治可能な病期である。幽門側胃切除術により胃の容量は約3分の1に減少し、胃の貯留機能と蠕動運動機能が著しく低下している。Billroth I法再建では胃と十二指腸を直接吻合するため、食物が直接十二指腸に流入しやすく、ダンピング症候群のリスクが高い術式である。
健康状態
術前の健康状態は良好で、日常生活動作は完全に自立していた。現在術後13日目で、手術創の治癒は順調であるが、術後合併症としてダンピング症候群様症状(食後の動悸、冷汗、めまい)が術後10日目から出現している。体重は術前48kgから現在42kgへと6kg(12.5%)の著明な減少を認めており、栄養状態の悪化が顕著である。血液検査では血清アルブミン値が4.1g/dlから3.2g/dlへ低下し、ヘモグロビン値も12.8g/dlから10.2g/dlへ減少しており、蛋白質・エネルギー栄養不良と軽度の貧血状態にある。82歳という高齢であることから、術後の回復には時間を要することが予想され、現在の栄養状態の改善が急務である。
受診行動、疾患や治療への理解、服薬状況
A氏は元小学校教員という職歴からも推察されるように教育水準が高く、疾患や治療に対する理解力は良好である。健康診断での上部消化管内視鏡検査により胃癌が発見されており、定期的な健康管理への意識は高い。現在の服薬状況は看護師管理下で適切に行われており、配薬時の服薬確認も確実に実施されている。本人の理解力が良好であることから退院後の自己管理は可能と判断されるが、新たに導入される術後の食事管理や症状観察について、十分な指導と理解の確認が必要である。几帳面で責任感が強い性格特性は服薬アドヒアランスの向上に寄与する一方で、過度な自己管理への負担感を生じる可能性もある。
身長、体重、BMI、運動習慣
身長152cm、術前体重48kg、現在体重42kgで、術前BMIは20.8kg/m²、現在BMIは18.2kg/m²である。術前BMIは正常範囲内であったが、現在は低体重に分類される状態まで低下している。高齢者における急激な体重減少は筋肉量の減少(サルコペニア)を招きやすく、身体機能の低下や転倒リスクの増加につながる可能性がある。運動習慣については具体的な情報が不足しており、術前の活動レベルや日常的な運動実施状況について詳細な情報収集が必要である。現在は歩行自立しており転倒歴もないが、栄養状態の悪化と体重減少により筋力低下のリスクが高まっている。
呼吸に関するアレルギー、飲酒、喫煙の有無
薬物アレルギーは認めず、呼吸器系のアレルギー反応の既往もない。喫煙歴はなく、飲酒も月に数回程度のビール1缶程度と極めて節制された生活習慣を維持していた。これらの良好な生活習慣は術後の創傷治癒や呼吸器合併症の予防に寄与している。高齢者では術後の呼吸器合併症のリスクが高いが、非喫煙者であることは予後改善因子として評価できる。アルコール摂取量も適量範囲内であり、肝機能への影響や術後の栄養吸収に対する悪影響は最小限と考えられる。
既往歴
高血圧症の既往があり、10年前からアムロジピン5mgで良好にコントロールされている。現在の血圧も125/75mmHgと安定しており、術後も血圧管理は良好である。糖尿病や心疾患の既往がないことは、術後の創傷治癒や感染リスクの観点から有利な条件である。82歳という年齢を考慮すると比較的既往歴が少なく、全身状態は良好であったと評価できる。ただし、高齢者では潜在的な心血管疾患や腎機能低下の可能性もあるため、継続的な全身状態の観察が重要である。
健康管理上の課題と看護介入
最も重要な課題は術後の栄養状態改善とダンピング症候群への対応である。現在の著明な体重減少と血清アルブミン値の低下は、創傷治癒の遅延、感染リスクの増加、筋力低下を招く可能性がある。ダンピング症候群様症状により食事摂取が制限されているため、少量頻回摂取の指導と症状観察を継続する必要がある。栄養士との連携による個別化された食事指導を実施し、患者と家族の両方に対して術後の食事管理方法について包括的な教育を提供することが重要である。また、几帳面な性格を活かして食事記録や症状記録の習慣化を図り、自己管理能力の向上を支援する必要がある。高齢者であることを考慮し、定期的な体重測定と血液検査による栄養状態のモニタリングを継続し、必要に応じて栄養補助食品の導入も検討する。退院後も外来での継続的なフォローアップを通じて、栄養状態の改善と生活の質の向上を目指した長期的な支援が必要である。
食事と水分の摂取量と摂取方法
A氏は現在術後13日目で、3分粥を1日4回に分けて摂取している。1回量は茶碗3分の1程度と著しく制限されており、総摂取量は必要量を大幅に下回っている状態である。術後10日目から出現したダンピング症候群様症状により、食後30分程度の臥床が必要となり、食事摂取に対する心理的負担も増加している。水分摂取については具体的な摂取量の記録が不足しており、詳細な摂取量の把握が必要である。現在は少量頻回摂取と糖質制限を基本とした食事療法が実施されているが、胃切除後の生理学的変化により従来の食事パターンの大幅な変更が余儀なくされている。嚥下機能は良好であるものの、食事に対する恐怖感や不安感が摂取量のさらなる制限要因となっている可能性がある。
好きな食べ物と食事に関するアレルギー
入院前は和食中心の食事を好んでいたことが確認されており、日本の伝統的な食文化に親しんできた背景がある。食事に関するアレルギーは認めず、薬物アレルギーの既往もないため、食品選択における制限は少ない。しかし、現在は術後の消化機能の変化により、以前好んでいた食品の多くが摂取困難となっている。特に繊維質の多い野菜類や脂肪分の多い食品、刺激の強い調味料などは当面摂取が制限される。食事が生活の楽しみであったという家族の証言からも、現在の食事制限が心理的苦痛の一因となっていることが推察される。
身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
身長152cm、術前体重48kg(BMI 20.8kg/m²)から現在体重42kg(BMI 18.2kg/m²)へと6kg(12.5%)の著明な減少を認めている。82歳女性の標準的な必要エネルギー量は約1400-1500kcal/日であるが、現在の摂取量はこれを大幅に下回っていると推定される。身体活動レベルは術前は自立していたが、現在は入院により活動量が制限されている。高齢者における急激な体重減少は筋肉量の減少を招きやすく、サルコペニアのリスクが高い状態である。必要蛋白質量は約1.0-1.2g/kg体重/日であり、現在の体重42kgでは42-50g/日が必要となるが、現在の摂取量では不足している可能性が高い。
食欲・嚥下機能・口腔内の状態
嚥下機能は良好で、誤嚥のリスクは低い状態である。しかし、食欲は術後の影響とダンピング症候群様症状により著しく低下している。食後の不快症状(動悸、冷汗、めまい)により食事に対する恐怖感が生じており、心理的要因も食欲低下に影響している。口腔内の状態については具体的な情報が不足しており、歯科的問題の有無、口腔乾燥の程度、舌苔の状況などについて詳細な評価が必要である。高齢者では口腔機能の低下や義歯の適合不良などが食事摂取に影響する可能性があるため、継続的な観察が重要である。
嘔吐・吐気
現在のところ明らかな嘔吐や吐気の症状は記録されていないが、ダンピング症候群の症状として食後の動悸、冷汗、めまいが出現している。これらの症状は早期ダンピング症候群の典型的な症状であり、食物が急速に小腸に移行することによる血管内容量の変化や血糖値の急激な変動が原因と考えられる。今後、食事形態の変更や摂取量の増加に伴い、晩期ダンピング症候群による低血糖症状や消化器症状が出現する可能性もあるため、継続的な症状観察が必要である。
皮膚の状態、褥創の有無
皮膚の状態について具体的な記録は不足しているが、血清アルブミン値の低下(4.1→3.2g/dl)と体重減少により、皮膚の弾力性低下や創傷治癒の遅延リスクが高い状態である。現在は歩行自立しており褥創の発生リスクは低いが、栄養状態の悪化により皮膚の脆弱性が増している可能性がある。手術創の治癒は順調とされているが、蛋白質不足により今後の創傷治癒に影響が生じる可能性もある。皮膚の色調、弾力性、浮腫の有無などについて定期的な観察と記録が必要である。
血液データ
血清アルブミン値は4.1g/dlから3.2g/dlへ著明に低下し、軽度から中等度の蛋白質栄養不良状態を示している。総蛋白も7.2g/dlから6.1g/dlへ低下している。赤血球数は420万/μlから380万/μlへ、ヘモグロビン値は12.8g/dlから10.2g/dlへ、ヘマトクリット値は38.5%から31.2%へと軽度の貧血状態を呈している。電解質では Na 140mEq/l、K 3.8mEq/lと正常範囲内であるが、Kはやや低値傾向である。その他の栄養関連指標である中性脂肪、総コレステロール、HbA1c、血糖値についてのデータが不足しており、包括的な栄養評価のための追加検査が必要である。
栄養管理上の課題と看護介入
最重要課題は術後の栄養不良状態の改善とダンピング症候群への適応である。現在の著明な体重減少と血清アルブミン値の低下は、免疫機能の低下、創傷治癒の遅延、筋力低下を招く可能性がある。栄養士との密接な連携により、個別化された栄養計画を立案し、段階的な食事形態の向上と摂取量の増加を図る必要がある。ダンピング症候群に対しては、少量頻回摂取、糖質制限、食後の安静などの指導を継続し、症状の軽減を図る。食事記録の徹底と体重の定期的測定により栄養状態の変化を客観的に評価し、必要に応じて栄養補助食品の導入も検討する。退院後の在宅での食事管理について、本人と家族に対する包括的な教育を実施し、長期的な栄養状態の改善を目指す。継続的な血液検査による栄養指標のモニタリングを行い、栄養状態の改善効果を定期的に評価する必要がある。
排便と排尿の回数と量と性状
A氏の排便パターンは術前の1日1回の自然排便から、現在は2-3日に1回の排便へと変化している。これは術後の消化管運動の低下、食事摂取量の減少、身体活動量の制限が複合的に影響した結果と考えられる。排便の性状についての詳細な記録が不足しており、便の硬さ、色調、量について継続的な観察と記録が必要である。排尿については1日6-7回と正常範囲内を維持しており、術後の水分バランスや腎機能には大きな問題がないと評価される。しかし、具体的な1回尿量や総尿量についての記録が不足しており、水分摂取量との関連でより詳細な評価が必要である。高齢者では膀胱機能の加齢変化により頻尿傾向となることが多いが、現在の排尿回数は年齢相応の範囲内と考えられる。
下剤使用の有無
現在、便秘時にセンノシド12mgを頓用で使用している。センノシドは刺激性下剤であり、大腸の蠕動運動を促進させる作用がある。術後の排便パターンの変化に対する適切な対応として処方されているが、長期使用による耐性や依存性のリスクもあるため、使用頻度と効果の評価が重要である。理想的には食事内容の改善、水分摂取量の増加、適度な運動により自然排便を促すことが望ましく、薬物に頼らない排便コントロールの確立が長期的な目標となる。現在の使用状況や効果について詳細な記録と評価が必要である。
水分出納バランス
具体的な水分摂取量と尿量の詳細な記録が不足しており、正確な水分出納バランスの評価が困難な状況である。現在の血液検査では血清ナトリウム値140mEq/l、カリウム値3.8mEq/lと電解質バランスは保たれているが、カリウム値はやや低値傾向である。術後の食事摂取量減少により水分摂取量も制限されている可能性があり、脱水のリスクが存在する。高齢者では口渇感の低下により水分摂取が不足しやすく、腎機能の加齢変化により水分調節機能も低下している。24時間の水分摂取量と尿量の正確な測定と記録が必要であり、適切な水分管理の指標とする必要がある。
排泄に関連した食事・水分摂取状況
現在の食事摂取量の著明な減少は排便に直接的な影響を与えている。食物繊維の摂取量が不足しており、便の形成や腸管運動の促進に必要な栄養素が不足している状態である。3分粥中心の食事では食物繊維や脂質の摂取が限定的であり、便秘の一因となっている。水分摂取量についても具体的な記録が不足しているが、食事摂取量の減少に伴い水分摂取量も不足している可能性が高い。今後の食事形態の向上に伴い、適切な食物繊維と水分の摂取により排便パターンの改善が期待される。排泄に有効な食品(プルーン、ヨーグルトなど)の導入についても検討が必要である。
安静度・バルーンカテーテルの有無
現在は歩行自立しており、移動や移乗についても自立している。バルーンカテーテルの挿入はなく、自然排尿が維持されていることは良好な状態である。しかし、術後初期は腹痛により動作がやや緩慢になったとの記録があり、身体活動量の一時的な低下が排便に影響した可能性がある。現在は改善傾向にあるが、入院環境による活動制限や心理的要因により、術前と比較して活動量が低下している可能性もある。適度な運動や歩行は腸管運動の促進に有効であるため、安全な範囲での活動量増加の支援が重要である。
腹部膨満・腸蠕動音
腹部膨満や腸蠕動音についての具体的な記録が不足しており、定期的な腹部理学的所見の評価が必要である。幽門側胃切除術後では消化管運動の変化が生じやすく、腹部膨満感や早期満腹感が出現する可能性がある。また、ダンピング症候群の症状として腹部症状が出現することもあるため、食事との関連性を含めた詳細な観察が重要である。腸蠕動音の聴取により消化管運動の状態を評価し、便秘の原因究明や治療効果の判定に活用する必要がある。食前後の腹部症状の変化についても継続的な観察が必要である。
血液データ(BUN、Cr、推算糸球体濾過量)
血中尿素窒素は18mg/dlから22mg/dlへ軽度上昇し、血清クレアチニン値は0.7mg/dlから0.8mg/dlへ軽度上昇している。これらの値は正常範囲内ではあるが上昇傾向を示しており、軽度の脱水や腎機能への影響が示唆される。82歳という年齢を考慮すると、推算糸球体濾過量は軽度低下している可能性がある。術後の食事摂取量減少による蛋白質摂取不足により血中尿素窒素の低下が予想されるが、実際には上昇しており、脱水や筋肉量減少の影響が考えられる。継続的な腎機能の監視と水分管理の適正化が必要である。
排泄管理上の課題と看護介入
主要な課題は術後の便秘と水分出納バランスの管理である。現在の排便パターンの変化は術後の生理学的変化、食事摂取量の減少、活動量の低下が複合的に影響した結果である。便秘の改善には、食事内容の段階的な改善、適切な水分摂取量の確保、安全な範囲での活動量増加が重要である。センノシドの使用については効果と副作用を評価し、自然排便の促進を目指した総合的なアプローチを実施する。24時間の正確な水分出納記録の実施により、適切な水分管理を行い、脱水の予防と腎機能の保護を図る。腹部理学的所見の定期的な評価により、消化管機能の変化を早期に発見し、適切な対応を行う。退院後の排泄管理について、本人と家族に対する教育を実施し、在宅での適切な排泄パターンの確立を支援する。継続的な血液検査により腎機能の変化を監視し、必要に応じて医師との連携により治療方針の調整を行う必要がある。
日常生活動作の状況、運動機能、運動歴、安静度、移動・移乗方法
A氏は現在歩行、移乗、排尿、排泄、入浴、衣類の着脱すべてにおいて自立を維持している。手術前と変わらず杖などの歩行補助具は不要であり、基本的な身体機能は良好に保たれている。術後初期は腹痛により動作がやや緩慢になったが、現在は改善傾向にあり、日常生活動作への大きな支障は認めていない。しかし、6kg(12.5%)の体重減少と血清アルブミン値の低下により、筋力低下のリスクが高まっている状態である。82歳という年齢と術後の栄養状態悪化により、今後サルコペニアの進行が懸念される。具体的な運動歴や日常的な活動量についての詳細な情報が不足しており、術前の活動レベルや運動習慣について追加の情報収集が必要である。現在の安静度は特に制限されていないが、入院環境により活動量が制限されている可能性がある。
バイタルサイン、呼吸機能
現在のバイタルサインは血圧125/75mmHg、脈拍68回/分・整、体温36.6℃、呼吸数16回/分、酸素飽和度99%(室内気)と安定した状態を維持している。入院時と比較して血圧は138/82mmHgから125/75mmHgへ低下し、脈拍も78回/分から68回/分へ減少している。これは手術侵襲からの回復と安静による影響と考えられるが、栄養状態の悪化による心拍出量の低下も考慮する必要がある。呼吸機能については具体的な評価データが不足しているが、酸素飽和度が良好であることから重篤な呼吸器合併症は認めていない。非喫煙者であることは術後の呼吸器合併症予防に有利な条件である。運動負荷時の循環動態の変化や呼吸機能の詳細な評価が必要である。
職業、住居環境
A氏は元小学校教員で現在は無職である。教員という職業は比較的活動的な職業であり、長期間にわたり一定の身体活動を維持していたと推測される。現在は長男夫婦と同居しており、家族のサポートが得られる環境にある。住居環境の詳細(階段の有無、バリアフリー対応状況、居室の配置など)についての情報が不足しており、退院後の安全な生活環境の評価が必要である。特に体重減少と筋力低下が予想される状況では、住環境の安全性確保が重要となる。家事動作や日常的な活動レベルについても詳細な情報収集が必要である。
血液データ(RBC、Hb、Ht、CRP)
赤血球数は420万/μlから380万/μl、ヘモグロビン値は12.8g/dlから10.2g/dl、ヘマトクリット値は38.5%から31.2%へと軽度の貧血状態を呈している。この貧血は術後の栄養状態悪化と鉄分摂取不足が主要因と考えられ、運動耐容能の低下や易疲労性の原因となっている可能性がある。炎症反応指標である血清CRP値は0.2mg/dlから0.3mg/dlと正常範囲内で安定しており、感染や炎症の兆候は認めていない。貧血の改善には鉄分を含む食品の摂取増加や、必要に応じて鉄剤の投与も検討が必要である。継続的な血液検査による貧血の経過観察が重要である。
転倒転落のリスク
A氏は過去5年間で転倒歴を認めておらず、現在も歩行は自立している。しかし、複数のリスク因子の存在により転倒リスクが増加している状況である。主要なリスク因子として、82歳という高齢、6kgの体重減少による筋力低下、軽度貧血による易疲労性、入院環境による活動量低下、ダンピング症候群による食後の血圧変動や低血糖様症状が挙げられる。特に食後のめまいや冷汗などの症状は転倒の直接的なリスクとなる。また、夜間の睡眠障害により睡眠導入剤を使用していることも、夜間の転倒リスクを高める要因となる。継続的な転倒リスクアセスメントと予防対策の実施が必要である。
活動・運動管理上の課題と看護介入
最重要課題は栄養状態悪化による筋力低下の予防と運動耐容能の維持である。現在の著明な体重減少と貧血により、今後さらなる身体機能の低下が懸念される。安全な範囲での段階的な活動量増加を図り、筋力維持・向上のための運動プログラムの導入が必要である。理学療法士との連携により、個別化された運動療法を実施し、サルコペニアの予防と身体機能の維持を図る。ダンピング症候群による症状が運動に与える影響を評価し、食事と運動のタイミングを適切に調整する。転倒予防対策として、環境整備、適切な履物の選択、夜間の照明確保などを実施する。バイタルサインの安定性を継続的に監視し、運動負荷による循環動態への影響を評価する。退院後の在宅での活動レベル維持について、本人と家族に対する指導を実施し、適切な運動習慣の確立を支援する。貧血の改善により運動耐容能の向上を図り、長期的な身体機能の維持を目指した包括的なアプローチが必要である。継続的な身体機能評価により、介入効果を客観的に評価し、必要に応じてプログラムの修正を行う。
睡眠時間、熟眠感、睡眠導入剤使用の有無
A氏は入院前、午後10時頃就寝、午前6時頃起床という規則正しい睡眠パターンを維持していた。8時間程度の睡眠時間は高齢者としては良好な睡眠習慣であったと評価される。しかし現在は入院環境の変化と手術後の不安により入眠困難を訴えることがあり、従来の睡眠パターンが大きく変化している。必要時にゾルピデム5mgを頓用で使用しており、薬物による睡眠導入を要する状況となっている。ゾルピデムは短時間作用型の睡眠導入剤であり、依存性や翌日への持ち越し効果のリスクは比較的低いが、高齢者では転倒リスクの増加や認知機能への影響も考慮する必要がある。使用頻度と効果、副作用の評価が重要である。熟眠感についての具体的な評価が不足しており、睡眠の質についてより詳細な情報収集が必要である。
日中・休日の過ごし方
入院前の日中や休日の過ごし方について具体的な情報が不足している。元小学校教員という職歴から、退職後も規則正しい生活リズムを維持していた可能性が高い。几帳面で責任感が強い性格からも、計画的で活動的な日常を送っていたと推測される。現在は入院により活動が大幅に制限されており、ベッド上で過ごす時間が増加している。日中の活動量不足は夜間の睡眠の質に影響する可能性があり、睡眠障害の一因となっている可能性がある。入院前の具体的な活動内容、趣味、社交活動について詳細な情報収集が必要である。また、現在の入院中の日中の過ごし方についても評価し、適切な活動プログラムの提供を検討する必要がある。
睡眠・休息管理上の課題と看護介入
主要な課題は入院環境適応困難による睡眠障害と薬物依存のリスクである。入院という環境変化、手術に対する不安、ダンピング症候群による身体症状、栄養状態の悪化などが複合的に睡眠の質に影響している。睡眠導入剤の使用は一時的な対症療法として有効だが、長期使用による依存性や副作用のリスクがあるため、非薬物的介入による睡眠の質改善を優先的に検討する必要がある。具体的な介入として、就寝前のリラクゼーション技法の指導、室内環境の調整(照明、温度、騒音の管理)、日中の適度な活動促進による睡眠・覚醒リズムの調整が重要である。また、食事と睡眠の関係についても検討し、ダンピング症候群の症状が睡眠に与える影響を最小限に抑える工夫が必要である。睡眠日誌の記録により睡眠パターンの客観的評価を行い、個別化された睡眠ケアプランを作成する。退院後の在宅での睡眠環境整備について、本人と家族に対する指導を実施し、薬物に依存しない良質な睡眠の確保を目指す。継続的な睡眠状況の評価により、介入効果を評価し、必要に応じて睡眠導入剤の減量・中止を検討する。心理的不安に対するサポートも並行して実施し、総合的な睡眠の質向上を図る必要がある。
意識レベル、認知機能
A氏の意識レベルは清明で、認知機能検査(MMSE)では28点と良好な結果を示している。30点満点中28点は軽度認知障害の疑いも認めない正常範囲であり、82歳という年齢を考慮すると非常に良好な認知機能を保持している。元小学校教員という職歴からも高い知的水準を維持しており、疾患や治療に対する理解力も優れている。手術侵襲や麻酔による一時的な認知機能への影響も認めず、術後せん妄の発症もなく経過している。しかし、入院環境の変化や身体的ストレスが認知機能に与える潜在的影響について継続的な観察が必要である。高齢者では急性疾患や環境変化により認知機能が変動しやすいため、定期的な評価と記録が重要である。
聴力、視力
視力については老眼鏡使用により日常生活に支障がない状態を維持している。これは年齢相応の生理的変化であり、適切な視力補正により機能が保たれている。聴力も正常であり、コミュニケーションに支障は認めていない。しかし、高齢者では感覚器機能の加齢変化が進行しやすく、特に入院中は環境の変化により感覚刺激が制限される可能性がある。視力・聴力の詳細な評価と継続的な観察が必要であり、必要に応じて眼科・耳鼻科的な専門的評価も検討する。また、術後の栄養状態悪化が感覚器機能に与える影響についても注意深く観察する必要がある。
認知機能
MMSE28点という結果は優秀な認知機能を示しており、記憶力、注意力、言語機能、空間認知能力などが良好に保たれている。疾患や治療に対する理解も良好で、医療スタッフとの意思疎通も円滑に行われている。几帳面で責任感が強い性格特性と相まって、治療への協力的な態度を示している。しかし、術後の栄養状態悪化、睡眠障害、心理的ストレスなどが認知機能に与える影響について継続的な評価が必要である。特に高齢者では、身体的ストレスや環境変化により認知機能が一時的に低下することがあるため、定期的な認知機能評価の実施が重要である。
不安の有無、表情
A氏は「手術は成功したと聞いて安心している」と述べる一方で、「食事が思うように食べられず体重が減ってしまって心配」「家族に迷惑をかけたくない」といった発言から、術後の身体状況と将来への不安を抱えていることが明らかである。表情についての詳細な記録は不足しているが、発言内容から心理的負担を感じている状況が推察される。特に食事摂取困難とダンピング症候群の症状により、日常生活の基本的な機能に対する不安が強いと考えられる。几帳面で他人に迷惑をかけることを嫌う性格特性により、家族への負担を懸念する気持ちも強い。継続的な心理状態の観察と適切な精神的サポートが必要である。
認知・知覚管理上の課題と看護介入
主要な課題は良好な認知機能の維持と心理的不安への対応である。現在の優秀な認知機能は治療への協力や自己管理能力の向上に有利な条件であるが、術後の身体的変化や栄養状態の悪化により今後影響を受ける可能性がある。定期的な認知機能評価により変化を早期に発見し、必要に応じて介入を行う。心理的不安に対しては、十分な情報提供と説明により不安の軽減を図り、術後の回復過程や食事管理について具体的で理解しやすい説明を提供する。几帳面な性格を活かして、食事記録や症状記録の習慣化により自己管理能力の向上を支援する。家族への負担に対する不安については、家族との十分な話し合いの機会を設け、サポート体制の確認と調整を行う。感覚器機能の維持のため、適切な環境調整と刺激の提供を行い、認知機能の活性化を図る活動プログラムの導入も検討する。退院後の在宅での認知機能維持について、本人と家族に対する指導を実施し、継続的な知的活動の促進を支援する。継続的な心理状態の評価により、必要に応じて専門的な心理的サポートの導入も検討する必要がある。
性格
A氏は几帳面で責任感が強く、他人に迷惑をかけることを嫌う性格特性を有している。これらの特性は元小学校教員という職業からも培われたものと推察され、規律正しい生活習慣や高い自己管理能力の基盤となっている。「家族に迷惑をかけたくないので、早く元の生活に戻りたい」という発言からも、他者への配慮を優先する傾向が強いことが明らかである。この性格特性は治療への協力的態度や服薬アドヒアランスの向上に寄与する一方で、過度な自己責任感や完璧主義的傾向により心理的負担を増加させる可能性もある。几帳面な性格により現在の身体状況の変化に対する戸惑いや焦燥感を感じている可能性があり、適切な心理的サポートが必要である。
ボディイメージ
術前48kgから現在42kgへの6kg(12.5%)の著明な体重減少により、ボディイメージに大きな変化が生じている。「食事が思うように食べられず体重が減ってしまって心配」という発言から、現在の身体状況に対する困惑と不安を抱えていることが明らかである。幽門側胃切除術により胃の機能が大幅に変化し、従来の食事パターンが維持できないことは、食事に対する自信や身体的自立感の低下をもたらしている。家族からの「食事作りが得意で、食べることが楽しみだった」という証言からも、食事と密接に結びついたボディイメージの変化が心理的影響を与えていると考えられる。高齢女性にとって急激な体重減少は外見上の変化も伴い、自己認識に影響を与える可能性がある。
疾患に対する認識
A氏は「手術は成功したと聞いて安心している」と述べており、手術の成功に対しては肯定的な認識を示している。元教員という職歴からも推察される高い教育水準と良好な認知機能により、疾患や治療に対する理解は適切である。しかし、術後のダンピング症候群や食事制限などの現実的な問題に直面し、予想以上の困難さに戸惑いを感じている状況が推察される。根治的手術が完了したという安心感と、現在の身体症状や生活制限に対する不安が混在している状態である。疾患の予後や今後の生活に対する具体的な見通しについて、さらなる情報提供と説明が必要である。
自尊感情
几帳面で責任感が強い性格特性と元小学校教員という職歴から、高い自尊感情を維持してきたと推測される。しかし、現在の身体機能の変化や食事摂取困難により、従来の自立性や有能感が脅かされている状況である。「家族に迷惑をかけたくない」という発言は、他者への依存に対する抵抗感を示しており、自立性の維持への強い願望を表している。体重減少や食事制限により、以前の健康な自分との差異を感じ、自己効力感の低下を経験している可能性がある。長年培ってきた自己のアイデンティティと現在の状況との間にギャップを感じており、適応過程における心理的支援が必要である。
育った文化や周囲の期待
元小学校教員という職業から、教育に対する価値観や社会的責任感を重視する文化背景を有していると推測される。また、日本の伝統的な家族観により、家族に負担をかけることに対する強い抵抗感を示している。「和食中心の食事」という生活様式からも、日本の伝統的な食文化に深く根ざした生活を送ってきたことが明らかである。高齢女性として、家族の世話をする立場から世話をされる立場への変化に対する複雑な感情を抱いている可能性がある。文化的背景を尊重した個別的なケアアプローチが必要である。
自己知覚・自己概念管理上の課題と看護介入
主要な課題は身体状況の変化に伴う自己概念の再構築と自尊感情の維持である。急激な体重減少と食事機能の変化により、従来の自己イメージとの乖離が生じており、新しい身体状況への適応支援が必要である。几帳面な性格特性を活かして、段階的な目標設定により自己効力感の回復を図る。食事記録や体重測定などの自己管理活動を通じて、主体的な治療参加による有能感の向上を支援する。家族への依存に対する抵抗感については、相互支援の概念を説明し、受援力の向上を図る。身体状況の改善見込みについて具体的な情報提供を行い、希望的な将来展望の構築を支援する。文化的背景を尊重した個別的なアプローチにより、尊厳を保持したケアを提供する。退院後の生活再構築について、本人の価値観や優先順位を尊重した計画立案を支援し、新しい生活様式への適応を促進する。継続的な心理状態の評価により、自己概念の変化を把握し、必要に応じて専門的な心理的サポートの導入も検討する必要がある。
職業、社会役割
A氏は元小学校教員で現在は無職である。長年にわたり教育者として社会的責任を担ってきた経歴は、高い社会的地位と尊敬を得る職業であり、強い職業的アイデンティティを形成してきたと推測される。教員という職業は他者への指導や支援を中心とした役割であり、几帳面で責任感が強い性格特性もこの職業経験から培われたものと考えられる。現在は退職により直接的な社会的役割は終了しているが、元教員としての知識や経験は家族や地域社会での役割継続の基盤となっている可能性がある。職業的アイデンティティの喪失感や社会的役割の変化が現在の心理状態に与える影響について評価が必要である。また、病気療養により一時的に社会参加が制限されることへの適応も課題となる。
家族の面会状況、キーパーソン
A氏は長男夫婦と同居しており、キーパーソンは長男である。長男は「母は昔から食事作りが得意で、食べることが楽しみだったので、今の状況は辛そうだ。家族としてできる限りサポートしたい」と述べており、家族の理解と協力的な姿勢が確認されている。また、退院後の食事管理について積極的に学習する姿勢を示しており、家族のサポート体制は良好である。しかし、具体的な面会頻度や他の家族成員(長男の配偶者等)の関与状況についての詳細な情報が不足している。家族全体のサポート体制と役割分担について詳細な評価が必要である。A氏の「家族に迷惑をかけたくない」という発言と家族の支援意欲との間で、適切なバランスを見つけることが重要である。
経済状況
経済状況についての具体的な情報は提供されていない。元小学校教員であることから、一定の年金収入が見込まれると推測されるが、詳細な評価が必要である。長男夫婦との同居により住居費等の負担軽減が図られている可能性があるが、医療費や介護費用に対する経済的負担の程度は不明である。今後の治療継続や栄養補助食品の導入、在宅でのサポートサービス利用などを検討する際に、経済的側面の評価は重要な要素となる。また、経済的不安が治療への影響や家族関係に与える影響についても考慮する必要がある。
役割・関係管理上の課題と看護介入
主要な課題は家族への依存に対する心理的抵抗感の軽減と適切な家族関係の構築である。A氏の「迷惑をかけたくない」という気持ちと家族の「サポートしたい」という意向を調整し、相互に満足できる関係性の確立が重要である。家族に対しては、A氏の心理的特性を理解してもらい、自立性を尊重した支援方法について具体的な指導を行う。A氏に対しては、家族からの支援を受け入れることの意義と、相互支援の概念について説明し、受援力の向上を図る。退院後の役割分担について、A氏ができること、家族が支援すること、専門職が関与することを明確に整理し、段階的な自立支援計画を作成する。社会的役割の再構築については、元教員としての経験を活かした新しい役割の可能性について検討し、生きがいの維持を支援する。経済状況については詳細な評価を行い、必要に応じて医療ソーシャルワーカーとの連携により経済的支援制度の活用を検討する。家族全体のサポート体制について包括的な評価を行い、持続可能な支援体制の構築を目指す。継続的な家族関係の評価により、関係性の変化を把握し、必要に応じて調整を行う必要がある。
年齢、家族構成、更年期症状の有無
A氏は82歳の女性であり、生殖可能年齢をはるかに超えた高齢期にある。長男夫婦と同居という家族構成から、過去に出産経験があることが推測される。この年齢では更年期は既に終了しており、現在は閉経後の生理的変化が完了した状態である。更年期症状については現在は該当しないが、過去の更年期経験が現在の健康状態や心理状態に与える影響について考慮する必要がある。高齢女性特有の身体的変化として、エストロゲン欠乏による骨密度低下、皮膚の萎縮、泌尿生殖器系の萎縮性変化などが生じている可能性があり、これらが現在の健康状態や生活の質に影響を与えている可能性がある。具体的な婦人科的既往歴や出産歴についての詳細な情報が不足しており、包括的な評価のための情報収集が必要である。
性・生殖管理上の課題と看護介入
82歳という年齢を考慮すると、性機能や生殖機能に関する直接的な課題は限定的である。しかし、高齢女性特有の身体的変化が現在の健康問題に与える影響について評価が必要である。特に、現在の栄養状態悪化や体重減少が、既存の骨密度低下や筋肉量減少をさらに促進する可能性がある。泌尿生殖器系の萎縮性変化により尿路感染症のリスクが高くなることもあり、適切な衛生管理の指導が重要である。また、女性としてのアイデンティティや尊厳の維持についても配慮が必要であり、プライバシーの保護と個人の尊厳を尊重したケアの提供が重要である。家族関係における女性としての役割の変化についても考慮し、心理的適応を支援する。必要に応じて婦人科的評価を検討し、高齢女性特有の健康問題に対する適切な医学的管理を実施する。継続的な全身状態の観察により、性・生殖に関連した健康問題の早期発見と対応を行う必要がある。
入院環境
A氏は5月28日から入院しており、現在術後13日目で約2週間の入院生活を経験している。入院前は長男夫婦との同居による慣れ親しんだ家庭環境で生活していたが、病院という制約の多い環境への適応が必要となっている。「入院環境の変化と手術後の不安により入眠困難を訴える」との記録から、環境変化が心理的ストレスの主要因となっていることが明らかである。病院の規則的なスケジュール、プライバシーの制限、騒音、照明などの物理的環境要因に加え、他患者との共同生活や医療スタッフとの頻繁な接触など、社会的環境の変化も適応を困難にしている可能性がある。几帳面な性格により、慣れない環境での生活リズムの乱れに対してより強いストレスを感じている可能性がある。
仕事や生活でのストレス状況、ストレス発散方法
現在は無職であり、退職により職業的ストレスは解消されている状況である。しかし、元小学校教員という責任の重い職業を長年続けていた経験から、規則正しい生活や責任感の強い行動パターンが身についており、現在の病気による制約や依存状況が新たなストレス源となっている可能性がある。「家族に迷惑をかけたくない」「早く元の生活に戻りたい」という発言から、現在の状況に対する焦燥感や無力感がストレス要因となっていることが推察される。従来のストレス発散方法についての具体的な情報が不足しており、読書、園芸、料理、社交活動など、どのような活動により心理的安定を図っていたかの評価が必要である。現在は入院により従来のストレス発散方法が制限されている可能性が高い。
家族のサポート状況、生活の支えとなるもの
長男は「家族としてできる限りサポートしたい」と述べており、積極的で協力的な家族サポートが確認されている。退院後の食事管理について学習意欲を示していることからも、継続的な支援体制が期待できる。長男夫婦との同居により、物理的・精神的サポートが得られる環境にあることは、ストレス軽減の重要な要因である。しかし、A氏自身が「迷惑をかけたくない」と感じていることから、家族のサポートを受け入れることに対する心理的負担も存在している。生活の支えとなるものについて具体的な情報が不足しており、信仰(仏教徒)、友人関係、趣味、生きがいなどについて詳細な評価が必要である。元教員としての社会的貢献への思いや、教え子との関係などが心理的支えとなっている可能性もある。
コーピング・ストレス耐性管理上の課題と看護介入
主要な課題は入院環境への適応困難と従来のコーピング戦略の使用制限である。現在の睡眠障害や心理的不安は、環境変化に対する適応反応と捉えることができ、適切なコーピング戦略の再構築が必要である。几帳面で責任感が強い性格特性を活かし、構造化された問題解決アプローチを用いてストレス管理を支援する。具体的には、現在の状況を客観的に整理し、解決可能な問題と受容すべき事実を明確に分ける認知的コーピングの指導を行う。入院環境のストレス軽減のため、可能な範囲での環境調整(照明、温度、騒音の管理)を実施し、個人的な持ち物の配置により心理的安心感の向上を図る。家族サポートの受け入れについては、相互支援の概念を説明し、受援力の向上を支援する。新しいストレス発散方法の開発として、読書、音楽鑑賞、軽い手工芸など、入院中でも実施可能な活動を提案し、心理的安定を図る。信仰心を活かした精神的支えの活用についても検討し、個人の価値観に基づいたコーピング戦略を支援する。退院後のストレス管理について、在宅での環境整備と新しい生活パターンへの適応を支援し、長期的なストレス耐性の向上を目指す。継続的な心理状態の評価により、コーピング戦略の効果を評価し、必要に応じて専門的な心理的支援の導入も検討する必要がある。
信仰、意思決定を決める価値観・信念、目標
A氏は仏教徒であり、日本の伝統的な宗教観を基盤とした価値観を有していると推測される。仏教の基本的な教えである慈悲、忍耐、因果応報などの概念が、日常生活における意思決定や困難への対処方法に影響を与えている可能性がある。「他人に迷惑をかけることを嫌う」という性格特性は、仏教的な利他の精神と日本の伝統的な社会道徳が融合した価値観を反映している。元小学校教員という職歴からも、教育への価値観、社会貢献への使命感、責任感などが重要な価値観として形成されていると考えられる。現在の「家族に迷惑をかけたくない」「早く元の生活に戻りたい」という発言からも、自立性と他者への配慮を重視する価値観が明確に表れている。信仰が現在の病気や困難にどのような意味づけを与えているか、また心理的支えとしてどの程度機能しているかについて詳細な評価が必要である。
価値・信念管理上の課題と看護介入
主要な課題は現在の状況と既存の価値観との調和を図ることである。A氏の自立性を重視する価値観と、現在の身体的依存を必要とする状況との間に葛藤が生じている。仏教的な受容の精神を活かし、現在の状況を受け入れながらも希望を維持できるよう支援する必要がある。教育者としてのアイデンティティと経験を活かした新しい役割の可能性について検討し、生きがいの維持と向上を図る。例えば、同じような手術を受ける患者への体験談の共有や、医療スタッフへの協力など、他者への貢献を通じた自己価値の確認を支援する。信仰心を活かした精神的支えの強化として、**個
看護計画
看護問題
胃切除術に伴う消化機能の変化に関連した栄養摂取不足
長期目標
退院時までに適切な食事摂取により栄養状態が改善し、体重減少が止まり安定する
短期目標
1週間以内にダンピング症候群の症状を理解し、5分粥への移行が可能となる
≪O-P≫観察計画
・食事摂取量と摂取時間の記録
・体重の日々の変化
・血清アルブミン値、総蛋白値、ヘモグロビン値の推移
・食後30分から2時間の症状(動悸、冷汗、めまい、腹痛)の観察
・排便の回数、性状、量の記録
・皮膚の色調、弾力性、浮腫の有無
・バイタルサインの食前後の変化
・嚥下状況と咀嚼機能の評価
・腹部膨満感や早期満腹感の程度
・水分摂取量と尿量の記録
・食事に対する反応や表情の変化
・家族の食事介助の様子
≪T-P≫援助計画
・少量頻回の食事提供と摂取時間の調整
・食後30分間の安静臥床の援助
・適切な食事環境の整備(静かで落ち着いた雰囲気作り)
・食事形態の段階的な向上の調整
・栄養補助食品の提供と摂取支援
・食事前後のバイタルサイン測定
・症状出現時の対症的ケアの実施
・適切な体位の保持と安楽な環境作り
・水分摂取のタイミング調整(食事と別の時間帯)
・栄養士との連携による個別栄養計画の調整
・医師との連携による薬物療法の検討
・家族との食事時間の調整と心理的支援
≪E-P≫教育・指導計画
・ダンピング症候群の病態と対処方法の説明
・適切な食事摂取方法(少量頻回、よく噛む)の指導
・食後の安静の重要性と具体的方法の説明
・症状出現時の対処方法の指導
・退院後の食事計画と買い物のポイントの説明
・栄養バランスを考慮した献立作成の指導
・体重測定の方法と記録の重要性の説明
・家族に対する食事介助の方法と注意点の指導
看護問題
術後合併症(ダンピング症候群)に伴う症状出現に関連した日常生活活動の制限
長期目標
院時までにダンピング症候群の症状が軽減し、安全に日常生活活動が実施できる
短期目標
1週間以内に症状出現時の対処方法を習得し、症状による活動制限が軽減する
≪O-P≫観察計画
・食後の症状(動悸、冷汗、めまい、脱力感)の程度と持続時間
・症状出現時のバイタルサインの変化
・活動時の身体症状と活動耐性の評価
・転倒リスクの評価と歩行状況の観察
・日常生活動作の自立度の変化
・症状に対する患者の反応と対処行動
・活動制限による心理的影響の観察
・睡眠への影響と休息の取り方
・家族の不安や心配の程度
・薬物の効果と副作用の観察
・血糖値の変動(必要時)
・水分バランスと脱水症状の有無
≪T-P≫援助計画
・症状出現時の安静確保と体位調整
・適切な環境調整(室温、照明、騒音の管理)
・段階的な活動量の調整と休息の確保
・転倒予防対策の実施(環境整備、見守り)
・症状軽減のための薬物投与の援助
・リラクゼーション技法の実施
・安全な移動の援助と付き添い
・適切な水分補給のタイミング調整
・ストレス軽減のための環境作り
・家族の不安軽減のための精神的支援
・医師や栄養士との連携による治療方針の調整
・症状日誌の記録援助
≪E-P≫教育・指導計画
・ダンピング症候群の症状と経過の説明
・症状出現時の具体的な対処方法の指導
・安全な活動方法と休息の取り方の説明
・転倒予防のための注意点の指導
・家族に対する症状理解と対応方法の説明
・退院後の生活における注意点の指導
看護問題
入院環境の変化と術後の身体状況に伴う不安に関連した睡眠パターンの変調
長期目標
退院時までに睡眠導入剤に依存せず良質な睡眠が確保できる
短期目標
1週間以内に入院環境に適応し、睡眠導入剤の使用頻度が減少する
≪O-P≫観察計画
・入眠時間と睡眠時間の記録
・中途覚醒の回数と原因の把握
・睡眠導入剤の使用頻度と効果
・日中の眠気や疲労感の程度
・睡眠に対する不安や心配の表出
・夜間の病棟環境(騒音、照明)の影響
・痛みや身体症状による睡眠への影響
・日中の活動量と休息の取り方
・ストレス要因と心理状態の変化
・家族に対する心配や不安の内容
・睡眠前の行動パターンや習慣
・薬物の副作用や翌日への影響
≪T-P≫援助計画
・就寝前の環境調整(照明、温度、騒音の管理)
・就寝前のリラクゼーション援助
・規則正しい生活リズムの確立支援
・日中の適度な活動促進
・痛みや不快症状の軽減ケア
・不安軽減のための傾聴と精神的支援
・睡眠導入剤の適切な使用タイミングの調整
・夜間の安全確保と見回り
・個人の睡眠習慣を尊重した環境作り
・ストレス要因の除去と対処支援
・家族との面会時間の調整
・医師との連携による薬物調整の検討
≪E-P≫教育・指導計画
・良質な睡眠のための生活習慣の指導
・入院環境での睡眠確保の工夫の説明
・ストレス軽減のためのリラクゼーション方法の指導
・睡眠導入剤の適切な使用方法と注意点の説明
・退院後の睡眠環境整備の指導
・家族に対する患者の心理状態の理解と支援方法の説明
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
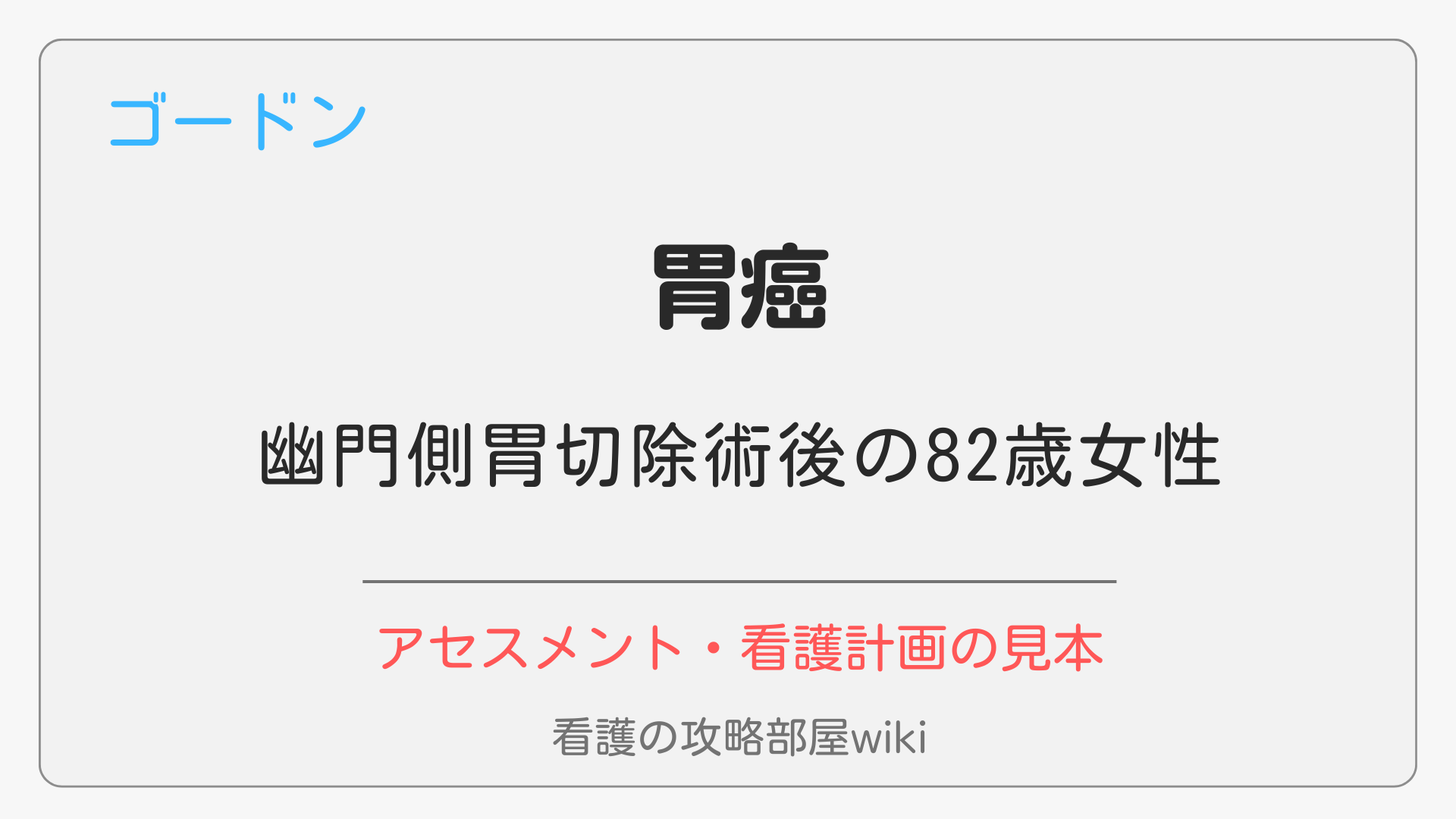
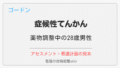
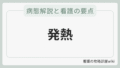
コメント