病態の概要
定義
フレイルとは、加齢に伴い心身の機能が徐々に低下し、健康な状態と要介護状態の中間に位置する状態のことですね。英語の「Frailty(虚弱)」が語源となっており、可逆性がある状態として注目されています。日本老年医学会では「加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態」と定義しています。
原因
フレイルの原因は多面的で複雑ですが、主に以下の要因が相互に関連し合って発生します。身体的要因として、筋肉量・筋力の減少(サルコペニア)、骨密度の低下、慢性疾患の併存、栄養不良、活動量の低下などがあります。心理的・認知的要因では、認知機能の低下、うつ状態、意欲の減退が関与します。社会的要因としては、社会的孤立、経済的困窮、住環境の問題などが挙げられるでしょう。これらの要因が複合的に作用することで、負のスパイラルを形成し、フレイルが進行していくのです。
病態生理
正常な状態
健康な高齢者では、加齢による生理機能の低下はあるものの、日常生活に必要な身体機能や認知機能が保たれています。筋肉量は年間1-2%程度の減少に留まり、適度な運動や栄養摂取により機能維持が可能な状態です。免疫機能も一定レベルを保ち、感染症への抵抗力も維持されています。また、社会的なつながりも保たれ、生活に対する意欲や目標を持って過ごすことができる状態といえるでしょう。
異常が起こる過程
フレイルの進行過程は段階的に進みます。まず、プレフレイル段階では、軽度の体重減少や疲労感、活動量の軽度低下が見られますが、まだ日常生活は自立しています。この段階では、適切な介入により健康な状態への回復が十分可能です。次にフレイル段階に入ると、明らかな筋力低下、歩行速度の低下、体重減少が顕著になり、日常生活動作に支障をきたし始めます。最終的に重度フレイル段階では、要介護状態となり、複数の慢性疾患を併発し、生命予後にも影響する状態となります。この過程では、炎症反応の慢性化、ホルモンバランスの変化、神経筋機能の低下が相互に関連し合って進行していきます。
症状
現れる症状とその理由
フレイルの症状は多岐にわたりますが、Fried基準と呼ばれる5つの項目で評価されることが多いです。まず体重減少は、食欲不振や咀嚼・嚥下機能の低下、消化吸収能力の低下により起こります。年間4.5kg以上または5%以上の意図しない体重減少が見られるでしょう。疲労感・倦怠感は、筋肉量の減少や心肺機能の低下、貧血、うつ状態などが原因となって現れます。活動量の低下は、筋力低下や関節痛、息切れなどにより、以前と同じ活動ができなくなることで生じます。歩行速度の低下は、筋力低下や バランス能力の低下、関節可動域の制限などが原因です。通常の歩行速度が1.0m/秒未満になると要注意とされています。握力の低下は、全身の筋力低下を反映する指標として重要で、男性26kg未満、女性18kg未満が基準となります。これらの症状が複合的に現れることで、転倒リスクの増加、感染症への易罹患性、入院期間の延長、死亡率の上昇などの問題につながっていくのです。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
・活動耐性低下
・転倒リスク状態
・栄養摂取消費バランス異常:必要量以下
・社会的孤立
・セルフケア不足(入浴・清潔、更衣・整容、摂食、排泄)
・慢性的混乱
・無力感
・家族介護者役割緊張
・非効果的健康管理
ゴードンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、フレイル状態への理解度や健康管理への意欲を評価することが重要です。患者さん自身がフレイルという概念を理解し、予防や改善への取り組みに対する動機を持てるよう支援していく必要があります。活動-運動パターンでは、日常生活動作の自立度、歩行能力、転倒歴、運動習慣などを詳細に評価します。特に歩行速度や握力などの客観的指標を用いた評価が有効でしょう。栄養-代謝パターンでは、食事摂取量、体重変化、咀嚼・嚥下機能、血液検査データ(アルブミン値など)を総合的に評価し、栄養状態の改善策を検討します。認知-知覚パターンでは、認知機能の評価とともに、痛みの有無や程度を評価し、活動制限の要因を特定することが大切です。
ヘンダーソンのポイント
正常な呼吸では、呼吸機能の評価とともに、活動時の息切れの程度を確認し、心肺機能に応じた活動レベルの調整を行います。適切な飲食は特に重要で、食事摂取量、嗜好の変化、口腔機能、消化機能を総合的に評価し、個別的な栄養管理計画を立てる必要があります。身体の動きと良肢位の保持では、関節可動域や筋力、バランス能力を評価し、安全で効果的な運動プログラムを提供します。学習の側面では、フレイル予防に関する知識の提供と、実践可能な生活習慣の獲得を支援することが重要です。遊びや娯楽、社会参加では、社会的つながりの維持・拡大を図り、生きがいや役割を持てるよう支援していきます。
看護計画・介入の内容
・個別的な運動プログラムの実施(筋力トレーニング、バランス訓練、有酸素運動)
・栄養状態の改善(食事内容の見直し、栄養補助食品の活用、口腔ケアの充実)
・転倒予防対策(環境整備、歩行補助具の適切な使用、転倒リスク評価)
・社会参加の促進(地域活動への参加支援、家族・友人との交流機会の確保)
・認知機能維持・向上のための活動支援
・服薬管理の支援(ポリファーマシーの評価と適正化)
・定期的な健康状態のモニタリング
・家族への教育と支援体制の構築
・多職種連携による継続的なケア提供
よくある疑問・Q&A
Q: フレイルとサルコペニアの違いは何ですか?
A: サルコペニアは主に筋肉量・筋力の減少に焦点を当てた概念で、フレイルはより包括的な概念です。サルコペニアは身体的な側面が中心ですが、フレイルは身体的要因に加えて、心理的・社会的要因も含んだ多面的な状態を表しています。サルコペニアがフレイルの一要因として位置づけられると考えるとよいでしょう。
Q: フレイルは本当に可逆的なのですか?
A: はい、特にプレフレイルや軽度フレイルの段階では、適切な介入により改善が期待できます。運動療法、栄養療法、社会参加の促進などの包括的なアプローチにより、健康な状態への回復や機能維持が可能です。ただし、重度フレイルになると改善は困難になるため、早期発見・早期介入が重要となります。
Q: フレイルの評価にはどのような方法がありますか?
A: 日本では基本チェックリストや後期高齢者の質問票が広く使用されています。国際的にはFried基準やSOF(Study of Osteoporotic Fractures)指標などが用いられます。これらの評価ツールは、身体機能、栄養状態、認知機能、社会的側面を総合的に評価するように設計されています。
Q: フレイル予防で最も効果的な介入は何ですか?
A: 単独の介入よりも、運動、栄養、社会参加を組み合わせた多面的介入が最も効果的とされています。特に筋力トレーニングを含む運動プログラムは基礎となりますが、それに加えて適切な栄養摂取と社会的つながりの維持が重要です。個人の状態に応じてオーダーメイドのプログラムを作成することが成功の鍵となります。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
看護過程の個別サポート
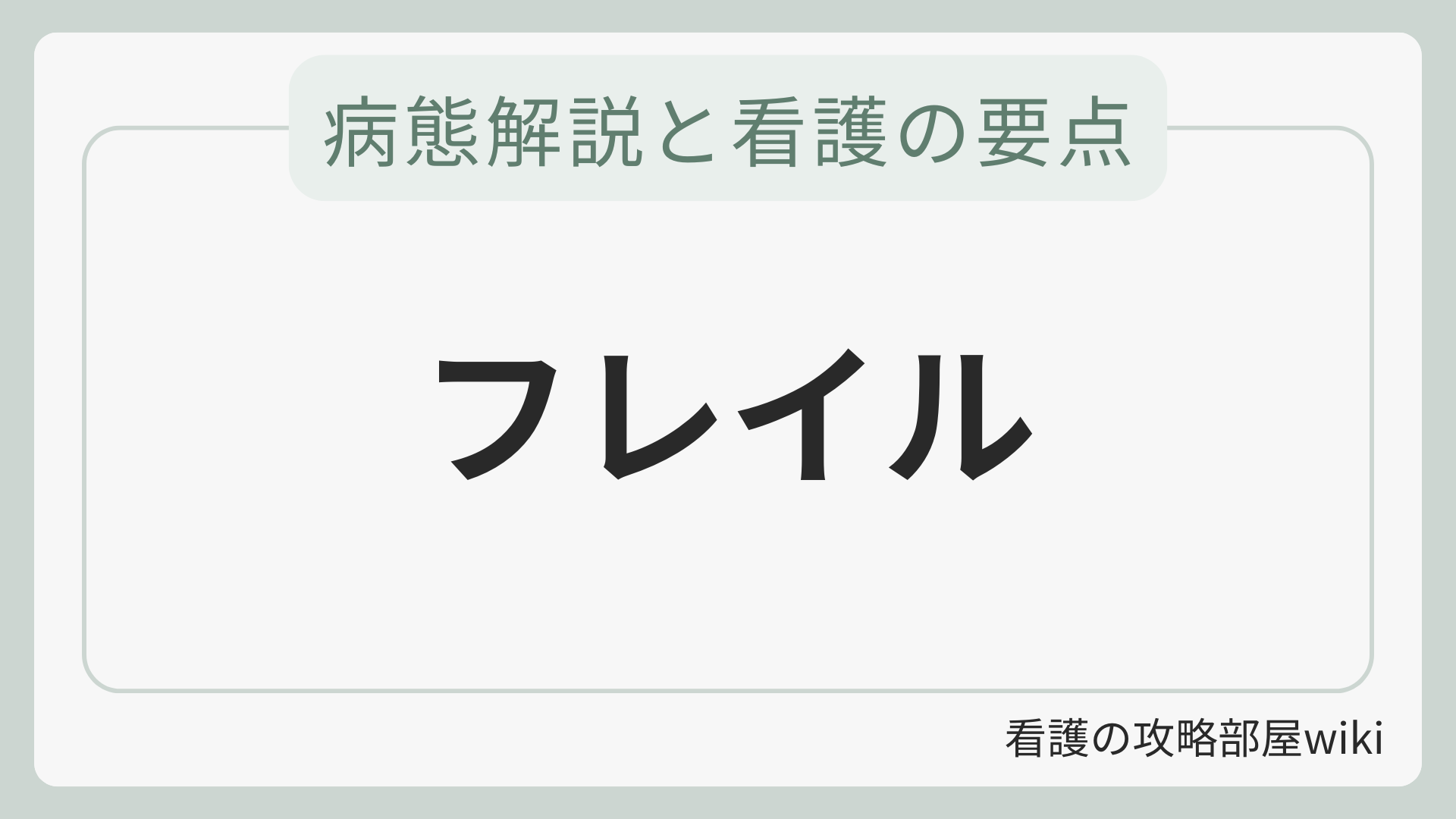
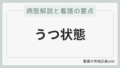
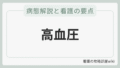
コメント