病態の概要
定義
高血圧は、血管内を流れる血液が血管壁に与える圧力が持続的に高い状態のことですね。一般的に、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の状態が続く場合に高血圧と診断されます。日本では約4,000万人が高血圧を患っており、まさに「サイレントキラー」と呼ばれる生活習慣病の代表格です。
原因
高血圧の原因は大きく分けて二つのタイプがあります。本態性高血圧は全体の約90%を占め、遺伝的要因、食塩の過剰摂取、肥満、運動不足、ストレス、喫煙、過度の飲酒などの生活習慣が複合的に関与しています。一方、二次性高血圧は約10%で、腎疾患、内分泌疾患(原発性アルドステロン症、褐色細胞腫など)、血管疾患、薬剤の副作用など、明確な基礎疾患が原因となって起こります。
病態生理
正常な状態
正常な血圧調節は、心拍出量と末梢血管抵抗のバランスによって維持されています。心臓から送り出される血液量(心拍出量)と血管の収縮・拡張(血管抵抗)が適切に調整されることで、組織への酸素や栄養素の供給が効率的に行われるのです。この調節には、交感神経系、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAAS)、血管内皮由来の血管作動物質などが複雑に関与しています。
異常が起こる過程
高血圧の発症には複数のメカニズムが関与します。まず、血管抵抗の増加では、血管平滑筋の収縮や血管壁の肥厚により血管が狭くなり、血液を送るために心臓がより強い力を必要とします。次に、体液量の増加では、腎臓での塩分と水分の排泄が低下し、循環血液量が増加することで血圧が上昇します。さらに、交感神経系の活性化により心拍数と心収縮力が増加し、血管も収縮しやすくなります。これらの変化が持続すると、血管壁に慢性的な負荷がかかり、動脈硬化が進行してさらに血圧が上昇するという悪循環が生まれてしまうのです。
症状
現れる症状とその理由
現れる症状とその理由 高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、初期段階では自覚症状がほとんどありません。これは、人間の体が血圧の上昇に徐々に適応してしまうためです。症状が現れる場合には、頭痛、めまい、肩こり、動悸、息切れ、疲労感などがありますが、これらは血圧上昇による血管への負荷や、臓器への血流不足が原因となります。重要なのは、症状がないからといって治療を怠ってはいけないということです。長期間放置すると、心筋梗塞、脳卒中、腎不全、大動脈解離などの重篤な合併症を引き起こす可能性が高くなります。特に収縮期血圧が180mmHg以上、拡張期血圧が110mmHg以上の高血圧緊急症では、頭痛、視野障害、意識障害、胸痛などの症状が急激に現れ、緊急治療が必要となります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
・心拍出量減少の危険性
・組織灌流低下の危険性
・活動耐性低下
・知識不足(疾患管理に関連した)
・治療計画の不履行
・不安
・急性疼痛(頭痛)
・転倒転落の危険性
ゴードンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さんの疾患に対する理解度と治療への取り組み姿勢を評価することが重要です。多くの高血圧患者さんは症状がないため疾患の重要性を理解していない場合があり、服薬コンプライアンスの低下につながります。栄養-代謝パターンでは、塩分摂取量、体重管理、食事内容の詳細な聴取が必要で、特に1日の塩分摂取量が6g未満になるよう指導します。活動-運動パターンでは、日常生活での活動量と運動習慣を評価し、心血管系への負荷を考慮した適切な運動プログラムを提案する必要があります。
ヘンダーソンのポイント
正常な呼吸では、高血圧による心不全の兆候として呼吸困難や起座呼吸がないかを観察します。適切な飲食においては、塩分制限食の理解と実践状況、水分バランスの管理が重要で、特に利尿薬使用時の脱水予防と電解質バランスの維持に注意が必要です。身体の清潔と身だしなみでは、入浴時の血圧変動リスクを考慮し、温度差による血圧上昇を防ぐための指導を行います。学習するでは、疾患理解、服薬管理、生活習慣改善に関する継続的な教育支援が不可欠となります。
看護計画・介入の内容
・バイタルサインの定期的な測定と記録(特に血圧値の変動パターンの観察)
・服薬状況の確認と服薬指導の実施
・塩分制限食に関する栄養指導(1日6g未満を目標)
・適切な運動療法の指導と実施支援
・体重測定と体重管理指導
・ストレス軽減のためのリラクゼーション技法の指導
・合併症の早期発見のための症状観察
・血圧測定方法の指導と家庭血圧測定の推奨
・生活習慣改善に向けた具体的な目標設定と評価
・定期受診の重要性について説明と受診継続支援
よくある疑問・Q&A
Q: なぜ高血圧は症状がないのに危険と言われるのですか?
A: 高血圧は血管に持続的な負荷をかけ続けるため、動脈硬化を進行させて心筋梗塞や脳卒中などの致命的な合併症を引き起こすリスクが高いからです。症状がないうちに血管の損傷は確実に進行しているため、早期発見と継続的な管理が重要になります。
Q: 血圧の薬は一度飲み始めたらやめられないのですか?
A: 血圧薬は血圧をコントロールするためのものであり、根本的な治療ではありません。しかし、生活習慣の改善により血圧が十分に下がれば、医師の判断で薬を減量したり中止したりできる場合もあります。自己判断での中断は危険ですので、必ず医師と相談することが大切です。
Q: 家庭血圧と病院で測る血圧、どちらが重要ですか?
A: 両方とも重要ですが、日常生活での血圧変動を把握できる家庭血圧の方が治療方針の決定により有用とされています。病院では緊張により血圧が上がる「白衣高血圧」や、逆に病院では正常だが家庭で高い「仮面高血圧」もあるため、家庭血圧の測定が推奨されます。
Q: 高血圧の人は運動してはいけないのですか?
A: 適切な運動は血圧を下げる効果があるため推奨されますが、急激で激しい運動は血圧を急上昇させるため危険です。ウォーキングや軽いジョギング、水中歩行などの有酸素運動を、医師と相談して段階的に始めることが重要です。運動前後の血圧測定も忘れずに行いましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
看護過程の個別サポート
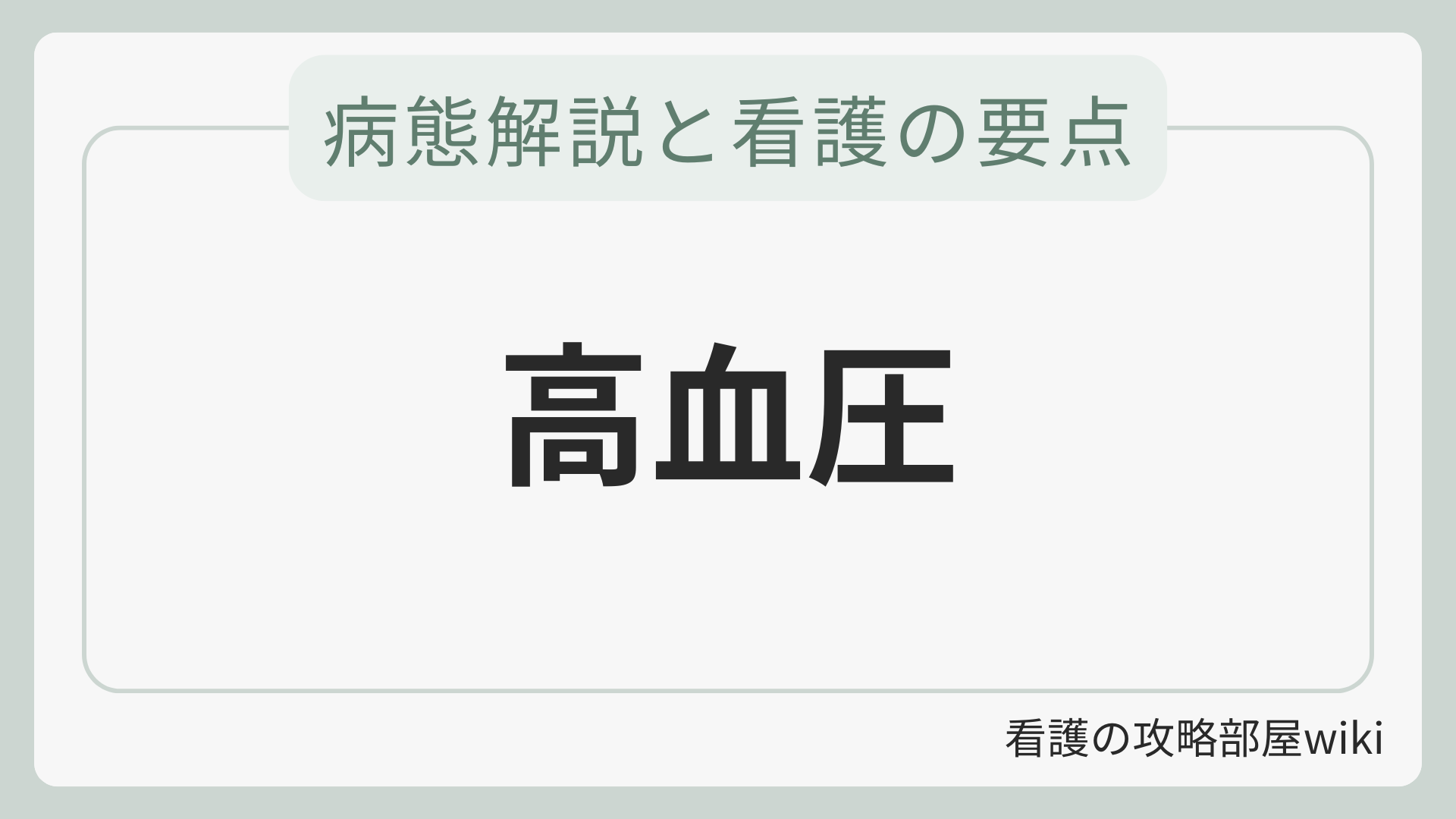
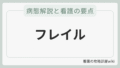
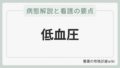
コメント