事例の要約
転倒転落リスクが高い高齢者の大腿骨頸部骨折術後患者の事例。11月15日、術後3日目の介入。
基本情報
A氏は78歳の女性で、身長152cm、体重48kgの小柄な体格である。家族構成は夫と二人暮らしで、キーパーソンは長男となっている。退職前は小学校教員として勤務しており、真面目で几帳面な性格だが、やや心配性な面もある。感染症の既往はなく、薬物アレルギーも認められない。認知機能はMMSE 24点で軽度の認知機能低下がみられ、時々見当識に混乱を示すことがある。
病名
右大腿骨頸部骨折(Garden分類 Stage III)、人工骨頭置換術施行
既往歴と治療状況
既往歴として高血圧、骨粗鬆症、変形性膝関節症があり、降圧薬とビスフォスフォネート製剤で治療中である。3年前に左手首の橈骨遠位端骨折の既往があり、転倒歴が複数回認められる。
入院から現在までの情報
A氏は自宅の階段で足を滑らせて転倒し、右股関節部の疼痛と歩行困難を主訴に救急搬送された。来院時のX線検査で右大腿骨頸部骨折が確認され、翌日に人工骨頭置換術が施行された。術後は順調に経過しているが、疼痛への不安と転倒への恐怖から活動性の低下がみられている。理学療法は術後2日目から開始され、現在は部分荷重での歩行訓練を行っている。
バイタルサイン
来院時は体温37.2℃、血圧158/92mmHg、脈拍98回/分、呼吸数22回/分、SpO2 96%(room air)であった。現在は体温36.8℃、血圧142/86mmHg、脈拍82回/分、呼吸数18回/分、SpO2 98%(room air)と安定している。
食事と嚥下状態
入院前は普通食を自立摂取していたが、入院後は疼痛や環境変化により食欲が低下し、摂取量は6割程度となっている。嚥下機能に問題はなく、水分摂取も良好である。喫煙歴はなく、飲酒は月に数回程度の晩酌をしていた。
排泄
入院前は排泄動作は自立していたが、夜間に1-2回の排尿があった。現在は術後の安静とカテーテル留置により、尿道カテーテル管理となっている。便秘傾向があり、酸化マグネシウムを定期内服している。
睡眠
入院前は23時頃に就寝し6時頃に起床する規則正しい生活を送っていた。現在は病院環境と疼痛により睡眠が浅く、頻繁に覚醒している。ゾルピデム5mgを眠前に使用している。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
老眼鏡使用で視力は良好、聴力も正常範囲内である。触覚・痛覚に異常はなく、コミュニケーションは良好に図れる。特定の宗教的信仰はない。
動作状況
歩行は術前から歩行器使用していたが、現在は部分荷重での歩行訓練中である。移乗動作は介助が必要で、転倒リスクが高い状態である。排泄動作は現在カテーテル管理中で、入浴は清拭で対応している。衣類の着脱は上肢の動作は自立しているが、下肢は介助が必要である。過去3年間で3回の転倒歴がある。
内服中の薬
アムロジピン 5mg 1日1回 朝食後
酸化マグネシウム 500mg 1日3回 毎食後
アレンドロン酸 35mg 1週間に1回 起床時
ロキソプロフェン 60mg 1日3回 毎食後 疼痛時
ゾルピデム 5mg 1日1回 眠前
服薬状況
入院前は本人による自己管理であったが、現在は看護師による管理となっている。
検査データ
検査データ
| 項目 | 入院時 | 最近(術後3日目) |
|---|---|---|
| WBC | 8,500 | 6,200 |
| RBC | 380 | 320 |
| Hb | 10.2 | 8.9 |
| Plt | 25.8 | 28.2 |
| TP | 6.8 | 6.5 |
| Alb | 3.8 | 3.2 |
| BUN | 22 | 18 |
| Cr | 0.9 | 0.8 |
| Na | 142 | 140 |
| K | 4.2 | 4.0 |
| CRP | 2.8 | 1.2 |
今後の治療方針と医師の指示
医師からは段階的な荷重増加と早期離床の方針が示されている。理学療法を継続し、全荷重歩行の獲得を目標とする。転倒予防のため、ベッド柵の使用と離床時の見守りが指示されている。また、貧血の改善のため鉄剤の投与も検討されている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「また転んでしまうのではないか」と強い不安を訴えており、「家に帰れるのか心配」と発言している。夫は「妻の介護は自分がする」と意欲的だが、年齢的な体力面での不安も表出している。長男は「安全に過ごせる環境を整えたい」と転倒予防への関心が高く、退院後のサポート体制について積極的に相談している。
アセスメント
疾患の簡単な説明
A氏は右大腿骨頸部骨折により人工骨頭置換術を受けた78歳女性である。整形外科的疾患であるため直接的な呼吸器疾患はないが、術後の安静臥床と疼痛による活動制限が呼吸機能に影響を与える可能性がある。高齢者では加齢による呼吸筋力低下や胸郭の可動性低下があり、術後の長期臥床は肺炎や無気肺のリスクを高める要因となる。また、全身麻酔による術後の呼吸抑制や、疼痛による浅呼吸も呼吸機能に影響を与える可能性がある。
呼吸数、SpO2、肺雑音、呼吸機能、胸部レントゲン
現在の呼吸数は18回/分と正常範囲内であり、SpO2は98%(room air)と良好な酸素化状態を示している。来院時と比較して呼吸数は改善傾向にあり、術後の呼吸状態は安定している。肺雑音については現在の事例では具体的な記載がないため、聴診による詳細な評価が必要である。78歳という高齢であることから、加齢による肺弾性の低下や呼吸筋力の減退が基礎にあると考えられる。胸部レントゲンの結果についても情報が不足しており、術前術後の比較評価や現在の肺野の状態について追加の情報収集が必要である。特に術後の臥床により下肺野の換気不全や軽度の無気肺の有無について確認が重要である。
呼吸苦、息切れ、咳、痰
現在のところ明らかな呼吸苦や息切れの訴えは記載されていないが、術後の疼痛や不安により浅呼吸になっている可能性がある。咳や痰の有無についても具体的な情報が不足しているため、詳細な症状の聴取が必要である。高齢者では咳嗽反射の低下があるため、下気道の分泌物の喀出能力が低下している可能性がある。術後の安静臥床により、分泌物の貯留が生じやすい状態にあると考えられる。また、全身麻酔による気道への影響や、術後の疼痛による深呼吸の制限も呼吸機能に影響を与えている可能性がある。
喫煙歴
A氏に喫煙歴はなく、この点は呼吸機能にとって良好な要因である。喫煙による慢性閉塞性肺疾患や肺癌のリスクがないため、基礎的な肺機能は比較的保たれていると考えられる。しかし、夫の喫煙状況や受動喫煙の影響については確認が必要である。非喫煙者であることは術後の呼吸機能回復にとって有利な条件となる。
呼吸に関するアレルギー
薬物アレルギーは認められないとされているが、吸入性アレルゲンや環境因子による呼吸器症状の既往についても詳細な確認が必要である。花粉症や動物アレルギー、ハウスダストアレルギーなどの有無は、入院環境での呼吸状態に影響を与える可能性がある。現在使用中の薬物による呼吸器系への副作用についても継続的な観察が必要である。
ニーズの充足状況
現在のSpO2値98%は良好であり、基本的な酸素化ニーズは充足されている状態である。しかし、術後3日目という時期は肺合併症のリスクが高い時期であり、継続的な呼吸状態の観察が重要である。深呼吸や咳嗽の励行による肺合併症の予防が必要な段階にある。高齢者の生理的変化として、肺活量の減少や残気量の増加があり、これらは術後の呼吸機能回復に影響を与える可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、術後肺合併症の予防が最優先である。具体的には深呼吸・咳嗽訓練の実施、体位ドレナージの促進、早期離床の推進が重要である。疼痛管理を適切に行うことで深呼吸を促し、分泌物の貯留予防を図る必要がある。また、定期的な呼吸音の聴診により肺雑音の有無を確認し、胸部レントゲンによる画像評価も継続的に行う必要がある。高齢者であることから嚥下機能の評価も重要であり、誤嚥性肺炎の予防にも注意を払う必要がある。観察項目として、呼吸数、SpO2、呼吸音、咳嗽の有無、痰の性状、呼吸困難感の有無を継続的に確認し、早期発見・早期対応の体制を整えることが重要である。
食事と水分の摂取量と摂取方法
A氏は入院前には普通食を自立摂取していたが、現在は摂取量が6割程度に低下している状況である。この低下は術後の疼痛、環境変化、不安などの複合的な要因によるものと考えられる。水分摂取については良好であるとされているが、具体的な摂取量や摂取方法については詳細な情報が不足している。経口摂取が可能な状態であることは確認されているが、術後の疼痛や不安が食欲に与える影響について継続的な評価が必要である。78歳という高齢であることから、加齢による味覚や嗅覚の変化も食欲低下の一因として考慮する必要がある。
食事に関するアレルギー
薬物アレルギーは認められないとされているが、食物アレルギーの詳細な情報については確認が必要である。特に高齢者では新たに食物アレルギーを発症することもあるため、入院中の食事摂取状況を観察し、アレルギー反応の有無を継続的に確認する必要がある。また、使用中の薬物との食物相互作用についても注意深く観察することが重要である。
身長、体重、BMI、必要栄養量、身体活動レベル
A氏の身長は152cm、体重は48kgで、BMIは約20.8kg/m²と正常範囲内である。しかし、78歳女性の標準的な体格と比較するとやや痩せ型の傾向がある。術後の安静臥床により身体活動レベルは著しく低下しており、必要栄養量の再計算が必要である。基礎代謝の低下と活動量の減少を考慮すると、現在の必要栄養量は約1200-1400kcal/日程度と推定されるが、創傷治癒や骨形成に必要な蛋白質やカルシウムの需要増加も考慮する必要がある。
食欲、嚥下機能、口腔内の状態
現在食欲低下が認められているが、嚥下機能に問題はないとされている。しかし、高齢者では嚥下反射の低下や口腔機能の低下が潜在的に存在する可能性があるため、詳細な嚥下評価が必要である。口腔内の状態については具体的な情報が不足しており、義歯の適合性、口腔乾燥、口腔内炎症の有無について確認が必要である。特に全身麻酔後は口腔乾燥が生じやすく、これが食欲低下の一因となっている可能性がある。
嘔吐、吐気
現在のところ明らかな嘔吐や吐気の記載はないが、術後の消化器症状について詳細な確認が必要である。使用中のロキソプロフェンは消化器系への副作用があるため、胃腸障害の有無を継続的に観察する必要がある。また、疼痛や不安が消化器症状に与える影響についても評価が重要である。
血液データ(TP、Alb、Hb、TG)
現在のTP値は6.5g/dL、Alb値は3.2g/dLと軽度低下を示している。入院時のAlb値3.8g/dLから低下傾向にあり、術後の炎症反応や摂食量低下が影響していると考えられる。Hb値は8.9g/dLと貧血を示しており、これは術中出血や術後の炎症反応による影響と考えられる。TGについては記載がないため、脂質代謝の評価のためにも情報収集が必要である。これらの値は栄養状態の悪化を示唆しており、積極的な栄養介入が必要である。
ニーズの充足状況
現在の栄養摂取状況はニーズが十分に充足されていない状態である。摂取量が6割程度に留まっていることから、エネルギーおよび蛋白質不足の状態にある。特に術後の創傷治癒と骨形成には十分な栄養が必要であり、現在の摂取状況では回復に支障をきたす可能性がある。血液データでも栄養指標の低下が認められており、早急な栄養状態の改善が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として術後の栄養状態悪化の予防と改善が挙げられる。具体的には食欲増進のための環境整備、疼痛管理の徹底、少量頻回の食事提供などが必要である。また、高蛋白・高カロリー食品の積極的な摂取を促し、必要に応じて栄養補助食品の使用も検討する。口腔ケアの徹底により食欲の改善を図り、家族の協力を得た食事支援も重要である。栄養状態の指標として、体重測定、血液データ(Alb、TP)の定期的な評価を行い、管理栄養士との連携による栄養計画の見直しも必要である。摂食量、食事内容、嚥下状況を継続的に観察し、早期の栄養状態改善を目指すことが重要である。
排便回数と量と性状、排尿回数と量と性状、発汗
A氏は入院前から便秘傾向があり、酸化マグネシウムを定期内服している状況である。術後の安静臥床と疼痛により腸蠕動が低下し、便秘の悪化が予想される。排便回数、量、性状についての具体的な情報は不足しており、詳細な観察記録が必要である。排尿については現在尿道カテーテル管理となっており、入院前は夜間1-2回の排尿があったことから、夜間頻尿の傾向が認められる。78歳という高齢であることから、膀胱機能の低下や前立腺肥大症の影響も考慮する必要がある。発汗状況については記載がないため、体温調節機能や水分バランスの評価のためにも観察が必要である。
in-outバランス
現在の水分摂取は良好とされているが、具体的な摂取量と排出量の詳細な記録が不足している。尿道カテーテル管理中であることから、正確な尿量測定が可能な状況であり、時間尿量の監視が重要である。術後の輸液管理との関連で、体液バランスの維持が必要であり、浮腫の有無や体重変化も併せて評価する必要がある。高齢者では腎機能の低下があるため、過剰な水分負荷や脱水に注意が必要である。
排泄に関連した食事、水分摂取状況
現在の食事摂取量が6割程度に低下していることが、便秘の悪化要因となっている。特に食物繊維の摂取不足は腸蠕動の低下を招く。水分摂取は良好とされているが、便性状の改善のためには十分な水分量の確保が重要である。術後の疼痛や食欲低下により、排便に必要な食事内容が確保できていない可能性がある。
麻痺の有無
現在の事例では明らかな麻痺の記載はないが、術後の疼痛による活動制限が排泄動作に影響を与えている。右大腿骨頸部骨折のため、体位変換や排泄姿勢の確保に制限がある状況である。高齢者では潜在的な神経機能の低下もあり、排泄に関連する神経機能について詳細な評価が必要である。
腹部膨満、腸蠕動音
術後の安静臥床と疼痛、使用薬剤の影響により腸蠕動の低下が予想される。腹部膨満や腸蠕動音の詳細な情報は現在不足しており、定期的な腹部の観察が必要である。特にロキソプロフェンなどの鎮痛薬は消化器機能に影響を与える可能性があるため、腸蠕動の変化を注意深く観察する必要がある。
血液データ(BUN、Cr、GFR)
現在のBUN値は18mg/dL、Cr値は0.8mg/dLと正常範囲内にある。入院時と比較してBUNは22mg/dLから18mg/dLへ改善傾向を示している。しかし、78歳という高齢であることから、加齢による腎機能の低下は基礎にあると考えられる。GFRの値は記載されていないため、腎機能の詳細な評価のためにも情報収集が必要である。現在の値は正常範囲内であるが、脱水や薬剤による腎機能への影響について継続的な監視が重要である。
ニーズの充足状況
排泄に関するニーズは十分に充足されていない状況である。尿道カテーテル管理により自然な排尿パターンが阻害され、便秘傾向の悪化により排便ニーズも障害されている。術後の疼痛と活動制限により、自立した排泄動作が困難な状態にある。特に高齢者にとって排泄の自立は尊厳に関わる重要な問題であり、早期の改善が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として便秘の予防と改善、適切な水分バランスの維持、早期のカテーテル抜去に向けた準備が挙げられる。便秘対策としては腹部マッサージ、可能な範囲での体位変換、食物繊維の摂取促進が必要である。水分バランスについては正確なin-outバランスの記録を継続し、脱水や浮腫の早期発見に努める。カテーテル抜去後の排尿自立に向けた訓練も重要であり、膀胱機能の評価と残尿量の測定を行う。腸蠕動音の聴取、腹部膨満の観察、排便状況の詳細な記録を継続し、消化器機能の回復を促進する介入を行う。また、プライバシーの確保と尊厳を保った排泄援助により、患者の心理的負担を軽減することも重要である。
ADL、麻痺、骨折の有無
A氏は右大腿骨頸部骨折により人工骨頭置換術を受けており、現在術後3日目の状況にある。明らかな麻痺はないものの、術後疼痛と手術部位の保護により活動が大幅に制限されている。入院前は歩行器を使用していた状況から、既に歩行機能の低下があったことが伺える。現在は部分荷重での歩行訓練中であり、移乗動作には介助が必要な状態である。78歳という高齢に加え、変形性膝関節症の既往があることから、関節可動域の制限や筋力低下も併存していると考えられる。
ドレーン、点滴の有無
現在尿道カテーテルが留置されており、これが体位変換や移動時の制約要因となっている。術後の点滴管理の詳細は記載されていないが、一般的に術後管理では輸液ラインが確保されていることが多く、これらのルート類が体位変換や移乗動作の妨げとなる可能性がある。ドレーンの有無についても具体的な情報が不足しており、創部ドレーンの存在が体位制限に与える影響について確認が必要である。
生活習慣、認知機能
A氏は元小学校教員で規則正しい生活を送っていたが、MMSE 24点と軽度の認知機能低下が認められる。時々見当識に混乱を示すことがあり、これが安全な体位変換や移動に影響を与える可能性がある。真面目で几帳面な性格である一方、やや心配性な面があることから、転倒への恐怖が積極的な活動を阻害している可能性がある。入院環境への適応にも時間を要することが予想される。
ADLに関連した呼吸機能
現在のSpO2は98%と良好であるが、術後の安静臥床により呼吸筋力の低下や肺活量の減少が懸念される。高齢者では加齢による胸郭の可動性低下があり、長期臥床により更なる呼吸機能の低下を招く可能性がある。体位変換時の呼吸状態の変化や、座位や立位での呼吸機能について詳細な評価が必要である。活動時の酸素飽和度の変化についても観察が重要である。
転倒転落のリスク
A氏は過去3年間で3回の転倒歴があり、極めて高い転倒リスクを有している。現在の状況として、術後疼痛、軽度認知機能低下、歩行器使用歴、高齢、骨粗鬆症の既往など複数のリスク因子が重複している。特に術後の環境変化と疼痛、不安により転倒リスクは更に増大している。ベッド柵の使用と離床時の見守りが医師により指示されているが、包括的な転倒予防対策が必要である。
ニーズの充足状況
現在の状況では体位変換と移動に関するニーズが十分に充足されていない状態である。自立した体位変換や移乗動作が困難であり、介助依存度が高い状況にある。術前から歩行器使用していたことを考慮すると、機能回復の目標設定が重要である。理学療法が開始されているものの、疼痛と不安により積極的な参加が阻害されている可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
最重要課題は転倒予防と安全な移動の確保である。具体的には環境整備、適切な移動・移乗方法の指導、段階的な活動拡大が必要である。疼痛管理を徹底し、理学療法への積極的な参加を促進する。体位変換は2時間毎に実施し、褥瘡予防と関節拘縮の予防を図る。認知機能低下を考慮し、見当識の確認と安全な環境作りが重要である。カテーテルやルート類の管理を適切に行い、安全な体位変換を実施する。家族への移乗介助方法の指導も退院に向けて必要である。継続的な観察項目として、疼痛レベル、転倒リスクの評価、ADLの改善度、認知機能の変化を定期的に評価し、個別性を重視したリハビリテーション計画の修正を行うことが重要である。また、離床時の血圧変動や起立性低血圧の有無についても注意深く観察する必要がある。
睡眠時間、パターン
A氏は入院前には23時頃就寝、6時頃起床という規則正しい睡眠パターンを維持していた。約7時間の睡眠時間は高齢者としては適切であり、生活リズムが整っていたことが伺える。しかし現在は病院環境と疼痛により睡眠が浅く、頻繁に覚醒している状況である。具体的な睡眠時間や中途覚醒の回数については詳細な情報が不足しており、睡眠日誌による記録が必要である。術後3日目という時期は疼痛や不安が強く、睡眠の質的・量的な障害が最も生じやすい時期である。
疼痛、掻痒感の有無、安静度
現在術後疼痛があり、これが睡眠障害の主要因となっている。疼痛は夜間に増強することが多く、深部痛や体位変換時痛が睡眠の妨げとなっている可能性が高い。掻痒感については記載がないが、高齢者では皮膚乾燥による掻痒が睡眠を妨げることがあるため確認が必要である。安静度については部分荷重歩行訓練中であり、日中の活動量不足が概日リズムの乱れを招いている可能性がある。術後の安静により筋緊張の変化も睡眠に影響を与えていると考えられる。
入眠剤の有無
現在ゾルピデム5mgを眠前に使用している。この薬剤は非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬であり、高齢者にとって比較的安全性が高いとされているが、転倒リスクの増加や翌日への持ち越し効果に注意が必要である。特にA氏は転倒歴があり、認知機能軽度低下もあることから、薬剤による転倒リスクの評価が重要である。薬剤の効果や副作用について継続的な評価が必要である。
疲労の状態
術後という状況下で身体的疲労は必然的に存在すると考えられる。手術侵襲による炎症反応や疼痛により、全身倦怠感が生じている可能性が高い。また、病院環境での精神的ストレスや不安により精神的疲労も蓄積していると考えられる。食事摂取量の低下により栄養状態の悪化も疲労感の増大に寄与している。しかし、現在の活動量低下により適度な身体的疲労が不足し、これが入眠困難の一因となっている可能性もある。
療養環境への適応状況、ストレス状況
A氏は自宅での生活から急激な環境変化を経験しており、病院という新しい環境への適応が困難な状況にある。騒音、照明、温度などの物理的環境要因が睡眠に影響を与えている。また、「また転んでしまうのではないか」「家に帰れるのか心配」という発言から、強い不安とストレスを抱えていることが明らかである。78歳という高齢であることから環境変化への適応能力の低下があり、これが睡眠障害を増強している要因となっている。
ニーズの充足状況
現在の睡眠ニーズは十分に充足されていない状態である。睡眠が浅く頻繁に覚醒していることから、回復に必要な質の良い睡眠が確保できていない。特に高齢者では深睡眠の減少があり、術後の回復には十分な休息が必要であるが、現在の状況では不十分である。規則正しい生活リズムが崩れており、概日リズムの調整が必要な状況である。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として疼痛管理による睡眠の質改善、療養環境の調整、概日リズムの回復が挙げられる。疼痛管理では薬物療法の最適化に加え、非薬物的疼痛緩和法の導入も検討する。環境調整として、夜間の騒音軽減、適切な照明管理、室温調整を行う。日中の活動促進により適度な疲労感を作り出し、夜間の自然な入眠を促進する。ゾルピデムの効果と副作用を継続的に評価し、転倒リスクとのバランスを考慮した薬剤調整を行う。睡眠衛生指導を実施し、入眠儀式の確立や就寝前のリラクゼーション技法を指導する。不安軽減のための傾聴とカウンセリングも重要であり、家族の面会による精神的安定も図る。継続的な観察項目として、睡眠時間、中途覚醒回数、日中の覚醒レベル、疼痛の程度を記録し、個別性を重視した睡眠改善計画を立案することが重要である。
ADL、運動機能、認知機能、麻痺の有無、活動意欲
A氏は現在上肢の動作は自立しているが、下肢については介助が必要な状態である。右大腿骨頸部骨折術後であることから、股関節の屈曲制限があり、下肢の衣類着脱動作に大きな制約がある。MMSE 24点の軽度認知機能低下があるものの、衣類選択に関する判断能力は概ね保たれていると考えられる。しかし、時々見当識に混乱を示すことがあるため、季節や気候に応じた適切な衣類選択に支援が必要な場合がある。活動意欲については、転倒への恐怖と不安により低下しており、これが衣類着脱への積極性にも影響を与えている可能性がある。
点滴、ルート類の有無
現在尿道カテーテルが留置されており、これが下肢の衣類着脱時の制約要因となっている。術後管理として点滴ラインが確保されている可能性があり、これらのルート類は上肢の衣類着脱動作に影響を与える。特に袖通しの際には、ルート類の牽引や圧迫に注意が必要である。カテーテルバッグの位置調整も衣類着脱時には重要な考慮事項となる。
発熱、吐気、倦怠感
現在の体温は36.8℃と安定しているが、術後の炎症反応により微熱が生じる可能性がある。発熱時には発汗により衣類の交換頻度が増加し、頻回な着脱動作が必要となる。明らかな吐気の記載はないが、使用中のロキソプロフェンによる消化器症状の可能性があり、これが衣類着脱時の体位変換に影響を与える可能性がある。術後の全身倦怠感により、衣類着脱に要する体力や集中力が低下していると考えられる。
ニーズの充足状況
現在の衣類着脱に関するニーズは部分的にしか充足されていない状況である。上肢の動作は自立しているものの、下肢の衣類着脱には全面的な介助が必要である。78歳という高齢に加え、関節可動域制限と疼痛により、自立した衣類着脱が困難な状態にある。特に高齢者にとって衣類の選択と着脱は自尊心と尊厳に関わる重要な活動であり、可能な限りの自立支援が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として安全で効率的な衣類着脱方法の確立、自立度の向上支援、尊厳の保持が挙げられる。具体的な介入として、股関節に負担をかけない着脱方法の指導を行い、前開きの衣類や伸縮性のある素材の使用を推奨する。ルート類の管理を適切に行い、安全な着脱手順を確立する。上肢機能は保たれているため、できる部分は本人が行うことで自立感を保持する。疼痛管理を徹底し、着脱時の疼痛軽減を図る。家族に対して適切な介助方法を指導し、退院後の継続的な支援体制を整備する。認知機能の変化を考慮し、時間をかけた丁寧な説明と見守りを行う。継続的な観察項目として、着脱動作の自立度、疼痛の程度、皮膚状態の変化を評価し、個別性を重視した段階的な自立支援計画を立案することが重要である。また、プライバシーの確保と羞恥心への配慮により、患者の心理的負担を軽減することも重要な介入である。
バイタルサイン
A氏の現在の体温は36.8℃と正常範囲内で安定している。来院時は37.2℃とやや高値を示していたが、これは外傷による炎症反応と疼痛によるストレス反応の結果と考えられる。術後3日目の現在、体温が正常化していることは感染兆候がないことを示唆している。血圧は142/86mmHgと軽度高値であるが、これは高血圧の既往と術後ストレスによるものと考えられる。脈拍82回/分、呼吸数18回/分は正常範囲内であり、循環動態は安定している。
療養環境の温度、湿度、空調
病院環境における室温・湿度管理の詳細な情報は不足している。高齢者は体温調節機能の低下があるため、適切な環境温度の維持が重要である。特に術後の安静臥床により体温産生能力が低下しており、環境温度への依存度が高くなっている。11月という季節を考慮すると、暖房による乾燥や温度変化への対応が必要である。空調の風が直接当たることによる体温低下や皮膚乾燥にも注意が必要である。
発熱の有無、感染症の有無
現在明らかな発熱は認められないが、術後感染のリスクは継続して存在する。手術部位感染、尿路感染、肺炎などの医療関連感染の可能性があり、継続的な観察が必要である。薬物アレルギーはないとされているが、薬剤熱の可能性も考慮する必要がある。高齢者では発熱反応が不十分なことがあり、感染があっても典型的な発熱を示さない場合があるため注意が必要である。
ADL
現在ADLの大幅な制限があり、これが体温調節に影響を与えている。活動量の低下により熱産生が減少し、体温維持能力が低下している。移乗動作に介助が必要であることから、適切な体位変換による体温調節も困難な状況である。衣類の調整も下肢については介助が必要であり、環境変化への迅速な対応が制限されている。
血液データ(WBC、CRP)
WBC値は6,200/μLと正常範囲内にあり、入院時の8,500/μLから改善している。CRP値は1.2mg/dLと軽度上昇しているが、入院時の2.8mg/dLから著明に改善傾向を示している。これらの値は術後の炎症反応の改善を示しており、現時点で活動性感染の可能性は低いと考えられる。しかし、高齢者では免疫機能の低下があるため、軽微な感染でも重篤化する可能性があり、継続的な監視が必要である。
ニーズの充足状況
現在の体温調節に関するニーズは概ね充足されている状況である。体温は正常範囲内で維持されており、明らかな体温調節障害は認められない。しかし、高齢による体温調節機能の低下と術後の活動制限により、環境変化に対する適応能力は低下している。特に急激な温度変化に対する対応能力が制限されている可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として術後感染の早期発見、適切な環境温度の維持、体温調節機能の支援が挙げられる。感染予防として手術部位の観察、尿道カテーテル管理の徹底、呼吸器合併症の予防を行う。環境調整では室温22-24℃、湿度50-60%の維持を図り、直接的な冷暖房の風を避ける。体温測定は4時間毎に実施し、発熱パターンの変化を観察する。衣類や寝具の調整により適切な保温を図り、発汗時には速やかな衣類交換を行う。血液データの定期的な評価により感染兆候の早期発見に努める。高齢者の特徴を考慮し、微細な体温変化や随伴症状にも注意を払う。継続的な観察項目として、体温の日内変動、発汗の有無、末梢循環の状態、感染兆候の有無を評価し、個別性を重視した体温管理計画を立案することが重要である。また、家族への感染予防指導も退院に向けて必要な介入である。
自宅/療養環境での入浴回数、方法、ADL、麻痺の有無
A氏は入院前の入浴習慣や清潔保持方法について詳細な情報が不足している。78歳という高齢であることから、加齢による皮膚機能の低下があり、皮脂分泌の減少や皮膚バリア機能の低下が基礎にあると考えられる。現在は清拭で対応している状況であり、全身浴や部分浴は術後の制限により実施できない状態である。右大腿骨頸部骨折術後であることから、股関節の動きに制限があり、会陰部や下肢の清潔保持に困難を生じている。明らかな麻痺はないものの、疼痛による動作制限が清潔行動に大きく影響している。
鼻腔、口腔の保清、爪
口腔ケアの実施状況について具体的な記載はないが、全身麻酔後であることから口腔乾燥や口腔内細菌の増殖が懸念される。高齢者では唾液分泌の減少があり、術後の脱水傾向や薬剤の影響により口腔乾燥が増強している可能性がある。鼻腔の清潔状態についても情報が不足しており、上気道の乾燥や分泌物の貯留について確認が必要である。爪の状態については記載がないが、高齢者では爪の肥厚や変形があることが多く、適切な爪切りや清潔保持が困難な場合がある。
尿失禁の有無、便失禁の有無
現在尿道カテーテル管理となっているため、尿失禁の直接的な問題はないが、カテーテル周囲の皮膚トラブルや感染リスクが存在する。便失禁については明らかな記載はないが、便秘傾向があることから便性状の変化により失禁のリスクがある。高齢者では括約筋機能の低下があり、術後の活動制限や薬剤の影響により排泄コントロールが困難になる可能性がある。失禁による皮膚の浸軟や炎症のリスクが高い状況である。
ニーズの充足状況
現在の清潔保持に関するニーズは十分に充足されていない状況である。全身浴が実施できないことにより、身体全体の清潔度が低下している可能性がある。特に高齢者では皮膚の自浄作用が低下しており、積極的な清潔援助が必要である。清拭のみでは除去しきれない皮脂や角質の蓄積により、皮膚トラブルのリスクが増大している。また、身だしなみを整えることへの意欲低下も認められ、自尊心の維持にも影響を与えている。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として術後の皮膚トラブル予防、感染予防、自尊心の維持が挙げられる。清拭を効果的に実施するため、温かいタオルの使用と十分な洗浄時間の確保を行う。特に圧迫部位や皮膚のひだの清潔に注意し、褥瘡予防を図る。口腔ケアを1日3回以上実施し、義歯の清潔や舌苔の除去を行う。カテーテル周囲の会陰部ケアを1日2回実施し、感染予防を徹底する。皮膚の観察を毎日行い、発赤、びらん、感染徴候の早期発見に努める。保湿剤の使用により皮膚乾燥を予防し、皮膚バリア機能を保持する。可能な範囲で本人の参加を促し、自立感と尊厳を保持する。家族に対して適切な清潔援助方法を指導し、退院後の継続的なケア体制を整備する。継続的な観察項目として、皮膚の状態、口腔内の変化、感染徴候の有無を評価し、個別性を重視した清潔ケア計画を立案することが重要である。また、プライバシーの確保と羞恥心への配慮により、患者の心理的負担を軽減することも重要な介入である。
危険箇所(段差、ルート類)の理解、認知機能
A氏はMMSE 24点と軽度の認知機能低下があり、時々見当識に混乱を示すことがある。このため病院環境の危険因子に対する認識や対処能力が低下している可能性がある。現在尿道カテーテルが留置されており、移動時のルート類への引っかかりや牽引による外傷のリスクが存在する。ベッド周囲の段差やベッド柵、点滴スタンドなどの医療機器による転倒リスクも高い状況である。過去3年間で3回の転倒歴があることから、危険予知能力の低下が認められ、環境要因への適応が困難な状態にある。
術後せん妄の有無
現在明らかなせん妄の記載はないが、78歳という高齢、手術侵襲、環境変化、疼痛、薬剤使用などせん妄発症のリスク因子が複数存在している。特にゾルピデムの使用は高齢者におけるせん妄のリスク因子となる可能性がある。軽度認知機能低下があることから、せん妄の発症しやすい状態にあり、継続的な観察が必要である。せん妄が発症した場合、危険行動や転倒リスクが著明に増加する可能性がある。
皮膚損傷の有無
現在の皮膚状態について詳細な記載はないが、術後の安静臥床により褥瘡発症のリスクが高い状況である。78歳という高齢に加え、BMI 20.8とやや痩せ型であることから、骨突出部の圧迫による皮膚損傷の可能性がある。Alb値3.2g/dLと低下していることも褥瘡発症のリスク因子となる。手術部位の創傷については感染や離開のリスクがあり、適切な創傷管理が必要である。
感染予防対策(手洗い、面会制限)
現在の感染予防対策について具体的な情報は不足している。尿道カテーテル留置により尿路感染のリスクが高く、カテーテル関連感染の予防が重要である。手術部位感染の予防のため、創部の清潔管理と適切な処置が必要である。高齢者は免疫機能の低下があり、院内感染に対する感受性が高い状況である。面会制限については詳細不明であるが、COVID-19対策を含めた感染管理が必要である。
血液データ(WBC、CRP)
WBC値は6,200/μLと正常範囲内にあり、CRP値は1.2mg/dLと軽度上昇している。入院時と比較して両値とも改善傾向にあり、現時点での活動性感染の可能性は低いと考えられる。しかし、高齢者では感染に対する反応が不十分なことがあり、軽微な感染兆候にも注意が必要である。継続的な監視により感染の早期発見と対応が重要である。
ニーズの充足状況
現在の安全確保に関するニーズは部分的にしか充足されていない状況である。医師によりベッド柵の使用と離床時の見守りが指示されているが、包括的な安全対策が必要である。認知機能低下と転倒歴を考慮すると、常時の安全確保が困難な状況にある。特に夜間や薬剤使用時の安全リスクが増大している可能性が高い。
健康管理上の課題と看護介入
最重要課題は転倒予防と総合的な安全管理である。環境整備としてベッド周囲の整理整頓、ナースコールの設置、適切な照明の確保を行う。ルート類の適切な固定と管理により、引っかかりや牽引を防止する。定期的な見回りと安全確認を実施し、特に夜間の安全管理を強化する。認知機能の変化を継続的に評価し、せん妄の早期発見に努める。褥瘡予防として2時間毎の体位変換と圧迫部位の観察を行う。感染予防では手指衛生の徹底、カテーテル管理の適正化、創部の清潔保持を実施する。家族に対して安全管理の重要性を説明し、面会時の協力を求める。継続的な観察項目として、認知機能の変化、転倒リスクの評価、皮膚状態、感染徴候の有無を評価し、多職種連携による安全管理体制を構築することが重要である。また、薬剤による副作用の監視も継続的に行う必要がある。
表情、言動、性格は問題ないか
A氏は真面目で几帳面な性格であるが、やや心配性な面もある。現在「また転んでしまうのではないか」「家に帰れるのか心配」という発言から、強い不安と恐怖感を抱いていることが明らかである。元小学校教員という職歴から、通常はコミュニケーション能力が高いと推測されるが、現在の状況では不安が先行している可能性がある。表情については具体的な記載がないが、不安や心配を表出していることから、表情にも不安感が現れている可能性が高い。
家族や医療者との関係性
家族関係については、夫は「妻の介護は自分がする」と意欲的であり、長男は「安全に過ごせる環境を整えたい」と積極的にサポート体制を構築しようとしている。これは良好な家族関係を示しており、家族の支援意欲が高いことが伺える。医療者との関係性について具体的な記載はないが、元教員としての経験から、医療者への質問や相談は比較的行いやすいと考えられる。しかし、現在の不安状態により、効果的なコミュニケーションが阻害されている可能性がある。
言語障害、視力、聴力、メガネ、補聴器
明らかな言語障害は認められず、老眼鏡使用で視力は良好とされている。聴力も正常範囲内であり、基本的なコミュニケーション機能は保たれている状況である。しかし、高齢者では聞き取りにくさや理解速度の低下があることも考慮する必要がある。病院環境では眼鏡の管理や破損のリスクもあり、視力確保への支援が必要である。
認知機能
MMSE 24点と軽度の認知機能低下があり、時々見当識に混乱を示すことがある。これは複雑な情報の理解や記憶に影響を与える可能性があり、医療者からの説明の理解や治療への協力に支障をきたす可能性がある。また、感情のコントロールや適切な感情表出にも影響を与える可能性があり、不安や恐怖感が増強されやすい状態にある。
面会者の来訪の有無
面会者の来訪状況について具体的な記載はないが、家族の積極的な関与意欲から、定期的な面会が行われていると推測される。しかし、COVID-19感染対策により面会制限がある可能性があり、これが孤独感や不安の増大に寄与している可能性がある。特に高齢者にとって家族との接触は精神的安定に重要な要素である。
ニーズの充足状況
現在のコミュニケーションニーズは部分的にしか充足されていない状況である。不安や恐怖感を表出できているものの、それに対する十分な支援や安心感が得られていない可能性がある。認知機能の軽度低下により、複雑な情報の理解や記憶に困難があり、適切な情報提供と説明が不足している可能性がある。家族とのコミュニケーションは良好であるが、医療者との効果的な意思疎通については改善の余地がある。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として不安軽減のための効果的なコミュニケーション、認知機能に配慮した情報提供、家族を含めた支援体制の構築が挙げられる。具体的には、積極的な傾聴により患者の不安や恐怖感を受け止め、共感的な関わりを継続する。認知機能低下を考慮し、簡潔で理解しやすい説明を繰り返し行い、視覚的な資料も活用する。転倒予防策について具体的で実行可能な方法を説明し、安心感を提供する。家族との定期的な情報共有を行い、患者を中心とした支援体制を構築する。非言語的コミュニケーションにも注意を払い、表情や態度から感情の変化を読み取る。必要に応じてカウンセリングや精神的支援も検討する。継続的な観察項目として、不安レベルの変化、コミュニケーションの質、家族関係の状況を評価し、個別性を重視した心理社会的支援計画を立案することが重要である。また、退院に向けた段階的な不安軽減のための計画的な関わりも必要である。
信仰の有無、価値観、信念、信仰による食事
A氏については特定の宗教的信仰はないとされている。しかし、78歳という年齢と元小学校教員という職歴から、教育に対する信念や人生観に基づく価値観を持っていると考えられる。日本の高齢者に多く見られる先祖供養や仏教的な慣習に親しんでいる可能性があり、これらの精神的な支えについて詳細な確認が必要である。現在の入院生活では、日常的な精神的慣習が中断されている可能性があり、これが心理的不安定さの一因となっている可能性がある。
治療法の制限
特定の宗教的信仰がないことから、宗教的理由による治療制限はないと考えられる。しかし、個人的な価値観や信念により、特定の治療方法への抵抗感がある可能性は否定できない。高齢者では伝統的な医療観や民間療法への信頼があることも多く、現代医療との調和について配慮が必要である。また、生命観や死生観についても個人的な考えがあり、これが治療への取り組み姿勢に影響を与える可能性がある。
ニーズの充足状況
現在の精神的・霊的ニーズは詳細な評価が不足している状況である。特定の宗教的信仰がないとされているが、人生の意味や価値、精神的な安らぎに対するニーズは存在すると考えられる。入院という人生の危機的状況において、精神的な支えや心の平安を求める気持ちが高まっている可能性がある。現在の不安や恐怖感の背景には、スピリチュアルペインが存在する可能性もある。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として精神的・霊的ニーズの適切な評価、個人の価値観の尊重、心の平安の支援が挙げられる。具体的には、患者の人生観や価値観について丁寧に聴取し、何が精神的な支えとなっているかを把握する。特定の宗教的実践がなくても、読書、音楽、自然との触れ合いなど、心の安らぎを得る方法について確認する。家族との絆や人生の振り返りを通じて、生きる意味や価値を見出すことを支援する。必要に応じてチャプレンやカウンセラーとの連携も検討する。静かな環境の提供や精神的な安らぎを得るための時間と空間を確保する。元教員としての人生経験や知識を活かし、他の患者への良い影響を与える機会を提供することで、自己価値感の向上を図る。継続的な観察項目として、精神的な安定度、生きがいや希望の有無、家族や人間関係への満足度を評価し、個別性を重視したスピリチュアルケア計画を立案することが重要である。また、退院後の生活への希望や目標設定を通じて、前向きな気持ちを支援することも必要な介入である。
職業、社会的役割、入院
A氏は元小学校教員として長年勤務しており、教育現場での豊富な経験と知識を有している。78歳という年齢から既に退職しているが、教育者としてのアイデンティティは重要な自己概念の一部であると考えられる。現在は夫との二人暮らしであり、妻としての役割も担っている。入院により、これらの日常的な役割が一時的に中断されており、特に夫の世話や家事などの家庭内役割が果たせない状況にある。
疾患が仕事/役割に与える影響
右大腿骨頸部骨折とその術後状態により、身体機能の大幅な制限が生じている。これまで自立して行っていた家事や日常生活動作が困難となり、夫への依存度が高くなっている。「家に帰れるのか心配」という発言からも、従来の役割を継続できるかへの強い不安が伺える。また、転倒への恐怖により、積極的な活動への意欲が低下し、これまでの社会的役割や生産的活動への参加が困難な状況となっている。高齢による加齢変化と疾患の影響により、役割遂行能力の回復には時間を要することが予想される。
ニーズの充足状況
現在の達成感や生産性に関するニーズは著しく障害されている状況である。入院により日常的な役割や責任が果たせず、自己効力感や自尊心の低下を招いている可能性が高い。特に元教員として他者への貢献や指導に喜びを感じていたと考えられるが、現在はそのような機会が制限されている。家庭内での妻としての役割も一時的に中断されており、これが無力感や罪悪感を生じさせている可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として役割の再構築と自己価値感の回復、段階的な活動参加の促進、新たな達成感の創出が挙げられる。具体的には、教員としての豊富な経験を活かし、他の患者や若い医療スタッフとの交流を通じて、知識や経験を共有する機会を提供する。リハビリテーションの進歩を小さな達成として評価し、段階的な目標設定により成功体験を積み重ねる。家族との役割分担の再調整について話し合い、現在の身体状況でも可能な家庭内での役割を見つける。退院後の生活において、新たな生きがいや社会参加の可能性について検討する。読書や手紙書きなど、ベッド上でも可能な知的活動を通じて、達成感を得る機会を創出する。家族に対して、患者の自立支援の重要性を説明し、過度な保護ではなく適切な支援を提供するよう指導する。継続的な観察項目として、自己効力感の変化、活動への意欲、家族関係の満足度を評価し、個別性を重視した役割再構築支援計画を立案することが重要である。また、地域の高齢者活動や生涯学習への参加も退院後の選択肢として情報提供することが必要である。
趣味、休日の過ごし方、余暇活動
A氏の具体的な趣味や余暇活動について詳細な情報は不足している。元小学校教員という職歴から、読書や学習活動への関心が高い可能性がある。78歳という年齢と夫との二人暮らしという生活状況から、園芸、手芸、テレビ鑑賞、散歩などの比較的静的な活動を好んでいた可能性が考えられる。規則正しい生活を送っていたことから、日常的なルーティンの中に楽しみや気分転換の要素が組み込まれていたと推測される。
入院、療養中の気分転換方法
現在の入院生活において、気分転換の機会が大幅に制限されている状況である。術後の疼痛と活動制限により、積極的なレクリエーション活動への参加が困難な状態にある。病院環境では馴染みのある娯楽用品や趣味用具が利用できず、これが精神的ストレスの増大に寄与している可能性がある。睡眠が浅く頻繁に覚醒していることから、適切な気分転換により精神的緊張の緩和が必要である。
運動機能障害
右大腿骨頸部骨折術後により著明な運動機能制限がある。現在は部分荷重での歩行訓練中であり、座位や立位での活動も制限されている。変形性膝関節症の既往もあり、関節可動域の制限が存在する。これらの身体的制約により、従来参加していた身体的レクリエーションへの参加が困難な状況である。
認知機能、ADL
MMSE 24点の軽度認知機能低下があり、複雑な認知的活動への参加に一部制限がある可能性がある。しかし、元教員としての知的基盤は保たれており、適切なレベルの知的活動は可能と考えられる。ADLの制限により、自立したレクリエーション活動の選択や実施が困難な状態にある。時々見当識に混乱を示すことがあるため、安全で理解しやすい活動の選択が重要である。
ニーズの充足状況
現在のレクリエーションニーズは著しく障害されている状況である。入院により馴染みのある娯楽や気分転換の機会が失われ、精神的ストレスの蓄積が懸念される。特に高齢者にとって楽しみや生きがいは精神的健康の維持に重要であり、現在の状況では十分に充足されていない。単調な入院生活により、時間の経過に対する感覚の混乱や抑うつ気分の発現が懸念される。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として身体制約下でのレクリエーション機会の創出、精神的ストレスの軽減、生活の質の向上が挙げられる。具体的には、ベッド上で可能な活動として読書、音楽鑑賞、ラジオ視聴、簡単な手工芸などを提案する。認知機能レベルに応じたパズルやクロスワードなどの知的活動を提供し、脳機能の維持を図る。家族との面会時間を有効活用し、昔話や写真鑑賞などの思い出を共有する活動を促進する。病院内のレクリエーション活動への参加を検討し、他の患者との交流機会を提供する。テレビ番組の選択や視聴時間の調整により、気分転換と情報収集を支援する。季節感を感じられる装飾や音楽により、入院環境の単調さを軽減する。理学療法士と連携し、楽しみながら行える運動やゲーム感覚のリハビリテーションを導入する。継続的な観察項目として、気分の変化、活動への関心度、他者との交流状況を評価し、個別性を重視したレクリエーション支援計画を立案することが重要である。また、退院後の趣味活動の再開に向けた段階的な準備も必要な介入である。
発達段階
A氏は78歳の高齢期にあり、エリクソンの発達段階では統合性対絶望の段階に位置している。この段階では人生を振り返り、自分の人生に意味と価値を見出すことが重要な発達課題となる。元小学校教員として長年勤務した経歴から、教育や学習に対する深い理解と価値観を持っていると考えられる。現在の骨折と入院は、身体的脆弱性の認識と今後の生活への不安を増大させ、発達課題の達成に影響を与えている可能性がある。
疾患と治療方法の理解
A氏の疾患と治療に対する理解度について具体的な記載は不足している。軽度認知機能低下(MMSE 24点)があるものの、元教員としての知的基盤は保たれており、適切な説明により理解可能と考えられる。しかし、時々見当識に混乱を示すことがあるため、複雑な医学的情報の理解には時間と繰り返しの説明が必要である。現在の不安状態により、情報の受容や理解が阻害されている可能性もある。
学習意欲、認知機能、学習機会への家族の参加度合い
元教員という職歴から本来は高い学習意欲を持っていたと推測されるが、現在の状況では疼痛と不安により学習への集中が困難な状態にある。認知機能の軽度低下により新しい情報の習得速度は低下しているが、既存の知識や経験を活用した学習は可能である。家族については、夫と長男が積極的に治療や今後のケアに関心を示しており、学習機会への参加意欲が高いことが伺える。特に長男は「安全に過ごせる環境を整えたい」と発言しており、具体的な学習ニーズがあると考えられる。
ニーズの充足状況
現在の学習ニーズは部分的にしか充足されていない状況である。疾患や治療に関する基本的な情報提供は行われていると考えられるが、患者の理解度や不安に応じた個別的な教育が不足している可能性がある。特に転倒予防に関する具体的な知識や技術の習得は、患者の強い不安に対応するために重要である。また、退院後の生活に向けた実践的な学習機会も必要である。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として認知機能に配慮した効果的な患者教育、不安軽減のための知識提供、家族を含めた包括的な学習支援が挙げられる。具体的には、簡潔で理解しやすい説明を心がけ、視覚的な教材や模型を活用して理解を促進する。転倒予防について具体的で実行可能な方法を段階的に指導し、実際の動作練習を通じて技術習得を支援する。疼痛管理の方法や薬剤の適切な使用について教育し、自己管理能力の向上を図る。家族に対しては介助方法や緊急時の対応について実技指導を含めた教育を実施する。退院後の生活環境整備について具体的な助言と情報提供を行う。元教員としての教育経験を活かした相互学習の機会を提供し、他の患者との知識共有を促進する。学習の評価として理解度の確認と実技の習得状況を定期的に評価し、必要に応じて教育内容を修正する。継続的な観察項目として、学習への関心度、理解度の変化、家族の学習参加状況を評価し、個別性を重視した患者・家族教育計画を立案することが重要である。また、生涯学習の視点から、退院後も継続できる学習機会についても情報提供することが必要である。
看護計画
看護問題
疾患に伴う転倒リスクの増大に関連した身体損傷の危険性
長期目標
・退院時までに安全な移動方法を習得し、転倒することなく歩行器を使用して移動できる
短期目標
・1週間以内に転倒リスクを理解し、ナースコールを適切に使用できる
・2週間以内に見守り下で安全に移乗動作を行うことができる
≪O-P≫観察計画
・転倒リスクアセスメントスケールによる評価値の変化
・歩行時のふらつきや不安定さの程度
・疼痛レベルと鎮痛薬使用後の影響
・認知機能の変化と見当識の状態
・ナースコール使用の適切性と頻度
・離床時の血圧変動と起立性低血圧の有無
・移乗動作時の安全性と自立度
・ベッド周囲の環境整備状況
・薬剤による眠気やふらつきの有無
・夜間の覚醒状況と不穏行動の有無
・家族の面会時における患者の安全意識
・歩行器使用時の姿勢と操作方法
≪T-P≫援助計画
・ベッド柵を適切な高さに設定し転落を防止する
・ベッド周囲の障害物を除去し安全な環境を整備する
・離床時は必ず看護師が付き添い見守りを行う
・移乗動作時は二人介助を基本とし安全を確保する
・歩行器の点検と適切な調整を行う
・滑り止めマットを設置し足元の安全を図る
・適切な履物の選択と着用を支援する
・夜間の照明を適度に確保し視界を良好に保つ
・疼痛時は我慢させず適切に鎮痛薬を投与する
・定期的な体位変換により筋力低下を予防する
・理学療法士と連携しバランス訓練を実施する
・転倒予防用品の適切な使用方法を指導する
≪E-P≫教育・指導計画
・転倒の危険性と予防の重要性について説明する
・ナースコールの適切な使用方法を指導する
・安全な移乗動作の方法を実技を交えて指導する
・歩行器の正しい使用方法と点検項目を指導する
・家族に対して安全な介助方法を指導する
・退院後の住環境整備について具体的に助言する
・緊急時の対応方法について家族に指導する
・転倒予防のための日常生活の注意点を指導する
看護問題
手術侵襲と疼痛に伴う活動耐性低下に関連した日常生活動作の障害
長期目標
・退院時までに歩行器を使用して自立歩行が可能となり、基本的な日常生活動作を安全に行うことができる
短期目標
・1週間以内に疼痛が軽減し、理学療法に積極的に参加できる
・2週間以内に見守り下で移乗動作が自立できる
≪O-P≫観察計画
・疼痛レベルの数値スケールによる評価
・理学療法時の参加意欲と疲労の程度
・移乗動作時の自立度と所要時間
・歩行距離と歩行時間の変化
・バイタルサインの安定性と活動時の変化
・呼吸状態と酸素飽和度の変化
・筋力と関節可動域の回復状況
・活動後の疲労感と回復時間
・食事摂取量と栄養状態の改善度
・睡眠時間と睡眠の質の変化
・褥瘡発生リスクと皮膚状態
・手術創部の治癒状況と感染徴候
≪T-P≫援助計画
・疼痛時は適切なタイミングで鎮痛薬を投与する
・理学療法前の十分な疼痛管理を実施する
・段階的な離床計画を立案し実行する
・移乗動作時は適切な介助技術を用いる
・筋力維持のためベッド上での運動を促進する
・関節拘縮予防のため他動的関節運動を実施する
・適切な体位変換により褥瘡発生を予防する
・栄養状態改善のため食事摂取を促進する
・水分摂取を励行し脱水を予防する
・理学療法士と連携し個別リハビリ計画を実行する
・活動と休息のバランスを適切に調整する
・褥瘡予防用具を適切に使用する
≪E-P≫教育・指導計画
・疼痛管理の重要性と鎮痛薬の適切な使用について指導する
・段階的な活動拡大の必要性について説明する
・理学療法の目的と効果について説明する
・自主訓練の方法と注意点について指導する
・適切な栄養摂取の重要性について指導する
・家族に対して日常生活動作の支援方法を指導する
・退院後の活動レベルと注意点について指導する
・疲労時の休息の取り方について指導する
看護問題
術後状態と環境変化に伴う不安に関連した睡眠パターンの障害
長期目標
・退院時までに不安が軽減し、夜間を通して良質な睡眠を6時間以上確保できる
短期目標
・1週間以内に転倒への不安を表出し、看護師と対処方法を話し合うことができる
・2週間以内に中途覚醒が減少し、連続4時間以上の睡眠を確保できる
≪O-P≫観察計画
・睡眠時間と睡眠の質の変化
・中途覚醒の回数と覚醒理由
・入眠時間と入眠困難の有無
・日中の眠気と覚醒レベル
・不安の表出内容と頻度
・疼痛と睡眠の関連性
・睡眠薬の効果と副作用
・夜間の転倒リスク行動の有無
・家族面会後の精神状態の変化
・病院環境への適応状況
・食欲と睡眠の関連性
・血圧や脈拍など自律神経系の変化
≪T-P≫援助計画
・夜間の騒音を最小限に抑制し静かな環境を提供する
・適切な室温と湿度を維持し快適な環境を整備する
・就寝前の疼痛管理を徹底し安楽な体位を確保する
・患者の不安や心配事に積極的に傾聴する
・リラクゼーション技法を指導し実践を支援する
・就寝前の入眠儀式の確立を支援する
・日中の適度な活動を促進し生活リズムを整える
・睡眠薬の効果を評価し医師と投与調整を検討する
・家族との面会時間を調整し精神的安定を図る
・転倒予防策について具体的に説明し安心感を提供する
・夜間の照明を適切に調整し安全で安心できる環境を作る
・規則正しい生活リズムの確立を支援する
≪E-P≫教育・指導計画
・良質な睡眠の重要性と睡眠衛生について指導する
・不安軽減のためのリラクゼーション方法を指導する
・転倒予防の具体的な方法について詳しく説明する
・睡眠薬の適切な使用方法と注意点について指導する
・退院後の生活環境整備について家族と話し合う
・ストレス対処法と相談窓口について情報提供する
・規則正しい生活リズムの維持方法について指導する
・家族に対して患者の不安軽減への協力を依頼する
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
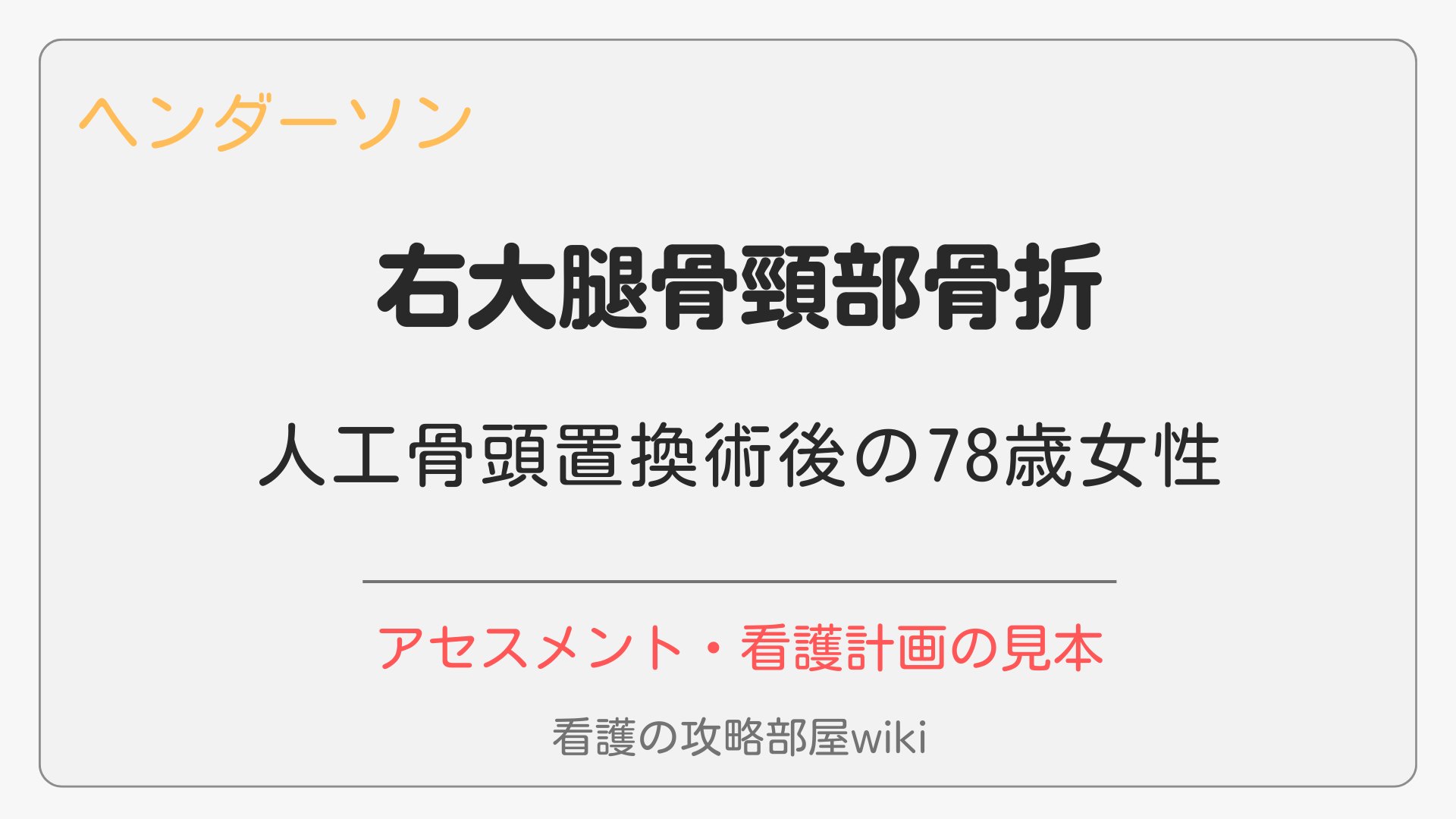
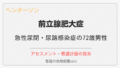
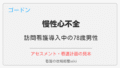
コメント